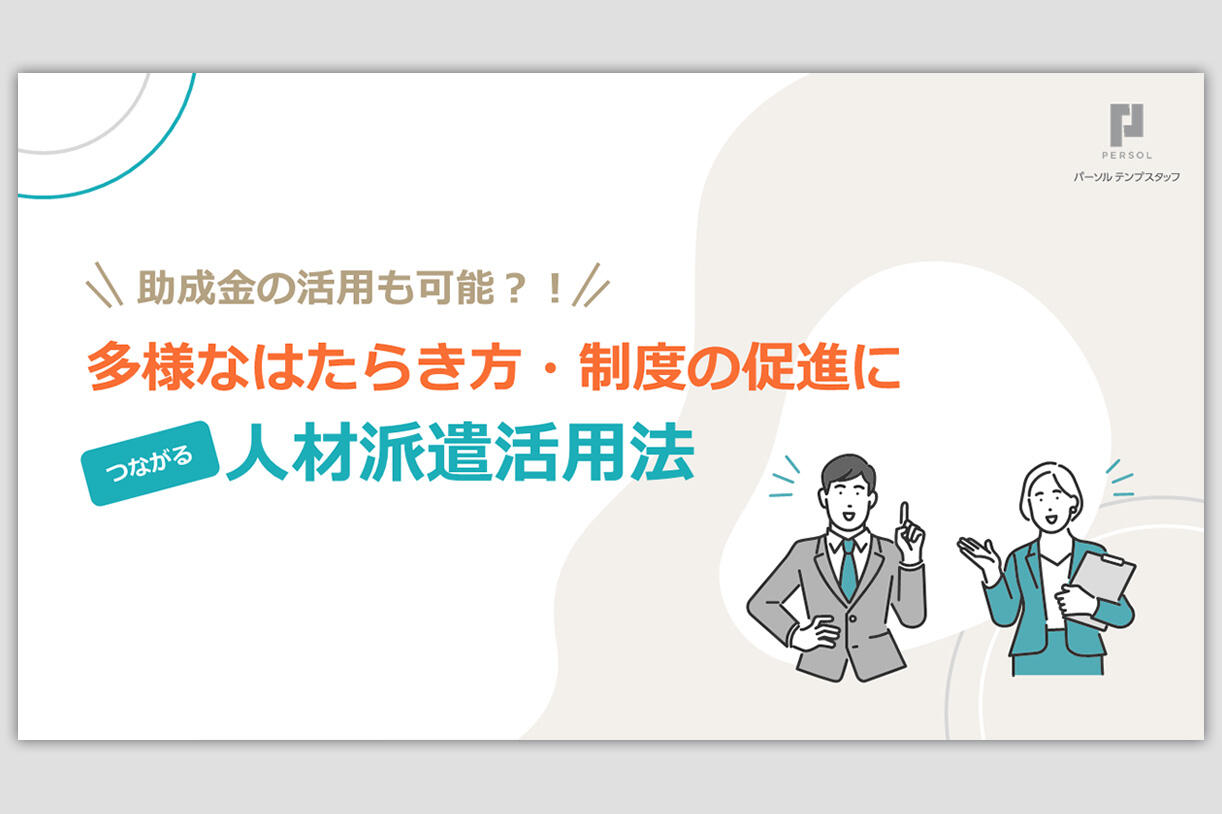HRナレッジライン
カテゴリ一覧
社員一人ひとりの能力を最大限に引き出す人材活用とは?
公開日:2025.07.11
- 記事をシェアする

少子高齢化の進行や市場環境の変化が加速する中、企業が持続的に成長していくためには、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出すための人材活用が重要なテーマとなっています。
これは単なる人材不足への対応にとどまらず、社員の意欲と生産性を引き出し、組織全体の競争力を高めるための本質的な取り組みです。
本記事では、人材活用の定義や目的をはじめ、実践に必要な具体的な方法や制度、事例などを紹介します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
社員一人ひとりが輝く人材活用とは
企業は、少子高齢化と急速なデジタル化という二重のプレッシャーの中で、いかに人材を最大限に活かすかが経営の最重要テーマとなっています。
企業が必要とする人材に対して求職者数が不足する「売り手市場」の状況は、今後も続くと考えられます。このような環境下で企業が持続的な成長を遂げるためには、社員一人ひとりが能力を発揮して輝くと同時に、企業も成長していけるような仕組みづくりが不可欠です。
では、社員一人ひとりが輝く人材活用とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
人材活用の定義と目的
人材活用とは、社員のスキル・経験・志向を可視化し、最適な機会と結び付けることで企業と社員が同時に成長・活躍するマネジメントプロセスのことです。
その目的は、業種や企業規模によって細部は異なりますが、主に社員の能力を最大限に引き出すための最適配置やリスキリングの推進、そして誰もが意欲的にはたらけるような制度・環境づくりに集約されます。
人材活用の現状と課題
多くの企業において、人材活用は依然としてさまざまな課題を抱えているのが現状です。
例えば、以下のような課題が考えられます。
- スキルアップやリスキリングの機会が十分に提供されていない
- 評価や報酬に納得感が得られず不公平感が募っている
- 多様化するはたらき方に対応できる柔軟な制度や環境が整っていない
これらは個別の課題に見えるかもしれませんが、背景には人事制度全体の整合性の欠如や、旧来のマネジメント手法からの脱却が遅れているといった、より構造的な問題が潜んでいる場合も少なくありません。
「社員が真に活躍するために、会社としてどのような環境を用意すべきか」という問いに真摯に向き合い、具体的な施策を実行し、その効果を丁寧に検証した上で改善を続けていく、地道な取り組みが不可欠です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
社員の力を発揮する3つの土台
ここでは、社員一人ひとりの能力が最大限に引き出され、組織全体の成長へとつなげるための3つの重要な土台について、個人・職場環境・組織という視点から解説します。
個人の成長を直接後押しする学びとキャリア設計
社員の成長の根幹となるのは、個人のスキル向上と将来に向けたキャリア形成への投資です。
社員が自身のスキルアップを実感し、明確なキャリアの見通しを持つことで、日々の業務が単なる作業ではなく、「自己成長=会社への価値提供」という意識へと変わり、それが主体的な行動を促します。
キャリアパス設計
社員一人ひとりのキャリア目標や興味分野を丁寧にヒアリングし、中長期的な成長を支援します。
各キャリアステップにおいて必要となるスキルや経験を明確に示すことで、社員は将来を見据え、主体的にキャリアを形成していくことができます。明確なキャリアパスは、社員のモチベーションを高め、組織への長期的な貢献を促します。
キャリアデザインの目的や企業の取り組みについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>>キャリアデザインの目的やメリットは?企業の取り組み方をご紹介
リスキリング・スキル開発
急速な技術革新や変化する市場ニーズに対応するためには、社員の継続的な学習が不可欠です。
企業は、研修や教育プログラム、社内外のセミナー参加を積極的に支援し、受講料補助などの制度を整備することで、社員の自発的なスキル習得を後押しします。これにより、社員は最新の知識やスキルを得て、変化に応じて行動できる実践的な力を身に付けます。
社員の自律的な学びを促進するために必要な視点や仕組みについては、以下のセミナーレポートをご参照ください。
>>【セミナーレポート】「リスキリング」を科学する
成長を続けるやる気とはたらきがいを生む環境づくり
社員が持つ能力を十分に発揮するためには、スキルだけでなく、高いモチベーションとはたらきやすい環境が不可欠です。ここでは、「評価」と「労働環境」という二つの側面から、社員の成長を支えるエネルギー源を確保するための取り組みについて解説します。
評価制度の整備
社員の頑張りを正しく評価する公正で明確な評価制度は、モチベーション向上に不可欠です。単に報酬を見直すだけでなく、上司や同僚からのフィードバックを充実させることで、社員は自身の貢献が認められていることを実感し、さらなる成長への意欲を高めることができます。
人事評価制度の導入目的や設計方法について、さらに詳しい情報は以下の記事をご覧ください。
>>人事評価制度とは?導入する目的やメリット、設計方法について解説
人事制度全体の目的や、評価・報酬に偏りがちな考え方への理解を深めたい方は、以下のコラムをご覧ください。
>>【ナレッジコラム】人事制度の真実 vol.001 人事制度の誤解と真実の目的
はたらきやすい環境整備
リモートワークや短時間勤務などの柔軟なはたらき方や多様なはたらき方の導入、快適なオフィス環境の整備、充実した福利厚生などは、社員が仕事に集中しやすい基盤となります。
そしてワーク・ライフ・バランスの実現は、社員の心身の健康を保ち、長期的な視点での生産性向上につながります。
ワーク・ライフ・バランスの詳細については、以下の記事をご参照ください。
>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説
チームで成果を最大化する配置とリーダー育成
個々の能力を最大限に引き出すだけでなく、組織全体の力を高めるためには、リーダーがメンバーの力をまとめ、メンバー同士の相乗効果を生み出すことが重要です。
人材配置
社員のスキル、経験、そしてキャリアに対する志向を深く理解し、それぞれの能力が最も活かされる最適なポジションに配置することが重要です。担当業務とのミスマッチを防ぐために、定期的な面談や部署異動を検討し、常に最適な人材配置を目指します。
リーダー育成
企業の持続的な成長に不可欠なリーダーを育成するために、管理職候補への研修やメンター制度を活用します。年齢や社歴に関わらず、誰もがリーダーシップを発揮できる機会を増やすことで、組織全体の活性化を促し、より高い成果を生み出すチーム作りを推進します。
リーダーシップの役割やスキルについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
>>リーダーシップとマネジメントの違いは?事例やスキルを育むポイントも解説
人材活用につながる制度
社員が多様なライフステージやキャリアプランを描けるようにするには、柔軟なはたらき方を支える制度が不可欠です。ここでは人材活用を後押しする代表的な4つの制度を紹介します。
リモートワーク
リモートワークは、時間や場所に縛られないはたらき方を可能にし、通勤時間の削減や採用範囲の拡大といった効果が期待できます。
ただし、雑談チャネルやオンライン会議ツールを活用した朝礼など、リモートワークを円滑に進める環境を整備しなければなりません。リモートワークでも社員のモチベーションを維持したり、社員の体調やメンタルヘルスの様子を確認することも重要です。
リモートワークのメリットや留意点について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
>>リモートワークとは?導入するメリットや留意点について解説
短時間労働
短時間労働は、育児や介護、自己研鑽といったライフステージの変化に合わせて、労働時間を短縮できる制度です。
従業員はキャリアを中断することなくはたらき続けられるため、企業にとっては専門性を持つ人材の離職を防ぐ上で有効な手段となります。この制度を導入する際は、チーム内の連携を考慮し、例えば勤務時間帯の重なりを確保するなど、円滑な運営のためのルール作りが重要です。
オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリッドワークについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>>ハイブリッドワークとは?メリットや導入する際のポイントを解説
育児休暇
育児休暇は仕事と家庭の両立を支援し、優秀な社員の離職を防ぐ制度です。休暇取得を推奨するだけでなく、復帰後の受け入れ体制や時短勤務の選択肢を用意し、キャリア継続を後押ししましょう。
子育て中の社員が活躍できる環境づくりや関わり方の工夫については、以下の記事をご参照ください
>>【ナレッジコラム】対話からはじめる本気のDE&I推進 vol.002 子育て社員も、関わり方を変えることで活躍人材になる!
子育て中の女性のキャリア支援に関する詳しい情報については、以下の記事をご参照ください。
>>【ナレッジコラム】「社労士がHRに伝えたい!キャリアも私生活も大切にしたはたらき方の実現」 vol.003子育て女性のキャリア支援
フレックスタイム
フレックスタイム制では、社員がコアタイム以外の始業・終業時刻を自由に設定できます。業務特性に応じた運用ルールを構築し、朝型・夜型など個々の生活リズムや集中しやすい時間帯に合わせてはたらくことで、生産性とワーク・ライフ・バランスの両立が可能です。
フレックスタイム制の目的や導入方法については、以下の記事をご参照ください。
>>フレックスタイム制の目的や導入する際のメリットや留意点をご紹介
HRテックで進化する人材活用
HRテックとは、人事領域にテクノロジーを導入し、採用から育成・配置・評価といった業務をデータでつなぎ、人材活用を高度化する取り組みです。
ここでは、その中核技術である人材管理システム(HRM)とAIの活用について解説します。
人材管理システム(HRM)の機能と導入効果
人材管理システム(HRM)は、社員のキャリア・スキル・評価など多様な情報を一元管理して可視化するプラットフォームです。
経験則に頼らずデータに基づいた客観的な配置・昇進やスキル開発のタイミングを決定できるため、社員の納得感が高まり、エンゲージメント向上・公平性確保・離職率低下といった効果が期待できます。
AIが変える人材マッチングの未来
HRMで整備したデータ基盤を活用し、人材とポジションのマッチング領域で高い効果を発揮するのがAI(人工知能)です。
例えば、職務経歴書・業務成果・学習データなど多様な情報源を解析し、社員のスキルや適性を人間が見落としがちなレベルの要素まで含めて正確に把握できます。
その上で、個人の特性と事業戦略やプロジェクトの要件を高精度に照合し、バイアスの少ない客観的な人材配置を実現します。なお、AIによるデータ利用時は社内規定と法令の遵守が前提です。
人材活用に取り組むメリット
社員一人ひとりが輝ける状態を目指す人材活用は、企業と社員の双方にとって有益な取り組みです。具体的なメリットを以下にご紹介します。
生産性アップ
社員が自身の強みを活かせる環境と、公正な評価制度が整備されることで、社員の意欲や満足度が高まりやすくなります。その結果、主体的な業務改善の提案やチーム間の協力が活発になり、付加価値の高い成果物が生まれやすくなるでしょう。
これは、企業にとっては売上や利益率の向上につながり、社員にとっては自身の成果が正当に評価されるという好循環を生み出します。
離職率低下
フレックスタイムやリモートワーク、透明な評価基準といったはたらきやすい制度を整備することは、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)の向上に寄与します。
「この会社ではたらき続けたい」という思いが社員に定着すれば、採用や教育にかかるコストの削減はもちろん、組織に蓄積されたノウハウの維持、ひいては競争力の強化にもつながります。
企業イメージ向上
人材活用への積極的な取り組みは、「人を大切にする企業」としての評価を確立し、社内外に好影響を与えます。
社員が誇りを持ってはたらく姿は、取引先や投資家からの信頼を高めます。また求職者にとっては魅力的な職場として映るため、優秀な人材の採用を後押しする要素にもなるでしょう。
人的資本経営やキャリア支援を通じて企業価値を高める考え方については、以下のインタビューをご覧ください。
>>【ナレッジインタビュー】法政大学 田中 氏 人が伸びれば事業は伸びる ー人事はキャリアをグロースさせるユニットー
人材活用につながる制度を導入する手順
ここでは、社員の視点も大切にしながら、人材活用に資する制度を導入するための基本的な手順をご説明します。
経営理念の確認
まず、自社の経営理念やビジョンを再確認し、目指すべき人材活用の方向性と一致しているかを見極めます。
この段階で、経営理念に基づき「社員を大切にし、その成長を支援する」という企業の姿勢を明確に打ち出すことが、社員の制度に対する納得感を高める上で重要です。
自社の現状を理解
次に、現場の社員へのヒアリングやアンケートを通じて、日々の業務や職場環境に対する課題を具体的に洗い出します。
スキルアップの機会不足、評価制度への不満、はたらき方の制約など、表面的な現象だけでなく、その根本にある本質的な問題を把握するよう心がけましょう。
制度を決める
現状分析で明らかになった課題を基に、企業と社員双方の課題解決に資する制度を具体的に検討・策定します。
例えば、「業務効率の向上が急務」といった課題に対しては、リモートワークやフレックスタイム制度の導入が考えられます。また、「特定のスキルを持つ人材の不足」が課題であれば、対象を絞った研修プログラムや資格取得支援制度の導入が有効です。
シミュレーションの実施
あたらしい制度を本格導入する前に、実際の運用現場でどのように機能するかを検証します。運用を担う部署と制度を利用する社員、それぞれの視点から問題点や懸念点を洗い出すためのシミュレーションが効果的です。
可能であれば、一部の部署でテスト導入(パイロット運用)を実施し、その結果を社員アンケートやヒアリングでフィードバックしてもらい、本格導入に向けた改善点を抽出しましょう。
制度の導入
導入にあたっては、制度の内容・目的・利用方法などを全社員に丁寧に周知徹底することが不可欠です。
また、導入初期は特に、社員がスムーズに制度を利用できるよう、説明会の開催や相談窓口の設置など、支援体制を整備しましょう。さらには導入後も、定期的に利用状況や効果測定を行い、現場の声を反映させながら、必要に応じて制度内容を見直し・改善していく姿勢が求められます。
人材活用に関する留意点
人材活用を効果的に進めるためには、社員一人ひとりが意欲的に、かつ最大限に能力を発揮できる環境を整えるには何が必要かという視点を常に持つことが重要です。
その上で、特に留意すべきポイントを以下にご紹介します。
十分な予算や時間を用意する
まず重要なのは、人材活用に必要な投資を惜しまないことです。例えば、あらたなスキルの習得を支援するリスキリング研修の実施や、人事評価制度の見直し・運用、はたらきがいを高めるための職場環境の整備などには、相応のコストと時間が必要となります。
すぐに大きな予算を確保するのが難しい中小企業などの場合は、最初から完璧を目指すのではなく、優先順位を明確にし、実行可能な範囲から段階的に取り組むことで、小さな成功体験を積み重ねるアプローチが有効です。
綿密に計画を立てる
人材活用において、どのような状態を目指すのかを具体的に設定することが求められます。そして、その目標達成に向けた導入プロセスを詳細に計画し、関係者全員が共通認識を持てるように可視化することが不可欠です。
計画を立案する際には、現状把握の段階で得られた社員の声を十分に反映させることが重要です。現場の実情やニーズを踏まえることで、机上の空論に終わらない、実践的で納得感の高い施策となります。
社員が活躍する人材活用の例
人材活用に成功している企業では、単に制度を導入するだけでなく、それが社員の意欲向上や能力発揮にどう結びつくかを考慮し、効果的に運用されています。
ここでは、効果的な人材活用の取り組みパターンをいくつかご紹介します。
はたらき方の柔軟性を高めて自律性を尊重する取り組み
多くの企業では、フレックスタイム制度やリモートワーク、あるいは勤務時間の一部を自由に調整できる裁量労働制などを導入する動きが見られます。
このように柔軟なはたらき方を認めることで、社員は育児や介護といった個々の事情やライフスタイルに応じて業務を調整しやすくなります。
結果として、通勤時間の削減や、集中しやすい環境を自ら選択できるようになり、生産性が向上するケースは少なくありません。さらに、会社から信頼され、自身の裁量で仕事を進められるという感覚は、社員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の確保・定着にも好影響を与えると報告されています。
フレックスタイム制の紹介については、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>フレックスタイム制の目的や導入する際のメリットや留意点をご紹介
リスキリングとスキルアップを戦略的に支援する取り組み
急速な市場環境の変化に対応するため、社員のリスキリングやあらたなスキル習得を組織的に支援する企業が増えています。
具体的には、業務に必要な専門知識を深める研修に加え、将来のキャリアチェンジを見据えた資格取得支援や、社内公募制度を通じたあらたな職務への挑戦機会の提供などが挙げられます。
こうした取り組みによって、社員は自身の市場価値を高め、変化への適応力を養うことができます。企業にとっても、内部人材の育成を通じて事業の継続性やあらたな価値の創出力を高めるというメリットが期待できるでしょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人材活用で、社員と企業がともに成長できる未来を目指そう
人材活用の本質は、社員一人ひとりが主体的に力を発揮できる環境を整え、その成長が企業の発展にもつながるという視点にあります。
リスキリングや柔軟なはたらき方といった取り組みを通じて、社員が自らの成長を実感できる職場づくりを進めることで、企業は変化の激しい社会においても持続的に成長できる強い組織へと進化していけるでしょう。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする