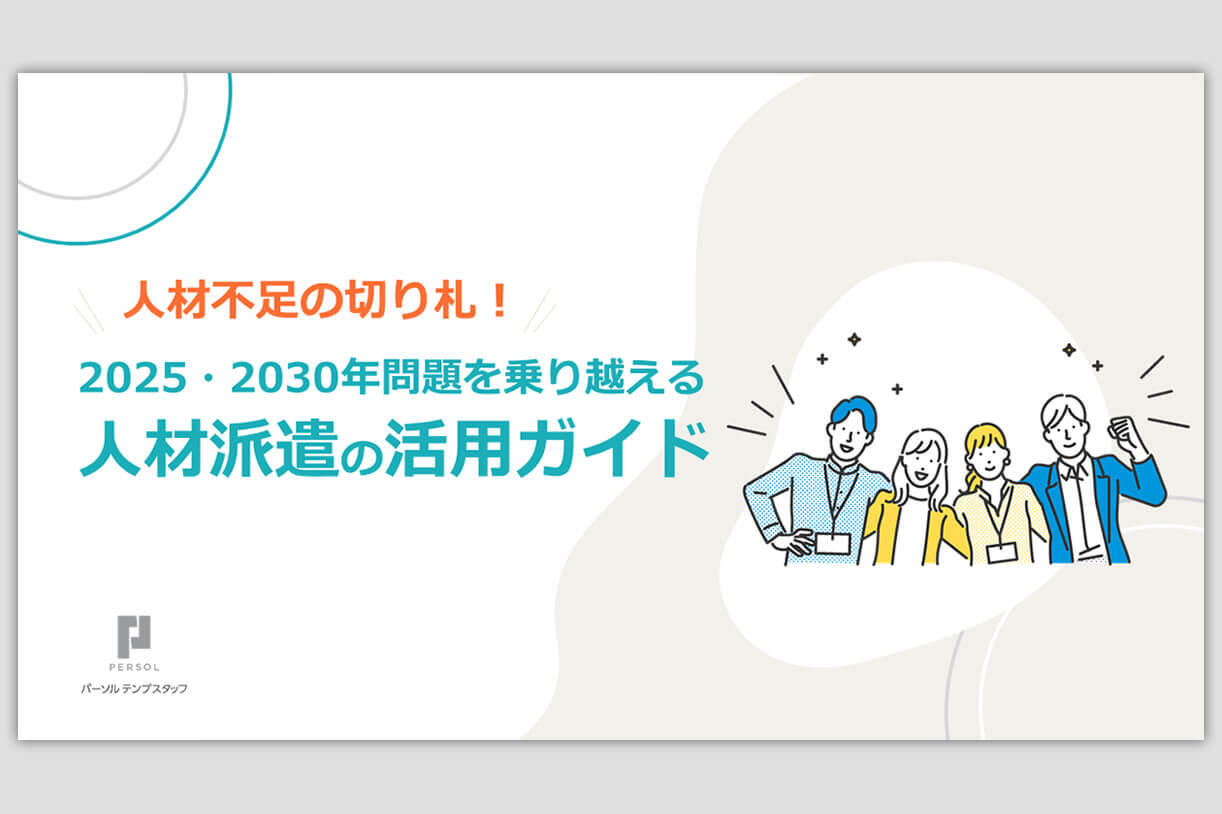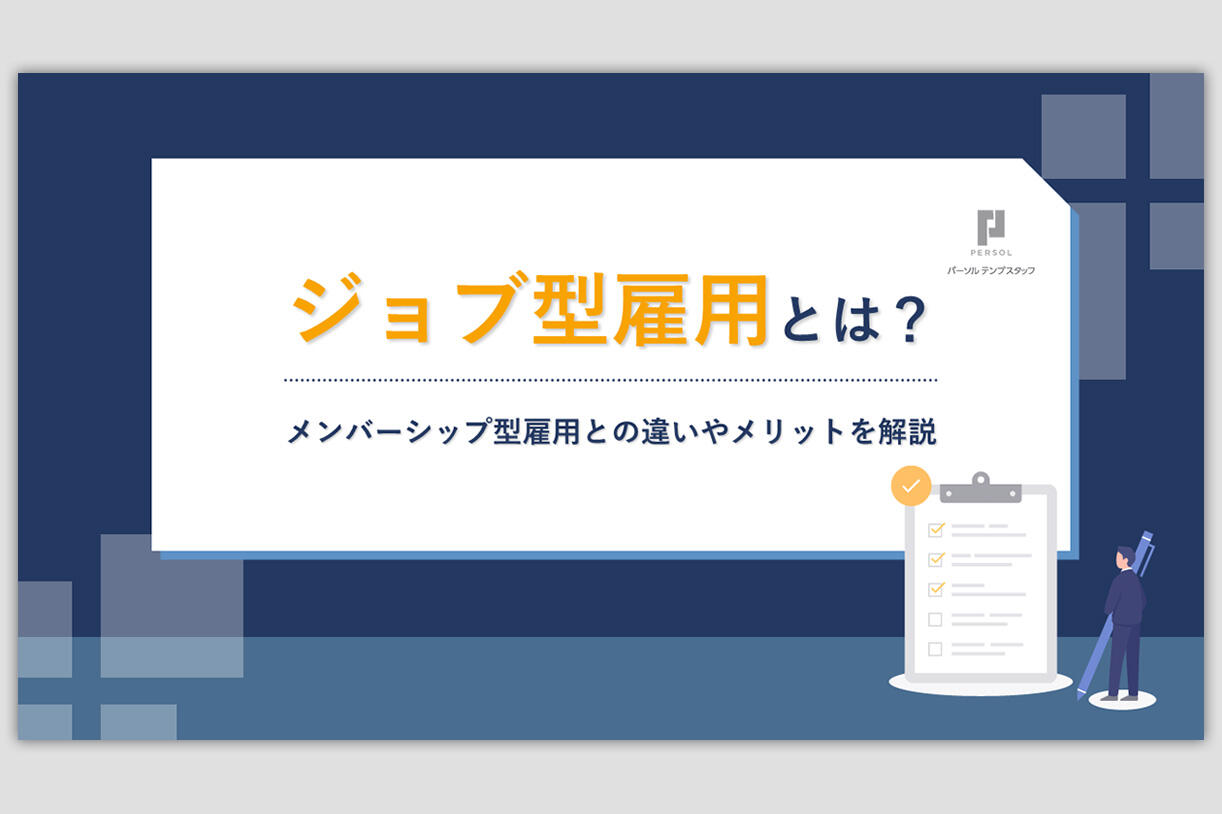HRナレッジライン
カテゴリ一覧
賃上げとは?企業に求められる背景と2025年の最新動向を徹底解説
公開日:2025.10.28
- 記事をシェアする

本記事では、賃上げの定義から始まり、実際の動向や政府の支援施策、そして企業が取り組む際のポイントや注意点を幅広く解説します。
賃上げを検討している企業の方はもちろん、労働者として給与事情を把握したい方にも役立つ情報をまとめました。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
賃上げとは
賃上げとは、企業が従業員の基本給や時給など給与水準を引き上げる行為を指します。
企業側はコスト増となる一方、従業員のモチベーション維持や人材確保、従業員の定着率アップにつながる重要な施策です。
優秀な人材を確保し続けるうえで、競合他社との給与水準比較は重要な要素の一つであり、労働市場が流動化している現在、賃上げ戦略は企業の生産性向上とも深く結びついています。
近年では給与以外の手当や福利厚生も含めたトータルな報酬設計が求められることが多く、賃上げをどのような形で実施するかが注目されています。
ベースアップと定期昇給の違い
賃上げには、ベースアップと定期昇給の2つの方法があります。
ベースアップは企業の業績や経済情勢、物価上昇率などを踏まえ、全従業員の給与を一律で引き上げる方法です。
一方、定期昇給は勤続年数やスキル、業務成果などを考慮し、個人別に昇給額を決定します。
一般的にベースアップは企業全体のモチベーションを高めやすいですが、財務負担が大きくなる点に留意が必要です。
定期昇給は個々の能力を評価しやすい反面、公平性の担保と評価制度の整備が課題になります。
定期昇給のメリット・デメリット
以下に定期昇給のメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 従業員のモチベーション向上 | 定期的な昇給により仕事への意欲が高まり、業務パフォーマンスの向上につながる。 |
| 従業員の定着率向上 | 企業の評価を示し、長期雇用を促進。離職率の低下が期待できる。 |
| 人材の獲得・維持 | 競争力のある給与体系を維持しやすく、優秀な人材の獲得につながる。 |
| キャリアパスの明示 | 昇給を評価基準の一つとし、キャリアパスを明示できる。 |
| 従業員の経済的安定 | 定期的な昇給により生活の安定を実現し、はたらく意欲が増す。 |
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 企業の財務負担 | 人件費の増加により、企業によっては財務的負担となる可能性がある。 |
| 昇給に対する期待の固定化 | 昇給が当然と考えられ、モチベーション低下のリスクがある。 |
| 業績と無関係な昇給のリスク | 業績連動無しで昇給が続くと、経営栄元の無駄とみなされる場合も。 |
| 昇給額の均一化 | 一律昇給だと、個々の業績やパフォーマンスが反映されにくくなる。 |
| 昇給のインフレ影響 | 物価上昇に追い付かず、実質賃金が下がる可能性がある。 |
最低賃金との関係性
最低賃金とは、法律で定められた労働者に支払うべき賃金の最低限度を指します。これにより、労働者が生活できる最低限の収入を保障することを目的としています。
賃上げと最低賃金は、労働市場や経済において互いに影響し合う関係にあります。 最低賃金は地域や産業によって異なりますが、最低賃金の引き上げは賃上げを促進し、逆に賃上げが広がることで最低賃金の水準も見直されることがあります。
賃上げ率とは
賃上げ率とは、労働者一人あたりの給与がどの程度引き上げられたかを示す指標です。
業界や企業規模、さらに企業の業績見通しなどによって変動し、個別の企業がどれだけ賃上げ実施できるかを判断する際の目安になります。
また賃上げ率は、以下の式を用いて計算されます。
賃上げ率 = (昇給後の基本給 - 昇給前の基本給) / 昇給前の基本給 × 100 (%)
【例】
- 元の給与:300,000円
- 賃上げ後の給与:315,000円
この場合、賃上げ率は以下のように計算されます。
賃上げ率 = (315,000 - 300,000) / 300,000 × 100 = 15,000 / 300,000 × 100 = 5%
この例では、賃上げ率は5%となります。
賃上げ率は、企業が従業員に対してどれだけ給与を増やしているかを示す指標であり、給与政策の一環として重要な要素です。
ただし、賃上げ率の高低だけでなく、給与体系全体の設計や評価制度とも組み合わせて考慮することが、従業員の納得感や企業の持続的成長を支えるポイントです。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
賃上げが求められる背景とメリット
近年の労働市場では優秀な人材の確保が難しくなっており、企業は優秀な人材を確保し、離職を防ぐために賃金を引き上げる必要性が高まっています。
また、物価や消費税の増税により、生活コストが上昇していることも背景の一つです。さらに、多様なはたらき方が進む中で、企業は魅力的な雇用条件を整える必要があり、賃上げは企業にとって重要な戦略となっています。
従業員満足度と人材確保への影響
多くの企業では優秀な人材の流出を防ぐために給与水準の見直しを行い、従業員満足度を高める施策を重視しています。賃金が上がることで、仕事への意欲ややる気が高まり、パフォーマンス向上も期待できます。
特に離職率の高い業界では、賃金アップが即戦力の確保につながる可能性が高いと言えます。さらに、賃上げ実施により企業のブランドイメージや社会的評価が向上することも、採用市場での優位性につながる大きなメリットです。
企業競争力向上と生産性アップ
企業の競争力は、社員の能力やモチベーションによって大きく左右されます。
企業が適正な賃金を支払うことは、従業員が安心して業務に打ち込める環境づくりにも寄与し、結果として生産性の向上を促す要因となるでしょう。
特に企業が継続的にベースアップや定期昇給を行うことで従業員の成長意欲も高まり、組織全体のレベルアップへつなげることができます。
賃上げ動向と政府の施策
景気や物価の状況、そして行政の支援策を背景に、賃上げのトレンドは大きく変化しています。ここでは最新の動向と政府の施策を中心に見ていきます。
2023年以降の賃上げトレンド 2025年は?
2023年は、大手企業を中心に賃上げの動きが活発化しました。日本労働組合総連合会が発表した「2023春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果」によると、平均賃上げ率は3.58%となり、2023年に初めて3%台を記録しました。これは、1994年以来の快挙です。(*1)
その翌年となる2024年の春闘でも、引き続き高水準の賃上げ回答が見られ、平均5.17%を記録しています。(*2)
さらに、2025年7月3日に発表された2025年春闘の最終集計では、基本給の底上げを目的としたベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げ率は5.25%となり、前年の5.10%を0.15ポイント上回りました。この水準は、1991年の5.66%以来、実に34年ぶりの高い水準です。
一方中小企業は4.65%となっており、その差が浮き彫りになっています。(*3)
また三大都市圏とそれ以外の地方圏を比較すると、地方でも賃金は上昇傾向にあるものの、コロナ禍を起点に賃金格差が再拡大しています。(*4)
なお、平均賃上げ率の上昇は4年連続となっています。
※参考:
*1「未来につながる転換点」となり得る高水準の回答 ~2023 春季生活闘争 第 7 回(最終)回答集計結果について~
*2中小の奮闘で定昇除く賃上げ分 3%超えが続く! ~2024 春季生活闘争 第 5 回回答集計結果について~
*3【重点分野-2】2025 春季生活闘争 まとめ ~評価と課題~
*4地域課題分析レポート(2025年冬号) ~地域における賃金の持続的な上昇に向けて~
構造的な賃上げ推進と行政支援
政府が推進する「構造的な賃上げ」とは、主に政策的な手段を通じて労働市場の賃金水準を持続的に引き上げることを目指す取り組みを指します。
これは単なる一時的な賃上げを超えた、長期的な視点での賃金改善を意味します。
構造的な賃上げの実現を目的の1つとして、2025年3月には「三位一体の労働市場改革の指針」が提唱されました。
日本経済の持続的な成長と国民の所得向上を目指すための政策で、「リスキリングによる能力向上支援」「ジョブ型人事(職務給)の導入」「成長分野への労働移動の円滑化」の3つの柱で構成されています。
以下の記事もぜひ参考にして下さい。
>>リスキリングとは?導入による企業のメリットと注意するポイントを解説
>>ジョブ型雇用の概要とメリット、導入するまでの流れをご紹介
賃上げ実現のための企業の取り組み
実際に賃上げを行うには、コストだけでなく事業全体を見直す必要があります。
生産性向上策や国の助成制度を活用するなど、無理なく賃上げを実現しましょう。
企業が負担を増やさずに賃上げを行うためには、まず自社の業務フローや無駄なコストを確認し、改善することが第一歩となります。作業の重複や情報共有の不備などが見つかれば、プロセス改革によって余剰コストを削減し、その一部を人件費に充てることが可能です。
また、賃上げを成功させるためには、新規事業開発や営業戦略の強化など、経営全体の収益拡大策も不可欠です。助成金や税制優遇を組み合わせて活用し、企業体質の強化と従業員への還元を両立させることが賃上げ実現の鍵となります。
業務プロセスの最適化と効率化
業務プロセスを最適化することで労働時間の削減を図り、生産性を向上させる取り組みは賃上げを持続的に行う基盤作りにつながります。
例えば、ITシステムの導入や業務の自動化により、定型業務を効率化することが可能です。
さらに、部門間や従業員間の情報共有をスムーズにするコミュニケーションツールを活用すれば、意思決定スピードを上げつつ無駄なコストを削減できます。
収益力強化策の実施
賃上げを継続的に実施するためには、売上と利益を高める施策が欠かせません。
新商品や新サービスの開発、海外市場への進出など、多角的な戦略を展開することで事業の成長性を高め、社員に安定した賃金を支払う余力を確保できます。
併せて、既存顧客の満足度を高める施策を実施することで、リピート率向上と収益の安定化を図ることも重要です。
賃上げ促進税制と助成金活用
国が用意している賃上げ促進税制や助成金制度を活用することで、企業が負担するコストを軽減できます。
決められた要件を満たせば税額の一部を控除できる仕組みや、従業員の給与を一定率以上引き上げた企業に対して補助金が交付される制度など、多様なメニューが用意されています。
ただし、それぞれの制度に適用条件が細かく定められているため、事前に情報収集を行い、自社に合った制度を見極める必要があります。
中小企業向け税制優遇のポイント
中小企業が賃上げを行った場合に受けられる税制優遇策には、税額控除率の上乗せなどがあります。(*5)
一定の賃上げ率を達成することが条件となるケースが多いため、事前に具体的な給与改定計画を立てておくとよいでしょう。さらに、社員の職業訓練やスキルアップを実施し、生産性向上と賃上げを組み合わせると、追加の税制上のメリットを得られる場合もあります。
助成金の種類と申請方法
厚生労働省を中心に用意されている複数の助成金パッケージは、対象となる企業規模や業種、賃上げ率や雇用形態など細かい条件によって要件が変わります。
基本的にはハローワークや各地方自治体の労働局などに申請書類を提出し、審査を経て助成金を受給します。
必要書類は給与規定の改定内容や人材育成計画など多岐にわたるため、早めに準備を始め、正確な運用と報告が求められます。
賃上げ実施時の注意点と企業が抱える課題
賃上げによって企業が得られるメリットは大きい反面、財務面や人事管理の難しさなどさまざまな問題も生まれます。ここではそれらの課題と解決策を解説します。
賞与や新卒採用への影響・対策
賃上げによって基本給が上がると、賞与の計算に影響が出る場合があります。
従業員にとってはプラスですが、企業側からすると予想以上に人件費が膨らむリスクがあるため、適切な賞与の算定基準や支給方針を設ける必要があります。
また、新卒採用においては給与水準の引き上げが競合他社との比較材料となり、優秀な学生を確保しやすくなります。また、採用予算全体の見直しも併せて行うとよいでしょう。
コスト増加を抑える
賃上げを実施すると企業の固定費が増えるため、事業計画の見直しやキャッシュフローのマネジメントが必須となります。特に、景気変動に左右されやすい業種では継続的に賃上げを実施できる体力を維持することが課題です。
社会保険や福利厚生費用の増加を最小限に抑える工夫として、各種補助金や税制優遇の活用だけではなく、働き方改革を進めることで業務効率を高め、長時間労働を削減する取り組みが挙げられます。
また、評価制度の明確化により、無駄なコストを削減しながら優秀な人材には公正な報酬を支払うというバランスを保つことが重要です。結果として、企業の負担を最小限に抑えつつ、従業員満足度を向上させることができます。
従業員への周知
給与テーブルの変更に伴い、従業員の評価や管理システムの再構築が必要となるケースも多く見られます。
従業員とのコミュニケーション不足による不満や混乱が発生しないよう、十分な説明や合意形成を行うことが重要です。
賃上げについてよくある質問
ここでは賃上げに関するよくある疑問をご紹介します。疑問を解消し、よりスムーズに賃上げを実施しましょう。
Q1.賃上げ促進税制とはなんですか?
賃上げ促進税制とは、従業員の給与を一定以上引き上げた企業に対して税制上の優遇措置を認める制度です。例えば、企業が達成した賃上げ率に応じて税額控除を受けられるなど、直接的なコスト軽減につながります。具体的な要件や控除率は企業規模や賃上げ率などによって異なるため、事前に制度の詳細を確認することが重要です。
Q2.2025年の平均賃上げ率は?
2025年春闘の最終集計では、基本給の底上げを目的としたベースアップ(ベア)と定期昇給を合わせた平均賃上げ率は5.25%となり、前年の5.10%を0.15ポイント上回りました。一方で中小企業は4.65%となっており、その差が浮き彫りになっています。
Q3.賃上げを実施する際に注意することは?
賃上げを実施する際には、就業規則を適切に改定し、従業員に対してその内容や背景、目的を丁寧に説明することが不可欠です。
また、好き勝手に全員の給与を上げるだけでは企業財務が圧迫される可能性が高いため、評価制度や業務改革と併せて慎重に進める必要があります。従業員とのコミュニケーションを密に行い、相互理解と合意を得ることで、賃上げによる組織活性化と従業員満足度の向上を両立できるでしょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
まとめ
賃上げは企業のコスト負担増を伴いますが、従業員満足度の向上や人材確保、企業全体の競争力強化につながります。ベースアップや定期昇給の形態の違い、最低賃金や税制優遇策との関係などを踏まえ、企業の財務状況と将来の成長戦略に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
また、行政の施策を活用しながら業務プロセスの効率化や収益力の強化を図ることで、無理のない賃上げを継続できる体制を整えることが求められます。
今後も少子高齢化や物価上昇など、外部環境の変化に伴い、賃上げの必要性が高まる可能性が十分にあります。正しい情報収集と計画的な対策により、企業と従業員双方が成長できる道を築いていきましょう。
人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする