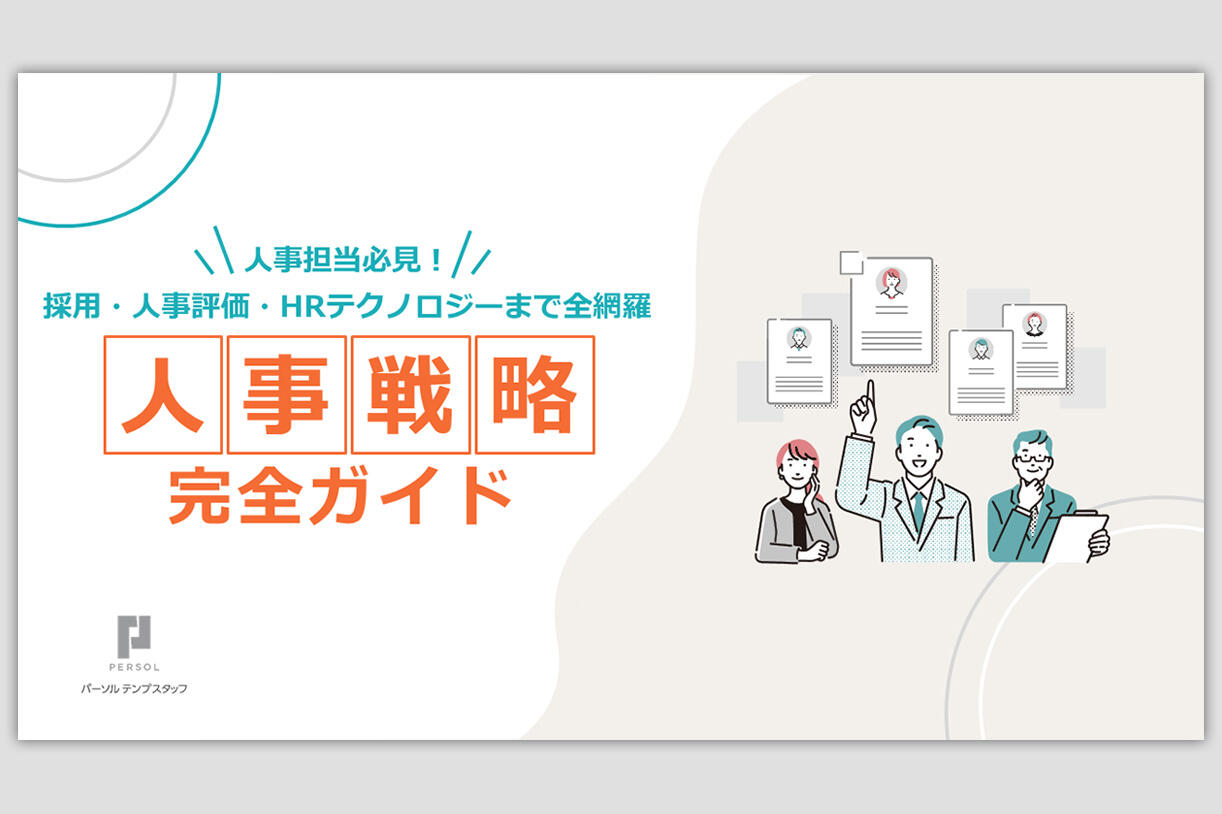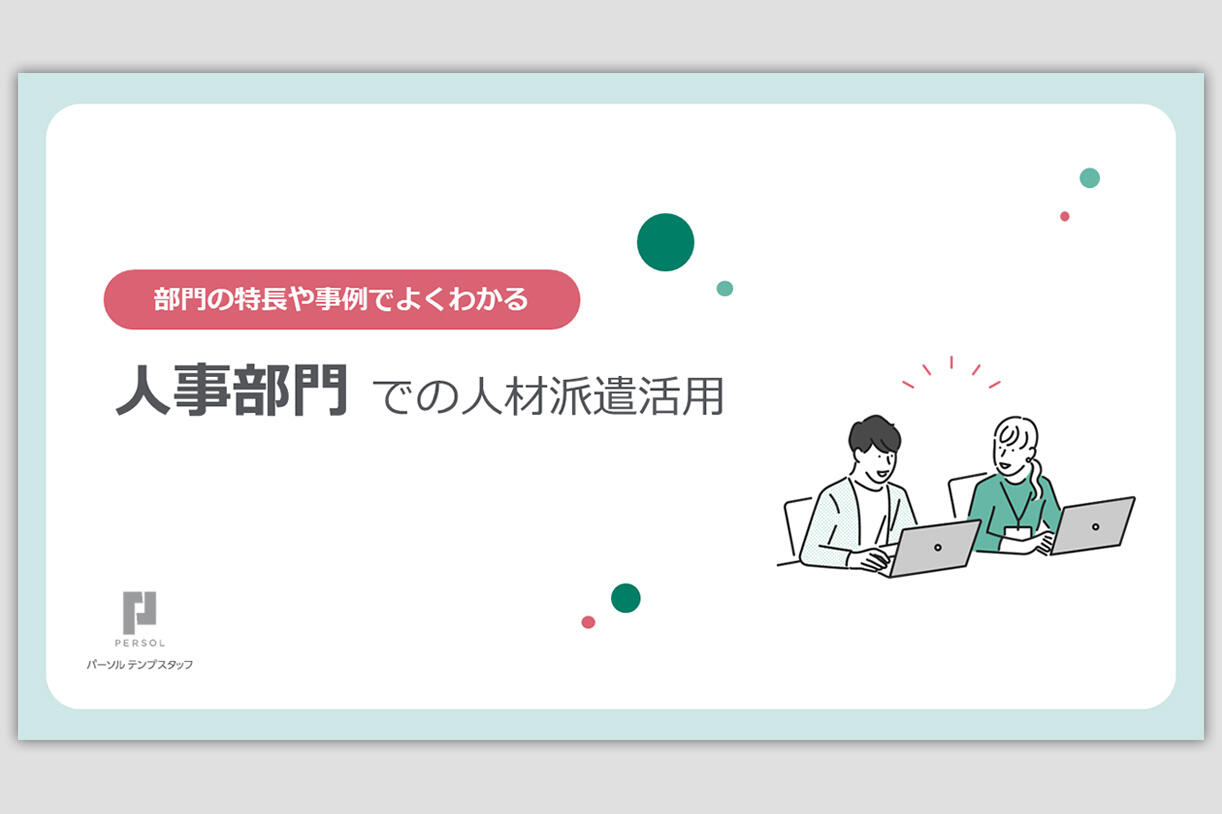HRナレッジライン
カテゴリ一覧
人事評価制度とは?導入する目的やメリット、設計方法について解説
- 記事をシェアする

人事評価制度とは、社員のはたらきぶりやスキル、自社への貢献度合いなどを評価し、給与や処遇などに反映する仕組みのことです。それだけでなく、適正な人事評価を実施することで社員の育成や定着、さらには企業の成長にもつながります。その一方で、公平な評価ができなければ社員の中で不満が募り、モチベーション低下の要因になってしまうことも事実です。
本記事では、人事評価制度の概要や目的はもちろん、評価制度の種類や導入するメリット・注意点などについて解説します。ぜひ、参考にしてみてください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
人事評価制度とは
人事評価制度とは、企業が社員のパフォーマンスやはたらきぶり、スキルを査定し、給与や昇格・降格などに反映させる仕組みを指します。
公平な人事評価制度を構築することで社員のモチベーションを高めていくだけでなく、人材の育成や定着、さらには業績の向上などにつなげていきます。加えて、企業が設定する目標に対してどのように行動して成果を残したか、社員が将来成長する可能性や得手・不得手を把握するのにも役立ちます。
人事制度の概要については、こちらの記事でご説明しています。
>>人事制度とは?種類や設計方法、ポイントについて分かりやすく解説
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事評価制度を導入する目的
給与や役職に反映するなど、人材を評価するだけの仕組みが人事評価制度ではありません。運用することにより、企業経営にさまざまな効果をもたらします。人事評価制度を導入することで、主にどのような目的が果たせるのかをご紹介します。
社員の配置の最適化
人事評価を実施することは、企業にとって社員のスキルや能力を把握する機会になります。その評価に基づいて役職・役割の見直し、人材配置の最適化を図れるでしょう。管理職に向いている人材はリーダーへ抜擢、能力を発揮できていない人材は適切な部署へ再配置するなど、社員の配置転換を考える際に役立ちます。
社員の処遇の決定
人事評価制度を確立し、公平かつ透明な評価を行うことで、社員の処遇に対する根拠を明らかにできます。根拠がないまま社員の処遇を決定すると「頑張っているのに給与が上がらない」「なぜ、他の社員と待遇差が発生するのか?」と、企業に対する不信感につながることがあります。しかし、社員の能力や貢献度などを客観的に評価することで、社員は自身の処遇に納得できます。
社員育成への活用
客観的な視点で社員の成果や能力を可視化する人事評価制度は、人材育成に活用できます。まず、明確になった社員の強み・弱みに応じて業務を調整するマネジメントができるようになります。また、社員の課題に応じて個々の成長を支援するための教育・訓練プログラムを効果的に実施することもできるでしょう。
組織の目標達成
人事評価制度の評価項目には、会社の経営方針や目指す方向性が色濃く反映されます。「どのような会社を目指しているのか?」「どのような人材に育ってほしいのか?」といったビジョンを明文化して共有することで、企業理念に沿った行動を社員に促すことができます。
人事評価制度の構成
人事評価制度は企業の成長を支える重要な要素です。主に報酬制度、評価制度、等級制度の3つで構成され、これらが組み合わさることで、公平で効果的な人事管理が実現します。それぞれの制度と目的について解説します。
報酬制度
報酬制度は仕事への成果や貢献度に応じた給与やボーナスを決定するための仕組みです。具体的には、基本給、業績に基づくボーナス、インセンティブ、手当などが含まれます。報酬制度の目的は、社員のモチベーションを高め、業務に対するパフォーマンスを向上させることです。
評価制度
評価制度は業績や行動を体系的に評価するための仕組みです。評価制度の目的は社員に対するフィードバックを提供し、成長の機会を作ることです。また、評価結果は報酬の決定や昇進、キャリア開発の基準となります。
等級制度
等級制度は、「職務」、「職能」、「役割」などレベルや責任に応じたキャリアパスを設定するための仕組みです。等級制度の目的は、社員を複数の等級に分類し、昇進や役職の基準を明確にすることです。これにより、キャリアパスの透明性を高め、社員の成長を促進するとともに、適切な人材配置や育成を行いやすくします。
人事評価制度の種類と具体例
人事評価制度にはさまざまな種類があります。それぞれの特徴を把握した上で、自社に合った評価方法を選ぶことが大事です。
MBO(目標管理制度)
MBO(目標管理制度)とは、社員が自主的に目標を決めて会社と認識を共有し、その目標をどのくらい達成したか評価する人事評価制度です。目標の内容は上司や同僚と話し合い、企業の目標とすり合わせて決めます。企業と目標の統一を図り、個人の目標達成が企業の目標達成へ貢献するように設計することで、組織との一体感を高めます。
この手法は社員本人が目標の設定をすることで自主性が芽生え、モチベーションや職務遂行能力の向上につながる点が特徴です。
評価期間をどう設定するかは業務によって異なります。1年ごとなど評価期間が長い場合、中間面談などでまめに状況を共有すると業務フォローが可能になります。逆に、期間が短過ぎると評価が難しくなってしまうでしょう。
OKR(目標と成果指標)
OKRはMBOと同様に、企業の目標を個人の目標に落とし込んで設定する人事評価制度です。MBOは人事評価や査定が主な目的ですが、OKRは組織全体の生産性向上や社員育成が目的です。また、OKRの目標はMBOより高めに目標を設定することが一般的で、MBOは100%の目標達成を目指す一方、OKRは60~70%の達成で成功とします。評価は1~3ヶ月のペースで頻繁に行われ、四半期にひとつの目標を設定することが原則になっています。
OKRについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>OKRとは?KPIやMBOとの違いや導入するメリットを解説
コンピテンシー評価
コンピテンシーとは、高い成果を上げている社員に共通する行動特性を指します。その行動特性を基準に評価項目を設定し、評価を行う人事評価制度の手法をコンピテンシー評価と呼びます。
コンピテンシー評価は、企業に貢献している社員にインタビューなどを行い、どのような行動を取っているか分析した上で評価項目とします。社員にとっては理想とされるモデルとのギャップや、自分の立ち位置などが把握でき、成長につながる具体的な行動をイメージしやすくなるため、人材育成の面でも有用といえます。
ただし、規範となる社員の行動特性をしっかりと分析しないまま運用してしまうと、期待する効果が得られない成果にもつながってしまいます。評価項目を定める際は、入念にヒアリングを行うことが重要です。
コンピテンシー評価については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>コンピテンシー評価とは?4つのメリットと留意点を解説
360度評価
「360度」という言葉の通り、上司からの評価だけでなく、同僚や部下、顧客などさまざまな立場の人が多面的に評価を行う手法です。偏りのない多角的な視点から下される評価は、上司だけでは見えていない社員の強みや弱み、特性を客観的に把握でき、公平性が高くなります。また、評価される本人に高い納得感を与えることができます。
一方、360度評価は評価に慣れていない社員も評価に関わります。評価する人が評価に関する知識を持っていないことも多いため、評価基準を明確にしておかないと精度が低くなる可能性もあります。
人事評価制度を導入するメリット
人事評価制度を正しく導入することで、企業は多くのメリットを得られます。主なメリットとして、以下の4つが挙げられます。各メリットについて詳しく解説します。
企業理念の浸透
人事評価制度導入するメリットとして、企業の価値観やビジョンを示し、社員に浸透させることができる点が挙げられます。特に、企業の理念に即した行動指針を評価項目に組み込むと、社員に具体的な行動を促せます。社員が企業理念やビジョンをしっかり理解し、共有すれば、組織全体が一丸となって目標に向かえるでしょう。
生産性の向上
人事評価制度の導入により、社員に対する定期的な評価とフィードバックが行われます。その結果、各社員が自身の強みを理解し、さらには弱点を改善することで、業務において能力を発揮しやすくなります。これにより個人のパフォーマンスは向上し、ゆくゆくは組織全体の生産性向上が期待できるでしょう。
生産性の向上については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
定着率の向上
企業に貢献しているにもかかわらず社員自身の頑張りが評価されなかった場合、不満を感じる社員も出てくるでしょう。離職率の上昇につながる恐れもあります。
しかし、適切で透明性の高い評価制度を運用し、評価に見合う給与が与えられれば、社員のモチベーションアップにつながります。また、正当に評価されていると感じることで企業への信頼感が増し、定着率の向上が期待できます。
定着率の向上については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
キャリア開発の支援
人事評価制度では社員のスキルや能力を把握できます。評価面談時に適切な評価やフィードバックを行うことで、社員のスキル向上が望めるでしょう。さらに、社員に対する適切なトレーニングプログラムやキャリアパスの提供によって、長期的な成長とキャリア発展が支援できます。
キャリア開発の支援については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>キャリアデザインの目的やメリットは?企業の取り組み方をご紹介
人事評価制度の見直す際のポイント
人事評価制度を運用するにあたって、いくつか注意しておくべき点があります。人事評価制度を見直す場合、押さえておきたいポイントを解説します。
会社のビジョンや理念に沿った評価制度になっているか
人事評価制度の内容が企業のビジョンや理念に沿っていなければ、社員のはたらきぶりとズレが生じてしまいます。組織の方向性と差異のある努力をしても、企業に貢献できません。人事評価制度は企業の理念に基づいて「どのような仕事をするべきか」を明確にし、評価項目として設定しましょう。
評価基準が明確化されているか
人事評価制度は評価する項目や基準を明確にし、社員にとってわかりやすいものになっていることが重要です。評価基準が曖昧だと、社員は自分がどのような基準で評価されているのか分からなくなってしまい、「あの人より自分の方が頑張っているのに」といったネガティブな感情を生み出しかねません。その結果、人事評価制度ならびに組織への信頼感を失う恐れがあります。誰もが評価の内容に納得できるように統一的な評価基準を設け、可視化した上で社員に説明しましょう。
等級と報酬が連動するような設計になっているか
社員がパフォーマンスを発揮し人事評価が高いにもかかわらず、給与が変わらなかった場合、社員は制度に対して不満や疑問を持つだけでなく、モチベーションの低下まで招いてしまうかもしれません。等級と給与の関係を明確にしておき、連動させることで、公平な評価を行うことができます。
定期的な見直しの機会を設定しているか
人事評価制度は、事業の拡大・縮小や社員の増減、企業を取り巻く状況の変化などに大きく影響を受けることがあります。それらの変化に応じて評価基準や方法を定期的に調整し、制度の効果を最大化することが重要です。また、人事評価制度を見直す際は社員からのフィードバックを取り入れ、制度の透明性と公平性を維持しましょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事評価制度を設計して企業成長につなげる
人事評価制度は企業が社員のはたらきぶりを評価し、給与や等級など処遇を決定する制度です。さらに、企業の理念やビジョンに沿って評価項目を設定することで、人材育成の効果や企業全体の生産性向上にも大きく寄与します。
ただし、制度の内容が自社の理念に沿っていないなど運用方法が不適切だと、社員の不満やモチベーション低下など問題を生じさせてしまう恐れもあります。加えて、適切な人事評価を行うためには企業を取り巻く環境の変化に対応し、定期的に制度を見直すことも必要でしょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする