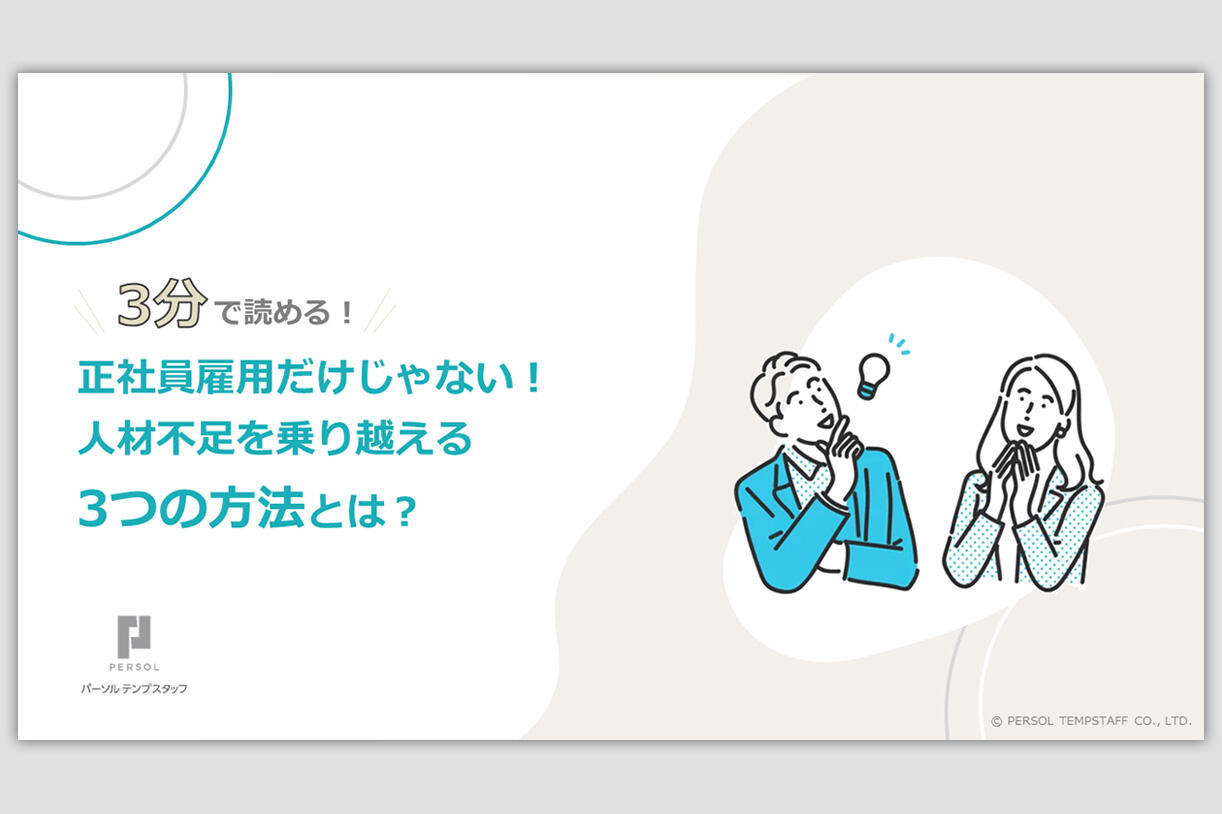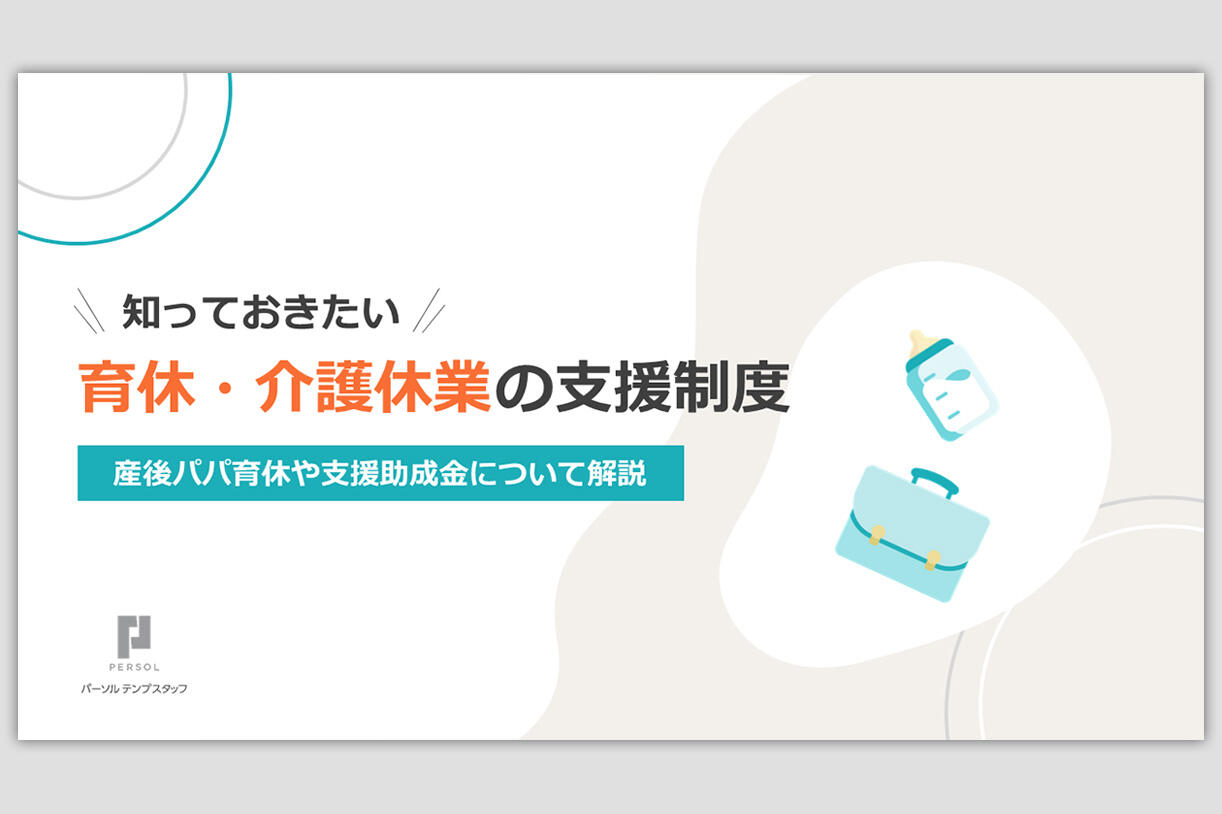HRナレッジライン
カテゴリ一覧
ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説
- 記事をシェアする

はたらき方に対する価値観の多様化によって「ワーク・ライフ・バランス」が重要視されています。ワーク・ライフ・バランスは社員の幸福や健康などに結びつくのと同時に、企業にも重要な課題の一つとして位置付けられています。本記事では、ワーク・ライフ・バランスの定義と共に企業が取り組むメリットや導入時の留意点などをご紹介します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
ワーク・ライフ・バランスとは
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活が調和した状態のことです。2007年12月に内閣府が策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」によると、仕事と生活の調和が実現した社会について以下のように定義しています。
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
ワーク・ライフ・バランスというとプライベートにばかりフォーカスされがちですが、決して「仕事の手を抜いてプライベートを充実させる」という意味ではありません。「仕事と生活を両立させ、双方の充実を目指すはたらき方・生き方」を指します。
ワーク・ライフ・インテグレーションとの違い
ワーク・ライフ・インテグレーションとは「仕事と生活を統合し、どちらも充実させる」という意味です。ワーク・ライフ・バランスと似た概念ですが、こちらは仕事と生活の境界をなくして双方が相乗するという考え方を指しています。具体的にはフレックスタイム制やテレワークなどを整備し、はたらく時間・場所を柔軟にすることです。
仕事と生活を明確に線引きし、双方のバランスを調整することで豊かな暮らしを目指すワーク・ライフ・バランスとはその点が異なります。
ワーク・ライフ・マネジメントとの違い
ワーク・ライフ・マネジメントとは、個人が仕事と生活を適切に管理することで双方を充実させるという考え方です。企業が主体になり、個人の仕事と生活のバランスの調整を実施するのがワーク・ライフ・バランスです。一方のワーク・ライフ・マネジメントは、自らの努力で仕事や生活の質を高めようとする姿勢が特徴です。つまり、社員が受け身の姿勢ではなく、社員自身が主体的に進めていく点がワーク・ライフ・バランスとは異なります。
ワーク・ライフ・バランスの歴史
ワーク・ライフ・バランスは1980年代後半にアメリカで生まれた概念です。家庭に専念していた女性たちの社会進出が進み、仕事と家事・育児との両立が難しくなってきたため、はたらく女性の負担の軽減や保育支援などの取り組みなど各企業はさまざまな支援を行うようになりました。
日本では1990年代以降からワーク・ライフ・バランスが意識されるようになったといわれています。雇用環境の悪化、男女雇用機会均等法の施行などに伴い、徐々にはたらき方に対する価値観が多様化したことがきっかけだといえます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
ワーク・ライフ・バランスの目標
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」によると、「仕事と生活の調和が実現した社会」とは以下の3つを兼ね備えたものと定義しています。
就労による経済的自立が可能な社会
経済的自立を目指す人、そのなかでもとりわけ若者が精力的にはたらける社会を目指します。就労によって結婚や子育てなど、暮らしのための経済的基盤の確保を実現できる社会が理想です。
健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
社会ではたらく人々の健康が維持されることを目指します。さらに、家族・友人と過ごす充実した時間、自己啓発や地域活動に参加するための時間などが持てる豊かな生活を実現していきます。
多様なはたらき方・生き方が選択できる社会
性別や年齢などにかかわらず、誰もが自分のやる気や能力を持ってさまざまなはたらき方や生き方にチャレンジできる社会の実現が目標です。さらに子育てや親の介護を行う時期は、個人の置かれた状況に合わせた多様で柔軟なはたらき方が選択でき、不公平な処遇がされない社会の実現を理想としています。
ワーク・ライフ・バランスを取り組むことによるメリット
ワーク・ライフ・バランスに取り組むことにより、社員のみならず企業にとっても大きなメリットがあります。それぞれのメリットについて一つずつ見ていきます。
多様なはたらき方に対応
女性の社会進出の取り組みとして、育児と両立しながら仕事を続けられる環境づくりは急務です。ほかにも、コロナ禍によってテレワークや在宅勤務が広まり、はたらき方に対する価値観は多様化しています。「親の介護と両立したい」「自分の好きな時間・場所ではたらきたい」「複数の仕事をしたい」といったニーズに合わせた環境を提供することで、今まではたらきたくてもはたらくことのできなかった人の雇用につながります。
少子高齢化や人口減少が進み、慢性的な人材不足に陥る企業にとって、人材の離職を防ぐという意味でも大きなメリットがあるでしょう。
ダイバーシティについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>ダイバーシティ推進の盲点!必要性と成功するための取り組み事例を解説
はたらく社員のモチベーション向上
ワーク・ライフ・バランスを推進すると、仕事と生活のバランスが調整されます。柔軟なはたらき方を取り入れることで、社員の長時間労働や休日出勤は見直され、プライベートも充実しやすくなります。その結果、はたらく社員の仕事へのモチベーションアップが期待できます。
社員のモチベーション向上について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>声かけでメンバーのモチベーションをあげる!効果的な言い換えや声かけのポイントを解説
社員定着率の向上
慢性的な人材不足が深刻化する昨今、ワーク・ライフ・バランスの実現ではたらきやすい環境づくりを行うと社員の満足度は高まり、社員定着率の向上が見込めます。また、育児や介護などライフステージに合わせた環境を提供することで、離職率の低下も期待できます。
さらに、ワーク・ライフ・バランスを重視する企業文化は数多くの入社希望者が集まる要因になり、企業にとって大きなメリットだといえるでしょう。
社員定着率の向上について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
人材採用時の企業イメージ向上
厚生労働省は、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業をホワイト企業として認め、公的な証明をする「安全衛生優良企業公表制度」を設けています。
この制度で認定を受ければ、ワーク・ライフ・バランスを推進した企業として公表することができます。また、その認証マークは3年間の使用が可能で求人広告にも付けられるため、人材採用時の企業イメージの向上に効果が期待できます。
中小企業の採用について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>中小企業が採用を成功させるポイントを徹底解説
ワーク・ライフ・バランスを推進する際の留意点
ワーク・ライフ・バランスの推進には多くのメリットがあります。その一方で、新しい制度や施策を実施する際に気を付けておきたい留意点を4つ解説します。
慎重に制度の導入を行う
ワーク・ライフ・バランスの推進は、必ずしもすべての社員から歓迎されるとは限りません。労働時間の短縮によって残業代が減り、不満を抱く人が出てくる可能性もあります。つまり、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた急激な制度導入は社内に混乱を招きかねません。
制度導入時は検討を重ね、社員にとって本当に必要な制度を計画することが重要です。加えて、トライアル期間を設けるなど段階的に制度を導入し、そこから徐々に範囲を広げていきましょう。
制度の見直しや新規導入を定期的に行う
ワーク・ライフ・バランスの取り組みは、制度を一度導入したら終わりというわけではありません。この取り組みは即座によい結果が表れるものではなく、導入後も制度の効果を検証する体制を維持することが重要です。制度を導入・実施したことにより、どのような効果が得られたのか、うまくいっていない場合は、施策のアプローチ方法を変える必要はないか、など次の改善アクションを考えることも求められます。
このような制度の見直しを怠るとあらたな課題に対処できなくなり、社員の満足度が低下する恐れがあります。定期的な評価や社内アンケートなどで感想を集め、制度の改善やあらたな制度導入を繰り返しながら取り組みを進めていきましょう。
各制度を利用しやすい環境作りをする
ワーク・ライフ・バランスを実現するためにあらたな制度や施策を実施しても、利用する社員が少なく、結果的に形骸化してしまうケースは少なくありません。
制度の運用において、まずはすべての社員がその情報を取得しやすい環境にしておくことが重要です。加えて、制度が浸透するまでは経営陣や管理職が自ら率先して制度を活用し、その制度が利用しやすい雰囲気を整えておくことも大事です。
ワーク・ライフ・バランスについての教育機会の提供
ワーク・ライフ・バランスに関しては、「仕事量を減らしてプライベートを充実させる」「女性のためだけの施策」という誤解が生じることがあります。このような認識を正すためにも、制度導入の際は取り組みの目的やワーク・ライフ・バランスの重要性などを社内に周知しておく必要があります。
具体的には、時間管理や目標管理、ストレス管理、コミュニケーションスキルなどを向上させるためのワークショップやセミナーを実施するなど、認識のアップデートを促していくことが大切です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
ワーク・ライフ・バランスの概要や注目されている背景を知る
ワーク・ライフ・バランスとは、はたらく人の仕事と生活が調和した状態のことです。育児や介護といったライフステージの変化やはたらき方に対する価値観の多様化に合わせ、一人ひとりの事情に応じた環境づくりに取り組む企業が増えています。
この取り組みは社員だけでなく、企業にとっても「社員のモチベーション向上」「社員定着率の向上」などさまざまなメリットが期待できます。本記事でご紹介した導入時の留意点などを参考に、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組みを検討しましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする