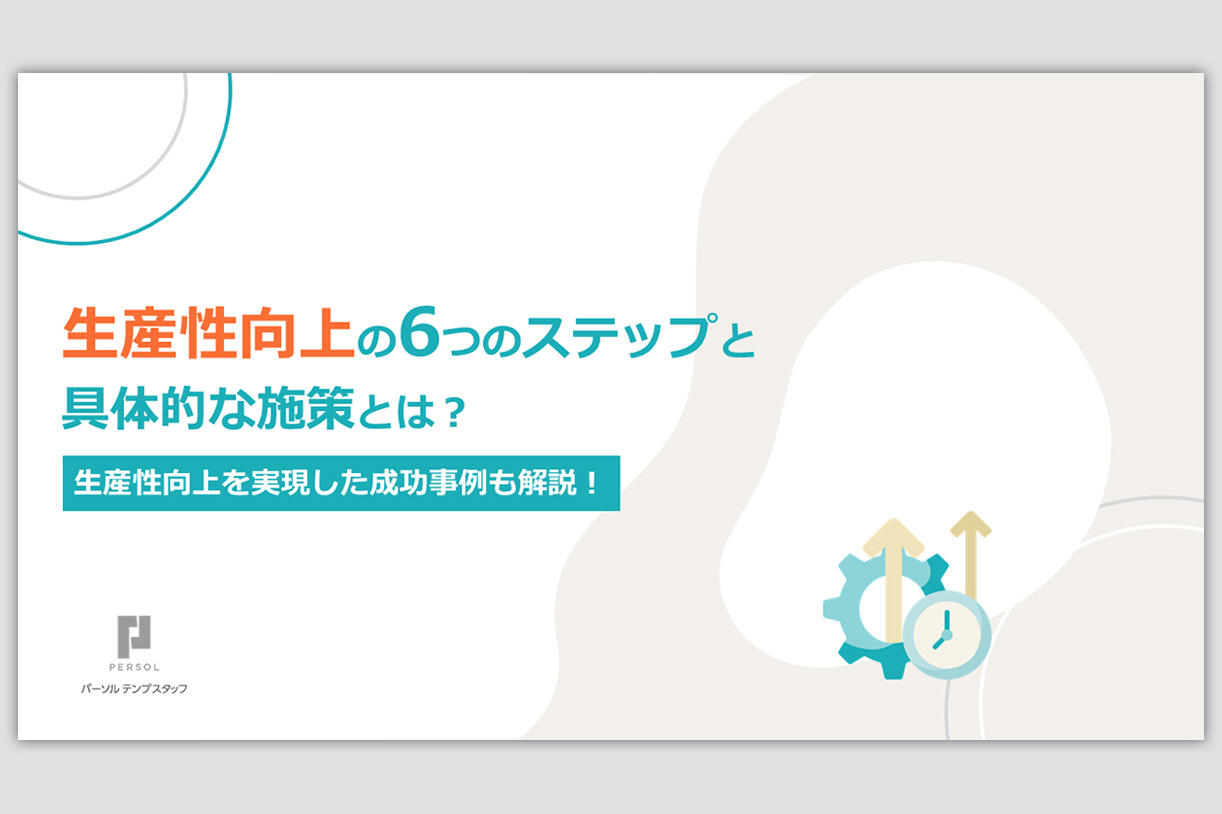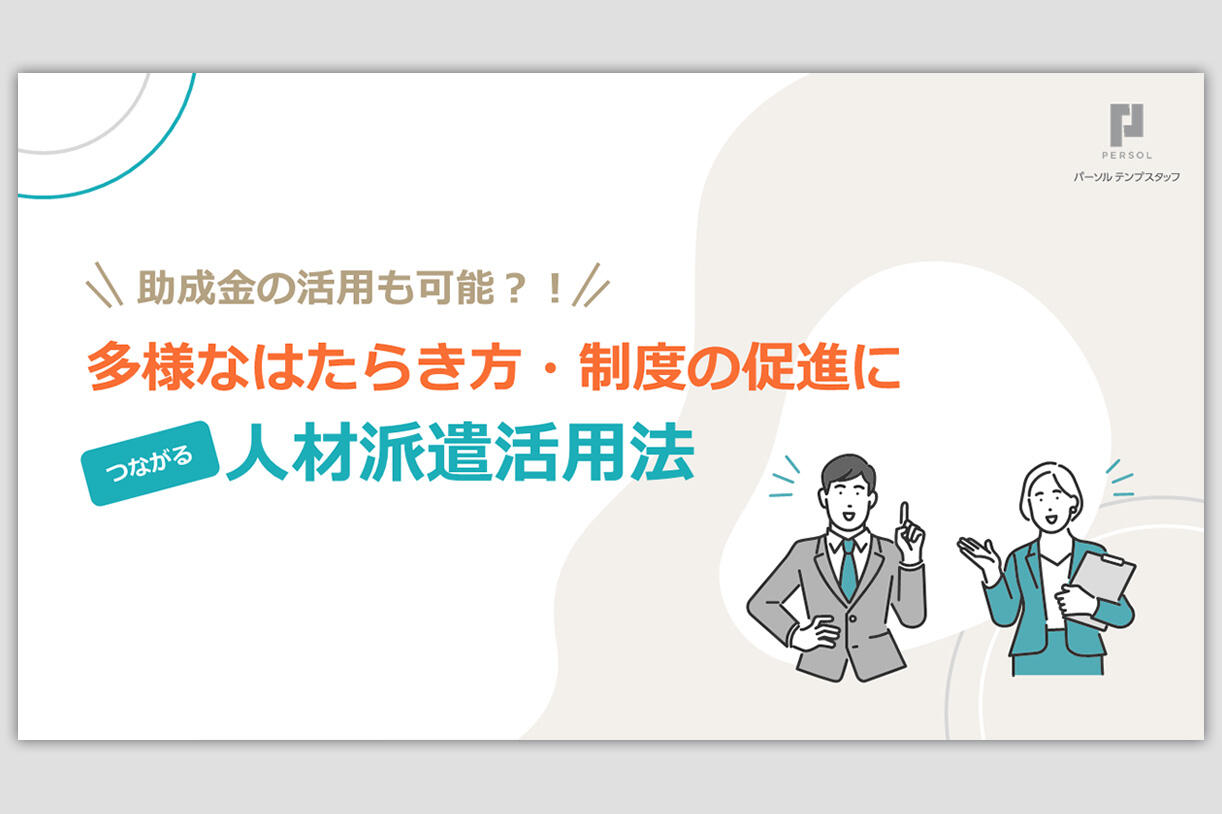HRナレッジライン
カテゴリ一覧
フレックスタイム制とは?目的や導入する際のメリットや留意点をご紹介
- 記事をシェアする

はたらく場所や時間を自由に選択できるはたらき方が増えている近年、フレックスタイム制を導入する企業も少なくありません。
子育てや介護などライフステージの変化によるはたらき方の変化に柔軟に対応できることはもちろん、社員それぞれの自由なはたらき方にも対応できます。
本記事では、フレックスタイム制の目的や導入メリット、導入時のポイントについて解説していきます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は、一定の期間においてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、その日の始業時刻・終業時刻・労働時間を社員が自由に設定できる制度です。社員は仕事とプライベートの調和を図りながらはたらくことができます。一般的には、必ず勤務しなければならない時間帯である「コアタイム」と始業・終業時間を自由に調整できる時間帯の「フレキシブルタイム」の2つの要素から成り立つ制度です。
フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。コアタイムを設定しないことによって、社員がはたらく⽇も自由に選択できるような制度を作ることも可能です。また、フレキシブルタイムでは一時離脱など、労働時間ではない時間を途中に差し込むことが可能です。

※引用:厚生労働省|フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
フレックスタイム制の目的
導入している企業も多いフレックスタイム制ですが、その目的は、社員のワーク・ライフ・バランスの向上が主な目的です。さらに社員のワーク・ライフ・バランスの向上によって、企業の生産性が高まることにも期待されています。
ワーク・ライフ・バランスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説
時差出勤との違い
フレックスタイムに似た制度に、時差出勤があります。時差出勤は決まった勤務時間帯をずらして出勤する制度で、一日の勤務時間の長さは変わりません。一方フレックスタイム制は、社員が自分で始業・終業時間を自由に設定できます。時差出勤は企業が設定した時間帯に従うのに対し、フレックスタイム制は社員それぞれが始業・終業時間の設定を任せられているという違いもあります。
時差出勤については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>時差出勤を企業が導入する際のポイントやメリットについてご紹介
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
フレックスタイム制を導入するメリット
近年多くの企業が導入するフレックスタイム制ですが、フレックスタイム制を導入することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
生産性の向上
まず、社員それぞれが集中力を最も発揮できる時間帯にはたらけることがメリットです。自身がはたらきやすい時間に業務が行えるため、質の高い成果を挙げられます。また、通勤ラッシュを避けられるため出社時のストレスが軽減され、仕事への集中力の向上も期待できるでしょう。
生産性を向上させるための方法、助成金などについてこちらの記事で詳しく解説しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
柔軟なはたらき方の実現
フレックスタイム制を導入すると、社員それぞれが自分のライフスタイルに合わせたはたらき方を実現できるため、ワーク・ライフ・バランスが向上します。例えば、育児や介護を行っている社員がそれぞれのはたらきやすい時間を選択・設定ができます。
時間外労働の削減
フレックスタイム制では、社員が自身の業務を行うのに最適な時間を設定し、柔軟なスケジュール管理を叶えられます。そのため、計画的に業務を完了しやすくなり、時間外労働の削減が期待できるのです。労働時間の適正化を図ることができます。
社員定着率の向上
一人ひとりの業務やライフスタイルにあった柔軟なはたらき方を提供することで、社員の満足度が向上し、離職率の低下につながることも期待できます。仕事とプライベートをバランスよく両立できるようになれば、ライフスタイルが変わるときにも離職することなく仕事を続けるという選択ができるようになり、長期的に企業に貢献する人材の育成や、社員自身の企業ではたらきたいという意欲を高めることができるのです。人材の流出を防ぎ、社員の定着率の向上が期待できます。
社員定着率が低い原因、定着率を上げる方法を知りたい方はこちらもご参照ください。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
多様な人材の確保
フレックスタイム制は、柔軟なはたらき方を求める人材や、ワーク・ライフ・バランスを大切にしたいと考える人材にとって、魅力的な制度といえます。若年層や専門職などの、ワーク・ライフ・バランスを重視する人材にとって、あるとうれしい制度です。フレックスタイム制を導入することによって、人材を引き付け、多様な人材の確保が期待できるでしょう。
ダイバーシティについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介
フレックスタイム制を導入する際の留意点と対策
メリットの多いフレックスタイム制ですが、導入する際にどのような留意点があるのでしょうか。主な留意点とその対策をご紹介します。
労働時間の管理の煩雑
社員それぞれが自由な労働時間を選択できるようになると、勤怠管理が煩雑化します。フレックスタイム制に対応できる適切な勤怠管理システムを導入し、社員が自ら労働時間を入力・管理できる環境を整えましょう。勤怠管理がうまく機能しているかの定期的なチェックを行うことも重要です。
パーソルグループでは、ホワイトなはたらき方を実現する労務管理ツール「MITERAS」を提供しています。
詳細はこちらをご覧ください。
業務の進捗管理が難しくなる可能性
勤務時間がバラバラになると、業務の進捗管理が把握しづらくなる可能性があります。直接進捗を確認することが難しければ、プロジェクトの管理ツールなどを活用すれば、個々のタスクの進捗状況を可視化することができます。定期的に進捗確認のミーティングを行い、業務の遅れを防ぐようにしましょう。
顧客対応機会の減少
フレックスタイム制を導入する際には、社内における業務管理だけでなく、顧客への対応機会の頻度に関しても注意してください。顧客対応が必要な時間帯には必ず担当者が対応できるように、出勤時間に関して相談・調整をしましょう。フレックスタイム制の導入によって顧客対応の質が低下してしまうことのないように注意が必要です。
社内コミュニケーションの減少
はたらく時間や場所の自由度を上げるとネックになるのが「社内コミュニケーション」です。はたらく時間にバラつきが出ることで、日頃の業務でのコミュニケーションが減る、部署やチームのスタッフ全員がそろう機会が少なくなるという問題が出てくることも考えられます。
こうした問題には、定期的な全体ミーティングの開催、オンラインツールを活用したコミュニケーションの促進が効果的です。フレックスタイム制の中にコアタイムを設定し、その時間帯に全員が出社するようにし、コミュニケーションの機会を確保するようにしましょう。
チームビルディングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>チームビルディングの目的とポイント、具体的な手法をご紹介
フレックスタイム制を導入する際のポイント
フレックスタイム制を導入する際のポイントについて解説します。まず、フレックスタイム制を導入するために、就業規則等への規定をすることと、労使協定の締結が必要です。
労使協定を締結する
まず、労使協定で制度の基本的枠組みを定めます。社員と企業が労働条件や勤務制度について合意する契約を指します。下記の事項を定める必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(※任意)
- フレキシブルタイム(※任意)
労使協定は同一労働同一賃金の実現に向けた重要な手段であり、企業内での賃金格差や労働条件の不均衡を是正するための基盤です。詳細は以下をご覧ください。
>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介
就業規則に規定する
フレックスタイム制を導入する際には、就業規則を変更する必要があります。就業規則には始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めてください。
就業規則は企業ではたらく際の労働条件や規律を定めたものです。全社員が遵守すべきであり、認識しているべき基本的なルールです。フレックスタイム制の具体的な運用方法や守るべきルールをきちんと就業規則に規定し、全社員への周知と制度の透明性・公平性を確保しましょう。
時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なる
フレックスタイム制では1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。また、1日のうちの標準の労働時間に達しない場合でも欠勤とはなりません。
清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間が時間外労働の対象となります。
法定労働時間の総枠については、以下の式で求めることができます。
清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦⽇数/7⽇
ただし、特例措置対象事業場(常時10⼈未満の労働者を使⽤する商業、映画・演劇業、保健衛⽣業、接客娯楽業など)については、週の法定労働時間が44時間となるため、1週間の法定労働時間を44時間とします。
清算期間における総労働時間と実労働時間との過不⾜に応じた賃⾦の⽀払いが必要
清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の清算を行う必要があります。

※引用:厚生労働省|フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
フレックスタイム制を導入して社員定着率を向上させる
一定の期間においてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、その日の始業時刻・終業時刻・労働時間を社員が自由に設定できる制度がフレックスタイム制です。これにより社員はワーク・ライフ・バランスを充実させることが可能になります。社員がはたらきやすくなれば、離職率の低下につながったり、モチベーションが上がり生産性が高まったりすることも期待できます。より良い職場環境を提供することができ、社員定着率を向上させる制度なのです。
社員定着率については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする