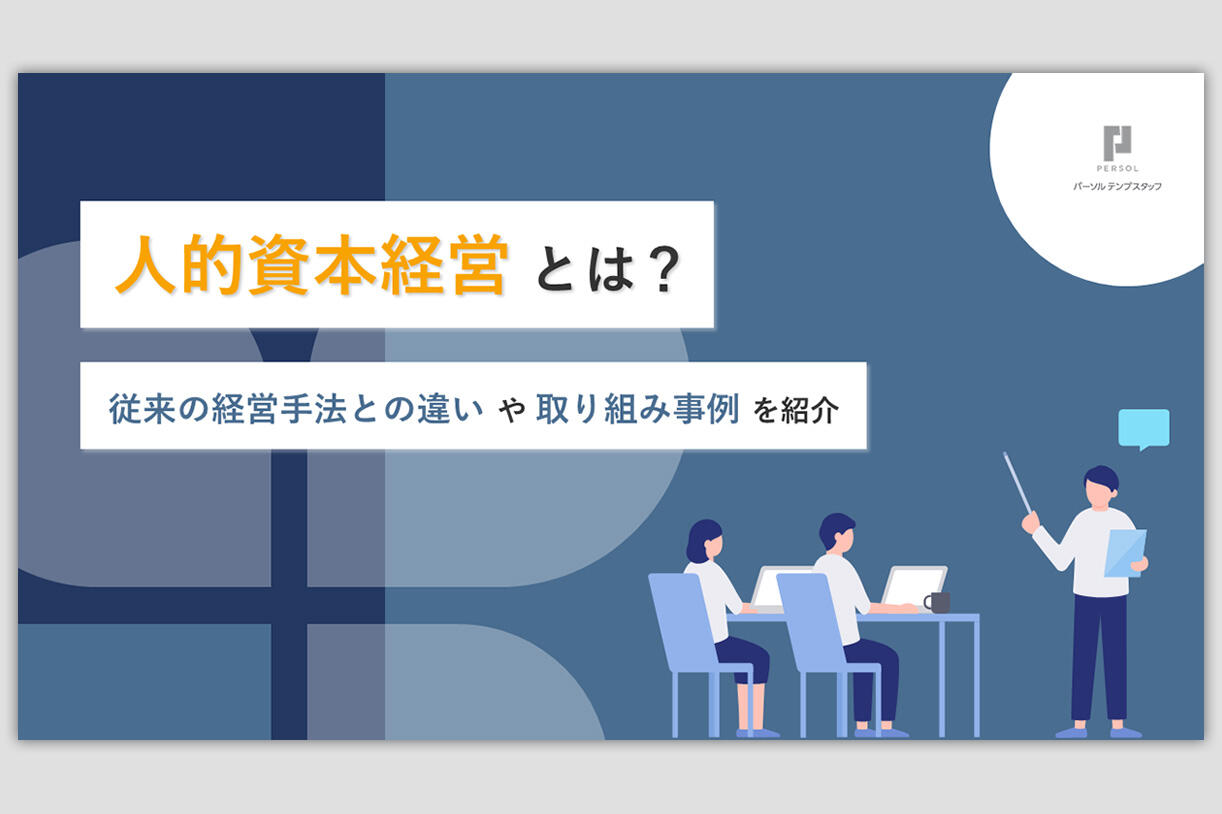HRナレッジライン
カテゴリ一覧
キャリア開発とは?企業が押さえるべきメリット・手法・事例【最新版】
- 記事をシェアする

キャリア開発とは、社員が自らのキャリアを主体的に描けるよう、企業が支援する取り組みのことです。人的資本経営やリスキリングが注目される今、企業にとっても「人材を活かす仕組み」として注目されています。
本記事では、キャリア開発の意味や背景から、企業が導入すべき7つの手法、厚生労働省の助成金制度、支援ツールの選び方までを網羅的に解説。「制度づくりの第一歩を踏み出したい」と考える人事・経営層のための実践ガイドとしてお役立てください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
キャリア開発とは何か
キャリア開発とは、企業が社員一人ひとりのキャリアを自律的に描けるよう、学習機会や挑戦の場を提供し、その成長を支援する人材育成施策のことです。
キャリア開発は単なる福利厚生ではなく、人材の流動化が進み、人的資本経営やデジタル化、業務変革に対応する学び直し(リスキリング)が不可欠な現代において、企業が競争力を維持するための重要な「人材投資インフラ」といえるでしょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
なぜ今、キャリア開発が求められるのか
現在のビジネス環境において、キャリア開発は企業にとって避けて通れないテーマとなっています。その背景には、大きく4つの変化があります。
1.人的資本経営と制度の変革
人的資本情報の開示が義務化され、企業は人材育成への投資がどのような効果をもたらすのか、明確に説明する責任を求められています。経営層に対して投資対効果を提示できる、より戦略的な育成スキームの構築が急務です。
人的資本経営に求められる人事の進化や、実際の企業での取り組み事例については、以下のセミナーレポートで詳しく紹介しています。
>>【セミナーレポート】人的資本経営の真価を引き出す人事部門の役割 ~HRBPとCoEを活かしたHRトランスフォーメーションの鍵~
>>【セミナーレポート】「人的資本経営」を目指すカゴメの人事改革 ー戦略人事とサステナブル人事の連動による経営改革ー
2.社員のキャリア自律への意識変化
終身雇用の形骸化と転職市場の活性化により、社員は企業に依存せず、自らの市場価値を高める「ポータブルスキル」の習得を重視しています。企業もまた、魅力的なキャリア支援を通じて、優秀な人材の定着と採用競争力の向上を両立させる必要があります。
なお、社員の定着に課題を感じている場合は、具体的な原因と改善策について解説したこちらの記事もあわせてご覧ください。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
3.技術進化に伴うリスキリングの不可欠性
DXやAI技術の急速な進展により、既存スキルの有効期間は「3〜5年」とも言われています。
こうした変化に対応するためには、継続的な学び直し(リスキリング)を制度として整備することが不可欠です。キャリア開発は、企業の競争力や存続に直結する戦略課題となっています。
リスキリングの実践例や設計のポイントについては、以下の記事でも詳しくご紹介しています。
>>リスキリングとは?導入による企業のメリットと注意するポイントを解説
>>【セミナーレポート】「リスキリング」を科学する
4.不確実な時代におけるキャリア自律の必要性
ビジネス環境は、VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)から、BANI(脆弱・不安・非線形・理解不能)へと変化しています。
こうした時代には、会社がすべてを決めるのではなく、社員一人ひとりが自らのキャリアを主体的に考え、行動する「キャリア自律」の考え方が、組織の持続的な成長を支える重要な要素となります。
キャリア開発の定義と具体的な範囲
似たような意味で使われがちなキャリア開発・キャリア形成・キャリアデザインですが、実はそれぞれに異なる主体と役割があります。
違いを簡単に整理すると、以下の通りです。
| 用語 | 主体 | 意味・範囲 |
|---|---|---|
| キャリア開発 | 企業+個人 | 個人のキャリア自律を促すために、企業が制度・環境・学習機会を提供する取り組み全般 |
| キャリア形成 | 個人 | 自らのキャリアを設計し、具体的な行動に移すプロセス |
| キャリアデザイン | 個人 | 自分の人生や仕事について、将来像を描き、計画を立てること |
それぞれの違いを正しく理解することで、施策設計や現場への浸透もスムーズになります。
具体的な取り組み事例や、キャリア形成・デザインの実践方法については、以下の記事も参考にしてください。
>>キャリアデザインの目的やメリットは?企業の取り組み方をご紹介
>>【セミナーレポート】今こそ、持続的なキャリア形成へ!社員と組織の「リスキルとキャリア自律」
キャリア開発・キャリア形成・キャリアデザインの使い分け
キャリア形成は、個人が自分の意思でキャリアを築いていく過程を指します。一方でキャリアデザインは、その前段として「どうありたいか」「何をやりたいか」といった理想像を描くステップです。
そしてキャリア開発は、個人のキャリア形成やキャリアデザインを支えるために、企業が制度面や学習機会を整え、環境を用意する仕組み全体を指します。社員のキャリア自律を後押しするインフラともいえる概念です。
キャリア開発への取り組みで企業が得られる3つのメリット
企業がキャリア開発に積極的に取り組むことで、さまざまなメリットが生まれます。
1.組織の活性化
キャリア開発を推進することで、社員は自らのキャリアを主体的に考え、行動するようになります。これにより、個々の社員のエンゲージメントが高まり、組織全体に活気が生まれます。
例えば、1on1ミーティングやOKR(目標と主要な結果)といった取り組みが形骸化することなく、本来の機能を果たしやすくなるでしょう。自律的な人材が増えることは、組織の機動性向上にもつながります。
OKRについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>OKRとは?KPIやMBOとの違いや導入するメリットを解説
2.採用力と定着率の強化
「社員の学びへの投資」は、企業が社員に提供できる魅力的な価値提案(EVP:従業員価値提案)の一つとなります。特に若手層にとって、自身の成長を支援してくれる企業は非常に魅力的です。
キャリア開発に力を入れていることを対外的に示すことで、優秀な人材の採用競争力を高められるだけでなく、社員の定着率向上にも寄与し、結果として離職率の低下にもつながります。
企業の魅力を的確に伝え、応募者とのマッチング精度を高める「採用ブランディング」の考え方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>採用ブランディングで応募者を増やす!企業の魅力を最大化する戦略
3.生産性と革新力の向上
社員がリスキリング(スキルや知識の学び直し)に取り組むことで、企業全体の生産性が向上し、新たな価値創造の機会が生まれます。
例えば、DX関連のスキルを習得した社員が、業務効率化の提案や新規事業のアイデアを生み出すといった具体的な成果が期待できます。学びを通じて得た知識やスキルが、企業の革新力へと直結するのです。
キャリア開発を組織に根付かせる4つの視点
キャリア開発は単に制度を導入するだけでなく、組織文化として根付かせることが大切です。以下にキャリア開発を成功に導く4つの視点をご紹介します。
1.キャリア自律を組織文化として育む
キャリア開発の出発点は、社員一人ひとりが自分のキャリアを主体的に考え、行動することです。この「キャリア自律」の意識を根付かせるには、企業としてのサポートが必要です。
例えば、OKRなどの目標管理手法に、自己学習やスキル開発に関する項目を含めることで、キャリア自律の実践を促進できます。
「半期で何時間学習したか」「どんな研修を受けたか」といった指標を設け、上司との1on1で継続的に確認する運用が効果的です。
2.経営戦略と人材戦略の連動
キャリア開発は企業成長に不可欠な人材投資です。しかし、経営ビジョンと人材像が乖離していると、育成の方向性が曖昧になります。
例えば、経営が「デジタル事業の拡大」を掲げている場合、社員全体のデジタルリテラシー強化や、選抜型のDX人材育成プログラムを導入することが重要です。
事業戦略から逆算して「今後3年で求められるスキル」や「各部門で必要なポジション像」を明確にし、人材開発の方向性に落とし込みましょう。
経営戦略と人材戦略を連動させるための設計アプローチについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>採用成功につなげる人材獲得戦略|戦略設計の5ステップ
3.多面的なフィードバックと継続的な対話
キャリア開発を個人任せにしないためには、上司や周囲との定期的な対話機会の設計がポイントとなります。
- 週次または月次の1on1ミーティング
- 四半期ごとの目標設定・振り返り
- 360度フィードバックやタレントレビュー
これらを通じて、個人が「自分の価値」を捉え直し、今後のキャリア選択を前向きに進められるようになります。
なお、フィードバックの場では「評価と切り離す」「安心して話せる関係性を築く」などの心理的安全性の確保が重要です。
4.学び→実践→越境の循環をつくる
キャリア開発は、インプット(学習)だけでなく、アウトプット(実践)と新たな挑戦(越境)がそろって初めて機能します。
例えば、以下のような循環を意図的に設計しましょう。
【学び】ラーニングや社内研修によるインプット
【実践】学んだ内容をOJTや小さなプロジェクトで試す
【越境】他部門への異動、社外活動、副業などを通じた視野の拡張
越境の機会をつくることで、社内では得られない視点やネットワークを獲得し、個人と組織の両方に新しい価値をもたらします。
キャリア開発を支える7つの具体施策
上記の4つの視点を現場で具体化していくには、日々の施策・制度が欠かせません。ここでは、実践的な7つの手法とその目的・KPI例をご紹介します。
1.キャリア面談・1on1
キャリア自律を支える基盤として、定期的なキャリア面談や1on1の実施は欠かせません。上司と部下が「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(求められること)」の3軸を対話することで、納得感あるキャリアプランの構築と行動促進が期待できます。
【KPI例】
- 面談完了率
- 行動計画の実行率
2.キャリア研修の導入
社員自身がキャリアを描けるようになるためには、「キャリアについて考える機会の提供」が必要です。若手にはキャリアの基礎知識を、中堅層にはリスキリングや部下育成の視点を、管理職にはキャリア支援の技法を、と階層別に学びの場を用意しましょう。
【KPI例】
- 研修後のNPS(満足度)
- 行動変容サーベイ
3.キャリアパスの明示
キャリアの選択肢が見えることで、人は初めて「主体的に選び、考える」ことができます。専門職・マネジメント職・他部門への異動など、複線型キャリアの選択肢を具体的に提示することで、成長意欲の喚起や離職防止につながります。
【KPI例】
- 社内公募件数
- パス変更希望者数
4.戦略的人事異動の仕組み化
キャリアの広がりと企業の成長を両立させるには、「戦略的な異動」が有効です。希望制や自己申告制を取り入れることで、社員の意思を尊重しつつ、スキルの最適配置を図れます。また、組織の硬直化を防ぎ、越境学習や適性発掘の機会にもつながります。
【KPI例】
- 異動希望者の充足率
5.自己啓発支援制度
学びたい意欲を行動に移すには、背中を押す仕掛けが必要です。書籍購入費や資格取得補助、eラーニングの提供といったインセンティブを用意することで、社員が安心して自己研鑽に取り組める土壌が整います。
【KPI例】
- 制度利用率
- 学習履修完了率
6.副業・社外越境の推進
企業内だけでは得られない視点・スキルを取り込む手段として、副業や社外への越境が注目されています。スタートアップ出向や自治体連携、副業制度などを通じて、新しい価値観と出会う機会を創出し、キャリアの多様性と社会性を高めていきましょう。
【KPI例】
- 越境プログラム参加人数
- 新規事業提案件数
7.リスキリングプログラムの提供
DXやAI時代に対応するためには、既存人材の再教育が不可欠です。例えば「デジタル基礎講座」「データ分析入門」などを提供することで、社員が時代に合った武器を持ち、変化に適応できる体制をつくれます。
【KPI例】
- 新資格取得数
- 業務への適用実績
キャリア開発を実施する上で注意したい企業側の留意点
ここでは、企業がキャリア開発を進める上で押さえておきたい5つの留意点を解説します。
1.社員の温度感やニーズに合った制度導入
制度を設計する際は、現場が何を求めているのかを丁寧にすり合わせることが大切です。社員が日々の業務で多忙な中でも、ニーズや期待に沿った制度であれば前向きに受け止められやすくなります。
導入前には、アンケートや対話を通じて社員の意見や不安を把握し、その上で制度の意義やメリットをしっかり伝えることで、制度が浸透しやすくなります。
2.制度だけで終わらせず、日常の対話・現場の納得感を重視
制度や仕組みは、キャリア開発を始めるためのきっかけにはなりますが、社員の本格的なキャリア形成は、上司との1on1や日常的な対話の中でこそ育まれていくものです。
例えば、年に一度の研修やキャリア申告制度だけでは不十分な場合もあります。キャリア開発を効果的に進めるためには、継続的なコミュニケーション設計や、定期的なフィードバックの場づくりが欠かせません。
3.人事施策と学習・経験とのつながりを意識
研修やリスキリングの機会を設けたら、それを評価やキャリア形成にどう結びつけるかが重要です。学びが現場で活かされ、人事施策と連動してこそ、社員のモチベーションや成長意欲は高まります。
異動・配置・昇格といった人事施策と、日々の学習や実務経験を有機的につなげることで、学びの効果を最大限に発揮できます。
4.管理職への適切な意識付けと巻き込み
管理職がキャリア開発の重要性を理解していなければ、どれだけ制度を整えても現場での運用は止まってしまいます。
部下のキャリア形成を支援する姿勢や、的確なフィードバックを行うスキルは、制度以上に成果に直結します。管理職向けの研修やメッセージ発信を通じて、キャリア支援に対する意識を高めていきましょう。
5.経営層が「口だけでなく」姿勢を示す必要性
キャリア開発を推進するには、経営層の本気度が現場に伝わることが何より重要です。「自律的なキャリア開発を」と言いつつ、短期的な成果だけを評価する体制では、現場に矛盾が生じてしまいます。
トップ自らが学び続ける姿勢を見せ、キャリア開発を重視するメッセージを発信することが、組織文化としての定着を後押しします。
キャリア開発におけるツール・プログラム選定の重要視点
効果的なキャリア開発を実現するためには、目的や人材戦略に合ったツールやプログラムの導入が不可欠です。選定時に押さえるべき重要な視点と代表的な手法をご紹介します。
タレントマネジメントシステムの活用
社員のスキルマップや経歴、キャリア志向などの情報を一元管理し、社内公募制度と連携して最適な人材配置を提案できるタレントマネジメントシステムは、キャリア開発を支援する有力なツールです。
人事担当者の業務負荷を軽減するだけでなく、社員にとっても成長機会の可視化や適切なアサインにつながります。
学び放題型のeラーニング導入
月額定額制のeラーニングは、自己主導型の学習を後押しする手段として有効です。社員は自身のキャリアに合わせて自由に学習を進めることができます。
ジョブ・カードとAI解析の組み合わせ
ジョブ・カードは、職務経歴・資格・キャリアプランなどを整理した書類で、厚生労働省が推奨するキャリア支援ツールです。
自然言語処理(NLP)を活用したAIで解析・タグ付けすることで、社員ごとに最適な研修プログラムを自動で推薦する仕組みを構築できます。個々の学習効率を高める施策として注目されています。
外部プロフェッショナル研修の活用
自社内では対応しづらい専門分野に関しては、外部講師によるプロフェッショナル研修を活用するのが効果的です。
「リーダーシップとコーチング」「データサイエンス基礎」など、職種横断的に活かせるスキルは、外部の専門家から質の高い学びを得ることで、組織全体のスキル底上げにつながります。
助成金を活用してキャリア開発コストを最小限に抑える(2025年最新版)
社員のキャリア開発に取り組む企業にとって、研修費用や制度設計にかかるコストは避けて通れない課題です。なお、2025年度は、いくつかの主要な助成金において制度改定が行われ、より柔軟かつ実務的な支援が受けやすくなっています。
ここでは、キャリア開発と相性のよい助成金制度のポイントを最新情報とともにご紹介します。
人材開発支援助成金|リスキリングやeラーニングにも対応
人材開発支援助成金は、計画的な職業訓練を実施する企業に対し、訓練にかかる賃金・経費を助成する制度です。社内外のOff-JT(座学研修など)が対象となり、特に「リスキリング」や「階層別研修」といった成長支援と親和性の高い取り組みです。
2025年4月の改定により、eラーニングを含むオンライン研修が1時間単位でも助成対象になるなど、より柔軟に利用できるようになりました。
また、「リスキリング支援コース」では、助成上限額が1社あたり最大1,200万円との報道もあり、大規模な育成計画にも対応可能です。
なお、申請には以下のような主な前提条件があります。
- 訓練開始日の1ヶ月前までに「計画届」の提出が必要(提出期間:6ヶ月前~1ヶ月前)
- 届出内容に不備があると受理されない可能性があるため、事前準備が重要
- 原則として正社員(無期雇用・フルタイム労働者)を対象とした訓練が対象
- 訓練内容や実施方法が制度の趣旨に適合している必要あり
- 有期実習型訓練など一部のコースでは、訓練後の正社員登用が条件となる場合あり
- ※本内容は2025年8月時点の制度情報に基づいて記載しています。
- ※参考資料:厚生労働省|人材開発支援助成金
キャリアアップ助成金|非正規雇用の処遇改善を後押し
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む企業を支援する制度です。
中でも「賃金規定等改定コース」は、基本給を3%以上引き上げた場合、1人あたり最大7万円が助成される制度です。加えて、職務評価の導入や昇給制度の新設を行った場合は、最大20万円の加算助成が受けられ、合計最大27万円となります。
また、2025年の改定では、申請手続きの一部電子化や書類様式の簡素化が進められ、企業側の手間が軽減されました。
なお、申請には以下のような主な前提条件があります。
- キャリアアップ計画書を、賃金規定等の改定前日までに労働局に提出していること
- 有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの非正規雇用労働者に対し、就業規則や賃金規定等に基づき、基本給を3%以上引き上げていること
- 賃金改定後、6ヶ月間にわたり引き上げ後の賃金を支給していること
- 改定前の賃金規定等を3ヶ月以上運用していた実績があること(または、過去3ヶ月の支給実績と比較可能な場合)
- 対象労働者が、申請時点で在籍中かつ雇用保険に加入していること
- 最低賃金改定による賃上げ分は、助成県労働局または最寄りのハローワークにて最新情報をご確認ください対象に含まない
これらの条件を満たす場合、事業所ごとに年間最大100名まで助成対象とすることが可能です。最新の制度内容や申請スケジュールについては、厚生労働省や都道府県労働局の情報をご確認ください。
- ※本記事は2025年8月時点の情報に基づいて作成しています。
- ※参考資料:厚生労働省|キャリアアップ助成金
短時間労働者労働時間延長支援コース|年収の壁対策に
2025年7月に新設されたキャリアアップ助成金の一部で、短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入を促進する目的で設けられました。いわゆる「年収の壁問題」への対策として注目されています。
新設ポイント(2025年7月以降)
- 週5時間以上の労働時間延長+社会保険適用:1人あたり最大28.4万円(生産性要件を満たす場合)
- 他コースと併用し、手取り減を防ぐ取り組みを行った場合:延長時間に応じて最大22.5万円(同28.4万円)を助成
- 助成対象人数:1事業所あたり年間15人まで
短時間労働者を安定的に雇用し、キャリア形成につなげる観点でも、有効な制度といえるでしょう。
なお、申請には以下のような主な前提条件があります。
- 「キャリアアップ計画」を賃金規定等の改定前日までに労働局へ提出していること
- 有期雇用労働者や短時間労働者など非正規雇用者が対象であること
- 賃金規定・就業規則・賃金一覧表などを3%以上増額改定し、6ヶ月間の賃金支給実績があること
- 規定の適用が全対象者または合理的に区分された対象者(職種別・部門別など)に行われていること
詳細は都道府県労働局または最寄りのハローワークにて最新情報をご確認ください。
- ※本内容は2025年8月時点の制度情報に基づいて作成しています。
- ※参考資料:厚生労働省|キャリアアップ助成金
事例紹介|パーソルテンプスタッフにおけるキャリア開発の実践「Temp University」
パーソルテンプスタッフは、社員一人ひとりのキャリア自律をサポートする目的で、2022年に企業内大学「Temp University」を開設しました。
この取り組みの大きな特徴は、社員自らが「学ぶ・教える・創る」という3つの役割で関わり、共に学びの場を築いていく点にあります。
研修は手挙げ式で、金融リテラシーやタイパ(時間効率)向上、ライフキャリアや性教育といった幅広いテーマをカバーしています。社内講師による実践的な講義を通じて、社員が自らの意志で学び、互いに成長し合う文化が根付いています。
開校からわずか2年で、のべ5,000名以上が参加。学びが「仕事」と「人生」の双方に直結するこの仕組みは、「はたらくこと」と「生きること」を豊かにするキャリア開発の好事例です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
キャリア開発は企業にとって必要な投資
キャリア開発は、社員のモチベーションや成長を促すだけでなく、企業の競争力を高める「戦略的人材投資」です。
人的資本経営の観点からも、社員のキャリア自律を支援する取り組みは、もはや「あったほうがよい」ではなく、「なくてはならない」ものへと変わりつつあります。
その実現には、「戦略 × 仕組み × カルチャー」が連動した三位一体の設計が不可欠です。制度の整備と現場での運用を両輪で進めながら、「学び・挑戦・越境」の循環を生み出すことこそが、社員と企業の未来を切り拓く第一歩になるでしょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする