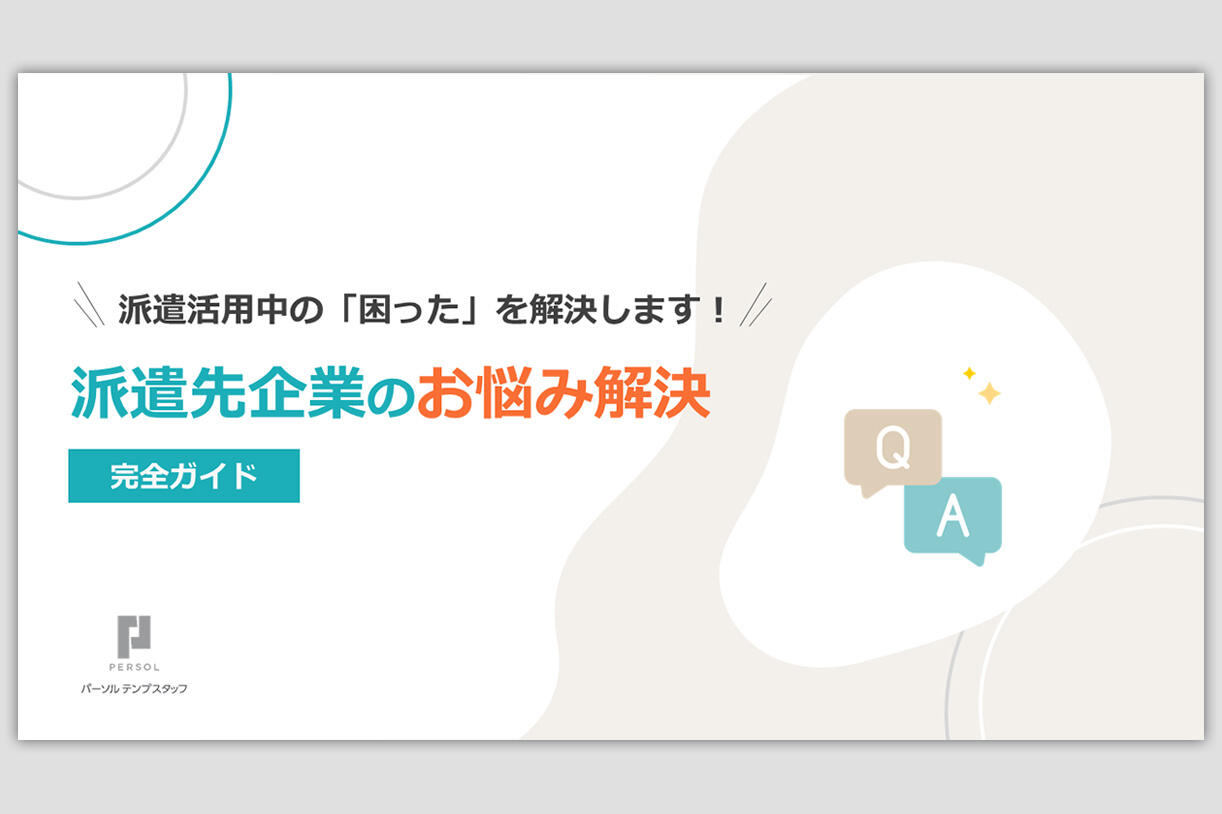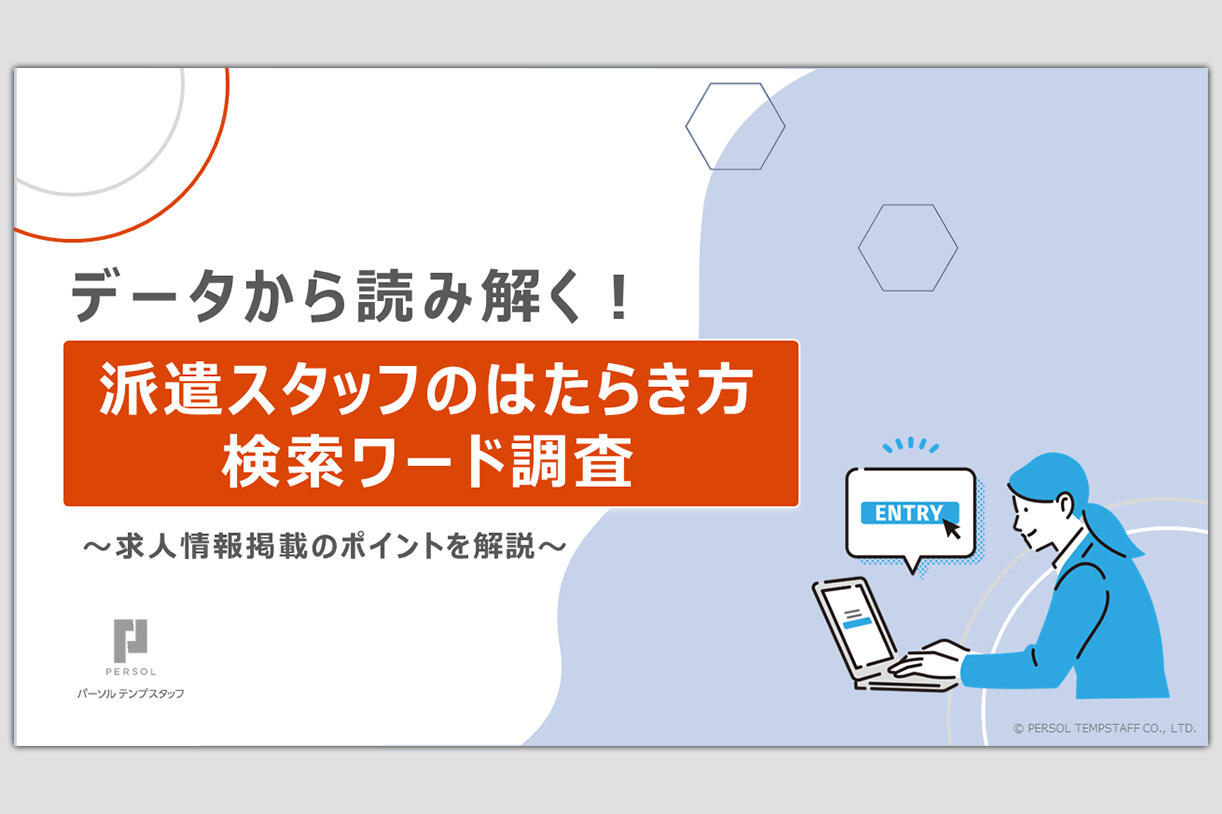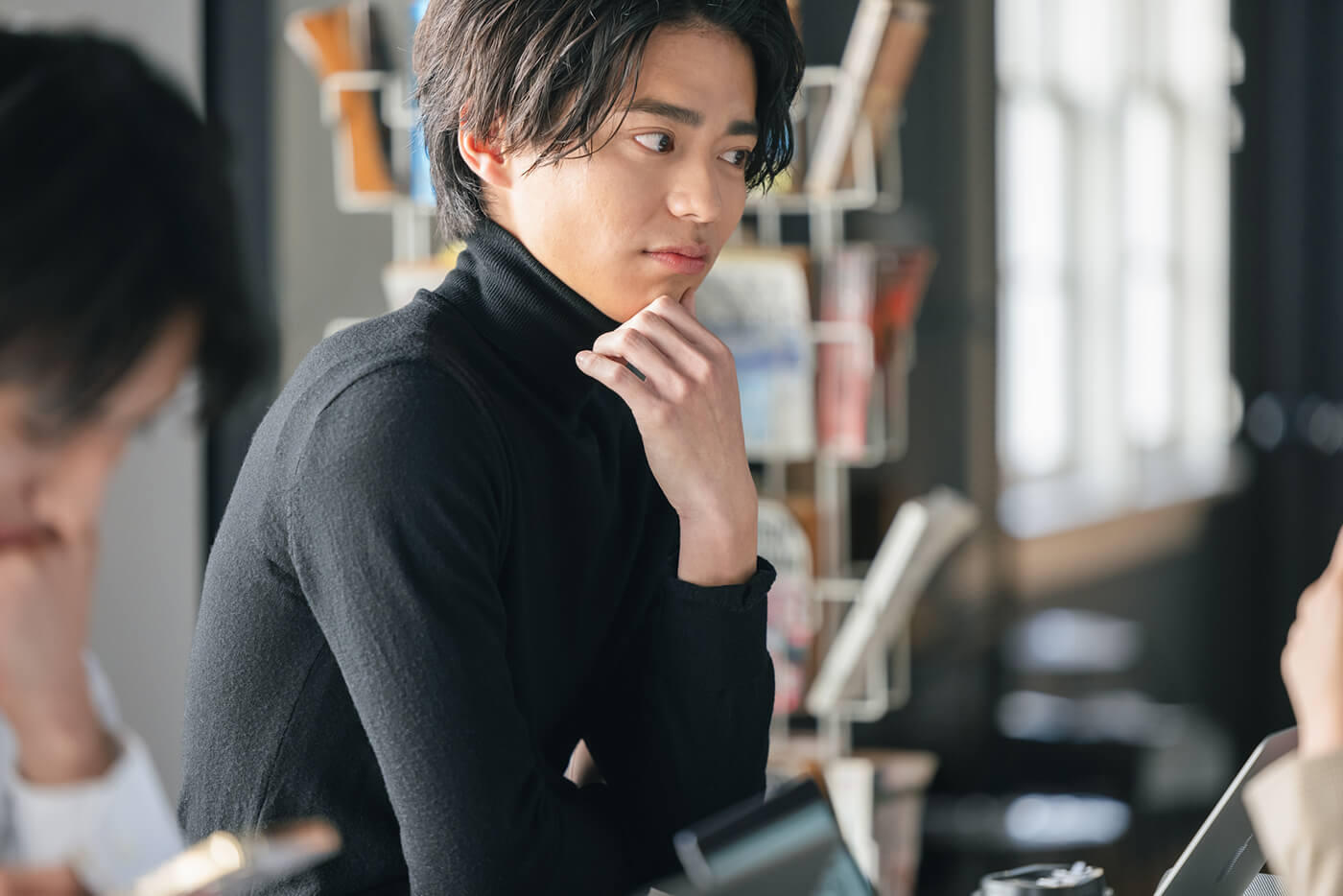HRナレッジライン
カテゴリ一覧
派遣社員とのトラブルを防止・解決する方法|具体例と未然に防止するための知識を紹介
- 記事をシェアする

企業ではたらく社員の数が多ければ多いほど、業務上のコミュニケーションの行き違いなど、社員同士のトラブルが起きる可能性は高くなると考えられます。特に派遣社員を受け入れる際には、自社社員とは勝手が異なる点が多く、コミュニケーションにズレが生じてトラブルに発展する恐れがあります。
本記事では、派遣社員を受け入れている派遣先企業が直面しがちなトラブルについて具体的に紹介するとともに、派遣先企業の立場で留意すべき点について解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣社員と派遣先企業の間でよくあるトラブルの例
派遣社員と派遣先企業の間で生じがちなトラブルについて、具体例に紹介します。加えて、派遣先企業側の留意点についても解説します。
引継ぎに関するトラブル
業務の引継ぎに関するトラブルが挙げられます。
前任の社員が産休・介護休暇などに入る場合、社員から派遣社員に引継ぎをする場面が想定されます。しかし、社員の教え方や引継ぎ資料の準備が不十分だと、派遣社員は「就業前の業務説明や、職場見学で見聞きしたことと違う」など、困惑する場面もあるかもしれません。
また、前任の派遣社員が契約満了となって、派遣先企業が派遣社員に次の担当者への引継ぎ業務を任せたい場面も考えられます。その場合、前任の派遣社員は「業務マニュアルを作成して後任者へ説明するところまでが自身の業務範囲なのだろうか」など、困惑してしまうケースもあるでしょう。
解決策と留意点
契約書にあらかじめ記載のない業務は、派遣社員に依頼できません。もし、契約時と変更が生じる場合には、人材派遣会社に相談して契約内容の見直しが必要です。
「契約書に明記のない業務は依頼できない」という観点を踏まえると、派遣社員同士(前任・後任)で引継ぎ業務を進めるよりは、社員から業務説明を行うことが望ましいと言えるでしょう。
なお、派遣社員の契約終了時に派遣先企業がするべきことについて、以下の記事で詳しく紹介していますのであわせてお読みください。
>>派遣社員の契約終了はいつ伝える?派遣先企業が行うべき対応と留意点を徹底解説
業務に関する指導の中でのトラブル
あたらしい派遣社員を受け入れて、業務の指導を行う場面も考えられます。複数の派遣社員を受け入れている場合、「業務に関する指導は派遣社員同士で進めてはどうだろうか」と考える派遣先企業もあるかもしれません。
しかし前述のように、派遣社員に依頼できる事項は契約書に明記されている業務内容に限ります。以前から受け入れている派遣社員に、後から受け入れた派遣社員の指導を依頼した場合「これは自分自身の業務範囲なのだろうか」と困惑を招く恐れもあるでしょう。
解決策と留意点
派遣社員に向けた業務の指導は、派遣社員同士で進めようと考えるのではなく、社員の中から派遣社員の指導にあたる「指揮命令者」を決めましょう。
その際には、指揮命令者が一貫して派遣社員の指導を行うことが大切です。また、派遣社員が日頃から円滑にはたらきやすい環境づくりを図ることも求められます。
なお、指揮命令者を選任しない場合、労働者派遣法に抵触し、罰則が科せられる場合があるため留意が必要です。
指揮命令者の選任については以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。
>>派遣法の指揮命令者とは?役割や選び方について分かりやすく解説
派遣社員受け入れ時の派遣先企業側の留意点については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
>>派遣社員の受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について
時給や業務内容に対する不満
時給や業務内容に関して派遣社員から「当初聞いていた業務負荷と違う」など不満が寄せられる場合も考えられます。
また、複数の派遣社員を受け入れていて、同じ仕事を依頼している場合、派遣社員によって業務量の偏りが起きる場面も想定されます。同じフロアで同じ仕事をしているのに「自分ばかり忙しい」「あの人ばかり忙しい」など、業務量に偏りのある状態が長く続くと、長期的に派遣社員の中で不満につながる場合も考えられるでしょう。
また業務量の偏りだけでなく、時給に違いがあることを派遣社員同士の会話で知ってしまうなどした場合にも不満が生じる可能性があります。その結果、長期的にはたらくモチベーションの低下につながりかねません。
解決策と留意点
派遣社員の時給・契約内容に関して再考が必要な場合には、人材派遣会社に相談しましょう。
また、複数の派遣社員の間で業務量が偏らないよう、社内の指揮命令者から仕事の割り振りをする体制を築くことが大切です。
人間関係のトラブル
一つの企業内に、社員・派遣社員などさまざまな人がはたらいている中で、人数が多ければ多いほど、業務を通した人間関係のあつれきやトラブルも多くなると考えられます。
例えば、「業務の指導の中で、つい強い口調になってしまった」「相手に不快感を与えるコミュニケーションがあった」という問題も起こり得ます。そのような場合には、派遣社員から人間関係に関して意見が出る場合も考えられるでしょう。
また、派遣社員を大勢受け入れている場合「派遣社員の中で人間関係がグループ化し、休憩時間に孤立している派遣社員がいる」といった場面も起こり得ます。
解決策と留意点
派遣社員から派遣先企業の担当者に宛ててパワーハラスメントやセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなどの意見があった場合、派遣先企業は人材派遣会社へ早急に報告・相談が必要です。
また、派遣社員間での人間関係についても、「派遣社員同士で解決を」と静観するばかりではなく、派遣先企業の担当者や指揮命令者が配慮することも大切です。社員と同じように考えて、派遣社員にとってもはたらきやすい環境づくりに配慮することが求められます。
遅刻・欠勤
派遣社員が交通事情や体調不良などを理由に遅刻・欠勤してしまうこともあるでしょう。その場合、派遣先企業の担当者が「遅刻・欠勤した場合、時給計算はどうなるのだろうか」と戸惑う場面もあるかもしれません。
解決策と留意点
派遣社員の時給は、業務開始時刻から発生します。よって、遅刻した時間分は計上されません。遅刻・欠勤も含めて正確に勤怠管理を行う必要があるため、派遣社員の勤務実態の管理は日頃から派遣先企業側で行うことが求められます。
なお、派遣先企業は、派遣社員の健康・安全衛生管理にも留意することが必要です。例えば、派遣社員の健康診断は人材派遣会社が実施しますが、派遣先企業は「きちんと休憩時間を取れているか」「緊急時の安否確認や、災害時の避難手順についてきちんと共有できているか」といった点を確認します。これは、2020年改正労働者派遣法の「社員と派遣社員との間で待遇の差をなくす」という考え方に基づくものです。
「同一労働同一賃金の適用」が定められ、同種の業務に従事する場合、派遣社員にも正規雇用者と同等の待遇が求められる点が大きなポイントだと言えます。派遣社員と正社員の待遇格差の解消を目指していることを理解しましょう。
なお、派遣社員の欠勤が続き、仕事が思うように進まない場合には、人材派遣会社に相談することが推奨されます。
派遣先企業が人材派遣を活用する際のよくある悩みと解決方法については、以下の記事でも紹介しています。あわせてお読みください。
>>【失敗から学ぶ】人材派遣活用時のよくあるお悩みと解決方法
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣トラブルを未然に防ぐには
派遣トラブルを未然に防ぐために、派遣先企業の担当者は以下のような知識を持っておくとよいでしょう。
派遣トラブルを防止するための基本知識を知る
まず、派遣社員と派遣先企業の関係を正確に理解しましょう。人材派遣とは、人材派遣会社に雇用されている派遣社員が、派遣先企業の指揮命令を受けて役務を提供する仕組みです。
次に、人材派遣会社の役割と責任を明確に理解しましょう。人材派遣会社は就業先の提案・賃金の支払いなどを通して、派遣社員が安定して就業できる環境を整える役割を担っています。
そして、契約内容を正しく把握することも大事です。契約書に記載のない業務は派遣社員に依頼できません。
これらの3つのポイントを意識することで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
派遣社員の受け入れ時について、詳細は以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
>>人材派遣とは?他サービスとの違いやメリット、選ぶ際のポイントを紹介
派遣社員の受け入れ時に仕事環境を整備する
派遣社員を派遣先企業へ受け入れる際に、仕事環境を整備する目的でいくつか配慮することで、派遣社員との良好な関係を築くことにつながり、長期就業や生産性向上につながると期待できます。
まず、コミュニケーションの重要性を改めて認識しましょう。一緒にはたらく社員への紹介、社内設備・フロアの案内、社内ルールの共有など、派遣社員にも社員と同じようなコミュニケーションを取ることが大切です。立場によって不公平な待遇が生じないようにしましょう。また、日頃から挨拶や報告・連絡・相談といったコミュニケーションを大切にし、業務に関して質問しやすい雰囲気を作ることも大切です。
さらに、業務に関係のない私的な話題はなるべく控え、就業条件の口外を避けるよう、派遣社員一人ひとりに対して促しましょう。派遣社員を複数受け入れている場合、一人ひとり就業条件が異なるケースも想定されます。互いに就業条件の違いを知ってしまうとあつれきが生じたり、モチベーション低下につながったりする恐れもあるからです。
依頼する業務内容と指揮命令系統を派遣社員に対して明確に伝え、派遣社員の意見も尊重しながら、同じチームの一員として扱う姿勢が大切です。
派遣社員の受け入れ準備のポイントは以下の記事でも解説していますので、あわせてお読みください。
>>派遣社員の受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について
派遣社員の権利と義務を理解する
派遣社員の権利と義務について理解しましょう。
まず、守秘義務についての理解が重要です。派遣社員も社員と同様に、業務上知り得た情報に関する守秘義務があります。派遣先企業は派遣社員に対して守秘義務の重要性を説明し、必要に応じて誓約書を取り交わすなどの対応が求められます。
また、有給休暇などの労働条件を確認しましょう。派遣社員にも労働基準法に基づく有給休暇の権利があります。派遣先企業は人材派遣会社と連携して派遣社員の有給休暇取得状況を把握し、適切な取得を促進しましょう。労働時間や休憩時間などの労働条件についても、人材派遣会社との契約内容を確認し、遵守することが重要です。
労働者派遣法を学ぶ
労働者派遣法の基礎について、派遣先企業の担当者も学んでおきましょう。労働者派遣法は、前述した派遣社員の権利と義務にも通じます。
労働者派遣法で重要なポイントとして、以下の3点が挙げられます。派遣社員を受け入れる派遣先企業は、理解しておくことが大切です。
- 派遣期間の制限を遵守する(原則として同じ事業所で3年以内)
- 派遣社員の雇用安定措置を理解し、必要に応じて派遣元と協力する(派遣期間終了後、派遣社員が続けてはたらける措置について検討する)
- 同一労働同一賃金の原則に基づき、不当な待遇差が生じないよう配慮する
労働者派遣法については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
>>【最新版】 労働者派遣法とは?詳しい内容や歴史、違反例を分かりやすく解説
派遣社員の就業について残業や有給について詳しくはこちらの記事でまとめています。
>>派遣社員への残業指示は可能?36協定や残業代の計算方法を解説
>>【企業向け】派遣社員の有給休暇は誰が付与する?条件やルール、日数を解説
まずは人材派遣会社に相談を
派遣社員と派遣先企業の間でトラブルが発生した場合には、まずは人材派遣会社に相談することが大切です。
人材派遣会社に相談する際には、派遣先企業で作成・管理している「派遣先管理台帳」の記載内容も伝えるとよいでしょう。派遣先管理台帳とは、一人ひとりの派遣社員について受け入れ時からの勤務実態を記載して一定期間、派遣先企業で保管しておくための書類です。
派遣先管理台帳については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
>>派遣先管理台帳とは?記載内容や保管方法を分かりやすく解説
派遣管理デスクの活用も検討する
受け入れている派遣社員の人数が多く、一人ひとりに対する細やかな管理業務に課題を抱えている場合には派遣管理デスクというサービスの活用もおすすめです。
「派遣管理デスク」とは、派遣社員の管理を人材派遣会社が派遣先企業に代わって進めるサービスで、派遣管理に関する自社の負担を低減できます。また、派遣法をはじめとする関連法に精通した人材派遣会社が提供するサービスであるため、コンプライアンスリスクも防止できます。
▼派遣管理デスク

派遣管理業務を代行し
人材派遣活用の最適化を実現する
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣社員のトラブルは早めに人材派遣会社へ相談を
本記事では、人材派遣を利用して派遣社員を企業に受け入れている中で、直面しがちなトラブルについて解説しました。
もしも派遣社員の受け入れ途中でトラブルが発生した場合には、早急に人材派遣会社へ相談することが重要です。
なお、パーソルテンプスタッフでは「派遣管理デスク」のサービスも提供しています。「数多くの派遣社員を受け入れているが、管理業務の負担が増大して悩んでいる」「常に最新の法令を遵守して適切に事業運営を進めたいが、自社内に知見が不足している」といった担当者さまのお悩みにお応えできるサービスです。
- 記事をシェアする