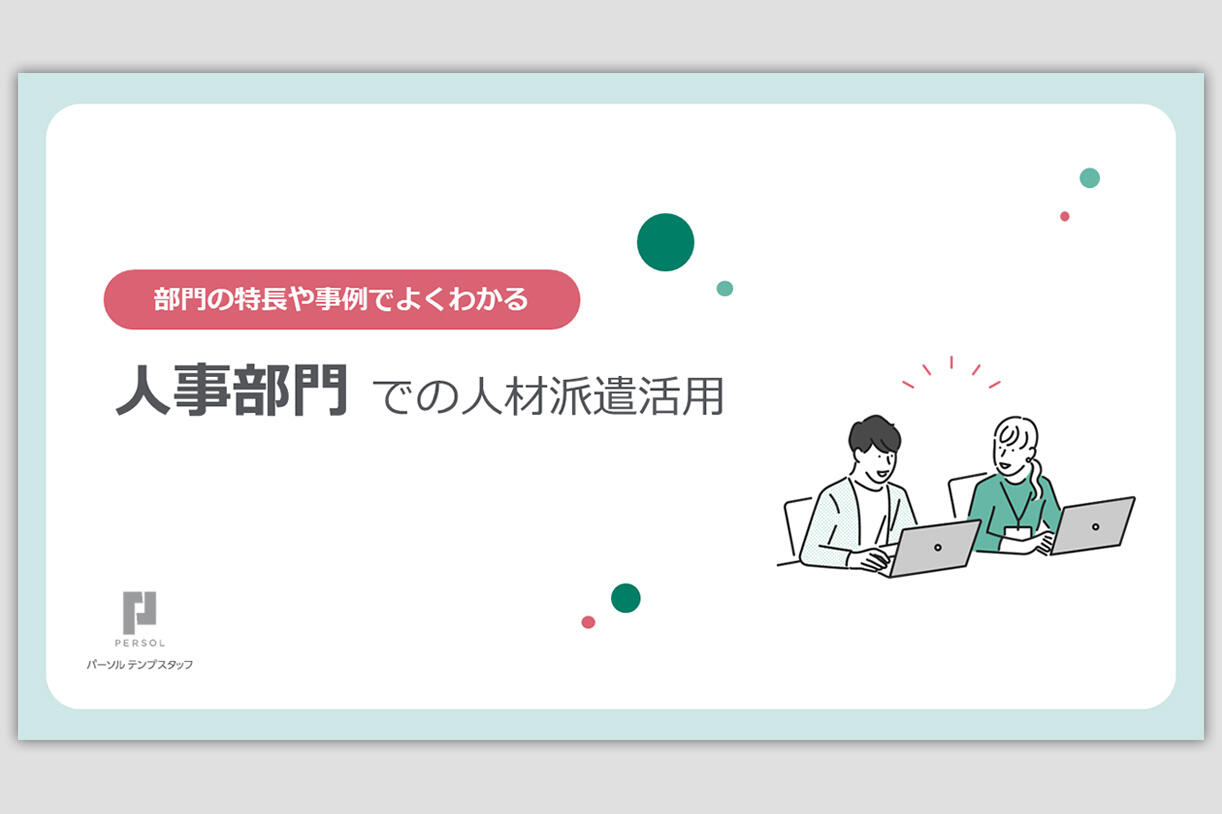HRナレッジライン
カテゴリ一覧
職能資格制度とは?メリットや導入時の留意点、職務等級制度との違いを解説
- 記事をシェアする

職能資格制度とは、職務を遂行する能力を基準に社員を評価し、給与算定の基礎となる等級を定める人事評価制度です。職能資格制度を導入することで、長期的な人材育成や、公平な評価システムの構築などのメリットが得られます。
この記事では、職能資格制度の仕組みや職務等級制度との違い、導入するメリット、導入時の留意点などを解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
職能資格制度とは
職能資格制度とは、職務を遂行する能力を基準に社員を評価し、給与算定の基礎となる等級を定める制度です。ただし、職務遂行力で個人を評価する一方で、経験に比例して等級が上がっていく側面もあり、勤続年数が多いほど高い職能があるとみなされます。したがって、等級が下がることは基本的にありません。
日本で誕生した人事評価制度で、職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度と3種類ある等級制度の中では、最も国内で普及したものといえます。戦後、年功序列や終身雇用制の考え方が広まっていった日本の企業と相性が良く、1970年代頃に定着していきました。
人事制度や評価制度についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>人事制度とは?種類や設計方法、ポイントについて分かりやすく解説
>>人事評価制度とは?導入する目的やメリット、設計方法について解説
職務等級制度との違い
職能資格制度と似た制度に、職務等級制度があります。職能資格制度が社員の職務遂行力など「人」を基準にしているのに対し、職務等級制度は職務ごとの達成度など「仕事」を基準にしています。職務等級制度では、営業や接客など個別の職務ごとに仕事内容や難易度を明確に規定した「職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)」 が用意され、そこで定められた職務が達成できているか否かが判断されます。
職務等級制度は主に欧米で発展を遂げた人事評価制度で、成果主義ともいえる点が特徴です。職能資格制度と違い、年齢や勤続年数は評価に関係ありません。人種差別排除の観点からも、多くの民族が暮らす国ほど人から切り離して仕事の達成度のみ評価するこの制度を採用する傾向があります。
また、職務等級制度を導入することで社員の専門性が高められるため、スペシャリストの育成や生産性を向上させたい場合に有効だといえます。
両者の違いを表にまとめました。
| 職能資格制度 | 職務等級制度 | |
|---|---|---|
| 評価基準 | 人の職務遂行力 | 任された仕事の内容とそれらに対する成果 |
| 給与 | 今までに蓄積してきた職務遂行力が反映され、能力伸長の度合いで変動。勤続年数に応じて上がりやすく、基本的に降格はしない | 現在担っている職務によって変動し、各等級の範囲内で評価に応じて増減 |
| 人材開発 | 幅広い知識に精通したゼネラリストの育成に向いている | スペシャリストの育成に向いている |
| メリット | 給与に影響を与えないため、柔軟な人事異動・職務変更が可能。また、社員にとって安心感がある | 職務内容が明確。また、給与と職務内容が連動しており、わかりやすく公正な成果主義 |
| 留意点 | 年功序列の風土になりやすい | 給与に影響を与える可能性が大きいため、組織が硬直化する可能性がある。他の職務と連携が生まれにくい |
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
職能資格制度を導入するメリット
職能資格制度を導入すると、企業や社員にとってさまざまなメリットがあります。各メリットについて解説します。
人事異動に対応しやすい
個々の職務が明確な職務等級制度と違い、職能資格制度はひとりがあらゆる職種・業務を経験する制度です。そのため、特定の部署で欠員が生じたときや大きな組織改編があったとき、人事異動や人材配置をスムーズに行うことができます。
また、社員の能力やスキルに基づいて等級が設定されるので、能力に応じた配置が容易になり、適材適所の人事異動が可能です。
長期的な人材育成ができる
年功序列や終身雇用制を前提にした職能資格制度は、勤続年数を重ねるほどに等級が上がる仕組みになっています。長期間にわたってさまざまな職種や業務を経験する社員が多いため、10年単位の時間をかけて汎用性の高いスキルを取得させる人材育成に適しています。
企業は長期的な人材戦略が立てやすくなり、教育や研修プログラムを計画的に設計することが可能です。その結果、企業全体の技術力や競争力は向上するでしょう。
ゼネラリストの育成ができる
ゼネラリスト(Generalist)とは、特定の専門分野に限定されず幅広いスキルや知識を持ち、多様な業務や職務に対応できる企業にとって貴重な人材を指します。
職務によって等級が決まる職務等級制度に対し、職能資格制度は個人の能力を基準に評価を行います。そのため、社員に職種を特化させず、さまざまな職種や業務を経験させることが可能です。その結果、幅広い視点から問題解決ができるゼネラリスト育成の促進につながり、組織全体の創造性や革新性は向上するでしょう。
公平な評価システムが構築できる
職能資格制度では個人のスキルや能力に応じた評価が行われるため、公平で透明性の高い評価システムが構築できます。社員同士の納得感が得られやすいだけでなく、能力を高めることで昇格・昇給も期待できるため、社員のモチベーション向上にもつながります。
職能資格制度を導入する際の留意点と対応策
職能資格制度の導入で多くのメリットが得られる一方、留意点もあります。どのようなことに留意すればよいか、さらにその対応策について解説します。
評価基準が曖昧になりやすい
職能資格制度は職務遂行力で評価が決められます。しかし、社員個人が持っている能力が担当する業務とそのまま直結していないこともあるため、実際の業務における成績と評価にズレが生じてしまう恐れがあります。また、他の制度では職務の成果や達成度に対して客観性をもって評価することが可能ですが、職能資格制度での評価は評価者の主観が入りやすく、不公平な結果になる可能性も出てくるでしょう。
対応策としては、定量的な指標と定性的な評価を組み合わせた明確な評価基準を設定することが肝要です。スキルや能力の測定はできるだけ客観的に行い、具体的な事例や行動基準を用いて評価しましょう。評価者のバイアスや主観が入るリスクに留意してください。加えて、設定した評価基準を全社員に共有することで、社員に安心感を与えられるでしょう。
多様なはたらき方に対応しにくい
働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、リモートワークや時短勤務、ワークシェアリングなどのはたらき方が普及しつつあります。この状況に応じ、人事評価の仕組みの見直しが必要になってきていますが、職能資格制度を採用している企業ではこれらのはたらき方に対応していない部分も多いのが現状です。職能資格制度においてもフレキシブルなはたらき方に対応した評価基準や仕組みを取り入れて、対応していくことが必要となります。
多様なはたらき方についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>ダイバーシティ推進の盲点!必要性と成功するための取り組み事例を解説
>>ハイブリッドワークとは?メリットや導入する際のポイントを解説
>>フレックスタイム制の目的や導入する際のメリットや留意点をご紹介
>>時差出勤を企業が導入する際のポイントやメリットについてご紹介
人件費が高騰する傾向がある
職能資格制度は社員の能力が下がらないことを前提に作られているため、退職がない限り基本的に降格しません。勤続年数の長い社員が多くなるほど支払う給与が増える仕組みのため、その分総人件費もかかる傾向があります。
他の制度では社員の成果によって等級が上下し、給与が下がるケースもあるため、ある程度の調整ができます。しかし、職能資格制度では余程の事情がなければ給与額が維持されます。その結果、経営を圧迫する原因となる恐れがあるでしょう。企業業績が順調に伸びているときは問題ないですが、業績が低下した場合は企業にとって負担となります。
対応策としては、能力に応じた適切な報酬体系を設計し、必要に応じて修正することです。コスト管理を強化し、予算内での運用を徹底しましょう。
人件費削減についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>人件費削減とは?メリット・留意点や具体的な方法を解説!
職能資格制度の導入と見直し方法
等級制度を効果的なものにするには、計画的に作成することが重要です。ここでは、職能資格制度の導入の流れと見直し方法をご説明します。
等級の決定や見直し
職能資格制度を導入するには、最初に等級数をいくつにするか決める必要があります。そして「上司から指示された仕事ができる」「指示がなくても自分で考えて仕事ができる」「後輩に指示を出せる」など、各等級のスキル要件や責任範囲を明確に定義しましょう。組織の変化や市場のニーズに対応するため、定期的に等級制度を見直すことも大事です。
評価基準の設計や見直し
各等級に求められる具体的なスキルや成果を評価項目として設定します。各等級の評価基準としては、「情意評価」「能力評価」「成績評価」の3つの観点から評価することが大切です。
「情意評価」とは、社員それぞれの仕事に対する姿勢や責任感、努力などを評価基準にするものです。会社のビジョンに基づいた行動や規律性、積極性などをポイントとします。
「能力評価」は業務に必要な知識やスキルを評価します。短絡的な成果では評価せず、業務に対する理解力や実行力などを長期的に評価します。企業にとって、「能力評価」は人材育成ができているかどうかの指標になるでしょう。
「成績評価」は、社員の業績や成果を評価します。目標の達成率やプロジェクトへの貢献度などを、具体的に数値化して計測していきます。
3つの観点から評価することで、公平かつ具体的な評価基準となります。また、これらの評価基準についてはその後も定期的に見直していくことが重要です。
能力要件の設計や見直し
企業が社員に期待する期待能力を等級別に示した「職能要件書」を作成します。これにより、スキルや能力など各等級の能力要件をより具体化することができます。
そのためには部署ごとに業務分析し、等級や職種などの実情に見合った評価基準を定めることが大切です。また、業務に必要なスキルと習熟度を一覧表にしたスキルマップを作成し、点数付けを行うことで、社員の能力開発の支援がしやすくなるでしょう。
組織の成長や市場の変化に応じて、能力要件の見直しを定期的に図ることも重要です。必要なタイミングで修正することで、持続的な人材育成が実現します。社員にとっても自身のキャリアパスを明確に描き、目標に向かって努力できるでしょう。
社員参加の促進とフィードバックの収集
職能資格制度を導入する前に制度の目的や意義を周知する説明会を実施し、制度の理解を深める必要があります。その際、社員からの意見やニーズを積極的に取り入れると改善点が見つけやすくなるでしょう。また、社員からのフィードバックを制度の改善へ反映させることで、社員の納得感は高まります。その結果、制度の効果的な運用も可能になります。
評価者から社員(被評価者)に対する評価結果のフィードバックも必要です。改善点や目標を明確に伝えることで、社員の成長を促すことができます。
管理者のトレーニングとサポート体制の構築
職能資格制度において、モチベーションや態度に関する評価は主観的に行われる可能性があります。その結果、社員の不満につながる可能性が出てくるでしょう。
それを避けるためには、管理者や評価者に対するサポート体制の構築が重要です。適切なトレーニングを行い、公平で適正なスキル評価を行う能力を向上させましょう。また、第三者の意見を取り入れたり、社員からのフィードバックを収集したりするなど、制度を正確に運用するための工夫も必要です。
職能資格制度についてよくある質問
ここでは、職能資格制度についてよくある質問とその回答をご紹介します。
Q1.職能資格制度の導入方法は?
まずは職能資格制度のメリットや留意点について理解した上で、等級数やスキル要件、責任範囲の明確化、職能要件書の作成を行いましょう。また、社員への周知やサポート体制の構築も必要です。
Q2.職能資格制度の等級数はいくつに分けるべき?
等級数の設定に法律上の決まりはなく、自由に設定できます。一般的な目安は、社員数が100人未満の場合は6等級、数百人規模の場合は6~9等級、1,000人以上の場合は9~10等級です。
Q3.職能の昇格を実施するタイミングは?
職能資格制度において、職能の昇格を実施するタイミングは、毎年春の昇給・昇格時が一般的です。試験や面接、レポートなどを実施し、要件を満たした社員を昇格させます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
職能資格制度のメリットや留意点を理解する
職能資格制度は個人の職務遂行力を評価対象とし、日本では多くの企業に導入されている等級制度です。
メリットとしては、幅広い業務を経験することでゼネラリストを育成しやすい、企業内での組織再編・人事異動を行いやすくなる、勤続年数も評価対象とされるので社員が長期にわたってはたらくことにつながるなどが挙げられます。
その一方で、人件費の負担が大きくなる、評価基準が曖昧になりやすく社員の不満につながる恐れがある、リモートワークや時短勤務など多様なはたらき方に対応しにくいなど留意点があるのも事実です。
メリットと留意点を把握し、適切な導入をすることで、職能資格制度は生産性向上などの大きな恩恵を企業にもたらすでしょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする