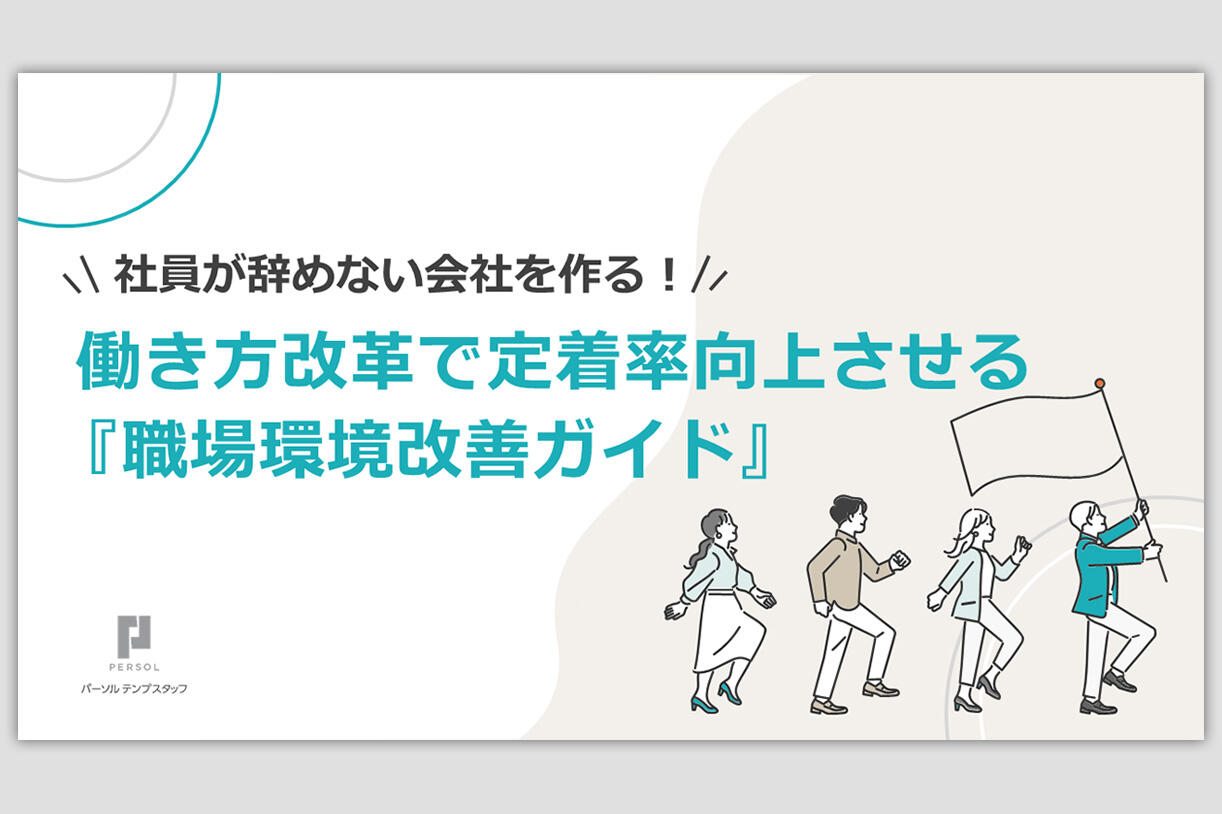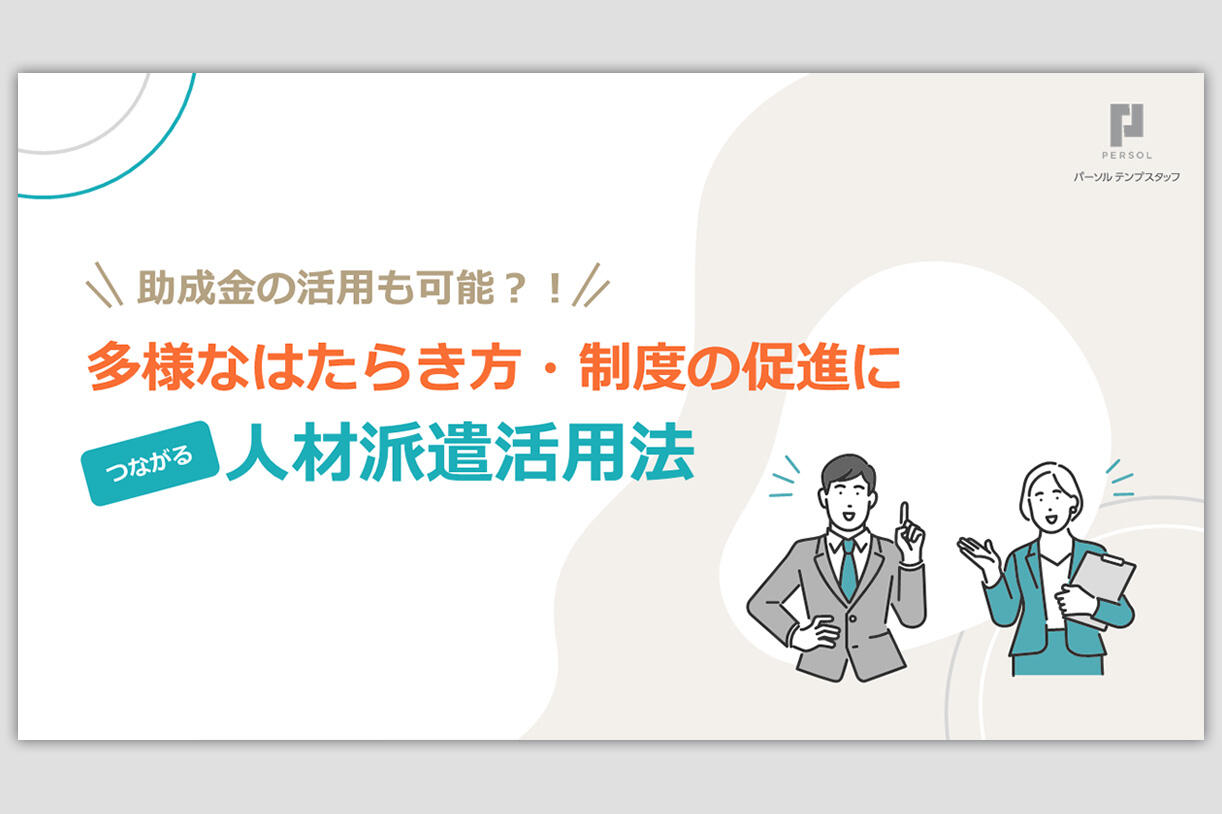HRナレッジライン
カテゴリ一覧
時差出勤とは?導入のポイントやメリットを解説
- 記事をシェアする

働き方改革やはたらき方の多様化により、勤務体系も多様化し、時間、場所、さまざまな選択が可能になりました。始業時間と終業時間を変更する時差出勤という勤務体系があります。鉄道や道路交通などの混雑緩和の目的もある一方で、育児や介護により業務時間を変更したい社員や、自身の業務が発生する時間のために業務時間を変更したい社員にとって、メリットの多いはたらき方として注目されています。時差出勤のメリット、時差出勤を導入する際のポイントなどを解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
時差出勤とは
時差出勤とは、事業所のすべてまたは一部の始業時間と終業時間を変更する勤務形態です。多くの企業が設定する一般的な始業・終業時間と異なる時間帯に出勤することで、出退勤時の鉄道や道路交通の混雑・過密を避けられます。通常は勤務時間の総時間数を変えず、時間のシフトのみで調整を行います。
フレックスタイム制度との違い
時差出勤の場合、出勤時間は事前に決められており、社員は決められた時間帯に出勤する必要があります。フレックスタイムは、一定期間(清算期間)のうちあらかじめ決めた総労働時間の中で、労働者が自分の意思で(1)始業時間、(2)終業時間、(3)1日の労働時間を決めることができる勤務形態で、より柔軟性の高い勤務形態です。多くの場合、一日の中で必ず出勤すべき時間帯(コアタイム)として、その前後の時間帯をフレキシブルタイムとします。フレキシブルタイム中なら何時でも出社・退社してもよい仕組みです。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
時差出勤のメリット
時差出勤を導入すると、企業やはたらく社員にとって、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。それぞれ詳しく解説していきます。
生産性の向上
時差出勤の導入により、通勤ラッシュを避けられ、通勤時間削減が可能です。ストレスや身体的負担を軽減し、業務に集中できるでしょう。より生産的な時間帯にはたらけるため、集中力や創造性を最大限に発揮することが期待できます。朝型の人は朝早く、昼型の人は日中からはたらくなど、個々の生産性のピークに合わせた柔軟なはたらき方が可能となります。
生産性向上については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
社員定着率の向上
はたらきやすさが向上すると、はたらくモチベーションがアップし、定着率の向上につながります。自身のパフォーマンスを最大限に発揮できることは、自身の評価を高めることにもつながります。その企業ではたらき続けたいという気持ちを持って、業務に取り組んでもらえるでしょう。
社員の定着率を向上させるための取り組みについては、こちらの記事でも解説しています。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
時間外労働の削減
時差出勤を導入すると、通勤ラッシュ時を避けて効率的に通勤できるようになります。これにより通勤時間を短縮し、仕事に充てられる時間が増えます。そのため、労働時間内に仕事を遂行しやすくなり、時間外労働の必要性が減少します。また、社員が夜遅くまではたらく必要がある場合、朝早く出勤しなくてもよい時間帯を選べるようにすると、時間外労働を減らせるかもしれません。より効率的にはたらける環境を整えることで、時間外労働が削減できる可能性が高まります。
ワーク・ライフ・バランスについては、こちらの記事でも解説しています。
>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説
採用時のイメージ向上
新たな人材を採用する際にも、柔軟なはたらき方を提供している企業であるというアピールポイントにより、企業のイメージは向上します。時差出勤の導入により、社員のワーク・ライフ・バランスを大切にしている、という企業の姿勢を伝えることができるでしょう。
中小企業の人材採用の現状や課題、採用成功のポイントは、こちらの記事でも解説しています。
>>中小企業が採用を成功させるポイントを徹底解説
時差出勤を導入する際の留意点と対策
メリットの多い時差出勤ですが、実際に企業が時差出勤を導入する際の留意点とその対策には、どのようなことが挙げられるでしょうか。
勤怠管理が複雑化する
留意点としてまず考えられるのは、社員の勤怠管理です。全社員が一律で同じ時間に出勤する場合の勤怠管理と比べ、時差出勤を導入することにより勤怠管理の工数が増えることが予想されます。まずは時差出勤が可能な時間帯に関しての明確なルールの策定、労務管理システムの導入やタイムカードや申請の電子化など、勤怠管理担当者の負担ができるだけ増えないよう、管理の手間を簡略化する工夫が必要になります。
パーソルグループでは、ホワイトなはたらき方を実現する労務管理ツール「MITERAS」を提供しています。
詳細はこちらをご覧ください。
深夜割増賃金を考慮する必要がある
時差出勤を導入する際には深夜割増賃金についても留意が必要です。22:00〜翌5:00までの労働には、深夜割増賃金が生じるため、時差出勤として設けている始業時間の設定によっては深夜割増賃金が生じる場合があるので注意が必要です。
深夜割増賃金が発生すると、勤怠管理の担当者の負担も増えるため、勤怠管理システムに深夜割増賃金の自動計算機能を付けるなどの工夫が必要です。また、遅い時間にはたらくことに関して、法令や労働規則を遵守することも重要となります。
社内連携が取りづらくなる場合がある
時差出勤の導入により、社内での連携が取りづらくなることもあるでしょう。部署内や、他部署でも同じ業務を社内で分担している場合もあります。それぞれが異なる就業時間であるため、業務連絡や打ち合わせの時間が取りづらかったり、コミュニケーションが不足したり、協力体制が構築されなかったりと、社員同士の協業・連携が困難になる場合が考えられます。
対策としては、定期的なミーティングやコミュニケーションツールの導入、共通の作業時間の設定など、短い時間でもお互いの業務の進捗などが共有できる仕組みが必要です。
時差出勤に向かない業務がある
すべての職種で時差出勤にメリットがあるわけではなく、時差出勤に向かない業務内容もあります。リアルタイムで対応が必要な業務は、時差出勤に向かないといえるでしょう。
代表的な業務では顧客対応、サポートのほか、生産ラインや製造業務、安全管理やセキュリティ業務などが挙げられます。社内にこのような業務がある場合、業務の優先度を考慮し、その業務に対応できるメンバーに割り当てるようにしましょう。また、社員と相談のうえ、時差出勤に適さない業務について個別の対応を行うなどの配慮も必要です。
時差出勤を導入する際のポイント
時差出勤を実際に導入する際のポイントについて解説します。時差出勤を検討する際にはこれらのポイントについてもあらかじめ確認しておきましょう。
対象の社員を設定する
まずは時差出勤の対象となる社員を設定します。これまで時差出勤が必要と考えられてきたのは、看護・介護や妊娠・育児中の人、傷病を負っている人などでした。しかし、近年では、ワーク・ライフ・バランスの向上、メリハリのあるはたらき方による生産性向上を目的に、より広い社員を対象とするパターンも見られているようです。
業務上の理由に限らず、自己都合でも利用可能にするなど、より広く利用しやすい制度にすることが求められます。保育園・介護施設への送迎や子の学校行事、通院など、これまで想定されていた活用方法だけではなく、自己啓発や社会活動への参画などをも適用事由にするといった対応を取ることは、社員のモチベーション向上にもつながります。全ての社員に適用するのか、あるいは時差出勤が可能な特定の部署や役職に限定するのかといったことも、社内で検討するようにしましょう。
就業規則を整える
就業規則の必須の記載事項である始業および終業時刻は明確にしなければなりません。そのため、従来の就業規則に始業・終業時間を変更できる旨の定めがない場合は、時差出勤導入時に労使の話し合いにより決められた始業・終業時間について記載する必要があります。
勤務時間の範囲、勤怠管理の方法などを規定しましょう。勤務時間に関しては、法令や労働規則を遵守したうえで、時差出勤に関する明確な規定や条件を示すようにしてください。
事前に社内周知を行う
制度の活発な利用を促すために、事前に社内周知・説明を行いましょう。導入理由やその目的に加えて、ルールや申請方法、従来との変更点を説明するようにします。社員が気兼ねなく利用しやすくするために、簡易な申請・許諾の仕組みを整えられるとよいでしょう。さまざまな職種・立場の社員の意見を事前に吸い上げることで、導入の際にも理解を得やすく、また利用しやすい制度にできます。
フィードバックと改善を行う
時差出勤導入後は定期的に社員からのフィードバックを収集し、制度やルールの改善点を検討するようにします。制度は導入して終わりではなく、その後の運用が大切です。問題点や改善すべき点を把握して迅速な対策を講じることで、制度の運用をより効果的にしていくことができるでしょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
時差出勤を導入してはたらきやすい環境を整える
導入にはメリットや留意点、気を付けるべきポイントがある時差出勤ですが、効果的な運用ができればその企業ではたらく社員のはたらきやすさは大きく向上します。通勤時間の快適さや、ワーク・ライフ・バランスの実現など、はたらく社員にとってのメリットに加えて、残業時間の削減や生産性の向上が期待されるため企業にも大きなメリットがあります。
一方で、勤怠管理に関して業務が増加したり、時差出勤ができない職種があったりと留意点もあるため、導入前に社内でシミュレーションをしたり、不平等にならないように対策を取ることが必要となります。多様なはたらき方を実現し、社員がはたらきやすい環境を整備するために、導入前に適切に準備をし、効果的な制度となるようにしましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする