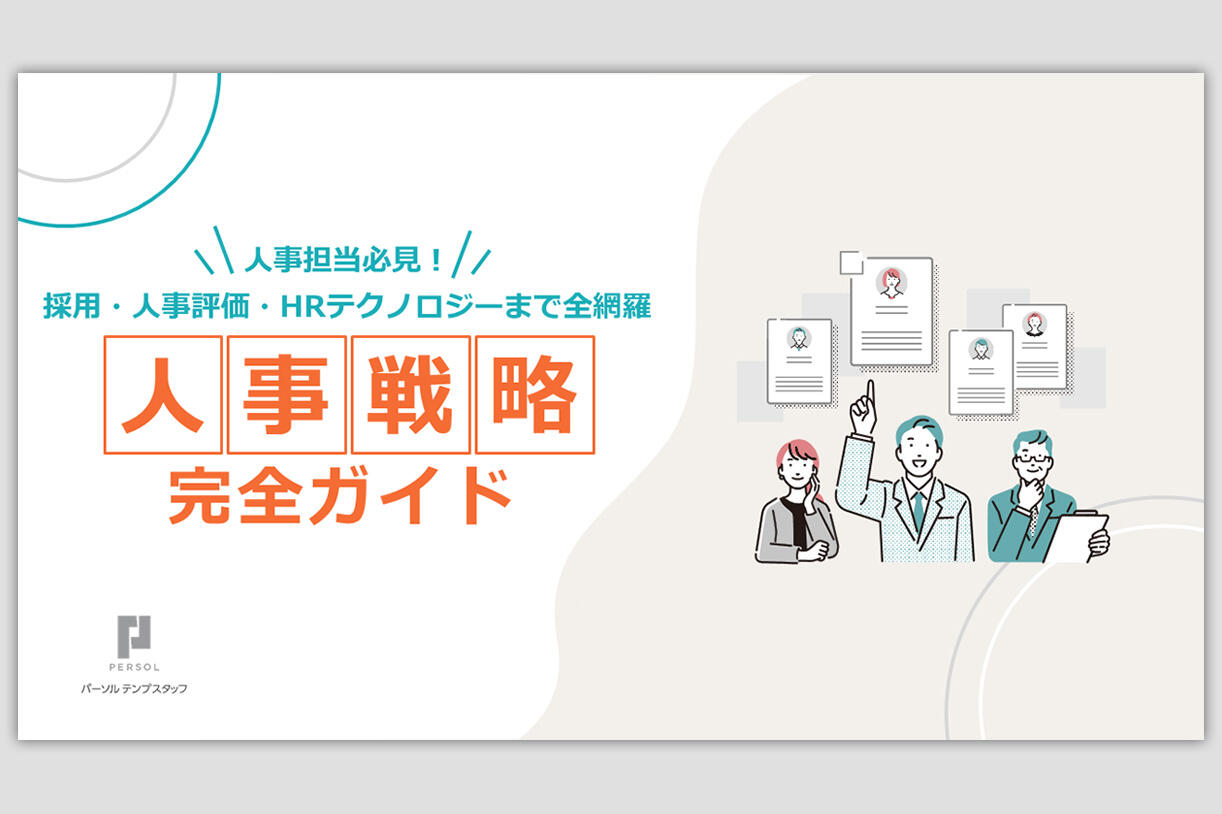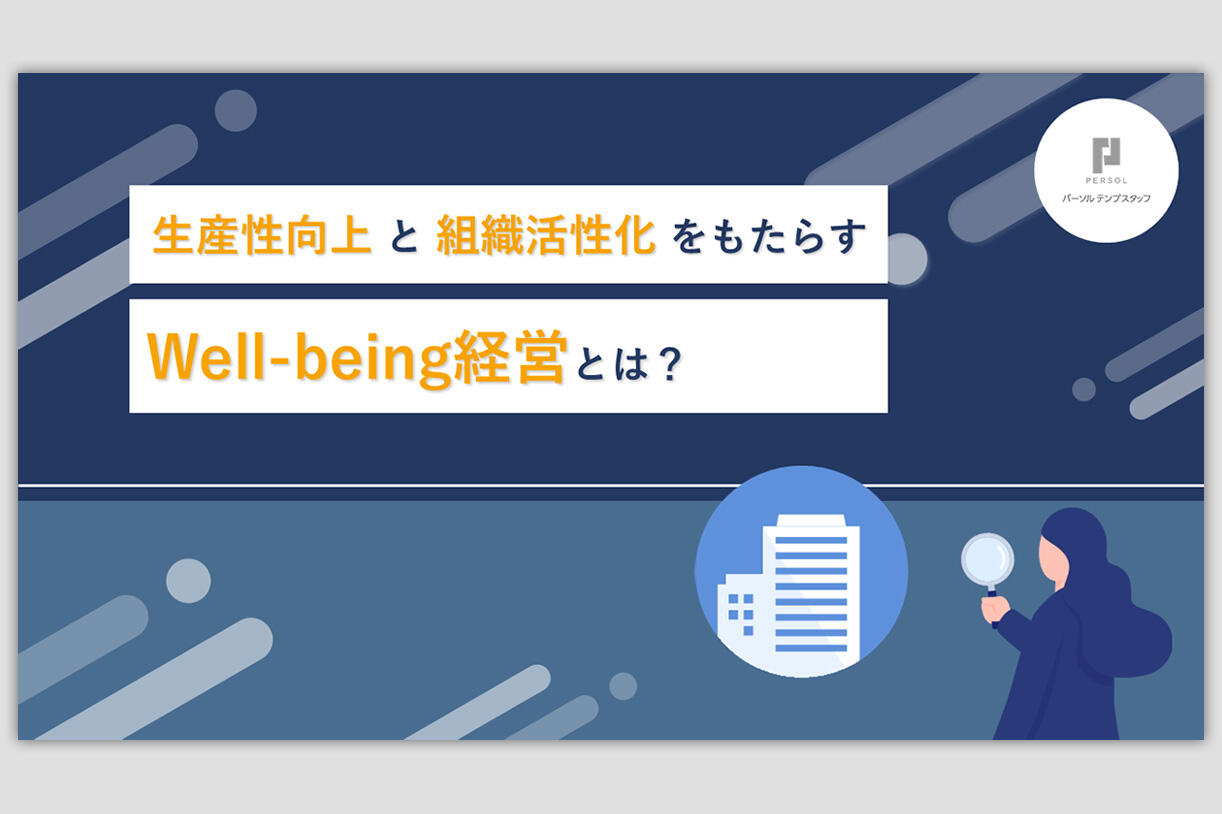HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【企業向け】人材育成とは?社員定着のための取り組みを解説
公開日:2025.10.28
- 記事をシェアする

企業の成長を支えるうえで欠かせないのが、人材育成の仕組み作りです。従業員一人ひとりの能力や意欲を引き出し、長期的に育成していく体制を構築することで、人材の定着と組織全体の成果が期待できます。
本記事では、人材育成の定義と目的から、よくある悩みとその解決策、具体的な育成手法や評価制度まで網羅的に解説します。
企業の成長を加速させる、「属人化しない」人材育成の仕組み構築にお役立てください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人材育成の定義と目的
人材育成とは、企業が従業員一人ひとりのスキルや能力を高めるために行う取り組みです。単なる研修やセミナーの実施だけでなく、組織全体の目標達成や事業継続を見据えた仕組み作りが重要とされています。
従業員の成長を促すことで、企業の競争力維持やイノベーション創出にもつながり、多様なビジネス環境に柔軟に対応できる組織へと発展していくのです。
さらに、人材を適切に育成することで、はたらく側のモチベーション向上も期待できます。自分の能力が企業から評価され、将来のキャリア形成につながると感じることが、エンゲージメント向上や離職防止の大きな要因となります。
特に、若手従業員の早期離職を防ぎ、長期的に組織を支える人材を確保するためには、計画的で継続的な育成施策が欠かせません。
人材育成が企業にとって重要な理由
企業の成長には、時代の変化に即した柔軟な戦略の立案と、戦略を実行できる人材の存在が必要です。
そこで、長期的に人材を育成し組織に定着させる体制を構築することは、優秀な人材を外部から取り込むだけでなく、内部からも生み出すことにつながります。
また、従業員一人ひとりのスキルやキャリア形成をサポートすることは、満足度が高まりやすく、離職率の低下にも寄与します。効果的な人材育成は社員のモチベーションを高め、コミュニケーションやチームワークの強化にもつながり、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。
つまり、人材育成は企業の成長と競争力を維持するために重要であるといえます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
よくある悩みと、人材育成がうまくいかない理由
人材育成を推進するうえで、よく挙がる問題点とその背景を把握することが重要です。
人材育成の導入や定着がうまくいかない理由について、一つずつ解説していきます。
育成能力と指導意識の不足
上司や先輩社員が教える役割を担う場合でも、その人自身が十分な育成方法を学んでいないケースがあります。
これによって、実務の場面で場当たり的な指導に終始し、従業員の理解度に差が生じやすくなります。
さらに、指導力や育成に対する意識が社内で認められにくい風土があると、教える側も主体的に指導を行わなくなる可能性があります。結果として、教育の質がばらつき、組織としての学習効果を最大化できない状況を招くのです。
実際に、厚生労働省の「人材育成上の課題」の調査によると、多くの企業が「上長等の育成能力や指導意識が不足している」を、課題として認識していることがわかります。
育成の目的・意義が社内で共有されていない
研修や育成制度を導入する意図が明確になっていないと、育成を受ける従業員は自分の成長と企業の目標をどのようにつなげればよいのかが分かりません。
個人ごとにばらばらの学習意欲や理解度を持つ状態では、組織的な成果を上げにくくなるのです。
組織のトップや管理職が明確なビジョンを示し、それを全社的に共有することが大切です。共有された方向性があるからこそ、従業員は自分の学習ニーズを企業の成長とリンクさせて理解できるようになります。
ノウハウ・仕組みが言語化されていない
優秀な管理職やベテラン社員の経験が属人的に蓄積され、情報が十分に言語化されていない場合があります。その結果、担当者が異動や退職するとノウハウが途切れてしまい、人材育成が継続しにくくなります。
このような属人化を防ぐために、育成ガイドやマニュアルなどを整備し、組織全体で共有する取り組みが必要です。
リアルタイムで更新しながら蓄積していくことで、常に最新の状況に即した知識・手法を伝えられるようになります。
評価制度と育成施策の連動が不十分
いくら研修や新人教育を実施しても、学習結果が評価制度に反映されなければ、従業員のモチベーションが下がる恐れがあります。
人材育成に力を入れた成果が見えないままでは、管理職にも新たな育成企画に取り組む意欲が生まれづらいでしょう。評価制度との連動が不十分であることで、「成長しても報われない」「何が評価されるかわからない」と感じてしまう原因になります。
従業員が自分の成長を実感し、それがキャリアアップや報酬に反映される仕組みが整備されることで、学ぶことへの意欲を長続きさせることができます。
会社全体の評価基準と連動した分かりやすい目標設定がカギとなるのです。
人材育成手法の種類と特徴
人材育成にもさまざまな手法があります。
自社の課題や育成したい人材像に合わせて、最適な手法・施策を取り入れ、人材育成の効果を最大化することが重要です。代表的な種類と特徴、メリットと注意点についてそれぞれ解説します。
OJT(On-the-Job Training)
OJTとは、職場の上司や先輩社員がトレーナーとして指導を行う手法です。職場での実務を通じて業務のスキルやノウハウを身に付けるため、習得した知識をそのまま仕事に活かせるというメリットがあります。
また、上司・先輩と部下・後輩がOJTを通じて直接コミュニケーションを取ることができる点もメリットです。
ただし、上司や先輩の指導スキルによって効果に差が出るため、指導担当者のフォローアップが必要です。
メリット
- 実務に直結する知識・スキルを効率的に学べる。
- 日々の業務内で行うため、コストがかからない。
- 教える側との関係性が築きやすく、育成と評価が近い。
注意点・導入のポイント
- 教える側の能力に大きく左右される(属人化のリスク)。
- 教える時間が確保できないと「見て覚えて」になりやすい。
- 教育内容が標準化されていないと、教え方・内容にばらつきが出る。
OJTについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事も参考もしてください。
>>OJT進め方 計画・指導のコツから、失敗例と対策
Off-JT(Off-the-Job Training)
Off-JTは日常の業務から一時的に離れて行う教育訓練のことです。
Off-JTでは、セミナーやウェビナーなど、実務から離れた場所での集中的な学習が可能です。業務フローを一時的に切り離すことで、知識を体系的に学ぶことができる点が大きな強みといえます。
特に新しい技術や専門的スキルを学ぶ場合に効果的で、講師や外部の専門家からのインプットが得られるのもメリットです。
メリット
- 業務から一歩引いて、体系的に知識を学べる。
- 社内にない視点や考え方に触れられる(特に外部講師を活用した場合)。
- 複数人で参加することで、社内コミュニケーションの活性化にもつながる。
注意点・導入のポイント
- 現場での実践とつながらないと、「学びっぱなし」で終わりやすい。
- 時間・コストがかかるため、対象やタイミングを精査する必要がある。
- 現場と連携した内容にすることで、実務に活かしやすくなる。
また、スケジュール調整や費用の面で課題がある場合は、オンデマンド形式のeラーニングを組み合わせるのも良い方法です。
e-ラーニングのメリット
- 場所・時間を選ばず学べるため、業務の合間でもスキルアップできる。
- 一律の学習内容を提供でき、教育のばらつきを防げる。
- 進捗管理・テスト機能で、習得度の見える化も可能。
e-ラーニングの注意点・導入のポイント
- 「見ただけ」で終わらないよう、アウトプットの場(実践や振り返り)をセットにすると効果的。
- コンテンツが自社の業務に合っているかを見極める必要がある。
- 受講の定着支援(上司が声かけする、評価に反映するなど)がないと形骸化しやすい。
メンター制度
メンター制度は、若手社員(メンティー)に対して、年次の近い先輩社員(メンター)が1対1で継続的にサポートする制度です。特に新入社員が早期に組織に馴染むために有効であり、離職率の低下にも寄与しやすい特徴があります。
業務の指導だけでなく、悩み相談・キャリア形成などメンタル面も含めた支援をすることができます。
メンターの役割と責任を明確に設定し、定期的にコミュニケーションを取ることで効果を高めることができるでしょう。
メリット
- 若手の早期離職防止につながる(不安を早く解消できる)。
- 職場に相談相手がいることで、安心感や帰属意識が高まる。
- メンター側の育成力・マネジメント力も養われる。
注意点・導入のポイント
- メンターの育成・指導スキルに差が出ないよう、研修やガイドラインの整備が必要。
- メンターに任せきりにせず、人事がフォローや面談チェックをする仕組みがあるとよい。
- メンター・メンティーの相性や目標設定も配慮が必要。
メンター制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にして下さい。
>>メンター制度とは?概要やメリット、導入までの流れについて解説
目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO)は、社員一人ひとりが業務の目標を設定し、定期的に上司と進捗を確認しながら成長を図る仕組みです。
多くの企業で評価制度と連動しており、自身の目標が組織全体の方針やビジョンと結びついていると感じられることで、モチベーションが高まりやすくなります。
メリット
- 社員自身が目標に向けて主体的に行動しやすくなる。
- 上司との面談を通じて、方向性のズレを防げる。
- 業績評価と人材育成を同時に進められる。
注意点・導入のポイント
- 目標が曖昧だったり難しすぎたりすると逆効果のため、SMART原則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)で設定。
- 単なる数字目標ではなく、成長プロセスに焦点をあてた目標設計が重要。
- 面談の質が制度の効果を大きく左右する(形式的にしない)。
目標管理制度(MBO)については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>目標管理制度(MBO)の種類、メリットや留意点について解説
その他の人材育成の手法
他にも、目的や企業規模に応じて使える人材育成の手法は多数あります。 その一例をご紹介します。
- ジョブローテーション
- コーチング
- 1on1ミーティング
- 社内勉強会
- アクションラーニング
- 外部セミナー・カンファレンス参加
- 資格取得支援制度
- リーダーシップ研修/マネジメント研修
それぞれ得意な部分が異なるので、自社の課題に合わせて組み合わせて使うのが良いでしょう。
人材育成で大切な5ステップ
計画的に取り組むことで、効率的かつ効果的な人材育成を実現できます。 人材育成を闇雲に進めるのではなく、ステップを踏んで計画的に実行することが重要です。
それぞれのステップにおける目的と、実際にやるべきこと、ポイントを解説します。
ステップ1:現状把握と課題の抽出
目的
人材育成を始める前に、「今、何が課題か」「どの層にどんな育成が必要か」を正しく理解する。
やること
- 組織内で求められているスキルや、従業員がすでに保有している能力を整理する。
- 社員アンケートや1on1で社員の声を集める(例:「育成に関して困っていること」「成長実感があるか」など)。
- 離職率、昇格率、スキルチェックなどの定量データを確認する。
- 現場のマネージャーにヒアリングして実情を把握する(「指導が属人化している」「新卒が続かない」など)。
ポイント
- 「なんとなく育てたい」ではなく、経営・現場の課題と結びついた育成テーマを見出すことが重要。
- 育成の前に、「まず何を変える必要があるか」を整理すること。
ステップ2:育成目的・目標の設定
目的
人材育成が向かう「ゴール(=あるべき姿)」を明確にすることで、手段がブレないようにする。
やること
- 「誰を(対象)」「どんな力を」「どのくらいの期間で」育てたいかを整理。
例:若手社員に3年以内で自律的にプロジェクトを任せられる力をつけたい。 - 経営ビジョンと人材像をつなげる。
例:「地域密着×顧客対応力」 → 顧客志向の若手営業を育てたい。 - SMARTの原則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)で目標設定。
ポイント
- 抽象的な表現(例:「人材を強化する」)ではなく、行動やスキルで測れる目標にする。
- 目標を現場にも共有し、育成への納得感を高める。
ステップ3:育成方法の選定と運用設計
目的
設定した目標に対して、最適な育成手段を選び、現場で継続的に運用できる仕組みを整える。
やること
- スキルや階層に応じて手法を組み合わせる。
例:新入社員 → OJT+e-ラーニング/中堅 → 目標管理制度+Off-JT - 社内でできること、外部に頼るべきことを切り分ける。
- 実施頻度・役割分担・評価タイミングなどの「運用ルール」を明文化。
ポイント
- 研修を「やって終わり」にしないよう、実践や振り返りの導線をセットで設計。
- 教える側・受ける側どちらにとっても無理のない運用設計がカギ。
ステップ4:教える人への「ガイド」を用意する
目的
育成が属人化せず、誰が教えても一定の質で人が育つ状態をつくる。
やること
- OJT担当やメンターに対して、役割・やり方・注意点をまとめたガイド資料を用意する(例:OJTチェックリスト、フィードバック例、面談の進め方テンプレートなど)。
- 必要に応じて教える側にも事前研修や勉強会を行う。
- 定期的に情報共有し、教える側も学び続ける仕組みをつくる。
ポイント
- 育成の質は「教える人の力」に大きく依存するため、教える側の支援を惜しまない。
- 現場に任せきりにせず、人事・育成担当が後方支援に回る。
ステップ5:実行・評価・フィードバック
目的
育成の効果を測定し、継続的に改善することで、育成のPDCAサイクルを回す。
やること
- 育成施策をスタートし、進捗や変化を定期的にチェックする。
例:3ヶ月ごとの面談、受講率、業務成果との比較など - 本人・上司・人事それぞれからフィードバックを集める。
- うまくいっていない部分があれば、手法や設計を見直す。
ポイント
- 数字だけでなく、行動の変化や定着具合にも注目する。
- フィードバックを通じて、本人が「自分は成長している」と実感できることが定着へのカギ。
階層別の人材育成計画
人材育成は、若手や新入社員を対象に考えがちですが、全社員にとって必要なものです。 従業員の成長段階やキャリアステージに応じた育成計画を用意しておくと、個々のニーズを踏まえた最適な学習機会を提供できます。
新入社員や若手社員、中堅社員、管理職といった階層別にそれぞれ目標や学ぶべき内容を明確化することで、組織としてバランスよく人材育成を進めることができ、会社全体の競争力や定着率が高まります。
新入社員・若手社員の育成
新しく組織に加わった社員には、まずはビジネスマナーや業務の基本的な流れを確実に習得させることがポイントです。OJTを中心にしながら、並行して自主学習やOff-JTの場を設けると、早期に基本スキルの底上げが期待できます。
加えて、メンター制度を用いることで、職場内の人間関係の構築や業務の疑問を気軽に相談できる環境を作れます。初期のサポートを充実させるほど、組織への愛着やモチベーションが高まりやすいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育成のねらい |
|
| 育成内容 |
|
| 育成手法 |
|
| 育成のポイント |
|
中堅社員の育成
中堅社員は、実務スキルに加えて部下や後輩の指導、プロジェクトのリードなど、より高度な役割を担うケースが多くなります。
そこで、専門スキルの深化だけでなく、リーダーシップやマネジメントの基礎を学ぶ機会を提供することが重要です。
特定の分野での専門教育と、組織横断的な視点を養う研修を組み合わせると、本人のキャリアパスも明確になり、中長期的な成長を促しやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育成のねらい |
|
| 育成内容 |
|
| 育成手法 |
|
| 育成のポイント |
|
管理職・リーダー層の育成
管理職やリーダー層には、現場全体を俯瞰し、戦略的にチームを導く力が求められます。 そのため、リーダーシップだけでなく、組織の経営方針や事業計画を理解しながら、人材を適所に配置するタレントマネジメントの知識も重要です。
さらに、組織変革を牽引するためのコミュニケーション能力や意思決定スキルの強化が必要となります。多様性を受け入れる風土作りや、チームメンバーの能力を引き出す指導法などを継続的に学ぶことで、強固な組織力を築いていくのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育成のねらい |
|
| 育成内容 |
|
| 育成手法 |
|
| 育成のポイント |
|
パーソルテンプスタッフでの人材育成実施例
パーソルテンプスタッフでは、新入社員に対し、丸1年間定期的な研修を実施しています。
まずは入社後1ヶ月間、ビジネスマナー研修や自社の理念・グループ会社の事業内容などをしっかりインプットします。そして現場に配属されてからも、コミュニケーション研修や目標設定振り返り研修など、定期的に全国の同期と顔を合わせ、グループワークなどを行います。
コミュニケーション研修では、傾聴力・理解力・伝達力を学び、目標設定振り返り研修では今までの振り返りや次の目標を立てることを中心に行います。行った内容についてはそのままにせず、オフィスに帰ってマネージャーに報告するところまでを研修とし、人事で管理することで、人事評価にも活かすことができるのです。
また全国の新卒を集めたロープレ大会も実施し、全社的に新卒を育成する体制を取っています。
さらに、新卒3年目では、自身のキャリアに向き合うための宿泊型研修を取り入れています。2024年度は、“自分のキャリアは自ら創る”をテーマに、自己資源の棚卸や、今後やりたいこと・ありたい姿を考えるワーク、マネーリテラシーの講座など、丸二日間かけて実施しました。
※参考:人事担当者に聞いた!新入社員研修って何するの?担当者の想いとは?~前編~|パーソルテンプスタッフ公式
またパーソルテンプスタッフは、社員一人ひとりのキャリア自律をサポートする目的で、2022年に企業内大学「Temp University」を開設しました。
研修は手挙げ式で、金融リテラシーやタイパ(時間効率)向上、ライフキャリアや性教育といった幅広いテーマをカバーしています。社内講師による実践的な講義を通じて、社員が自らの意志で学び、互いに成長し合う文化が根づいており、社員のエンゲージメントにも寄与しています。
※参考:
社員とともにつくる企業内大学。「Temp University」はどのようにして生まれたか
【Temp University】社内講師も学んで成長! 講師勉強会を初開催!
人材育成を促進する評価制度と組織風土
評価制度と企業文化を連動させることで、人材育成の成果を最大化する環境を整えます。
人材育成を軌道に乗せるには、評価制度と組織風土が育成と切り離されずに機能していることが不可欠です。
学習成果や成長度合いが正当に評価される仕組みがあれば、従業員はさらなる挑戦と自律的な学習に意欲を持つようになります。
また、組織全体で「学び続ける姿勢」を大切にする文化を醸成することで、継続的な人材の成長と企業の活性化を両立しやすくなるのです。
タレントマネジメントによる適材適所
タレントマネジメントとは、社員一人ひとりのスキル・経験・特性・志向性などを可視化し、最適な配置・育成・登用を行う仕組みのことです。
社員の強み・弱みを理解することで、個人の能力が最大限発揮されるだけでなく、社内の人材配置もスムーズに行いやすくなります。異動や配属を戦略的に行うことで、成長機会を提供でき、社員それぞれが「自分はどう成長していくべきか」を明確にとらえやすくなり、育成施策へのモチベーションアップにもつながります。
研修・評価を一体的に運用するポイント
研修プログラムだけを充実させても、それが評価に全く反映されないと社員が学習した意味を見失う可能性があります。
研修と評価を連動させることで、学んだことが具体的にどのように仕事に役立ち、業績やキャリアアップに結びつくかを可視化しやすくなります。
また、評価結果から次回の研修テーマやアプローチを見直すことで、より効果的な育成計画を組み立てていくことができます。PDCAサイクルを回すように、学習と評価を絶えず連動させて改善を重ねる姿勢が不可欠です。
人材育成に使える補助金・助成金
人材育成に使える補助金・助成金として、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金などの制度がありますので、ぜひご活用下さい(2025年10月時点)。
人材開発支援助成金は、業務に必要な職業訓練や研修を行う際にかかる費用を一定割合で支援する制度です。特定の分野や新しいスキルの習得に焦点を当てた研修プログラムを計画するうえで利用しやすく、企業の負担を減らす手段として注目されています。
申請にあたっては、研修内容や実施期間を明確に示す必要があるため、計画段階から助成金の利用を見据えてプログラムを作成すると手続きがスムーズになるでしょう。
また、キャリアアップ助成金は、非正規雇用から正規雇用への転換や人材のスキルアップを促進するための支援制度です。アルバイト・パート社員などの雇用形態を見直し、キャリア形成に積極的に取り組む企業を後押しする意図があります。
多様な雇用形態を活用している企業にとって、人材を長期的に育成する仕組み作りとともに、雇用形態の見直しやキャリア支援が同時に進むメリットがあります。
人材育成についてよくあるご質問
人材育成についてよく寄せられる相談事項と、その解決に向けたポイントをまとめました。
Q1.育成計画はどのように作ればよいでしょうか?
育成計画を作る際は、まず組織の戦略や全社目標を明確にし、そこから逆算して必要なスキルや人材像を洗い出すことが基本です。次に、対象となる従業員の現状スキルを把握し、どのような育成手法をどのタイミングで用いるかを具体的に決めます。
実行段階では、教育担当者や部署間の連携を強化し、スケジュール通りに学習が進むよう調整しましょう。定期的なレビューとフィードバックを入れて計画を改善していくことも大切です。
Q2.新入社員以外にも人材育成は必要ですか?
すべての層において人材育成は必要です。特に中堅社員や管理職層は、組織を支え、後輩を導く役割を担うため、自身のスキルアップが組織の成長に直結します。
また、キャリアの後半に差しかかる社員であっても、新たな分野の経験を積むことでマルチスキルを形成でき、組織全体の柔軟性を高める効果があります。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人材育成で企業の成長を加速させよう
人材育成は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。明確な目的と属人化しない仕組みを整え、社員全体が能力を伸ばせる環境を作ることで、競争力の高い組織へと導きましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする