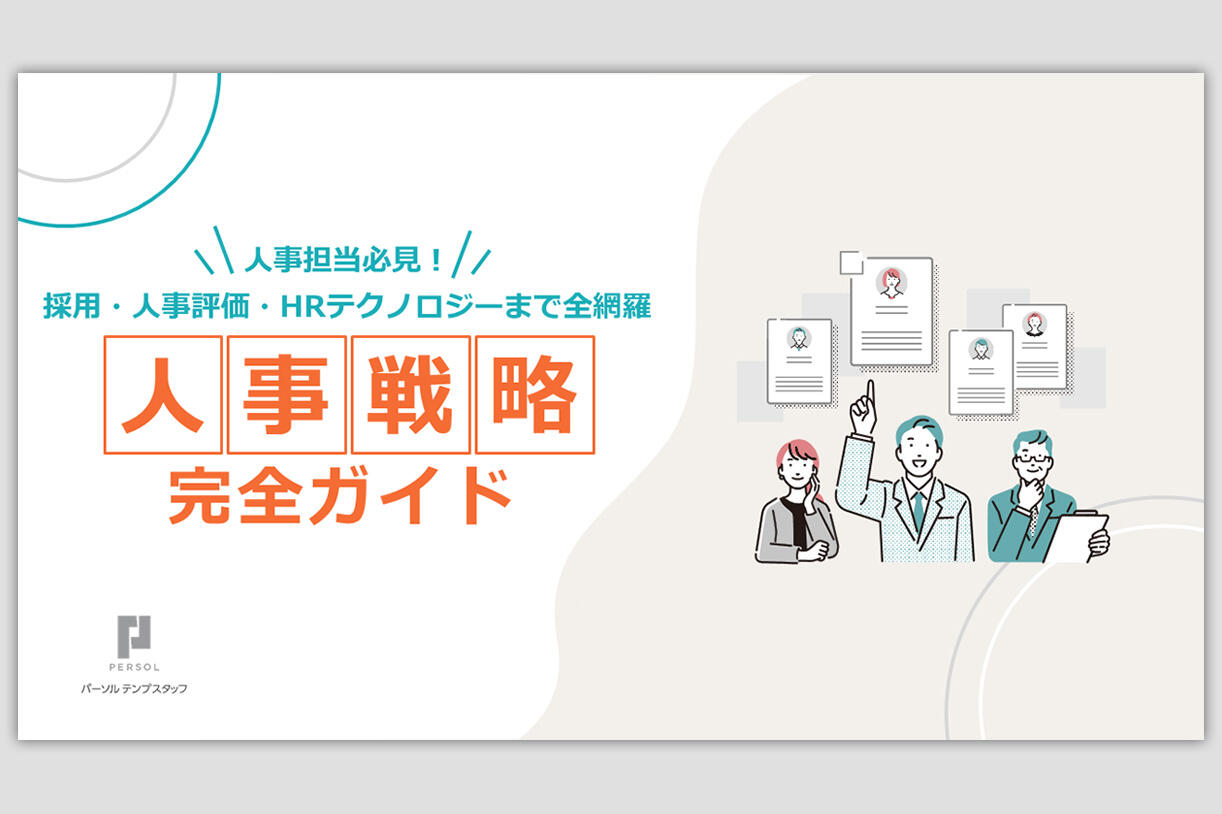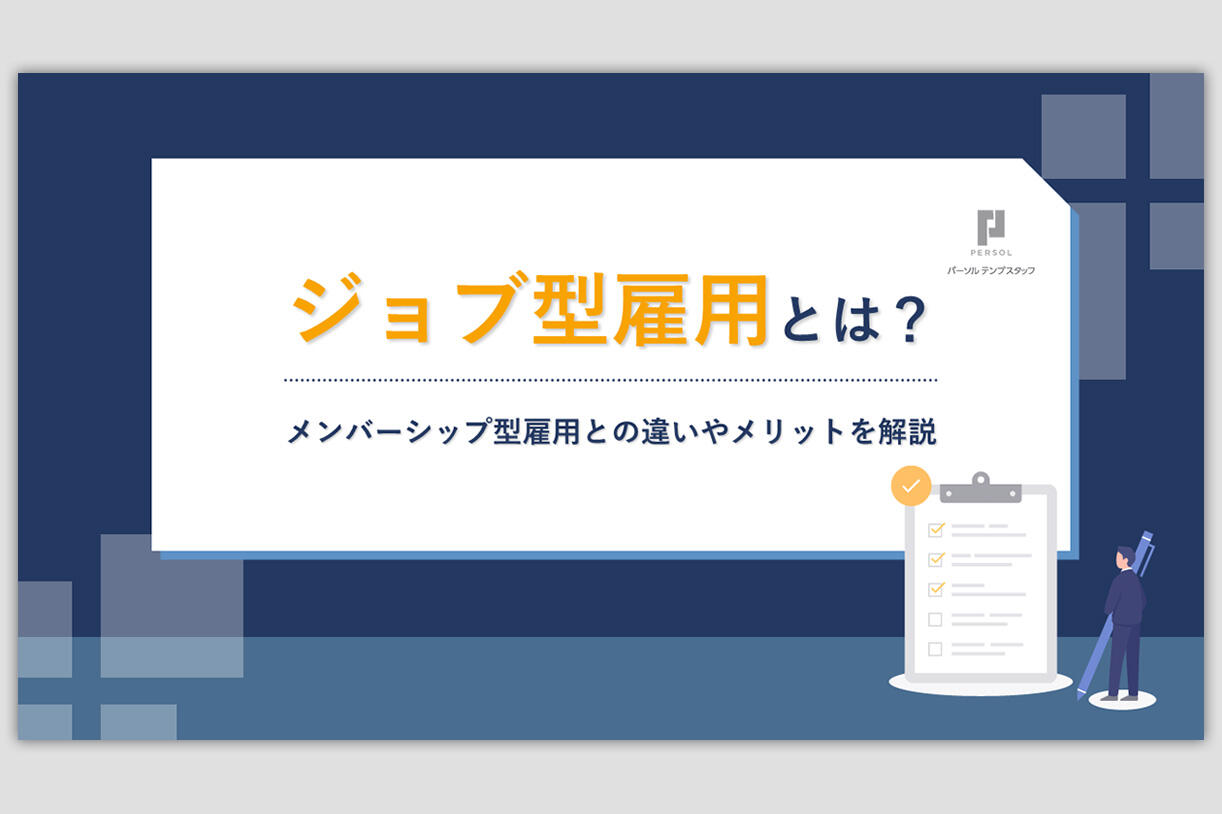HRナレッジライン
カテゴリ一覧
人事制度とは?設計方法や目的、見直しのポイントについて分かりやすく解説
- 記事をシェアする

人事制度は企業にとって、社員のモチベーションや生産性を向上させるために大切な制度です。
はたらき方や雇用の方法の変化が起こっている近年、人事制度の見直しをすることを検討している企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、人事制度の概要からあらたな人事制度の設計方法と見直し方法を解説します。
自社の人事制度の設計や見直しについて確認していきましょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
人事制度とは
人事制度は企業が社員の採用、雇用期間中の昇進・評価・報酬など、人材に関する制度を広く指します。
人事制度を設計する目的
人事制度は、組織内での人材の有効活用や組織自体の発展を促進することを目的としています。企業の目標達成や、競争力向上を図るために、社員のモチベーションを高め、生産性を向上させる役割があります。組織の公平性を保つことや、社員の生産性向上や定着率の改善を通じて、より一層企業を成長へ導く大切な制度なのです。
生産性向上については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事制度の主要な種類とその詳細
人事制度には主に3つの制度があります。等級制度、評価制度、報酬制度です。それぞれが大きな役割を担っています。
等級制度
等級制度とは社員の能力(職能)・職務・役割などによってランク分けする人事制度です。等級には序列があり、それに応じて給与や処遇が決まります。人材育成や配属の決定などにも用いられる制度です。
| 等級制度 | 対象 |
|---|---|
| 職務等級制度 | 職務内容や責任範囲に基づいて設定 |
| 役割等級制度 | 担う役割や貢献度に基づいて設定 |
| 職能資格制度 | スキルや能力に基づいて設定 |
職務等級制度
職務内容や責任範囲に基づいて設定されるのが職務等級です。職務の重要度や難易度に応じて等級が決まります。
役割等級制度
役割等級制度は、担う役割や貢献度に基づいて等級を設定します。役割の大きさや影響力に応じて等級が決まる制度です。
職能資格制度
社員が持つスキルや能力に基づいて等級を設定する制度です。業務に特に必要と考えられる特定の職能や資格を持つ社員を高く評価します。
評価制度
評価制度は、社員の業績や社員個人の能力を評価するための仕組みです。
| 評価制度 | 対象 |
|---|---|
| 職務評価 | 職務の内容や責任範囲を評価 |
| 役割評価 | 担う役割やチーム内での貢献度を評価 |
| 能力評価 | スキルや能力に基づいて評価 |
| 成果評価 | 業績や目標の達成に基づいて評価 |
職務評価
社員が担当する職務の内容や責任範囲を評価します。職務の重要度や難易度に基づいて評価します。
役割評価
社内で担う役割やチーム内での貢献度を評価します。役割の大きさや影響力に基づき評価を行います。
能力評価
スキルや能力による評価です。業務に特に必要と考えられる特定の職能や資格を持つ社員を高く評価、それに基づいて報酬を決定します。スキルアップやキャリア開発を促進するために用いられるものです。
成果評価
業績や目標の達成に基づいて評価をします。個人やチームの成果を数値や目標達成度で評価し、それに基づいて報酬を決定します。この評価方法は社員のモチベーション向上に寄与しやすいメリットがあります。
報酬制度
評価に基づいて、社員の給与やその他の報酬を決定する制度のことです。大きく4種類に分けられます。
| 報酬制度 | 対象 |
|---|---|
| 基本給 | 業績に応じて支給される特別な報酬 |
| 賞与 | 業績に応じて支給される特別な報酬 |
| 手当 | 基本給以外に支給される特別な給与 |
| 退職金 | 退職する際に支給される一時金 |
基本給
就業することで支払われる基本的な給与であり、定期的に支払われます。職務内容や等級、勤務年数などに基づいて設定される場合が多いでしょう。
賞与
所属部署・担当業務の業績や、企業の業績に応じて支給される特別な報酬です。年に数回支給されることが一般的です。業績に応じて金額が変動します。
手当
基本給以外に支給される特別な給与を指します。通勤手当や住宅手当など、特定の条件に基づいて支給される給与です。社員の生活や業務に関連する費用を補助する目的で支給されることが一般的です。
退職金
退職する際に支給される一時金を指します。勤務年数や最終給与額に基づいて計算され、社員の長期的な貢献を評価し支給されます。また、掛金を支払い、投資信託などで運用して60歳以降に老齢給付金として受け取る、確定拠出年金なども退職金制度の一つです。
人事制度の設計方法と見直しのポイント
評価制度の設計方法と見直しのポイントについて解説します。制度全てを設計する方法だけでなく、人事制度の中にあらたな制度を設ける場合、既存の評価制度の見直しについても解説します。
STEP1.経営理念の確認
まずは、経営理念を確認し、経営理念と人事制度に相違がないかをすり合わせましょう。人事制度の設計は、企業の戦略と一致させることが重要です。見直しの場合も、経営理念の変化がないか確認し、あらたな戦略や方針に合わせて調整することが求められます。
STEP2.現状の人事制度の分析
続いて現状の制度の分析です。現在の課題や問題点を洗い出します。アンケートや面談を実施し、社員の意見や要望をヒアリングしましょう。見直しの場合、過去のフィードバックや評価結果を活用し、改善点を具体的に特定するとスムーズです。
STEP3.各制度の設計
各制度について、企業のビジョンや戦略に基づいた目標を設定します。目標に応じた具体的な人事制度を設計し、評価基準や報酬制度、研修プログラムなどを具体化しましょう。見直しの場合、現行制度のどの部分が効果的で、どの部分の改善が必要かを明確にし、あたらしい視点やアプローチを取り入れます。
STEP4.シミュレーションの実施
最後の準備はシミュレーションです。新制度がどのように機能するかを事前に確認する必要があります。結果をもとに、必要な調整や修正を行い、制度の実効性を高めます。特に評価や報酬の基準が公平に運用されるか、問題点を洗い出して改善していきます。見直しの場合、変更点が現場にどのような影響を与えるか、シミュレーションを通じて確認し、リスクを最小限に抑えます。
STEP5.運用開始
社員に対して新制度の内容を十分に説明し、理解を促したのち運用開始するようにしましょう。定期的に制度の効果を検証し、フィードバックの仕組みを設けることが重要です。社員の意見を反映させながら柔軟に対応し、必要に応じて改善することを心掛けましょう。見直しの場合も、継続的な評価とフィードバックを通じて、制度の改善を図り、企業全体の成長を促進します。
人事制度にまつわる課題
人事制度にまつわる課題にはどのようなものがあり、その対応策にはどのようなことが考えられるのでしょうか。人事制度に関する課題について説明します。
多様なはたらき方への対応
近年増えている多様なはたらき方を導入することは、柔軟な勤務制度を設けるだけでなく、それに適応した評価基準や報酬制度の準備も検討しなければなりません。これまでと同様の評価や報酬では、バランスが悪くなる場合もあるからです。
多様なはたらき方に関しては、「ダイバーシティ」、「ワーク・ライフ・バランス」の概念も知っておく必要があります。詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介
>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説
専門的な業務の増加に伴う評価の複雑化
専門スキルを持つ社員の育成と確保を目指している企業も多い中、その社員たちの適切な研修プログラムやキャリアパスの整備、専門スキルに見合った評価と報酬の仕組みを導入する必要があります。また、専門職と一般職の間で評価基準を明確化しなければ、公平性の視点から社員の納得を得ることができません。
成果主義による人事制度の限界
成果主義を導入したにも関わらず、従来の人事制度のままだと、下記のような問題が発生する可能性があります。
- 短期的な成果に偏りがちで、長期的な視点が不足する。
- チームワークよりも個人の成果が優先されるため、社内の協力体制が崩れる可能性がある。
- 評価基準が曖昧だと、社員間に不公平感が生まれ、モチベーションが低下する。
これらの問題を解決するためには、あらたな人事制度の導入が必要になってきます。短期と長期の成果をバランス良く評価し、個人の成果だけでなく、チームの協力やチームへの貢献度も評価する仕組みを導入するようにしましょう。
チームビルディングについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>チームビルディングの目的とポイント、具体的な手法をご紹介
注目されている人事制度の例
近年注目されている人事制度を3つ紹介します。高い成果を生み出す社員を指標にして評価を行うコンピテンシー評価、ある職務実行のために求められるスキルや経験、資格などを持っているかどうかで人材を採用するジョブ型評価、組織全体の目標を定め目標を管理するOKR(Objectives and Key Results)です。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、高い成果を生み出している社員にヒアリングし、その成果の要因となっている行動特性を確認し、その社員をモデルに成果はもちろん、明確な基準を示すことが難しいとされていた業務プロセスに対しての客観的な評価ができる評価制度です。
コンピテンシー評価については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>コンピテンシー評価とは?4つのメリットと留意点を解説
ジョブ型雇用
ジョブ型雇用とは、企業が採用したい職種に関して、職務を実行するために必要となるスキルや経験、資格などを持つかを判断材料として、人材を採用する雇用方法です。
ジョブ型雇用については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>ジョブ型雇用の概要とメリット、導入するまでの流れをご紹介
OKR(Objectives and Key Results)
また、人事制度とは異なりますが、近年注目を集めているOKRもご紹介します。OKRとは、組織が設定する「目標」と「主要結果指標」を結び付け、企業の方向性を明確にする目標管理方法です。進捗確認や評価をしながら達成や生産性アップを目指し、企業・部門チーム・個人の階層ごとにOKRを設定して企業全体で同じ課題に取り組むことができます。
OKRについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>OKRとは?KPIやMBOとの違いや導入するメリットを解説
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事制度を設計して企業成長につなげる
人事制度の目的は、組織内での人材の有効活用や組織自体の発展を促進することです。企業の目標達成や、競争力向上を図るために、社員のモチベーションを高め、生産性を向上させる役割があります。そのため、人事制度の設計は企業の成長にもつながる重要な事項であると位置づけられます。人事制度は、等級制度、評価制度、報酬制度などに分けることができます。設計の際には企業理念などを再度振り返り、自社にあった人事制度を設計し、企業成長につなげましょう。
人事制度についてコラム記事があります。ぜひご覧ください。
>>【ナレッジコラム】人事制度の真実 vol.001 人事制度の誤解と真実の目的
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする