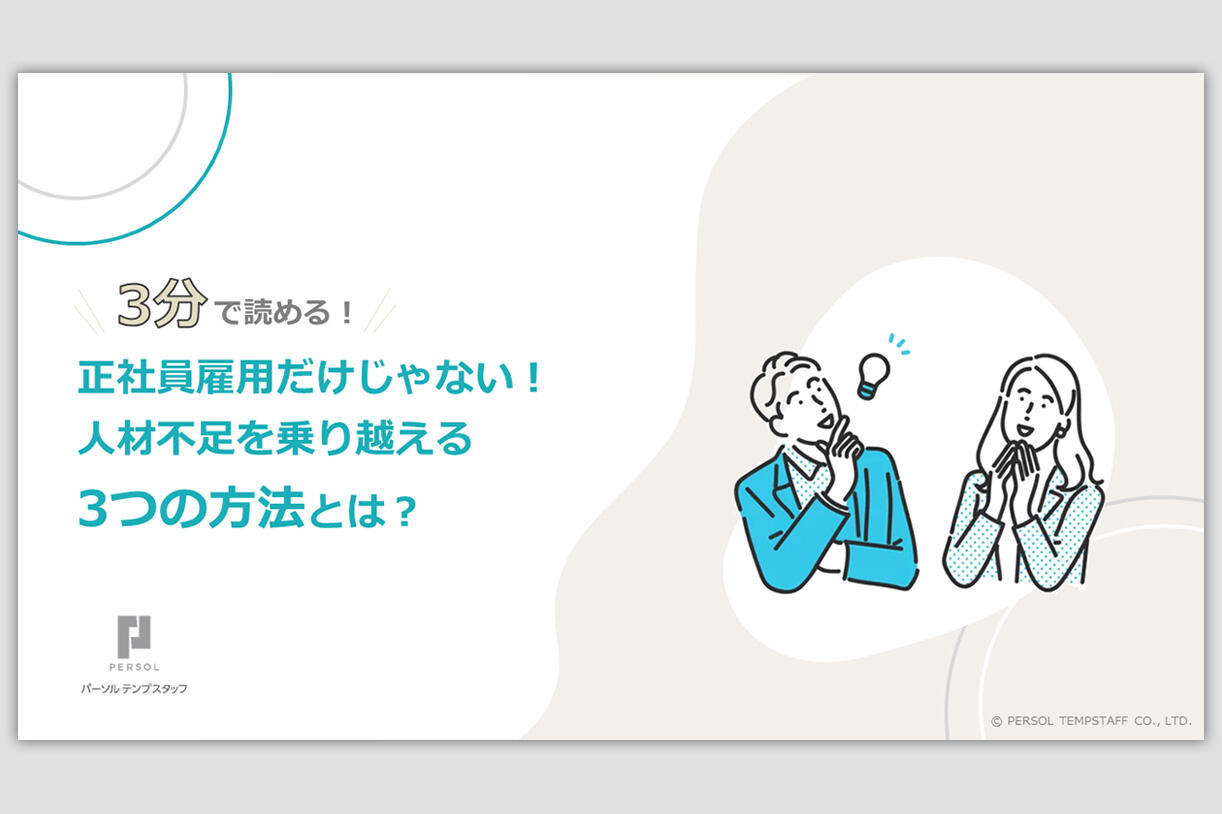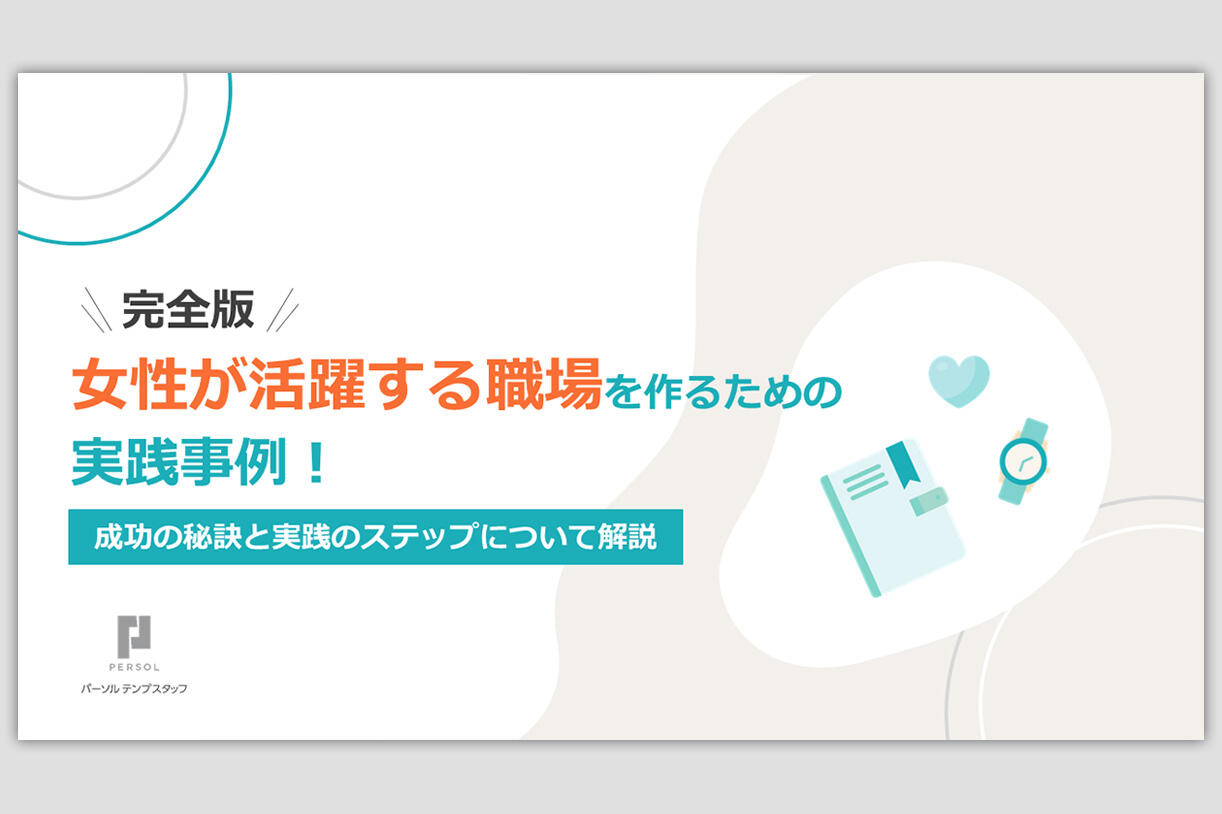HRナレッジライン
カテゴリ一覧
チームビルディングの目的とポイント、具体的な手法をご紹介
- 記事をシェアする

チームビルディングとは、チームのメンバーが能力とスキルを十分に発揮し、全員が一丸となって目標に向かうことのできる組織づくりの手法です。チームビルディングを導入することで、組織力の強化や生産性の向上などさまざまなメリットが期待できます。本記事ではチームビルディングの目的やメリット、実践方法などを詳しく解説します。チームのメンバーが最高のパフォーマンスを発揮するチームをつくるために、ぜひご確認ください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
チームビルディングとは
チームビルディングとは、メンバー一人ひとりが自分自身のスキルや能力を最大限に発揮し、ハイパフォーマンスを発揮できる環境づくりや取り組みのことを指します。
チームワークとの違い
チームビルディングと似た言葉に、チームワークがあります。チームビルディングは、チームづくりの具体的な取り組みを指します。業務の効率化などを達成すると共に、メンバー一人ひとりのそれぞれのスキルや能力を成長させる形でチーム全体が底上げすることも目的です。
一方でチームワークは、メンバー同士の結束を固めながら課題を達成することが重視されます。ただし、メンバーそれぞれの能力や人材育成させることは目的ではありません。チームビルディングとチームワークは、一人ひとりの能力を活かすための意識が異なります。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
チームビルディングの目的とメリット
新型コロナウイルス感染症の影響によるはたらき方の変化もあり、チームビルディングが注目されています。多くの企業がテレワークを推進してきたことから、メンバー同士が直接コミュニケーションを図る機会が減り、団結力の低下を懸念する企業は少なくありません。また、DX化やグローバル化によってビジネスを取り巻く環境が複雑化しており、スピーディかつ柔軟な意思決定が求められています。こうした問題を解決するためにも、チームビルディングを行う企業が増えています。
チームビルディングを実施することで、大きく以下4つのメリットがあります。それぞれについて解説します。
モチベーションの向上
チームビルディングによって、仕事に対するモチベーションが向上します。コミュニケーションの活発化などによってメンバー同士に信頼関係が築かれ、チームに一体感が生まれると、「自分もチームに貢献したい」というチームへの帰属意識やモチベーションがメンバーに生まれます。この感情が一人ひとりの能動的なアクションにつながり、チームの成果として反映されます。具体的な成果が表れると、メンバー自身のモチベーションがさらに向上するという好循環にもつながります。
生産性の向上
チームビルディングを通じて人間関係が良好になると、一体感が高まります。結果としてチームの機能性が増し、生産性や業務効率の向上が期待できます。
また、チーム内のコミュニケーションが円滑になりお互いに情報共有しやすくなることで、一人ひとりの生産性の向上も期待できます。加えて、チーム内の議論が活発になることでアイデアが生まれやすい環境にもなるでしょう。
生産性向上については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
マインドセットの形成
マインドセットとは、人間が持っている習慣化した思考パターンのことです。チームで目標を達成するためには、メンバーの認識をあわせることが重要です。チームビルディングを通じてメンバー同士が信頼関係を築き、一体感が生まれれば、それぞれのチームに対する貢献意欲は高まります。つまり、チームの目標達成のために必要なマインドセットをメンバー全員が新たに形成することが、チームビルディングを行う目的でありメリットと言えます。
チームメンバーの関係構築
チームビルディングによってメンバー全員が共通の目的、マインドセットを持つことでチーム内のコミュニケーションは活発になり、メンバー間で関係性が構築されます。コミュニケーションが活発なチームにいると他のメンバーの考え方や得意な仕事の分野がわかるようになり、相互理解も深まります。その結果、チームのパフォーマンスがよくなり、課題を解決しやすい環境づくりにつながります。さらに、チームの士気が高まることも期待できます。
チームビルディングの5段階プロセス
チームビルディングは、アメリカの心理学者ブルース.W.タックマン氏が1965年に提唱した「タックマンモデル」を用いると効果的に行うことができます。チームの成長を5段階のステージに分類し、各ステージでチームがどういう状況なのか示すことで効果的な施策の検討がしやすくなります。
タックマンモデルは以下5段階のステージとなります。
- 形成期
- 混乱期
- 統一期
- 機能期
- 散会期
ここからは、5つのステージの特徴について詳しく解説します。
1.形成期
チームの構成が決まったばかりで、メンバーはまだお互いのことをよくわかっていない状態です。チームとして目指すべき共通の目標も定まっておらず、それぞれの役割も決まっていません。自分が何をすればいいのかわからず、チーム内のコミュニケーションにも遠慮と緊張感があり、不安を抱えている人も多いでしょう。
この段階ではゲームやアクティビティなどのアイスブレイク活動や自己紹介など、お互いを知る機会を増やす施策を行うことが有効です。
2.混乱期
混乱期にはチームが始動し、アイデアや意見がたくさん出てきます。しかし、チームとしての目標が明確に定まっていないため、メンバー同士の意見が食い違いで衝突が生じやすい時期でもあります。
この段階で求められるのは、お互いを理解するためのディスカッションです。ワークショップなどを通じてメンバー間で対立を恐れずに意見を主張し合い、議論を重ねながら理解を深めるための対話を行うことが重要になってきます。その際はファシリテーター(スムーズな会議の進行を実現するための進行役)を導入するなど、お互いが納得するまで話し合えるようにサポートしましょう。
3.統一期
混乱期を乗り越えると、チームのビジョンや理念が徐々に浸透することで意見が統一され、協力し合える関係が構築できているフェーズへと入ります。
しかし、適切なコミュニケーションを維持しなければ、チーム内の統一感が失われる可能性もあります。その状態を避けるためにはメンバー同士のより深いコミュニケーションを推進し、共通の価値観の確立を目指して、チームのパフォーマンス力をさらに高める施策を行う必要があります。ビジネスゲームなどを取り入れたチームビルディング活動を通じ、一体感を強化していくことが有効と言えるでしょう。
4.機能期
機能期はチームが効果的に機能し、業務やプロジェクトに対して高いパフォーマンスを発揮する段階を指します。チームは共通の目的に向かって一丸となっており、メンバーは指示を受けなくても自分の役割を果たすために率先して行動することができます。チーム内には結束力があり、メンバー同士が互いにフォローできている状態でもあります。
しかし、過度なルーチン化や達成感によってマンネリに陥り、チームが停滞する可能性もあります。効果的に機能した状態を維持するためには定期的な評価や振り返りを行い、プロセスの改善を図っていく必要があるでしょう。
5.散会期
タックマンモデルの最後のステージである散会期は、チームが解散する段階です。目標の達成やメンバーの配置転換、時間的な制約などの理由で、チームは必ず散会期を迎えます。そして、メンバーは次のミッションに向かってチームを卒業していきます。
この時期、チームの解散や状況の変化により、不安を抱えたり、感情が不安定になったりするメンバーが出てくることがあります。チームリーダーはチームが今までにあげた成果や学びを振り返り、感謝やフィードバックの機会を設けるようにします。メンバー同士が互いに称賛し合う、チームの解散を惜しむ姿が見られるなどの場合、チームビルディングは成功したと判断できます。
チームビルディングに効果的な手法の具体例
チームビルディングを進めるための具体的な手法を5つご紹介します。自分のチームに合った、効果的な手法を取り入れることが重要です。
チームのルール作り
チームビルディングを実践する際は、メンバーが安心してはたらける心理的安全性が確保された環境が必要です。そのためには、チームビルディングを円滑に進めるためのルールづくりを検討します。
例えば、「他人の意見を否定しない」、「客観的なデータに基づいて判断する」など、メンバーを束縛するためではなく、互いを信頼し協力し合うためのルールづくりを意識することが大切です。
1on1の実施
1on1とは、チームリーダーと各メンバーがマンツーマンの状態でざっくばらんに話し合うことです。こうした機会を設け、全体ミーティングではわからなかったメンバー一人ひとりの意見を吸い上げます。
はたらき方や心身の健康状態、人間関係、不安要素などについてメンバーが本音を吐き出せる場を設けることで、問題の早期解決や信頼関係の構築につながります。その結果、風通しのよいチームをつくることができるでしょう。
ワークショップやセミナーの実施
ワークショップやセミナーを実施すると、チームワークを強めることに集中できます。ワークショップは、自発的なミーティングや共同作業によって参加者たちがひとつの目標達成を目指します。この取り組みで共通の目標を達成するという経験を重ねることで、チームに対する信頼や安心感が生まれ、一体感を強められます。
例えば、セミナーを開催してコミュニケーションスキルについての基礎的な知識をインプットする場を設け、取得した知識をワークショップでアウトプットするというカリキュラムを組むのもおすすめです。この際の目標達成経験によってチームに一体感が生まれ、チームビルディングにも役立つことが期待できます。
ゲームやレクリエーションの実施
ゲームの実施も効果的な手法です。タックマンモデルの5段階プロセスに合わせ、状況に合ったゲーム内容を決定することが大切です。
以下に、チームビルディングに活用されるゲームの代表的な例をご紹介します。
リーダーズインテグレーション
リーダーズインテグレーションはチームリーダーとメンバー間の信頼構築に役立つゲームで、チーム内のコミュニケーションがまだ十分でない「形成期」に行うと効果的です。
最初にリーダーがメンバーの前で自己紹介をしたのち、退室します。そして、残されたメンバーだけでリーダーに聞きたい質問や自分について知っておいてほしいことなどの意見を出し合い、ホワイトボードや紙に書き出します。その後、メンバーが退室し、入れ替わる形で入室したリーダーが書かれた内容への回答を考えます。最後にメンバーが改めて部屋へ戻り、リーダーが一つひとつの質問やメッセージに自分の意見を返します。
形成期はリーダーもメンバーも互いのことを理解できていません。しかし、メンバーの意見にリーダーが真摯に向き合うことで相互理解は深まり、チームの一体感が醸成されるでしょう。
アイスブレイク
アイスブレイクは特定のゲームを指す言葉ではありません。ゲームをすることで感情の氷を溶かし、気持ちの中の壁を壊すことを目的にメンバー間のコミュニケーションを円滑にさせる活動を言います。
代表的な例としては、自己紹介をかねて自分が興味を持っているトピックスについて話したり、相手に簡単な質問を投げかけたり形式のものがあります。よい雰囲気を作り出し、メンバー同士が気軽に話すことができるようにすることが目的です。軽いトピックから始めることで、メンバーが自然な形でコミュニケーションをとりやすくなります。チーム内の活発な議論が必要な「形成期」と「混乱期」に適しています。
チームビルディングを進める際のポイントや留意点
チームビルディングは、取り入れれば必ず成功するというものではありません。ここでは、成功させるために必要ないくつかのポイントと留意点を解説します。
明確なチーム目標の設定をする
チームビルディングを成功させるためには、明確なチーム目標の設定をすることが大切です。チームとして達成したい目標が抽象的だったり、明確に定められていなかったりすると、メンバーは何から取り組めばよいのかわからなくなり、モチベーションを保つことが困難になってしまいます。
リーダーが主導してチーム目標を定め、そのために全員の力が必要だと認識できれば、メンバーはより主体的に動きやすくなります。
メンバーの役割の明確化する
チームの能力を発揮させるためには、それぞれのメンバーの役割を明確化することが重要です。役割が明確になると、自分が何をするべきかが定まりやすく、どうすればチームに貢献できるか考えて行動しやすくなります。つまり、それぞれ最大限のパフォーマンスを発揮しやすくなり、チームとしての成果につながるでしょう。
メンバーの役割が明確化されていないと、プロジェクトがスムーズに進行しない、チームがうまく機能しない、などの恐れがあります。
多様な価値観を尊重する
チームビルディングを成功させるためには、メンバーそれぞれが持つ価値観を尊重する必要があります。全員が同じ方向を向くように強要するのではなく、個人が持つ考えや価値観を尊重することで相互理解は進み、チームの結束力は高まります。
メンバーが勇気を出して発信した意見を否定するのではなく、全体で尊重し合う雰囲気づくりも大切です。その結果、メンバー間で相互にサポートし合えるチームづくりにつながっていきます。
ダイバーシティについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介
チームの成功を共有し、認識する
成功体験はモチベーションの向上につながります。チームメンバーが成果を上げた際、その功績を表彰するなど、賞賛の気持ちを積極的に表しましょう。この取り組みによって、目標達成の事実がチーム内に共有されます。チームの成功がフィードバックされることで、さらなるチームビルディングの向上につながることが期待できます。
チームビルディング活動を継続的に実施する
チームビルディングで重要なのは一度きりで終わらせるのではなく、日々の業務の中で継続的に取り組みを実施することです。定期的にさまざまなチームビルディング活動を実施し、新たな課題に対処することで、チームの長期的な成長や結束など大きな効果につなげていきます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
チームメンバーの能力を最大限発揮できる環境をつくる
個人の能力やスキル、経験を最大限に活かしながら目標達成に向かって一丸となり、チームとして最高のパフォーマンスを発揮させること、それがチームビルディングの目的です。
チームビルディングの導入は、メンバー間のコミュニケーションの活性化やモチベーションと生産性の向上につながります。その結果、チームワークは強固になり、チームとしての成果や目標達成が期待できるでしょう。そのためにも、「タックマンモデル」を参考にしたゲームを行ってコミュニケーションを重ねたり、メンバーの役割を明確化したりすることが重要となります。それぞれの組織に合ったチームビルディングの実施は、組織の長期的な成長や発展につながるでしょう。
良質なチームをつくるために“ひと言声かけ”することも大切です。
チームのコミュニケーション作りについてはこちらも記事もぜひご確認ください。
>>声かけでメンバーのモチベーションをあげる!効果的な言い換えや声かけのポイントを解説
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする