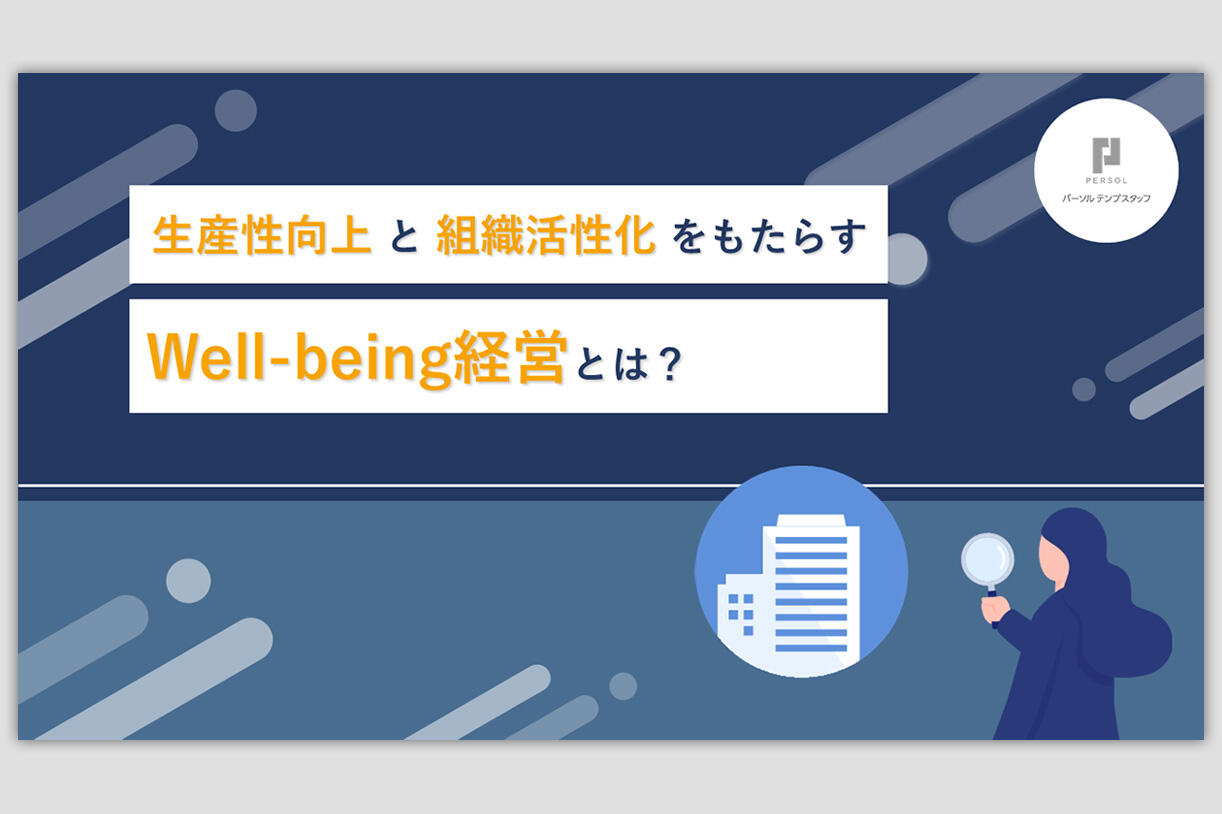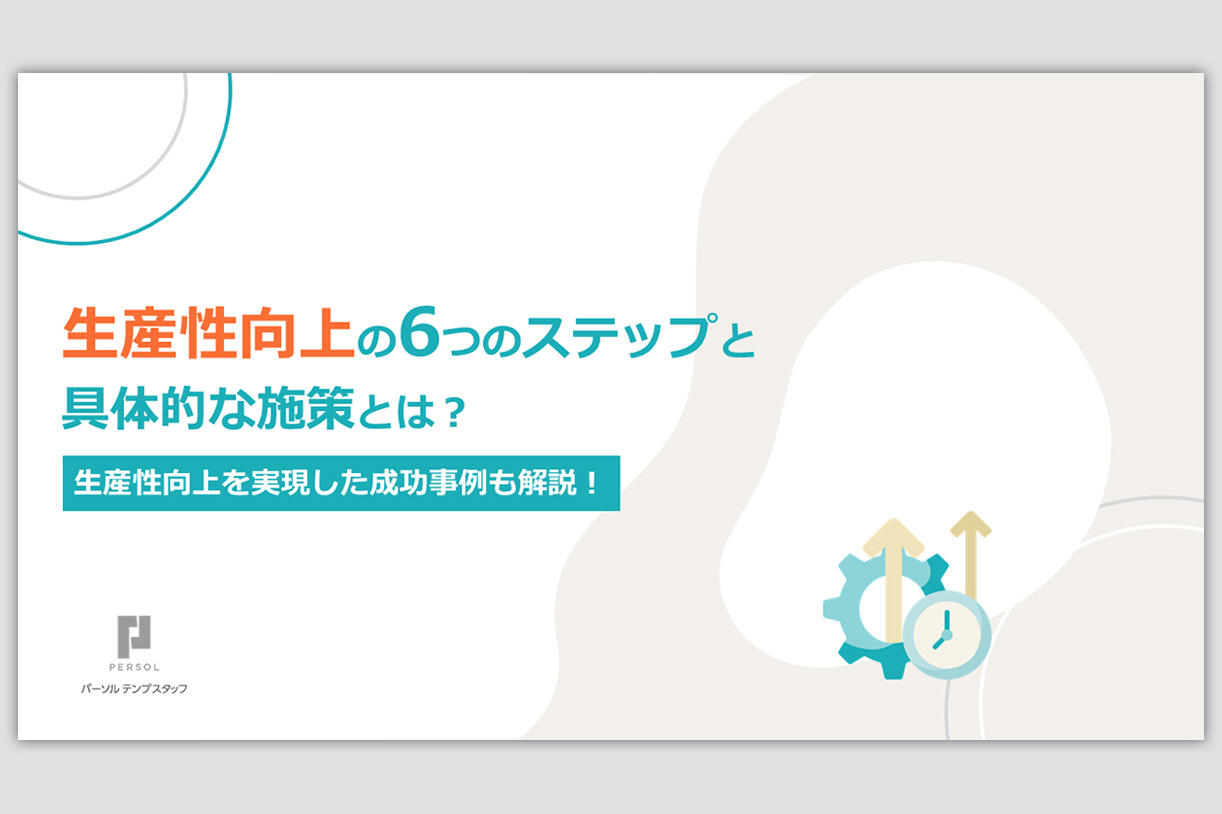HRナレッジライン
カテゴリ一覧
Well-being(ウェルビーイング)のメリットや留意点を解説
- 記事をシェアする

近年、社員のワーク・ライフ・バランスが重視され、働き方改革が推進されている中、企業の理想的な経営手法として「Well-being(ウェルビーイング)」が注目されています。しかし、「そもそもWell-beingとは何なのか」「具体的にどう実践すればいいのかわからない」とお悩みの方もいるかもしれません。
本記事ではWell-beingの意味や導入した場合のメリットなどを解説し、取り組み事例を紹介していきます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
Well-being(ウェルビーイング)とは
Well-being(ウェルビーイング)とは、Well(よい)とBeing(状態)を組み合わせた言葉であり、「よく在る」「よく居る」を意味した概念です。つまり、心身ともに満たされた状態を表しており、もともとは16世紀のイタリア語「benessere(ベネッセレ)」が語源です。
1947年に採択されたWHO憲章によれば、健康とは「身体的、精神的、社会的な側面すべてにおいて良好な状態」と定義されています。この定義はWell-beingの説明として用いられることもありますが、現在のWell-beingは一人ひとりの生活の質や経済的な生活条件、集団や社会といった範囲まで対象にした概念と認識されています。
また、幸せと訳されることの多いHappinessは一時的・瞬間的な幸福感を表しています。Well-beingはこの「Happiness」や「健康」を含んでおり、Happinessよりも幅広い概念と言えるでしょう。
Wellness(ウェルネス)との違い
Well-beingは生活の質や経済的な生活条件など、社会的な充実度や満足度が良好な状態を指します。対して、Wellness(ウェルネス)は主に身体的・精神的に健康になることを意味します。つまり、Well-beingはより包括的で総合的な概念であり、Wellness(ウェルネス)はその一部であると言えます。
Welfare(ウェルフェア)との違い
Welfare(ウェルフェア)とは福祉と訳され、社会的に弱い人や生活に困窮している人を救済するサービスという意味合いも含んでいます。一人ひとりの権利が尊重され、自己実現を社会的に保証するWell-beingとは意味合いが異なります。
Well-beingを実現させるために、Welfare(ウェルフェア)を整えると考えるとわかりやすいでしょう。Welfare(ウェルフェア)が手段で、Well-beingは目的という文脈で用いられることがあります。
Happiness(ハピネス)との違い
幸福を英訳するとHappiness(ハピネス)になりますが、これは一時的な幸せの感情を表しています。つまり、個人の主観的なスパンの短い幸せを指します。一方、Well-beingが表す幸福は一人の主観だけでなく、個人を取り巻く町や国が満たされた状態が持続することを指します。
つまり、Well-beingは社会が長期的に良好な状態になることを意味し、Happiness(ハピネス)と比較するとより包括的です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
Well-being(ウェルビーイング)の構成要素5つ(PERMA理論)
米国の心理学者マーティン・セリグマンは、Well-beingには5つの要素があると唱えています。P(Positive Emotion/ポジティブな感情)、E(Engagement/物事への積極的な関わり)、R(Relationships/他者とのよい関係)、M(Meaning/人生の意味や意義の自覚)、A(Achievement/達成感)の5つです。それぞれの頭文字をとり、「PERMA理論」と名付けられました。
これらの要素に積極的に取り組むとWell-beingを高めるだけでなく、心理的安全性の確保にもつながるでしょう。ここからは、PERMA理論の5つの要素をそれぞれ解説していきます。
ポジティブ感情(Positive Emotion)
ポジティブ感情は人生の幸福度を向上させる主要な指標です。うれしい・面白い・楽しい・感動・感激・感謝・希望などの肯定的な感情があります。日常生活での楽しい出来事や成功体験、他人からの賞賛や感謝の言葉などによって、ポジティブ感情を増やすことができます。
エンゲージメント(Engagement)
エンゲージメントとは時間を忘れて何かに積極的に関わったり、夢中になって興味を持つことを指します。「趣味や仕事に没頭する」、「自分の能力を最大限に活かして挑戦する」といった状況です。没頭・夢中、熱中などの感情があります。
関係性(Relationship)
Well-beingには友情や家族関係など他者との良好なつながり、すなわち関係性が大きな影響を与えます。友人や家族との交流、支え合うコミュニティーやチームメンバーとの協力関係など、援助や意思疎通は人生の幸福感や満足度を高めてくれるでしょう。
意味(Meaning)
自分自身より大きなものとの関係を意識し、自分は何のために生きているのかを見出すと、人生の意味や意義の自覚につながります。仕事や課外活動、ボランティア活動を通じて社会や他人に与える意義を理解し、実現することなどによって、人生の意味や意義を構築することができます。人生の目的を明確にしていくとWell-beingは高まります。
達成(Accomplishment)
目標を達成し、成功を感じると幸福感が向上します。例えば、プロジェクトの完了、スポーツや仕事での記録更新、個人的な成長や目標達成などの体験はポジティブ感情の源になり、大きなWell-beingを得られます。
Well-being(ウェルビーイング)が注目される背景
Well-beingに注目が集まってきた要因や背景は、主に4つあります。それぞれについて解説していきます。Well-beingが注目される理由を知ることでより深くこの概念を理解できるでしょう。
はたらき方の多様化
働き方改革の推進などにより、はたらき方の多様化しました。働き方改革とは、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保など、社員たちの職務満足の改善を目指したものです。リモートワークやフレックスタイム制の導入など社員にとってはたらきやすい環境の提供は、Well-beingを実現するための大切なポイントです。はたらき方の多様化で新しい価値観が求められている今、企業は一人ひとりの社員の立場を尊重することが求められています。
ダイバーシティについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介
人材不足の影響
少子高齢化で労働人口が減少し、人材不足で悩む企業が増えています。このような状況下でも、よりよい人材を確保するため企業ははたらきやすい環境づくりなど社員の幸福を考えることが大切です。社員のWell-beingを実現させることが、必要な人材の確保に役立つためです。
人手不足については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>人手不足の対策8選!自社でできる解決策と外部企業を活用する方法を解説
新型コロナウイルス感染症による影響
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、多くの企業がリモートワークを導入しました。はたらき方が多様化した一方で、社員間のコミュニケーション不足が課題となりました。
こういった職場や家庭での変化、感染症拡大に対する政府の対応、企業の経営戦略の変化など、将来の見通しが不透明で予測困難な状況により、社員がストレスを抱える事例が多発しています。メンタルヘルスの問題も指摘されるようになりました。このような状況で健康と幸福に対する意識が高まり、Well-beingの視点はより重要視されています。
Well-being(ウェルビーイング)が経営にもたらすメリット
Well-beingに類似する言葉として「健康経営」があります。健康経営とは企業が社員の健康を重視し、健康管理に取り組むことで業績と生産力の向上を期待する経営手法をいいます。
一方、Well-beingとは社員の健康状態や心理的な幸福感、モチベーションにまで焦点を当てた経営手法です。企業がWell-beingを実現すれば、健康経営も推進されるでしょう。ここからは、企業がWell-beingに取り組むことで得られる3つのメリットをご紹介します。
生産性の向上
Well-beingによって社員一人ひとりが幸せにはたらけるようになれば、企業の生産性向上につながります。実際にはたらく幸せを実感している人は、低い人と比べて個人のパフォーマンスが高い傾向が見られ、所属組織の生産性向上や売上に大きく貢献していることもわかっています。Well-beingを推進することは、企業の生産性向上につながると言えるでしょう。
生産性向上のための具体的な手段については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
離職率の低下
Well-beingの推進で職場の人間関係や労働環境が改善すれば、社員は幸せにはたらけるようになり、離職率の低下につながります。少子高齢化に伴い労働人口が減少している今、人材の流出を防ぐという意味でもWell-beingを重視することは企業にとって非常に重要です。
離職率の低下については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>社員を定着させるには?平均離職率や離職率がもたらす影響を解説
>>コールセンターの離職率が高いのはなぜ?原因と対策をご紹介
>>営業職の離職率が高い原因と低下させる対策を解説
>>エンジニアの離職率の現状とは?離職の原因と防ぐための対処法を解説
SDGsの推進
SDGsとは日本語訳では「持続可能な開発目標」と表され、経済発展のみに取り組むのではなく、環境や社会が抱える問題にも目を向け、その根本的な解決によって、世界を持続させるも目標のことを指します。
SDGsにおける17の目標の3つ目には「すべての人に健康と福祉を」が、8番目には「はたらきがいも経済成長も」があります。この2つの目標はWell-beingと密接に関連する目標と言えるでしょう。SDGs達成の一環であるWell-beingの推進は、社会的責任を果たすことと同義です。社員の健康と幸福度を高めることは、企業価値向上も期待できます。

- ※引用:国際連合広報ポスター|SDGsポスター(17のアイコン 日本語版)
Well-being(ウェルビーイング)経営の留意点
ここまではWell-beingがもたらすメリットなどについて解説してきました。しかし、実際にWell-being経営に取り組む際は以下の4つの留意点を意識しておくことも重要です。
長期的な目線が必要
Well-beingの効果はすぐに表れるものではありません。制度の導入や労働環境の整備だけで終わらせるのではなく、定期的なアンケート調査や健康診断を実施して効果の評価・分析を行ってください。継続してWell-beingに取り組むためには、長期的な効果を見据えた計画を立てる必要があります。
総合的なアプローチが必要
Well-beingは身体的な側面だけでなく、精神的、社会的すべてにおいて満たされていることが大切です。そのためには健康管理のみに注力するのではなく、職場文化やリーダーシップ、労働環境など組織全体の側面を考慮する必要があります。総合的に良好な状態の維持を目指し、取り組みを進めていく必要があるでしょう。
一定のコストがかかる
Well-beingを推進する際は、コストや手間がかかるものです。しかし、その取り組みによって労働環境などは改善され、社員のパフォーマンスや生産性が向上します。また、企業の大きな利益につながるでしょう。Well-being推進にかかるコストは必要な投資と考えることが大切です。
また、その際はコスト効果の高いプログラムや取り組みを選択することが重要です。予算を透明化し、適切に管理することを心掛けましょう。
社員の参加とフィードバックが重要
Well-beingを推進する際は、社員が参加しやすいプログラムを設計しましょう。社員にアンケートを取ったり、社内で評価し合ったり、施策に対するフィードバックを積極的に収集します。このようにして、社員のニーズに応える形で改善を行うことが重要です。
Well-being(ウェルビーイング)の事例
パーソルグループが実施しているWell-beingの事例を紹介します。
はたらくWell-beingについて
Well-beingを推進する際は、社員が参加しやすいプログラムを設計しましょう。社員にアンケートを取ったり、社内で評価し合ったり、施策に対するフィードバックを積極的に収集します。このようにして、社員のニーズに応える形で改善を行うことが重要です。
パーソルグループは、多様なはたらき方や学びの機会の提供を通じて一人ひとりの選択肢を広げ、はたらく自由を広げることで、個人と社会の幸せを広げることを目指しています。
「はたらくWell-being」について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
具体的に、パーソルグループは以下のような課題やお悩みに対応します。
- Well-beingのためにどのような取り組みが必要なのか悩ましい
- 社員のWell-beingの状態をどのように可視化すればよいか、わからない
- Well-beingにとって影響力の大きい、経営層・管理職層の理解を深め、メンバーへのはたらきかけを強化したい
これらの課題に効果的なサーベイや研修・ワークショップなど学びの機会の提供し、企業のさらなるWell-being向上のための課題設定、施策立案・実行、効果測定までを伴走します。
パーソルグループでは、東京都市大学と共同ではたらくWell-beingを体感できる対話型ゲーム「いいゆ」を開発しました。本ゲームを使い、自分と他者のはたらく幸せや不幸せを体感し、“はたらくWell-being”への理解を深め、職場での実践に結びつけることができます。
はたらくWell-beingを体感できる対話型ゲーム「いいゆ」について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
またパーソルグループでは社員の多様なはたらき方を推進するために、移動や宿泊にかかる費用を会社が負担する「ワーケーション制度」の運用を開始しました。多様なはたらき方の機会を提供し、「はたらくWell-being」を推進しています。
はたらくWell-being推進のための「ワーケーション制度」について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
スタッフウェルビーイングについて
パーソルグループでは、派遣スタッフ一人ひとりの価値観や将来ビジョンを尊重しています。特に重要視しているテーマは、“はたらく機会の創出”と“ファンづくり”の2つです。
“はたらく機会の創出”では派遣スタッフのさまざまなニーズに応えるために、多種多様な雇用の創出、仕事のご紹介と継続的な就業支援を併せた「フィッティング」という考え方の導入、人材開発の3点を重視しています。
“ファンづくり”では、就業時における心理的安全性を高めるためのサポートによって、パーソルに対する信頼・愛着を深めてもらい、より多くの人に「パーソルだからはたらき続けたい」と感じてもらうことを目指します。
この2つのテーマに沿った取り組みとして、パーソルグループでは「“仕事探し”へのサポート」に注力しています。具体的には、案件紹介前のカウンセリング面談やさまざまなテクノロジーを活用しながら、スキルや就業内容だけでなく、それぞれの派遣スタッフの価値観も踏まえた上で一人ひとりに合う案件を紹介します。
加えて、「“成長とキャリア構築”へのサポート」も重視しています。派遣スタッフが希望するキャリアを実現するために、必要とされる知識向上やスキルアップをサポートする人材開発投資を積極的に行い、教育施策の実施やスキルの見える化に取り組みます。
さらに「安心して安定的にはたらくためのサポート」についても留意しています。個々のワーク・ライフ・バランスに合わせてはたらけるよう、就業時間・就業場所の観点でさまざまな選択肢を提供し、より多くの派遣スタッフの希望に沿った就業の実現を目指します。また、安定して継続的にはたらけるよう、派遣スタッフが心身共に健康でいられるためのサポートを提供します。
パーソルグループは、家庭との両立を実現するワーク・ライフ・バランスや、未経験の領域にチャレンジできるキャリアアップといった価値観を尊重しています。そして、自分らしくはたらくために就業に関してさまざまな選択をできることが、Well-being向上につながると考えています。
「スタッフウェルビーイング」について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
Well-being(ウェルビーイング)経営のメリットや構成要素を理解する
Well-being経営は、社員の心身の健康だけでなく、社会的な充実度や満足度が良好な状態を追求する経営手法です。
企業がWell-beingを構成する「PERMA理論」に積極的に取り組み、Well-beingの向上を推し進めると社員のモチベーションアップなどにつながります。ひいては、生産性アップや離職率の低下などのメリットも生まれるでしょう。Well-being推進は企業の発展に大きな影響を与えます。社員はもちろん、組織全体にとってもメリットの多いWell-being経営の実践を検討してみてはいかがでしょうか。
パーソルテンプスタッフはHRに関するセミナー「HRナレッジセミナー」を開催しています。Well-beingについてより詳しく知りたい方は、こちらのアーカイブ動画をご参照ください。
>>HRナレッジラインセミナー|ウェルビーイング経営の実現と従業員体験(EX)
>>HRナレッジラインセミナー|ウェルビーイング(幸せ)な組織の作り方ー大規模調査から読み解く「幸せ」のヒントー
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする