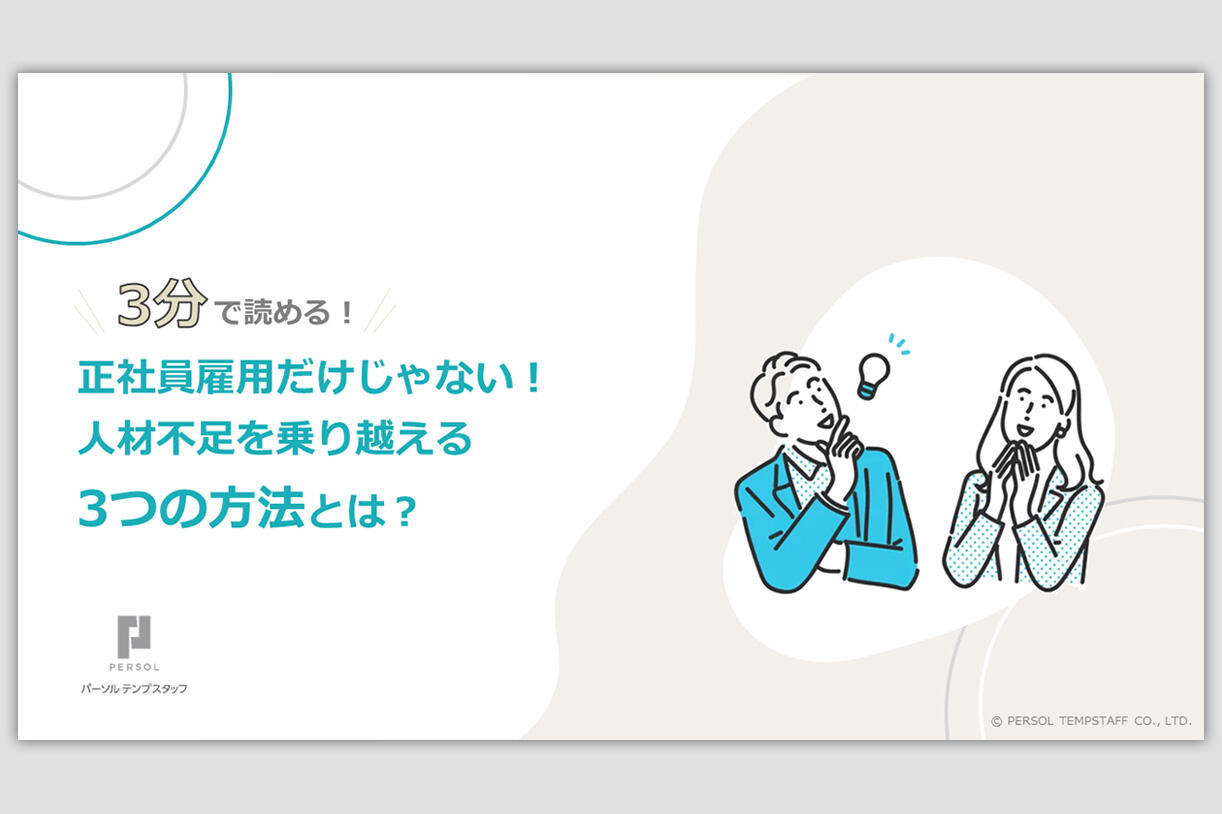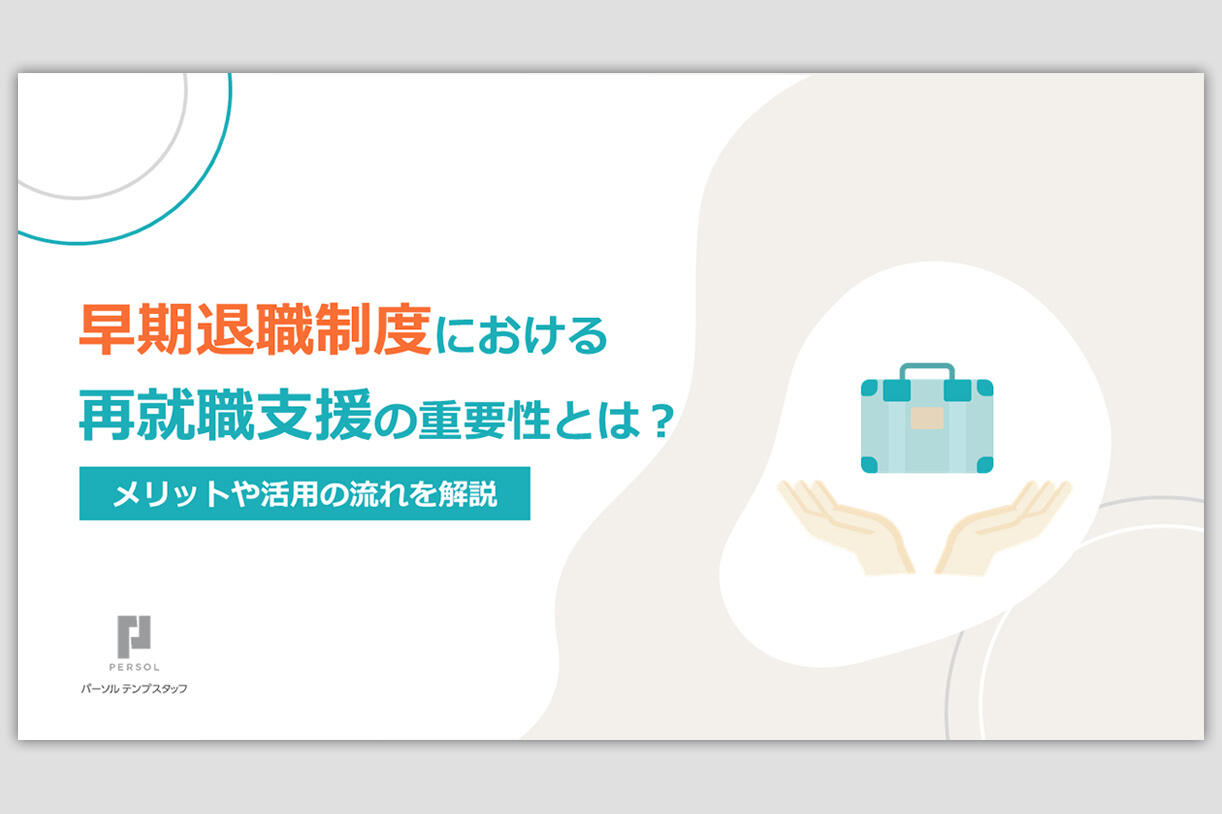HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【企業向け】定年後再雇用とは?メリットや課題、ポイントについて徹底解説
公開日:2025.10.14
- 記事をシェアする

定年後再雇用制度とは、定年を迎えた従業員を引き続き雇用するための制度です。
本記事では、高年齢者就業確保措置の概要や再雇用制度と勤務延長制度の違い、実際に再雇用を実施する際のポイントなどを整理し、メリットや課題を詳しく解説します。
定年後再雇用制度の導入を検討している企業担当者にとって、具体的な流れや注意点を理解する一助となれば幸いです。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
定年後再雇用制度とは?
定年後再雇用制度とは、60歳または65歳を定年とする企業において、退職者が希望する場合に再度雇用を継続できる制度です。
高齢者雇用安定法の施行に伴い、多くの企業は定年の引き上げや勤務延長、再雇用などいずれかの施策での対応が求められています。
一度退職の手続きを経た上で、新たな雇用条件を設定する点が特徴で、給与や業務内容を見直して再スタートを切るケースも多く見られます。
定年後再雇用制度の仕組み
定年後再雇用制度は、2013年に定められた「高齢者雇用確保措置」のうちの一つです。
定年を迎えた従業員が一度退職という形を取り、新たな雇用契約を締結するのが基本的な流れとなり、賃金や勤務時間などの条件は、企業や従業員の事情を踏まえて再設定されます。
適用対象は希望者全員とするのが原則であり、企業は再雇用希望者に対して具体的な雇用条件を提示する義務があります。
必要性と社会的背景
少子高齢化による労働力不足や公的年金への財政的負担増などが背景となり、高齢者が長く就労する機会を確保することが社会的課題となっています。
さらに、2021年の法改正によって70歳までの就業機会確保が努力義務化され、高齢者の就労を支援する姿勢が一段と国全体で強化される流れとなっています。
時代に即した柔軟なはたらき方を整備することが求められ、結果的に企業の競争力維持にもつながっています。
企業における導入状況
大企業だけでなく、中小企業でも定年後再雇用制度の導入事例が増えています。
多くの企業は人材不足を深刻に捉えており、再雇用を通じて熟練人材を維持することで生産性を高める効果を期待しています。
一方で、賃金体系やポジション調整などの課題も多く、導入時には就業規則や評価制度を再設計するケースが少なくありません。企業規模や業界特性に合わせたカスタマイズが成功の鍵となります。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
高齢者雇用確保措置の概要
高齢者の継続雇用を義務付けるための法的措置について、その概要を説明します。
高年齢者就業確保措置は、企業が定年を60歳以上に設定し、65歳までの雇用を確保するよう義務化した仕組みです。
近年はさらに70歳までの就業機会確保に関する施策が強化され、定年引き上げや勤務延長、業務委託など多様なはたらき方を実現する方向へと進んでいます。
企業側には雇用を確保するための具体的な取り組みを行う責任があります。十分な社会保険や年金との連携を踏まえ、適切な就業形態を整備することが重要です。
65歳までの雇用措置確保義務
現在、高齢者雇用確保措置の適用範囲は「65歳までの雇用確保」です。
2025年4月から、高年齢者雇用安定法の改正により、定年後再雇用制度に重要な変更が加わりました。
まず現在の経過措置が終了し、すべての企業において65歳までの雇用確保措置が完全義務化されました。
具体的な実施方法として、定年の引き上げ、定年制の廃止、継続雇用制度の導入が認められ、企業の状況に応じて柔軟に選択できます。
とはいえ、労働条件や評価制度を整備しなければ不満やトラブルの原因になるため、就業規則の改定や説明会の開催など慎重な対応が必要です。
また、この法改正では、高年齢者の雇用確保に関する書面での通知が義務付けられます。
企業は、従業員が60歳に達する前に、65歳までの雇用確保措置の内容を書面で通知する必要があります。
※参考:厚生労働省 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針
高齢者雇用安定法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
>>高年齢者雇用安定法とは?概要や改正内容について分かりやすく解説
70歳までの就業機会確保
上記の改正に先駆け、2021年4月に施行された改正法によって「高年齢者就業確保措置」が追加され、70歳までの就業機会確保は努力義務として位置づけられました。
高年齢者就業確保措置では、次の5つのうち1つを講じることとされています。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)の導入
- 70歳まで継続的に従業員と業務委託契約を結ぶ制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- 事業主が実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、資金提供する団体が実施する社会貢献事業
再雇用制度と勤務延長制度の違い
定年後の雇用形態には、再雇用制度と勤務延長制度の2種類が存在します。以下でそれぞれの違いを解説します。
再雇用制度は、定年退職を迎えた社員の雇用形態や勤務条件などを見直し、再度雇用する制度です。
これに対し、勤務延長制度は定年延長とも呼ばれており、定年前の役職や待遇、雇用形態を維持して勤務を継続する制度です。
つまり、一度退職し新たに雇用されるのが再雇用制度、定年後も役職と条件が継続して雇用が継続されるのが勤務延長制度です。
勤務延長制度はスムーズな継続に利点がある一方で、人事制度上の調整が難しい場合もあり、企業の状況や社員の希望によって適切な制度を選ぶことが重要です。
| 再雇用制度 | 勤務延長制度 | |
|---|---|---|
| 概要 | 定年退職を迎えた社員を、一度退職後に雇用形態や勤務条件を見直して再度雇用する制度。 | 定年前の役職や待遇、雇用形態を維持したまま、定年後も勤務を継続する制度。 |
| 雇用形態 | 新たな雇用契約を結ぶ。 | 定年前の雇用契約をそのまま継続する。 |
| 退職手続き | 一度退職手続きを行う。 | 退職手続きは不要。 |
| メリット | 雇用形態や条件を柔軟に設定できる。 | スムーズに勤務を継続できる。 |
| デメリット |
| 人事制度上の調整が難しい場合がある。 |
| 適用のポイント | 企業の状況や社員の希望に応じて、柔軟に条件を設定する。 | 企業の状況や社員の希望に応じて、調整を行う必要がある。 |
定年後再雇用時に考えるポイント
定年後再雇用を実施する際に確認しておきたい、雇用形態や待遇、社会保険の扱いなどを解説します。
定年後のはたらき方を選択するうえで重要なのが、再雇用時の労働条件や契約期間の取り決めです。企業は従業員の意向を尊重しながら、業務内容や待遇を適切に再設定し、就業規則や労使協定と整合を取る必要があります。
また、社会保険や年金制度といった公的な枠組みとの重なりを考慮し、従業員が不利にならないように設計することも大切です。最終的には、企業・従業員双方にとって安心して長くはたらける環境の整備が求められます。
雇用形態と雇用期間
定年後再雇用の多くは、有期契約で一定期間ごとに更新される形が一般的です。
契約更新時には、業務成果や健康状態を考慮しながら、雇用期間を延長するかどうかを判断します。
なお、再雇用制度での雇用期間は、就業規則に明記しなければなりません。再雇用制度での雇用形態は特に定められておらず、必要に応じて、パートタイムや嘱託など柔軟な雇用形態を導入する企業も増えています。
待遇(給与・賞与・各種手当)
定年前との大きな違いとして、再雇用後の給与水準や手当の扱いが挙げられます。
企業は、従業員のモチベーションを維持するために報酬設計を工夫する必要がありますが、業績や個人の貢献度によっては現役時代より下がるケースも少なくありません。
昇給や賞与の支給基準などを明確化し、納得感のある仕組みを構築することが大切です。
有給休暇
再雇用に伴って新たに雇用契約を結ぶ場合でも、以前の勤続期間を考慮して有給休暇が付与されるケースが多いです。
企業側は労働基準法や就業規則の規定を踏まえ、どのように有給休暇を計算するかを明示しておくことが求められます。
従業員目線では休暇取得のしやすさも重要であり、再雇用後の負担を軽減し、長期的にはたらきやすい環境を整備する効果があります。
社会保険・年金との関係
再雇用後も一定の所定労働時間や賃金要件を満たしていれば、厚生年金や健康保険の加入対象となります。
在職老齢年金の仕組みや収入上限などとの兼ね合いが複雑なため、従業員・企業双方が正確な情報を共有し、手続きを求めることが重要です。
特に60歳以降は公的年金の受給開始時期や金額が変わることも多く、注意が必要です。
再雇用制度のメリット
企業が定年後再雇用制度を導入することは、業務効率や人材の安定化につながるメリットがあります。
豊富な経験を活かし、新人教育や組織全体の底上げに貢献するシニア人材は、企業にとって貴重な財産となるでしょう。ここでは代表的なメリットを5つ取り上げます。
1.安定した人材確保
シニア人材は長年培ってきた専門知識やノウハウを持っており、即戦力として活躍が見込めます。
少子化による労働力不足が深刻化するなか、再雇用によってその空白を補うことができます。また企業文化や価値観を分かっているため定着率が高くなる傾向があります。
2.経験や知識の活用
長く職場を経験してきた従業員ほど、会社の文化や業務プロセスを深く理解しています。
蓄積されたノウハウを若手に伝授することで、組織全体のスキル向上が期待できます。特に専門性の高い業種では、熟練者の知識を継承する仕組みづくりが事業継続の鍵となります。
3.採用や教育に対するコスト削減
新規採用や育成には莫大なコストと時間がかかりますが、再雇用者は基本的な業務知識を既に持っています。
研修やOJTの手間を最小限に抑えられる点は企業にとって大きなメリットです。
4.企業の社会的責任(CSR)への貢献
高齢者の雇用を進めることは、企業の社会的貢献度を高めることにもつながります。
少子高齢化や年金財政の問題など、社会全体の課題に企業が積極的に取り組む姿勢として評価されるでしょう。適切な高齢者雇用を推進する企業は、ステークホルダーからの信頼も得やすくなります。
5.柔軟なはたらき方の提供
フルタイムだけでなく、パートタイムや時短勤務など多様なはたらき方を用意することによって、企業のイメージアップにもつながり、若い世代にとってもはたらきやすい職場環境づくりの一環となります。
またシニア層の生活や健康状況にも配慮することができます。はたらき方の選択肢を増やすことで、定着率の向上や離職率の低減も見込めるでしょう。
想定される課題と対策
定年後再雇用制度には多くのメリットがある一方で、従業員を再雇用するにあたっては、給与水準の設定や職場での役割分担など多くの課題が生じる可能性があります。
企業と従業員が健全に協力関係を築き、長くはたらく環境を作るためにどのような対策を取るべきかを考えることが重要です。法令遵守やコンプライアンス面も含め、適切な手続きと運用が求められます。
従業員の受け入れ体制
再雇用者を組織の中でどのようなポジションにつけるのかは、重要な検討事項です。
管理職や専門職としての継続か、通常のスタッフとしての運用かで仕事内容や人事評価も変わります。受け入れ部署や業務範囲を明確にし、新旧従業員のコミュニケーションを円滑にすることが求められます。
若手社員に対しては、定年後再雇用制度の目的やメリットを明確にし、社内説明会や研修を通じて理解を深めることが重要です。また、他社の成功事例や社内での成功体験を共有することで、ポジティブなイメージを醸成することも有効です。
給与や待遇の調整
定年後の給与や手当は現役時代と大幅に変わるケースが多く、モチベーションの維持や公平性の確保が課題となります。
企業は等級制度や評価基準を見直し、合理的な説明ができる給与体系を構築することが大切です。業績に応じてインセンティブ制度の導入を検討することで再雇用者のモチベーションを維持することも有効です。
業務内容の見直し
高齢の従業員に重労働や長時間労働を課すのは現実的ではなく、健康面への配慮が必要です。体力的負担を減らせるよう業務内容や勤務日数の見直しを行い、無理のないはたらき方を提案します。
適材適所を実現するためにも、再雇用者の得意分野やスキルを把握して配置することが重要です。
法的問題やコンプライアンス
高齢者雇用安定法や労働基準法といった法令の遵守はもちろん、個々の雇用契約や就業規則との整合も求められます。
違反リスクを避けるために、社内規定の整備や定期的な監査などコンプライアンス体制を強化することが重要です。
特に継続雇用を拒否する場合は、適切な手続きを踏む必要があります。
定年後再雇用制度を実施する流れ
実際に再雇用制度を導入するために必要なプロセスをステップごとに解説します。
各ステップで従業員とのコミュニケーションや法令準拠を意識しながら、就業規則の改定や労使協定の締結、個別契約などを進めなければなりません。
以下のステップを踏むことで、スムーズな再雇用制度の運用が期待できます。
ステップ1:再雇用制度の制度設計
まずは現行の定年制度や就業規則を見直し、定年後再雇用を行うための具体的な条件を設定することから始めます。
企業内で定年後再雇用制度の趣旨と目的を明確にし、対象範囲や雇用条件を話し合います。法的要件や経営方針を踏まえ、賃金水準や職務範囲などを検討しながら就業規則と整合させます。
経理や人事担当者だけでなく、現場の管理職や従業員からも意見を聞き、実務上の問題点やリスクを洗い出す段階が重要です。また労働基準監督署への届け出も必要です。
ステップ2:対象社員への説明
制度化が進んだら、定年前の従業員に対して説明会や個別面談を行います。
再雇用時の雇用条件や具体的な手続きスケジュールを説明し、疑問点や不安を解消するのが狙いです。十分な情報提供が難しいと制度への理解が進まず、後のトラブルにつながる可能性があります。
ステップ3:再雇用条件の調整・決定
当事者となる従業員の希望や健康状態、これまでの実績などを考慮しながら、最終的な待遇や勤務形態を決めます。
例えば週数日のパート勤務を望む場合や、正社員としてフルタイム継続を希望する場合など、個別のケースに応じて柔軟に検討します。企業としても経営方針と照らし合わせ、適切な補償や評価制度を落とし込む必要があります。
ステップ4:再雇用契約の締結
合意に至った雇用条件をもとに、正式な雇用契約を交わします。契約書には給与や業務範囲、契約期間などが明示され、どちらの立場にとっても曖昧な点がないようにすることが大切です。
締結後は社内システムへの登録や社会保険手続き、関係部門との連絡など、円滑なスタートを切るための準備が求められます。
定年後再雇用制度の注意点
定年後再雇用制度には、企業文化や人事制度との調整、当事者の納得感を得るための工夫など、さまざまな留意事項があります。
契約更新のルールが曖昧なままだと後のトラブルにつながりやすく、健康問題などで再度の雇止めを検討する場合にも慎重な対応が必要です。
以下のポイントをしっかりと押さえることで、スムーズな運用と良好な労使関係の維持が期待できます。
就業規則と労使協定の整備
再雇用制度を導入する場合、定年後の雇用条件をどのように取り扱うかを就業規則や労使協定で明文化する必要があります。
企業の実情と法令を両立させるためにも、専門家の意見を取り入れて整備を進める企業が増えています。
契約更新とトラブル回避
数年にわたり再雇用を継続する場合、契約更新の手続きや評価基準を明確にしておくことが重要です。
従業員能力や健康状態の変化を踏まえ、客観的な評価やエビデンスをもとに更新を判断することで、不満や紛争を防ぎやすくなります。
評価制度を導入する場合は、公平性と透明性を保つ仕組みづくりが不可欠です。
再雇用拒否が成立する場合
企業が希望者を再雇用しない正当な理由としては、勤務態度の重大な問題や健康上の大きな支障が挙げられます。
雇用契約を更新しない(雇止め)場合でも、事前通知や説明責任があります。労使トラブルに発展しやすい領域ですので、企業側は必ず適法かつ納得できるプロセスを踏むように注意を払わなければなりません。
契約内容の変更
再雇用期間中に、従業員の希望や企業状況の変化などで契約内容を変更する必要が出てくる場合があります。
給与や勤務時間の見直しを行う際は、双方の合意のもとで変更契約を結び、書面で明確に示すことが大切です。曖昧なままで進めると、後に手続き上の問題や給与計算でのトラブルが発生するリスクが高まります。
賃金や待遇の見直し
再雇用後の賃金水準は、一度設定すると長期的に継続する場合が多いため、定期的な評価見直しが重要になります。
職務や役割の変化に伴って公正に報酬を決定しなければ、モチベーションや人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。従業員と経営側の間で適切なコミュニケーションを図り、評価方法や報酬ルールを明確化しておくことが大切です。
高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法は、企業に65歳までの雇用機会確保を義務付ける法律であり、70歳までの就業機会確保は努力義務として位置付けられています。
適切な対応を怠ると行政指導の対象になる場合もあるため、定期的に法改正情報をチェックすることが重要です。従業員とのトラブルを回避し、安定した雇用環境を作るためにも、企業はこの法を常に意識しながら運用を行う必要があります。
社会保険や税金の取り扱い
年金受給中の再雇用では、在職老齢年金の調整や厚生年金・健康保険への加入義務などが複雑に絡み合います。契約時に従業員へ正確な情報を提供し、加入や保険料負担について十分に説明することが求められます。給与や年金額が変動することで税金の計算にも影響が出るため、経理担当者との連携を密にして手続きを進めることが大切です。
再雇用時に活用できる助成金・給付金
定年後再雇用を促進するために利用できる公的支援制度もあります(例:高年齢雇用継続基本給付金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者処遇改善促進助成金 など)。
高齢者の継続雇用を支援する助成金や給付金は、企業と従業員双方にメリットをもたらす貴重な資源です。支給要件や申請手続きには多くの条件があり、制度に精通していなければ活用しにくい点もあります。
しっかりと情報収集し、自社の状況に合った制度を活用することで、人件費負担を抑えながらシニア人材を積極的に活用できるでしょう。
※参考:
事業主の行う事務手続き_2校.indd
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省
高年齢労働者処遇改善促進助成金|厚生労働省
定年後再雇用制度についてよくある質問
ここでは、定年後再雇用制度についてよくある質問をまとめました。
Q1.定年後再雇用制度は法律で義務付けられていますか?
高年齢者雇用安定法により、企業は65歳までの雇用確保措置を講じる義務があります。ただし、具体的に「再雇用制度」を導入するかどうかは、企業の裁量に委ねられています。制度の有無や内容は各企業によって異なります。
Q2.再雇用時の契約形態は?
再雇用時の契約形態は、企業や従業員の希望によりさまざまですが、契約社員やパートタイムなど、有期契約で一定期間ごとに更新される形が一般的です。
契約期間や待遇、勤務時間などは、就業規則や労働契約書で明示し、公平に運用されることが重要です。
Q3.定年後再雇用制度で契約時に注意することは?
再雇用制度を導入する際には、労働条件や制度の内容を明確にし、公平かつ適正に運用することが重要です。
また、契約の更新については、更新の条件や手続き、可否をあらかじめ合意し、書面にすることが望ましいです。本人の希望や意思も尊重し、再雇用を希望するかどうかやはたらき方についても確認しておくことがポイントです。
Q4.定年後再雇用までの流れは?
定年再雇用の決定までの流れは、主に以下の通りです。
- 制度設計
- 対象者への通達・継続雇用への意思確認
- 対象者との面談・雇用条件提示
- 再雇用の決定・諸手続
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
適切に定年後再雇用制度を導入しましょう
定年後再雇用制度は、高齢者雇用を取り巻く法制度や企業の実態に即した重要な選択肢です。適切に制度を設計・運用することで、企業と従業員の双方に大きなメリットをもたらすでしょう。
定年後再雇用は、人材不足の時代において企業にとっても従業員にとっても価値がある手段と言えます。
高齢者雇用安定法や社会保険制度など複雑なルールを理解しながら、給与やはたらき方を柔軟に設計することが成功の鍵です。
法令を順守しつつ、個々のニーズにきめ細かく対応することで、定年退職者と企業の双方が安心して新たなステージを築けるようになるでしょう。
人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする