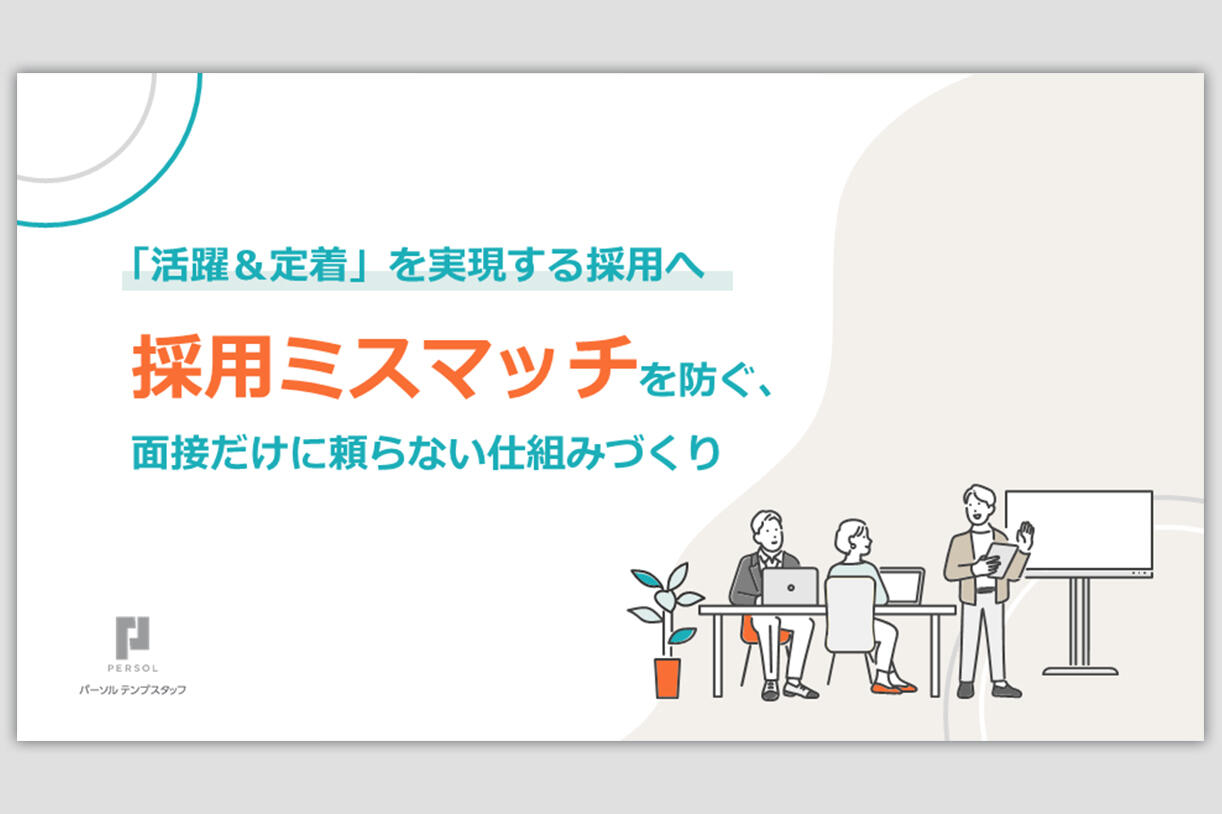HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【人事必見】内定辞退の防止策!企業が取り組むべき施策を解説
公開日:2025.09.30
- 記事をシェアする

内定辞退とは、採用活動において企業から内定を出したにもかかわらず、内定者が最終的に入社を辞退してしまうことを指します。
内定辞退は、企業の人事部門の担当者や経営者にとって深刻な課題です。特に、時間とコストをかけて選考した優秀な人材に内定を辞退されてしまうことは、採用計画に大きな影響を与えかねません。
そこで本記事では、新卒採用と中途採用それぞれの内定辞退の現状と背景にある理由を詳しく解説するとともに、企業が内定辞退を防止するために取り組むべき具体的な対策をまとめました。
さらに、万が一内定辞退が発生してしまった場合の対処法についてもご紹介します。内定者の獲得と定着にお役立ていただくために、ぜひ最後までお読みください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
内定辞退の現状
パーソル総合研究所が実施した調査によると、2024年4月に入社予定で、複数の企業から内々定を得て就職活動を終えた大学生・大学院生のうち「内々定を辞退した件数」は「平均3.4社」でした。
この結果から、学生は複数の企業から内定を得た上で、最終的な入社先を選択する傾向があると伺えます。
上記データは、新卒採用における内定辞退が企業にとって重要な問題であることを示唆しており、特に優秀な人材の獲得競争においては、より一層の内定辞退対策が求められるでしょう。
また、マイナビが2024年に実施した調査によると、中途採用の内定者の内定辞退率は「9.0%」というデータもあります。企業の採用担当者にとっては、内定を出しても辞退されるケースが一定数想定され、採用の時間・コストが大きくなることを踏まえると、内定辞退率を低く抑えることが課題だと考えられます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
内定辞退が起きる背景
採用活動において、企業が内定を出したにもかかわらず、内定者が最終的に入社を辞退してしまうことは、企業にとって大きな痛手となります。ここでは、内定辞退が起きる背景について解説します。
求人内容や条件面でのギャップ
会社説明会や面接で聞いていた情報と、内定後に提示された労働条件や待遇に差異を感じた場合、内定者は辞退を検討する可能性があります。
例えば、転勤に関する条件や、休暇制度やはたらき方、リモートワークの可否など、事前にアピールされていた内容と実態が異なると感じる場合が挙げられます。
企業は、候補者の本音を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。採用のミスマッチを防ぐためにも、条件や制度、業務内容を正確かつ詳細に伝える必要があります。
なお、労働条件の明示義務については以下の記事で解説しています。あわせてお読みください。
>>労働条件明示とは?労働契約締結・更新時に担当者が知っておくべきポイントを解説
企業環境への不安
面接官の態度や企業の雰囲気から、自身に合った環境ではたらけるかどうかに不安を感じることがあります。
また、企業の安定性や将来性への懸念が、内定辞退の要因となることもあります。
他社からの内定獲得
選考を受けていた他の企業があり、より自身の考えに合致する条件や企業文化を持つ企業から内定を得た場合、内定者は先に得ていた内定を辞退する可能性も考えられます。
内定辞退の防止策
内定辞退は、採用活動における大きな課題です。特に、多くの時間とコストをかけて選考した優秀な人材の内定辞退は、企業にとって大きな損失となります。
ここでは、内定辞退を防ぐために企業が取り組むべき具体的な施策を、新卒採用と中途採用に分けてご紹介します。
新卒採用における内定辞退防止策
新卒採用の場合に想定される内定辞退防止策を紹介します。
内定者との継続的なコミュニケーション
内定を出した後も定期的に連絡を取り、内定者のエンゲージメントを維持しましょう。
例えば、内定者懇親会や内定者向けのイベントなどを開催し、同期入社予定者との交流を促すことで、入社への期待感を高めることができます。
特に、若手社員との座談会や職場見学の機会を設けると、入社後のイメージを具体的に持ってもらうことにつながります。
不安の解消と疑問への対応
入社までの準備や配属、キャリアパスなど、内定者が抱える可能性のある不安や疑問に対して積極的に情報提供を行い、個別相談の機会を設けましょう。
メンター制度を導入し、内定者一人ひとりに先輩社員を付け、安心して入社を迎えられるようにサポートすることも有効です。
入社意欲の向上
企業の理念やビジョン、事業の将来性などを改めて伝え、入社することの意義や期待感を持ってもらいましょう。
内定者のスキルや強みを認め、入社後の具体的な仕事内容や活躍できるフィールドを示すことで、モチベーションを高められます。
企業理解の促進
社内報やブログなどを通じて、企業の最新情報や社員の活躍を紹介し、企業文化への理解を深めてもらいましょう。
また、入社前にeラーニングなどの研修機会を提供することで、スムーズな入社準備をサポートするとともに、企業への帰属意識を高められます。
中途採用における内定辞退防止策
中途採用においては、即戦力となる人材であるため、個々のニーズやキャリアプランに合わせた対応が重要になります。
求職者への迅速なレスポンス
中途採用の求職者の場合、複数の企業を対象に転職活動を行っている場合が多いです。そのため、企業からの迅速なレスポンスによって「対応に誠意を感じられる」「意思決定が早い」などの好印象を持ってもらえるでしょう。
一方で、企業側の意思決定のスピードや内定通知が遅いと自社の印象や信頼度が低下し、候補者が他企業を選んでしまう可能性が高まります。
企業の担当者は試験や面接に関する連絡をはじめ、内定通知、その後の連絡をできる限り迅速に対応することが重要です。
条件面の再確認と交渉
内定を出す前に、給与や待遇などの条件面について、候補者の希望を十分にヒアリングし、可能な範囲で調整を行いましょう。内定後にも、改めて条件面について確認し、認識の齟齬がないように努めます。
企業文化やはたらく環境の理解促進
面接時だけでなく、内定後にも職場の雰囲気やチーム構成、一緒にはたらく社員などを具体的に伝え、入社後のイメージを持ってもらいましょう。職場見学や社員との顔合わせの機会を設けることも有効です。
キャリアパスと成長機会の提示
入社後のキャリアパスや成長機会について具体的に説明し、自身のキャリアプランと合致しているかどうかを確認してもらいましょう。研修制度や資格取得支援制度など、スキルアップをサポートする制度をアピールすることも重要です。
競合企業の動向を把握
中途採用の候補者が複数の企業に応募している可能性も想定し、競合企業の選考状況や条件などを把握し、自社の魅力を効果的に伝えられるようにしましょう。
これらの対策を講じることで、内定辞退を減らし、優秀な人材の確保につなげることが期待できます。内定者は、入社を決めるにあたってさまざまな不安や期待を抱えています。企業として真摯に向き合い、丁寧なコミュニケーションを心がけることが、内定辞退防止の第一歩といえるでしょう。
なお、採用通知後は企業と内定者との間で「入社誓約書」や「入社承諾書」といった文書を作成して取り交わす必要があります。採用決定者の入社にあたり遵守すべき事項について理解を促し、その遵守について誓約していただくための書面です。パーソルテンプスタッフではテンプレートをご用意していますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
入社後に従業員が守るべき規則や条件を定めた書類で、入社後の義務を明確にするものです。
>>入社誓約書 テンプレート
内定者が企業に入社することを承諾する意思表示の書類です。
>>入社承諾書 テンプレート
内定辞退が発生した場合の対処法
内定辞退防止策を講じても、予期せず内定辞退が発生してしまうことがあります。そのような状況でも、企業は迅速に人材を確保するための対策を講じる必要があります。
速やかな状況把握と原因分析
まずは、内定辞退の連絡を受けたら、速やかに状況を把握し、可能な範囲で辞退理由を確認しましょう。今回の内定辞退が、自社の採用活動のどの段階に原因があったのかを分析することで、今後の対策につなげられます。
候補者への再アプローチ
辞退理由によっては、条件面や待遇面などで再交渉の余地があるかもしれません。すぐに諦めずに、誠意をもって再アプローチを試みると有効な場合があります。
繰り上げ内定の検討
今回の採用枠に、最終選考まで進んだ優秀な候補者が他にいる場合は、その候補者への繰り上げ内定も検討しましょう。選考時の評価を再度確認し、自社のニーズに合致するかどうかを見極めることが大事です。
採用活動の再開
繰り上げ内定が難しい場合には、速やかに採用活動を再開する必要があります。これまでの選考活動で得られた情報(応募者のデータや選考の感触など)を分析し、次回の採用活動をより効果的に進めるための改善点を見つけましょう。
人材派遣会社の活用
急な人材確保が必要な場合は、人材派遣の活用を検討するとよいでしょう。人材派遣会社には、専門スキル・経験を持った派遣社員が登録しているため、即戦力として期待できます。
人材派遣の仕組みについては以下の記事で解説しています。あわせてお読みください。
>>人材派遣とは?仕組みや料金、活用時の留意点を解説
なお、中長期的な視点で人材確保を考えている場合には、紹介予定派遣というサービスが有効です。紹介予定派遣とは、一定期間(最長6ヶ月)派遣社員として就業した後、企業と派遣社員双方の合意があれば、正社員や契約社員として直接雇用に切り替わる制度です。
紹介予定派遣の仕組みやメリットについては以下の記事で解説しています。あわせてお読みください。
>>紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説
紹介予定派遣のメリットは、派遣期間中に、派遣社員のスキルや適性、企業文化との適合性などをじっくりと見極めることができます。直接雇用前に相互理解を深めることができるため、採用ミスマッチのリスク低減が可能です。また、通常の採用活動よりも比較的早く人材を確保できる可能性があります。
新卒者の内定辞退に関して課題を感じている場合は、高い成長意欲を持つ若年層の無期雇用派遣社員をご紹介可能なサービス「funtable」についてもご一読ください。
>>育成型無期雇用派遣のfuntable(ファンタブル)|パーソルテンプスタッフ
若手採用を成功させるポイントについては、以下の記事でも解説しています。あわせてお読みください。
>>若手採用を成功させるポイントとは?組織にあらたな人材を取り入れる
内定辞退に関してよくある質問
内定辞退に関して採用担当者が抱きがちな疑問と回答をまとめました。
Q1.内定辞退を防止するためのポイントは?
内定辞退を防止するためには、内定者との丁寧なコミュニケーションが非常に重要です。内定後も定期的に連絡を取り、不安を解消し、企業への理解を深めてもらうように努めましょう。
具体的には、懇親会や職場見学の機会を設けたり、メンター制度を導入したりすることが効果的です。また、企業の魅力や入社後のキャリアパスを明確に伝え、入社意欲を高めることも大切です。
Q2.内定辞退防止のために実施するとよい具体的なイベントはありますか?
内定辞退を防ぐための具体的なイベントとして、例えば以下が考えられます。
- 内定式:入社の意思を改めて確認し、会社への期待感を高めるフォーマルなイベント。
- 内定者懇親会:内定者同士や先輩社員と交流できる場を設け、入社後の人間関係をスムーズにする助けとなる。遠方に住む内定者も気軽に参加できるオンラインでの交流会も効果的。
- 内定者向け研修:会社の事業内容や文化、入社後のはたらき方などを学ぶ機会を提供し、不安を解消する。
- 職場見学会:実際にはたらくオフィスを見学することで、内定者が入社後のイメージを具体的にできる。
イベントを通じて、内定者の会社へのエンゲージメントを高めることが重要です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
内定者との丁寧なコミュニケーションが重要
本記事では、企業の人事担当者や経営者の方々に向けて、採用活動における内定辞退の現状、その背景にある理由、そして内定辞退を防止するために企業が取り組むべき対策について解説しました。
内定辞退は、新卒採用・中途採用のいずれにおいても起こりうるものであり、企業にとって人材確保の大きな課題となります。内定辞退を未然に防ぐためには、候補者との丁寧なコミュニケーションを図り、企業の魅力を効果的に伝え、不安を解消することが重要です。
しかしながら、万が一内定辞退が発生してしまった場合は、迅速かつ適切な対応が求められます。繰り上げ内定の検討や採用活動の再開と並行して、人材派遣会社の活用も有効な選択肢となるでしょう。
特に、紹介予定派遣は、一定期間派遣社員として就業した後、企業と派遣社員による双方の合意のもと直接雇用に切り替わるシステムです。企業は採用前に候補者の適性や能力を見極めることができ、ミスマッチを防ぎながら、急な人材ニーズにも柔軟に対応することが可能です。
内定辞退は、企業にとって損失であると同時に、採用活動を見直すよい機会でもあります。本記事が採用活動の一助となれば幸いです。
▼紹介予定派遣サービス

ミスマッチを防ぎ、自社に合った人材を採用
紹介予定派遣ならパーソルテンプスタッフ
人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする