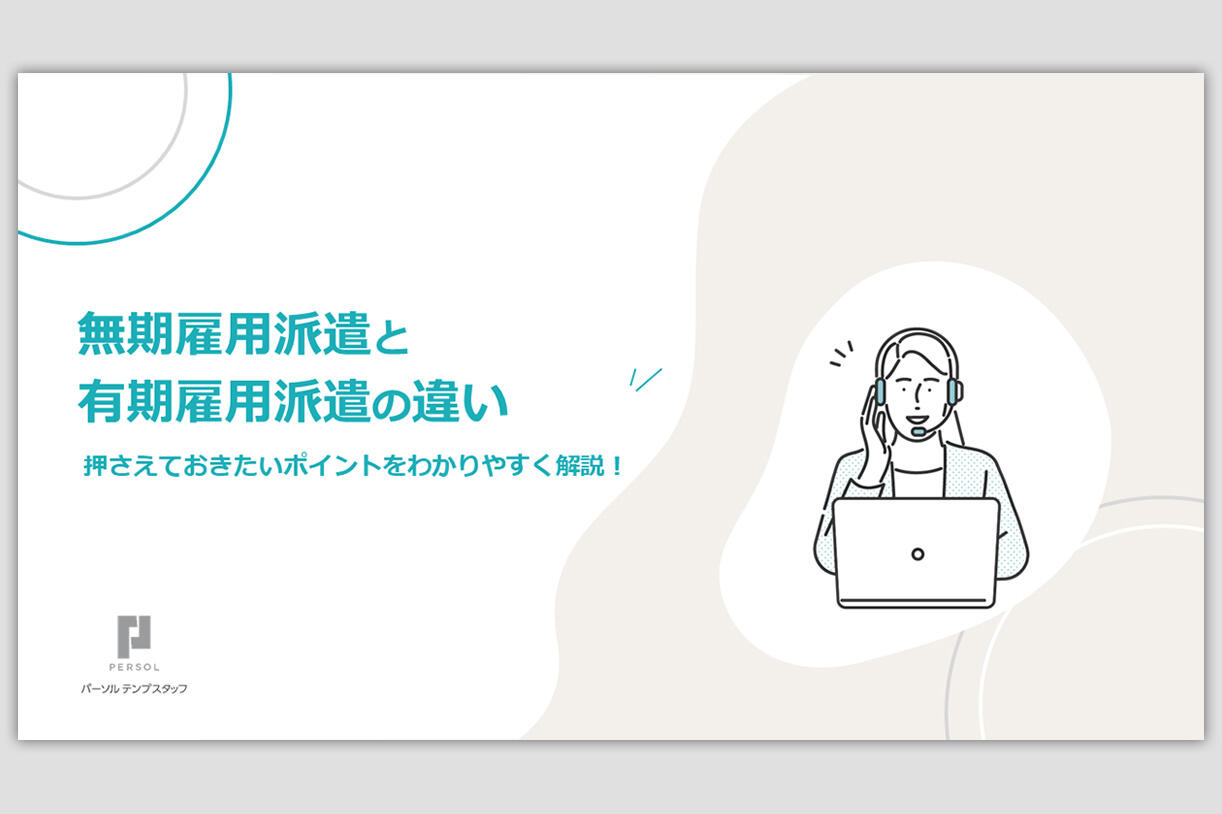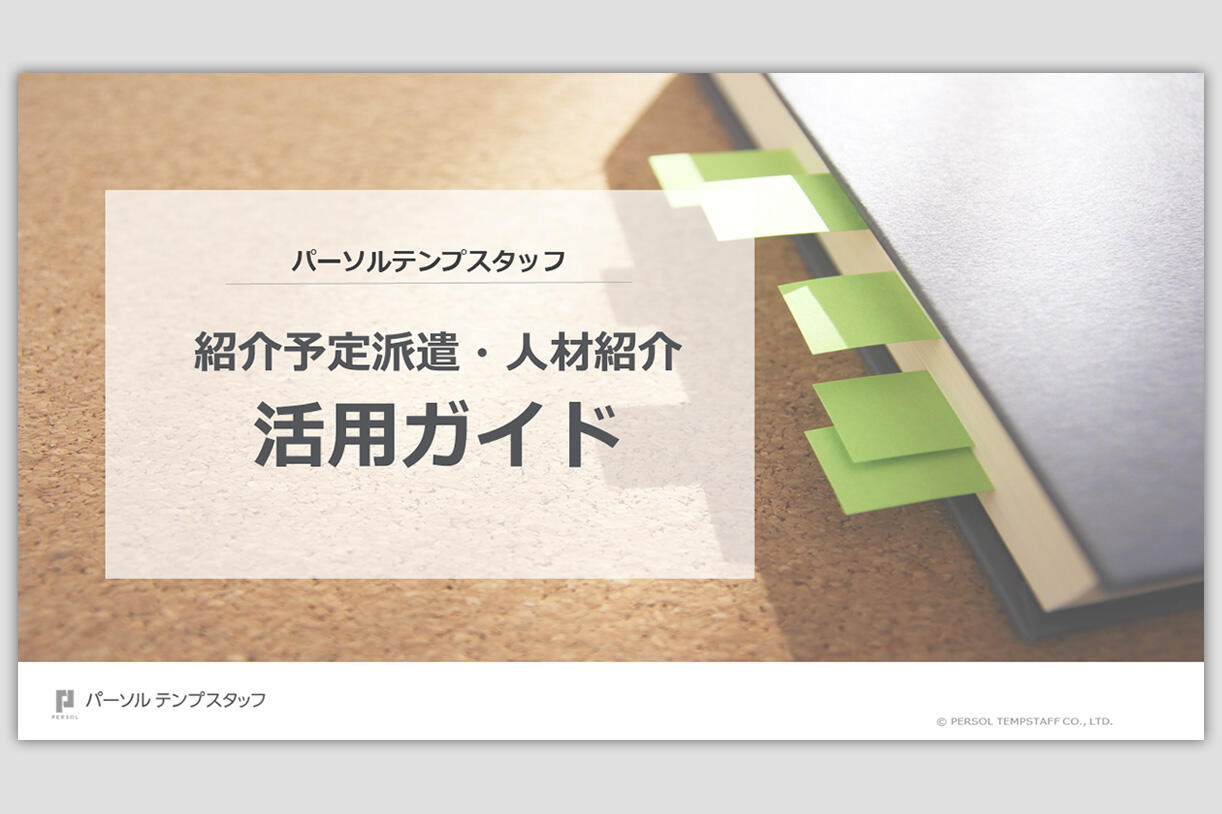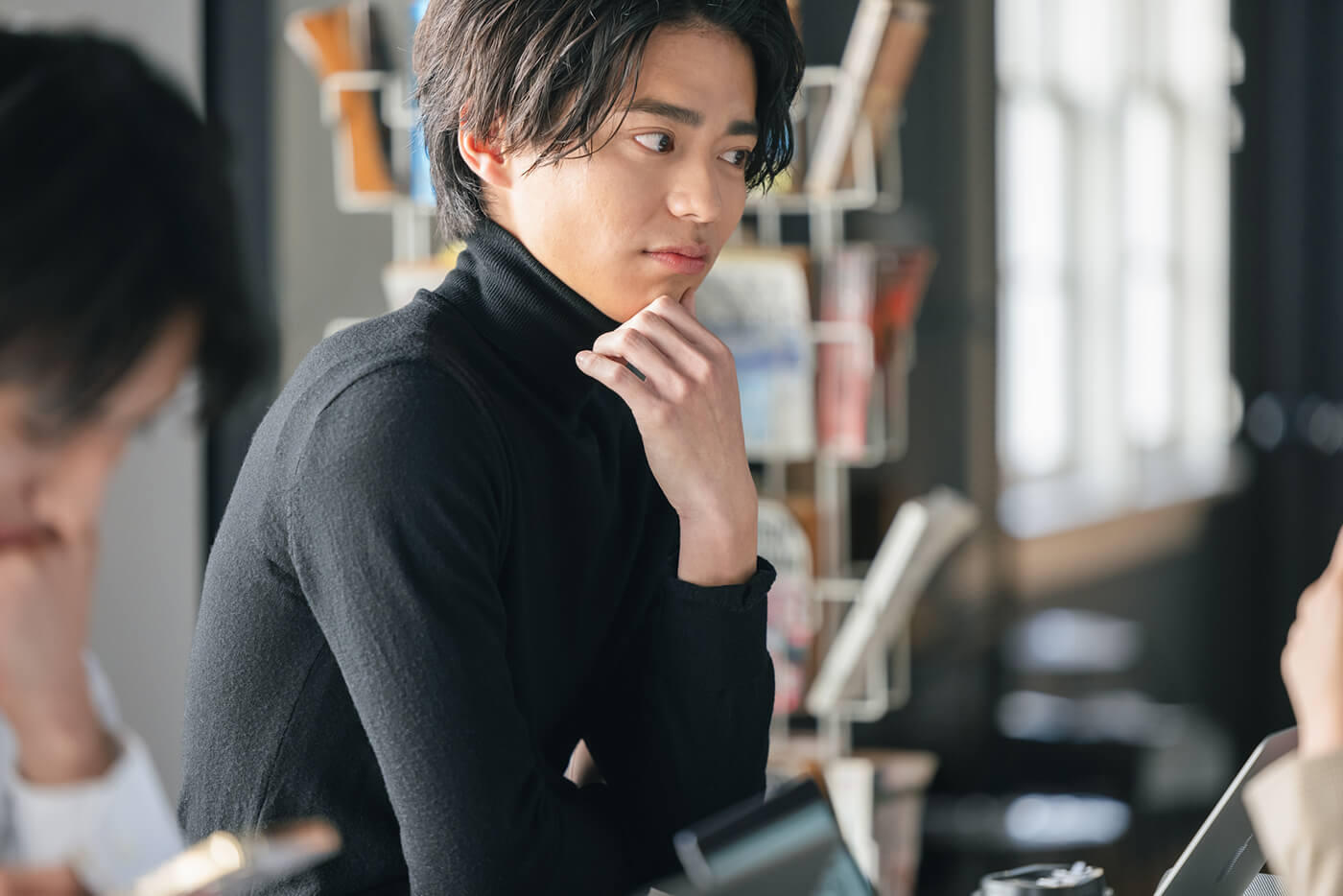HRナレッジライン
カテゴリ一覧
人事担当者必見!派遣の主要な種類と、それぞれのメリット・留意点を解説
公開日:2025.11.12
- 記事をシェアする

人材派遣には、「有期雇用派遣(登録型)」「無期雇用派遣(常用型)」「紹介予定派遣」といった複数の形態があり、それぞれ雇用契約の期間、運用ルール、法的制限が異なります。
自社で派遣社員の受け入れを検討する際は、それぞれの特徴を正しく理解し、自社に最適な契約形態を選ぶことが非常に重要です。
この記事では、主要な派遣形態の定義やメリット、留意点を整理した上で、請負契約や業務委託との違い、法令遵守のポイント、業務内容に応じた判断基準までを体系的に解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣契約とは?仕組みと企業の役割

企業が外部の労働力を受け入れる手段として広く利用されているのが「派遣契約」です。
これは、人材派遣会社と雇用契約を締結した派遣社員が、派遣先企業の指揮命令のもとで就業するという、三者関係によって成り立つ労働形態です。
派遣契約は、業務の繁閑や突発的な人員不足といった変動に柔軟に対応しやすく、必要なスキルを持つ人材を一定期間受け入れられる点で、多くの企業にとって有効な選択肢となっています。
しかし、指揮命令権が派遣先企業にあること、また、労働者派遣法に基づく厳格な運用ルールがあるため、契約形態や派遣期間、業務範囲などにおいて注意が必要です。
特に、請負契約や業務委託契約との混同は偽装請負と見なされるリスクがあるため、区別を明確にしておくことが不可欠です。
※参考:厚生労働省|第5 労働者派遣契約
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人材派遣の種類とそれぞれの特徴
人材派遣には主に以下の3種類があります。それぞれ、雇用期間や契約の目的、法的制限が異なり、自社の人員体制や事業の特性に応じて適切に選択することが求められます。
| 有期雇用派遣(登録型派遣) | 無期雇用派遣(常用型派遣) | 紹介予定派遣 | |
|---|---|---|---|
| 雇用契約の期間 | 派遣期間中のみ | 期間の定めなし | 最長6ヶ月の派遣期間 |
| 雇用形態 | 有期雇用 | 無期雇用(人材派遣会社の正社員・契約社員) | 有期雇用(直接雇用を前提) |
| 特徴 | 短期的・スポット的なニーズに対応 | 長期的・専門性の高い業務に適応 | 採用ミスマッチ防止・直接雇用への移行 |
| 主な法的制限 | 同一組織単位で原則3年まで | 期間制限なし | 派遣期間最長6ヶ月 |
上記の表で概要を把握した上で、それぞれの派遣形態について詳しく見ていきましょう。
有期雇用派遣(登録型派遣)
有期雇用派遣は、人材派遣会社に登録している派遣社員が、派遣先企業で一定期間のみ勤務する形態です。雇用契約は派遣期間中のみ結ばれ、契約終了後は再び待機状態となるか、別の派遣先を紹介されることになります。
特徴
短期的・スポット的なニーズに柔軟に対応できることが大きな特徴です。特定の業務や繁忙期、欠員補充など、限定された期間での就業に適しています。
法的制限
同一の派遣社員を同一組織単位(部署など)で受け入れられる期間は原則3年までと定められています。
依頼しやすい業務例
ルーティン業務や一時的なプロジェクト、産休・育休の代替など、特定の期間に集中的に発生する業務や、定型業務のサポートをお願いする際に適しています。
【例】
- 経理の決算補助
- データ入力
- 受付
- コールセンター
- 一般事務
- WEBサイトの更新作業
※参考:厚生労働省|派遣先の皆様へ
有期雇用派遣については以下の記事で詳しく解説しています。
>>有期雇用派遣とは?無期雇用派遣との違いを分かりやすく解説
派遣の3年ルールについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください。
>>派遣の3年ルールとは?例外や3年を超える場合の手続きを解説
無期雇用派遣(常用型派遣)
無期雇用派遣は、派遣社員が人材派遣会社と無期の雇用契約を結び、派遣先企業で就業する形態です。派遣社員は人材派遣会社の正社員または契約社員として位置づけられ、派遣先での業務がない期間も継続して雇用されます。
特徴
長期的な視点での雇用安定やキャリア形成が可能となる形態であり、高度な専門性や継続的な業務支援が求められる場合に適しています。
法的制限
有期雇用派遣と異なり、期間制限は設けられていません。
依頼しやすい業務例
ITエンジニアや研究開発職、医療系専門職など、高い専門性を要する業務や、長期的なプロジェクト、継続的なサポートが必要な基幹業務に適しています。
【例】
- システム開発・運用
- ネットワーク構築
- 特定分野の研究補助
- 医療事務専門職
無期雇用派遣については以下の記事で詳しく解説しています。
>>無期雇用派遣とは?メリットや留意点、派遣先企業で必要な対応を解説
紹介予定派遣
紹介予定派遣は、最長6ヶ月間の派遣期間を経て、派遣先企業との直接雇用を前提とした形態です。派遣期間中に企業と派遣社員の双方が業務内容や職場環境への適合性を見極めた上で、直接雇用に移行するかを判断できます。
特徴
採用前に実務での適性を確認できるため、ミスマッチを防ぐ有効な手段となります。さらに、派遣社員の受け入れ時には人材派遣会社が紹介を行うため、初期段階の工数削減にもつながります。
法的制限
通常の人材派遣では禁止されている履歴書の提出や面接の実施が認められており、派遣期間は最大6ヶ月までです。
依頼しやすい業務例
新卒・中途採用の試用期間のような位置づけで、長期的な視点での人材育成や、採用ミスマッチを避けたい重要なポジションに適しています。
【例】
- 営業職
- 企画職
- 事務総合職
- 新卒採用の代替
- 幹部候補
紹介予定派遣については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>紹介予定派遣の手数料は高い?費用構造や相場、活用方法について解説
派遣契約と請負契約・業務委託の違いとは
外部リソースを活用する際に混同されやすいのが、「派遣契約」「請負契約」「業務委託」といった契約形態の違いです。これらは似ているようでいて、法的な位置づけや業務指示の在り方に大きな違いがあります。
| 派遣契約(有期・無期) | 請負契約 | 業務委託(準委任) | |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 労働者派遣契約 | 請負契約 | 委任契約・準委任契約 |
| 雇用関係 | 派遣社員と人材派遣会社 | 請負従業員と請負会社 | 業務委託先の従業員と受託企業 |
| 指揮命令権 | 派遣先企業が持つ | 請負会社が持つ | 受託企業が持つ |
| 業務目的 | 労働力の提供 | 成果物の完成 | 業務の遂行(継続的) |
| 契約の特徴 | 派遣先の指示に従って業務を遂行 | 発注者が指揮命令できない。成果物の完成で報酬が発生 | 成果ではなくプロセス遂行が目的。報酬は業務遂行自体に発生 |
特に注意が必要なのは、派遣契約であるにもかかわらず請負契約として契約書を作成し、実態は派遣として業務を進める「偽装請負」です。これは法令違反として処罰対象になるおそれがあり、企業の社会的信用を損なう重大なリスクとなります。
そのため、契約形態の選定にあたっては、業務内容や業務指示の範囲、雇用関係の所在を明確に区別し、正しい契約形態を選ぶことが必須です。
人材派遣の種類別メリット・留意点
各派遣の種類には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、企業の状況や求める人材像によって最適な活用戦略が異なります。
有期雇用派遣のメリットと留意点
有期雇用派遣は最も一般的な派遣形態であり、短期ニーズへの柔軟な対応力が魅力です。一方で、期間制限やノウハウ継承といった課題に留意が必要です。
メリット
企業は必要な期間だけ人材を受け入れることができ、柔軟な人員補強が可能となります。これにより、繁忙期や突発的な人手不足にも迅速に対応できます。
また、労務管理などの業務は人材派遣会社が担うため、企業側の事務負担を軽減できる点も大きなメリットです。人件費を固定費ではなく変動費として調整でき、コントロールがしやすくなります。
留意点
同一部署での受け入れは原則3年までと定められているため、長期的な人員計画には注意が必要です。派遣期間満了に伴い人材が交代することで、業務ノウハウの継続性が課題となることもあります。
加えて、日々の業務指示や教育は派遣先企業側で行う必要があるため、一定の管理工数が発生します。
さらに、労働契約法に基づき、同一の派遣社員が通算5年を超えて有期契約で就業した場合、派遣社員からの申し込みにより人材派遣会社との雇用契約が「無期雇用」に切り替わる仕組み(5年ルール)があります。
無期雇用化されると契約の継続は可能ですが、派遣費用や契約条件が変更となるケースがあるため、長期的に同じ派遣社員を受け入れる場合は、事前に人材派遣会社と確認しておくことが重要です。
5年ルールの詳細や、派遣契約における3年ルールとの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>>人材派遣の5年ルールとは?概要や3年ルールとの違いを解説
無期雇用派遣のメリットと留意点
無期雇用派遣は、長期的に安定した人材を確保したい企業に適した派遣形態です。教育・育成の投資効果も高い一方、コストやマッチングの点では慎重な検討が求められます。
メリット
専門性の高い業務や継続的なプロジェクトにおいて、長期にわたり安定した人材を受け入れられる点は、大きなメリットです。派遣社員は人材派遣会社の正社員であるため、定着率が高い傾向があり、企業側としても人材育成への投資効果を期待しやすくなります。
また、人材派遣会社が無期雇用契約を結んでいるため、派遣先企業は派遣契約期間の制限を受けることなく、必要な期間、専門スキルを持つ人材を受け入れることができます。有期雇用派遣と同じく、労務管理の手間が少ない点も魅力です。
留意点
無期雇用派遣では、人材派遣会社が人材を正社員として雇用しているため、ミスマッチが起きると人材派遣会社側の負担が大きくなります。
このような背景から、派遣社員として受け入れる人材の選定は、有期雇用派遣に比べて慎重に行われる傾向があります。そのため、急ぎで人員を確保したい場合には、対応が難しいことがあります。
紹介予定派遣のメリットと留意点
紹介予定派遣は、採用ミスマッチのリスクを低減しつつ、効率的な採用活動を行いたい企業に適しています。しかし、採用までの期間や手数料、直接雇用に至らない可能性も考慮が必要です。
メリット
最大のメリットは、採用ミスマッチのリスクを大幅に減らせる点です。最長6ヶ月の派遣期間中に、企業は実際の業務内容や職場の雰囲気、派遣社員の人柄などをじっくり見極めることができます。
さらに、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて、業務への適性や成長の可能性を確認した上で、直接雇用するかどうかを判断できるため、入社後の定着率向上にもつながります。
留意点
企業側が直接雇用を希望しても、派遣社員側が雇用を拒否する可能性もあります。この場合、新たな人材を探さなければなりません。
直接雇用に至った場合には、人材派遣会社へ紹介手数料を支払う必要があります。この手数料は人材紹介サービスと同等の水準になることが多いため、事前に費用構造を把握しておくことが重要です。
派遣社員を受け入れる際に注意すべき3つのポイント
派遣の種類にかかわらず、労働者派遣法の遵守は企業のコンプライアンス体制において極めて重要です。法令違反は、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を損なうリスクも伴います。ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
ポイント1.期間制限の遵守(有期雇用派遣)
有期雇用派遣には、いずれも派遣社員を受け入れられる期間に制限があります。主な制限は以下の通りです。
- 事業所単位の制限:同一の事業所で派遣社員を受け入れられる期間は、原則として最長3年までです。ただし、過半数労働組合または労働者代表の意見を聴取すれば、さらに3年間の延長が可能です。
- 個人単位の制限:同一の派遣社員を、同じ部署やチームなど「同一の組織単位」で受け入れられる期間も、原則として3年が上限です。
労働契約申込みみなし制度とは、違法な派遣が行われた場合に、派遣先企業が派遣社員に対して、人材派遣会社と同一の労働条件で労働契約を申し込んだものとみなされる制度です。
みなされた日から1年以内に、派遣社員がその申込みを承諾する意思を示した場合、派遣先企業との間に労働契約が成立します。
労働契約申込みみなし制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>労働契約申込みみなし制度の対象となるのは?ポイントと対策を解説
ポイント2.同一労働同一賃金への対応
2020年4月施行の改正労働者派遣法により、派遣社員と正社員との間での不合理な待遇差をなくすことが義務化されました。派遣先企業は、以下のいずれかの方式で待遇格差の是正に取り組む必要があります。
- 派遣先均等・均衡方式:派遣先企業の通常の労働者との均等・均衡を基準に、派遣社員の待遇を決定します。
- 労使協定方式:人材派遣会社が、労働者代表と労使協定を締結し、その協定内容に基づいて待遇を決定します。
派遣先企業は人材派遣会社と連携し、自社の派遣社員がどちらの方式で待遇決定されているかを把握し、適切に対応する必要があります。
同一労働同一賃金については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介
ポイント3.派遣禁止業務の確認
労働者派遣法では、安全性や公共性の観点から、以下の業務への派遣が原則禁止とされています(一部例外あり)。
- 建設業務(現場作業員など)
- 港湾運送業務
- 警備業務
- 医療機関における医療行為(看護師・医師など)
これらの業務に派遣社員を従事させることは原則認められていません。万が一該当する業務での派遣社員の受け入れが発覚した場合、派遣契約そのものが無効とされる可能性があるため、事前の法的確認が必須です。
派遣禁止業務については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説
自社の課題別・最適な派遣形態の選び方
人材派遣を活用する際、「どの形態が最適か」は、自社の人材ニーズ・業務の特性・将来的な採用方針によって異なります。
ここでは、よくある5つの課題・シチュエーション別に、最適な派遣形態と活用のヒントを整理しました。
専門スキルを持つ人材を、今すぐ受け入れたい
即戦力が求められる短期案件では、有期雇用派遣の柔軟性が効果を発揮します。
【おすすめの派遣形態】
- 有期雇用派遣(登録型)
【受け入れの具体例】
- WEBデザイナーを3ヶ月だけ確保したい
- 会計期末だけ決算補助の人手を増やしたい
長期的に育成・定着してほしい
スキルの蓄積や人材の育成を重視するなら、無期雇用派遣や紹介予定派遣が有効です。
ただし、派遣先企業が無期雇用の派遣社員を希望していても、要望が通るかは人材派遣会社の運用方針や雇用契約の状況によります。受け入れを検討する際は、事前に人材派遣会社に確認するようにしましょう。
【おすすめの派遣形態】
- 教育しながら長くはたらいてもらいたい→無期雇用派遣
- いずれ正社員として採用したい→紹介予定派遣
【受け入れの具体例】
- 新規事業部門の専任スタッフを長期で育成したい
- 組織カルチャーに馴染む人材を見極めてから採用したい
無期雇用派遣の活用や紹介予定派遣サービスについては、以下のサービスページもご覧ください。
>>育成型無期雇用派遣のfuntable(ファンタブル)
>>パーソルテンプスタッフの紹介予定派遣
一時的な人手不足や業務増加に対応したい
産休代替や突発的な増員には、有期雇用派遣が最適です。
【おすすめの派遣形態】
- 有期雇用派遣
【受け入れの具体例】
- 半年間だけ事務スタッフを補充したい
- システム導入期間だけ、ITサポート人員を増やしたい
人材派遣の種類に関するよくある質問
ここでは、人材派遣の種類に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q1.自社に最適な人材派遣の種類は、どうやって選べばよいですか?
人材派遣の種類は、主に以下の3点から検討するのが効果的です。
- 求める人材のスキルや即戦力性:短期的な即戦力が必要なら有期雇用派遣、専門性や継続性を重視するなら無期雇用派遣。
- 業務の性質と期間:一時的な業務支援なら有期、長期的な育成・定着を狙うなら紹介予定派遣が有効です。
- 将来的な採用方針:正社員化を見据える場合は、紹介予定派遣がミスマッチのリスクを抑えられます。
上記を踏まえて判断することで、自社に合った契約形態を選ぶことができます。
Q2.紹介予定派遣」と「人材紹介」はどう違うのですか?
最大の違いは、採用前に実務で見極められるかどうかです。
- 紹介予定派遣:最長6ヶ月の派遣期間を経て、企業と派遣社員双方が合意すれば直接雇用へ。派遣期間中に職場の適性やスキルを確認でき、ミスマッチを防げます。
- 人材紹介:初めから正社員(または契約社員)として採用。実務評価なしでの採用判断となるため、即戦力向けです。
採用リスクを抑えたい場合は、紹介予定派遣の方が安心です。
Q3.派遣社員を受け入れる際、法律上の注意点はありますか?
労働者派遣法に基づく運用ルールを遵守する必要があります。主な注意点は以下の通りです。
- 期間制限:有期雇用派遣の場合、同一の派遣社員を、同一の組織単位で受け入れるのは最大3年までなどの制限があります。
- 同一労働同一賃金:派遣社員と正社員の待遇差是正が義務化されています。
- 派遣禁止業務:建設・警備・医療行為など、一部業務には派遣が原則禁止されています。
- 偽装請負の回避:契約書と現場運用が一致していない場合、法令違反と判断されるリスクがあります。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人材派遣の種類を正しく理解し、最適な人材戦略を
有期雇用派遣、無期雇用派遣、紹介予定派遣といった主要な人材派遣の種類について、その定義、メリットや留意点、そして企業が遵守すべき法的注意点を詳細に解説しました。
多様な人材派遣の種類を正しく理解し、貴社の事業課題や人材ニーズに合致した最適な派遣活用戦略を構築することで、法的なリスクを回避しつつ、持続的な事業成長を実現できるでしょう。
人材戦略の一環として、派遣の受け入れに関してさらに詳しく知りたい点や、具体的なケースについてご相談がある場合は、どうぞお気軽にお声がけください。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする