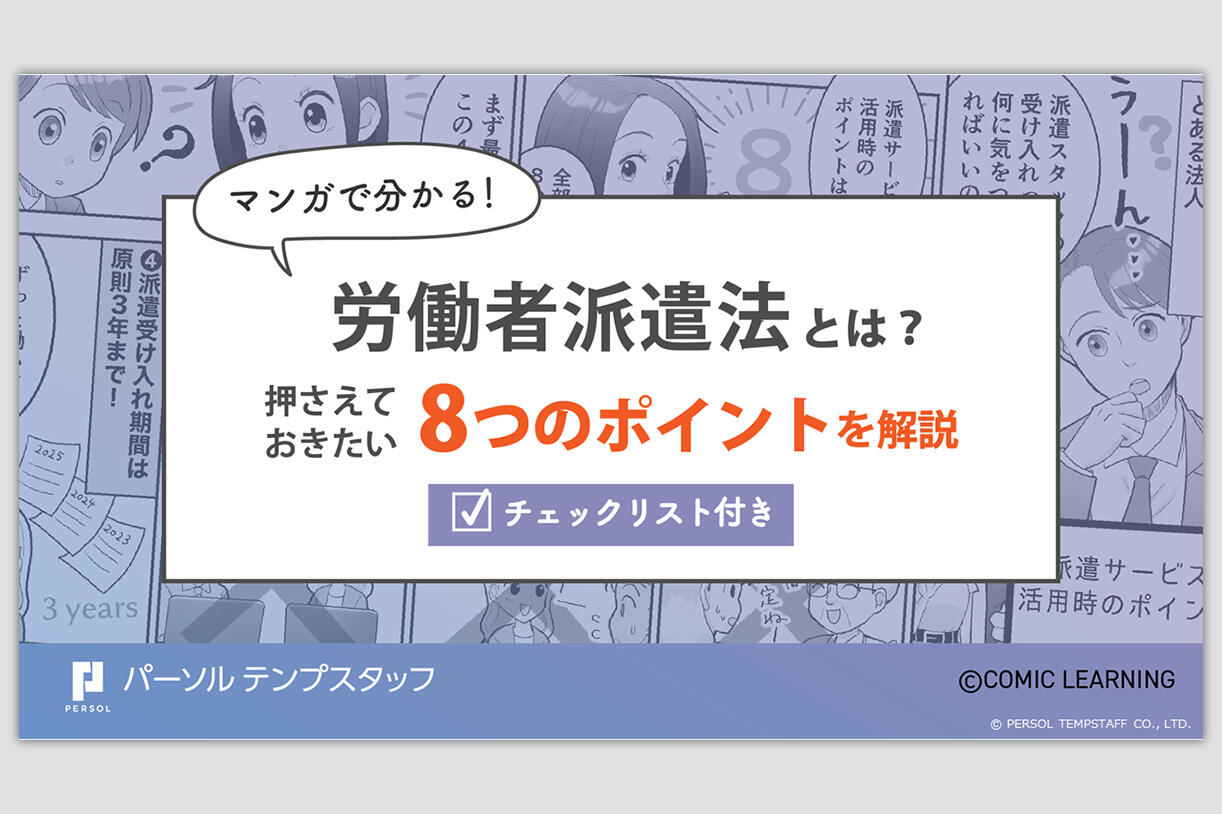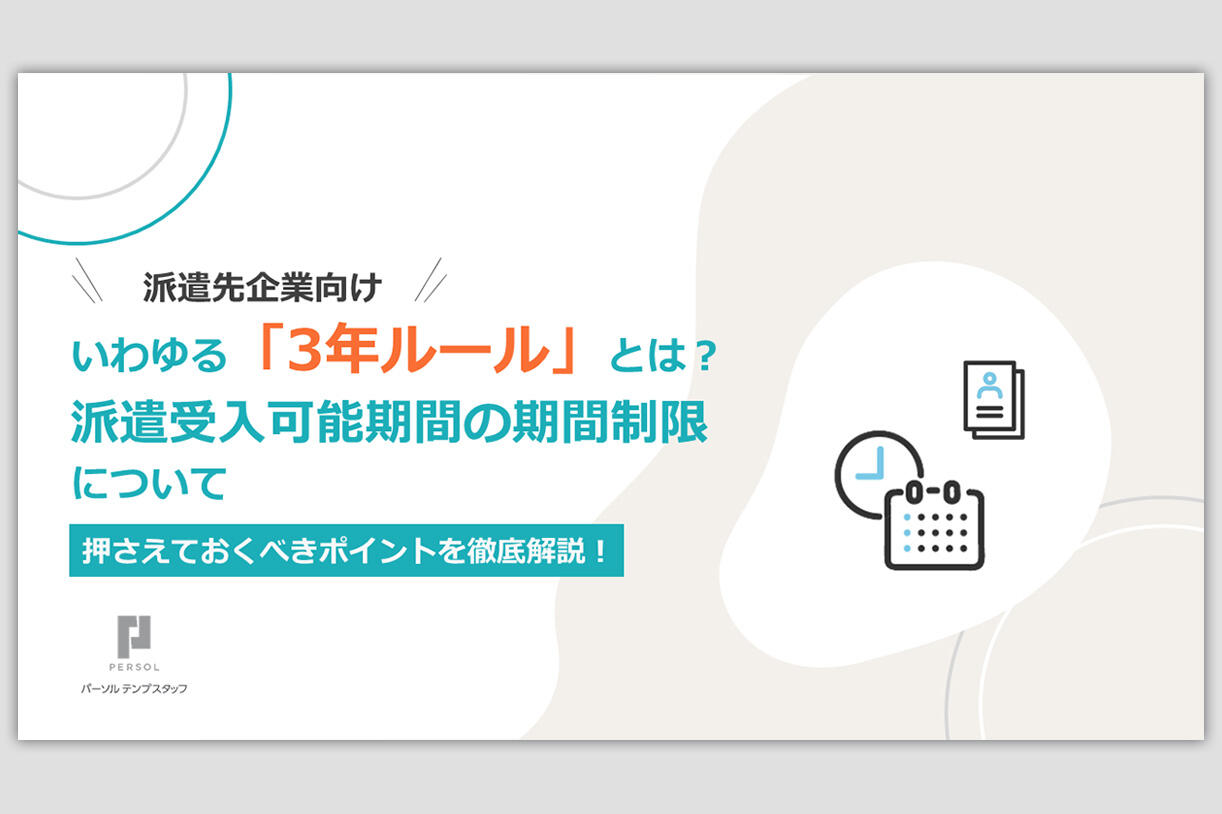HRナレッジライン
カテゴリ一覧
人材派遣の5年ルールとは?概要や3年ルールとの違いを解説
- 記事をシェアする

派遣社員が同一の人材派遣会社との有期労働契約が5年を超えると、本人の希望により「契約期間の定めがない」雇用形態、すなわち無期雇用へと転換することができます。これは無期転換ルール、通称「5年ルール」と呼ばれています。
この記事では、この5年ルールについて、3年ルールとの違い、適用されるための条件のチェックリスト、そして企業側のメリットと留意点を、図解を用いて分かりやすく解説しています。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人材派遣のいわゆる「5年ルール」とは
5年ルールとは、同一の企業との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される制度のことです。5年ルールは、無期転換ルールと呼ばれることもあります。
労働者から無期転換の申し出があった場合に無期労働契約が成立し、申し出を受けた企業は断ることができません。
いわゆる「人材派遣の5年ルール」という言葉を耳にした方もいると思いますが、上記のように、このルールは派遣社員に限ったものではありません。
無期転換ルールが導入された目的
有期労働契約は、1年や6ヶ月単位などあらかじめ期間を決めて締結する労働契約を指します。その契約期間が満了した際、契約更新されるか終了となるかは企業の判断に委ねられがちだったため、有期契約労働者の処遇の改善が課題となっていました。
有期労働契約を反復更新して労働者を長期間継続雇用するという有期労働契約の濫用的利用を防ぎ、有期雇用労働者の雇用の安定を図ることを目的に、無期転換ルールが制度化されました。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
5年ルールと3年ルールの違い
いわゆる5年ルールとは、同一の企業に5年を超えて勤務した有期契約労働者が申し出た場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
一方、いわゆる人材派遣の3年ルールとは、派遣社員を同一の派遣先企業にて継続して受け入れることができる期間(派遣可能期間)の制限のことです。
5年ルールと大きく異なる点は、対象が派遣社員のみであることです。5年ルールのようにパート・アルバイトや契約社員は対象にならず、派遣社員に適用される制度が3年ルールです。
3年ルールについて詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>派遣の3年ルールとは?概要や例外となるパターンなどを解説
無期転換ルールの適用条件
どのようなケースで無期転換が可能なのでしょうか。2012年の労働契約法改正で、無期労働契約への転換ルールが規定されました。
それによって、派遣社員をはじめ、パートタイマー、契約社員など有期労働契約の労働者は、条件を満たしていれば無期雇用契約に転換できるようになったのです。
直接雇用のパートタイマーや契約社員といった労働者から申し出があった場合には、自社で無期雇用へ転換することになります。ただし派遣社員の場合は、自社(派遣先企業)が無期転換することはありません。雇用主は人材派遣会社のため、派遣社員が無期雇用を申し出る場合には人材派遣会社に申し込みをします。
以下の条件・ケースをすべて満たせば、無期転換が可能となります。
- 有期労働契約期間が通算5年を超えて更新された場合
- 有期労働契約の更新が1回以上ある
- 有期労働契約を結んでいる
それぞれについて詳しく解説していきます。
有期労働契約期間が通算5年を超えて更新された場合
派遣社員として同一の使用者との間で、通算5年を超えて何回も更新されている場合には、無期転換ルールが適用されます。派遣社員側から人材派遣会社に無期転換の申し込みがあった場合には、断ることはできません。労働契約法によって、必ず受け入れなければならないことになっています。
例えば、1回の契約期間が1年間と定められていた場合には、5回目すなわち5年たったときに無期転換申し込み権が発生します。
※引用:厚生労働省|無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方 | 有期契約労働者の無期転換サイト
有期労働契約の更新が1回以上ある
同一の使用者との間で契約の更新回数が1回以上あることも、無期転換ルールが適用される条件となります。
有期労働契約を結んでいる
上記の無期転換ルールが適用される派遣社員は、人材派遣会社との有期労働契約の期間中であることが条件となります。
※参照:無期転換ルールについて(厚生労働省)
無期雇用派遣について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>無期雇用派遣とは?活用するメリットや留意点についてご紹介
無期転換ルールのメリット
無期転換ルールに基づいて労働者を有期雇用から無期雇用に転換することは、労働者だけでなく企業にとってもメリットがあります。考えられる主なメリットは以下の2つです。
- 人材を長期的に雇用することができる
- 採用コストや教育コストを削減できる
それぞれについて詳しく解説していきます。
人材を長期的に雇用することができる
無期転換することで、労働者を長期的に雇用でき、企業の業務に精通する社員を確保することができます。労働者も安定的に就業でき、自社の業務に特化したスキルを蓄積することができ意欲的に就業することができます。
その結果、業務プロセスの効率も向上し、業務の安定性と品質は高まるでしょう。
また、無期雇用で労働者が長期間勤務すると想定すれば、長期的な人材戦略が立てやすくなります。専門的なスキルを身に付けてもらう、もしくは幹部候補として教育するなど、人材育成を考える上でも可能性は広がります。
採用コストや教育コストを削減できる
同一企業での勤務年数が5年を超えているということは、その労働者が現在の職場環境になじみ、業務を理解した上で貴重な存在になっている証拠といえるでしょう。
つまり、企業はあらたな人材を確保する必要がなくなり、教育コストを削減できる可能性があります。引き続き業務に携わってくれるため、即戦力としてこれまで同様に活躍が期待できます。
無期転換ルールの留意点
無期転換ルールには企業にとってメリットがありますが、その一方で下記のような留意点も存在します。
- 人材の配置が難しくなる可能性がある
- 正社員と無期転換した従業員の差がでてしまう可能性がある
人材の配置が難しくなる可能性がある
無期転換ルールに基づく無期雇用契約は、長期的に人材を確保したい企業にとっては歓迎すべきものです。その一方で、急な業務変動に応じ柔軟に人員調整しづらくなるという面もあります。
例えば、有期雇用労働者の場合、契約期間に応じて雇用契約を終了することが可能です。しかし、無期雇用契約の場合は、契約期間の満了はなく、雇用契約終了に際しては、労働基準法や就業規則に基づき、厳格におこなわなければなりません。そのため人員を自由に調整することが難しくなります。
社員と無期転換した社員の待遇差が出ないように配慮する
特に留意しなければならないのは、待遇についてです。無期転換者を社員にした際は問題ないのですが、もし社員にしなかった場合、待遇や福利厚生の面で既存の社員と差が生じる可能性があります。
社員と同内容の業務を担当しているにもかかわらず、社員より給与が低かったり昇進が望めなかったりする場合、モチベーションの低下や離職のリスクが高まります。加えて、組織全体の協調性に影響が出るおそれもあります。
そうならないためにも、無期転換者に対しては昇進の機会や賃金制度について明確に提示しておきましょう。
5年ルールに関するよくある質問
Q1.誰が5年ルール(無期転換ルール)の対象となりますか?
同一の雇用主(企業・人材派遣会社など)と有期労働契約を結び、契約の更新により通算5年を超えてはたらすべての労働者が対象です。派遣社員・契約社員・パート・アルバイトなど名称や職種は問いません。
ただし、厚生労働省令に基づく特例措置として、都道府県労働局長の認定を受けた「高度専門職」や「定年後に継続雇用される高齢者」などは、無期転換申込権が猶予・除外される場合があります。
Q2.5年ルールに例外はありますか?
はい。いったん契約が切れた後、同じ雇用主とまったく契約を結ばない「空白期間(クーリング期間)」を設ければ、それより前の勤務期間は5年カウントから外れます。
直前の契約が1年以上続いていた場合は、6ヶ月と1日以上の空白が必要です。一方、直前の契約が1年未満だった場合は、その契約期間の半分を超える長さに1日を足した期間を空ければリセットされます。
Q3.同じ派遣社員を契約満了後に再び受け入れる方法はありますか?
同じ派遣社員を同一事業所・同一組織単位で受け入れられる期間は原則3年です。制限をリセットするには、派遣受入れを3ヶ月と1日以上空ける「クーリング期間」を設ける必要があります。
ただし、派遣元で無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は個人単位の期間制限の対象外なので、クーリング期間を置かずに再受入れ可能です。
また、当該派遣社員が派遣元との通算契約期間5年超で無期転換を申し出た場合、人材派遣会社との間で無期雇用契約が成立します。派遣先企業は、その労働者を無期雇用派遣として受け入れることはできますが、直接雇用する法的義務はありません。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
無期転換ルールの適用条件やメリット、留意点を理解する
有期契約労働者が同じ企業で5年以上はたらいた場合、無期転換ルールが適用されます。5年を超えた期間を含む有期労働契約期間内に無期転換申込権が発生し、その期間内に使用者に対して権利行使をすると、その契約期間が終了した翌日から無期雇用労働者になります。
有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し出により無期労働契約が成立し、申し出を受けた企業は断ることができません。また、派遣社員に関しても派遣元に対して無期転換することが可能です。
無期転換は、不況時や閑散期において人材の配置が難しくなるという留意点が存在します。その一方、自社の業務に精通した労働者が長期間定着するという点が企業にとってはメリットです。これらのメリットや留意点を踏まえた上で、無期転換した社員にも十分に活躍してもらいましょう。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする