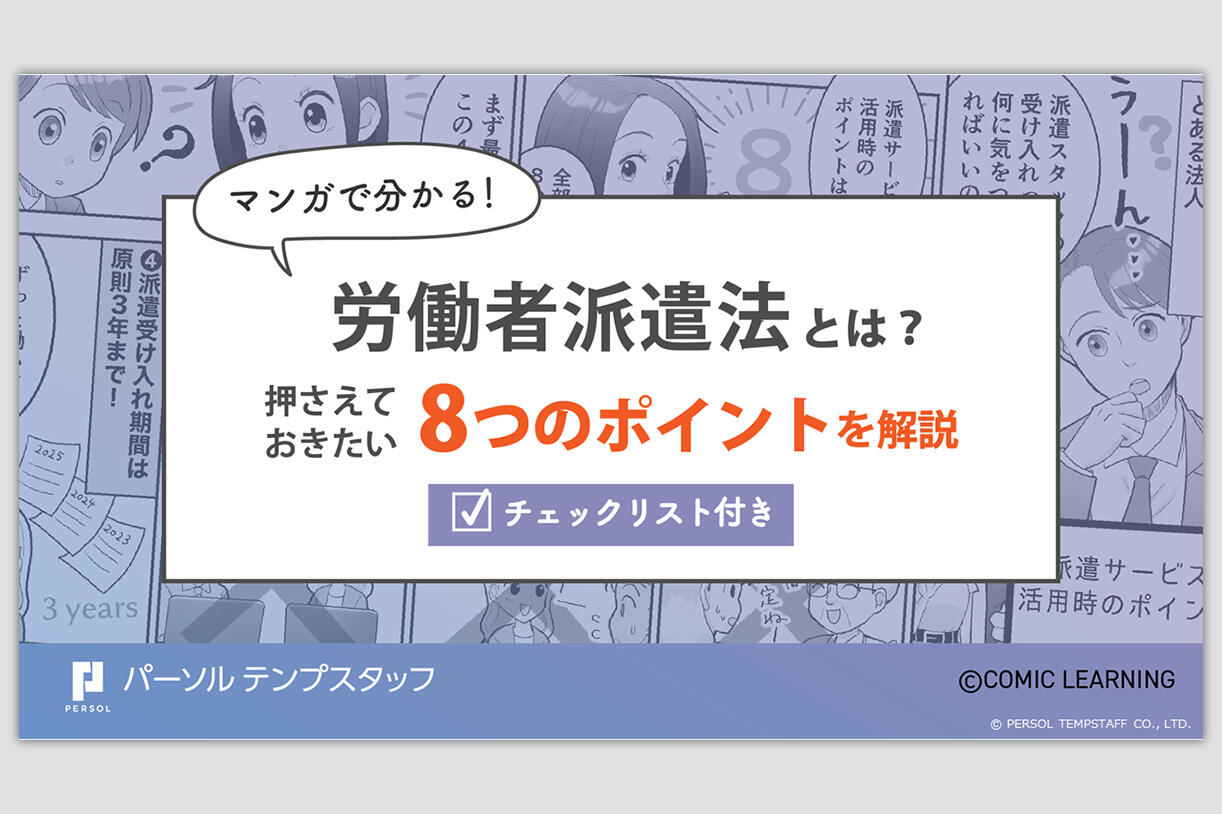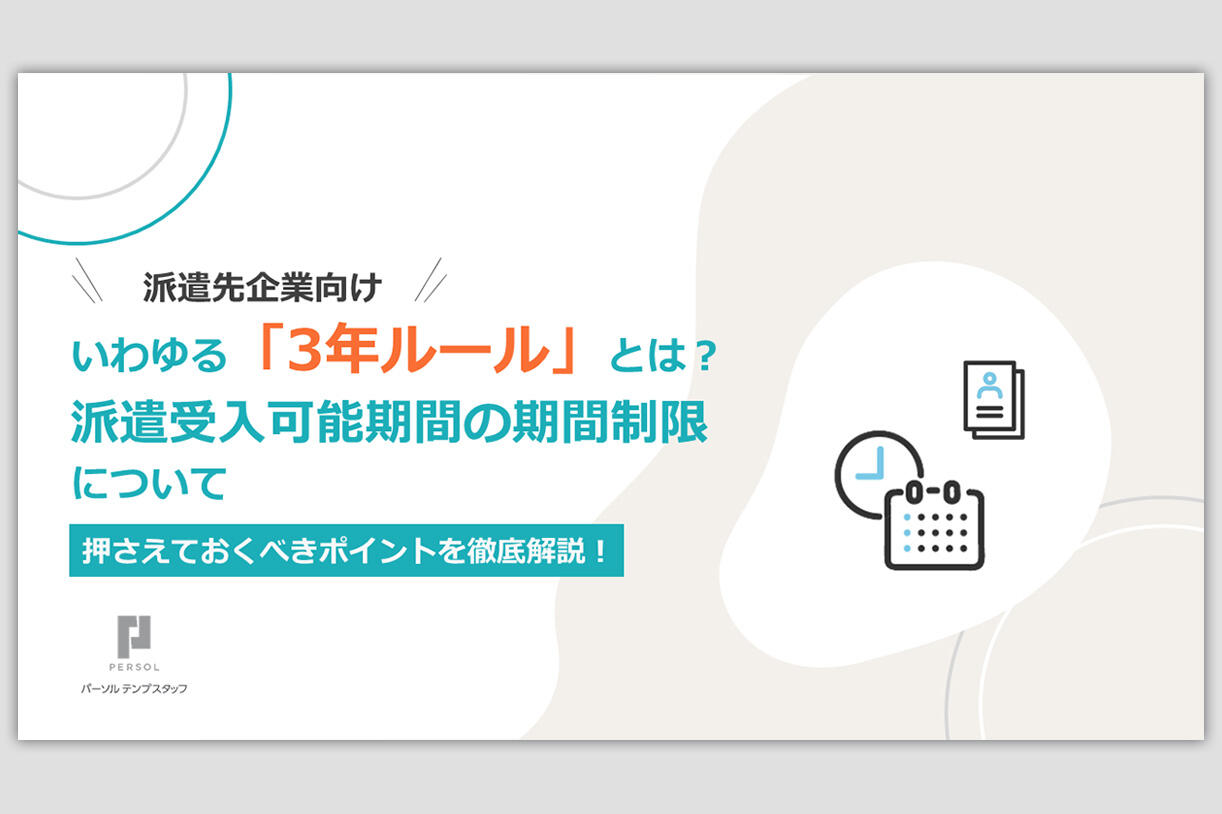HRナレッジライン
カテゴリ一覧
派遣社員の配置転換とは?|企業が知っておきたいルールと留意点、手続きのポイント
公開日:2025.10.14
- 記事をシェアする

派遣社員の配置転換は、契約内容の範囲を超える場合には原則として認められていません。ただし、人材派遣会社(派遣元)との合意や契約内容の変更があれば、一定の条件下で配置転換が認められることもあります。
本記事では、以下のポイントを実務担当者の視点から分かりやすく解説します。
- 派遣社員の「配置転換」や「転勤」の違いと法的ルール
- 配置転換を申し出る際の実務フローと留意点
- 契約・手続きの見直しでトラブルを防ぐ方法
なお、本記事での「配置転換」とは、派遣先の自社社員に対する人事異動ではなく、人材派遣会社との契約変更に伴い、派遣社員の担当業務や部署を変更することを指します。
現場の要望に応じて派遣社員を配置転換したいものの、契約上どこまで対応できるのか判断に迷う方は、ぜひご一読ください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣社員の配置転換や転勤の基礎知識
派遣社員に関して現場から「別部署での勤務をお願いできないか」と相談を受けることもあるのではないでしょうか。しかし、派遣社員の就業条件は契約書に定められているため、派遣先企業の判断だけで配置転換を指示すると、労働者派遣法の違反となるおそれがあります。
まずは、「配置転換」と「転勤」の違いを整理し、それぞれの特徴を理解しましょう。
派遣社員の「配置転換」とは
派遣社員の配置転換とは、現在就業している部署や業務内容を変更することです。例えば、総務部に配属されている派遣社員を経理部で勤務させるケースなどが該当します。これは「部署配置転換」「配置換え」とも呼ばれます。
派遣契約では、業務内容や部署・指揮命令者などが詳細に定められており、これを逸脱する変更は、原則として人材派遣会社との再協議・再契約が必要です。
配置転換と転勤の違い
「配置転換」と「転勤」は、一見似ているようで意味が異なります。最大の違いは「勤務地が変わるかどうか」です。
配置転換は、勤務地はそのままで、部署や業務内容のみが変更される異動です。主に組織の活性化や人材育成などを目的として行われます。
転勤は勤務地そのものが変わる異動です。例えば、東京本社から大阪支社へ移るケースなどが該当します。通勤時間の増加や引っ越しが必要になる場合もあります。
配置転換と転勤はいずれも「人を動かす措置」ではありますが、その影響範囲には大きな差があります。
派遣社員の異動には契約上の制限がある
配置転換や転勤は、いずれも労働契約や派遣契約における重要な労働条件の変更にあたります。派遣社員の場合、契約書に明記された就業場所や業務内容が変更される際には、人材派遣会社および派遣社員本人との合意が必須です。
派遣契約に記載されていない配置転換や転勤を行う場合は、人材派遣会社が派遣社員と十分に協議し、明確な合意を得た上で契約を再締結する必要があります。
なお、派遣先企業が一方的に配置転換の指示を出すことは、労働者派遣法に抵触するおそれがあり、原則として認められていません。配置転換を希望する場合は、必ず人材派遣会社に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
労働者派遣法における配置転換・転勤の3つの留意点|契約外の対応はリスクも
派遣社員の配置転換や業務変更については、労働者派遣法の観点から明確な制限があります。「少しだけ」「短期間だけ」といった軽い判断で契約外の業務を任せると、労働者派遣法の違反や偽装請負とみなされる可能性があります。
ここでは、派遣先企業が留意すべき3つのルールについて整理します。
契約内容と異なる業務は原則NG
派遣社員が行う業務や就業場所は、「労働者派遣契約」および「就業条件明示書」に明記されており、その範囲外の業務を命じることは原則として認められていません。
例えば、事務職として契約している派遣社員に、受付・販売・倉庫作業など異なる職種の業務を任せた場合、労働者派遣法に違反するおそれがあります。
こうした業務変更を行いたい場合は、人材派遣会社と協議の上、契約書を再作成・更新することが必要です。
派遣契約の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>>派遣契約の流れを3つのステップに分けて徹底解説
指揮命令者の変更にも留意が必要
業務内容や部署が変わると、実際に指示を出す「指揮命令者」も変わるケースが出てきます。 指揮命令者が変わる場合、人材派遣会社は就業条件明示書に記載する情報を更新し、派遣社員と契約をし直す必要があります。
派遣先企業が一方的に変更するのではなく、人材派遣会社との事前合意と書面での手続きが求められます。軽微な変更に見えても、書面に残しておかないと後々トラブルにつながる可能性があります。
指揮命令者の役割や選定のポイントについては、以下の記事をご参照ください。
>>派遣法の指揮命令者とは?役割や選び方について分かりやすく解説
短期の「応援勤務」でも契約範囲を超えるとNG
「今週だけ別のチームを手伝ってもらいたい」など、短期的な配置転換・応援勤務であっても、契約に明記されていない業務・場所・指揮命令者の変更を伴う場合は、労働者派遣法の違反に該当する可能性があります。
たとえ派遣社員本人が了承していたとしても、人材派遣会社の合意なしでは法的に無効と判断されるリスクがあるため留意が必要です。こうした「一時的対応」は見落とされやすいため、契約を再確認した上で、人材派遣会社と適切な再契約や覚書の締結を検討しましょう。
配置転換を可能とする三者合意と契約変更
派遣社員の配置転換には、人材派遣会社・派遣先企業・派遣社員本人の三者合意が不可欠です。合意があっても、口頭だけの了承では認められません。
具体的には、以下の契約書類・記録を改訂する必要があります。
- 労働者派遣個別契約書(派遣先企業と人材派遣会社で締結)
- 派遣先管理台帳(派遣先企業が作成・備付け)
これらには「新しい業務内容」「勤務場所」「指揮命令者」などを明記し、必ず書面として整備する必要があります。本人が了承していたとしても、契約変更が伴っていなければ労働者派遣法の違反(違法派遣・偽装請負)となる可能性があるため、手続きは徹底しましょう。
配置転換の進め方|人材派遣会社と連携した安全な手続き
派遣社員の配置転換は、正社員の配置転換とは異なり、法的な制約や手続きが多く存在します。特に、労働者派遣契約や就業条件明示書に明記された就業条件が変更される場合は、人材派遣会社・派遣先企業・本人の三者間で適切な手続きを踏む必要があります。
ここでは、派遣社員の配置転換を安全かつ円滑に進めるための基本的な4ステップを紹介します。
ステップ1.事前に人材派遣会社と協議
配置転換の必要性が生じた際は、まず人材派遣会社と協議を行います。人員配置の背景や配置転換理由、想定している配置転換先部署・業務内容・期間などの情報を共有しましょう。
この時点では、人材派遣会社は派遣社員の意向や適性を踏まえて対応の可否を判断し、法的観点からの助言を行います。メールや議事録などで協議内容を記録に残しておくことが望ましいです。
ステップ2.本人への説明・同意取得
労働契約の変更には、派遣社員本人の事前同意が不可欠です。人材派遣会社を通じて、配置転換の理由、配置転換後の業務内容、時給や労働時間の変更有無などを丁寧に説明し、本人が納得した上で書面による同意を取得します。
特に、配置転換が本人にとって不利益となる場合には、慎重な対応が求められます。人材派遣会社が本人への説明責任を負うことになるため、派遣先企業は情報提供と連携に努めましょう。
ステップ3.派遣契約・明示書の再作成
配置転換により、業務内容や就業場所、指揮命令者が変更される場合、労働者派遣個別契約書および就業条件明示書の更新が必要です。
派遣契約書には、業務の範囲・勤務地・受け入れ期間などが記載されており、これに変更が生じる場合は、人材派遣会社と派遣先企業との間で再契約が必要になります。同時に、派遣社員本人に交付される就業条件明示書も、最新の条件に沿って改訂しなければなりません。
ステップ4.受け入れ先部署との調整
配置転換後の配属先では、受け入れ体制の整備が重要です。業務の引継ぎ、OJTの実施体制、業務マニュアルの整備、教育担当者の指定など、実務面での準備を進めます。
特に初日対応や業務開始までのフォローが不十分だと、配置転換の目的が果たされないばかりか、定着にも支障が出る可能性があります。事前に受け入れ部署と調整し、スムーズなスタートを支援しましょう。
派遣社員の配置転換で変わる可能性のある5つの要素
派遣社員の配置転換を検討する際、最も重要なのは「何がどのように変わるか」を正確に把握することです。派遣労働は、契約ベースで業務内容・勤務条件が明文化されているため、たとえ同じ企業・同じ建物内での配置転換であっても、契約変更が必要になるケースは少なくありません。
ここでは、配置転換によって変更が生じやすい5つの要素を取り上げ、それぞれのポイントや留意点を実務目線で解説します。人事・現場担当者がリスクを避けつつ、スムーズな運用につなげるための指針としてご活用ください。
1.指揮命令者と部署名
派遣契約には、「どの部署で」「誰の指揮命令のもとに」はたらくのかを明記した上で契約します。したがって、配置転換により部署が変更になれば、指揮命令者(通常は課長や係長クラス)も変わるのが一般的です。
この場合、人材派遣会社との間で就業条件明示書と契約書の再調整が必要となります。書面に反映せずに変更を進めると、労働者派遣法の違反や偽装請負とみなされる可能性があるため、細部まで確認を行いましょう。
2.業務内容
派遣社員が従事する業務内容は、労働者派遣契約において非常に重要な記載事項の1つです。例えば「一般事務」から「営業事務」へ、「製造ライン」から「検品業務」へといったように業務の性質が変わる場合は、新たな契約を締結しなければなりません。
仕事内容が似ているからといって契約変更を省略するのは法的にリスクがあるため、業務の具体的な範囲や責任の程度を含め、契約書への記載を徹底しましょう。
3.勤務時間・休憩時間
配置転換にともない、始業・終業時刻や休憩時間が変更となることもあります。例えば製造ライン勤務から物流センターの早朝シフトに配置転換するようなケースでは、労働時間帯が大幅に変わることもあるでしょう。
派遣契約書には、勤務時間・休憩時間・所定労働時間数が明記されるため、変更があれば必ず再契約・再確認を行う必要があります。
4.抵触日との関係
「抵触日」とは、派遣社員が同一の事業所の同一の組織単位(通常は「課」など)で継続して受け入れられる期間の上限を超えた最初の日のことです(労働者派遣法第40条の2、第40条の3)。同一の組織単位で派遣社員を受け入れられる期間は3年となっているため、抵触日は3年後の同日にあたります。
抵触日は、企業が同一の派遣社員を長期間にわたって恒常的に使用し続けることを防ぐために設けられています。よくある誤解として、「部署配置転換をさせれば抵触日がリセットされる」といった認識がありますが、これは誤りです。
抵触日のリセットには、以下のような実質的な変更が必要です。
- 組織単位の変更(課など)
- 指揮命令者の変更
- 業務内容の大幅な変更
これらが実態として確認されなければ、単なる形式的な配置転換では引き続き同じ組織単位での就業とみなされる可能性があります。その場合、3年の受け入れ期間は通算され、抵触日がリセットされることはありません。
したがって、抵触日との関係で配置転換を検討する場合には、人材派遣会社との綿密な確認と、必要に応じた契約変更が不可欠です。
抵触日の基本的な考え方や仕組みについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>>派遣の抵触日のルールや派遣先企業が行うべき手続きは?図解で分かりやすく解説
5.時給の変動
配置転換によって業務の専門性や責任の程度が変わる場合、時給の見直しが発生することもあります。これは「同一労働同一賃金」の原則に基づいたものであり、2020年の労働者派遣法改正により、職務内容や能力・経験に応じた適正な待遇が義務化されています。
人材派遣会社との間で、職種のレベルや評価基準に基づいたすり合わせを行い、時給や各種手当の調整を適切に行うことが重要です。
派遣社員の配置転換に関するよくある質問
派遣社員の配置転換に関しては、正社員と異なるルールが適用されます。そのため、実務担当者や管理者の間でも誤解が生じやすい領域です。
以下では、現場でよく寄せられる疑問と回答をまとめました。
Q1.派遣社員に配置転換を依頼できますか?
派遣先企業の判断のみで配置転換はできません。
派遣社員の就業条件(業務内容・部署・勤務地・指揮命令者など)は、人材派遣会社との契約(労働者派遣契約書)および派遣社員への就業条件明示書により明確に定められています。
派遣先企業がこれらを一方的に変更することは、労働者派遣法に違反する可能性があります。
ただし、人材派遣会社・派遣社員本人と三者間で合意し、契約変更手続き(再契約や覚書の締結)を行えば、合法的に配置転換を実現することは可能です。配置転換の前には必ず人材派遣会社と協議の上、正式な手続きを取りましょう。
Q2.派遣社員が配置転換を希望した場合は、対応できますか?
対応は可能ですが、本人の希望だけでは配置転換は成立しません。
たとえ派遣社員から配置転換希望があっても、人材派遣会社との合意が必要です。また、業務内容や勤務地が変わる場合は、派遣契約および就業条件明示書の変更手続きが必須となります。
本人の希望に応じる場合も、人材派遣会社を通じて正式な調整を行いましょう。
Q3.配置転換後に業務内容が変わっても問題ありませんか?
契約内容と一致していれば問題ありませんが、契約と異なる場合は留意が必要です。
配置転換後の業務内容が契約書および就業条件明示書に明記されていれば、問題ありません。
ただし、業務内容が文書に記載されておらず、実態と契約に齟齬がある場合は、「個別契約書記載不備」や「偽装請負」と見なされるリスクがあります。
業務変更がある際は、事前に人材派遣会社と協議し、契約内容の見直し・再交付を必ず行ってください。
Q4.配置転換により、派遣社員の時給を変更することは認められますか?
派遣社員の時給の変更には、人材派遣会社を通じた説明と同意が必要です。
業務内容や責任の範囲が異なる部署へ配置転換する場合、派遣料金や時給が見直されることがあります。2020年4月施行の「同一労働同一賃金」対応により、待遇の変更には合理性と本人への説明義務が伴います。
派遣先企業が直接説明するのではなく、人材派遣会社を通じて正当なプロセスを踏んでもらいましょう。
Q5.派遣先企業の都合で配置転換をお願いしたところ、本人に断られました。どうすればいいですか?
派遣先企業には、派遣社員に対する配置転換命令権はありません。本人の同意が得られない場合、強制はできません。
派遣先企業は、派遣社員に対して人事権を持っていないため、配置転換や業務変更を一方的に命じることはできません。
本人が拒否した場合には、人材派遣会社を通じて再度話し合いを行うか、契約終了後に新しい契約内容での派遣を依頼するなど、別の形で対応する必要があります。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
契約と合意をもとに、柔軟かつ適正な対応を
派遣社員の配置転換は、派遣法と契約に基づいて慎重に行う必要があります。現場の急な要望に応えたい気持ちはあっても、契約外の対応はリスクを伴います。
ポイントは「三者合意」と「契約の更新」です。これらを丁寧に進めることで、柔軟かつ合法的な人員配置が実現します。人材派遣会社との信頼関係を築きながら、派遣社員の理解も得て、よりよい職場環境を構築していきましょう。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする