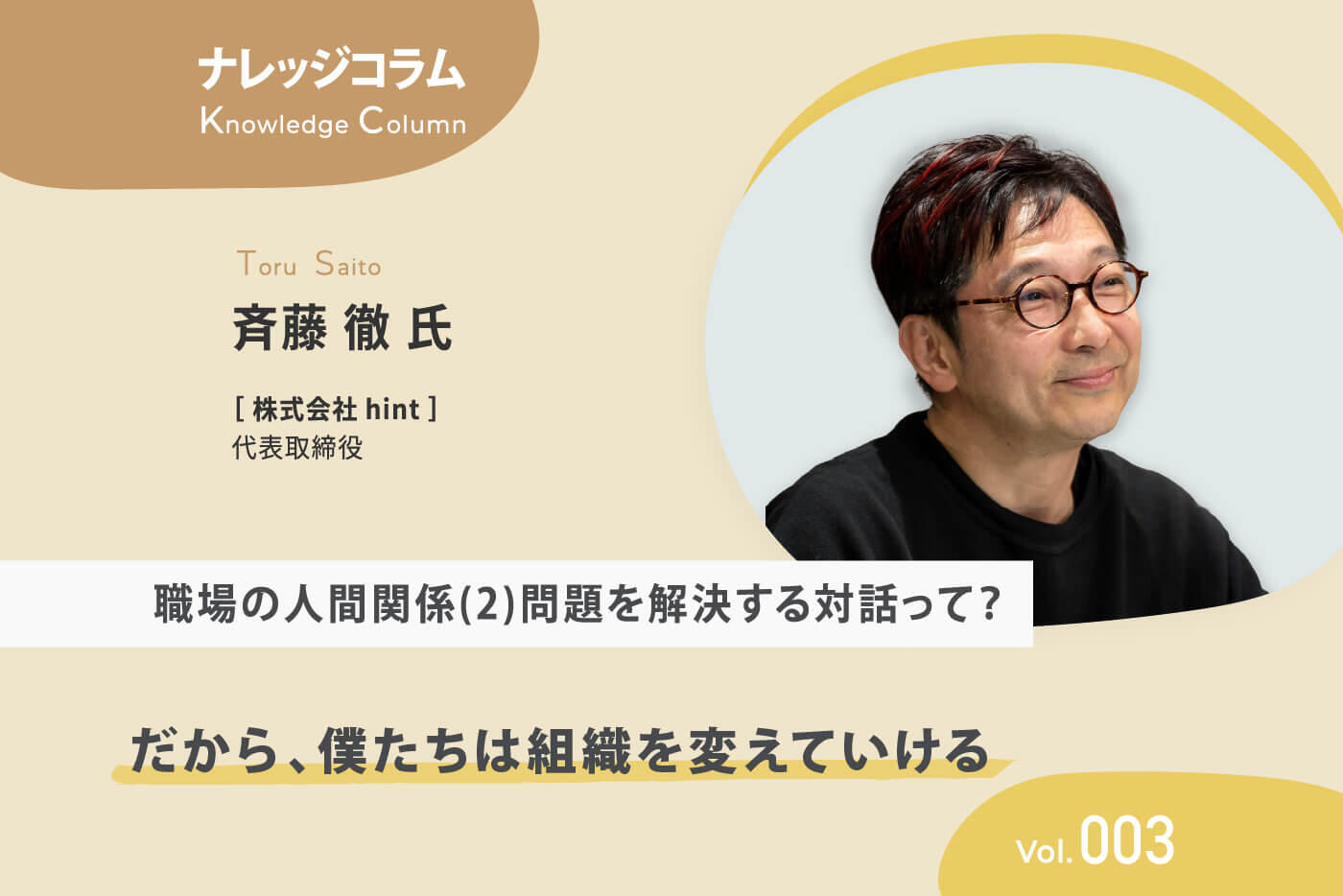HRナレッジライン
カテゴリ一覧
“チームで成果を出す”プレイングマネージャー術
公開日:2025.09.30
- 記事をシェアする
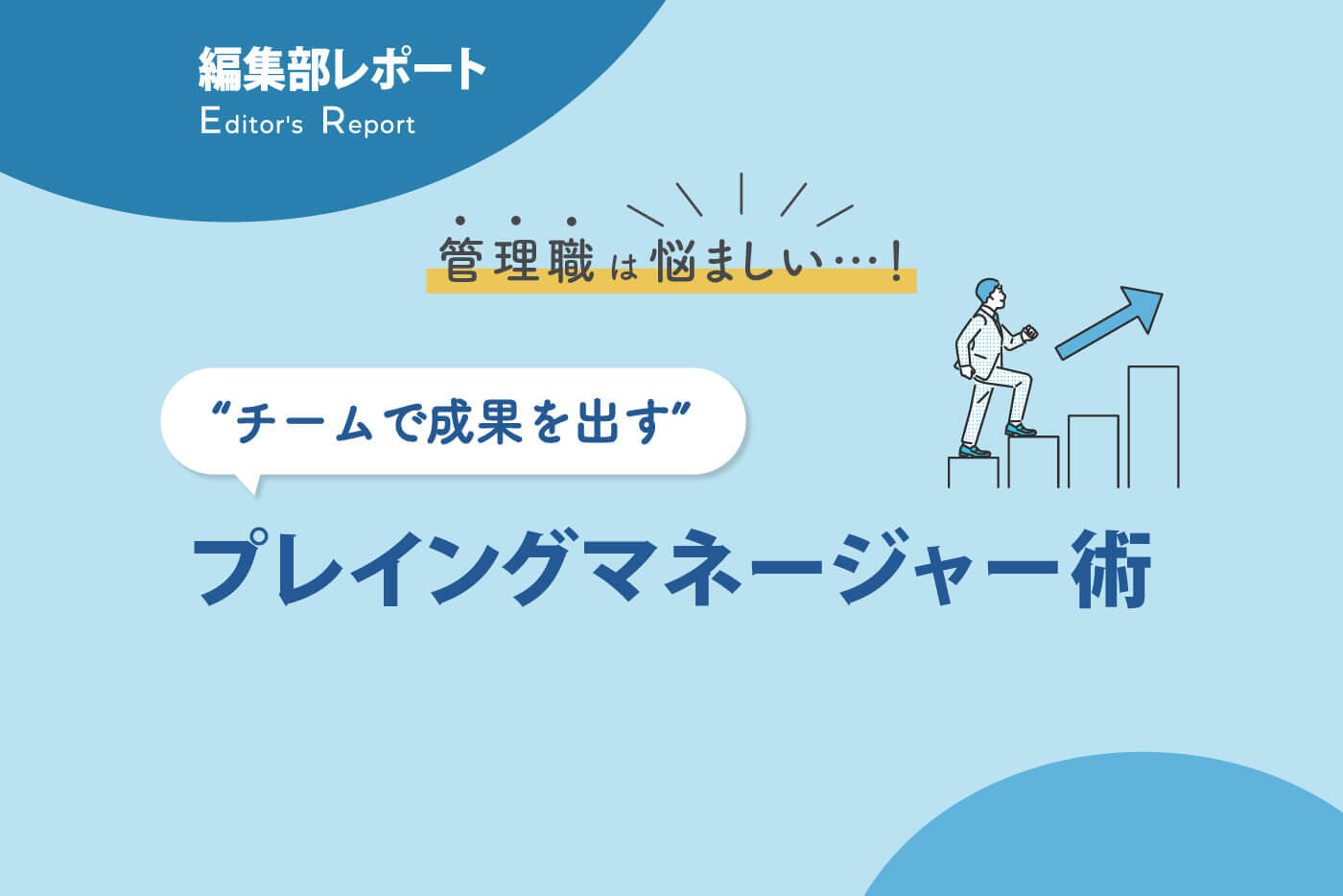
HRナレッジライン編集部が、管理職の皆さんのお悩みについて一緒に考える「管理職は悩ましい」シリーズ。今回のテーマは「プレイングマネージャー」です。
企業の中で、プレイングマネージャーは“現場のエース”でありながら“チームのまとめ役”もこなす、まさに二刀流の存在で重要なポジションです。でも、実際には「忙しすぎてチーム運営まで手が回らない」という声も少なくありません。プレイヤーとして成果を出しながら、マネージャー、管理職としてチームを導く・・・その両立は簡単ではありません。チーム全員で成果を出すために、どうしたらよいのか。プレイングマネージャーが陥りがちな落とし穴と、チーム運営で成功するための考え方・実践方法を深堀りします。
目次
プレイングマネージャーがチーム運営で失敗する理由とは
現場とマネジメント、両方を担う“二刀流”のリーダー
プレイングマネージャーは、現場の最前線でプレイヤーとして活躍しながら、チームの成果や成長にも責任を持つポジションです。バブル崩壊後の人件費削減を背景に、マネジメント専任のポストが減少し、現場とマネジメントを兼任するスタイルが定着しました。
このポジションの魅力は、現場との距離が近く、リアルな情報をもとに判断や指導ができること。部下との信頼関係も築きやすく、組織の生産性向上にも貢献できます。
プレイングマネージャーの強みとよくある落とし穴
プレイングマネージャーの強みとしては以下のようなものがあげられます。
- 現場のリアルな情報をキャッチできる
- 部下の仕事を深く理解できる
- プレイヤーとしての姿勢が信頼につながる
- 現場を知ることで生産性の高い組織づくりに貢献できる
しかし、強みがある一方で、よくある落とし穴があります。それは「全部自分でやってしまう」問題、です。
優秀なプレイヤーほど、「自分でやった方が早い」「任せるより自分でやる方が安心」と思いがちです。しかし、その結果、以下のような状態に陥ってしまいます。
- 部下が育たない
- チームが“自分中心”になってしまう
- マネジメントの時間が取れない
- 長時間労働で余裕がなくなる
- ストレスが溜まり、強権的になってしまう
こうした状況が続くとチームの成長も止まり、自身も疲弊してしまいます。
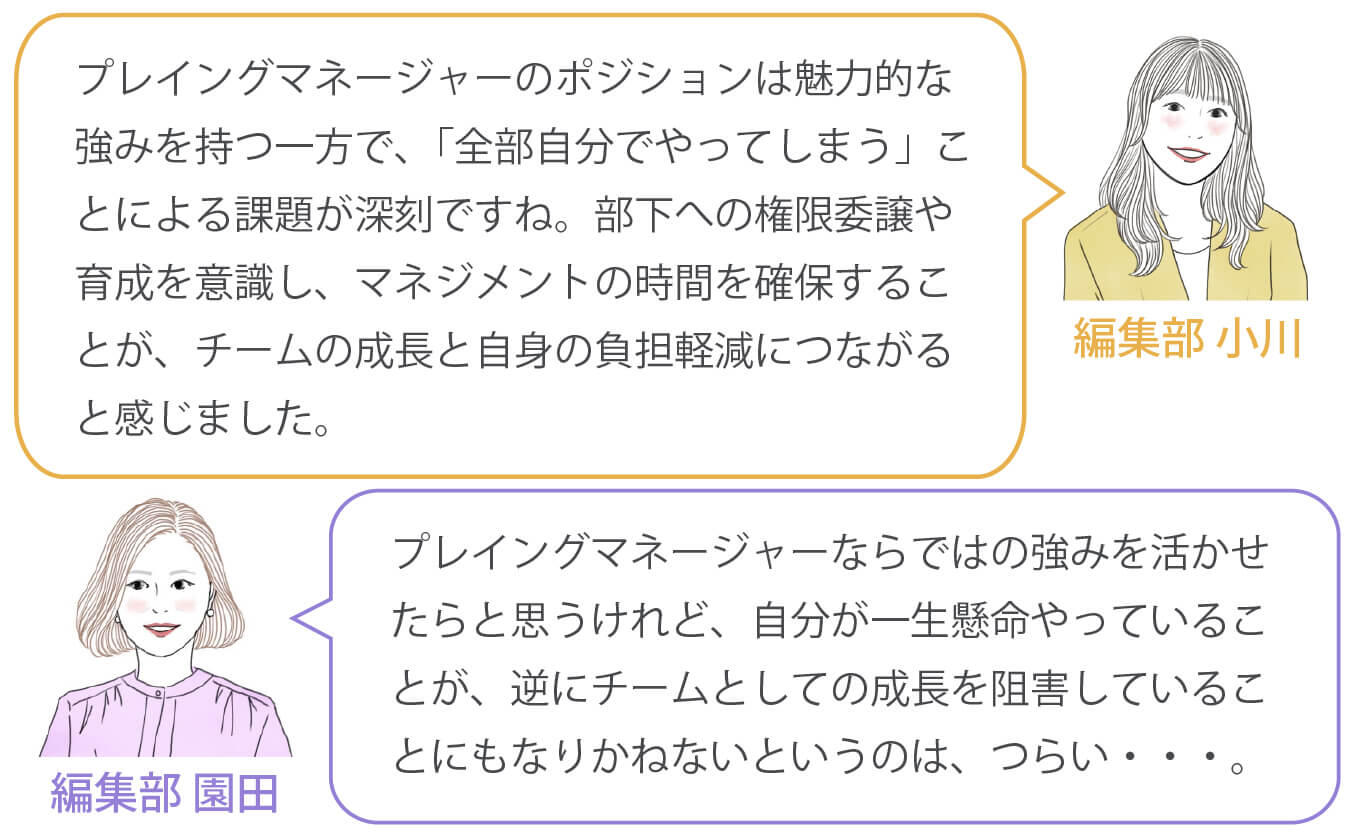
自身の業務とチーム運営のバランス
この主な原因は、自身の業務とチーム運営をバランスよくこなせないことにあります。特にこれまで現場でプレイヤーとして優秀だった人ほど、部下に頼らず自分の力でなんとかしようとしがちです。
結果、部下を育てられずに自分中心のチーム運営から脱却できなくなり、失敗してしまうのです。そうならないためには、早期に部下に力をつけさせて、チーム全員で成果を出せるようにしなければなりません。目指すべきは、マネージャーがいなくても、メンバーが自主的に動いて成果が出せるチームになることです。
チーム運営で成功するためのコツ
チーム運営で成功するための7つの心得
プレイングマネージャーとして目指すべきは、自分がいなくても回るチームをつくること。そのために大事なチーム運営で成功するための7つの心得をご紹介します。
| 心得 | 内容 |
|---|---|
| 「自分でやってしまいたい」を捨てる | 実績のある人ほど自分でやってしまおうとする。意識を変えるために、部下の力を借りると決めてしまう。 |
| 致命的なミス以外はかすり傷と考え、部下に仕事を任す | 部下のスキルアップを待てないため、「部下の仕事にミスは付きもの」とし、失敗への許容度を高めておく。致命的なミス以外は挽回可能と考え、対処法を考えておく。ミスの多い部下には「細かく伝える」「不安、不明点がないかを聞く」「復唱してもらう」のステップで任せる。 |
| 今ではなく1年後に視点を置き、部下を育てる | 目先しか考えないと自分でやってしまうため、1年後に視点を置き、部下に仕事を任せて育てる。手間はかかるが、その苦しみも最初だけと割り切る。 |
| 自分が会議や打ち合わせに出席しない回をつくり、部下の自主性を養う | 「会議や打ち合わせには全員必ず出席するもの」という常識をなくし、部下に任せるようにしてみる。それにより部下は「任されている」という自覚が持て、大きく成長できる。 |
| ナンバー2の参謀を置き、自分がいなくても勝手に動く「自主運営のチーム」をつくる | 自分一人でまとめようとせず、チーム内にナンバー2の参謀を育てて、自分とメンバーが連動するための要になってもらう。そして、メンバーたちは任された仕事はある程度自分たちで解決できる自主運営の状態をつくる。 |
| 現場でトライアルを繰り返し、イノベーションを起こす | プレイングマネージャーの利点は「常に現場にいる」「アイデアを実践できる」こと。顧客に不満・不安・不便があれば、すぐに対策を講じてトライアルを行う。その繰り返しでイノベーションを起こす。 |
※伊庭正康『メンバーが勝手に動く最高のチームをつくる プレイングマネージャーの基本』かんき出版を参考に作成
大事なことは、部下を信じて任せること。そして、チームの自走力を高める仕組みづくりです。
プレイングマネージャーは現場に近いため、部下に仕事を割り振って、後でフォローしたり、業務のトライアルを行いやすい利点があります。こまめなトライアンドエラーでよりよい手法を見出し、仕事を任せることで部下を育て、自分がいなくても回るチーム運営を目指しましょう。
チームにまとまりが生まれる仕組みをつくる
自分がいなくても回るチームをつくるには、個々のメンバーが互いの存在を認識し、互いに「常に見守られている」と思える仕組みづくりが必要になります。チーム内でリードする人とリードされる人をつくらないためにも、メンバー個々に役割を与えることが重要です。例えば、チーム内の広報や勉強会担当、同業他社の調査係、顧客の声を反映したツール作成など、日々活動ができて意味のある役割を与えます。また、互いに成果を認め、感謝される場をつくることも大事です。マネージャー、同僚、顧客から感謝される機会を意識的につくることが、個々のやる気や満足度を上げることにつながります。
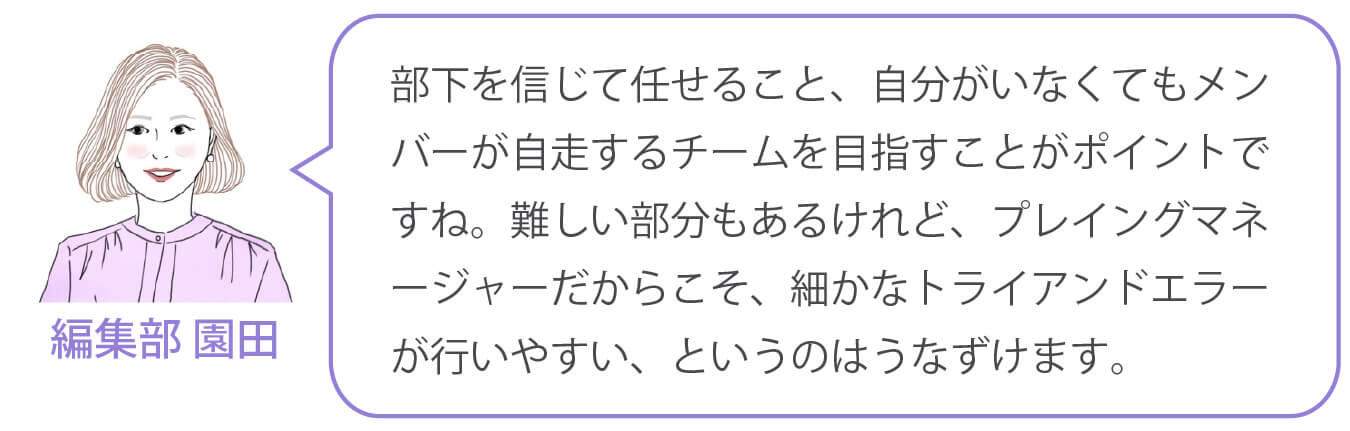
忙しさから抜け出すには「ムダを省く」ことも大事
業務の棚卸しと作業効率化の見直し
部下に仕事を任せる前に、業務の棚卸しをしてみましょう。マネージャーの仕事を部下に割り振るといっても、仕事が忙しいのは部下も同じです。仕事の絶対量を減らさなければスムーズな仕事の移行はできません。また、仕事の質や生産性を向上させる意味でもムダを省くことは必要です。
また、ITツールなどテクノロジーの活用や人員配置の見直しもポイントです。こういったことで作業を効率化できれば負担は軽減し、組織の業務全体の業務効率化にもつながります。育成と並行して業務の最適化を実施しましょう。
仕事のムダを省く改善の4ステップを活用する
仕事のムダを省くには改善の4ステップ「ECRS」で考えることが効果的です。ECRSのステップは改善の効果が大きく、効率を逸するようなアンバランスな改善が避けられ、不要なトラブルも少ないといわれています。顧客満足や効率性、コンプライアンス、メンバーの意向や意欲などに照らし合わせながら、仕事にムダがないかを点検してみましょう。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. E (Eliminate:排除) | なくせる仕事はないか? |
| 2. C (Combine:結合・分離) | まとめられる業務は? |
| 3. R (Rearrange:入替え・代替) | 順番や方法を変えられないか? |
| 4. S (Simplify:簡素化) | もっとシンプルにできないか? |
プレイングマネージャーの強みを活かそう
現場にいるからこそ、部下の気持ちがわかる。現場にいるからこそ、すぐにトライアルができる。現場は常に変動するからこそ、その場で部下と共に活動することに意味があります。部下を信じて仕事を割り振りつつ、自分は考える余裕を持って、常に次の一手を打てる態勢をつくること。そんなプレイングマネージャーの強みを活かして、「考える余裕」と「任せる勇気」を持つことが、チーム運営の成功につながります。
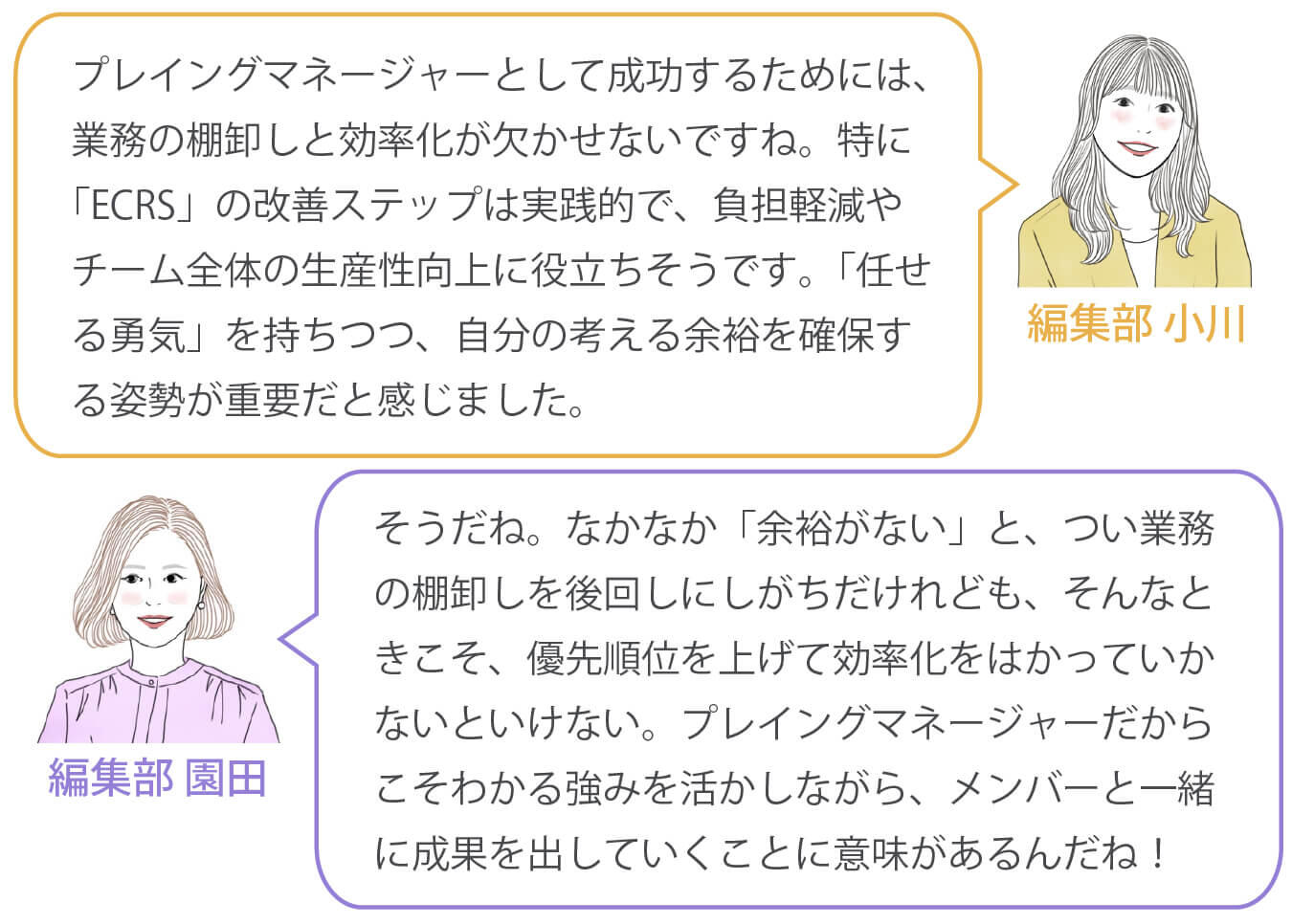
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
【出典・引用】
『メンバーが勝手に動く最高のチームをつくる プレイングマネージャーの基本』伊庭正康
「管理職は悩ましい」シリーズのバックナンバーはこちら!
>>「部下育成」はどうしたらうまくいく?
>>なぜ伝わらない?タイプ別に攻略!「部下とのコミュニケーション」
>>社内チャットのコミュニケーションとは?部下が戸惑うチャット例をご紹介
>>「分かり合えない」を乗り越えよう!アサーティブコミュニケーションで信頼を築く
>>職場の信頼関係、半数は部下の片思い?「信頼関係のメカニズム」
>>定着と戦力化を図るオンボーディング
- 記事をシェアする