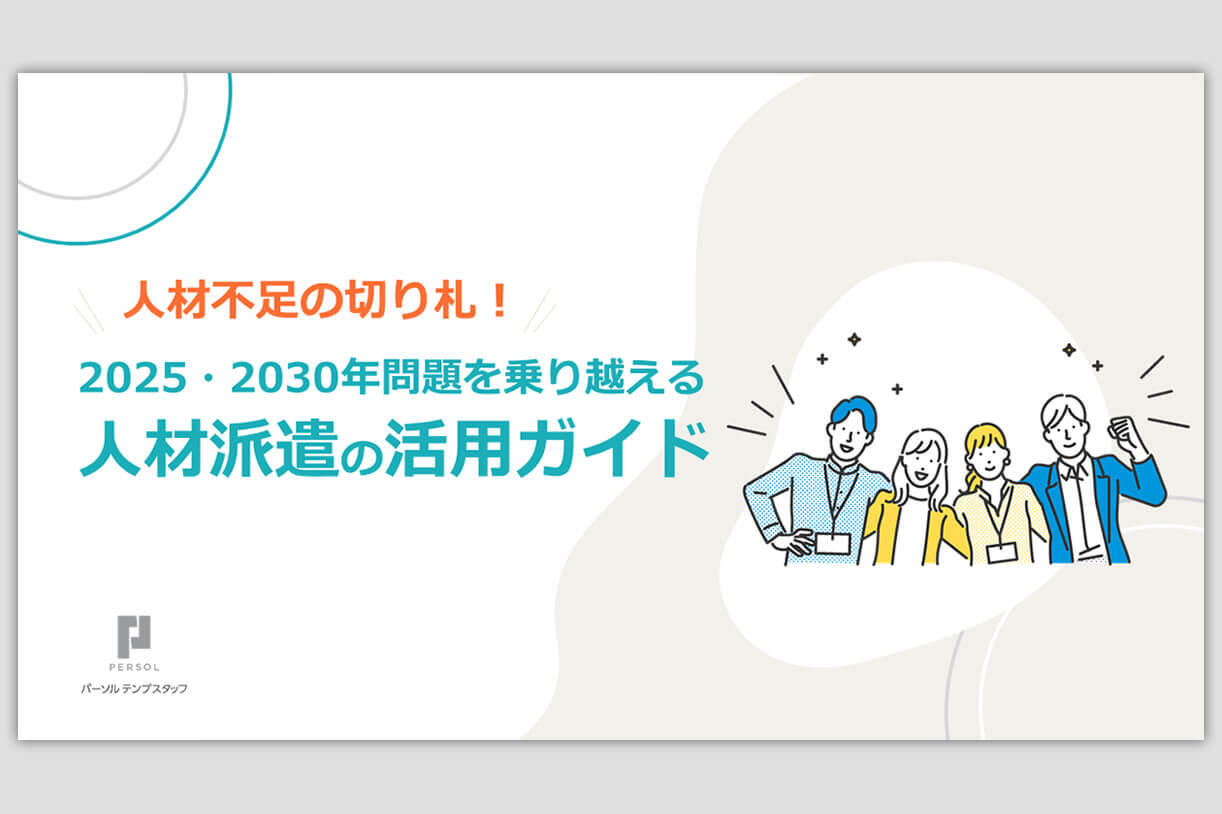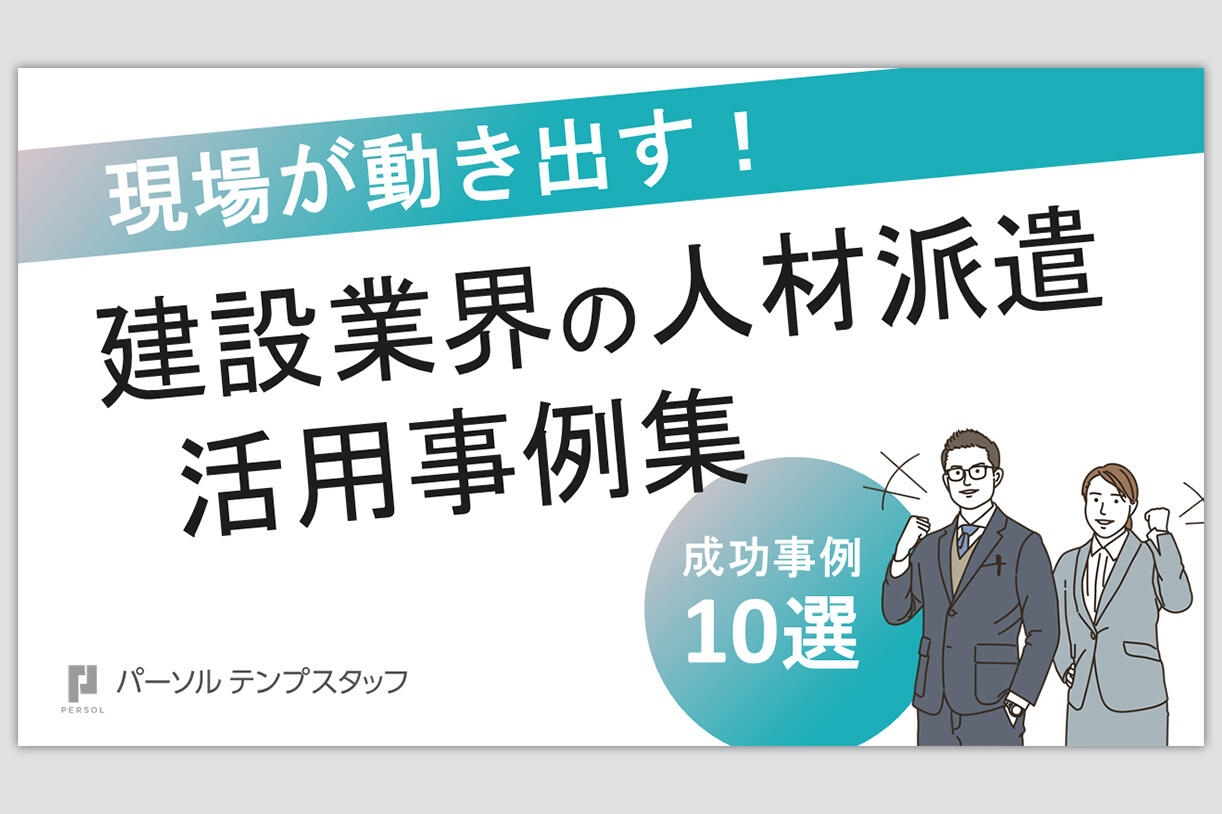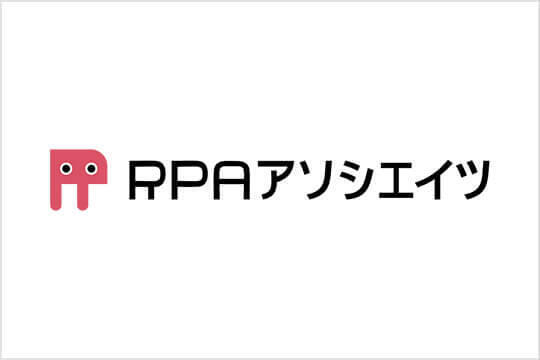HRナレッジライン
カテゴリ一覧
2030年問題とは?企業に与える影響や取るべき対策をご紹介
- 記事をシェアする

世界各国で高齢化が大きな社会問題の一つとなっています。医療技術の発達による平均寿命の延びが大きな理由ですが、特に日本では少子化も相まって、世界で最も高い高齢化率となっています。
今後、高齢化に他の社会問題が複雑に絡み合うことで、企業の経営に大きな影響を与えるとされるタイミングがありますが、その一つが2030年問題です。
この記事では、2030年問題が企業の経営に与える影響や、その対策を解説します。また、特にインパクトの大きいとされる業界もご紹介します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
2030年問題とは

※引用:内閣府|「令和7年版高齢社会白書」
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、2030年には日本の人口に占める65歳以上の割合が3割を超えると推計されており、超高齢社会が一段と進展すると考えられています。
その主な要因は、高齢者の増加と出生数の減少です。高齢者は増え続ける一方、生まれる子どもの数は減っているため、世界にも例を見ない急激なスピードで少子高齢化が進んでいます。
特に、生産と消費活動の中核を担い、高齢者の生活を支える生産年齢人口(15~64歳)の減少は、あらゆる業界での人材不足、さまざまなサービスの水準低下、社会保障制度の破綻などを招きます。これらの諸問題をまとめて、2030年問題と呼びます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
2030年問題が企業に与える影響
2030年問題は企業にどのような影響を与えるのでしょうか。考えられる4つの具体的な影響を解説します。
人材不足の深刻化
労働力が社会全体で減少すると、これまで維持されてきた社会インフラやサービス水準が受けられなくなります。
例えば、高齢者の増加により医師や看護師、介護士の数が足りず、介護事業の維持が困難になります。また身近なところでは、ネットショッピングで購入した商品が届くのが遅くなる、コンビニの24時間営業がなくなる、バスの本数が減るといった事態が想定されます。
商品の品質は優れており、市場のニーズも高いにもかかわらず、人材不足が原因で倒産する事例も発生しています。実際、東京商工リサーチの調査によれば、人材不足による倒産は増加を続けており、2025年には、2013年の調査開始以来、はじめて年間300社を超えました。
※参考:東京商工リサーチ「1-10月の「人手不足」倒産323件、年間最多を更新 労働集約型で倒産が急増、「従業員退職」が1.5倍増」
人手不足倒産については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>人手不足倒産とは?深刻化の原因と解決策を詳しく解説
採用難易度の高まり
人材不足により、今後は採用競争の激化が予想されます。適切なスキルと経験を持つ求職者が限られ、企業が求める要件にマッチする人材の採用の難易度が高まることから、採用を成功させるための工夫がより一層必要となるでしょう。
組織の力強い成長を支えるためにも、採用は非常に重要です。HRナレッジラインでは、採用活動を成功させるポイント、年齢や性別にかかわらずそれぞれの企業にマッチした採用方法など、幅広い視点で解説しています。自社に合った人材活用の参考にしてください。
採用については、こちらの記事もあわせてお読みください。
>>中小企業が採用を成功させる6つのポイントを徹底解説
>>シニア採用が必要とされる背景、メリットと留意点についてご紹介
>>若手採用を成功させるポイントとは?採用方法や若手採用のメリットを解説
人件費の増加
人材を確保・維持するため、これまでより高い給与や福利厚生を提供する必要も発生します。自社に入社してもらうために、また自社ではたらき続けてもらうために、人件費増加は必須といえるでしょう。人件費の増加が避けられない中、できる限り経営コストを抑えるための対策も必要です。
人件費削減については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>人件費削減とは?メリット・留意点や具体的な方法を解説!
社会保障制度のバランスが崩れる可能性
社会保障は現役世代が高齢者を支える仕組み(賦課方式)で成り立っており、支える側(現役世代)が減り、支えられる側(高齢者)が増えると、制度のバランスが崩れる恐れがあります。
国の社会保障費の大きなウエートを占める年金、医療、介護のサービスの恩恵を受けるのは高齢者ですが、現状の仕組みを維持すれば、現役世代1人あたりの負担は増加し続けます。
国立社会保障・人口問題研究所の2021年の出生動向調査によると、理想の数の子どもを持たない理由を夫婦に尋ねたアンケートで最も多かった回答は、経済的理由でした。その原因の一端は、税や社会保険料の負担にあると考えられます。高齢化が少子化を加速させ、社会保障制度の持続が困難になる悪循環に陥っていると考えられます。
- ※出典:厚生労働省「給付と負担について」
- ※出典:国立社会保障・人口問題研究所「第Ⅱ部 夫婦調査の結果」
2030年問題で影響を受けると予想される業界
続いて、2030年問題で特に影響を受けると予想される6つの業界をご紹介します。
物流・運輸業
物流・運輸業では、ECサイトの普及に伴って仕事の量が増え続ける一方で、すでに深刻な人材難となっています。
新型コロナウイルス感染症が流行した2020年、運送業者が取り扱う宅配便の個数は前年を大きく上回りました。巣ごもり需要でECサイトの利用者が増え、日用品だけでなく、食材や薬など、インターネットで購入できる商品の選択肢も増えました。コロナ終息以降も市場規模は拡大し続けており、今後もECサイトの利用による物流量は増加を続けるでしょう。
しかし、物流を支える業界では、担い手の高齢化、若い世代の業界離れなどを背景とした深刻なドライバー不足に直面しています。効果的な対策を施さなければ、2030年度には輸送能力が34%(9億トン)不足すると予測されています。
今後、労働者の給与や待遇の改善が進まなければ、サプライチェーンが停滞し、ECサイトの当日配送や翌日配送などのサービスが受けられなくなったり、製造業や小売店の事業活動に影響が出たりすることは避けられません。
※出典:厚生労働省「物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題」
サービス業
ここでいうサービス業とは、飲食サービス業などに分類されない、廃棄物や自動車整備などを扱う業種のことです。
サービス業は離職率の高さが人材不足の主な原因といえます。2025年に厚生労働省が公表した「令和6年 雇用動向調査結果の概要」によると、サービス業(他に分類されないもの)は19.0%で、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業などを抑え、全体の約2倍と高い水準を示しています。

離職率が高い要因の一つに、非正規労働の多さが考えられます。正社員以外の契約社員やパートなどで雇用されている人の比率が男女共に全産業平均よりも高く、退職理由も契約満了を原因としたものが多くなっています。
こうした不安定な立場での雇用に加え、長時間労働や休日、深夜勤務など、ワーク・ライフ・バランスを実現しづらい労働環境が、離職率の高さにつながっていると考えられます。
医療・介護業界
医療、介護業界は、需要と供給のバランスが崩れていることから人材不足となっています。2030年には人口の3分の1が高齢者になるとされており、これまで以上に医療や介護サービスの必要性が増すと考えられています。
2018年10月23日に公表された、パーソル総合研究所と中央大学の共同研究による「労働市場の未来推計2030」では、2030年には医療・福祉業界は187万人の人材が不足すると考えられています。
医師や看護師、介護福祉士など、医療や介護従事者が不足すれば、病院で診てもらえない、入所できる介護施設が見つからない、などといった医療難民、介護難民が発生することは否定できません。さらには、少ないリソースで患者や利用者を支えようと長時間労働をしたり、深夜勤務が続いたりすることも考えられます。そうした状況が続けば、現場が疲弊し、離職者の増加につながるでしょう。
宿泊・飲食サービス業界
宿泊業と飲食サービス業は、離職率の高さが人材不足の原因となっています。離職率が高い理由としては以下のような要因が考えられます。
- 土日祝に営業している店舗が多い
- 深夜や盆正月に営業している店舗もある
- 長期的に連続した休暇を取ることが難しい職種も多い
家族や友人との休日や長期休暇が合わせづらい職場であることから、宿泊業と飲食サービス業を敬遠する求職者は多いと考えられます。近年ではカスタマーハラスメントの問題も人材不足の一因となっています。
人材の不足はサービスの品質低下につながり、顧客離れを起こす恐れがあります。その解決策として自動化システムや配膳ロボなどを導入する方法もありますが、大きな設備投資をしづらい企業ではどうしても人に頼る部分が大きくなり、サービスを維持するための人材の維持は不可欠です。
しかし、人材獲得のためには給与水準を上げざるを得ず、人件費が高騰して価格転嫁を進めるなどしなければ、経営に大きな影響があるでしょう。
飲食業界の人材不足については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>飲食業界の人手不足の現状と背景、解決策をご紹介
建設業界
建設業も、物流業界同様、労働者の高齢化と若者の不足が課題となっている業界です。
現場で作業を行う建設技能者は、1997年の455万人をピークに、2024年は300万人にまで減少しました。60歳以上が25.8%と全体の4分の1以上を占め、10年後には技能者の高齢化によって、大量離職が懸念されています。一方、29歳以下は11.7%で、次世代への技術承継が課題となっています。
建設業界は他の産業に比べて労働時間が長く、休日も少ない上、賃金も低い実態があります。国を挙げて処遇改善に取り組んでいるものの、このまま人材不足が続けば、私たちの生活も影響を受ける可能性があります。道路や橋、トンネル、水道管など、建設から数十年が経過して老朽化しているにもかかわらず、補修や点検作業を行う技術者や作業者が不足すれば、インフラの維持は困難となり、道路の陥没や水道管の破裂などが全国各地で頻発したり、災害からの復旧が迅速に行われなかったりする状況になりかねません。
また、人材確保のために人件費が高騰すれば、一般住宅や商業ビルなどの建設にかかるコストも大きくなります。その結果、当初の見積もりよりも建設費が膨らむこと、そもそも作業者が確保できずに工期が長期化することなどが懸念されます。
※出典:国土交通省「最近の建設産業行政について」
IT・情報通信業界
経済産業省が2019年に公表したIT人材需給に関する調査によると、2030年にはIT人材が最大で79万人不足するとされています。
IT人材が不足すると、市民生活に大きな影響を及ぼします。企業が人材不足対策でデジタル技術を用いた自動化やシステム化を進めようとしても、それを推進できるエンジニアがいないため、社会全体の生産性が上がりません。新規事業や新商品開発に取り組むリソースも確保できず、経済成長が期待しづらくなるでしょう。
また、行政や民間の既存のシステム(レガシーシステム)を維持・管理・更新するエンジニアが現場を離れれば、社会インフラを支えるようなシステムですら維持できなくなるリスクが高まります。
さらに、サーバーセキュリティを担える人材がいなければ、システムの脆弱性をついてサイバー攻撃を受けて社会が大混乱に陥ったり、企業の製品が出荷できなくなったりと、さまざまな分野に影響がおよびます。
※出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」
2030年問題に向けて企業が取り組むべき対策
では、2030年問題に向けて企業が取り組むべき対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
はたらきやすい環境づくり
まずは、自社のはたらく環境について見直します。はたらきにくい、不満が生まれやすいなどの環境になっていないかを再確認し、人材の流出を防ぎましょう。
同時に、採用の際に自社を選んでもらうために、リモートワークの環境整備や福利厚生の充実、休暇や休業の取得の推進などに取り組みましょう。
シニア人材の活用
人材不足を解消する大きなカギを握るのは、シニア人材の活用です。経験豊富で実績のあるシニア人材を採用できれば、企業にとっても大きなメリットとなります。シニア人材も、年金の支給年齢が引き上げられた背景などから、まだはたらきたいと考えている人は多いようです。
シニア採用については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>シニア採用が必要とされる背景、メリットと留意点についてご紹介
外国人人材の活用
外国人人材の活用を検討するのも一つの方法です。海外に拠点を持つ企業やこれから海外展開を検討する企業にとっては有効な選択肢となります。外国人の採用や育成のノウハウがなく、自社での採用が難しい場合には、人材派遣を活用することも解決策となるでしょう。
パーソルテンプスタッフでは、外国人の人材派遣・人材紹介を行っています。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
▼外国人の人材派遣・人材紹介

英語・中国語・韓国語をはじめさまざまな言語をネイティブとするさまざまなニーズにお応えできる外国人にご登録いただいています
リスキリングの実施
部署や職種によって人材不足の深刻さに差がある場合、リスキリングを実施しましょう。
リスキリングを実施すれば、将来の事業戦略に必要なスキルを持つ人材や、社内で不足しているスキルを持つ人材を増やすことにつながります。その結果、人材不足が深刻な部署に適材適所で人材を配置できるようになります。
IT技術の活用
人材の確保が難しい場合は、IT技術の活用も検討します。RPAやデジタルツールを新たに導入すると、これまで人材が必要だった業務が自動化できたり、スタッフがコア業務に集中できるようになったりして、人材不足の解消につながることが期待できます。
パーソルテンプスタッフでは、RPAに関連するサポートも行っています。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
外部企業の活用
自社で施策を行っても人材不足が解消できない場合は、外部企業の支援を受けるのも一つの方法です。 ここでは、人材不足解消につながる4つのサービスをご紹介します。
- 人材派遣
- 紹介予定派遣
- 人材紹介
- アウトソーシング
【人材派遣】必要な時に必要なスキルを持った人材を活用する
人材派遣では、必要なときに必要なスキルを持つ人材を受け入れることができます。
人材派遣を活用すれば、人材確保のコストや工数を軽減できる上、自社で雇用しないため労務管理の負担などもありません。繁忙期に人員補充したい、急な退職や育児休業の社員の代替が必要、などのシーンで有効に活用できます。
▼人材派遣サービス

テンプスタッフの人材派遣|必要な時に、必要なスキルを持つ人材を必要な期間活用
【紹介予定派遣】派遣期間を経て直接雇用に切り替える
紹介予定派遣は、直接雇用を見据えて一定期間(最長6ヶ月)派遣社員として受け入れ、派遣期間終了後に直接雇用に切り替えることができます。
派遣期間中に能力・適性を見極めることができ、書類選考や面接も可能なため、採用時のミスマッチを防ぎ、早期離職の抑制につながります。
▼紹介予定派遣サービス

テンプスタッフの紹介予定派遣|ご利用の流れ・人材派遣との違い
【人材紹介】採用業務の負荷軽減は人材紹介を活用する
人材紹介は、企業に求職者を紹介し、採用業務を支援するサービスです。求人票の作成支援から求職者情報の整理、条件交渉などを代行してくれます。採用業務の負担を軽減しながら直接雇用できる人材を探す場合にぴったりです。
▼人材紹介サービス

テンプスタッフの人材紹介|募集要件に適した人材を効率的に採用
【アウトソーシング】自社業務の一部を外部に委託する
アウトソーシングとは、自社の業務の一部を外部に委託することです。事務業務を委託するBPOや情報システム業務を委託するITOなど、いくつか種類があります。
業務の一部を外部の専門企業に委託することで、経営資源の選択と集中、外部企業の知見やノウハウを活かした品質向上を図るなどのメリットが得られます。
社内体制が整っていない企業や、人材の採用・管理の手間を抑えたい企業に適しています。
▼アウトソーシングサービス

テンプスタッフのアウトソーシング|総務・経理業務やコールセンター、物流まで幅広く対応
2030年問題以外の「年問題」について
ここまで、2030年問題とその原因、対策について解説してきましたが、2030年を乗り切れば安心という訳ではありません。高齢化や生産年齢人口の減少による問題は他にもあります。
2025年問題
第1次ベビーブーム(1947~1949年)に生まれた団塊の世代(約800万人)が全員75歳以上の後期高齢者となる2025年は、医療・介護ニーズが増加してリソースがひっ迫すると指摘され、2025年問題と呼ばれてきました。
また、老朽化・複雑化・ブラックボックス化した企業のレガシーシステムがDX推進の足かせとなり、企業の成長に悪影響を与えるとして、「2025年の崖」という言葉も広がりました。レガシーシステムの維持管理には多額の費用がかかる上、自社のデータを有効活用できずに市場での競争に敗れ、社会全体で巨額の経済損失が発生する恐れがあると指摘されていました。
現場の努力もあり、2025年時点ではそうした大きな混乱は発生していません。しかし、2025年が過ぎたから安心するのではなく、2025年以降も引き続き懸念される問題であるという考え方が必要です。
2025年問題については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>危惧されている2025年問題の概要と企業が取り組むべきこととは
2040年問題
2030年問題の次には、2040年問題もあります。2040年問題とは、1971年~1974年の第2次ベビーブームに生まれた団塊ジュニア世代が65歳以上となることで生産年齢人口の割合が減り、財源の不足やインフラの老朽化、人材不足が起こる問題です。
内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」によると、2040年には2030年よりも高齢者の割合が増加し、人口の34.8%となることが予測されています。これは、約1.6人で1人の高齢者を支える計算となります。
2030年問題よりも一層はたらく人の割合が減ることで、税収や社会保険料収入も減り、財源の不足はもちろん、インフラの老朽化や人材不足など、問題がより深刻になると予測されています。
2054年問題
2054年問題とは、生産年齢人口が減少する反面、75歳以上の人口が2054年まで増え続けるという問題です。かつては2054年問題として知られていましたが、最新の調査結果では、2055年にピークに達する見込みです。
いずれにせよ、日本は4人に1人が75歳以上という超々高齢社会を迎えるのは確実です。国立社会保障・人口問題研究所が2023年に公表した「日本の将来推計人口」によると、2056年には日本の人口が1億人を下回り9,965万人となり、2070年にはさらに減少し8,700万人になると推計されています。また、65歳以上の人口が2070年では約38%になると予測されています。
はたらくことを選択する高齢者も増えており、時代に合わせて高齢者の定義が変わっていくことも考えられるでしょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
2030年問題に備え、前もって対策を打つ
2030年問題は、2030年のみに起こる問題ではありません。すでに高齢化は進んでおり、2030年以降も、2040年問題、2054年問題と、高齢化が企業経営に与える影響は拡大し続けるため、企業は人材不足やニーズの変化に対応し続けなければなりません。
問題が起きてから対処するのではなく、早めに手を打つことで、影響を最小限に抑えましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする