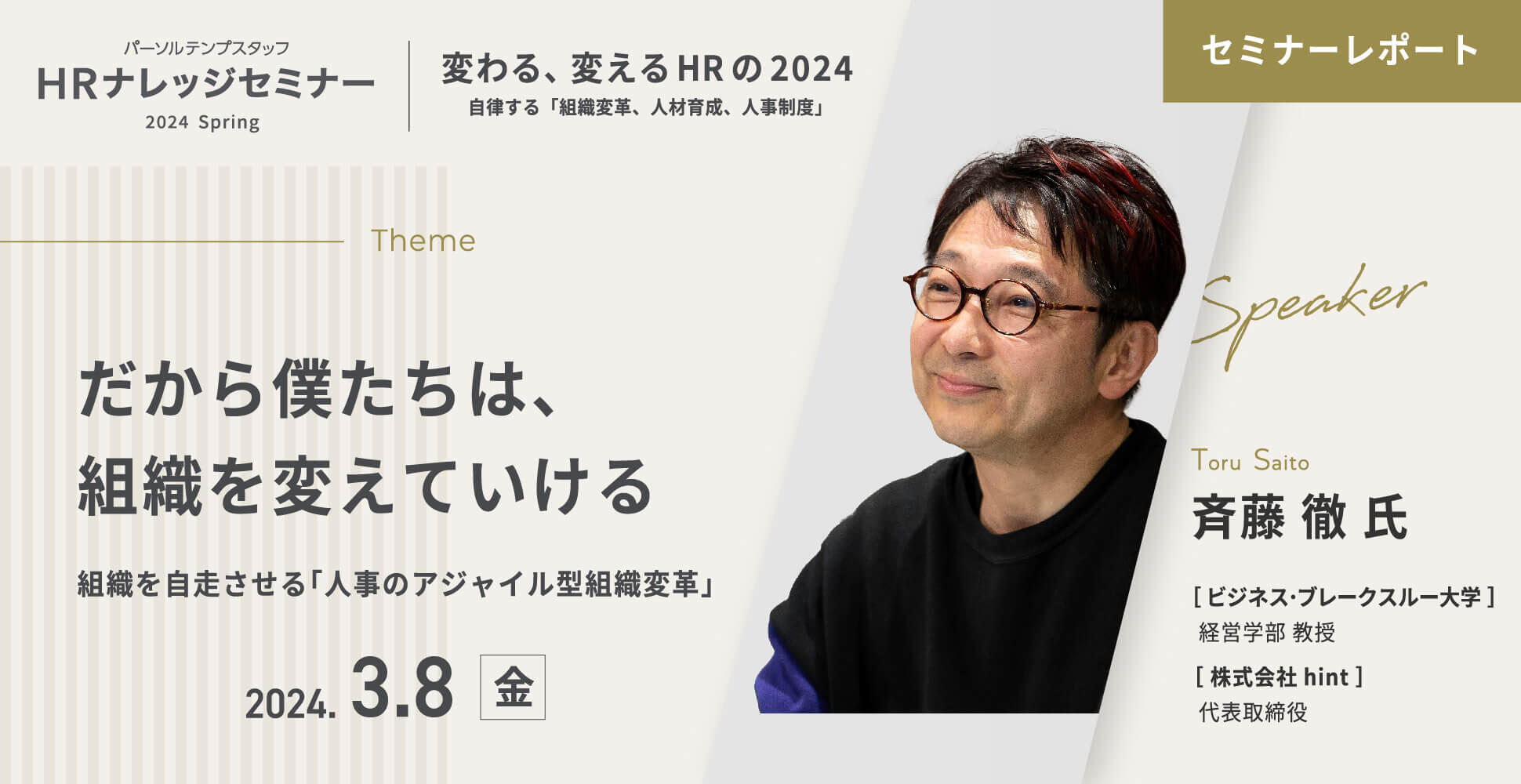HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジコラム】
人事制度の真実 vol.006
自社の人事制度2.0へ ~BANI時代の人事制度~
公開日:2025.03.13
- 記事をシェアする
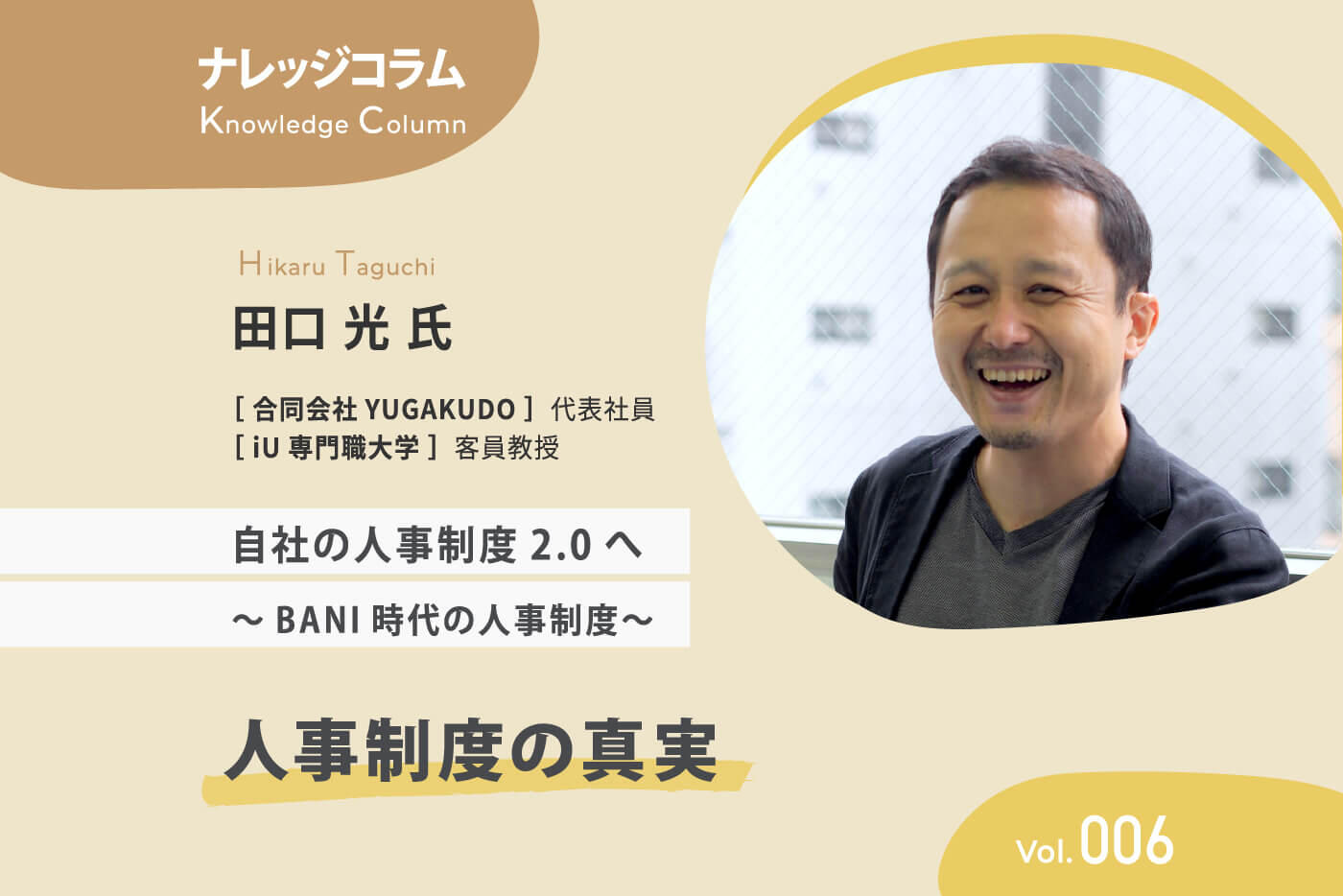
合同会社YUGAKUDO 代表社員
iU専門職大学 客員教授
田口 光 氏
HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。合同会社YUGAKUDO 代表、iU専門職大学 客員教授の田口 光氏による「人事制度の真実」の第4回は「報酬の真実」。
人事制度の中核となる「報酬」について、金銭報酬だけでなく、非金銭報酬や内発的報酬も含めた「トータルリワード」の視点から探求します。
▼コラムスピンオフセミナーはこちら
▼バックナンバーはこちら
vol.001:人事制度の誤解と真実の目的
vol.002:目標の真実
vol.003:考課・評価の真実
vol.004:報酬の真実
vol.005:策定と運用の真実
前回「策定と運用の真実」のおさらい
前回は、人事制度を策定する際の方針や主体、運用について取り上げました。
人事制度の策定には、経営の意思に基づいて行われ ますが、時に外部環境の変化に左右されがちです。そこで、会社の人事に対する基本方針となるHRポリシーが必要とされます。HRポリシーは、採用・配置・育成・評価・報酬などの制度と結びつき、組織の一貫性を支えます。制度設計は人事部門だけでなく、現場の意見や外部の知見を活用し、実態に合った仕組みを構築することが求められます。運用を見据えた逆算設計を行い、社員の納得感を高めることが制度の定着につながります。制度は人事だけでなく現場も関与し、適切な運用が組織の成長を支えます。
自社の人事制度2.0へ ~BANI時代の人事制度~
はじめに ― なぜ人事制度2.0が必要なのか
人事制度2.0とは
まず、「人事制度2.0」といった一般用語は存在せず、まったくの私の造語です。
これまでの5回の連載では、人事制度にまつわるさまざまな固定観念を打破するような記述をしてきたわけですが、2.0という言葉で言いたいことは、ちょこちょこと部分改修を続け、だましだまし現行制度の延命を図る“1.1”、“1.2”といった歩みではなく、事業環境や自社内部の変化、法律の変化にあわせてリニューアルを図る2.0を考えましょうということなのです。
しかし、さまざまな変化に対応していかねばならないということは、当たり前のことでもあり、わざわざ2.0などと呼称するのは大げさでは?と思う方もおられるでしょう。実際、少し調べれば多くの方が環境変化に適応するのだ!といった同様のコメントをしておられます。
それでも、「環境変化に対応できている実態」を、私たちはそう多くは目にしておりません。それは、私たちを縛る鎖、呪縛と言ってもいいものがあるからなのです。
日本の人事制度を縛る呪縛
5回の連載では、一貫して【人事制度とは「明日、また頑張ろう」と思えるためのさまざまな取り決めである】というメッセージを強調してきました。
このメッセージは、人事制度の本質を端的に伝えるものであるのと同時に、「日本の人事制度では常識的に扱われ、それでいてあまり議論されることなく存在してきた誤解」を解消するためのものでもありました。それこそが呪縛であり、今一度5回の連載を俯瞰して眺めていただくと、個々のテーマの掘り下げとは違った見方ができるかと思います。
その呪縛は、具体的には以下のようなものです。
- 人は金銭報酬のみでつき動かされるという呪縛(vol.001、003、004)
霞を食べて生きているわけではありませんから、働く上で金銭は重要な要素です。しかし、自分の事を鑑みれば、決して金銭のみで、働く場や職種の意思決定をしているわけではないことにすぐに気が付くでしょう。
しかし、他者を動かす立場、人事や管理者になると、なぜか人は金銭のみで動くものだと思ってしまうのです。ここに呪縛があります。 - 話し合いをするとまとまらないので、一方通行がよいという呪縛(vol.001、002、003、005)
もちろん、企業規模が大きくなればなるほど、多くの方と話し合いを重ねるのは難しくなります。時間コストを筆頭に多くのコストがかかるからです。もちろん、ここで言いたいことは、いついかなる場合でも話し合いが良いということではありません。
そうした「話し合いに物理的なコストがかかること」と、「話し合うことの効用の有無」は別のこと、効果から考える必要がある場合がありませんかということなのです。
Vol.002では、目標設定において対話を行うことを科学的な側面から明らかにし、vol.005では制度の策定において、浸透して使ってもらうためには結局のところ、策定にできるだけ参加してもらうことの効率の良さについて言及しました。
「通達することは、いかなる場合でも効率が良いことなのだ、あるいは致し方ないことなのだ」という考えも呪縛と言えるでしょう。もっとも、見聞きする範囲だけでしかありませんが、この呪縛は年々減少しているように見受けられます。
人事制度の思考の枠を超える3つの視点
こうした呪縛から解放されるためには、3つの視点を取り入れることが効果的です。
組織は流動的である
現代は、VUCAをこえてBANIの時代だとも言われています。BANIとは、Jamais Cascio氏によって提唱された概念で、4つの単語の頭文字をとったものです。
| Brittle | 脆弱性:一見すると強固に見えるが、実際には非常にもろく、急に崩壊する可能性がある状態。 |
|---|---|
| Anxious | 不安・恐怖:急速な変化・脆弱性・予測不可能な未来が個人や組織にもたらす心理的な不安。 |
| Nonlinear | 非線形成:物事が単純な因果関係では説明できず、複雑に絡み合っている状態(小さな要因が想定外の大きな影響を与えることもある)。 |
| Incomprehensible | 理解不能:情報があふれすぎており、既存のロジックではどの情報が正しいのか判断が難しくなり、調査などが意味をなさなくなる状態。 |
一見VUCAと類似した概念のように見えますが、Jamais Cascio氏によれば、VUCAは混沌である状態はあるものの情報やデータをもとに対応可能であることを示しているのに対し、BANIはそれを受け入れ、適応していかねばならないことを示しているとのことです。
これを人事制度に当てはめれば、心理的安全性の確保を前提にしつつも、前例を踏襲することこそが危険であることがよくわかります。事業環境は予測も理解も不可能で常に不安定、それに適応するには組織も柔軟に変化させていかねばなりません。その組織を効果的に運営していく人事制度もこれまでと同様ではいられないのです。
しかし、慣性の法則からいっても人は大きな変化を好みません。慣れ親しんできた組織形態であればなおのことです。誰しもが違和感を覚えながらもなんとなくそのままになっているような組織では、誰かひとりの力で変えていくことは難しく、おのずと対話の必要性も気付かされるはずです。
未来の人事制度はポートフォリオ型である
BANIであることを前提とすると、一定ではない事業環境下で、かつ、さまざまな雇用形態、さまざまな働き方が混在する社会において、自社だけが安定的でシンプルな構造でいられることはないでしょう。そのような状態において、人事制度も単一の型で運用できるのかということについては強い疑問が生じます。
例えば、いわゆるジョブ型について考えてみましょう。その名の通り、職務ありきでその要件に合致する人材を当てはめていく型ですが、転職が当たり前で人材の流動性が高まっている現在では有効性が高く評価されています。他方、日本の法制度では解雇規制が強く、変動する事業環境で当該職務が消滅しても、その職に就いていた人材を解雇することができません。
また、新卒一括採用は、日本の雇用システムにおける特徴の一つですが、卒業してすぐにジョブに当てはめる難儀さもあります。これらは実務家であれば、日々感じておられることではないでしょうか。
「従来のような単一の制度であり続けることができる」と断定することには無理があり、さまざまな方法を組み合わせて運用する時代になってくるでしょう。
人事制度は納得感が高くあるべき
人事制度においては「公平」という言葉がよく用いられますが、この「公平」という言葉は、「平等」という言葉との混同等、とかく誤解が多い言葉です。人事制度においても、「制度の公平性とは全員に同じ基準を適用する」といった誤解があるでしょう。
例えば、とある等級の全社員を「リーダーシップ」「問題解決能力」など、共通の基準で評価することは、全員に同じ基準を適用しているといえますね。しかし、クリエイティブ職に対しても、営業職と同じ「積極的な外交ネットワークの形成」といった評価基準を用いることは、公平と言えるのでしょうか。そうではありませんよね。
※上記の例は、あくまでも一例で産業や組織文化によっては、公平となるケースも想定されます
報酬においても同じでしょう。すべての雇用形態のすべての年代のすべての職種の人が、全員金銭報酬のみを欲しているという前提で同じ基準を当てはめることには無理があります(市場価格にみあった金銭報酬が担保されることは大前提で)。
「公平=自社の状況、社員それぞれの状況や役割に応じた適切な制度を提供すること」、すなわち、高い納得感を得られる設計が自然体となるでしょう。
もちろん、これは簡単なことではありません。試行錯誤の過程でうまくいかないことも高い確率であるでしょう。しかし、前述のとおり、一律であることは公平とはいえないBANIの時代なのです。
実践に向けたチェックリスト ― 自社の人事制度を見直すための3つの問い
前章では既存の思考の枠をどのようにして超えていくかについて言及しました。ここでは、そのアクションをする必要があるか否かの簡単なチェックリストを提示します。
この制度の賞味期限は設定されているか
たとえば、5年後も有効か否かということです。これは、5年後もまったく同じ内容を維持できるかということではなく、変化に対応できる柔軟性があるか否かということです。
私は常々、「制度に余白を設ける必要性」を説きます。ガチガチに固められた制度は、わかりやすい反面、柔軟性を欠きます。職種や等級によって臨機応変にできる記述の粒度を設けておくだけでも柔軟性は高まります。別の視点ですが、ガチガチに固められた制度は、担い手(マネージャー)に“やらされ感”を感じさせてしまいます。人事制度を運用することは、本来は事業を成長させ、組織の人員の成長を促すクリエイティブな仕事のはずなのに。
この制度の社員の納得感は高いか
社員が受け入れやすくなっているかどうかということです。一律同じ基準の導入ではなく、職種や等級、地域といった、できるだけ幅広いカテゴリで受け入れやすくなっているかが、真の公平性と言えるでしょう。
当然に、これは人事や経営の主観だけで担保されることではありません。かといって一律アンケートをとっても、納得感の高低の背景まではつかみきれません。ここにも対話が必要なのです。
この制度は競争力向上に貢献しているか
人事制度が、単なる社内ルールではなく、採用やリテンション、社員の成長において競争力を生む設計になっているか否かということです。
人事制度は複雑なパズルです。考慮する要素は、社内の整合性だけではなく、むしろ出発点は事業環境や自社の事業構造です。何をもって新たな市場を切り開くのか、何を強みにして競合と渡り合うのか、それらに貢献しない人事制度はピースの半分しか埋まっていないジグソーパズルと同じです。
おわりに ― 人事制度の既成概念を超えるために
もうお気付きかと思いますが、私が、このコラムで最も重視していたことは、人事制度に対する規制の固定観念を揺さぶることでした。今回のコラムで取り上げたもの以外にも存在します。
人事制度は、会社の未来を創る重要な要素です。しかし、それは固定のものではなく常にアップデートされるべきものです。また、そのアップデートの方法もタイミングも一律ではありません。外部にも競合他社にも正解は転がっていません(ヒントやきっかけはある)。自社の正解(その時点で最も正解だと考えられるもの。厳密には正解かどうかはわからない)は、自社で導き出すしかないのです。
そのためにも、本コラムの読者の皆さま自身が、自社の制度そのものや制度設計の考え方、自社の“当たり前”に疑問を持ち、どうすべきかを考える第一歩を踏み出していただきたかったというのが私の真なる想いです。この想いのあまり、耳目を集めるような強めの言い回しや、やや過激な問いかけがあったことは、私の言語能力の至らなさであり、ご勘弁をいただきたいところです。
読者の皆さまの企業は、世にその必要性を感じられているからこそ、これまで存続してきているはずです。しかし、今後も世の中に必要とされるかは補償されるところではありません。
かつての日本では、ほとんどの男性が「ソフト帽」と言われる帽子を着用していました。しかし、現在そうした姿が目に留まることはありません。
これは、帽子産業の各社の怠慢なのでしょうか。帽子を製作する技術に退廃があったのでしょうか。そうではありませんよね。これは、誠実に実直に事業を営んでいても、「どうしようもない環境変化」がやってくるという一例です。
読者の皆さまには、このBANIの時代における「どうしようもない環境変化」に適応していくべく、企業の根幹となる人事制度に対する考え方について、今一度考察を深めていただけますことを願い、この連載の締めくくりとさせていただきます。
【参考文献】
Cascio, J. (2022). Human Responses to a BANI World, Oct22.(2025年2月7日閲覧)
田口(2023)『スタートアップ企業の人事制度』, 労務行政.
読売新聞オンライン(2023)『紳士の象徴だったソフト帽』, 9月22日(2025年2月7日閲覧)
\田口氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】
成長意欲を引き出す「目標・評価」とは
~人事制度の誤解と真実~
Profile

合同会社YUGAKUDO 代表社員
iU専門職大学 客員教授
田口 光 氏
早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて 新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を歴任し、IPO 準備・M&A などのPJも担当する。
その後、外資系企業の人材開発部門長を経て起業。組織開発事業、スタートアップ支援事業を柱とし、多くのスタートアップ企業で 顧問・役員を務める。
現在は事業の傍ら法政大学政策創造研究科/研究生として研究に打ち込む。
【所属団体】
経営行動科学学会、人材育成学会、日本労務学会、日本人材マネジメント協会
【著書】
スタートアップ企業の人事戦略(労務行政)
組織文化診断と組織開発(共著:産業能率大学出版)
労働条件不利益変更の判断と実務(共著:新日本法規)
- 記事をシェアする