HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジインタビュー】
立教大学 田中氏
「これから」のリーダー、人事、CHRO【後編】
公開日:2025.05.28
- 記事をシェアする
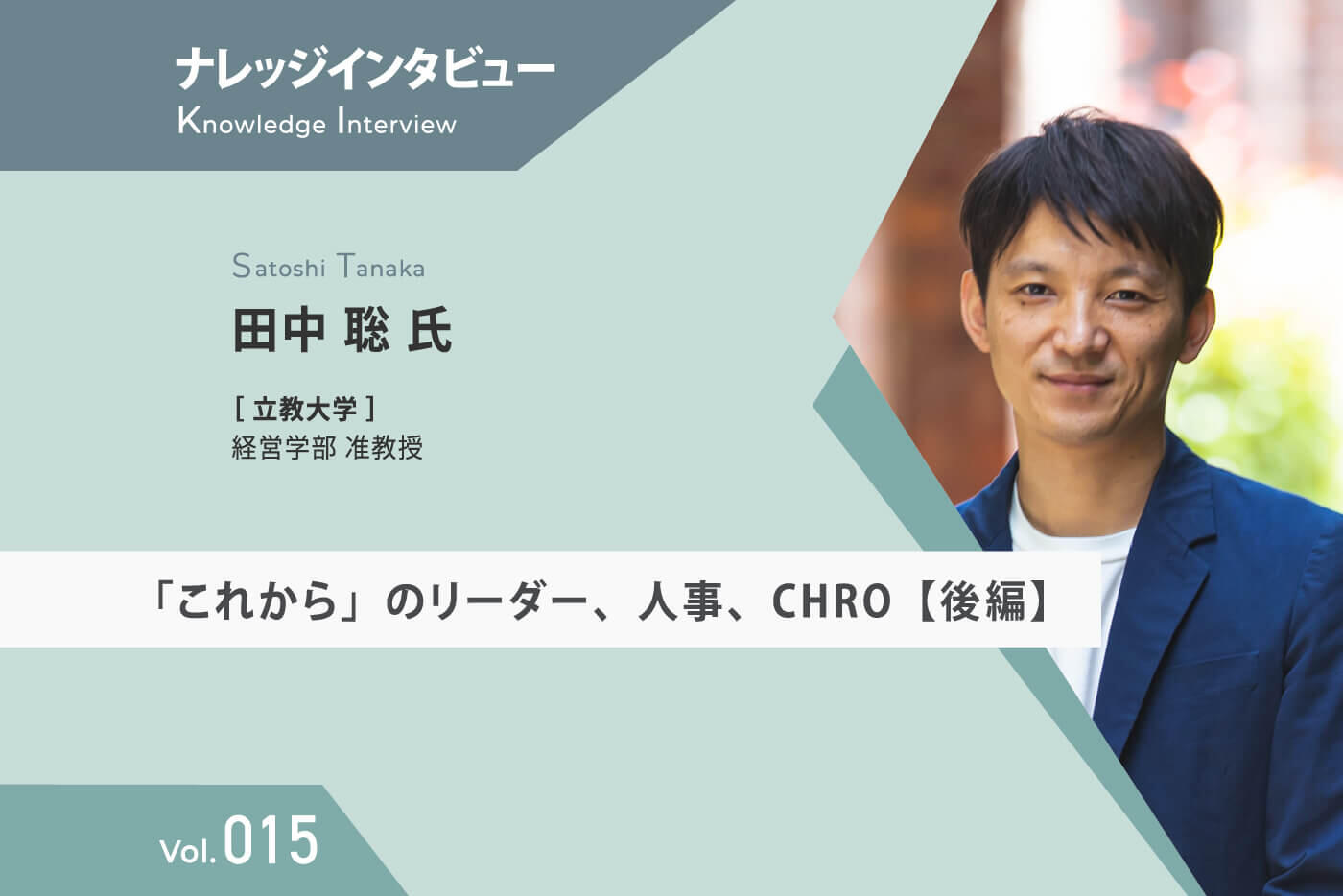
立教大学
経営学部 准教授
田中 聡 氏
今回のナレッジインタビューは、HRナレッジセミナー2025 Spring DAY2『これからのリーダー育成を科学する』の講演をいただいた立教大学 田中聡氏のイベント後インタビューです。
【前編】では当日時間内にお答えしきれなかった質問に回答をいただきました。【後編】では、講演を踏まえての管理職課題や人事のこれからについてのお話を紹介します。
― 講演の最後の質問で、リーダーへのアレルギーの話が出ましたが、管理職になりたくない問題とつながりそうです。
今日の講演では若手社員の「管理職になりたくない問題」については触れませんでしたが、本当に根深い問題だと思います。わたしはEYストラテジー・アンド・コンサルティング社と共同研究をしています。
まず、管理職というのは、実は非常に成長機会が多く、その会社にとって最も戦略的なポジションであり、高度な専門性が求められる職務です。会社として、そのような認識をしっかりとつくっていく必要がありますよね。
先程お伝えしたように、「誰にでもできる仕事なのに報酬が見合っていない」「将来の市場価値にもつながらない」というイメージを持たれている場合、管理職は敬遠されがちです。一方で、「会社の将来に貢献しながら、自分自身も成長できる、極めて専門性の高い職務である」と捉えられれば、管理職という役割の見方も大きく変わってきます。残念ながら、今の日本企業では、後者のような捉え方をされているケースはまだ少ないのが現状です。
また、多くの企業では「エキスパート職に進むか、それとも管理職を目指すか」という二択を提示していますが、そもそも管理職も一種のエキスパートです。「なぜ管理職は“非エキスパート”という前提で語られるのか?」という問いを持つことが大切です。マネジメントとは、極めて高度な専門性が求められる“プロフェッショナル・ジョブ”であるにもかかわらず、未だに“ジェネラル職”のように扱われている傾向があります。このイメージをアンラーン(学びほぐし)していく必要があります。
エンジニア職、営業職、と同じようにマネジメント“職”なんですよね。「営業で実績を上げた人がマネジメントするべき」という発想には限界があります。プレイヤーとして成果を出したかどうかで管理職適性を判断してしまうと、プレイングの経験がない人は将来的にその部門を率いることができなくなってしまいます。
では、社長はどうでしょうか。全部の職務経験を一通り経験していないとできないのでしょうか。そんなことはないわけです。コーポレートのCXO(Chief x Officer:企業の特定の分野や機能における最高責任者の総称)や取締役に求められるのは、未経験の領域を含めて全体を俯瞰し、戦略的に判断し、投資の優先順位を決めていく能力です。
それぞれの職種には、それぞれに必要な能力や資質があります。それを理解せずに、単に“経験の有無”で語ることは、職務や役割の本質を歪めてしまうと思います。
― 講演の中で、リーダー育成に携わる部分だけでも思いましたが、人事の仕事はキャリアの意味や実態の変化、価値観の変化や多様化に伴って、複雑で大変になっていると思います。画一的に進めたり、判断できないことが増えました。

おっしゃる通り、人事の業務はますます複雑化しています。キャリアの意味やあり方、働く価値観が多様化し、これまでのような画一的な対応では難しい場面が増えてきました。
ただ、働く側の視点に立てば、今は非常に自由度が高く、キャリアを主体的に描きやすい時代になったとも言えます。「将来こんな仕事がしたい」「今の仕事を通じて何を得たいか」といった問いを、自分なりに考えながら働いている人にとっては、非常に働きやすい環境です。
一方で、「その問いを誰かから与えてほしい」「用意されたレールに乗っていたい」というタイプの人にとっては、自由度の高さが逆に不安や苦しさにつながることもあるでしょう。
人事の視点に立てば、これまで、一人ひとりに意思や主体性がなかったかというわけではなく、これまでもあったけれど見えなかったのだと思います。「3年目にはこの業務、5年目にはこの評価」といった横並びの枠組みの中で運用されてきました。そのため、一人ひとりの意思や個性が“見えていなかった”というだけで、存在していなかったわけではありません。
今は、個人が自らキャリアを描く“キャリア自律”の時代です。会社側もそれを支援する役割へと変わりつつあります。人事が“お世話係”のように社員一人ひとりの希望を汲み取って動くのではなく、「意思を持って成長しようとする人の背中を支える存在」としての人事へと、役割が進化しているのです。
― これからも、“はたらく”が変わる、その中で人事の役割も変わっていきますね。部署名も「人事」や「HR」ではなく、いろいろな名前になってきています。人事はこれからどうなっていき、どのような言葉だったら「あるべき人事」を表現できるでしょうか。
まず経営資源としての人の優位性は高まると思います。もちろんAIに代替されるものは出てきますけれど、それによって人がいらなくなるとか人の価値が下がるとかそんなことはないと思います。
経営資源としての人の優位性は高まると、人を活かす、伸ばす経営をしている会社や、人に投資をしている会社に本質的に人が集まってくる。労働市場から優れた人材を惹きつけられる会社に基本的にお金は集まっていくので、人事を経験していたり、人材マネジメントについて明るい経営者を登用しようと考える会社が増える。だから今後はCHROやHRBPを経験した人がCEOとして選ばれるケースも増えてくるでしょう。
その逆もあると思います。CEOを経験した後のキャリアとしてCHROに就く、という選択肢もあってよいと思います。かつてのように“会長や相談役”に収まるだけでなく、再び企業の根幹である「人」の課題に向き合うCHROという役割に戻る。そのような柔軟なキャリアパスもあり得るのではないでしょうか。
また、今は人事部門と経営企画部門の間に厚い壁がありますが、「人と事業」「人と経営」というものが一体となって語られるように、組織も変わっていくはずです。実際、経営人材育成を経営企画部門が主管している企業も少なくありません。
最近では、HRBPのように、人事が事業に深く関わっていくスタイルが広まりつつありますが、これはコーポレートレベルにも波及していくべきだと思います。人と経営の関係性をより一体的に捉え直す動きが、今後の組織変革において鍵になるでしょう。
【前編】のあとがきでの「CHROはCEOと同じかそれ以上の視会社の未来のことを考えていないといけない」からつながる、ワンチームであるべき「人と事業」「人と経営」、そしてCHROを経験したCEOや、CEOからCHROへのキャリアという道まで、CHRO、人事の持つ役割や視点について、また、管理職課題についてもお話を伺いました。
参加者のみなさんからの質問や相談に対して、その質問の言葉の裏側、根本の部分を常に考えながら、一つひとつに言葉を選んでお話されていました。
\田中氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2025 Spring】
これからのリーダー育成を科学する
\田中氏登壇のセミナーレポートはこちら/

【HRナレッジセミナー2025 Spring】
これからのリーダー育成を科学する
Profile

立教大学
経営学部 准教授
田中 聡 氏
東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。大学卒業後、パーソル・グループに入社。株式会社パーソル総合研究所を立ち上げ、同社リサーチ室長・主任研究員を務めた後、2018年より現職。専門は人的資源管理論。研究テーマは人とチームの学習。主な書籍に、『シン人事の大研究』(ダイヤモンド社)、『経営人材育成論』(東京大学出版会)、『チームワーキング』(JMAM)、『事業を創る人の大研究』(クロスメディアパブリッシング)など。
- 記事をシェアする








