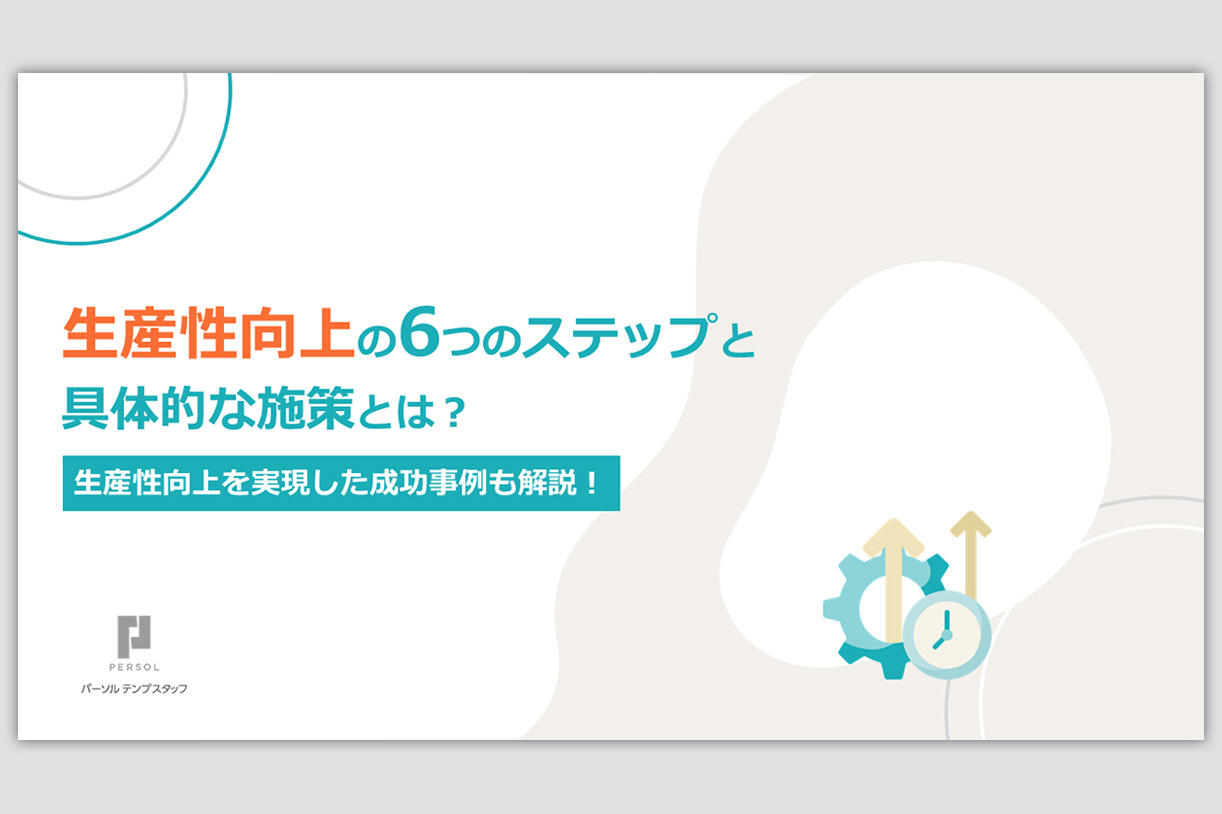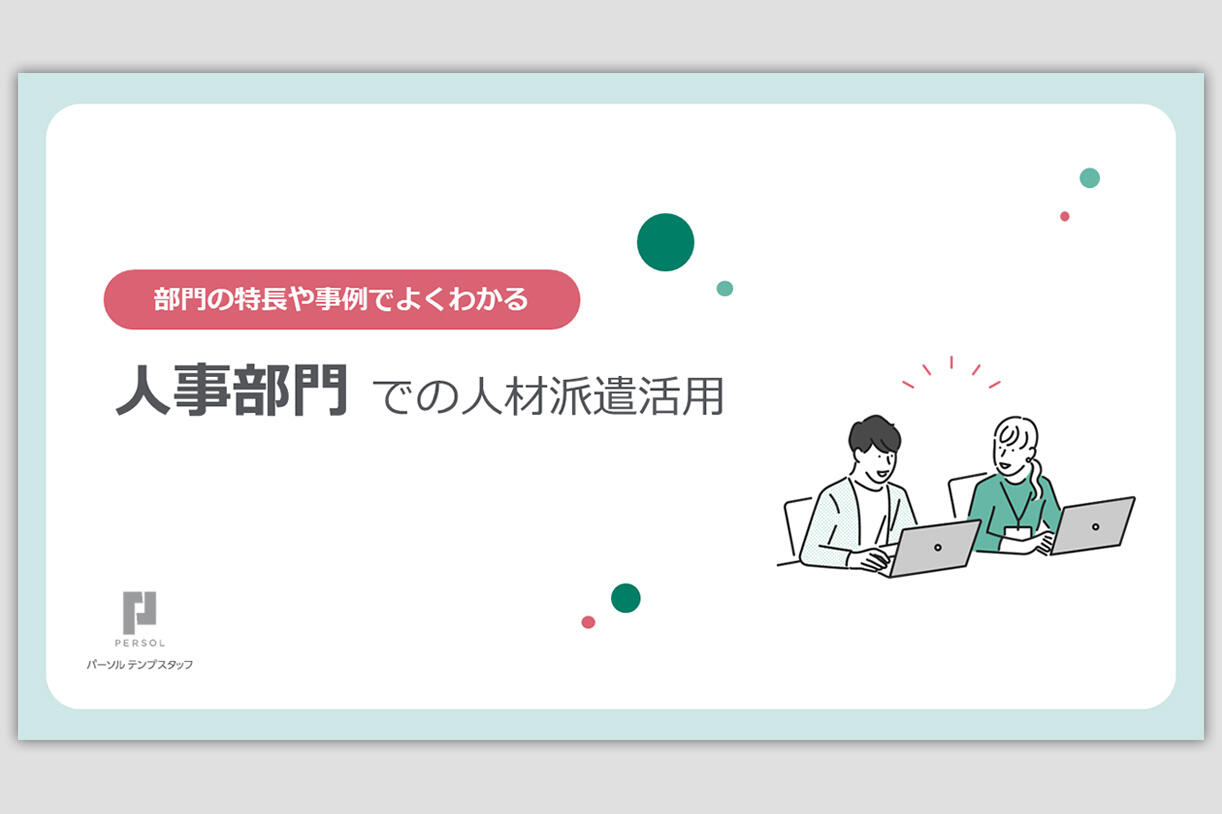HRナレッジライン
カテゴリ一覧
メンター制度とは?メリットや留意点、導入までの流れについて解説
- 記事をシェアする

メンター制度とは、先輩社員が新入社員や後輩社員をサポートする制度です。
メンタル面のサポートをメインにすることから社員の心理的安全性を高められ、早期離職の防止や社内コミュニケーションの活性化が期待できます。
しかし、制度を導入したものの期待した成果が得られない、社員の業務負担が大きくなり逆効果になるなど、理想通りに運用できないケースがあるのも事実です。
そこで本記事ではメンター制度の概要から、導入するメリットと留意点、具体的な導入までの手順などを詳しく解説します。ぜひ、ご一読ください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
メンター制度とは
メンター制度とは、仕事の指示・命令を下す直属の上司とは別に、社内の先輩社員が新入社員や後輩社員などの育成対象(メンティ)に対して行う個別支援活動です。具体的には、先輩社員と後輩社員の定期的な面談(メンタリング)を制度化し、仕事上の課題や悩みなどの相談にのります。面談での対話を通じて先輩社員は後輩社員のキャリア形成上の課題解決を援助し、個人の成長をサポートします。

※引用:厚生労働省|メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル
エルダー制度との違い
メンター制度と近しい制度として、エルダー制度があります。エルダーには「先輩・年長者」という意味があり、メンター制度と同様に先輩社員が新入社員や後輩社員をサポートします。メンター制度は仕事上の悩みなど、メンタル面のサポートがメインになります。そのため、人間関係のしがらみを気にせず相談できるよう、仕事の利害関係がない他部署の人がメンターを担当することが一般的です。
一方、エルダー制度とは主に新入社員に対して行われるOJT制度の一種を指します。業務の直接的な指導に重点を置くため、同じ部署で仕事をする先輩社員がサポートを担当します。企業によっては、OJTリーダー制度、ブラザー制度、シスター制度などと呼ぶこともあります。
OJT制度との違い
OJT(On-the-Job Training)制度とは、職場で実際の業務を通じて行う研修方法です。新人や新しく配属された社員が、日常業務を通じてスキルや知識を習得します。実務に基づく学習が特徴で、理論と実践が直結しており、主に経験豊富な先輩社員や上司が直接指導を行います。これにより、即戦力となる人材の育成が期待できます。OJT制度は実務を通じた教育であるのに対し、メンター制度は特定の先輩社員が継続的に指導やサポートを提供する制度であり、個別の成長やキャリア支援に重点を置いています。
コーチング・ティーチングとの違い
コーチングとは、育成対象への質問・傾聴を繰り返すことで本人が内面と向き合い、自身の中から答えを導き出して問題解決できるようにサポートする指導法を指します。一方、メンター制度では先輩社員が培ってきた経験や知見を積極的に後輩社員へシェアします。つまり、コーチングは対話の中でアドバイスや経験のシェアはせず、本人が自分で考えることを重視しています。答えやアドバイスを与えるメンター制度とは対話の内容が異なります。
また、ティーチングは正しい仕事の手順や知識、技能など決まった正解を教える指導法を指します。メンター制度はメンタル面のサポートがメインになるのに対し、ティーチングはより具体的に業務に直結する内容が多く、社員のメンタル面までサポートするわけではありません。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
メンター制度の目的
メンター制度の目的として、新入社員の早期離職防止があります。業務上の困りごとや社内の人間関係の悩みを相談でき、先輩社員がアドバイスする場所をつくることは、新入社員の定着率の向上に有効です。
多くの企業で、新入社員の早期離職は課題となっています。厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者が37.0%、新規大卒就職者が32.3%でした。

※引用:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します
メンター制度を導入することで新入社員が抱える不安や悩みに対応でき、早期離職の防止が期待できるでしょう。
また、パーソルテンプスタッフでは、弊社が新卒採用した事務職・無期雇用派遣社員を派遣期間の定めなくご活用のうえで、社員登用に切り替えることができるサービス「新卒ファンタブル」を提供しています。
人材派遣期間中は、長期・安定就業や社員登用に向けた研修や定期的なフォロー面談を実施し、加えて、人材派遣期間中の就業時の活躍をご覧いただいた上で判断できるため、社員登用後のミスマッチを未然に防止できます。
▼育成型無期雇用派遣 funtable

厳選採用した派遣スタッフを無期雇用派遣で受け入れて直接雇用まで育成支援
メンター制度のメリット
メンター制度の導入は、企業に大きなメリットをもたらしてくれます。以下でそれぞれのメリットについて詳しく解説します。
社員定着率の向上
新入社員はまだ環境になじめていない場合も多く、業務や人間関係で精神的な不安を抱えやすい立場です。しかし、メンターを付けることで相談しやすくなり、心理的安全性を高めることができます。不安を相談できる先輩社員の存在がいれば、悩みを抱えたままの新入社員は減り、定着率の向上につながるでしょう。
社員定着率の向上についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
社員の成長
メンター制度を導入すると、後輩社員と先輩社員のどちらも成長が期待できます。後輩社員は先輩社員のサポートによって業務上の技能や知識を習得できます。また、パフォーマンスの向上だけでなく、自発性の向上も期待できるでしょう。一方、先輩社員は先輩としての振る舞いを求められることで、マネジメント能力が向上します。メンター制度は、双方社員の成長を促す制度といえます。
社内コミュニケーションの活性化
メンター制度では基本的に、他部署の先輩社員がメンターを担当します。新入社員や若手社員はメンター制度を通じ、通常の業務では関わることのない社員と部署を越えた人間関係を構築できます。また、メンター制度をきっかけに他部署の社員に些細なことも相談できるようになるなど、社内コミュニケーションの活発化も期待できます。
社員の指導力の向上
メンターに選ばれた社員は、後輩社員へのサポートを通して指導力が向上するでしょう。新入社員や若手社員を指導することで、組織運営に欠かせないマネジメント能力が身に付けられます。
先輩社員の役割は、管理職の仕事と似た部分があります。管理職に昇進すると、部下の育成は重要なミッションになります。先輩社員として新入社員を育成した経験はリーダーシップを養い、将来、管理職になったときに活きてくるはずです。
メンター制度導入の留意点
企業にさまざまなメリットをもたらすメンター制度ですが、いくつかの留意点もあります。効果的な運用のために、以下のポイントを認識しておきましょう。
社員の負担が大きくなる
メンター制度を実施すると、先輩社員は通常の業務に加えて後輩社員をフォローする業務も発生します。業務負担が過重となる可能性があるため、繁忙期を避けたり、業務量を調整したりするなど、組織がメンター先輩社員をサポートする体制を整えることが必要になります。
一方、後輩社員側の留意点として先輩社員との相性が挙げられます。価値観や仕事観、人間性など先輩社員との相性が悪かった場合、不安や悩みを相談することができず、後輩社員にとってストレス要因になる可能性は否定できません。
社員による指導のバラつきが発生する
先輩社員の指導能力には個人差があり、後輩社員の成長にばらつきが出てしまう可能性があります。そうした事態を避けるためには、適性のある社員をメンターに選出する、事前の研修において共通の指導方法を伝えるなどの対策が必要となります。
離職率が高くなる可能性がある
先輩社員の質、または先輩社員と後輩社員の相性が悪かった場合、双方に精神的なストレスがかかってしまい、メンター制度そのものが悪影響の要因になり得ます。その結果、離職につながる可能性も考えられるでしょう。そうした事態を避けるためにも、先輩社員と後輩社員のマッチングは慎重に行う必要があります。
ハラスメント、プライバシー侵害に注意する
先輩社員と後輩社員の対話には、プライバシーに関わる話題が含まれることがあります。当然、その相談内容には守秘義務があるため、他人に話してはなりません。プライバシー侵害には十分に気を付ける必要があります。
また、対話をする際にプライベートのことばかり話題にしていると、後輩社員が不快になってしまうケースもあるでしょう。ハラスメント行為にならないように注意も必要です。
メンター制度導入までの流れ
メンター制度をうまく運用するためには、以下の4つのステップで進めていくのが効果的です。各手順について解説します。
STEP1.導入する目的やルールを決める
まず、どのような目的でメンター制度を導入するかを明確にしましょう。導入の目的は、主に「若手社員の離職防止」「女性社員の活躍」などが挙げられます。現場社員にヒアリングやアンケートを実施し、自社の課題を整理した上で目的を設定してください。これらの目的を明確にしておくと、先輩社員が指導に迷ったときの道しるべとなります。
メンター制度を導入する目的が決まったら、運用方法やルールを設定しましょう。先輩社員と後輩社員が話した情報の守秘義務や問題が発生した際の相談窓口、定期的な面談を実施する期間や頻度などを決めておくことが重要です。
STEP2.対象者を決める
次に対象となる先輩社員と後輩社員の選定を行います。選定方法には、それぞれの社員のバックグラウンドや相性を見て人事部がマッチングさせる「アサインメント方式」と、後輩社員が先輩社員候補者の中から希望者を選び、人事部が最終決定する「ドラフト方式」があります。
マッチングはメンター制度の成功を左右するカギとなります。目的に照らし合わせ、先輩社員としての適性がある社員を選ばなければなりません。
STEP3.実運用を開始する
あらかじめ定めた目的やルールに沿って、実運用を開始します。定期的な面談の実施中は先輩社員と後輩社員の関係性をウォッチし、先輩社員の負担を緩和できるようにフォローし、後輩社員にストレスがかかっていないかを注視してください。実施状況を把握するため、先輩社員と後輩社員の双方に報告を求めることも重要です。その結果、相性が良くなかった場合はマッチングの変更も検討しましょう。
STEP4.振り返りと改善を行う
定期的な面談の実施期間が終わったら、先輩社員と後輩社員の双方にヒアリングやアンケートを実施し、制度に対する意見や課題などを特定・分析しましょう。それらを改善した上で、次回の制度運用に反映させることが大切です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
メンター制度を導入して離職率低下を図る
メンター制度は、他部署の先輩社員が新入社員や後輩社員をサポートする取り組みです。適切なサポートを提供すれば、新入社員の離職防止につながります。また、新入社員の育成だけでなく、先輩社員が管理職になったときに経験が活かせるなど社員個人の成長にもつながります。社内のコミュニケーション活性化にも有効な施策なので、うまく運用できれば組織全体に影響をもたらすでしょう。
ただし、先輩社員の選定は難度が高く、先輩社員と後輩社員の相性が悪かったり先輩社員の指導力が不足したりする場合は、制度そのものが悪影響の要因になりかねません。先輩社員と後輩社員が置かれている状況を見極めながら、メンター制度のメリットを十分に活かした人材育成の体制を構築することが大切です。
離職率低下の対策についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
>>社員を定着させるには?平均離職率や離職率がもたらす影響を解説
>>コールセンターの離職率が高いのはなぜ?原因と対策をご紹介
>>営業職の離職率が高い原因と低下させる対策を解説
>>エンジニアの離職率の現状とは?離職の原因と防ぐための対処法を解説
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする