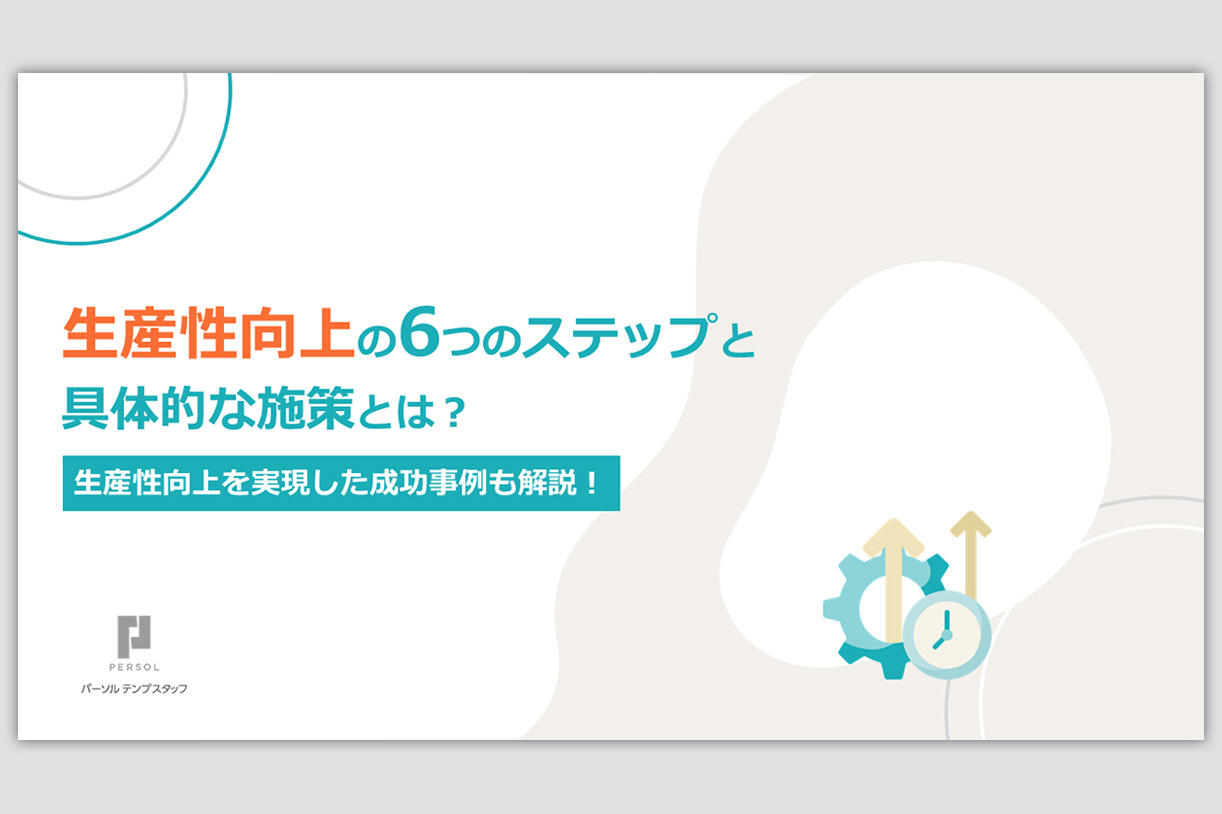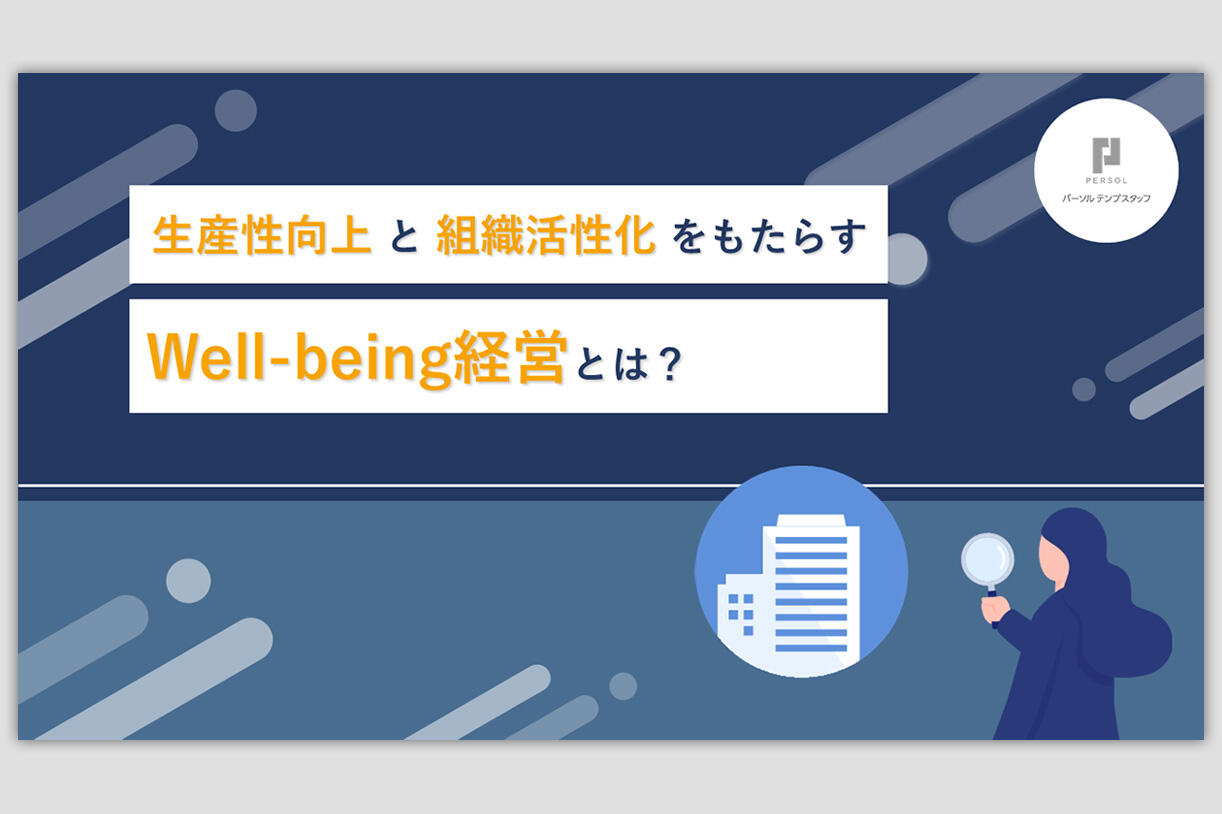HRナレッジライン
カテゴリ一覧
ジョブローテーションとは?人事異動との違いやメリット、導入に向いている企業を解説
- 記事をシェアする

ジョブローテーションは企業を支えるさまざまな業務について知ることができたり、ゼネラリストや幹部の育成ができるなど、企業の業務全体を見渡せる人材育成に役立ちます。
また、最適な人材配置が可能になり、企業の業績向上にもつながる可能性のある制度です。
本記事ではジョブローテーションの意味、メリットなどについて解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
ジョブローテーションとは
社員の能力開発のために、社員が定期的に異なる業務や部署を経験する人事制度です。人事計画に基づいて行われる戦略的人事異動を指します。柔軟で多様な経験を持つ社員育成のために導入されています。
人事異動との違い
人事異動は昇格・降格・解雇・配置転換など「組織の活性化」のため必要な配置転換です。一方でジョブローテーションは「教育のため」の異動であり、配置転換といえます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
ジョブローテーションのメリット
ジョブローテーションの導入には多くのメリットがあり、たくさんの企業でも導入されています。どのようなメリットがあるのか、解説します。
最適な人材配置が可能
社員一人ひとりの適性や強みを把握しやすくなり、その社員の能力や強みを活かすための最適な部署や業務への配置が可能です。これにより、一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境が整備できます。
ゼネラリストの育成が可能
さまざまな業務を経験すれば、社員が幅広いスキルや知識を身につけられ、能力開発やマルチスキル化が進みます。組織全体の柔軟性が向上し、複雑な業務に対応できる人材が育ちやすくなります。
生産性の向上
社内のさまざまな部署や業務を経験すると、会社全体の業務フローを深く理解できます。全体のフローを理解したうえで業務を行い、部署間の連携がスムーズになり、業務プロセスの改善が促進されます。無駄な作業が減り、業務について生産性の向上が期待できます。
生産性向上の具体的な実践法は、こちらで詳しく解説しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
社内の活性化につながる
定期的な配置転換により、あたらしい業務や部署での経験を通じて社員のモチベーションを維持できる可能性があります。同じ業務を続けるとマンネリ化が起こる場合がありますが、それを防ぎ、社内の活性化が期待できます。
コスト削減につながる
社員一人ひとりが多様なスキルを身につけ、さまざまな業務への配属ができるようになると、採用活動やトレーニングのコストの削減につながります。内部リソースを有効活用は、コスト効率アップが期待できるでしょう。
コスト削減の方法、それぞれの具体的な方法についてはこちらでも詳しく解説しています。
>>コスト削減とは?発生するコストごとに具体的な施策をご紹介
ジョブローテーションの留意点
メリットが多くあるジョブローテーションですが、気を付けるべき留意点もあります。留意点とその対策について解説します。
スペシャリストの育成に時間がかかってしまう
ジョブローテーションは、ゼネラリストの育成に適している一方で、スペシャリストを育成する場合時間がかかってしまう可能性があります。特定の分野における専門知識を深める時間が不足しているため、育成に時間がかかってしまうからです。職種によってスペシャリストの必要性の高さは異なるため、スペシャリストの育成が必要な職種については、ローテーションの頻度を調整し、専門分野のスキルアップに集中する時間の確保が大切です。
離職率が高くなる可能性がある
頻繁な配置転換はモチベーションが上がる場合もあれば、安定感を失いストレスを感じる場合もあります。目的が不明確な異動は、モチベーションを下げてしまう危険性があります。
ジョブローテーションが適切に行われず、社員が自身のスキルや興味と乖離した業務に配置され、離職につながるケースもあります。社員の適性や希望を考慮したローテーションを計画するように気を付けましょう。ジョブローテーションの目的やメリットを十分に説明し理解を得て、社員の意見や希望を尊重した柔軟な計画の策定が重要です。
離職率が高い職種とその原因、対策については下記の記事をご参照ください。
>>営業職の離職率が高い原因と低下させる対策を解説
>>コールセンターの離職率が高いのはなぜ?原因と対策をご紹介
あたらしい部署や業務への適応期間が必要になる
あたらしい業務や部署に異動する際、社員には適応期間が必要です。適応期間とは、業務を覚える期間や環境になれて通常通りのパフォーマンスを発揮できるようになるまでに要する期間を指します。その間は一時的に生産性が低下する可能性があります。それに伴い、一時的な業績低下の可能性も想定しなくてはなりません。対策としては、適応期間の研修やサポート体制の整備が挙げられます。スムーズな異動を支援するようにしましょう。
ジョブローテーション導入に向いている企業
ジョブローテーションは企業によって導入の向き・不向きがあります。ジョブローテーションに向いている企業はどんな特徴があるのでしょうか。4つのケースを紹介します。
成長を重視する企業
社員のスキル向上や多様な経験を重視する企業は、ジョブローテーションは効果的です。さまざまな業務や部署での経験を通じて、社員の成長を促進すると、企業全体の業績向上につながるでしょう。
幹部育成を促進したい企業
ジョブローテーションは幹部の育成にも適した制度です。さまざまな部門や立場を経験すると、幹部としての視野の広さを身につけたり、異なる環境でのリーダーシップを発揮する機会を提供できたりします。そのため、幹部育成を促進したい企業に向いている制度といえるでしょう。
フラットな組織構造を持つ企業
仕事の役割が明確には分かれておらず、業務フラットな組織構造を持つ企業にも向いているといえます。員が複数の役割を担うケースが多い企業ではジョブローテーションを行い、より柔軟な人材配置が可能となり、組織全体の柔軟性がさらに向上するでしょう。
高度なコミュニケーションが必要な企業
部署間の連携やコミュニケーションが重要な企業にとって、ジョブローテーションは効果的な制度です。それぞれの社員がさまざまな部署での経験を積むと、コミュニケーションが取りやすくなり、部門間の連携が強化されます。
ジョブローテーション導入に向いていない企業
なかにはジョブローテーションに向いていない企業もあります。どのような企業が向いていないのか、その傾向をご紹介します。
専門知識・専門スキルが重要な企業
高度な専門知識やスキルが必要な業務を多数抱える企業では、ジョブローテーションは適さない場合があります。特定の分野での深い知識やスキルの習得に時間がかかるため、頻繁な異動は逆効果となるケースも考えられます。
安定性が重要視される企業
業務の安定性が重視され、一貫した業務遂行を優先する企業では、頻繁な異動が業務の効率・品質にマイナスの影響を与える可能性があります。また、業務の安定性以外にも、社員の安定や満足度を重視し、安定したキャリアパスの提供を重視する企業文化がある場合、社員の不安感を引き起こす可能性があります。
小規模で専門性が集中する企業
企業の規模が小規模で、少人数の社員が専門的な業務に従事する企業や、特定の分野に特化している企業では、一人ひとりの社員の深い専門性が求められるため、ジョブローテーションが実施しにくい場合があります。
中途採用が多い企業
中途採用が多い企業では、即戦力を目的とした専門性の高い社員を採用しているケースが多く、そういった社員に対してジョブローテーションを行うと、モチベーションの低下につながる可能性もあります。
中途採用が多い企業と、ジョブローテーション制度の相性は、あまり良くないと考えられます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
ジョブローテーションを導入して属人化を防ぐ
社員の能力開発のために、社員が定期的に異なる業務や部署を経験するジョブローテーションは、ゼネラリストを育成したり、幹部候補を育成したり、部署間のコミュニケーションを取りやすくしたりと、多くのメリットを享受できます。その一方で、専門知識が身に付きにくいなどの留意点もあり、導入の際には注意が必要です。
業務の属人化を防ぎ、柔軟な人材配置を行えるようになると、生産性の向上にもつながります。計画的に導入して、企業の業績向上や離職率の低下を目指しましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする