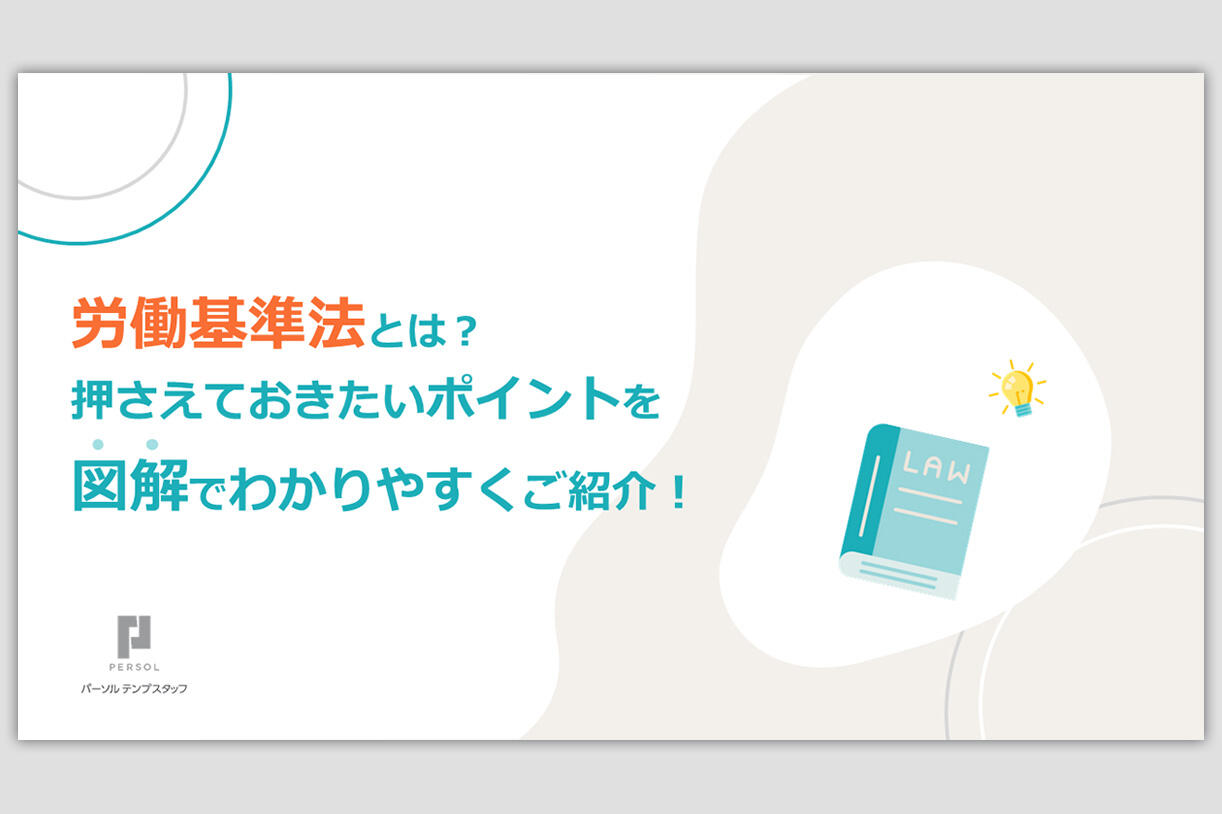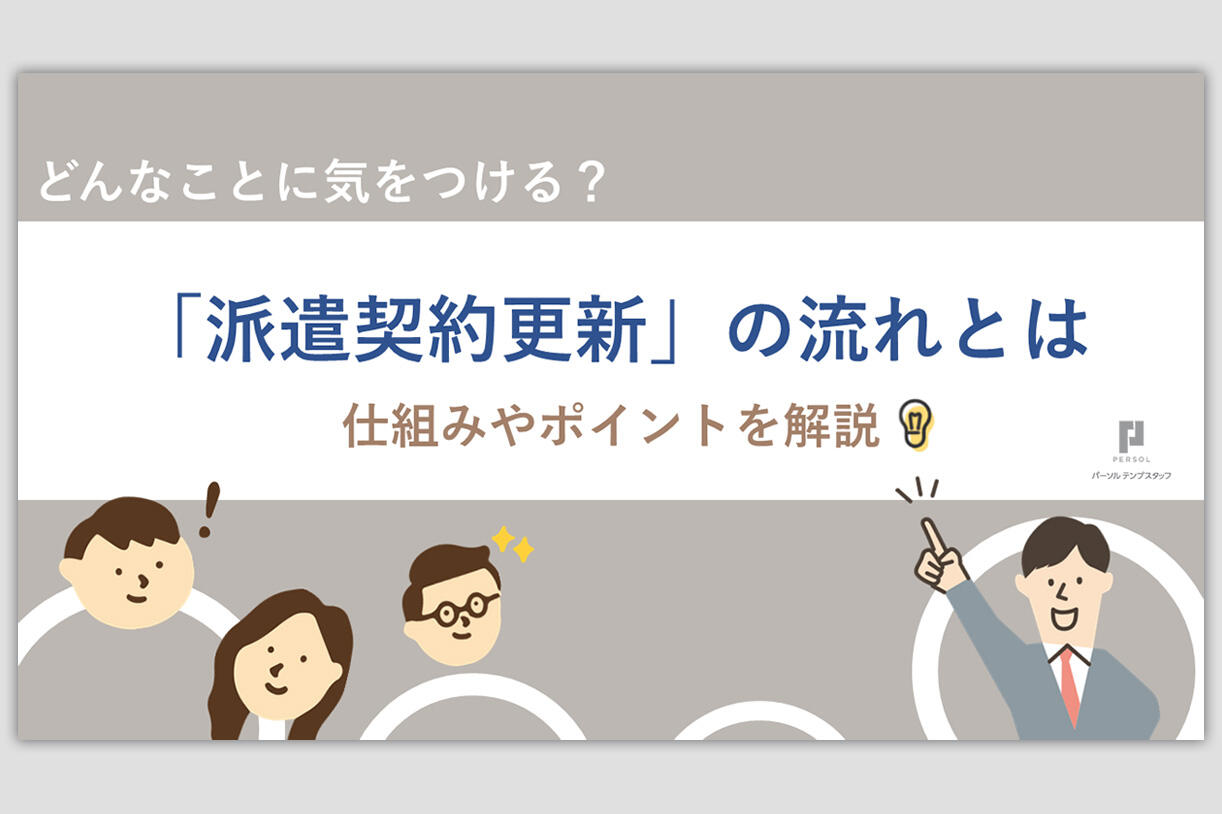HRナレッジライン
カテゴリ一覧
労働条件明示とは?労働契約締結・更新時に担当者が知っておくべきポイントを解説
公開日:2025.07.11
- 記事をシェアする

2024年4月に、労働条件明示のルールが改正されました。
企業が従業員を1人でも雇っている場合、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、「労働契約を締結するとき」「変更・更新するとき」に労働条件を適切に明示しなくてはなりません。また、求人時にも同様の条件明示が求められます。
改正後は、ルールに違反すると罰則が課せられる場合もあり、実際に労働基準監督署から是正勧告を受けたり、労使間で係争になった組織の事例も報じられました。
そこで本記事では、労働条件明示のルールについて、企業の担当者が理解すべきポイントについて解説します。記事後半では法改正後の課題や、起こりやすい不備、気をつけるべき点を企業向けに解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
2024年4月からの労働条件明示ルール改正概要
2024年4月に、労働条件明示のルールが改正されました。まずはそのポイントを簡潔に解説します。
新ルールに伴う変更点
労働条件明示の新ルールでは、企業が従業員に対して明示すべき労働条件項目が追加されました。追加された項目は以下の通りです。
- 就業場所・業務の変更範囲
- 更新上限の有無と内容
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
新ルールの適用範囲
従業員に対して労働条件を明示するタイミングは「労働契約を締結するとき」や「契約内容を変更・更新するとき」です。
2024年4月以降の改正ルールは、正社員・契約社員・パートタイマーなどすべての雇用形態に対して適用され、求人時から契約締結・更新時まで一貫した条件明示が求められるようになりました。企業規模に関わらず、従業員を1人でも雇用している場合には、対応が必要です。
企業が注意すべきポイント
企業は、就業場所・業務の変更範囲と、有期契約の更新上限を明確に記載する必要があります。また、先々の配置転換などによって就業場所や業務が変わる可能性がある場合には、「変更の範囲」まで明示が必要で、違反すると30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、職業安定法施行規則の2024年4月1日改正により、求人時にも同様の条件明示が求められるようになりました。
| 対象 | 明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 |
|---|---|---|
| すべての従業員 | 労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 | 就業場所・業務の変更の範囲 (例)「九州内の各営業所」といった地理的範囲や、「総務課の業務全般」といった業務範囲を明確に示す |
| 有期契約の従業員 | 有期労働契約の締結時と更新時 |
(例)「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など
|
| 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
|
改正の目的と背景
2024年4月のルール改正は、従業員の権利保護と、雇用条件の透明化を主な目的としています。
ルール改正の背景には、無期転換ルールの認知度不足や、多様なはたらき方の普及による短時間従業員の増加が挙げられます。無期転換ルールとは、有期契約ではたらく従業員が同じ企業で通算5年以上はたらいた場合、本人の希望により無期限の正社員などに転換できる制度です。
2024年4月の労働条件明示ルールの改正では、特に、就業場所や業務内容の変更範囲を事前に明示することが求められるようになりました。
これにより、従業員は自身が「将来配置転換が見込まれる地域・職務」などについて、あらかじめ把握できます。また、有期雇用の従業員は無期雇用への転換条件を事前に把握しやすくなります。はたらく人のキャリアプラン策定を支援し、労使間のトラブル防止を図ることが目的です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
従業員への通知と交付方法
労働条件明示に関して、従業員に対する通知と交付方法を説明します。
明示するタイミングと頻度
労働契約の締結時と、有期契約の更新時のたびに明示が必要です。求人時から採用後まで一貫した条件提示が求められ、内容に変更が生じた場合には、速やかに再通知をしなければなりません。
明示の手段
労働条件のうち、特定の事項については書面交付が必須です。
一部の明示事項は口頭でも可能ですが、「言った・言わない」のトラブル防止のため、書面化することが推奨されます。FAX・電子メールによる交付も認められていますが、従業員が内容を確認できる方法を選択する必要があります。
書面の形式については自由ですが、厚生労働省がモデル様式を公開しているため、ぜひ参考にしてください。
※参考:労働条件通知書
通知書の具体的な記載項目
従業員に対する通知書に明記すべき項目は以下のとおりです。
書面交付が必須の明示事項
以下の項目については、書面交付が必須です。
- 労働契約の期間
- 契約更新の基準(有期契約の場合)
- 就業場所・業務内容
- 勤務時間・休憩・休日など
- 賃金(昇給は除く)
- 退職(解雇含む)
使用者が定める場合に明示が必要な事項
以下に挙げる項目は、会社の就業規則などで定めがある場合に明示が必要です。なお、従業員が希望する場合には、FAX・電子メールによる交付も認められます。
- 退職手当
- 賞与・最低賃金・臨時の賃金
- 従業員負担の費用(食費・作業用品など)
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁
- 休職制度
労働条件明示の新ルールに関して企業が取るべき対応のポイント
労働条件明示の新ルールに関して、企業が取るべき対応のポイントを紹介します。
労働条件通知書を見直す
まずは、労働条件通知書の見直しをしましょう。
厚生労働省のモデル様式を参考に、就業場所・業務の変更範囲を具体的に記載する必要があります。
特に「就業場所・業務の変更範囲」については、「東京本社(変更可能範囲:関東地域の支店)」といった地理的限定や、「営業事務(変更可能範囲:総務・経理関連業務)」といった業務範囲の明示が必須です。
また、電子交付をする場合も「添付ファイルを受け渡しできる」「文字数を十分に記載できる」など、従業員が確実に内容を確認できる方法を選択しましょう。
有期契約従業員向けの更新基準を整備する
有期契約の従業員向けの更新基準を整備しましょう。
「通算5年」や「更新5回」など、具体的な上限を設定する場合にはその根拠を明確にし、従業員に説明する義務があります。例えば、「採用計画に基づく」といった経営上の理由などを明文化しましょう。
また、更新上限を新設する場合には、「現時点の勤務年数をリセットしない」などの既存の有期契約の従業員への経過措置も検討すべきです。これまでの勤続年数を無条件にリセットすることは、従業員のはたらく意思やキャリア形成を損なう行為となるためです。厚生労働省のガイドラインでは「合理的な理由なく不利益な変更をしてはならない」との立場が示されているため、「経過措置期間」を設けることが推奨されています。
無期転換制度の運用を見直す
無期転換制度の運用について、見直しをしましょう。
はたらき始めてから通算5年を超える有期契約の従業員に対して、転換可能な労働条件(賃金体系・職務内容など)を就業規則で事前に定めておく必要があります。
特に「転換後は基本給が変更になる」など、労働条件が現行の契約と異なる場合は、その内容を採用時から明示することが求められます。
また、対象者には個別面談などを実施し、転換希望の有無を確認するプロセスも推奨されます。
求人媒体の条件記載を見直す
求人媒体に記載している内容を見直しましょう。
募集段階から、後々変更になり得る業務範囲・勤務地範囲を明記することが義務化されました。「全国転勤の可能性あり」といった抽象的な表現ではなく、「関東圏の店舗」など具体的な範囲を示す必要があります。
加えて、採用面接時の説明資料も同様の基準で作成しなければなりません。
労働条件明示の新ルールに関連して企業が留意すべきポイント
労働条件明示の新ルールに関連して、企業が留意すべきポイントを解説します。
従業員からの無期転換の申し出は拒否できない
新ルールにおける追加明示項目の中に、「無期転換申込機会の明示」があります。
従業員から無期転換の申し出があった場合には、企業はその申し出を拒否できません。申し出があった時点で、無期労働契約が成立することとなります。
また、無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないと考えられます。有期契約の満了前に、使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もあるため、慎重な対応が必要です。
無期転換後は必ず正社員となるわけではない
無期転換は、雇用期間が無期限になるだけで、必ずしも正社員になるわけではありません。ここでいう正社員とは、雇用期間の定めがなく、企業に直接雇用されている従業員を指します。無期転換後の従業員の労働条件は、正社員と同条件である必要はありません。無期転換前と同じ労働条件で、雇用期間だけを無期に変更することも可能です。
よって、契約更新時や新規契約時には、法改正に対応した最新の「労働条件通知書」を用意し、雇用期間の更新上限の新設・短縮を行う場合には、従業員に対する丁寧な説明と記録が重要だといえます。
また、社内の労務担当者や管理職に法改正の内容を周知し、適切な理解・対応を促すことも必要です。
労働条件明示がなく、労働基準監督署から指導を受けるとともに労使間で係争に発展した事例
労働条件明示ができていなかったために、労働基準監督署から指導を受けたり、従業員との間で係争が生じたりするケースもあります。
ある学校法人で、教員との間で労働契約を締結する際に労働条件を書面で明示しておらず、勤怠管理も正確にできていなかったため、管轄の労働基準監督署から是正勧告を受けました。また、当該の教員との間で「労働契約上の地位確認」「未払い残業代の支払い請求」を理由に、裁判での係争に発展しています。
この事例は、労働契約の締結は2020年で、労働基準監督署から指導が行われたのは2023年のことです。2024年4月1日以降の出来事ではありませんが、労働条件明示をしなかったために労使間で係争となったケースは、これまでにいくつも報じられています。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
労働条件明示のルールを適切に理解しよう
本記事では、労働条件明示の新ルールについて企業向けに解説しました。
労使間で労働契約について認識の食い違いが生じてしまうと、「言った・言わない」という係争に発展するリスクが考えられます。
労使間のトラブル防止の観点も理解した上で、「求人時」「労働契約締結時」「契約更新時」にはそれぞれ、労働条件を細かく明示することが重要です。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする