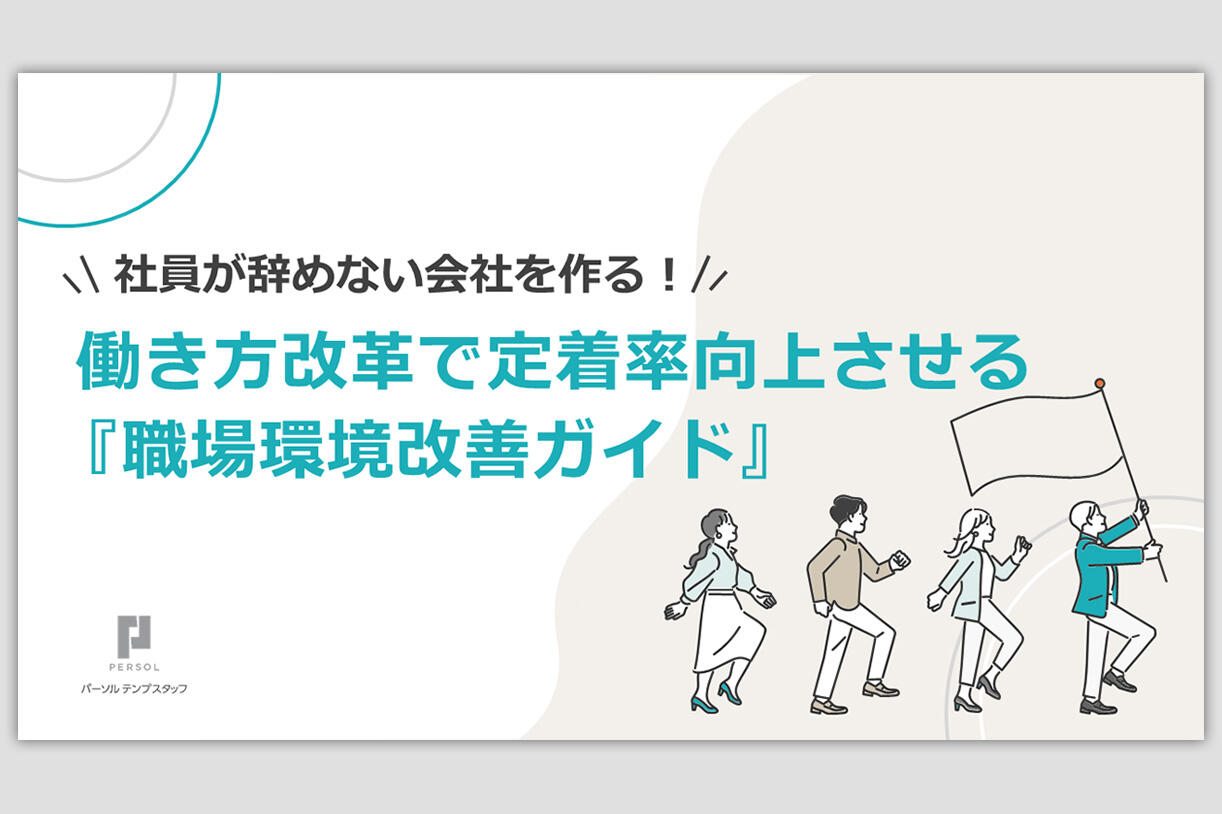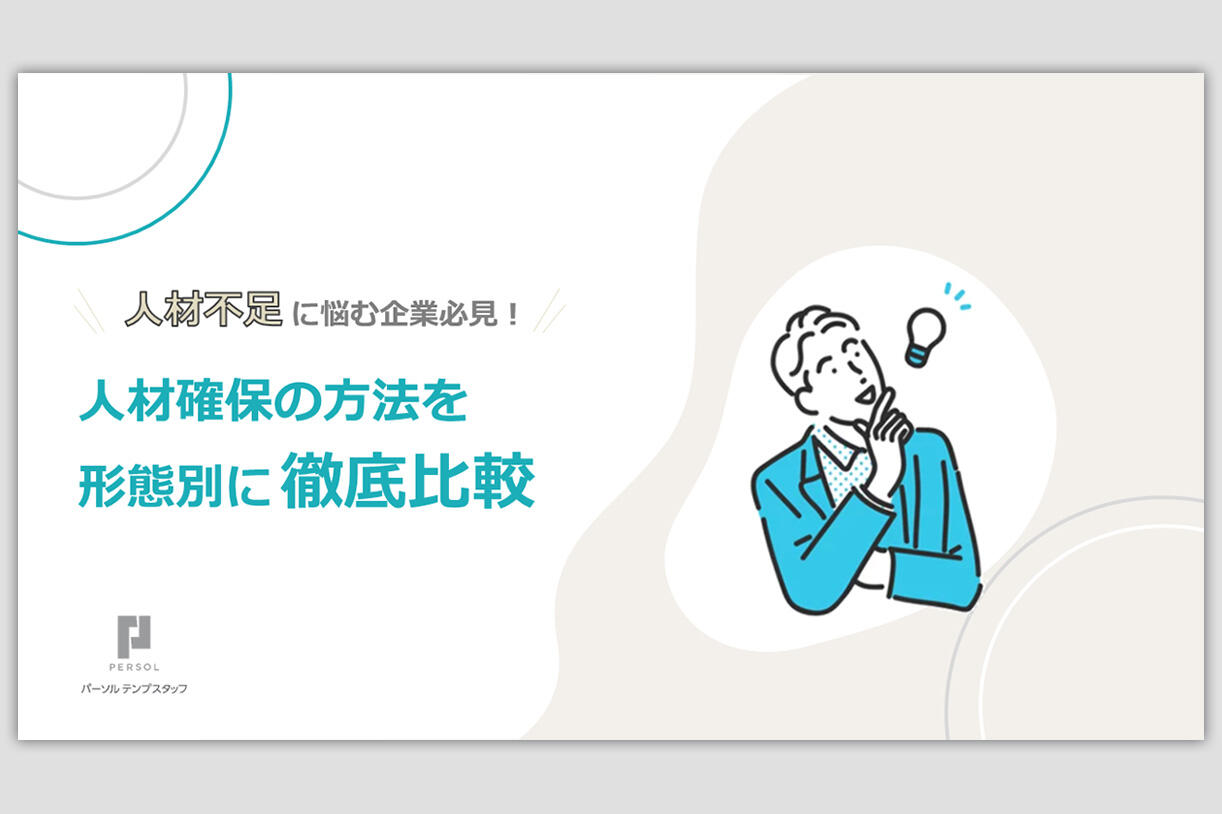HRナレッジライン
カテゴリ一覧
評価面談の完全ガイド|進め方・対話技術・フィードバックまで徹底解説
- 記事をシェアする

評価面談とは、社員の成長を支援し、納得感のある処遇を実現するための重要な対話の場です。
本記事では「評価面談の目的・進め方・フィードバック技術」まで、最新トレンドをもとに実務で使えるテンプレートやNG例・OK例付きで解説します。
AI活用や法改正への対応方法も網羅し、「形骸化しない面談」を実現したい人事・マネージャー必読の実践ガイドです。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事評価面談とは?目的や意味を分かりやすく解説
人事評価面談は、社員の業績・能力・勤務態度を定められた基準に基づいて評価し、その結果を本人に伝える場です。単に待遇を決定するだけでなく、上司と部下が社員の成長や能力開発を支援する、重要な対話の機会として位置づけられています。
多くの企業では、評価情報の共有や準備作業の効率化のため、独自の評価面談シートや人事評価システムを導入しています。これにより、フィードバックの質が向上、期待値が明確になることで認識のずれが減少し、面談の納得感と実効性が高まります。
さらに、評価プロセスを記録に残すことは、法的なリスクを回避し、説明責任を明確にする上でも役立ちます。
人事評価制度について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参照ください。
>>人事評価制度とは?導入する目的やメリット、設計方法について解説
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事評価面談の基本目的
人事評価面談の主な目的は、大きく分けて以下の3つに集約されます。
- 公正な評価と処遇の決定
- 人材育成の促進
- 社員のモチベーション維持・向上
それぞれの内容を解説します。
公正な評価と処遇の決定
面談では、対象期間における社員の貢献度を客観的かつ公正に評価し、その結果に基づいて昇給・昇格・賞与などの処遇を決定します。このプロセスによって、評価の透明性と公平性が担保され、社員が納得感を持って業務に取り組める基盤が築かれます。
人材育成の促進
評価結果をもとに、社員一人ひとりの強みや改善点を具体的に共有します。次の期間に向けた成長目標や能力開発計画を共に設定することで、社員が主体的にスキルを高め、キャリアを形成できるよう支援します。
社員のモチベーション維持・向上
日々の努力や成果を正当に評価し、その承認を伝えることで、社員の仕事への意欲を維持・向上させます。 あわせて、今後の活躍への期待を共有することで、組織へのエンゲージメントを深め、さらなるパフォーマンスの発揮を促します。
1on1との違い
| 項目 | 評価面談 | 1on1 |
|---|---|---|
| 実施頻度 | 年1〜2回(半期・年度ごと) | 週1〜月1回(継続的) |
| 主な目的 | 評価・処遇決定・目標設定 | 日々の課題共有・関係構築・成長支援 |
| 面談スタイル | フォーマル(評価シートに基づく) | カジュアル(自由記述・相談ベース) |
| 成果物 | 評価記録・目標設定シート | 行動プラン・振り返り内容 |
評価面談と1on1は、どちらも上司と部下の対話の場ですが、その目的、頻度、スタイル、そして成果物には明確な違いがあります。
評価面談は、一定期間の業績や行動に基づき、評価・目標設定・育成方針を共有するフォーマルな対話の場です。処遇決定や組織的な評価制度と密接に結びついており、客観的な記録が重視されます。
一方、1on1は、業務の進捗確認・悩み相談・キャリア形成支援などを目的とした、継続的で柔軟なコミュニケーションの場です。上司と部下の関係性を深め、日常的な支援や早期の課題解決を促す役割を担います。
このように、評価面談と1on1は目的と役割が異なるため、どちらか一方だけでは十分ではありません。それぞれの特性を理解し、適切に併用することで、納得感のある評価と継続的な人材育成を効果的に両立できます。
なぜ今、評価面談の「質」が重要なのか?納得感・離職率との関係を解説
リモートワークの定着やはたらき方の多様化、賃上げ要求の高まりなど、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中で、社員の貢献を公正に評価し、納得感のある処遇や成長機会を提供することは、企業の持続的成長に直結する重要な課題です。
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査」によると、離職理由の上位に「労働条件」「収入」「人間関係」が挙げられています。これらは直接的に評価制度に起因するものではないものの、「努力が報われない」と感じる評価への不満が背景にあるケースも少なくありません。
また、パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査」では、「評価不満因子(=仕事の努力が報われないと感じる)」を実感している層が3割を超えており、評価への納得感の欠如が、離職意向に影響を与えていることがうかがえます。
したがって、評価面談は形式的な手続きで終わらせるのではなく、成長と信頼を築く対話の機会として、その「質」を高めていくことが求められています
評価面談の留意点|法改正・説明責任・デジタル対応のポイント
評価面談を効果的に運用するためには、法的な要請への適切な対応と、HRテクノロジーを活用した実務の最新動向を把握しておくことが重要です。
法改正と説明責任の強化
2024年4月の労働基準法施行規則の改正により、労働契約の締結・更新時に「就業場所・業務の変更の範囲」を明示することが義務化されました。
この法改正を受け、評価面談では「どのような行動や成果が、なぜこの評価に結びついたのか」「それが今後の処遇やキャリアにどう影響するのか」を、具体的な事実や基準に基づき、より丁寧に説明することが求められます。
曖昧な評価や説明不足は、社員の納得感を損ない、モチベーション低下や離職リスクを高めるだけでなく、法的トラブルに発展する可能性もあります。
そのため、主観に頼らず、評価シートや行動記録、目標達成度といった客観的な根拠に基づいた説明とフィードバックが不可欠です。
引用:厚生労働省|「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
労働条件明示の変更について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
>>【最新版】労働基準法改正の背景と人事が押さえるべきポイントを解説
デジタル活用による業務効率化と面談の質向上
近年、HRテクノロジーの導入が進み、評価面談の準備や運用の効率化、質の向上に大きく貢献しています。
例えば、目標設定や進捗状況、評価データを一元管理できる人事評価システムは、面談準備にかかる工数を大幅に削減し、記録の抜け漏れを防ぐ上でも有効です。
さらに、リモート面談では録画機能やAI議事録ツールの活用により、面談内容の自動要約や文字起こしが可能となり、記録の正確性向上と担当者の負担軽減が実現します。
こうしたツールを評価システムと連携させることで、情報の一元化とフィードバックの質の底上げが可能になります。評価の透明性や納得性を高める上でも、テクノロジーの活用は今後ますます重要な要素となるでしょう。
評価面談で評価者が準備すべき3つのポイントとは?事前準備で差がつく
評価面談は、当日の対話そのものだけでなく、実施前の準備段階の質が面談全体の成否・部下の納得感・成長に大きく影響します。
評価者による事前準備のポイントは以下の3つです。
1.評価基準の再確認と根拠の明確化
まず、自社の評価制度や適用される評価基準(等級要件・目標達成基準など)を再確認しましょう。
その上で、評価対象期間中の具体的な行動事実、 成果・目標達成度などの客観的な事実や記録に基づき、「なぜ、この評価に至ったのか」という根拠を明確に整理しておく必要があります。これにより、評価のブレを防ぎ、論理的で説得力のある説明が可能となります。
以下は、簡易的な評価面談シートの例です。被評価者(部下)には、事前に自己評価欄への記入を依頼し、その内容をもとに評価者が準備を進める形が望ましいです。

2.客観的な実績・行動データの収集・整理
評価の根拠となる情報は、事前に収集・整理しておきます。例えば、日々の業務に関する記録、1on1のメモ、目標管理の内容、他部署からのフィードバックなどが挙げられます。
前述の人事評価システムなどを活用すれば、こうした情報を効率よく集め、抜け漏れなく管理でき、評価の公正性や納得感を高められます。
3.評価バイアスのセルフチェック
評価者自身が、無意識のうちに抱えているかもしれない「評価の偏り(バイアス)」に気づき、それが評価に影響しないよう注意しましょう。
評価面談シートの記入前や面談の実施前には、評価者用のチェックリストなどを使って、自分の判断を冷静に見直すことが推奨されます。

評価面談の進め方5ステップ|納得感を高める進行方法
評価面談は、双方向のコミュニケーションを軸に据え、以下の5ステップを踏むことで、効果的に実施できます。
ステップ1.アイスブレイクと面談の目的・進行共有(約5分)
面談の冒頭では、緊張を和らげるために労いの言葉や軽い雑談を交わしましょう。続けて、面談の目的・流れ・所要時間を簡潔に伝えることで、部下は安心して臨めます。
| NG例 | 「お互い忙しいので今回はサクッと済ませましょうか。」 |
|---|---|
| OK例 | 「〇〇さん、今期もお疲れさまでした。今日はこの期間を一緒に振り返りつつ、次に向けた話をしていけたらと思います。時間は1時間程度で、まず自己評価をお聞きし、私からのフィードバック、最後に次期の目標を話し合う流れです。よろしいでしょうか?」 |
NG例では、対話を軽視する姿勢と受け取られかねません。そのため、雑談の後に本題に入るようにしましょう。
ステップ2.自己評価のヒアリング・傾聴(約15分)
部下に自己評価を話してもらい、評価者は最後まで遮らずに傾聴することが大切です。話の途中で評価者が結論を急ぐと、率直な対話の機会を損なう可能性があります。
質問する際は、行動のプロセスや工夫、課題をどう乗り越えたかに焦点を当てましょう。これにより、部下自身の振り返りが深まり、次の期間に向けた課題認識も明確になります。
| NG例 | 「(部下が話している最中に)「いや、それは違うと思うな」などと遮る。 |
|---|---|
| OK例 | (部下の自己評価コメントに対し)「なるほど、○○について、もう少し詳しく聞かせてもらえますか?」と、さらなる説明を促す。 |
OK例では、行動や思考プロセスに焦点を当てた質問により、部下の振り返りを支援し、自己認識へと導きます。
ステップ3.評価・フィードバックの伝達(約20分)
評価内容は、事実とデータに基づき、丁寧かつ論理的に説明しましょう。まずは感謝と承認から伝え、その後に課題や改善点へ進みます。人格を否定せず、「行動」や「事実」に焦点を当てることが大原則です。
| NG例 | 「〇〇プロジェクトで納期が守れなかったのは、主体性が足りないからかもしれませんね。」 |
|---|---|
| OK例 | 「〇〇プロジェクトの推進、ありがとうございました。特に△△の進め方は非常に良かったと思います。一方で、タスクのいくつかで納期管理に遅れがありました。次はタスク分解や早めの相談を意識し、一緒に改善していければと思います。」 |
人格ではなく行動に焦点を当て、一緒に解決するという姿勢を示すことが大事です。
ステップ4.次期目標と能力開発の合意形成(約15分)
フィードバックを踏まえ、今後の目標や育成計画を部下と一緒に考えましょう。目標はSMART原則を満たすように設計し、組織の目標と本人の成長意欲の両方を考慮した上で合意を図ります。
なお、SMART原則とは、目標設定において「具体性・測定可能性・達成可能性・関連性・期限」の5つの要素を意識することで、より実行可能で効果的な目標を立てやすくするフレームワークです。
| NG例 | (評価者が一方的に作成した目標に対して)「とにかく頑張ろう」「もっと成長しよう」などといった抽象的な目標設定を促す。 |
|---|---|
| OK例 | 「この半年でさらに伸ばしたいスキルは何だと考えていますか?例えば『プレゼン資料の質を上げる』という観点で、具体的にどのような行動をとればよいか、一緒に整理してみましょう。」 |
OK例では、部下の意向を確認しながら、具体的な目標内容・達成基準・測定方法などについて、対話を通じて明確にしていきます。評価者はあくまで目標設定の支援者というスタンスが大切です。
ステップ5.クロージングとフォローアップの設定(約5分)
評価面談の締めくくりでは、評価内容と合意事項を簡潔に整理し、部下との認識にズレがないか確認しましょう。
合わせて、感謝と期待を改めて伝えることで、前向きな終わり方にできます。次回のフォローアップ時期を明示し、面談が「やりっぱなし」にならないよう注意が必要です。
| NG例 | (要約や確認をせず)「本日はこれで終わりです。」と打ち切る。 |
|---|---|
| OK例 | 「今回の評価は〇〇、次期の目標は△△、アクションとしては□□という内容で合意しました。ここまでの内容で確認や質問はありますか?」 (確認後) 「本日はありがとうございました。今期の成果、本当に立派でした。次期の取り組みにも期待していますし、しっかり支援していきます。まずは来月の1on1で進捗を確認させてください。日程は改めて調整しましょう。」 |
決定事項の相互確認、ポジティブなクロージングメッセージ、そして具体的で約束されたフォローアップの設定により、継続的な支援へとつなげられます。
評価者スキルを高めるには?問いかけ技法とバイアス対策を解説
評価面談の質を高めるには、評価者のスキル向上が不可欠です。ここでは、そのための具体的な施策を紹介します。
フィードバックの質を高める「問いかけ技術の習得」
フィードバックは、一方的な指摘ではなく、部下の気づきを促す対話の場であるべきです。評価面談では、上司からの問いかけが部下の内省を深め、行動の変化につながります。
なかでも効果的なのが、拡大質問と肯定質問の組み合わせです。拡大質問は「はい・いいえ」で終わらない問いで、部下の考えや感情を深く掘り下げられます。肯定質問はポジティブな視点をもとに、努力や工夫に目を向けることで、自己効力感や前向きな意欲を育てます。
| NG例 | OK例(拡大質問・肯定質問に該当) |
|---|---|
| なんでできなかったの? | もし次に同じような状況になったら、どう対応しますか? |
| どうしてミスしたの? | 今回の経験から得た学びは何ですか? |
| 本当に努力しているの? | どんな工夫をしたか教えてもらえますか? |
| 目標達成できなかった理由は? | この取り組みを将来的にどう活かしていきたいですか? |
過去の失敗や原因を直接的に問いただすような質問は、相手を萎縮させてしまうでしょう。具体的なプロセスや努力に焦点を当てることで、自分の行動を認め、さらなる改善への意欲を引き出せます。
公平性と透明性を高める「評価バイアス対策」
評価者は誰でも無意識の偏り(バイアス)を持っています。これを完全になくすのは難しいのですが、低減させる努力はできます。先に紹介したセルフチェックリストと合わせて、組織としても評価者の教育に体系的に取り組みましょう。
- 評価者トレーニングを定期的に実施し、バイアスの理解と評価スキルを養う
- 評価基準を明文化し、評価の根拠を記録として残す
- 他者の視点も取り入れるため、360度評価などを導入する
- 評価会議を設け、評価者間で評価基準のすり合わせを行う
こうした取り組みによって、公平性と透明性の高い評価を実現できます。
評価面談を継続的な成長につなげるには?フォローアップの重要性
評価面談はゴールではなくスタートです。設定した目標やアクションプランが形骸化しないよう、継続的なフォローと、評価面談制度そのものの効果を測定し、改善していくことが重要です。
継続的なフォローアップ設計
上司と部下が毎月実施する成長目標の進捗確認(例:チャレンジ面談)や、目標の中間レビュー、月次の1on1などを通じて、日常的に進捗を確認し、課題を相談し、必要に応じて軌道修正を行います。
こうした継続的な対話により、評価面談の実効性を高めることができます。 数値目標については、客観的な指標で測定し、改善につなげていく姿勢が必要です。
評価面談の効果測定
評価面談が有効に機能しているかどうかは、業務のパフォーマンスを測る指標であるKPIを用いて客観的に測定・分析します。
設定すべきKPIの例としては、以下のようなものがあります。
- 社員満足度調査(特に評価制度に関する項目)
- エンゲージメントスコア(eNPSなど)
- 目標達成率
- 離職率・定着率
- 評価者・被評価者アンケート
これらのKPIを可視化し、人事部門と現場マネージャーが連携して改善策を検討・実行するPDCAサイクルを構築することが、組織全体の評価力と育成力を高めるポイントです。
よくある質問|評価面談に関するQ&A5選
評価面談について、よくある質問を5つにまとめました。
Q1.評価面談は絶対に実施しないといけませんか?
法的に義務ではありませんが、社員の納得感や育成機会の確保、説明責任の観点から多くの企業が導入しています。最近では、処遇の透明性を高める手段としても注目されています。
Q2.評価面談と1on1の違いは何ですか?
評価面談は「成果評価や処遇決定」が主目的のフォーマルな場で、1on1は「日常的な対話と成長支援」が目的の継続的な面談です。両者を併用することで効果が高まります。
Q3.評価面談で部下が納得しないとき、どうすればいいですか?
納得を得るには「評価の根拠を明確に説明する」「感情ではなく行動に焦点を当てる」ことが重要です。相手の意見に耳を傾けた上で、双方が理解し合えるような対話を心がけましょう。
Q4.オンラインで評価面談をする際に注意すべき点はありますか?
通信環境の安定性はもちろん、顔の見える設定や非言語的反応の読み取りを意識しましょう。録画や記録を残す場合は事前に了承を得て、プライバシーにも配慮してください。
Q5.面談の内容はどの程度記録するべきですか?
評価の根拠、フィードバック内容、設定した目標、今後の支援方針などは記録しておくのが望ましいと考えられます。面談記録は後からのトラブル防止や育成支援にも活用できます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
質の高い評価面談で組織成長を加速
評価面談は、単なる査定の場ではありません。「準備」「対話(面談実施)」「フォローアップ」が一体となった、戦略的なコミュニケーションの機会です。
社員一人ひとりの納得感を醸成し、成長意欲を引き出すことで、エンゲージメント向上、ひいては組織全体の競争力強化へとつなげられるでしょう。
テンプレートダウンロード
【無料DL】目標設定・自己評価シート(Excel)
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする