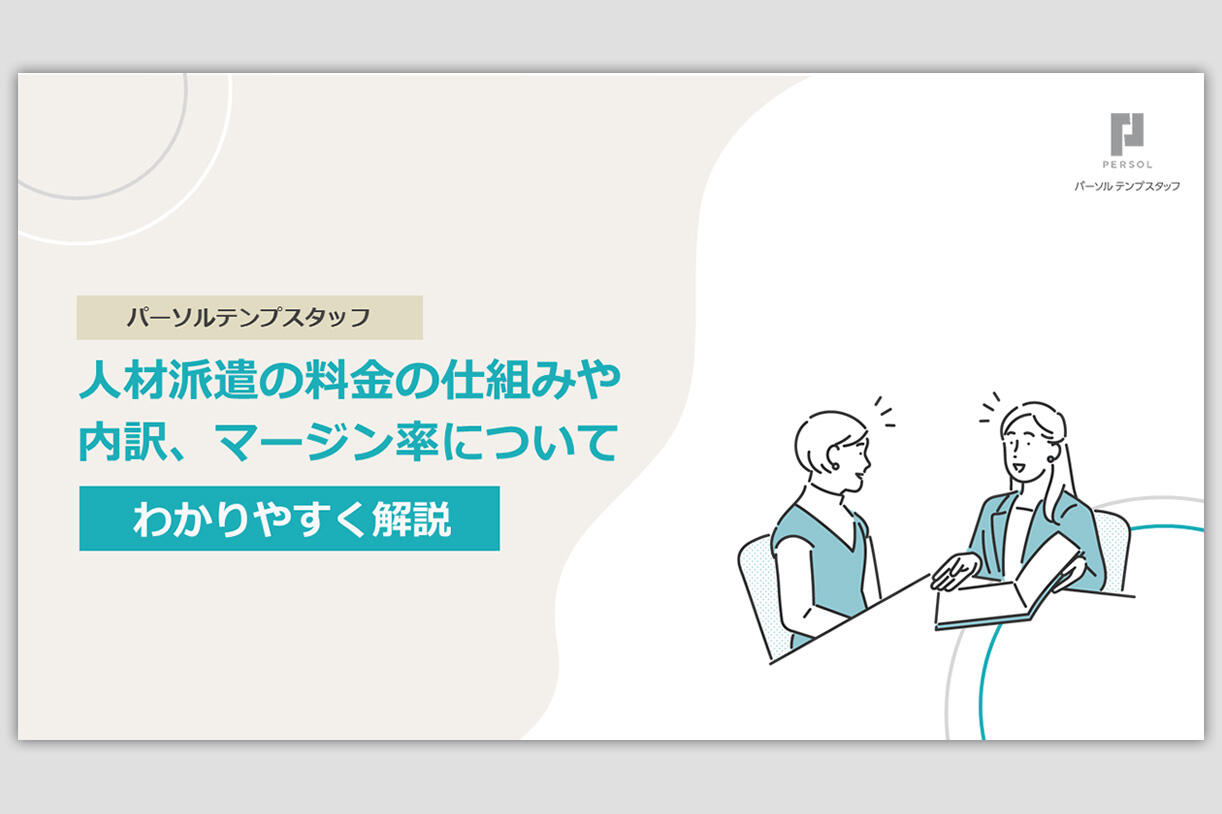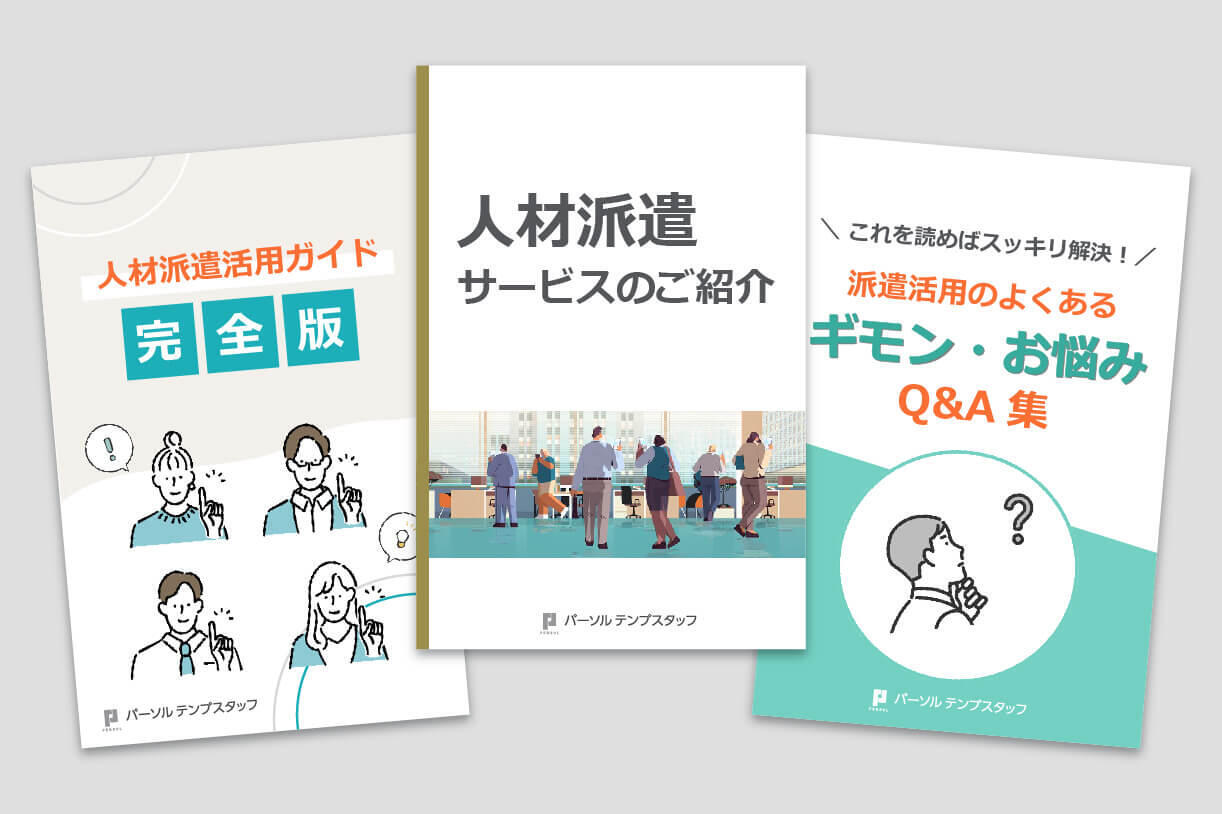HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【企業向け】派遣社員の通勤手当・業務交通費の実務対応と留意点
- 記事をシェアする
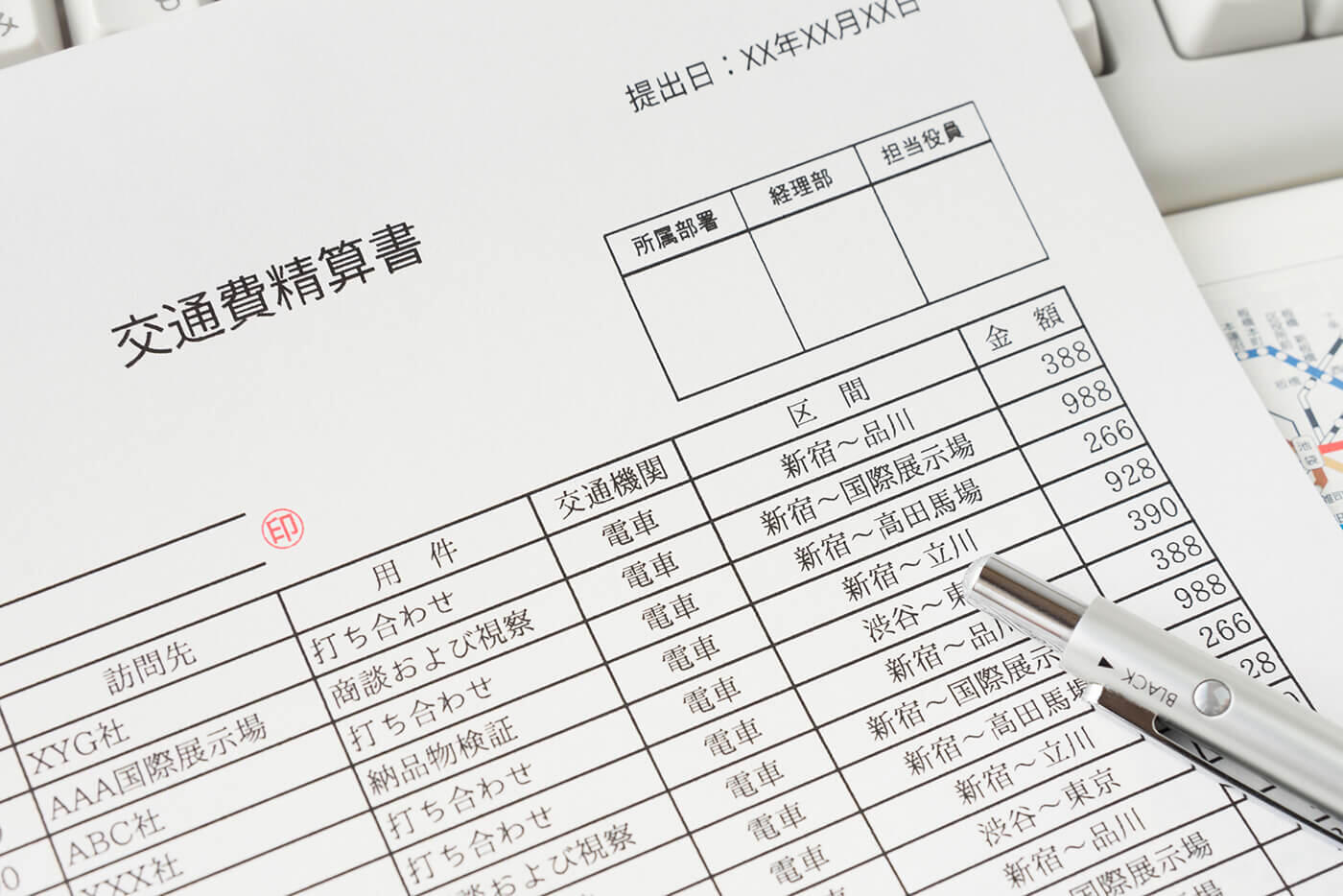
派遣社員に支払う交通費(通勤手当や業務交通費)は、法改正やインボイス制度の影響を受けており、派遣先企業にとって見過ごせない重要なテーマです。
「出張費のインボイス対応はどうすればよいか」「通勤費の取り扱いは契約方式によってどう異なるのか」など、現場でよくある疑問を整理し、対応のヒントをまとめました。
本記事では、2025年8月時点の最新制度を踏まえ、派遣先企業が押さえるべき実務対応のポイントを分かりやすく解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣社員の交通費(通勤手当)は派遣料金に含まれる
2020年に施行された改正労働者派遣法は、「同一労働同一賃金」の原則のもと、派遣社員と正社員との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。この法改正により、派遣社員に対しても通勤交通費(通勤手当)の支給が義務化されました。
これに伴い、人材派遣会社(派遣元)は派遣社員に通勤手当を支給する必要があり、派遣先企業が実質的に通勤交通費を負担することになります。
派遣先企業が派遣社員に直接通勤手当を支給するわけではありませんが、派遣契約の締結時には、交通費を含めた派遣料金単価の取り決めが行われます。このため、派遣先企業としても費用構成の内訳を理解しておくことが重要です。
なお、出張旅費や業務交通費については通勤手当とは別枠の費用となり、契約書上で別途規定するのが一般的です。これらの費用については、インボイス制度の「出張旅費等特例」が適用できるかどうかも合わせて確認しておく必要があります(詳細は後述します)。
労働者派遣法の全体像や改正の背景について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
>>【最新版】労働者派遣法の概要や改正、違反例や企業の注意点を解説
同一労働同一賃金による企業への影響について知りたい方は、以下をご覧ください。
>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣社員の交通費(通勤手当)の決まり方|「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つの支給方法
派遣社員の交通費(通勤手当)は、法令で定める次のいずれかで決まります。
派遣先均等・均衡方式|正社員と同等または均衡の額を支給
派遣先企業の正社員と同等または均衡の額を支給する方式です。派遣先企業は自社正社員(比較対象労働者)の通勤手当額を人材派遣会社へ提供し、それを基準に派遣社員の手当が決まります。
精算フローは以下の4段階が原則です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 派遣社員 → 派遣元へ申請 |
| 2 | 派遣元 → 派遣先へ請求 |
| 3 | 派遣先 → 派遣元へ支払い |
| 4 | 派遣元 → 派遣社員へ支給 |
なお、派遣先企業が派遣社員へ直接支給することはできません。
労使協定方式|あらかじめ決めた金額を支給
労使協定方式とは、人材派遣会社が労働組合(または過半数代表者)と締結した協定に基づいて、あらかじめ決めた金額を支給する方式です。一般通勤手当については、厚生労働省の基準額以上(令和7年度は73円/時)を支給する必要があります。
例えば、1日8時間・週5日勤務の場合、「73円×8時間×5日×52週÷12ヵ月」で月額12,654円が支給額の下限の目安となります。
契約締結時には、「上限額÷平均所定内労働時間(時間)」の計算で時給換算額を算出し、73円を下回らないかを確認してください。なお、計算方法や上限額は、労使間で協議・合意しておくことが重要です。
労使協定方式の詳細や、均等・均衡方式との違いについては、以下の記事をご参照ください。
>>労使協定方式とは?均等均衡方式との違いや派遣先企業に求められるポイント
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の比較表
派遣社員の通勤手当については、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかで支給方法が決まります。
それぞれの特徴やメリット・注意点を、以下の表にまとめました。
| 観点 | 派遣先均等・均衡方式 (実費支給) |
労使協定方式 (定額支給) |
|---|---|---|
| 金額根拠 |
|
|
| メリット |
|
|
| 留意点 |
|
|
派遣先企業は、自社で導入されている方式(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)に基づき、人材派遣会社と契約を結ぶことになります。
その際、申請や支給に関する工数や負担を踏まえながら、契約書には具体的な支給方法や上限金額を明記しておくことが重要です。
派遣先企業が押さえておくべき派遣社員の交通費に関する3つのポイント
2023年10月に施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、派遣社員にかかる交通費の取り扱いが複雑になっています。
具体的には、「通勤手当(派遣料金に含まれる費用)」と、「業務交通費・出張旅費(業務上の立替経費)」とで、消費税の処理方法が異なります。
この対応は、人材派遣会社がインボイス発行事業者として登録されているかどうか、および費用の性質によって変わります。派遣先企業が確実に仕入税額控除を行うためには、こうした違いを踏まえた実務対応が必要です。
ここでは、押さえておくべき3つのポイントを整理します。
引用:国税庁|インボイス制度について
ポイント1.通勤手当を含む派遣料金のインボイス要件を確認する
人材派遣会社が課税事業者である場合、派遣料金(通勤手当相当額を含む)については、登録番号・税率・税額が記載された適格請求書(インボイス)を受領・保存することで、仕入税額控除の対象とできます。
なお、通勤手当が請求書内で一括表示されていても、個別明細であっても、控除の可否には影響しません。
一方、人材派遣会社が免税事業者である場合には、インボイスの発行ができないため、原則として控除は適用できません。ただし、経過措置として、2026年9月30日までは支払額の80%、2029年9月30日までは50%を限度に控除が認められています。
この経過措置が終了すると、仕入税額控除は完全に不可となるため、契約更新時には人材派遣会社が課税事業者への転換を予定しているかどうかを確認しておくとよいでしょう。
インボイス制度の全体像について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
>>インボイス制度を徹底解説!企業に与える影響を改めて確認しよう
ポイント2.業務交通費・出張旅費は「出張旅費等特例」の適用を検討
派遣社員が業務上の出張等において立て替えた交通費や宿泊費などを、人材派遣会社を通じて派遣先企業に請求するケースでは、「出張旅費等特例」の適用が検討できます。
この特例を活用すれば、一定の要件を満たす場合に限り、適格請求書(インボイス)を保存していなくても、帳簿への正確な記載のみで仕入税額控除を受けられます。
特例を適用するための主な要件は、次の通りです。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 対象費用の必要性 | 派遣社員の業務遂行に通常必要と認められる旅費(交通費、宿泊費)、日当などが対象である(人材派遣社員の通勤手当は対象外となる)。 |
| 人材派遣会社からの請求内容の確認 | 人材派遣会社からの請求書等において、当該費用が特例の対象となる旅費交通費等であるかを確認する。費用の内訳が明確になっていることが重要である。 |
| 帳簿への記載 | 派遣先企業の帳簿には、通常の記載事項に加え、この特例の適用を受ける旨、出張した派遣社員の氏名、出張の目的や期間、支払先(人材派遣会社名)、支払年月日、支払額などを記載する必要がある。 |
ポイント3.契約条項と経理フローを整備して控除漏れを防ぐ
| 区分 | 実務対応 |
|---|---|
| 労働者派遣契約書 | 通勤手当:インボイス方式で請求する旨を明記 業務交通費:出張旅費等特例を適用する旨を明記 |
| 経理システム |
|
| 証憑保管 | 適格請求書はもちろん、特例取引の立替経費精算書や領収証・IC利用明細も人材派遣会社経由で回収し、帳簿と紐づけて保存する |
通勤手当については、インボイス制度に則り適格請求書の保存が必要です。一方、業務交通費や出張旅費は「出張旅費等特例」の適用により、帳簿記載のみで仕入税額控除が可能になる場合があります。
加えて、人材派遣会社の課税区分(課税事業者/免税事業者)を定期的に確認し、契約更新時に課税事業者であることを確認しておくことで、仕入税額控除の漏れを未然に防げます。
派遣社員の交通費でよくある質問
派遣社員の通勤手当や交通費の取り扱いに関して、派遣先企業や人事担当者から寄せられる代表的な疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1.派遣社員が公共交通機関の定期券を購入した場合、通勤手当はどう処理しますか?
派遣先均等・均衡方式の場合、定期券代は実費支給が原則です。距離区分や一律額での概算支給は認められていません。派遣社員が購入した定期券の金額を、領収書やICカード履歴などの証憑により確認し、その実額を支給します。
Q2.徒歩圏(例:1km未満)の通勤費を不支給にできますか?
取り扱いは支給方式によって異なります。派遣先均等・均衡方式の場合、合理的な徒歩圏(目安:2km未満)については不支給とすることが認められます。
ただし、その範囲を超える距離については実費の支給が必要です。一方、労使協定方式では、定額支給が前提となり、徒歩圏カットは認められていません。
Q3.マイカー通勤の場合、ガソリン代はどう計算しますか?
派遣先均等・均衡方式の場合、代表的な算定方法は以下の2通りです。
| 方式 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 距離別定額表方式 | 「1km当たり○円」×距離区分表に基づき算出 | 実費算定が難しい場合に限り適用可能 |
| 実費計算式 | 1km単価×往復距離(km)×実勤務日数 | 単価・上限・測定方法を社内規程で明示し、合理性の確保が必要 |
いずれの方式においても、社内規程で単価・上限・測定方法を明記し、合理性を担保する必要があります。
Q4.在宅勤務日は交通費をカットできますか?
在宅勤務で実際に出勤しない日は、不支給または日割り減額が可能です。ただし、その取り扱いを就業規則・派遣契約書・労使協定のいずれかに明記しておく必要があります。
在宅勤務日における交通費の取り扱いは、支給方法によって異なります。
| 支給方法 | 交通費の取扱い |
|---|---|
| 実費支給の場合 | 実際に出勤しない日は、交通費を不支給または日割りで減額できます。ただし、その取り扱いについては、就業規則・派遣契約書・労使協定のいずれかに明記しておく必要があります。 |
| 定額支給(時給に通勤手当を含む)方式の場合 | 交通費が時給に含まれているため、在宅勤務かどうかにかかわらず、時給を変更することはできません。 |
Q5.派遣期間途中で運賃改定があった場合、差額はどう精算しますか?
差額精算の方法は、派遣契約または労使協定の定めにより、以下の2通りが考えられます。
- 運賃改定日にさかのぼって差額を支給・調整する
- 次回契約更新時に改定後運賃を反映する
いずれを採用するかは、契約締結時に条項で明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
- 引用:厚生労働省「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」
- 引用:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金履行確保のためのオンラインセミナー」
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
派遣社員の交通費は法令改正チェックで万全に
派遣社員の交通費については、法令改正のたびに社内規程を見直し、制度に即した運用を徹底しましょう。
通勤手当はインボイス制度に基づき、「適格請求書の保存」が必須です。一方、業務交通費や出張旅費は「出張旅費等特例」により、帳簿記載のみで仕入税額控除を受けられます。
これらの違いを正しく把握し、実務に落とし込むことが重要です。
さらに、人材派遣会社の「課税事業者/免税事業者」区分を定期的に確認し、控除要件を満たしているかを継続的にチェックしましょう。
こうした対応を経理・契約フローに組み込むことで、コンプライアンスの順守・コストの最適化・ガバナンスの強化を同時に実現できます。
人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする