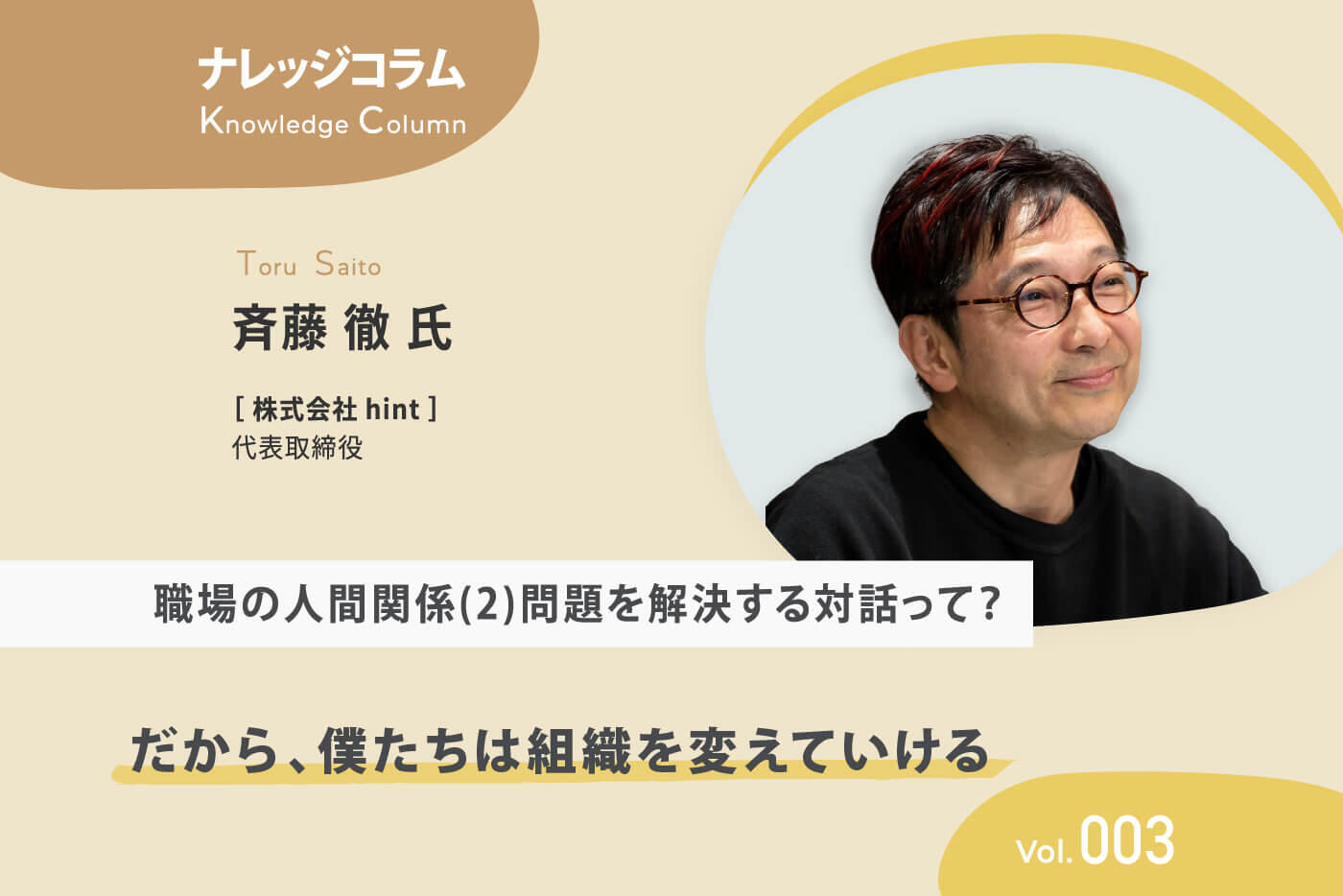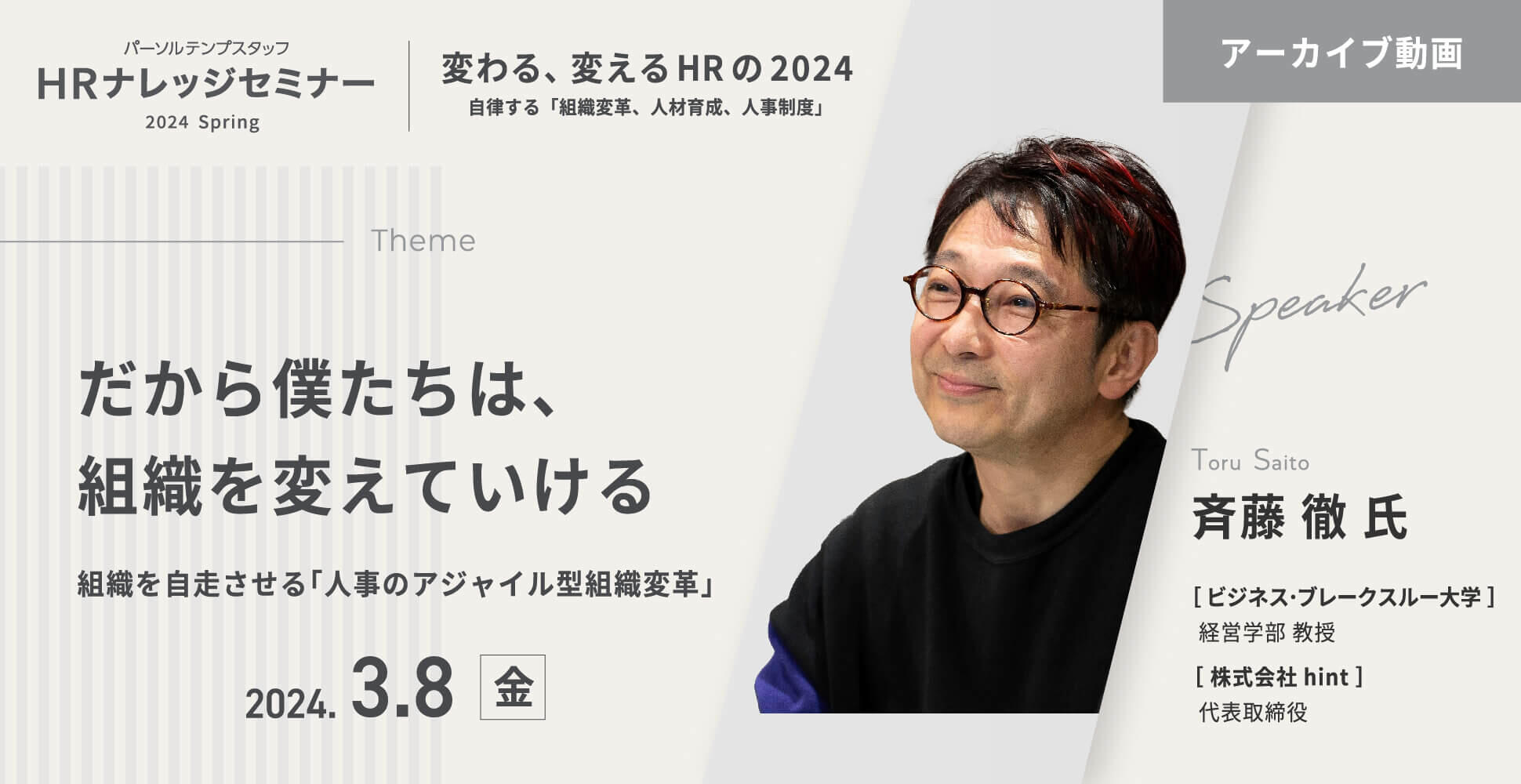HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジインタビュー】
パーソル総合研究所 小林氏
複雑化・加速化していく世間にあらがい、くさびを打ちこむような仕事を
公開日:2025.01.29
- 記事をシェアする
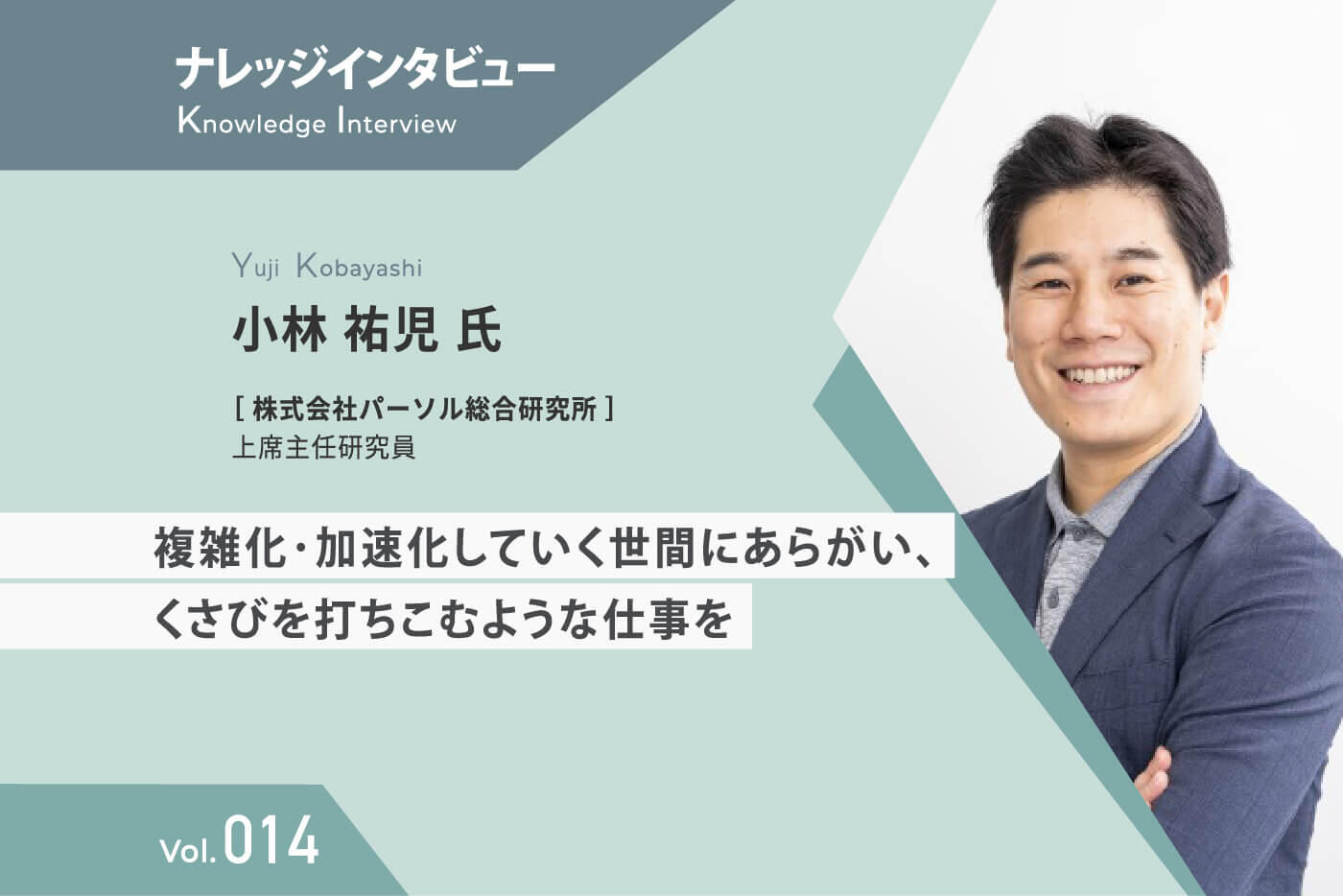
株式会社パーソル総合研究所
上席主任研究員
小林 祐児 氏
今回のナレッジインタビューは、HRナレッジセミナー2024 Autumn DAY2『リーダーシップは誰のもの? ~管理職依存を脱する、フォロワーシップ・アプローチの考え方』の講演をいただいたパーソル総合研究所 小林 祐児氏のイベント後インタビューです。まさに「今」の課題、そして多岐に渡るテーマで研究をされている小林さん。幅広いテーマのそれぞれの現実や本質にどのように着目し、情報収集し、向き合っているのか。また「人と組織」に対する想いを伺いました。
― 小林さんには、今まで「日本型雇用」「テレワーク」「リスキリング」、そして今回は「管理職課題」についてご講演をいただきました。データによる裏付けや背景、そしてこれからの方向やそこに向かう方法などについても具体的にお話いただけて、毎回たくさんの学びがあります。研究テーマの範囲が本当に幅広く、かつ多くを同時進行されていらっしゃいますよね。テーマ選びはどのようにしているのでしょうか。

研究のテーマについては、誰かに依頼をされるということではなく、自分でテーマを出して、予算がとれるかです(笑)。今は「OJT」と「スポットワーク」が目の前で走っていて、分析中です。あと「テレワーク」についても引き続き研究しています。
テーマは、例えばソーシャルリスニング(SNSやブログ、口コミサイトなどのソーシャルメディア上の会話を収集・分析して、マーケティングなどに役立てる手法)で、「労働系のワードは何がどれくらいつぶやかれているだろう」とか「何が増えているのかな」などをランキングで見たりしています。それは、結構、勉強になりますよ。
ちなみに、今年(2024年)で増加率一位のワードはなんだと思いますか。これ、わかったらすごいですよ(笑)。私も「なるほどな」と思いました。
労働、雇用、マネジメント、はたらく系で…特に上半期、何があったかを思い出してみてください…総裁選があったんですよ。一位は「通称使用」です。
選択的夫婦別姓の話でアジェンダセッティングされて、その時に「職場で通称使用できているからいいでしょう」という話があったんですよね。これが増加率一位でした。(なるほど!)以前がそんなに多くなかったということもありますね。
ちなみに二位は「スポットワーク」系でした。この関連は今年とても多かったですね。株式会社タイミーの上場、株式会社メルカリの参入もありました。
― 「スポットワーク」について、どう思われていますか。
現場ではものすごく広がっていると思います。人が埋まるので現場で繰り返し使って、人事がコントロールできないみたいなことにもなっています。
問題はそれがホワイトカラーに行くかどうかですよ。簡単な作業であれば、たまにホワイトカラーでもお願いしたいなということってあるじゃないですか。常時は必要ないけれど、週1ぐらいで事務アシスタントが来てくれたらいいな、呼んだらすぐに来てくれるよ、みたいなことはあるかなとも思うんですね。
― 「今、現場ってこうだね」「でも人事、経営の視点はこうだよね」「でも実態ってこうなっている」というような実態のお話が多く、だからこそ、より説得力があると思っています。そのような実態、現状を知る、わかるということは、すごく大変なことだと思います。どのようにキャッチする、実態をつかんでいるのですか。

ヒアリングとかインタビューや定量データもそうなんですけれど、例えば、現場の現状を知りたいと思ったときに、サーベイでデータをとって、ヒアリングして「こうなんです、現場は」というふうに提出する。それは、「現場の書いてきたアンケート、もしくは現場人事が言っていることが正しい」という前提があるんですね。
しかし、多くの場合それは誤りです。基本的に人というのは、いわゆる氷山モデルで言えば、見えている一番上の部分しか見えていない。
アンケートにはその見えている一番上の部分しか見えていません。その「見えない下の部分がわかるかどうか」に関わるのが、「深い仮説があるかどうか」だと思います。
そうでないとエンゲージメントサーベイが広がったことで、「こういうアンケート・データが出たんです」と、データに振り回される人はすごく多いです。「経営はこう言っています」「現場はこう言っているんですよね」と言うけれども、重要なのは「いや、それであなたはどう思ったんですか」ということです。
ここがあるかないかはすごく重要で、そうした意見や洞察が無いのであれば、いくら調べても無駄だなって思います。だから私は現場にも人事にも話を聞きますし、アンケートも取りますが、ある種どれも一定範囲でしか信じていません。どうせ見えている範囲は、どうしても狭くなるので。
人って、基本的にはやっぱり、自分の言葉と自分の見えている範囲でしかものを語れないので、それよりも「引きの視点をどれだけ持てるか」が重要かなと思います。私がやってきた社会学って、どちらかというとそういう思考形態なので、得意領域かなとは思いますね。
― 「自分の予測がちょっと違っていたのか」というようなことはありますか。
それはよくありますよ。特に多変動解析は予想できない結果の方が多いので、また考え直すっていうことですね。うん。その繰り返しです。
― 小林さんは苦手なものがなさそうなイメージです(笑)好きなこと、苦手なことを教えてください。
お酒を飲む場が好きですね。フィールドワークと称しつつ、週末は日本全国の居酒屋を飛び回っています。苦手なのは互いに空気を読むだけの会議ですね。特にホワイトカラーにおいて会議という意思決定の方法は、生産性が低すぎるので根底からやり方を変えたほうが良いだろうと思っています。『残業学』に具体的な方法は書きました。
― どのような想いで人と組織に向き合っていますか。また、どんなところが好きでこの仕事をやっていますか。
法人という虚構の人格は入れ替えがききますが、そこで働く人の人生やキャリアは入れ替えがききません。集合的なメカニズムを解き明かして法人側を変えることで、入れ替え不可能な領域にまで影響を及ぼすことができるのが面白いところですね。今まで私が書いてきたほぼすべての本は、そういう構造をしています。
― これからのステップをどう考えているか、教えていただけますか。
飽き性ですので、まだまだ研究したいことは幅広くありますし、それと同時に本は書けるところまで書きたいですね。本という物理的メディアは、ネット言説よりも先ほどの「入れ替え可能性」に強い特徴があります。複雑化して加速化していく世間にあらがって、くさびを打ちこむような仕事を続けていきたいですね。
今回のナレッジインタビューはセミナー講演後インタビューではありましたが、その内容そのものからは離れ、小林さんご自身のことを多く伺いました。「小林さんのアタマの中ってどうなっているんだろう」という、純粋な興味からいろいろな質問をさせていただきましたが、さまざまな研究の根本のお話を伺うことができました。
\小林氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2024 Autumn】
リーダーシップは誰のもの? 〜管理職依存を脱する、フォロワーシップ・アプローチの考え方
\小林氏登壇のセミナーレポート無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2024 Autumn】
リーダーシップは誰のもの? 〜管理職依存を脱する、フォロワーシップ・アプローチの考え方
Profile

株式会社パーソル総合研究所
上席主任研究員
小林 祐児 氏
上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。
NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年より現職。
労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行う。
専門分野は人的資源管理論・理論社会学。
著作に『罰ゲーム化する管理職』(集英社インターナショナル)、『リスキリングは経営課題』(光文社)、『早期退職時代のサバイバル術』(幻冬舎)、『残業学』(光文社)、『転職学』(KADOKAWA)など多数。
- 記事をシェアする