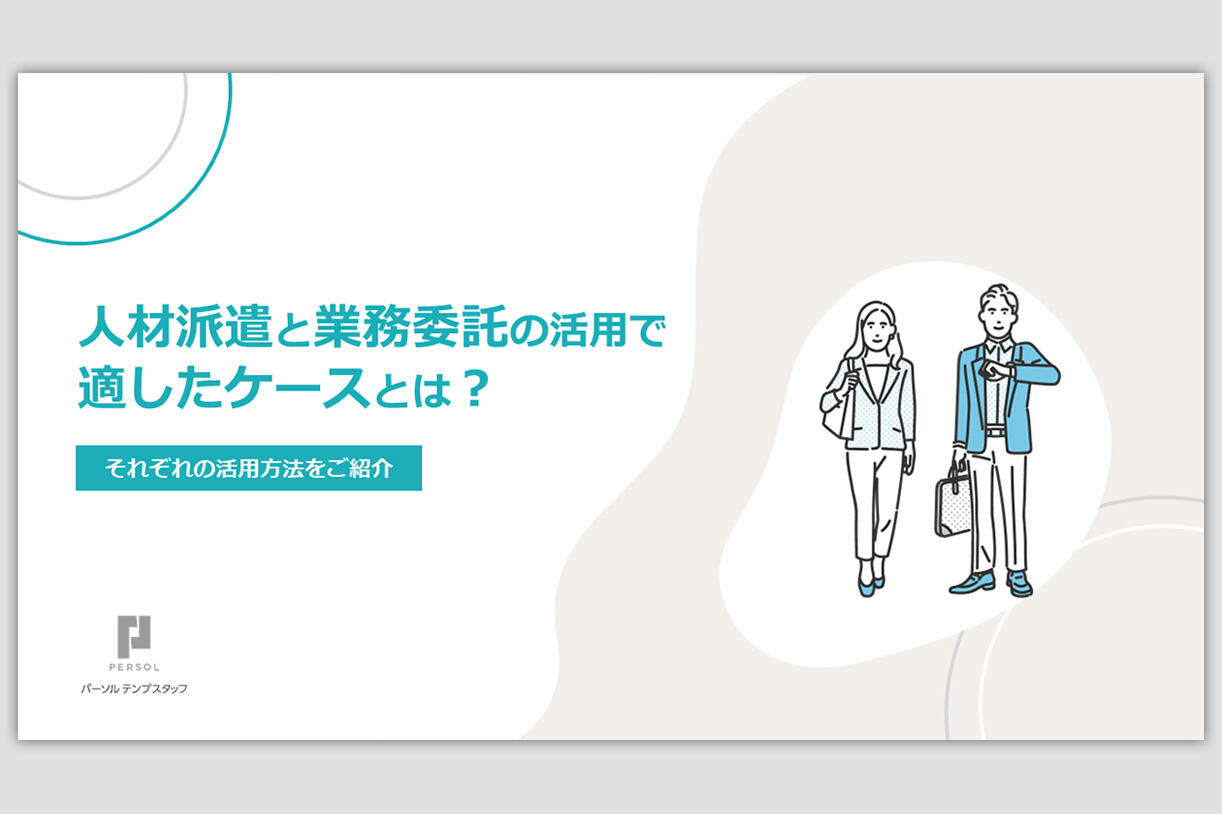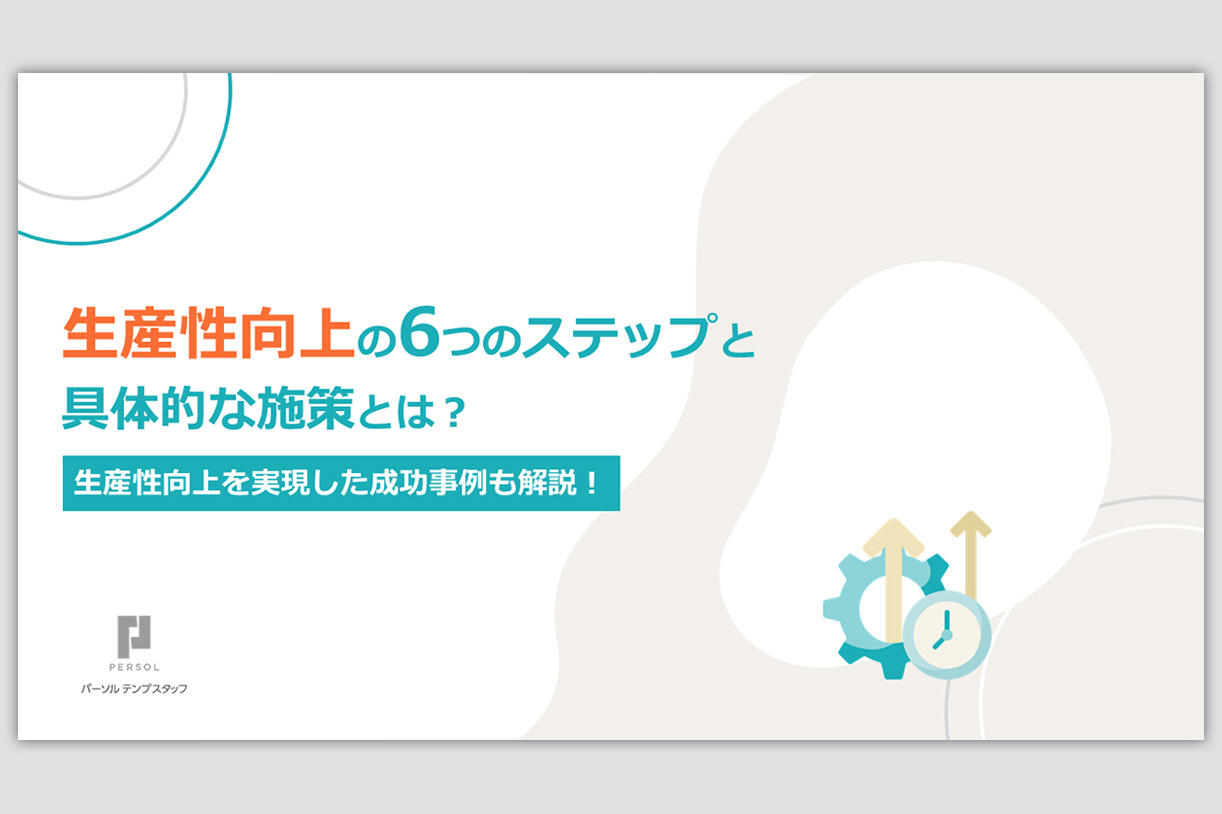HRナレッジライン
カテゴリ一覧
業務効率化とは?手順と成功のポイント、注意点、活用ツールを解説
- 記事をシェアする

人材不足の解消や、働き方改革に伴う時間外労働の抑制のために、業務効率化に向けた取り組みが必要となっています。しかし、
「業務効率化とはどのような施策があるのか」
「どのように取り組みを進めていけばよいのか」
「注意すべきことや知っておいた方がよいポイントはあるのか」
など、悩みや疑問も多いのではないでしょうか。
本記事では、業務効率化とは何か、取り組みにより得られるメリット、取り組みの進め方や具体的な施策について詳しく解説します。取り組みの注意点や効果的なツールもご紹介していますので参考にしてください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
業務効率化とは
業務効率化とは、非効率な業務の改善に向けた取り組みのことを指します。
例えば、非効率的な業務フローの改善や形式的な会議を削減する、スケジュールを見直し無理のないスケジュールに変更する、繁閑の業務量のムラをなくすなどの施策が考えられます。
業務効率化が必要な理由
業務効率化が必要とされている主な理由として、以下の2つが挙げられます。
- 労働人口の減少
- 働き方改革の推進
2018年10月23日公表、パーソル総合研究所と中央大学が共同研究した「労働市場の未来推計 2030」によると、日本の労働人口(生産年齢人口)は減り続けていくことが予想され、2017年から2030年にかけて767万人の労働人口(生産年齢人口)が減少すると試算されています。
また、2019年4月には「働き方改革関連法」が施行され、社員の時間外労働に上限が設けられるなど、人材不足や時間外労働を抑制するため、業務効率化が注目されています。
生産性向上との違い
業務効率化と混同されやすい「生産性向上」とは、投入する「資源(インプット)」でどれだけの「成果(アウトプット)」を得られたか評価する考え方です。少ない「資源(インプット)」で多くの「成果(アウトプット)」を得られれば「生産性が高い」と評価できます。
一方の業務効率化は、非効率な業務を解消し工数やコストの削減に向けた取り組みを指します。業務効率化は業務上の課題に対する「改善」が目的であるのに対し、生産性向上は「成果(アウトプット)」を向上させるのが目的です。ただし業務効率化は、生産性向上をするための施策として、実施されることが一般的です。
つまり、生産性向上は目的(目標)であり、業務効率化はそのための手段や施策の一つといえます。
生産性向上について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
業務効率化を進める3つのメリット
業務効率化を進めるメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 時間・コストの削減につながる
- 社員の意識向上・モチベーションアップにつながる
- 経営資源の最適化につながる
時間・コストの削減につながる
非効率なフローの改善や無駄な業務がないか確認し改善することで、これまでかかっていた工数を削減でき、残業時間の抑制にもつながります。業務の見直し、改善をしたことにより、結果的にミスを減らしたり、質の向上につながったりする可能性もあります。
社員の意識向上・モチベーションアップにつながる
業務が効率化されることで、社員は自身のコア業務に集中できる環境を作りやすくなります。また、自己研鑽に充てる時間も確保しやすくなるでしょう。
結果的に社員のスキルアップや、モチベーション向上につながります。モチベーションの向上は、社員のエンゲージメントを高めることや、社員の定着率向上にも効果があります。
経営資源の最適化につながる
業務効率化によって削減できた工数やコストを、集中したい業務や事業に投資することが可能です。例えば、新規事業の立ち上げや、人材を採用するための採用費用に充てるなど、企業によってさまざまな活用方法があります。
経営資源の最適化ができれば、他社との差別化や企業の競争力強化につながります。
業務効率化の注意点
業務効率化に取り組むにあたって、注意点は以下の2つです。
- ツール導入によるコストやセキュリティリスクの増加
- 社員への周知方法に工夫が必要
ツール導入によるコストやセキュリティリスクの増加
導入するツールによっては、導入費や運用費がかさむものの、業務効率化の効果を実感できない場合もあります。また、サイバー攻撃やアカウントの乗っ取りなどが起きた場合、自社の機密情報が漏えいしてしまうなど、セキュリティリスクが増加することが考えられます。
まずは、ツールを選ぶ前に、具体的にどの程度工数を削減したいかなど目標を設定しておくことが大切です。さらに、ツール導入後は、あらかじめ設定した目標を達成できているか定期的にモニタリングしながら、効果を検証するとよいでしょう。また、セキュリティ対策が徹底されているツールを選んだ上で、自社でもセキュリティリスクへの対策をしましょう。
社員に周知するまでに時間がかかる
業務効率化には、取り組みを行う社員が主体的に進めていくことが重要です。業務効率化に取り組むことを周知し、社員の意識を変えるには時間がかかるため、以下の方法で周知をするとよいでしょう。
- 各事業所に掲示・備え付ける
- 書面で社員に周知する
- ポータルサイトなどいつでもアクセスできる場所に掲載する
パソコンを使用した業務の有無や、出社・テレワークなどの就業体系に左右されないように、すべての関係者の目に留まるように周知することが重要です。
業務効率化の進め方

業務効率化は、「目的を明確にし、課題を洗い出した上で実行する」ことが重要です。
この章では、業務効率化をスムーズに進めるための5つの手順について詳しく解説します。
- 業務効率化に向けた目的・問題意識を共有する
- 現状把握と課題を見える化する
- 課題に優先順位をつける
- 業務効率化の計画を立て実行する
- 効果を検証する
手順1. 業務効率化に向けた目的・問題意識を共有する
目的・問題意識を共有する際は、「なぜ業務効率化に取り組むのか」、「成果として何を期待しているか」などについて認識を合わせます。目的を達成するために何が課題になっているのか、このままの状況が続けばどのような影響があるのかなど、問題意識を関係者と共有することが大切です。
手順2. 現状把握と課題を見える化する
業務の棚卸しを行い、全体像を把握した上で、解決すべき課題の見える化を行います。業務の全体像を把握するためには「業務に携わる社員数」「繁閑の時期」「業務内容」「業務にかかる時間」など、多面的に業務内容を把握する必要があります。
以上のポイントを押さえ、業務の全体像を把握し、課題となる問題点を探します。課題を見つけるポイントとして、以下のような視点で考えるとよいでしょう。
- 担当者によってやり方や所要時間、品質に差が出ていないか
- 仕事の負荷が特定の社員に偏っていないか
- 繁閑の業務量の差が著しくないか
手順3. 課題に優先順位をつける
手順2で発見した課題に優先順位をつけます。すべての課題に対して同時進行で解決していく方法もありますが、現場が混乱するなどのリスクがあります。また新しい業務フローなどが浸透し成果が得られるまでには時間も必要です。
どの課題から解決するかは自由に決められますが、比較的簡単に行えるものや、定期的に発生する業務など、成果を得られやすい業務から行うとよいでしょう。
手順4. 業務効率化の計画を立て実行する
取り組むべき課題の優先順位が決まったら、何を、いつまでに実行するのか計画を立てます。計画を立てる際は、半期または年度で期間を定め、課題に対してどのような施策を行うのかを決めます。また計画と合わせて「〇〇業務の工数を◯時間削減」「残業時間を◯時間削減」など、定量的な目標を計画に盛り込むと、振り返りがしやすくなります。
もし、課題に対しての解決策が分からない場合は、「ECRS(イクルス)」を取り入れてみることも一つです。ECRS(イクルス)とは、業務改善を行うための順番と考え方を下記のように示したものです。
- E【Eliminate(排除)】:業務や工程をなくす
- C【Combine(結合と分離)】:業務を結合する・分離する
- R【Rearrange(入替え)】:工程や担当者を入れ替える
- S【Simplify(簡略化)】:工程や業務を簡略化する
上記のような方法を活用し、可能な限り具体的に施策内容を決定し、実行に移せるようにします。
手順5. 効果を検証する
計画した通りに施策が実行できたのか、成果は得られたのかなどを検証します。振り返りを定期的に行い、「PDCAサイクル」を回しながら、継続的に改善を行うことが効果的です。
業務効率化の10個の手法・アイデア
この章では、企業が抱える課題を直接的に解決に導くための、業務効率化の手法を4つご紹介します。どのような手法を取り入れるかは、業務内容や体制に合わせて選ぶ必要があります。
- 必要な業務を整理する
- 業務ごとの工数を可視化する
- 業務の優先順位をつける
- 業務を一つにまとめる
- 業務のマニュアル・フローチャートを作成する
- データベースを作成する
- コミュニケーションツールを導入する
- 業務を自動化する
- 業務の担当を変更する
- 業務をアウトソーシングする
それぞれ詳しく解説します。
必要な業務を整理する
業務の洗い出しをして必要な業務と不要な業務を線引きし、形骸的に行ってきた無駄な作業や工程を排除することは効率化につながります。無駄があるからこそ業務は非効率的になり、無駄な業務をなくすと空いた時間を他の業務に充てられるようになります。
具体的には、定例だからという理由のみで行われている会議、ほとんど活用されていない資料や報告書の作成などが挙げられます。無駄をなくすコツは、「今の業務は何のために行っているのだろうか」、「今準備していることは本当に必要なのだろうか」と日頃から考えながら行動することです。
もし無駄な業務すべてをなくすことが難しい場合は、頻度を減らしたり、簡素化したり、段階的に減らしていくのもよいでしょう。
業務ごとの工数を可視化する
業務効率化を進める際は、業務を行う上でどの程度の時間・工数がかかっているか可視化してみてください。工数を見直して、どの不要な業務を削減するか見極めることが必要です。「工数」とは、一つの業務を完了するまでにかかる時間と人数のことを指します。
不要な業務や人数を減らし、適切なリソース管理を行えば、原価を減らすことができるため業務効率化につながります。
業務の優先順位をつける
業務の優先順位を設定することにより、業務効率化を図る方法もあります。それぞれの業務の優先順位が明確化し、優先順位の高い業務にリソースを割くことで、リソースの最適化を図ることができるでしょう。
優先順位が低い業務に関しては、今後省略しても問題がないかを検討するとよいでしょう。結果的になくしてもよい業務が見つけやすくなります。
業務を一つにまとめる
複数ある業務を一つにまとめると、手間や時間を削減できて業務の効率化につながります。複数のユニットや担当者で行っていた業務を一つのユニット、または一人の担当者に集約すると、業務の担当者が減って情報共有がスムーズになるためです。また、似たような業務を一度に行うことで作業工数が削減でき、必要な機器やデータの準備も一括でできるようになるでしょう。
「この業務は分ける必要があるのか」という視点を持ち、重複した業務を見つけた場合は、積極的に削って業務の効率化を心掛けていください。
業務のマニュアル・フローチャートを作成する
マニュアル・フローチャートを作成し、属人化を防ぐことで、確認作業の削減やミスを減らせます。マニュアルやフローチャートは、定型業務や頻繁に発生する業務に対して作成するとよいでしょう。図や表を挿入しながら誰が見ても分かりやすいものであることが重要です。
データベースを作成する
データベースを作成し、社内に情報共有することも効率化に効果的です。データベースとは業務遂行におけるデータを蓄積したシステムのことを指します。データベースには顧客情報や予算情報、販売情報、在庫数など、さまざまな情報を蓄積します。
データベースを、業務に携わる関係者全員が閲覧できれば、情報共有の手間が減ります。データは分類ごとに管理することで、どこにどの資料があるか分かりやすくなり、資料を探す工数の削減にもつながります。
また、管理するデータの閲覧・編集権限を適切に設定することで、承認作業を省略し工数を削減できたり、個人情報や機密情報を取り扱う社員を限定できるため、セキュリティ対策にもなります。
コミュニケーションツールを導入する
チャットツールの導入でスムーズな意思疎通が可能となることや、WEB会議システムの導入で出張や移動が不要となり時間を有効活用できるなど、さまざまな効果があります。
チャットツールやWEB会議システム以外にもたくさんのツールがあるため、利用する目的を決め予算内に収まるか、自社に適しているかを見極めた上で導入するとよいでしょう。
業務を自動化する
業務内容を見ていくと、毎日のように繰り返されているマニュアル化しやすい業務もあります。必ずしも人間が行わなくてよい類の業務は、自動化することで効率化できます。
例えば、入力したデータをもとにいつも同じ式で計算を行っている場合、Excelのマクロを活用することにより、ワンクリックで処理できるようになります。また、膨大な量の顧客情報の整理・収集は、RPAによる自動化で個々の顧客へのアプローチが適切に行えるようになります。カスタマーサポートなどの業務では、定型的な質問への対応をAIのチャットボットに切り替えることで業務効率化が図れます。
さらに、人間が行っている業務を自動化することによって、ヒューマンエラーが低減するという効果も期待できるでしょう。
RPAについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
>>RPAとは?注目されている背景やメリットをご紹介
業務の担当を変更する
社員によって、経験値や得意不得意、保持するスキルは異なります。それぞれの適性を考慮した上で、それぞれの得意な分野を最大限に生かせる業務担当を割り振ったほうが業務効率は上がるでしょう。実際に担当者の変更により、業務がスムーズに流れるようになったというケースは珍しくありません。
例えば、コミュニケーション能力が高い社員は営業部門に、製品事情に詳しい社員はマーケティング部門に、ITスキルが高い社員は情報システム部門に、英語が得意な社員は海外部門に配置するといった調整を行ってみましょう。業務の担当者を適切な部門に配置することで、さらなる業務効率化が期待できます。
業務をアウトソーシングする
アウトソーシングは、一般的に自社の業務に必要な人的資源やサービスを契約によって調達し、生産性向上や競争力強化などを目指す経営手法を指します。主に業務単位、または前後のプロセスも含め、外部企業に委託します。
アウトソーシングを活用することで、社員の業務負荷の削減や、繁閑期の業務量のムラを解消できます。
アウトソーングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
>>アウトソーシングとは?活用メリットや導入時のポイントをご紹介
業務効率化を成功させるためのポイント

業務効率化を成功させるためのポイントは、以下の4点が挙げられます。
- 業務効率化に取り組むための事前準備を十分に行う
- 社員に定着させやすい手法・アイデアを採用する
- 業務効率化そのものを目的化させない
- 効果の検証・フィードバックを丁寧に行う
業務効率化に取り組むための事前準備を十分に行う
施策を実行する前に業務効率化の目的を明確にし、社員へ周知する必要があります。その上で業務を見える化し、課題を洗い出し、具体的に取り組む手法、計画を立てます。
事前準備を行っていない場合は、目的がずれたり、取り組みが中途半端になってしまったりするリスクがあります。施策を実行するタイミングは、繁忙期を避けるなど、社員が業務効率化に取り組みやすい環境を整備した上で行いましょう。
社員に定着させやすい手法・アイデアを採用する
例えば、業務効率化のためにITツールを導入したとしても、社員がツールを使いこなせなければ効率化が図れません。そのため、手法を決める際は、関係者の意見を反映させることをおすすめします。
業務効率化そのものを目的化させない
業務効率化はあくまで手段であるため、目的を明確にして業務効率化に取り組む必要があります。業務効率化を優先するあまり、コストや工数が増加しては本末転倒です。
業務効率化を行う目的を周知し、認識を合わせることが必要です。
効果の検証・フィードバックを丁寧に行う
効果の検証やフィードバックができなければ、施策が成功しているのか、改善するべき点はないのかなどの判断ができません。綿密に計画を立てても、想定外のトラブルが発生したり、思うような成果につながらないこともよくあります。
PDCAサイクルを回しながら、継続して改善に取り組み、一つずつ課題を解決していきます。
業務効率化の効果検証方法
効果的な業務効率化を行うには目標を設定して、さらに行った施策の効果を検証することが大事です。具体的には、以下のような流れです。
- 現状の数値を把握する
- KPIを設定する
- 効果測定の期間を設ける
- 設定したKPIと比較し考察する
STEP1 現状の数値を把握する
業務効率化に限らず、仕事の成果を測る際は数値化することが基本となります。業務効率化を行う際は、あらゆる職種の現状を数値化しましょう。そうすれば、あとはその数字をいかに目標へ近づけるかに注力できます。なかには数値化が難しい職種もありますが、できる限り客観的指標を設けて、それを基準に数値化してください。
STEP2 KPIを設定する
業務効率化を達成するためには、目に見える目標をベースにします。「残業を減らす」「費用を削減する」といったあいまいな目標設定では、業務効率化が達成できているか検証することは困難です。業務効率化の目標は、「〇%アップ」「〇時間削減」など具体的な数字に落としこむことが大事です。目標を数値化することで、業務効率化の達成の度合いを客観的に把握できます。
業務効率化の目的ごとの指標を数値化する際、利用されることが多いのは「KPI」です。KPIとは「重要業績評価指標」を指し、目標達成の度合いを測るものさしだと考えればイメージしやすいでしょう。KPIには「粗利率」「営業利益率」「人件費」「人件費率」などさまざまな種類があり、いずれもデータに基づいた根拠のある数値であることが重要です。
業務効率化の目的に適したKPIを設定するには、前年度のデータをもとに数値を決めることが一般的です。漠然と「経費削減」という目標を掲げるのではなく、「○○費を前年度より15%削減」「客単価を従来の1.5倍に」「会議の回数を〇回に削減」といった形で設定しましょう。
STEP3 効果測定の期間を設ける
業務効率化を目指す際は、「来年までに〇%アップ」「半年後までに〇時間削減」など期間を具体的な数字に落としこむ必要があります。期間をしっかり区切ることにより、設定した目標に対する達成の度合いを客観的に把握できるからです。
STEP4 設定したKPIと比較し考察する
KPI運用開始後は、日、週、月、四半期ごとなどの単位で定期的に達成の度合いを測定し、施策を期間ごとに評価することが重要です。計画通りの効果が出ていなければ、改善策を立案して実行していくことが求められます。
業務効率化に役立つツール
業務効率化に役立つツールとして、チャットツールやファイル共有ツールなどがあります。チャットツールはメールに比べると、手軽にやり取りができるためコミュニケーションスピードの向上、コミュニケーションコストの軽減ができます。ファイル共有ツールの場合は、メールにファイルを添付するよりも大きいサイズのデータの受け渡しが可能です。これまでメールに添付するためにサイズダウンをする作業を行っていたのであれば工数の削減になります。
例えば、パーソルグループでは、以下のような業務効率化を支援するツールもご提供しています。
【MITERAS
勤怠】
MITERAS勤怠は勤怠状況をリアルタイムで可視化できるツールです。はたらき過ぎている社員へのアラートや、社員のコンディション確認、工数管理やシフト管理などが1つのツールで完結します。多忙なマネジメント層社員の業務効率化に適しています。
【Bizer team】
Bizer
teamは、チームの進捗状況などを管理できるツールです。チーム内で個人のタスクを共有し、タスクに対するコメントやファイル共有などのやり取りもツールの中で完結します。その他、業務の細かい手順のリスト化やファイル管理、工数管理などの機能もあります。
このように、さまざまな種類のツールがあるため「自社の課題を解決できるのか」「自社の社員が使いやすいものか」などを踏まえて、ツールを選んでください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
業務効率化のご相談ならパーソルテンプスタッフへ
今回は業務の効率化を成功させるポイントや、具体的な注意点について解説しました。社員の負担を軽減して組織的な生産性向上が期待できるため、企業運営を見直す際には「業務効率化」を意識しましょう。
一方で業務の効率化を適切に進めるためには、現状把握や施策立案について正しい調査や慎重な検討が必要です。組織運営の問題を見誤れば業務効率化のための費用がかさみます。また新たな施策として推進するためには、旗振り役の社員やチームが必要になります。組織風土によっては既存の業務フローを変えづらい場合も考えられるでしょう。
業務効率化でお困りのことやご相談がありましたら、是非お気軽にお問い合わせください。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする