HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジコラム】
対話からはじめる本気のDE&I推進 vol.001
育休復帰社員への対応は、忖度 じゃなく本音を聴き、後押しすることが大切!
公開日:2022.11.28
- 記事をシェアする
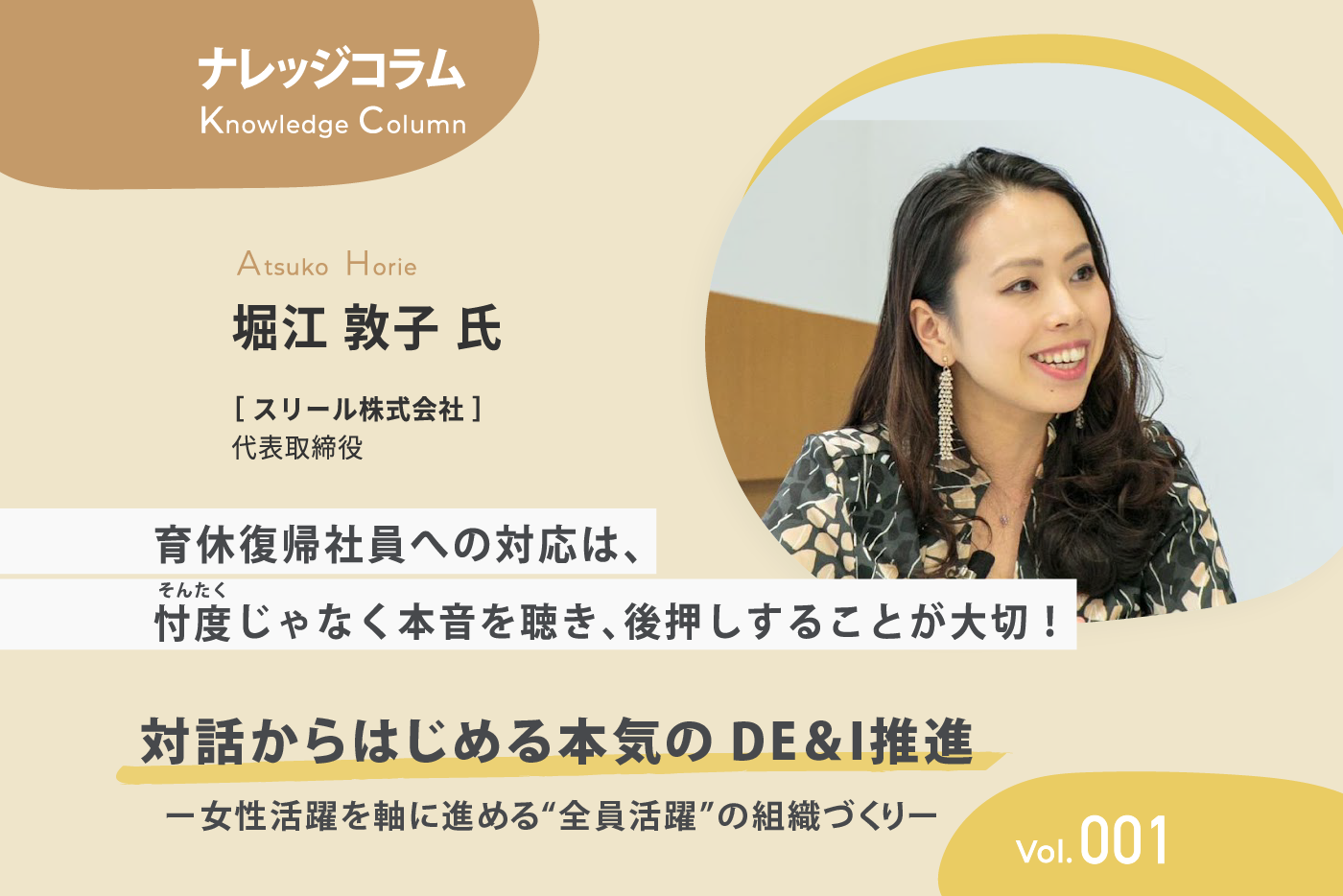
スリール株式会社 代表取締役
堀江 敦子 氏
さまざまなHRエキスパートによるナレッジをお伝えするコンテンツ『ナレッジコラム』。
スリール株式会社 代表取締役の堀江 敦子氏による「これからの女性活躍推進」に向けたメッセージを4回連載でお届けします。
女性活躍推進法等の一部改正や育児・介護休業法の法改正など、2022年は会社や人事にとって自社の女性活躍推進を改めて考える重要な年になりました。
最近では、人的資本への重要性も高まるなど、「女性活躍推進」を目指す流れは大きな波となって社会を変化させつつあります。それを裏付けるように、えるぼし認定*企業は2022年9月の時点で全国1,906社に上りました。
私は2010年にスリール株式会社を創業し、長年「女性活躍推進」に携わってきました。その中で強く感じるのは、「女性活躍推進」は一筋縄ではいかないということです。
制度を整えさえすれば、女性活躍が推進されていくと考える企業の方は少なからずいらっしゃいます。ただ、私が声を大にして言いたいのは、制度を充実させるだけでなく女性活躍推進が実現できる土壌、つまり組織と個人の意識変革が必要であり、それは一朝一夕には実現しないということです。人事として制度を創ったから、施策を行ったから手放してしまうのではなく、最低でも3年~5年、状況に合わせて変化させていきながら根気強く取り組んでいくことが重要です。従業員の声を聴きながら本質的にブラッシュアップし続けていけば、3年間で成果は出てきます。
昨今では、女性活躍も含めた多様な人材が活躍できることを掲げる「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)」という考え方が浸透しつつあります。ダイバーシティという観点の第一歩として「女性」は重要な位置付けであり、DE&I推進を目指すならば女性活躍から展開していくことが重要です。女性活躍を推進する上では、確実に「働き方の柔軟性」と「公平な評価」、そして育成支援を行う必要がありますが、これらはすべて社員が活躍する上で重要なポイントです。
とはいえ「何から始めたらよいのかわからない」「取り組んでいるけれど、効果を感じられない」という声をよくいただくのも事実。そこで、スリールで提供する研修やコンサルティングも参考にしながら、人事の方に知っておいてほしい、すぐに役立つ情報をお伝えしていきたいと思います。
*えるぼし認定:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度。
育休復帰社員への対応は、 忖度 じゃなく本音を聴き、後押しすることが大切!
春は、保育園入園とともに育休取得中の社員が復帰してくる季節です。「女性活躍推進」を語る上で、女性社員が出産・子育てというライフステージをどう捉えるかは企業にとって大きな要素であり、特に復職のタイミングはキャリアを形成する上で重要なフェーズと言えます。また最近では、男性も含めて育休を取得し、パートナーと共に育児を行っているケースが多くあります。
育休から復帰したものの、モチベーションが下がっている。また上司も扱いに困っている。そんな状況はありませんか?こういったケースは、本人の意識の問題だけではありません。上司の固定観念や、人事の働きかけが足りない事により影響している場合も多くあります。
「お子さんがまだ小さいから時短勤務で責任の軽い仕事が本人もいいだろう」
「子育て中だと、大きなプロジェクトは荷が重すぎるかな」
「時短勤務を希望しているから、忙しい部署には配属できないな」
こういった判断を、良かれと思って当事者本人にヒアリングすることなく決定したことはありませんか?
実はこういった “忖度” が子育て社員を逆に悩ませているかもしれません。
「復帰後も以前の部署でバリバリ働きたかったのに、別の部署に異動になってしまった」
「大きなプロジェクトを経験したいが、時短勤務のためアサインされない」
「同期がどんどんキャリアアップしていくのを見ていると、モチベーションが下がる」
こんなモヤモヤを抱えていると「もっと活躍したい」という想いを持っていたとしても、「私には無理なんだ」と諦めてしまうことにつながります。
では、どうしたらいいのでしょう?
大切なのは、当事者本人の状況をよく理解し、その上で仕事やキャリアに対してどう思っているか“本音”を聴くことです。ここでは、育休復帰社員との面談を効果的に進めるためのポイントをお伝えしていきます。

育休復帰社員との面談のポイント
育休復帰社員との面談を行う際、大切なのは話を聴くための空間づくりと、話を聴くという姿勢です。人事や上司が気をつけておきたいことについて、解説していきます。
心理的安全性を確保する
・プライベートな話ができる空間の用意
育休復帰について面談する際は、プライベートな話も多くなります。周囲の環境に配慮し、会議室などを用意しましょう。
・対話の意識を持つ
人事のほか、上司が立ち会う場合も多いでしょう。当事者から本音を引き出すという意識で、尋問的に質問をたたみかけるのではなく、あなたを期待し働き続けて欲しいからこそ“話を聴く”という姿勢で対応しましょう。
伝えるべき自社の制度を整理する
育児期には法律で定められたさまざまな制度があります。「短時間勤務制度」「所定外労働・時間外労働・深夜残業の制限」「子の看護休暇」などです。また、これらに紐づいた企業での制度もあるかと思います。育休復帰直後の面談では特にしっかりと当事者に伝えましょう。
ヒアリングシートを用意する
面談時に必要なこととして、人事や上司は制度を説明するだけではなく、育休復帰社員に対して「何をどのように期待しているのか」を伝えることが大切です。また、育休復帰社員からも自身の状況を開示してもらい、本当はどうしたいのかといった希望や「なりたい姿」についてもヒアリングすることが重要になってきます。
ただし、面談時に急に希望や将来について質問をしても、育休復帰社員が答えられないこともあるでしょう。あらかじめ面談で聞きたいこと、伝えてほしいことをシートにしておくと面談がスムーズになります。「育休復帰社員の現状」「配慮してほしいこと」「将来の展望」などを含めておくとよいでしょう。また将来の展望は、「すべての物事が上手く行ったと仮定したらどんなことがしたいか?」などと聴いてみるとよいかもしれません。

人事・上司の方に知っておいてほしい“育休復帰社員のキモチ”
育休から復帰する社員は、初めて場合は子育てと仕事の両立に不安を持っている方もいます。仕事を頑張りたいけれど、どのようにバランスを取ればいいかわからない、先のことは不安だけれど何から始めていいかわからないといった将来に対する不安です。
さらに女性の特徴として、仕事やキャリアについて考えるとき、プライベートや周囲との関係なども同時に考えてしまい120%頑張らなければいけないと思ってしまう傾向があります。悩みに対して整理と交渉が苦手な面もあり、悩みが複雑になりがちです。
また、育休復帰社員を悩ませる要因に、周囲の固定観念があります。「育児中だから今までの様にできないだろう」と決めつけたり配慮しすぎてしまうのは、頑張りたいという育休復帰社員の気持ちに寄り添えていないかもしれません。
育休復帰社員もそれぞれに想いや背景があり、仕事やキャリアへのアクセルを踏む時期もさまざまです。会社として希望している部分をしっかりと伝えつつ、育休復帰社員の想いをヒアリングすることで、建設的に話を進めることができるでしょう。
育休復帰者を活躍人材にするヒアリングシート
面談前にヒアリングシートを用意しておくという話は前述した通りですが、スリールがおすすめするヒアリング項目について特別にお伝えします。スリール株式会社の「復職後面談準備シート」からも無料でダウンロードできますので、ご興味のある方はダウンロードしてみてください。
※スリール株式会社様のWebサイトとなります。
育休復帰社員の現状について
・現在の壁・懸念点
現在不安に思っている点、自身では解決できない壁や懸念点を共有してもらいましょう。
・懸念点に対して、意識的にやってきたいこと
育休復帰社員が懸念点に対して、どのように取り組んでいるかがわかればサポートについても明確化できます。
配慮してほしいこと
・自分ではどうにもならなそうなこと
子どもの体調やパートナーの仕事についてなど、プライベート面で当事者が行き詰まっている点を伝えてもらいましょう。育休復帰社員が悩んでいることが、制度や上司の対応で解決できるかもしれません。
・上司や職場でどんな協力・理解があれば、前向きに進めそうか
育休復帰社員から自身の希望を伝えてもらうことで、必要な体制を整えたりと対策を検討できます。
将来の展望
・3年後の理想のキャリアの状態(なりたい姿)
育休復帰の段階では、目の前のことに視線が向きがちです。将来を考える上で、少し先の未来である3年後をイメージしてもらいます。キャリアについての本音を知ることができます。
・面談で達成したいこと
面談において自信が期待していること、伝えておきたいことや理解してほしいことなどをあらかじめ整理しておくことができます。
ヒアリングシートは面談を行う上で、無理なく「自己開示」と「ヒアリング」ができるツールです。育休復帰者にシートを記入しながら事前に整理をしてもらうことで、必要なポイントを押さえた面談・コミュニケーションが可能になります。こういったツールは育休復帰者だけでなく、介護など制約を持った社員へのコミュニケーションにも有効です。ぜひ効果的な面談を進めていってください。
▼バックナンバーはこちら
vol.002:子育て社員も、関わり方を変えることで活躍人材になる!
vol.003:若手社員が抱えるモヤモヤの正体と定着率向上のカギ
vol.004:人的資本経営のカギは「女性活躍推進」である理由
\堀江氏登壇のセミナーレポート無料配布中!/
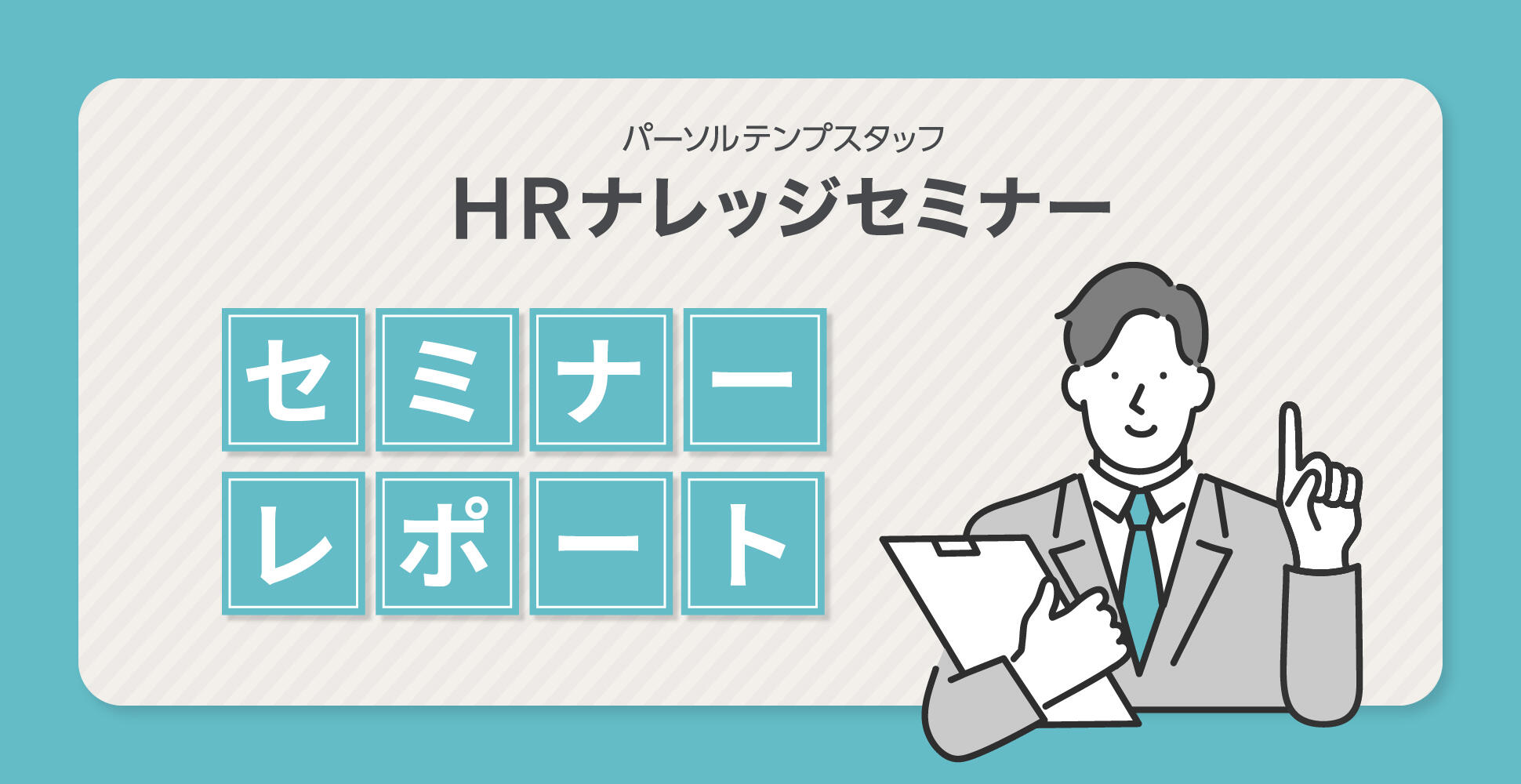
【HRナレッジセミナー2021 Winter】
HRが取り組むNEXT課題ー変化の中でも人を活かす・人が活きる組織へー
Profile

スリール株式会社 代表取締役
堀江 敦子 氏
2010年に創業してから一貫し、女性活躍から始めるサスティナブル経営の実現に向けた支援を多方面(企業/国・地方自治体/大学)に実施。企業に対しては、独自開発した体験型プログラムを中核に、人材教育・人材開発コンサルティング事業を展開。その他、内閣府男女共同参画局 専門委員として第5次男女共同参画基本計画の策定に関わるなど、政策実現に向けて精力的に活動する。日本女子大学社会福祉学科卒業。立教大学大学院経営学研究科(博士前期課程/リーダーシップ開発コース)修了。厚生労働省 イクメンプロジェクト委員、こども家庭庁設置法案等準備室委員、千葉大学 非常勤講師を務める。著書に『新・ワーママ入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)がある。
- 記事をシェアする








