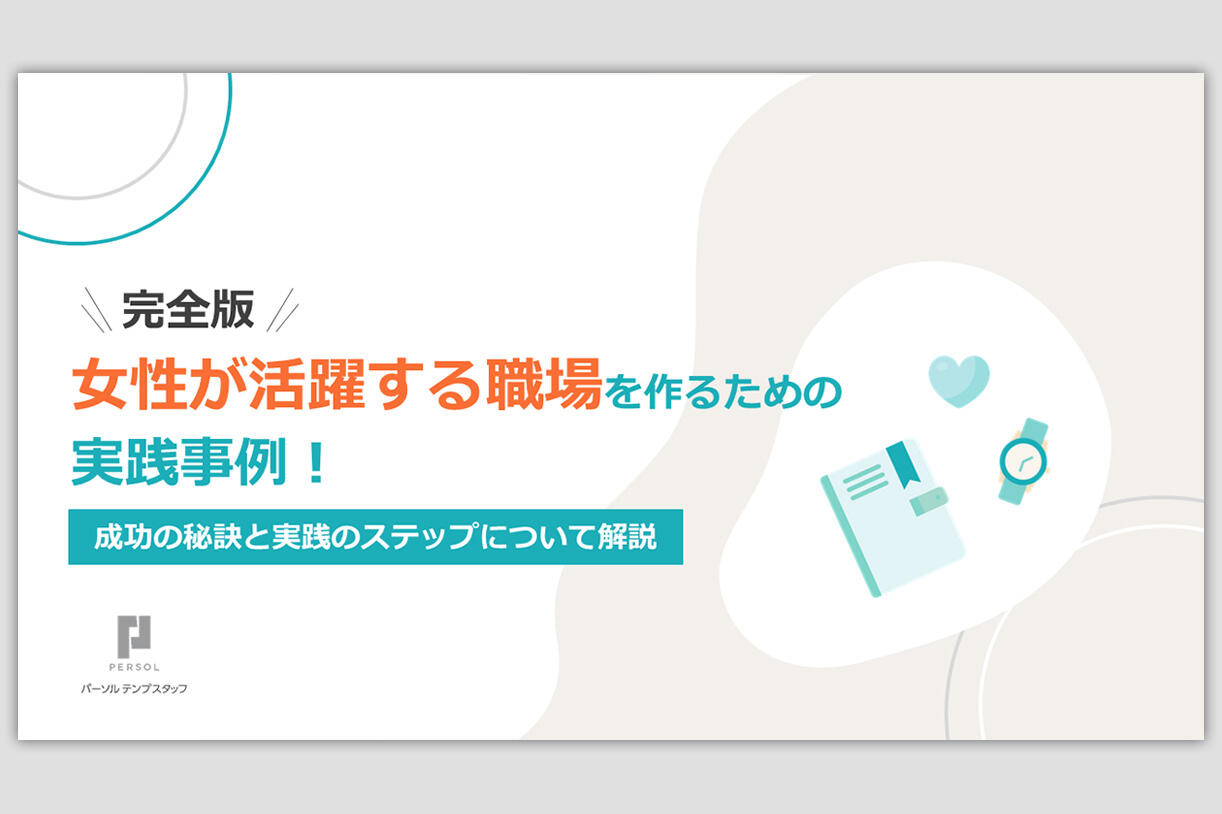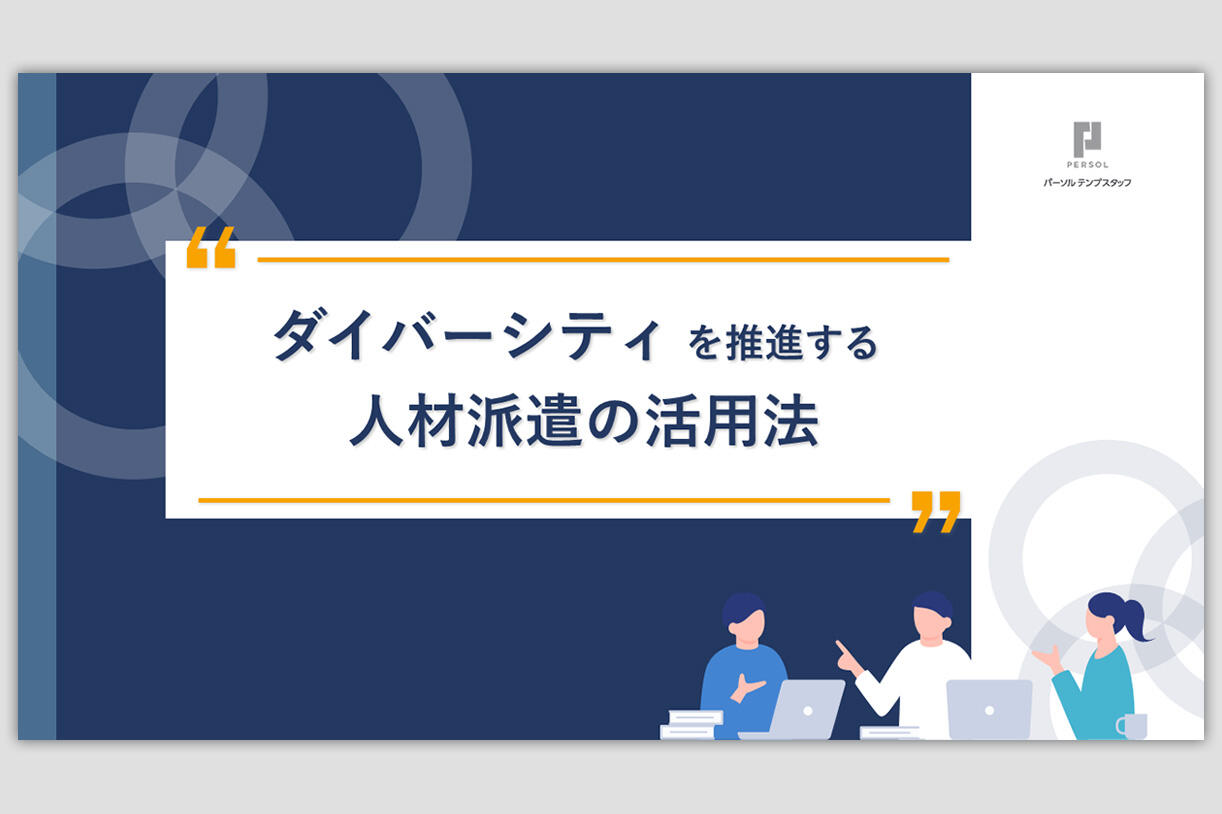HRナレッジライン
カテゴリ一覧
女性活躍推進法の改正内容と企業の対応ポイント|企業が取り組むべきこととは
- 記事をシェアする

女性活躍推進は、はたらきたいと思っているすべての女性が、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指す一連の取り組みのことを指します。労働人口が減少している日本において、人材不足解消の1つの方法としても注目されています。また、女性活躍をさらに後押しするために、女性活躍推進法は2022年4月に改正されました。
そこで本記事では、女性活躍推進の定義や女性活躍推進法の概要、男女共同参画との違い、取り組みで得られるメリット、改正内容、取り組みでのポイントなどについて詳しく解説します。
目次
- 女性が活躍する社会を目指す「女性活躍推進」とは
- 女性活躍推進の4つのポイント
女性が活躍する社会を目指す「女性活躍推進」とは
女性活躍推進とは「はたらきたい女性がその個性と能力を十分に発揮し活躍できる社会」を目指す一連の施策のことをいい、労働人口が減少している日本において、重要な取り組みとなっています。
2016年4月に「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が制定され、ますます女性活躍に向けての動きが注目されています。
女性活躍推進法では、女性が職場で活躍できる環境・制度を整え、安心して働き続けられる仕組みづくりが実現できるように、企業に対して3つの取り組みが義務化されています。
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表
- 女性の活躍に関する情報公表
女性活躍推進法の制定当時は「301人以上の労働者を雇用する事業主」が対象でしたが、2022年4月の法改正で「労働者101人~300人の中小企業」も対象となり、取り組みが必要な企業が拡大されました。
女性活躍推進を「見える化」する内閣府の取り組み
女性活躍推進の具体的な状況を把握し、課題解決につなげるための情報源として、内閣府男女共同参画局が運営する「女性活躍推進法『見える化』サイト」というWEBサイトがあります。
このサイトでは、女性活躍推進法に基づき、国家公務員や地方公務員における女性の採用・登用状況、男女別の育児休業取得率、職員の男女間給与の差異などが「見える化」されており、各組織の取り組み状況が明確に示されています。
これは、企業や地方公共団体が自社の女性活躍推進の現状を客観的に把握し、さらなる改善に向けた具体的な行動計画を策定する上で、有益な情報源となるでしょう。具体的には、女性の採用や登用の促進、男女間の給与格差の是正、そして育児休業の取得推進といった効果が期待されています。
※参考:「女性活躍推進法『見える化』サイト」
「女性活躍推進」「男女共同参画」のそれぞれの定義と違い
国や企業が女性活躍への取り組みを積極的に行う中で「女性活躍推進」と「男女共同参画」の違いがよく分からない、という方も多いのではないでしょうか。
女性活躍推進と男女共同参画は、制定されている法律や目的、取り組み方法が異なります。以下では、女性活躍推進と男女共同参画の違いについて解説します。
男女共同参画社会、5つの基本理念
男女共同参画社会とは「男性」「女性」など性別にとらわれず、一人ひとりが個性や能力を発揮できる社会のことを指します。仕事だけではなく家庭、地域などあらゆる分野で性別による差別をなくすことを目的としています。
国は男女共同参画社会を目指すために、1999年に「男女共同参画社会基本法」を制定しました。男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会を実現するための基本理念として5つの柱を掲げています。
※引用:男女共同参画局|「男女共同参画社会」って何だろう?
5つの柱では、男女共同参画社会を実現するために、行政と国民それぞれが行うべき役割が定められています。
女性活躍推進とは「女性のワークライフを充実する」施策の一つ
女性活躍推進とは「仕事を通して女性の活躍を推進する」ことを目的としており、以下の3つの基本原則があります。
- 『女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること』
- 『職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること』
- 『女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと』
※引用:厚生労働省|女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要
女性活躍を推進するために、国や企業では、はたらきたい女性が個性や能力を十分に発揮できる職場づくりや、仕事と家庭を両立できる制度づくりが重要となります。
女性活躍推進と男女共同参画の違い
女性活躍推進と男女共同参画の主な違いは「法律」「目的」「取り組み方法」の3点です。それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 女性活躍推進 | 男女共同参画 | |
|---|---|---|
| 法律 | 女性活躍推進法 | 男女共同参画社会基本法 |
| 目的 | 女性の職業生活における活躍を促進する | 社会のあらゆる分野で性別による差をなくす |
| 取組方法 | 女性の活躍に関する状況把握・課題分析状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表女性の活躍に関する情報公表 | ポジティブアクション (社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供すること) |
それぞれに関係する法律は、「女性活躍推進法」、「男女共同参画社会基本法」であり、適用される法律が異なります。また目的も異なり、女性活躍推進は、はたらきたい女性が活躍できる社会づくりを目的としている一方、男女共同参画は社会のあらゆる分野で性別による差別をなくすことを目的としています。
女性活躍推進では、301人以上の労働者を雇用する事業主と労働者101人~300人を雇用する中小企業に対し、状況の把握・課題分析・行動計画策定・計画の実施・効果の測定・情報公表という一連の流れで、取り組みが行われています。
男女共同参画は社会的・構造的な差別によって不利益を被っている人に対して特別の機会を提供する「ポジティブアクション」による取り組みが推進されています。
女性活躍推進法ができた背景と法整備で期待される4つの効果
男女共同参画社会基本法で性別による差別をなくす取り組みが行われているにもかかわらず「なぜ女性活躍推進法が制定されたのか?」「法律を制定して得られる効果はあるのか?」など、疑問に思う方も少なくはないでしょう。
この章では、女性活躍推進法が制定された背景と、期待される4つの効果について解説します。
女性活躍推進法が制定された背景
男女共同参画社会基本法や、職場における性別の差別をなくし、男女とも平等に扱うことを定めた「男女雇用機会均等法」など、法律の整備は整いつつありますが、いまだに実態面での格差は残っているのが現状です。
2003年に政府が掲げた「社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」という趣旨の「2020年30%」目標がありましたが、現在も達成できていない状況が続いています。
少子高齢化が進み労働人口の減少が深刻化する中で、企業が持続的に成長していくためには、はたらきたいと思っている女性に仕事を通して活き活きと活躍してもらうことが1つの解決策となっています。
女性活躍推進を促進するため、2016年に「女性活躍推進法」を制定し、対象となる企業に対し状況の把握・課題分析・行動計画策定・情報公表を義務化しました。
また、女性活躍推進への取り組みに対して一定の効果を得られた企業に対しては、政府から「えるぼし認定」が受けられます。
女性活躍推進法で期待される4つの効果
女性活躍推進法の制定で期待される以下の4つの効果について、一つずつ詳しく解説していきます。
- 女性の管理職比率の向上
- 採用や昇進機会の平等
- 仕事と家庭の両立
- ライフステージに合ったキャリア形成の実現
女性の管理職比率の向上
女性が活躍できる環境や制度を整えることで、女性の管理職比率の向上を目指せます。
女性が管理職にいたとしても、その人数が全体として少なければ、女性視点の意見が少数派の意見として取り入れられないことも少なくありません。そのため政府は、国連ナイロビ将来戦略勧告で提示された30%の目標数値や諸外国の状況を踏まえて、女性管理職比率30%を設定しました。
30%という数値は「クリティカル・マス」とも呼ばれ、企業の意思決定において影響を与えることが可能な割合として設定されています。
女性管理職比率を向上できれば、女性社員がはたらきやすい環境や制度への意見を反映させやすく、女性が活躍できる企業づくりができるでしょう。
採用や昇進機会の平等
性別に関わらず、適切な評価で採用や昇進の機会を与えること、努力・スキルに応じた正当な評価は、社内の人事評価の公平性や透明性を高めることにつながります。
また「頑張りが認められる」環境は、社員の意識も変わり仕事へのモチベーションが上がるというメリットもあります。
仕事と家庭の両立
女性がはたらきやすい環境をつくることで、仕事と家庭の両立が可能となります。
仕事と家庭の両立が実現できれば、女性が結婚や出産などライフステージに左右されずに「仕事を続ける」という選択ができるようになります。
企業にとっては、女性の定着率向上につながり、キャリアを積んだ人材を活かすことができるなどのメリットもあります。
ライフステージに合ったキャリア形成の実現
柔軟にキャリア形成ができる制度を整えることで、女性が出産や育児などライフステージの変化があっても活躍し続けることが可能となります。
ライフステージにあったキャリア形成の実現のためだけに限りませんが、女性が活躍できる職場にするためには、男性の家事や育児への参加なども大切です。これらの制度を考える際は、女性側だけの課題だと考え制度を設計するのではなく、性別に関係なくはたらきやすい職場とはどのような職場か、という視点で考えるとよいでしょう。
女性活躍推進法 2022年4月の法改正内容
女性活躍推進法は、2019年5月に女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、2022年4月に施行され対象となる企業が拡大されました。
| 労働者数 | 法改正前 | 法改正後 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 義務 | 義務 |
| 101〜300人 | 努力義務 | 義務 |
| 100人以下 | 努力義務 | 努力義務 |
法改正により、労働者が101人~300人の企業も女性活躍推進への取り組みが義務化されました。「労働者」とは、正社員やパート・アルバイト・派遣社員などの雇用形態に関わらず、以下いずれかの要件に当てはまる社員を指します。
- 雇用期間の定めがない人
- 過去1年以上雇用されている、または1年以上雇用する見込みがある人
対象となる企業は、状況の把握・課題分析・行動計画策定・情報公表が必要となります。
女性活躍推進に関連する法律の整理
女性活躍推進に関連する5つの法律について整理します。次表はそれぞれの法律のポイントをまとめたものです。
| 法律名 | 概要 | 対象 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 男女雇用機会均等法 | 性別を理由とした差別の禁止 | すべての事業主 | 募集・採用・昇進などでの男女平等 |
| 育児・介護休業法 | 仕事と育児・介護の両立支援 | すべての労働者と事業主 | 育児休業・介護休業の取得促進 |
| 次世代育成支援対策推進法 | 子育て支援を推進 | 主に従業員101人以上の企業 | 行動計画の策定・公表 |
| 労働施策総合推進法(パワハラ防止法) | 職場のハラスメント防止 | すべての事業主 | パワハラの防止措置義務化 |
| 女性活躍推進法 | 女性の活躍促進 | 主に101人以上の企業(努力義務含む) | 状況把握・行動計画・情報公表の義務化 |
男女雇用機会均等法との関係
「男女雇用機会均等法」は、雇用の募集・採用・昇進などにおける性別による差別の禁止を規定したものです。
一方、「女性活躍推進法」は、女性の活躍をさらに促すための積極的な行動計画を企業に対して求めるものです。
育児・介護休業法との関係
「育児・介護休業法」は、育児や介護と仕事の両立を支援する仕組みづくりを後押しするものです。女性活躍推進の実現には、育児・介護の負担軽減策と連動が重要だといえます。
次世代育成支援対策推進法との関係
「次世代育成支援対策推進法」は、子育て支援の観点から企業に行動計画の策定を求める法律です。具体的な行動計画の策定が企業に対して義務づけられる点で女性活躍推進法との親和性が高いといえます。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)との関係
「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」は、職場におけるハラスメント防止を強化することが目的です。女性活躍推進の職場環境づくりには、パワハラ防止対策も重要です。
女性活躍推進法と他法令の位置づけの違い
女性活躍推進法と、他法令の位置づけの違いについて整理します。
| 法律名 | 目的 |
|---|---|
| 男女雇用機会均等法 | 機会均等を保障 |
| 育児・介護休業法 | 育児・介護との両立支援 |
| 次世代育成支援対策推進法 | 子育て支援施策の具体的な計画を企業に計画・公開させる |
| 労働施策総合推進法(パワハラ防止法) | ハラスメント防止 |
| 女性活躍推進法 | 企業がいかに積極的に取り組んでいるかを計画・公表させる |
女性活躍における日本の現状
性別による差別をなくすためのさまざまな法律が制定されていますが、日本ではどの程度女性活躍が進んでいるのでしょうか。
この章では、指導的地位に占める女性の割合や就業率、世界との比較など、データを用いて解説していきます。
各分野における指導的地位に占める女性の割合
以下のグラフは、男女共同参画局が公表したパンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~」の2019年の各分野における『指導的地位』に占める女性の割合をまとめたものです。
指導的地位とは「議会議員」「法人・団体等における課長相当職以上の者」「専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する者」の3つが定義されています。
※引用:男女共同参画局|ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~
指導的地位に占める女性の割合が30%を超えている分野は、一部の行政分野(国家公務員の採用者・国の審議会委員)と一部の専門職業(薬剤師、獣医師)のみとなっています。民間企業の女性管理職比率を表している雇用分野は、他の分野よりも低いことが分かります。
また、2021年8月16日に株式会社帝国データバンクが公表した「女性登用に対する企業の意識調査(2021年)」では、女性管理職の平均割合は8.9%にとどまっているという調査結果も出ています。
同調査では、企業に占める女性の割合も発表されています。
※引用:株式会社帝国データバンク|女性登用に対する企業の意識調査(2021年)
企業に占める女性従業員の割合が30%以下と回答した企業は、調査した企業全体で70%近くを占めていることから、女性従業員の雇用が十分ではないことも、女性管理職の低さにつながっているといえます。
ただし、企業に占める女性従業員の割合が30%以上と回答した企業は、年々微増傾向にあるため、女性従業員を雇用する動きが広まりつつあるといえます。
国内の女性就業状況とは
以下のグラフは、厚生労働省が公表したパンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」から2020年の女性の年齢別就業率と潜在的労働力率を表したデータです。
潜在的労働力率とは、就業の有無に関係なく、はたらくことが可能な人が15歳以上の人口に占める割合を示したものです。
※引用:厚生労働省|女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画を 策定しましょう!(2020年)
25〜44歳の女性の年齢別就業率と潜在的労働力率にギャップがあり「はたらきたくてもはたらけない女性が多い」ことが読み取れます。一般的に、25〜44歳の間で結婚や出産、子育てなどライフイベントが発生することが多い年代です。
2019年6月27日に株式会社パーソル総合研究所が公表した「ワーキングマザー調査」では、出産に伴い退職した女性の6割が、出産後も仕事を続けたかったと考えていたことが分かりました。
※引用:パーソル総合研究所|ワーキングマザー調査(2019年)
このように、ライフイベントの発生で、一定数の女性はキャリアを中断するという選択をしていることが推測されます。
非正規雇用比率の推移
以下のグラフは、男女共同参画局が公表したパンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~」の男女別非正規雇用比率の推移を示しています。
※引用:男女共同参画局|ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~
最新の令和元年(2019年)の非正規雇用比率は、労働者のうち、男性が22.8%、女性が56%と、女性の半数以上は非正規雇用で就業しており、男性の2倍近く高い数値でした。女性の管理職割合が増えないのは、非正規雇用の女性が男性よりも多いことも要因の一つとして考えられます。
女性活躍の国際比較
以下のデータは、男女共同参画局が公表したパンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~」から2020年の世界における日本のGGI(ジェンダー・ギャップ指数)の位置関係を示したものです。
GGI(ジェンダー・ギャップ指数)とは、スイスの世界経済フォーラムが算定した男女格差を測る指数のことです。経済分野・教育分野・保健分野・政治分野の4つの分野から算出され、GGI値が1だと完全平等、0だと完全不平等を意味しています。
※引用:男女共同参画局|ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~
日本のGGI指数は、153ヶ国中121位のため、世界と比較し日本の水準が低いことが分かります。経済分野と政治分野においては、GGI値が低いため、特に性別による格差が残っているのが現状です。
女性活躍推進が難しい3つの理由
ここまで、データで日本の現状をお伝えしましたが、日本における女性活躍が進んでいない理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
考えられる以下の3つの理由について解説します。
- 男性中心の企業風土
- 家事・育児との両立が難しい
- 社内のロールモデル不在
男性中心の企業風土
「男性が出世しやすい」「性別で業務内容を区別する」など、男性中心の企業風土は女性活躍推進を阻む一つの要因です。
男性中心の企業風土は、頑張っても報われない、望むキャリアを歩めないなど、女性社員の仕事に対するモチベーションを下げてしまう可能性があります。男性中心の企業風土が残っている企業は、企業全体で、女性活躍推進の必要性を理解してもらう必要があります。
家事・育児との両立が難しい
仕事と家事・育児の両立が難しい要因には、以下の2つがあります。
- 家事、育児は女性がするものという考え方
- 責任が増えることに対する女性側の不安
近年、男性の育休取得への理解は少しずつ広がっていますが、2022年7月29日に厚生労働省が発表した「令和5年度雇用均等基本調査」では、男性の育休取得率が37.9%と、まだまだ高い数字とはいえません。男性の育休取得率が増えることで、性別に関係なく家事や育児へ参加するという認識が一般的なものになり、女性が職場でも活躍しやすくなるでしょう。
また、子育てをする女性は、残業が難しいことや突発的な休みが発生する可能性があることから、責任が増える管理職へのキャリアアップを望まない人もいます。しかし、実績や経験が豊富な女性社員が育児をしながらでも活躍できる環境を整えることができれば、人材不足の解消などにつながります。
社内のロールモデル不在
今後ライフイベントを控える女性にとって、家庭と仕事との両立は、将来のキャリア形成に大きく関わります。社内にロールモデルとなる女性がいない場合、自分がはたらき続けているイメージが持てずに不安を抱いたり、社員の成長を阻んでしまう可能性があります。
社内にロールモデルがいない場合は、他社で活躍している女性を参考にしながら、社内でもロールモデルとなる女性社員を育成することが重要です。さらに、女性社員のキャリアアップに対するネガティブなイメージを払拭させる取り組みを行いましょう。
女性活躍推進を企業が行う5つのメリット
企業は女性活躍推進に取り組むことで、さまざまなメリットが得られます。
以下の主な5つのメリットについて解説します。
- 業務体制の改善
- 経験や実績が豊富な人材確保
- 多様な人材の活躍につながる
- 企業イメージの向上
- 公的機関からの支援がある
業務体制の改善
業務標準化による残業の抑制やテレワークの普及など、女性が家庭と仕事を両立しやすい環境づくりができれば業務体制も改善されます。業務を標準化しムダを省くことができれば、限られた時間で効率的に作業を進められます。結果的に、残業の抑制だけではなく、企業の生産性向上にもつながります。
また、テレワークを活用すれば、可処分時間が増え勤務時間の延長ができ、仕事と育児・介護などを両立しながらはたらきやすい環境が整います。
経験や実績が豊富な人材の確保
女性が活躍しやすい環境を整えることで、経験や実績が豊富な女性社員が定着、また長期的なキャリア形成と安定した雇用にもつながります。
さらに結婚や出産で止むを得ず退職した人材や、ライフイベントを控えている世代へのアピールにもなります。
多様な人材の活躍につながる
女性活躍の推進は、将来的に人材の多様化が進みダイバーシティ経営への取り組みにもつながります。
ダイバーシティ経営は、労働人口が減少している日本において、女性をはじめ高齢者や外国人、障害者などの人材を活用することで、企業の多様性を高めていくための施策の一つです。例えば、時短制度やフレックスの導入、福利厚生の改善など、さまざまな制度の導入や改善は女性に限らず幅広い社員がはたらきやすいと感じる取り組みといえます。
結果的に、バックグラウンドの異なる多様な人材が活躍できる企業づくりにもつながります。
企業イメージの向上
女性活躍推進で一定の効果を得た企業は、厚生労働大臣から「えるぼし認定」が受けられます。
えるぼし認定が受けられると、女性活躍推進に積極的に取り組んでいる企業として認知されるため、企業イメージのアップが期待できます。
企業のイメージアップは利益の拡大や、実績や経験が豊富な人材を集めやすくなる、社員の満足度を上げられるなど、さまざまなメリットがあります。
公的機関からの支援がある
企業は、公的機関から助成金や優遇金利を受けながら、女性活躍推進への取り組みができます。
厚生労働省管轄の「両立支援等助成金」は、妊娠や子育て、介護などと仕事を両立させたい社員の支援を目的に企業が受け取れる助成金です。受け取れる金額は条件によって異なりますが、20万円~60万円程度の助成金が支給されます。
また、えるぼし認定を受けると、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強貸付)」を低金利で利用できます。
働き方改革推進支援資金は、社員の待遇改善を行うことや、福利厚生を拡充させるなどの目的で資金を借入できる仕組みで、はたらきやすい制度の導入や体制の構築がスムーズに行いやすくなります。
女性活躍推進法で政府や企業が行う取り組み
企業が実際に女性活躍推進に取り組むにあたって、女性活躍推進法では、実際にどんなことを、どういった手順で実行するのでしょうか。
この章では、女性活躍推進で政府が実施している取り組みと、企業が求められる取り組みをステップごとに解説します。
政府が実施している取り組み
政府が企業の女性活躍推進を支援するために行っている、2つの取り組みを詳しく紹介します。
- えるぼし認定
- 女性の活躍推進企業データベース
えるぼし認定
「えるぼし認定」は、女性活躍推進法に基づき、一定の基準を満たした優良な企業を認定する制度です。
政府は、企業の女性活躍推進への取り組み結果を、以下5つの項目で評価しています。
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等のはたらき方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
えるぼし認定には段階があり、5つの評価項目の中で、どのくらい基準を満たしているかによって得られるえるぼしが異なります。
また、より高い水準で評価項目を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けられます。
えるぼし・プラチナえるぼし認定を受けた企業は、認定マークを企業の商品や広告、名刺、求人票などへの使用ができ、社内外へのアピールが可能です。
また、えるぼし・プラチナえるぼし認定には、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強貸付)」を低金利で利用できる、「両立支援等助成金」の女性活躍加速化コースが適用となる、国からの公共調達における加点評価を受けられるなど、さまざまなメリットがあります。
女性の活躍推進企業データベース
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」は、企業が女性活躍推進の取り組みを発信するためのウェブサイトです。企業は女性の活躍推進企業データベースに、女性活躍推進に関する行動計画や、企業の女性活躍に関する情報を登録できます。
登録された情報は一般公開されており、求職者や就職活動中の学生など、多くの方に見られています。女性の活躍推進企業データベースの活用で、企業のイメージアップや競合他社との差別化にもつなげられます。
企業が求められる取り組み
企業は、政府の支援を上手く活用しながら、以下で紹介する4つのステップに沿って女性活躍推進への取り組みを行いましょう。
4つのステップの詳しい内容や注意事項については、厚生労働省が発行するパンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」を参考にしてください。
ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
まずは自社の女性活躍における状況を把握するために、基礎項目である以下4つの数値を算出します。
状況を把握し、自社の女性活躍に関する課題を分析します。
- 採用した労働者に占める⼥性労働者の割合
- 男⼥の平均継続勤務年数の差異
- 労働者の1ヶ月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
- 管理職に占める⼥性労働者の割合
ステップ2:⼀般事業主⾏動計画の策定、社内周知、公表
ステップ1で分析した課題を基に、女性活躍推進の⼀般事業主⾏動計画(行動計画)を作成します。行動計画には、以下4つの項目を盛り込むことが必要です。
- 計画期間
- 数値目標
- 取り組み内容
- 取り組みの実施時期
作成した行動計画を、社内外に公表しましょう。
社内へは、ポータルサイト掲載や、計画書の掲示、メール送付などで企業の社員に周知を行います。社外へは、⼥性の活躍推進企業データベースへの登録や、自社ホームページへの掲載を行い、公表します。
ステップ3:⼀般事業主⾏動計画を策定した旨の届出
行動計画の策定をしたら、管轄の都道府県労働局へ「一般事業主行動計画策定・変更届」の提出が必要です。都道府県労働局へは、電子申請、郵送、持参による提出が可能です。
ステップ4:取り組みの実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画の実施状況を点検・評価しましょう。
女性活躍推進の4つのポイント
実際に女性活躍推進を成功させるために、どのようなポイントを押さえて取り組みを行えばよいか分からない方も多いと思います。
この章では、女性社員の採用、教育やスキルアップなどの支援を経て、女性社員がはたらき続けられる職場になるためのポイントを、以下4つに絞って解説します。
- 女性の採用を強化する
- 女性社員が能力を発揮できる体制をつくる
- 女性社員がはたらきやすい環境づくりをする
- 女性活躍推進取り組みへの組織づくりが重要
女性の採用を強化する
女性活躍の推進への取り組みを進めようと思っても、企業に女性社員が少ない場合は「女性の積極的な採用」を目標とするケースもあります。その場合、経験や実績が豊富な女性の応募を増やすために、以下のような施策が効果的です。
- 女性が安心してはたらき続けられる環境と制度をつくる
- 採用条件を見直し応募できる人材の幅を広げる
- 女性活躍推進への取り組みをアピールする
仕事と育児などを両立しながら、長期的にはたらきたいと考えている人は「はたらきやすい制度はあるか?」「制度が利用しやすいか(育児休業などが取得しやすいかなど)」などが気になっていると考えられます。そのため、まずは在籍している女性社員にヒアリングするなど、女性がはたらき続けやすい環境や制度を整えましょう。
また女性の多くは家事や育児、介護など、時間的な制約があることが多く、応募したくてもできない場合もあります。より多くの女性が応募できるように採用条件を見直し、テレワークや時短勤務などを取り入れるとよいでしょう。
また「次世代育成支援対策推進法」に基づき、仕事と子育ての両立支援を行っている企業が受けられる「くるみん認定」を受けたり、女性活躍に関する情報を発信することで、女性が入社後に活躍できるイメージがつきやすくなります。企業のイメージも向上し、実績や経験が豊富な人材の採用にもつながります。
女性社員が能力を発揮できる体制をつくる
入社した女性が、十分に能力を発揮できる体制づくりには、入社後のサポートと昇進後のサポートが重要です。
入社後のサポート:能力の開発支援
入社後に、女性社員の能力開発支援を行うことで、企業における女性管理職の比率を上げることが可能です。能力の開発支援には、以下のように精神面のサポートとスキル面のサポートが必要となります。
- 管理職へのマイナスイメージを解消する
- 重要な業務を任せ、スキルアップにつなげる
まずは「管理職になる自信がない」「責任が多くて大変そう」など、管理職に対してマイナスイメージを持っている女性社員に対し、定期的なキャリア面談を行い不安な点をヒアリングしマイナスイメージの払拭を行います。
さらに、重要な仕事を「任せる」「結果を振り返る」のサイクルを繰り返すことで、仕事の経験や実績を増やしスキルアップへのサポートを行います。
昇進後のサポート:管理職としてのスキルアップ支援
女性社員が管理職として活躍できるように、昇進後のサポートも重要です。
女性は、女性との横のつながりを持つことで心理的安心感を得られるといわれています。既に活躍している女性管理職や、これから管理職となる女性社員と関わりを持てるような場を提供し、管理職への不安を払拭させましょう。
また、多様な視点を持つための「アンコンシャスバイアス研修」や実践的な「マネジメント研修」を行い、管理職としてのスキルを向上させられる研修も重要です。
このように、昇進後のサポートにおいても、精神面とスキル面を合わせた支援がポイントです。
女性社員がはたらきやすい環境づくりをする
役職関係なくすべての女性社員が、はたらきやすいと感じる環境づくりを行うことで、女性社員の定着や新たな人材の採用がしやすくなります。
柔軟なはたらき方への制度づくり
女性が、ライフイベントや家庭に左右されず柔軟なはたらき方ができるようにするため、企業が導入できる制度には以下のようなものがあります。
- 時短勤務
- フレックス制度
- テレワーク
家庭の事情に合わせて出勤時間を変えたり、自宅で業務ができれば、時間や場所に縛られずはたらくことができます。
上記のような企業で導入できる制度や「くるみん」などの、国が推進する子育てサポート支援も掛け合わせることで、女性社員の仕事と家事・育児の両立への負担を軽減することも可能です。
また、先輩社員が後輩社員の相談を聞き精神的なサポートをする「メンター制度」の導入も、女性社員の不安を解消し、将来的なキャリアアップをポジティブなものにできるため、女性活躍推進において有効な手段です。
女性がキャリア形成できる人事制度
企業では、ライフイベントに左右されず女性社員が望むキャリア形成ができるような評価制度を取り入れましょう。
従来の「残業した人が評価されやすい」「飲み会に参加することで昇進の機会を得やすい」などの不平等な企業文化を改革し、誰もが納得できる適切な評価項目の制定が重要となります。
まずは、従来の評価制度を見直し、女性社員や、必要によっては外部企業の意見を取り入れながら自社に合った人事制度を確立させましょう。
女性活躍推進取り組みへの組織づくりが重要
2019年6月27日に株式会社パーソル総合研究所が公表した「ワーキングマザー調査」では、子育てをしながらはたらく女性の4割が、自分が声をあげても職場は変わらないと思う「職場内対話無力感」を抱えているという調査結果が出ています。
女性の意見を反映し、女性活躍推進への取り組みを成功させるためには、社員一人一人の理解と協力が必要不可欠です。取り組みへの理解と協力を得るためには、以下2つを実施しましょう。
- 女性活躍推進の取り組みを組織に周知
- 推進チームの立ち上げ
女性活躍推進の取り組みへの理解を得るために、まずは社内に周知することが重要です。さらに、社員が主体的に取り組めるように、部署や課単位で取り組みへの目標を立てるといった工夫もできます。
社内で女性活躍推進チームをつくることで、社員の意見を収集、反映することで実態に即した施策の立案・実行が可能となります。女性活躍推進チームは、年齢や役職、職種などできるだけ多様な社員で構成し、さまざまな意見を取り入れられるようにしましょう。
女性活躍推進に関してよくある質問
Q1.女性活躍推進は、なぜ企業に義務付けられているのですか?
女性活躍推進法は、少子高齢化による労働力人口の減少が進む中で、女性がその能力を最大限に発揮できる社会を実現することで、企業の持続的な成長と競争力強化を図ることを目的としています。
企業が女性の活躍を推進することは、多様な視点を取り入れることによるイノベーション創出や、優秀な人材の確保、企業イメージの向上にもつながり、社会全体の活性化に貢献するため、法的な義務が課せられています。
Q2.自社に合った行動計画を策定するためのポイントは何ですか?
自社に合った行動計画を策定するには、まず自社の女性活躍に関する現状(女性従業員の比率、管理職比率、勤続年数、育児休業取得状況など)を正確に把握し、課題を特定することが重要です。
その上で、目標達成に向けた具体的な取り組み内容を、従業員の意見も踏まえながら検討しましょう。
特に、男性従業員の育児参加促進や、多様なはたらき方を可能にする制度設計なども含めると、より実効性の高い計画となります。
Q3.行動計画の策定・公表をしない場合、企業にどのようなデメリットが考えられますか?
行動計画の策定・公表は企業規模によって義務または努力義務と位置づけられています。実施しない場合、直接的な罰則規定は現在のところありません。
しかし、企業のWEBサイトや求人情報などで女性活躍に関する情報公開が求められており、未対応の場合、求職者からの関心を得にくくなる可能性があります。
また、優良な取り組みを行う企業が認定を受けられる「えるぼし認定」などの取得も不可能となり、企業イメージや採用活動において不利になる場合が考えられます。
女性活躍推進を正しく理解し、誰もがはたらきやすい環境づくりを
女性活躍推進は、仕事を通して女性が個性や能力を発揮し、活躍できる社会づくりを目指すものです。企業は、女性の活躍を促すために、女性社員の管理職比率の向上や、女性の採用強化などの取り組みが必要となります。
例えば、柔軟にはたらける環境づくりや、ライフイベントに関わらずキャリア形成できる人事評価の設定など、家庭と仕事を両立できる支援が重要です。またこれらの施策は、ただ制度があるだけでなく、実際に利用されること、利用がしやすい企業風土をつくることが大切です。
これらの取り組みは女性だけではなく、性別や年齢、バックグラウンドに関係なくすべての社員がはたらきやすい環境を整えることができます。はたらきやすい環境を整えることで、人材不足や社員の定着率の課題解消にもつながるでしょう。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする