HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート】
新規事業を生み出す人づくり・組織づくり
ー新規事業開発とタレントマネジメントの交点をさぐるー
公開日:2025.05.14
- 記事をシェアする

立教大学 経営学部 准教授
田中 聡 氏
法政大学大学院 政策創造研究科 教授
石山 恒貴 氏
多くの企業が新規事業開発に意欲的である一方、「人と組織の問題」でつまずいてしまう組織が少なくないのが現状もあるでしょう。そんな、人と組織のマネジメントの課題解決に向けて、<新規事業開発×人材開発・チーム開発>を研究する立教大学 田中聡氏と、<タレントマネジメント研究>の第一人者である法政大学大学院 石山恒貴氏が登壇。田中氏による調査データと学術理論を踏まえた実践ポイントの解説に対し、石山氏にタレントマネジメントの観点から問題提起いただきました。
“新規事業はイノベーターによってゼロから革新的なアイデアが生み出される”は大きな誤解
多くの企業が新規事業開発に意欲的である一方、「人と組織の問題」でつまずいてしまう組織が少なくないのが現状もあるでしょう。そんな、人と組織のマネジメントの課題解決に向けて、<新規事業開発×人材開発・チーム開発>を研究する立教大学 田中聡氏と、<タレントマネジメント研究>の第一人者である法政大学大学院 石山恒貴氏が登壇。田中氏による調査データと学術理論を踏まえた実践ポイントの解説に対し、石山氏にタレントマネジメントの観点から問題提起いただきました。
新規事業は「資源を動員する組織的なプロセス」「既存事業が培ってきたノウハウ・資源の活用」「経済成果を生み出す活動」の3つがポイントです。つまり、「創る人」「支える人」「育てる組織」の“三位一体”で推進していくことが重要となります。
さまざまな研究で、新規事業の創出は「経営人材の育成」に最も有用な経験であることが解明されています。なぜなら新規事業は修羅場の連続であり、成長機会の宝庫であるためです。また、新規事業にあたって支援が不可欠ですが、全社の経営層からの内省支援(視座を上げていくために必要な内省を促す)と社外の新規事業担当者からの業務支援(どのように事業をつくっていけばよいか)を得ることが効果的です。さらに経営層が直接関与する新規事業ほど成果を上げやすいことが判明しています。加えて、上級管理職は積極的にスポンサーとして新規事業創出者と経営者や外部との関係をつないでいく、ナレッジブローカーとしての役が必要です。
新規事業は「全社の経営課題」であるため、新規事業を行う戦略的意図(Why)を明確にしないと成功は遠ざかってしまう傾向です。これには共通アイデンティティを持てる全社ビジョンを掲げることが不可欠と言えるでしょう。(田中氏)
タレントマネジメントとは「多様な個性を有するタレントの才能を爆発的に開花させる取り組み」
タレントには客観アプローチ(特性を持つ人としてのタレント)と主観アプローチ(人としてのタレント)の2つがあります。また戦略的タレントマネジメントは、「企業の中の競争優位に貢献するキーポジションを特定し、それらのキーポジションにふさわしい高い潜在能力を有する人材をタレントプールで開発すること。またその有能な人材がキーポジションを充足できる人材アーキテクチャーを構築し、有能な人材の組織への継続的コミットメントを確保すること※」と定義されています。
タレントマネジメントを自社で創る際には、「全員に注力するかor一部に注力するか」「生まれながらのタレントを見るかorタレント育成に焦点を当てるか」アセスメントを「努力や動機などの潜在(インプット)を重視するor成果(アウトプット)重視する」など、さまざまな観点があります。タレントマネジメントが機能していれば創る人も支える人も育成されるものの、実際はそう容易ではありません。よってタレントマネジメントは、経営戦略に紐づく創る人の人材像定義やキーポジションの設定範囲の考え方、創る人を迫害しない企業文化醸成などが重要なポイントとなるのです。(石山氏)
まとめ
会社として新規事業を生み出すためには「創る人」になりたいという人を一人でも多く増やし、彼らの挑戦を後押しする環境(人・組織)を整備することが最も有効です。つまり事業を育てる組織のカギは「挑戦母数を増やすこと」と言えます。また挑戦した結果の失敗を「学習成果」として評価することも肝心です。(田中氏)
タレントマネジメントを創る人のように、新しいイノベーションをもたらす人は批判もされやすいという一面があります。それを避けるためには越境学習を通じて、個人の中での多様性を獲得することが必要です。(石山氏)
※出典:Collings, David G. and Mellahi Kamel (2009) “Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda,” Human Resource Management Review, Vol.19, No.4, pp.304-313, p304.
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

立教大学 経営学部 准教授
田中 聡 氏
1983年山口県周南市生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程 修了。東京大学・博士(学際情報学)。慶應義塾大学商学部卒業後、株式会社インテリジェンス(現・パーソルキャリア株式会社)に入社。大手総合商社とのジョイントベンチャーに出向して事業部門を経験した後、人と組織に関する調査研究・コンサルティング事業を専門とする株式会社インテリジェンスHITO総合研究所(現・株式会社パーソル総合研究所)の立ち上げに参画。同社リサーチ室長・主任研究員・フェローなどを務め、2018年より現職。専門は人的資源管理論・組織行動論。人材開発・チーム開発について研究している。著書に『経営人材育成論』(東京大学出版会)、『チームワーキング』(共著:日本能率協会マネジメントセンター)、『「事業を創る人」の大研究』(共著:クロスメディア・パブリッシング)など。
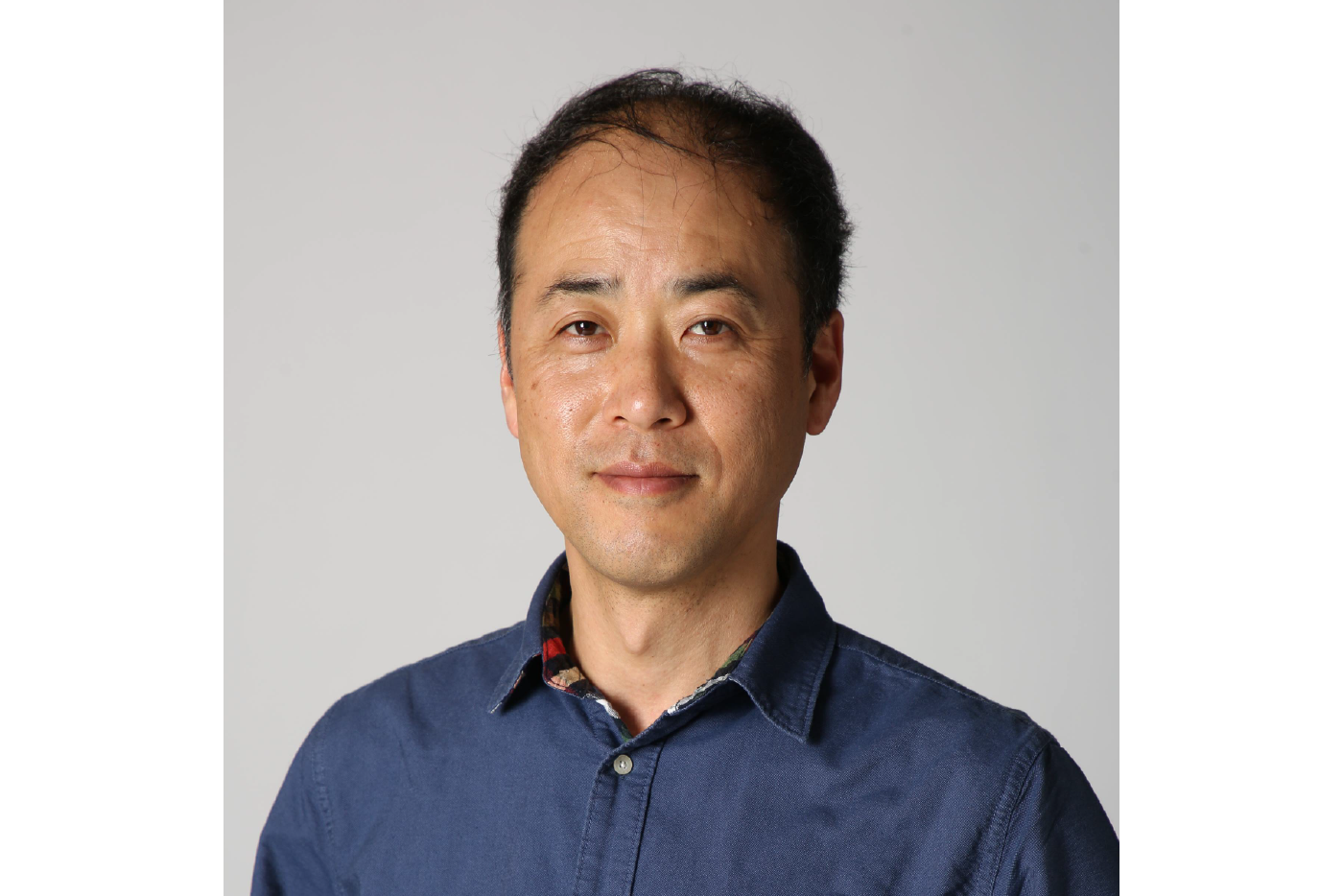
法政大学大学院 政策創造研究科 教授
石山 恒貴 氏
一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。越境的学習、キャリア形成、人的資源管理、タレントマネジメント等が研究領域。日本労務学会副会長、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会理事、人事実践科学会議共同代表、一般社団法人シニアセカンドキャリア推進協会顧問、NPO法人二枚目の名刺共同研究パートナー、フリーランス協会アドバイザリーボード、専門社会調査士等。主な著書:『カゴメの人事改革』(共著)中央経済社、『越境学習入門』(共著)日本能率協会マネジメントセンター等多数。
- 記事をシェアする









