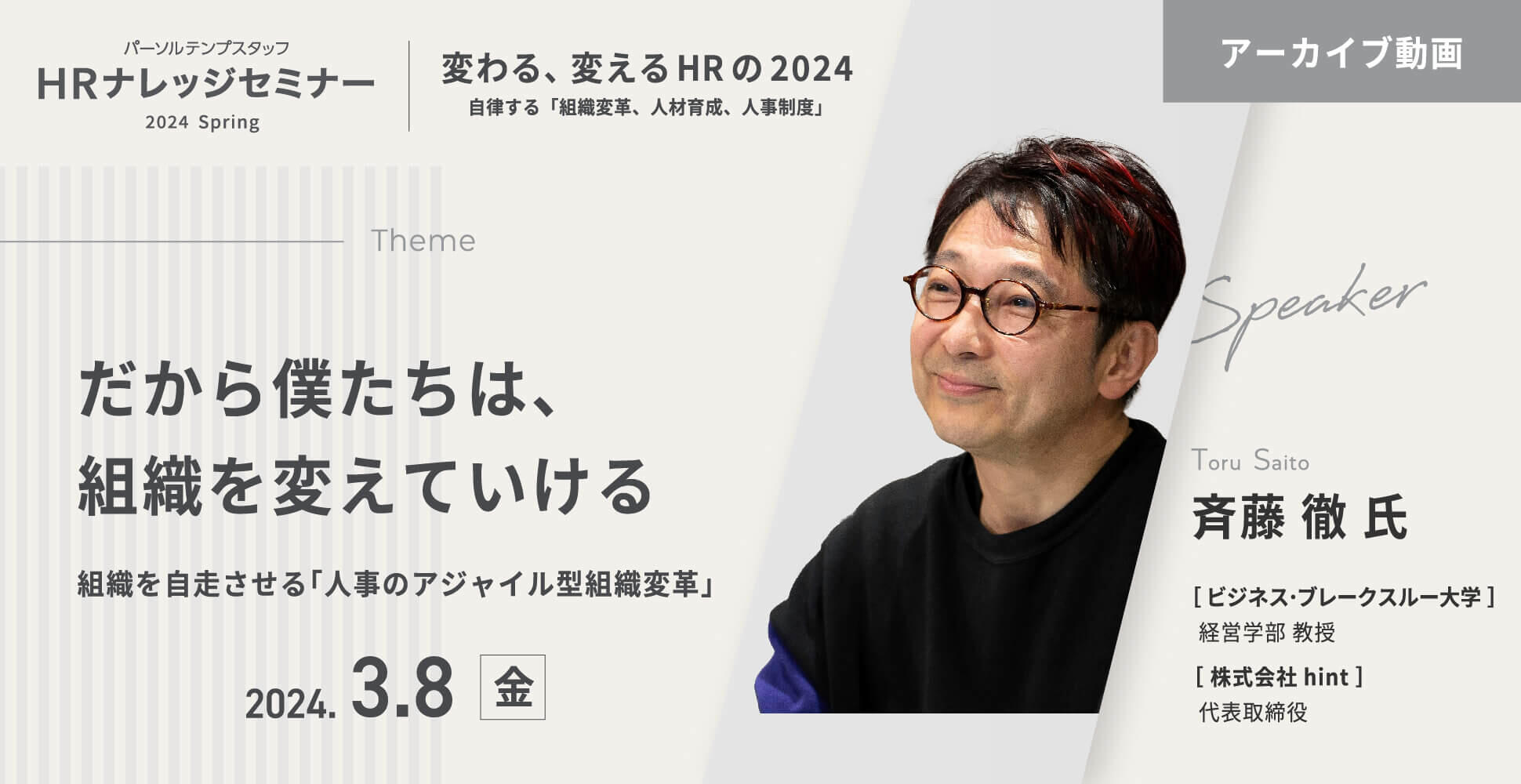HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート】
ミドルシニア問題の本質 〜地に足のついた課題解決に向けて
公開日:2024.12.23
- 記事をシェアする
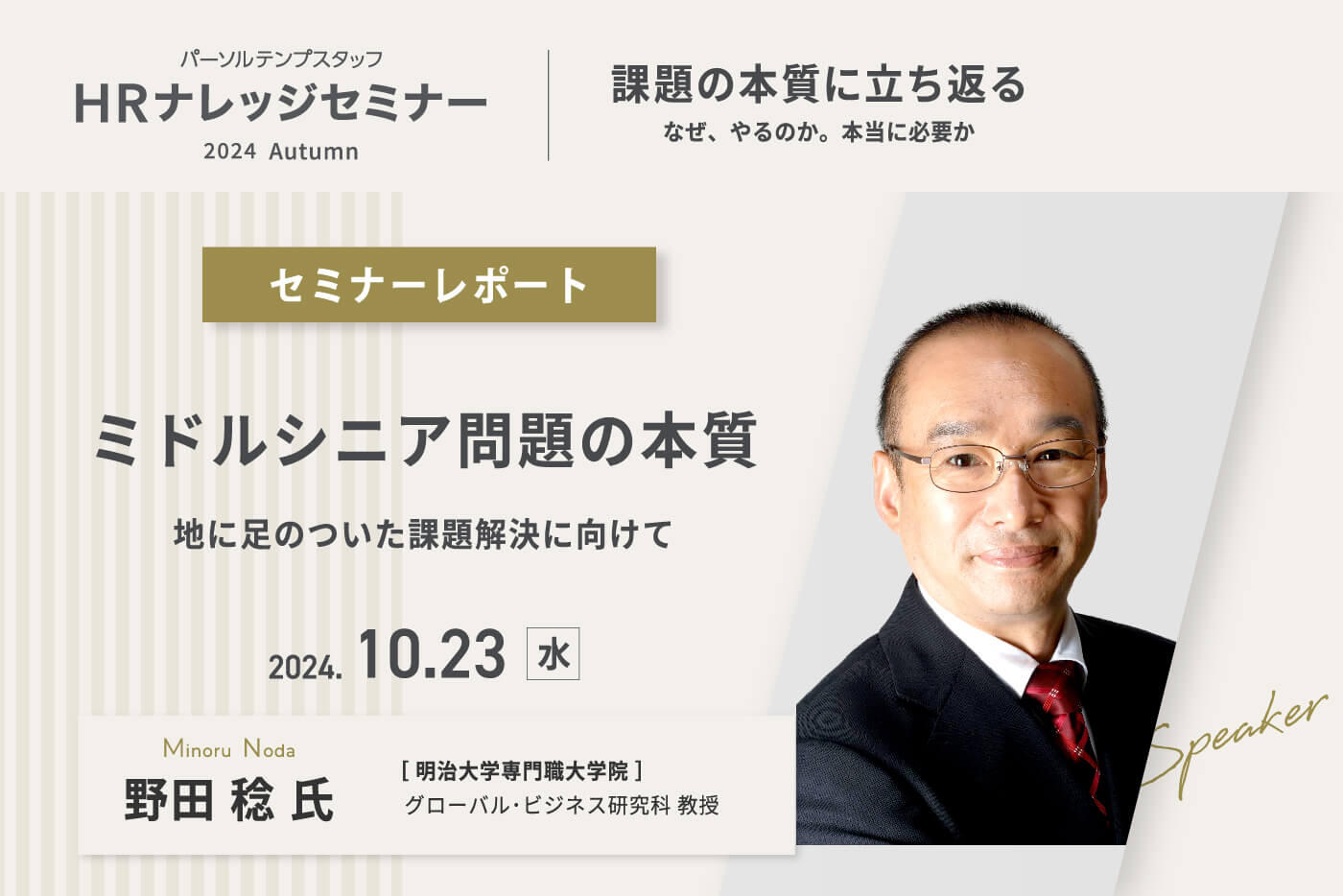
明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科
教授
野田 稔 氏
「役職定年を続けるのか止めるのか」「リスキリングをするのか否か」「セカンドキャリアに会社はどこまで踏み込むのか」―。近年のミドルシニアを取り巻く問題は実に多岐にわたります。また、これらの問題は会社によって状況が異なるのが現状です。よって解決策を見出すためには他社の動向を参考にするのではなく、自社としっかり向き合い、本質的な課題に対処する必要があります。
明治大学専門職大学院 教授 野田 稔氏に、ミドルシニア問題を解決するためのポイントや、行うべき施策などをお話いただいた講演の一部をご紹介します。
ミドルシニア社員のモチベーションを考える
近年、諸外国では「定年制度」を廃止する企業が増えつつありますが、日本ではまだまだ多いのが現状です。また一定の年齢に達したら、役職から退く「役職定年制度」も“当たり前”のように設けています。そもそも、こういったことは「当たり前」なのでしょうか。改めて立ち戻って考える必要があると思います。こうした制度により経済的処遇や社会的欲求が低下した状況下では、ミドルシニアのモチベーションは上がりづらいといえます。
逆に言えば、ミドルシニアがモチベーションを上げ、活躍するためには、やりがいのある仕事を割り当て、しかるべき経済的処遇を与えることで実現の可能性が高まります。
また新たな役割を担うミドルシニアに、周囲が期待することも重要となってきます。すなわち、新たなモチベーションの創造をしない限り、ミドルシニア問題は解決できないでしょう。
人と組織の「共進化」
ミドルシニアが活躍するために大きなカギとなるのが、人と組織の「共進化(Co-evolution)」です。共進化とは生物学用語で、複数の種が互いに影響しあいながら相互に進化していくことを意味します。つまり、ミドルシニアが進化し、それに合わせて組織も進化することで、新しい人と組織の均衡解が生まれるといえます。
また、ミドルシニアの進化において大切なのは、“ラベル剥がし”です。「私は部長だ」「私は役員だ」といったラベルにあまりにも執着しすぎると、活躍する道は閉ざされるでしょう。ここで非常に参考になるのが、映画「マイ・インターン」です。ロバート・デ・ニーロ演じる主人公が、ファッション通販企業にインターンとして働くというストーリーで、ミドルシニアの活躍を考える上で学ぶべき点が数多くあります。彼は70歳越えの人材ですが、「前職では管理職だったが今は新人」と自ら宣言し、過去の自慢話などは一切しません。その一方で、自分自身のスタイルをしっかり持ち、長年培った人間関係構築力を新たな職場で発揮するのです。
そのストーリーには、米国の心理学者のジョン・D・クランボルツ教授が発表した、偶然の出来事が人のキャリアに大きな影響を及ぼし、予定外の出来事はむしろ望ましいものであると主張する「計画的偶発性理論」が働いていると見受けられます。外に出れば偶然が起こりやすくなる。言い換えれば、チャンスを増やして良き偶然が来るのを待つことで、可能性もきっと広がるでしょう。
“変身”の擬似体験としての越境的学習

ミドルシニアが活躍する有効な手段の一つが「越境的学習」です。越境的学習は副業や兼業、ボランティアなどいろいろな手段がありますが、趣味もとても優れた越境的学習の機会を与えてくれると感じています。熱中できることであれば新しい世界に飛び込みやすくなり、充実した時間を過ごせば、認知と賞賛を得るだけでなく、社会貢献や経済的成功につながる可能性も高まるはずです。
「ビール缶集め」などの複数の趣味から新たなキャリアを得た私のシニア友人いわく、趣味は「できるだけマイナーな趣味であること」「空間的・時間的に広がりがあること」「努力できること」「鑑賞系の趣味も持つこと」「昔、熱中したこと」を推奨しています。
また、ミドルシニアの進化には「自己ブランディング」が欠かせません。この自己ブランディングで私が提案しているのが専門性の向上です。昔からあるべき人材像として語られてきた、高度な専門性と広い知識を持つ「T字人材」(特定の分野を極めながら、その他の幅広いジャンルに対しても知見を持っている人材)が取り上げられていますが、ミドルシニアの自己ブランディングにおいては、専門性が複数ある状態が理想的です。
「複数の専門性」で意識したいのが、オリンピックの代表を目指すようなことではなく、小学校1学年で1番くらいのレベルで良いということです。100人中1番程度の専門性を3つ兼ね備えれば、1/1,000,000の希少な人材になれます。この状態になれば周囲の反応も変わるはずです。
一人ひとりの強みを活かして社会に貢献する
ミドルシニアの強みとは、今まで培ってきた仕事に関する知識や技能、経験だけでなく、学ぶ力や使命感、交渉力など実にさまざまです。脳科学の研究では、脳の最大出力期は56歳で、84歳まで続くという報告もあります。そういった意味で、ミドルシニアが進化できるチャンスは大いにあるのです。
近年では、「誰か」「何か」「どこか」に身を委ねる生き方は、危険といわれています。長い人生のウェルビーイングを考えると、後半に受け身から主体化へ、延長線上から飛び地へと、可能性を広げていくことが必須となるでしょう。
またミドルシニアの進化に伴い、組織も彼らを受け止めるべく動いていく必要があります。つまり、組織・制度も進化しなくてはならないのです。
ここでポイントとなるのが「ミドルシニア自らがjobを創造する」ということです。この経験は将来キャリア自立する際に大いに役立つことでしょう。
ミドルシニアの活躍には“変身資産”が大切な要素に

ミドルシニア問題を解決するためには、人も組織も変化することが不可欠です。さらに言えば、「変わる力」を再確認することに大きな意味があるといえます。この力は、イギリスの組織論学者、リンダ・グラットン氏の著書「LIFE SHIFT」で示された「変身資産」と捉えることができます。
彼女は人生100年時代のウェルビーイングのためには、所得を増やすための「生産性資産」と、肉体的・精神的な健康と幸福といった「活力資産」にくわえ、自分自身が変わる「変身資産<」が大切な要素になると指摘しています。さらに変身資産を培うためには、自分についてよく知ることが第一としています。
近年では、変身資産を“見える化”するツールも登場しています。例えば、LIFE SHIFT JAPANが開発した「変身資産アセスメント」では自分の変わろうとする力や、その力を高めるために必要な要素や、変化を妨げる癖などを知ることができます。そういったツールをうまく活用しながら、まずミドルシニアが変わる力を鍛え、組織はミドルシニアをしっかり後押しし、その貢献に報いる経済的処遇を与えていくことが非常に有効であるといえます。
まとめ
ご存じの通り、近年日本の人口は減少し続けています。その中で特に問題視されているのが労働人口の減少です。現在の日本における労働人口の総数は約6,600万人ですが、この数字は2040年に向けて増えていくと予想されています。人口が減るにもかかわらず労働需要が増える理由は、高齢化に伴って介護や医療、福祉などの領域で多くの人材が必要となるためです。一方で、労働供給はどんどん減ると予測されています。リクルートが行ったシミュレーションによると、2040年には1,100万人の労働力不足が生じると判明しました。この状態では日本経済は決して回らないでしょう。
したがって、企業はすべての社員ができるだけ長く働けるように、今の段階から準備することが非常に重要です。そのカギとなるのがミドルシニアと企業の進化であることは間違いありません。人と組織の共進化を行うことで、労働供給制約時代をうまく乗り越えられると私は考えます。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科
教授
野田 稔 氏
一橋大学大学院 商学研究科 修士課程修了。
野村総合研究所、リクルート新規事業担当フェロー、多摩大学経営情報学部教授などを経て、2008年より現職。専門は組織論、組織開発論、人事・人材育成論、経営戦略論、ミーティングマネジメント。学生の指導に当たる一方、企業に向けて組織・人事領域を中心に、幅広いテーマで実践的なコンサルティング活動や講演活動を行う。人材マネジメント分野の開拓者の一人である。最近ではメタバースを応用した業務の効率化、イノベーションの推進の研究にも取り組んでいる。
組織論、リーダーシップ論に関する書籍多数、ニュース番組のキャスターやコメンテーターなど、メディア出演も多数。
- 記事をシェアする