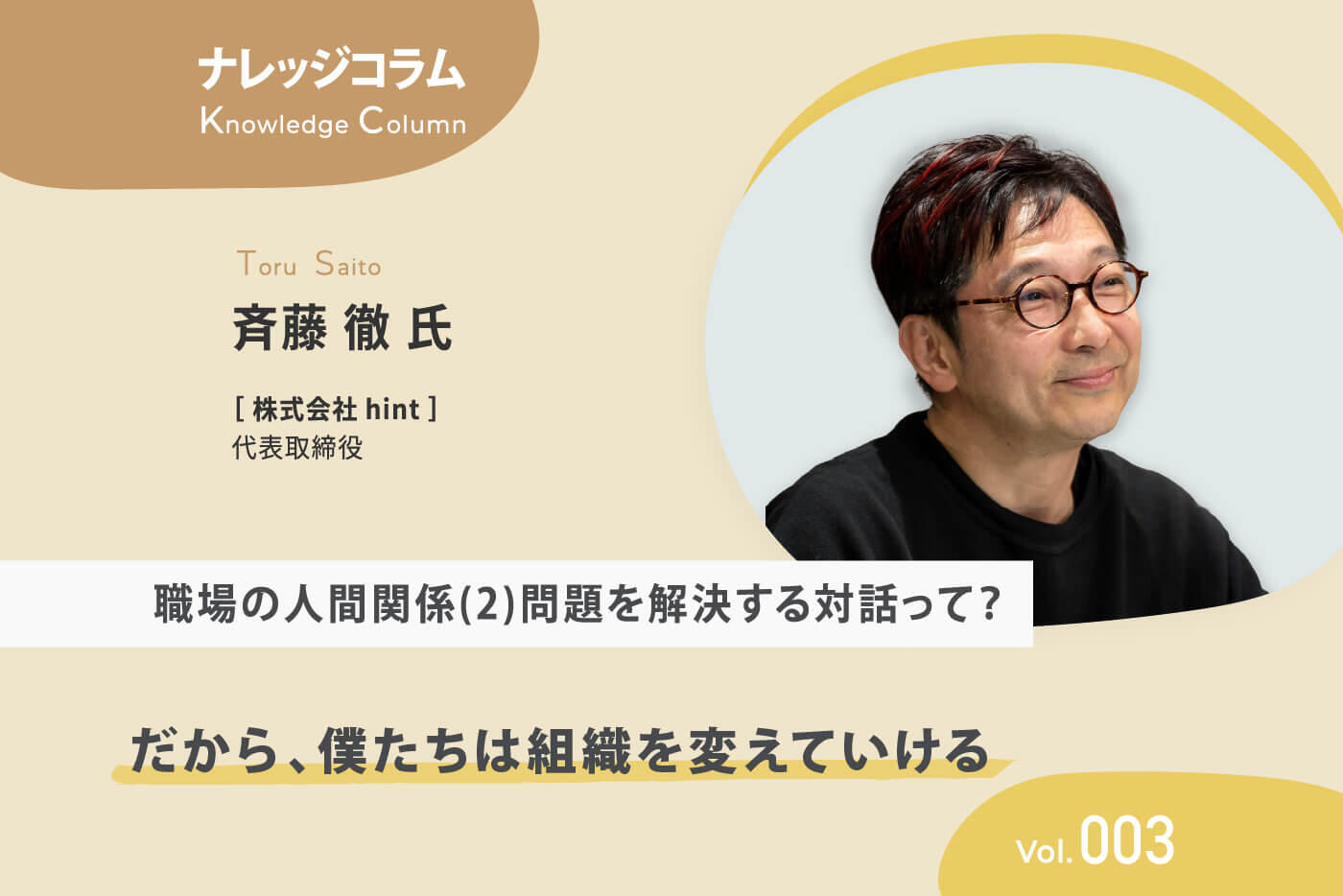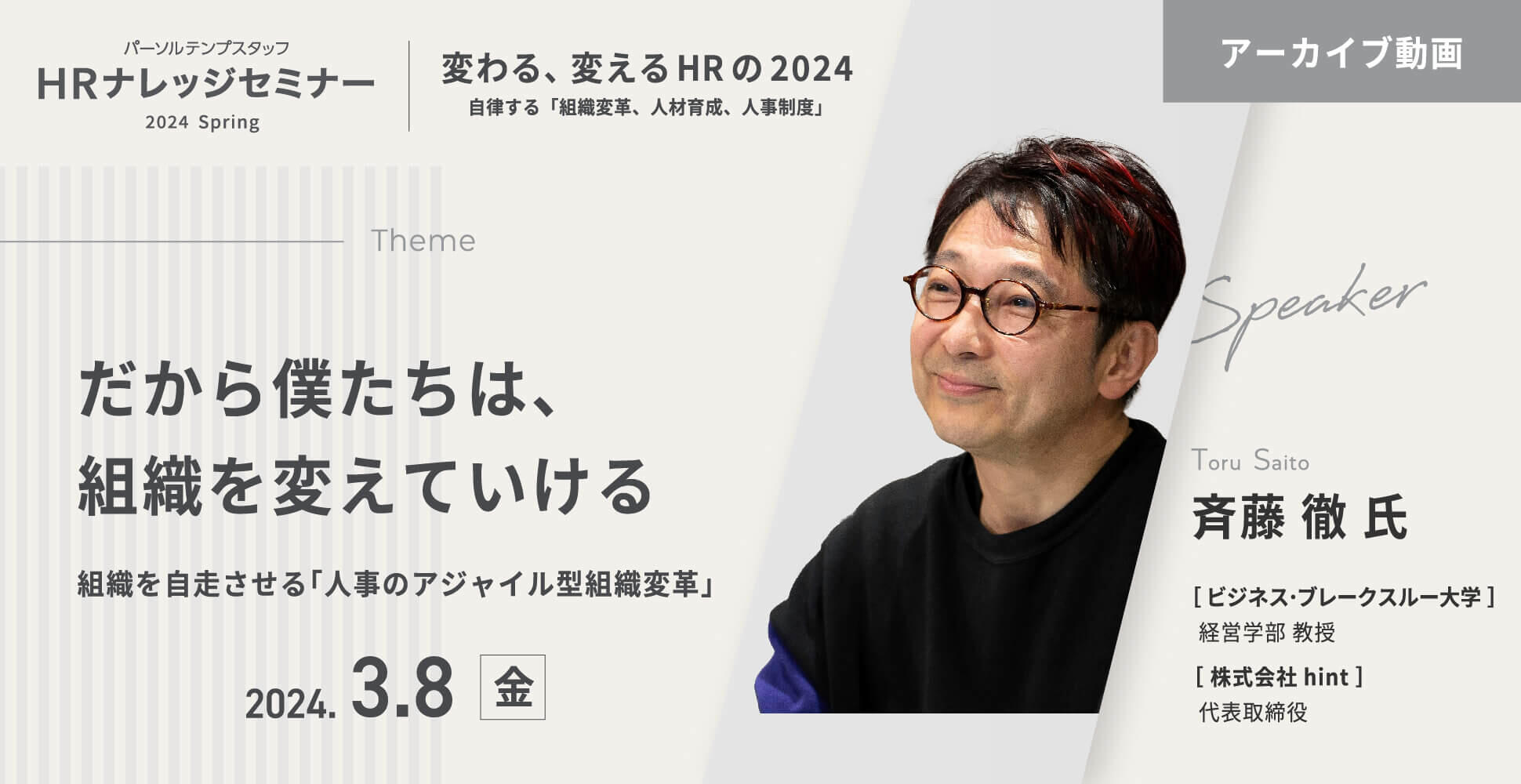HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジインタビュー】
明治大学専門職大学院 野田氏
自分を振り返り再設計し続けながら、まず「やってみる」
公開日:2024.12.06
- 記事をシェアする
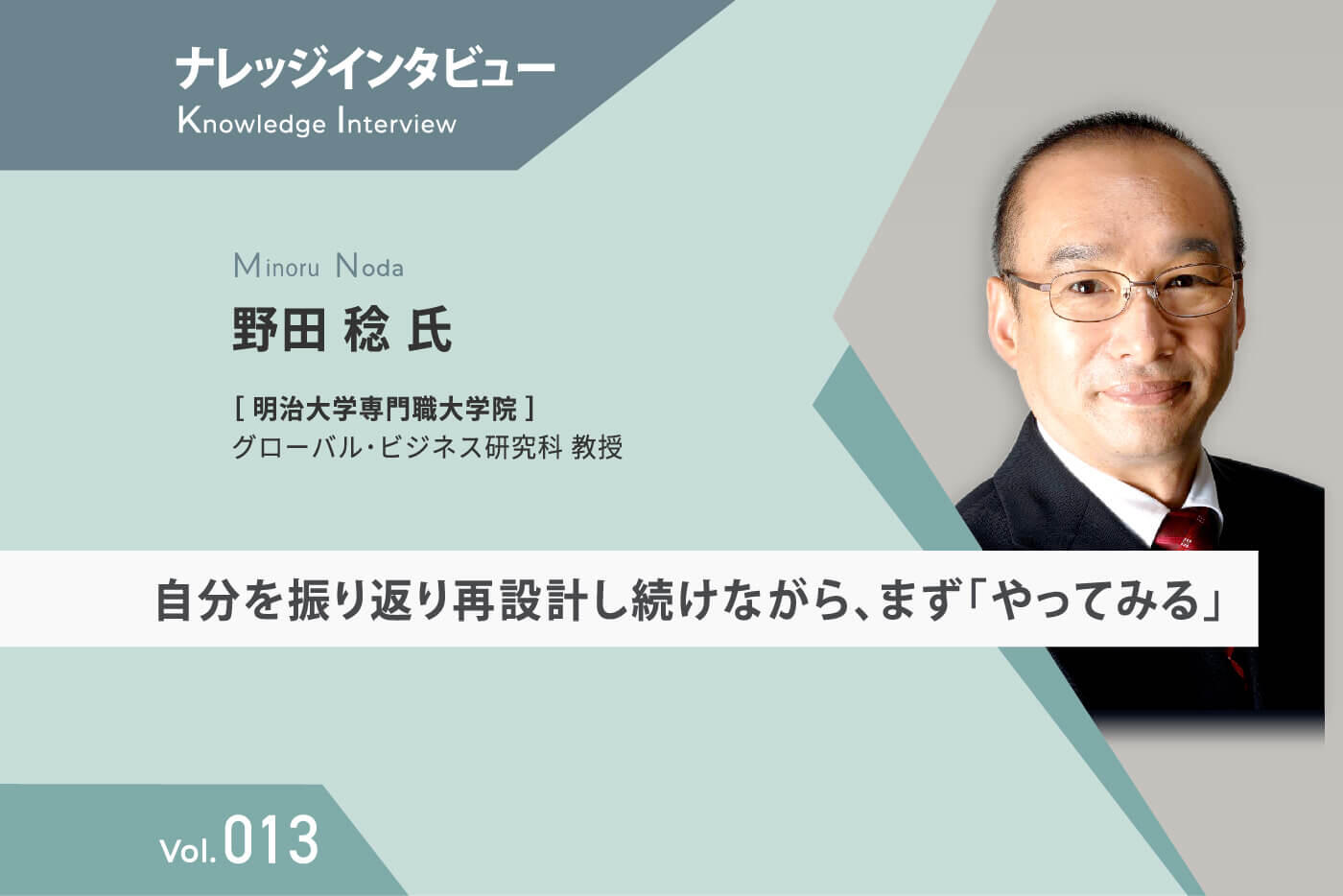
明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科
教授
野田 稔 氏
今回のナレッジインタビューは、HRナレッジセミナー2024 Autumn DAY1『ミドルシニア問題の本質 〜地に足のついた課題解決に向けて』の講演をいただいた明治大学専門職大学院 野田 稔教授のイベント後インタビューです。講演内容を踏まえて、年功序列やキャリアについての考え方、人事としての取り組み方についてお話いただきました。
― 今回のセミナーの総テーマでもありますが「そもそも、なんでやるの?やらないの?」という、ミドルシニア課題について本質に立ち返る時間でした。思考のスタート位置や立ち止まる、振り返る位置を「ここだよ」と仰っていただいたような気がしました。「年功序列」についての議論もしかり、です。
年功序列って、別に否定する必要はないんです。皆、そこばかりに目を向けるのだけれど、儒教文化の「長幼之序(ちょうようのじょ:年長者と年少者の間で当然守るべき社会的・道徳的な秩序のこと。儒教における五つの徳目[五倫:ごりん]の一つ)」を均衡点に我々は長らく過ごしてきました。それを今、変えようとしているんですよね。
もっと言うなら「そもそも」で、「そもそも、何でこれ(年功序列)を変えなきゃいけないの?」というところをちゃんと議論するべきです。年功序列が一概に全部悪いものだということではないと私は思っています。年功序列というのは「年年歳歳(ねんねんさいさい)、功績を積んできた人は、多分これからも功績を積むであろう。だから重く用いる」ことです。ということは、「今まで功績を積んできた人は、これからも功績を積むであろう」という前提があれば、年功序列でいいんです。 ただし、今は変化が激しいので「今まで功績を積んできたからといって、これからも功績を積むとは限らないから、年功序列をやめよう」と言っているだけなんです。ここを勘違いすると私は大変だと思っています。
「年功によらずに、誰が1番活躍しそうですか」と問うと、大体「今まで業績を上げた人」と答えるんです。「そうすると、年功序列ですよね」となる。言っていることとやっていることがズレてくる。結局のところ、感情論になっているのです。自分の上に偉そうな人がいて、「あの人からああだこうだと小言を言われるのが嫌だ」というような感覚です。全然、合理性がありません。そこは、本当に気を付けた方がいいと思っています。
講演の質疑の時間に出たような、若い人にはとてもじゃないけれどできないような高い技術を持っている、ミドルシニアの方もいるわけです。そういう人を年齢でカットするなんて、もうナンセンス極まりないと思います。
― すべての年功序列を無くすと、実際どうなるのでしょうか。

私が以前にいた会社が特殊だったのかもしれませんが、若い時から本当にいろいろなことをやらせてもらったんです。むしろ、私のほうがおじけづくようなことばかり。自分で手を挙げて何かを始めないと、もう1ミリたりとも評価されないような会社でした。下克上はしょっちゅうある、本当に年齢や社歴にまったく関係のない、すごく緊張感のある世界でした。私はそういう世界は、誰もが耐えられる環境だとは思わなかったです。私もギリギリでなんとか運よく生き抜いた感じでした。
今の多くの若い人たちは「年功序列は悪だ」と言うかもしれないけれども、とはいえ、あの時の私がいた会社のようなシビアな競争だけの世界でやっていけるのか?と思うんです。ある意味では仮想的有能感ですよね。多分多くの人は、緩やかな年功序列のほうがカンファタブル(comfortable:落ち着いているさま。快適なさま。居心地がいいさま)なんです。アメリカのプロフェッショナルファームのような、生き馬の目を抜くようなところで快適に生きていける人はほんの一握りだと思います。
自分はどういう人間なのか、自分はキャリアや人生に何を求め、大事にしているのか、「自分を知る」ことが大事です。『LIFE SHIFT』のリンダ・グラットンも言っていましたよね、「自分の性格を、ちゃんと考えてごらんなさい」と。
年功序列がダメだと言っても、自分の志向性と能力水準を考えた時に、「本当に自分はそれに耐えられるのか。あなたもそれを突きつけられるんだよ」ということを認識しないといけない。
― 「環境や価値観が変わっていくこと」を前提に「今」を考えるためには、どういう考え方をしながらキャリアを積んでいくと変化に対して柔軟に対応できるようになりますか。
『ネオキャリア論の失敗』という論文をご存知でしょうか。私はそれを読んで「一理あるな」と思いました。今のキャリア論って「皆、どんなキャリアでもいいんだよ」なんて言いながらも、結局右肩上がりを前提にしているようなところがあるんです。「私はこのままでいいんです」というような考え方って、否定されるんですよ。これね、現実的じゃないなと思ったんです。大部分の方は「常に上昇志向!」というわけではなくて、実はもっとマイルドなんですよ。私だってそうです。そんなね、ガリガリ上を目指そうなんて毛頭思わない。
でも、上を目指し続けること、右肩上がりになることを良しとするような、「ガリガリやらなきゃ人間のクズだ」、「勝った人だけが勝者で、あとは全部敗者だ」みたいな。そんな世の中は、おかしいんです。
ですので、まず「自分の志向性をちゃんと見極めましょう」です。それこそ。エドガー・シャインの『キャリア・アンカー』をやってみてもいいですよ。保障・安定(Security/Stability)や生活様式(Lifestyle)のタイプだったりすると、脱・年功序列の能力主義なんて辛いです。自分は一体どういうはたらき方の癖があって、どういうことを幸せだと思うか、認識、自己理解をすることです。
エドガー・シャインは「キャリア・アンカーは変わらない」と言っていますが、環境によって変わるんです。だから、時代時代に応じて、自分のはたらき方を振り返りながらちゃんと再設計をし続けること、これがむしろプロティアンだと、私は思います。
― 年齢に関係なく、自分を知ること、そのために客観的、俯瞰的に自分を見つめる機会を意識的に設けることは、大事ですね。

私もね、特に年齢を重ねてから「本当に自分はまだ続けられるのか」「私はまだチャレンジできるのか」ということを自分に問いかけています。それでね、まだまだ気力はありそうだと。ただ、先日ぎっくり腰になったら全くやる気がなくなって(笑)「こんなふうに俺もなるんだな」と思いました。「まだ俺はいけるのか」と自分に問いかけながら歩んでいくのは、やっぱミドルシニアだと思うんですよね。でも逆に言うと、「まだできるかもしれない」と思ったら、それをやらなきゃダメです。すぐ翼は萎えますから。そこはもう「やれよ!動けよ!」です。
― 会社として何をどこまでやればいいのか、施策が効いているかどうかわからない人事の方も多いのではないかと思います。
講演でもお話しましたが、人と組織を「共進化」させなければいけない。今の均衡点では両方が不幸になっています。これを、よりWinWinの均衡点に遷移させなければいけない。
私は、人から動かすべきだと思っていて、まずはミドルシニアそのものを変えなければいけない。このミドルシニアの中の人たちに、自分の可能性を信じてもらって「もう1回やってみようかな」という気持ちにしていくことが重要です。
全員が一気に変わるなんていうことはありません。まずは最初、それこそ普及曲線と同じで、イノベーター、アーリーアダプターぐらいを動かすわけです。そこからアーリーマジョリティに持っていくというのが常道ですから、まずはイノベーター、アリーアダプターでいいからキャリア自律を促して、「なんか面白いことできそうだ」っていう人たちに対して「この会社の中で自分ができる仕事って、他に何があるのか考えてみよう」というような研修をさせることなんだと思います。
「どこまでやるか」ということを、あまり考えない方がいいですよ。まずはやってみること。 どこまでやったらいい、いけない、という基準なんてないのだから。それを考えると「やらないための理由」になるんです。そうではなくて、やってもらう。まず、人の進化を促すような研修などをやった方がいいと思います。その後にジョブ開発を真面目に組織としてやっていく。
例えば、ミドルシニアだけを集めたサービサー会社や営業会社を作ってみてもいい。皆やらないだけなので、なんでもやってごらんと。そのうちに自分たちに1番身の丈に合ったものが見つかるから。そしたら、そこを拡大していけばいい。
これもエフェクチュエーション(Effectuation:ビジネスを進めながら決定要因を決めていく手法)的なやり方ですよね。コーゼーション(Causation:最上位に存在する目標数値を最初に設定して、その目標を達成するために、戦略を決め戦術に落とし込む、目標ありきの考え方)をするべきではないと思います。
― 講演の中でも、「失敗はどれぐらいなのか」「成功はどれくらいなんだ」「どれくらい儲かるのか」ではなく、「これぐらいの損失なのであれば、やっちゃえ!」というお話がありましたが、その考え方になかなか気付かないというか、なりにくいですよね。
エフェクチュエーションという理論があるのだから、それを使ってしまえばいいと思いますよ。サラス・サラスパシーの分厚い本は読みにくいけれど、日本人が書いたエフェクチュエーションの進め方、入門書のようなものもあります。そういう本をとりあえずは読んでみて「動いてみる」じゃないですかね。
気付いたら、やらない理由の方向に考える癖がついてしまっているんですよね。それで自分では真面目に仕事をしてるつもりになっている。リスクを考えるとかね。それは、違うと思うな。
講演に続き、まさに本質に立ち返る「そもそも」のお話や、現実的にどこからどう動くことが本質的な課題解決や結果につながるのかということを教えていただきました。人と組織の「共進化」、WinWinの均衡点に遷移させていくこと、それにはまずは人から動かすこと。「まだできるかもしれない」と思ったらやること、「どこまでやるか」ということを考えずに、まずはやってみること。
個人も人事も「動いてみる」。今日のお話を「そもそも」のきっかけにしていただけたらと思います。
\野田氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2024 Autumn】
ミドルシニア問題の本質 〜地に足のついた課題解決に向けて
\野田氏登壇のセミナーレポート無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2024 Autumn】
ミドルシニア問題の本質 〜地に足のついた課題解決に向けて
Profile

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科
教授
野田 稔 氏
一橋大学大学院 商学研究科 修士課程修了。
野村総合研究所、リクルート新規事業担当フェロー、多摩大学経営情報学部教授などを経て、2008年より現職。専門は組織論、組織開発論、人事・人材育成論、経営戦略論、ミーティングマネジメント。学生の指導に当たる一方、企業に向けて組織・人事領域を中心に、幅広いテーマで実践的なコンサルティング活動や講演活動を行う。人材マネジメント分野の開拓者の一人である。最近ではメタバースを応用した業務の効率化、イノベーションの推進の研究にも取り組んでいる。
組織論、リーダーシップ論に関する書籍多数、ニュース番組のキャスターやコメンテーターなど、メディア出演も多数。
- 記事をシェアする