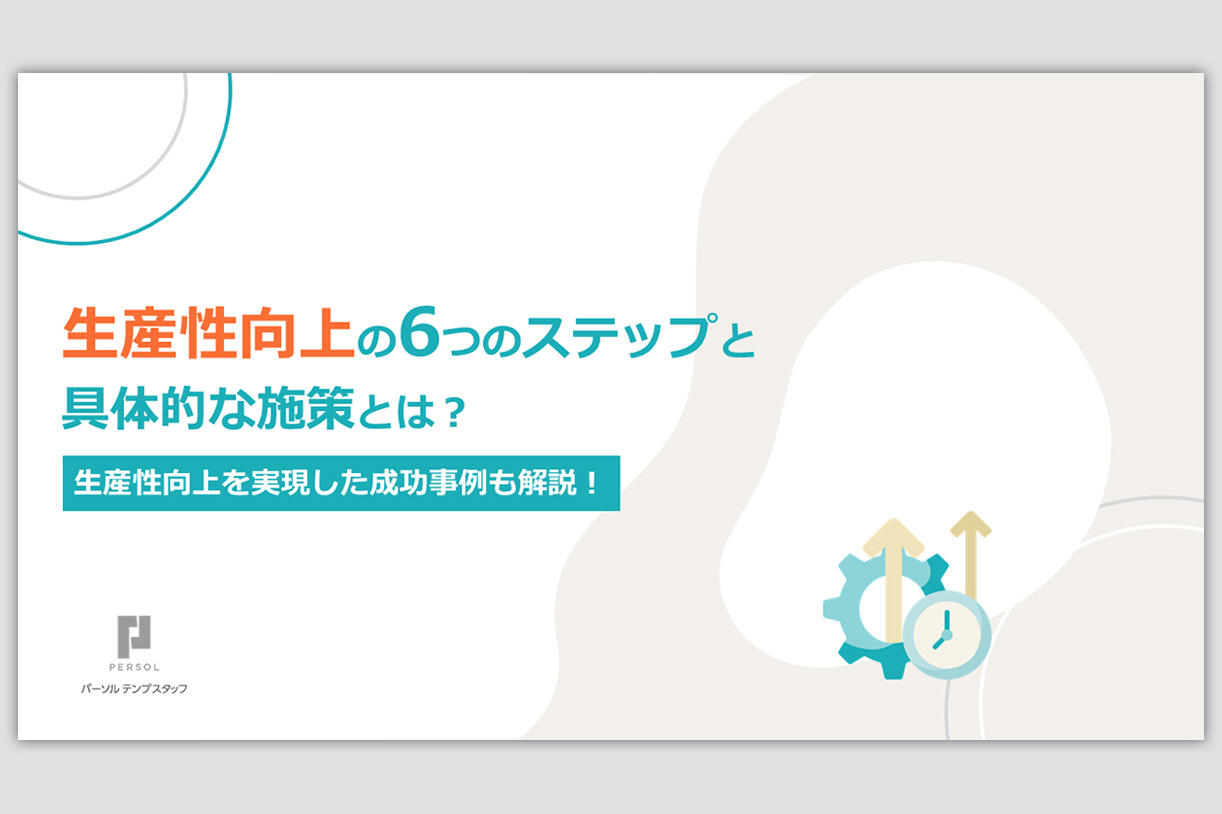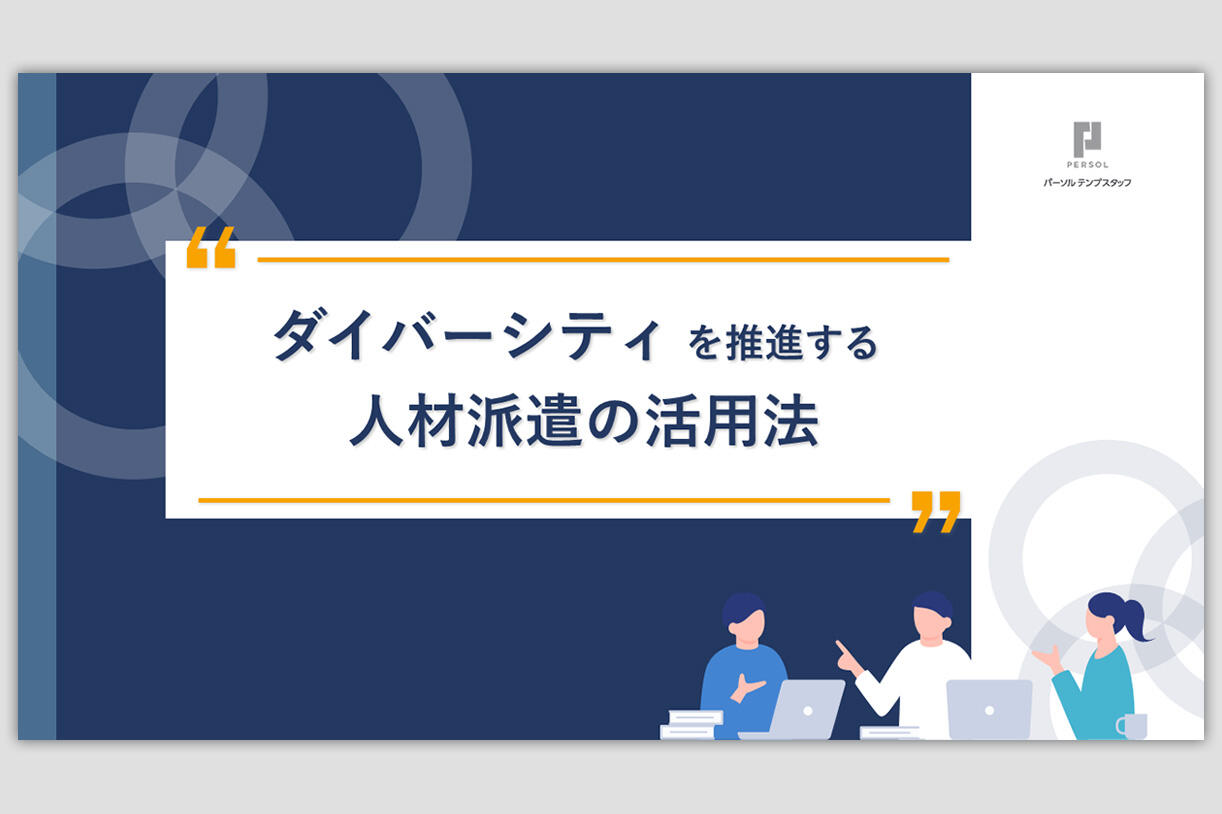HRナレッジライン
カテゴリ一覧
フリーアドレスとは?目的や導入の流れ、メリット、留意点について解説
- 記事をシェアする

働き方改革やデジタル化が進む中、固定席を設けず、自由な席で仕事ができるフリーアドレスを導入する企業が増えています。その目的は、コミュニケーションの活性化やあらたなイノベーションの創出などさまざまです。多くのメリットがあるフリーアドレスですが、各社員の席が決まっている固定席とは異なるため留意すべき点もあります。
今回は、フリーアドレスの概要や導入するメリット、留意点、導入の流れを解説します。フリーアドレスの導入を検討している方は、ぜひご一読ください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
フリーアドレスとは
フリーアドレスとは、オフィス内に各社員の固定席を設けず、はたらく場所を自由に選択できるはたらき方のことです。
フリーアドレスには、部署や組織を超えて自由に席を選べる「完全フリーアドレス」と部署内に限定した「グループアドレス」の2パターンがあります。いずれも部署やチームを超えたコミュニケーションがとりやすくなる点が大きな特徴です。
また、席の配置・種類も企業によって異なり、立ちながら作業ができるスタンディングデスクやソファー席、WEB会議に使えるブース席などを設けているケースもあります。
このように、フリーアドレスは社員ごとに専用の席が与えられるのではなく、はたらく場所を自由に選択できる新しいはたらき方といえるでしょう。
フリーアドレスが注目されるようになった背景
フリーアドレスを導入する企業が増えた背景には、厚生労働省より「働き方改革」が推進されていることが挙げられます。例えば、働き方改革のテーマの一つであるテレワークは、場所や時間を問わずに業務を遂行するというはたらき方です。テレワークの普及でオフィスへ出社する社員が減少したことにより、社内スペースを有効活用しようという企業が増えています。また、テレワークでは、社員同士のコミュニケーションの希薄化という課題もあがりました。こうした背景を受け、社内スペースを有効活用しながら、活発的にコミュニケーションを取れる方法としてフリーアドレスが注目されています。
さらに、モバイル端末の普及やデジタル化もフリーアドレスが浸透した背景の一つです。こうした技術が浸透する以前の業務では、社員や部署ごとに資料を管理する必要がありました。そのため、各社員にデスクを配置し、固定電話やパソコン、資料を保管するキャビネットを設けなければなりません。しかし、テクノロジーの進化により、資料はクラウド上で管理できるようになったほか、ノートパソコンやスマートフォン、タブレットの普及によりオフィスでなくても業務ができ、業務に伴う物理的な障壁が解消されたため、場所に捉われずにはたらくフリーアドレスが注目されています。
フリーアドレスの目的
フリーアドレスを導入する目的は、社員同士のコミュニケーションを活性化させることです。オフィス内の自由な席ではたらけるようになると、部署やチームだけでなく役職の壁を超えた交流が生まれやすくなります。
また、社内のスペースを有効活用する点もフリーアドレスを導入する目的の一つです。フリーアドレスでは社員ごとにデスクを設ける必要がないため、レイアウトの自由度が上がります。その結果、休憩スペースやWEB会議用スペースを設けるなど、用途に合わせた活用が可能です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
フリーアドレスを導入するメリット
フリーアドレスを導入する主なメリットして以下の3点が挙げられます。
- 社内コミュニケーションの活性化
- オフィススペースの有効活用
- 生産性の向上
それぞれのメリットについて解説します。
社内コミュニケーションの活発化
固定席では、同じ顔ぶれの中で仕事するケースが一般的でした。一方で、フリーアドレスでは日々隣ではたらいている社員が異なり、これまでに交流する機会がなかった他部署や役職の異なる社員とのコミュニケーションが図りやすくなります。
社内コミュニケーションが活発になると、自身とは異なる視点やアイデアが生まれ、あらたなイノベーションの創造につながります。また、仕事の悩みや課題についても相談しやすくなるため、社員のはたらきやすさが向上するでしょう。
オフィススペースの有効活用
フリーアドレスを導入すると、社員ごとにデスクを設ける必要がなくなります。これによりスペースに余剰が生まれ、オフィススペースを別の用途として有効活用できるでしょう。例えば、空きスペースを休憩や社員コミュニケーションの場所として活用すれば、より快適な職場環境が整い、柔軟なアイデアが生まれやすくなるでしょう。
また、社員一人ひとりのデスクが不要になれば、その分オフィスを縮小することも可能です。その結果、オフィスの賃料の削減にも期待できます。
生産性の向上
フリーアドレスの導入により、社員自身が業務内容に合わせたはたらき方ができるため、主体性や行動力が上がり、生産性の向上にもつながります。
例えば、部署を超えたチームで業務を行う場合にはコミュニケーションを取りやすいフリースペースを活用したり、集中して資料を作る際は個室やパーソナルスペースを活用したりなど、状況に合わせてはたらく場所を決めることが可能です。
このように、フリーアドレスの導入により、社員一人ひとりに合ったはたらき方ができることは、はたらく人にとって大きなメリットといえるでしょう。
生産性の向上については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説
フリーアドレスを導入する際の留意点
フリーアドレスを導入することで多くのメリットを得られますが、以降でご紹介するような留意点も存在します。フリーアドレスを導入した際の留意点について見ていきましょう。
部署での連携が煩雑化する
フリーアドレスの導入により、部署を超えたコミュニケーションが活性化する一方で、部署内における連携が不足する可能性があります。
固定席であれば、目の届く範囲に部下や同僚がいるため、互いの進捗状況や抱えている課題などを把握できるでしょう。しかし、自由な席で仕事をすることで部署内の状況に目が行き届かなくなると、進捗の遅れやトラブルが発生した場合に適切な対応が難しくなります。また、新入社員の教育がしにくい点もフリーアドレスを導入する際の留意点といえます。
座席管理が難しくなる
自席が固定されていないフリーアドレスでは、誰がどこで作業しているのか把握しづらく座席管理が困難です。例えば、電話を取り次ぐ際に、当該社員の所在が分からなければ取引先や顧客を待たせることになるでしょう。
また、固定席であれば社員の出社状況を一目で把握できますが、フリーアドレスの場合は状況把握に手間がかかります。
私物や持ち物の管理が難しくなる
固定席の場合、各社員にデスクが与えられるため、私物や持ち物は自分のキャビネットで管理するケースが一般的です。しかし、フリーアドレスの場合、特定のデスクがなく、席を移動するたびに荷物を持ち歩く必要があります。
荷物の中には貴重品や重要書類などもあり、持ち運びの手間がかかるだけでなく、持ち歩くのを忘れたことにより紛失するリスクもあるでしょう。忘れ物があっても、誰の持ち物か分からないというケースも考えられます。
フリーアドレスを導入する際のポイント

先述の通り、フリーアドレスを導入することで、部署内での連携が煩雑になったり、座席管理や私物・持ち物管理が難しくなったりなど留意すべき点があります。こうした留意点を解決するには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- フリーアドレスを導入する目的を浸透させる
- フリーアドレス内での仕組みを作る
- 業務のデジタル化を図る
3つのポイントについて詳しく解説します。
フリーアドレスを導入する目的を浸透させる
社員が目的を理解しないままフリーアドレスを導入しても、いつも同じ社員の隣で業務したり、業務内容と合わない座席のスペースになったりするため、コミュニケーションの活性化やアイデアの共有などのメリットを十分に得ることはできません。こうした事態を防ぐためにも、フリーアドレスを導入する際は、目的を明確にした上で社員に共有することが大切です。
また、フリーアドレス化に向けて、社員からアンケートを取り、意見を反映していく必要もあるでしょう。例えば、自由な席を設けるだけでなく、一人で集中して作業ができる個室やWEB会議に使える防音ブースなどが必要という意見があれば、反映することでよりフリーアドレスが浸透しやすくなります。
フリーアドレス内での仕組みを作る
フリーアドレスを導入した上で、部署内で連携が取れる仕組みを作ることも重要です。仕組みが整っていなければ、フリーアドレスの導入により、業務効率が落ちる可能性があります。
例えば、部署内の連携を取りやすくするには、定期的に同一部署内でミーティングを設けることが効果的です。また、グループごとに席のエリアを決めるといった「グループアドレス」を運用するのもよいでしょう。
そのほか、フリーアドレスは気心の知れた社員同士が集まりやすいため、雑談が増える可能性があります。そうなれば、会話に集中してしまい業務の生産性が低下するでしょう。このような課題を解決するには、いつも同じ顔ぶれが集まらないように席を替える日を設けたり、オープンスペースとプライベートスペースを明確に分けたり、といった工夫が必要です。
業務のデジタル化を図る
フリーアドレスの導入を前に、業務のデジタル化を図ることも重要です。例えば、ペーパーレス化が実現すると、重要な情報を持ち歩く手間が減るほか、紛失のリスクも解消されます。また、座席管理システムを取り入れれば、各社員の所在を把握しやすくなるでしょう。
その他、RPA(Robotic Process Automation)もフリーアドレス導入に向けたデジタル化に適しています。RPAとは、パソコンを使ってデスクワークを自動化するソフトウェアロボットです。例えば、社員の勤怠管理や製品の在庫管理、請求書発行など業務フローが明確な作業に活用できます。従来では手作業で行っていた業務をRPAに任せられれば、空いた時間を利益に直結する業務に充てることが可能です。その結果、社員同士の交流やアイデア、知見のやりとりに時間を割けられるため、より一層の生産性向上が期待できるでしょう。
RPAについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>RPAとは?注目されている背景やメリットをご紹介
フリーアドレスを導入する流れ
フリーアドレスの導入効果を最大限発揮するには、導入までの流れを把握した上で、正しく進めることが大切です。フリーアドレスの導入までの流れについて解説します。
STEP1.フリーアドレス導入の目的を決める
フリーアドレスを導入する際は、まず導入する目的を決めることから始めます。「社内のコミュニケーションを活性化させたい」「生産性向上を目指したい」「利益向上のためにあらたなイノベーションが必要」など、自社の状況を洗い出した上で目的を決めましょう。
また、各社員の席が決まっている固定席が浸透している企業では、あらたなはたらき方に不安を覚える社員も多いでしょう。フリーアドレスについて社員が安心して取り組めるように、導入する目的を丁寧に説明することが必要です。
STEP2.フリーアドレスの対象となる社員を決める
フリーアドレスを導入する目的が決まったら、次にフリーアドレスの対象となる社員を決めます。すべての業務にフリーアドレスが適しているとは限りません。例えば、総務や人事、経理など、特に社内との連携が必要な部門は、社員の所在を明確にしていた方が効率的です。また、商品サンプルや社内の機密情報などを取り扱う業務でも、セキュリティ保護のために固定席が向いているでしょう。
一方で、社外に出かけることの多い営業職や、会議・ミーティングで席を外す機会がある企画担当者などの席は、フリーアドレスを導入することで有効的なスペースを作り出せます。このように、フリーアドレスを導入する際は、業務内容を考慮した上で対象となる社員を選ぶことが大切です。
STEP3.座席数や運用を決める
フリーアドレスの対象となる社員を選定したら、オフィスに用意する座席数を検討する必要があります。座席数を決める際は、出社する社員の割合を示す在席率を考慮するとスムーズです。週ごと、時間ごとに社員の在席状況を調査し、用意すべき座席数を算出するとよいでしょう。
また、座席の運用方法を決めることも重要です。例えば、部署を超えた社員同士の交流やあらたなアイデアの創出を目的とする場合は「完全フリーアドレス」が適しています。一方、部署内の連携強化や試験的にフリーアドレスを導入する場合は「グループアドレス」を導入するとよいでしょう。
STEP4.必要な備品やルールを決める
フリーアドレスの導入にあたり、業務内容に見合った備品を選定する必要があります。例えば、社員同士の交流が目的であれば大勢が座れるテーブルスタイルのデスクが適しているでしょう。状況に合わせてレイアウトを変える場合は、キャスター付きのデスクが向いています。ほかにも、個室ブースやソファーなど、どのような備品があると作業効率が向上するかを検討しながら選定しましょう。
また、フリーアドレスをうまく活用するためには、運用ルールの整備も欠かせません。例えば、「前日と同じ席は使えない」というルールを決めれば、いつも同じ社員が集う問題を解消できます。さらに、私物の紛失を防ぐには、収納ルールも必要でしょう。誰もが快適に仕事ができるように、フリーアドレスの運用ルールはあらかじめ策定し、社員全体に周知することが大切です。
STEP5.運用を開始する
フリーアドレスの運用ルールまで整ったら実際に運用を開始します。しかし、フリーアドレスを導入しただけでは、期待する効果が得られるとは限りません。導入後、社員に対して面談やアンケートを行い、フリーアドレス化による課題、不明点がないか細かく分析することが大切です。その上で、必要があれば状況に応じて改善し、社員全体が快適にはたらける環境整備を整えるとよいでしょう。
また、フリーアドレス化した後も、導入による課題の洗い出しや改善を定期的に行い、よりよい職場環境を作ることが大切です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
フリーアドレスを導入してはたらきやすい環境を作る
フリーアドレスは、固定席とは異なりはたらく席を自由に選べるオフィススタイルです。フリーアドレスの導入により、チームや部署、役職を超えたコミュニケーションの活性化・あらたなイノベーション創出に役立ちます。
一方で、部署内の連携が希薄になったり、座席管理が困難になったりといった留意点もあるため注意が必要です。こうした課題を解消してメリットを確実に得るには、事前に導入の目的を明確にする必要があります。その上で、対象となる社員や必要な備品、ルールなどを決めて運用を開始するとよいでしょう。また、運用開始後も定期的に効果を測定し、問題があればその都度改善することも大切です。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする