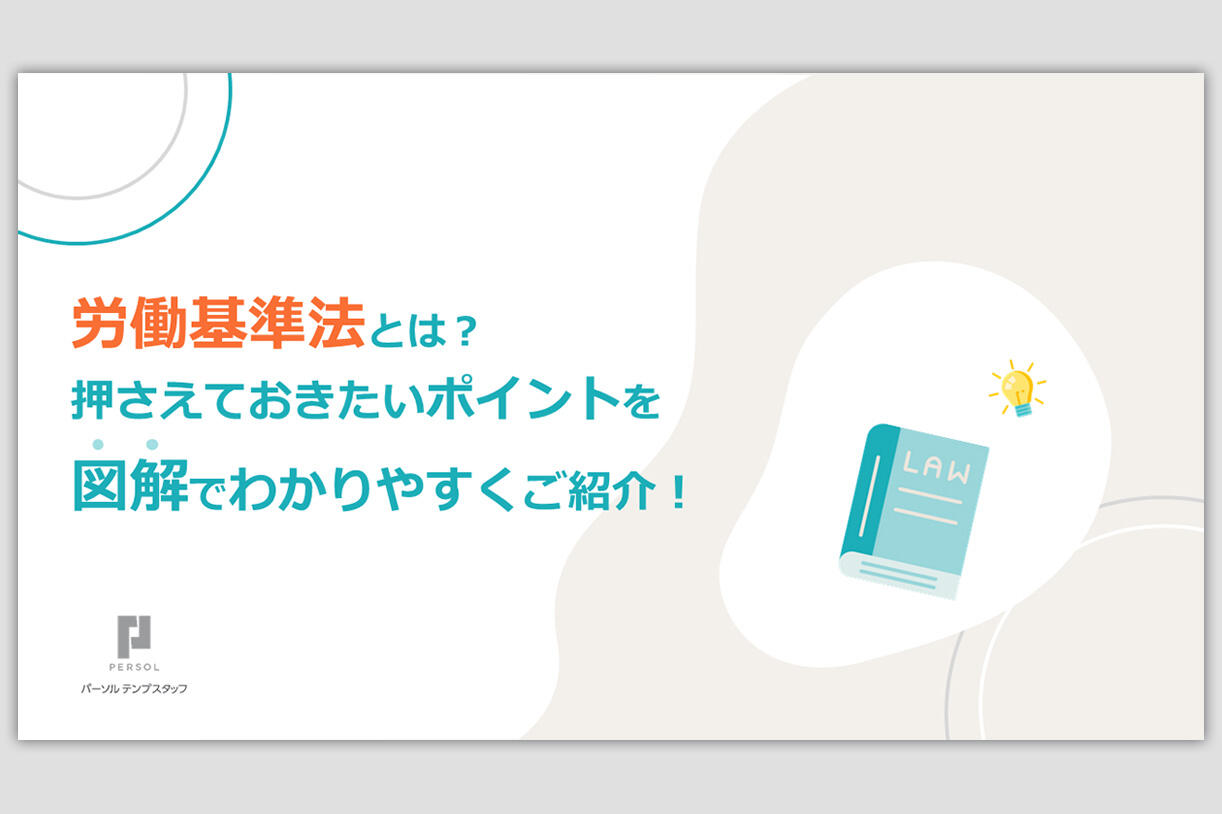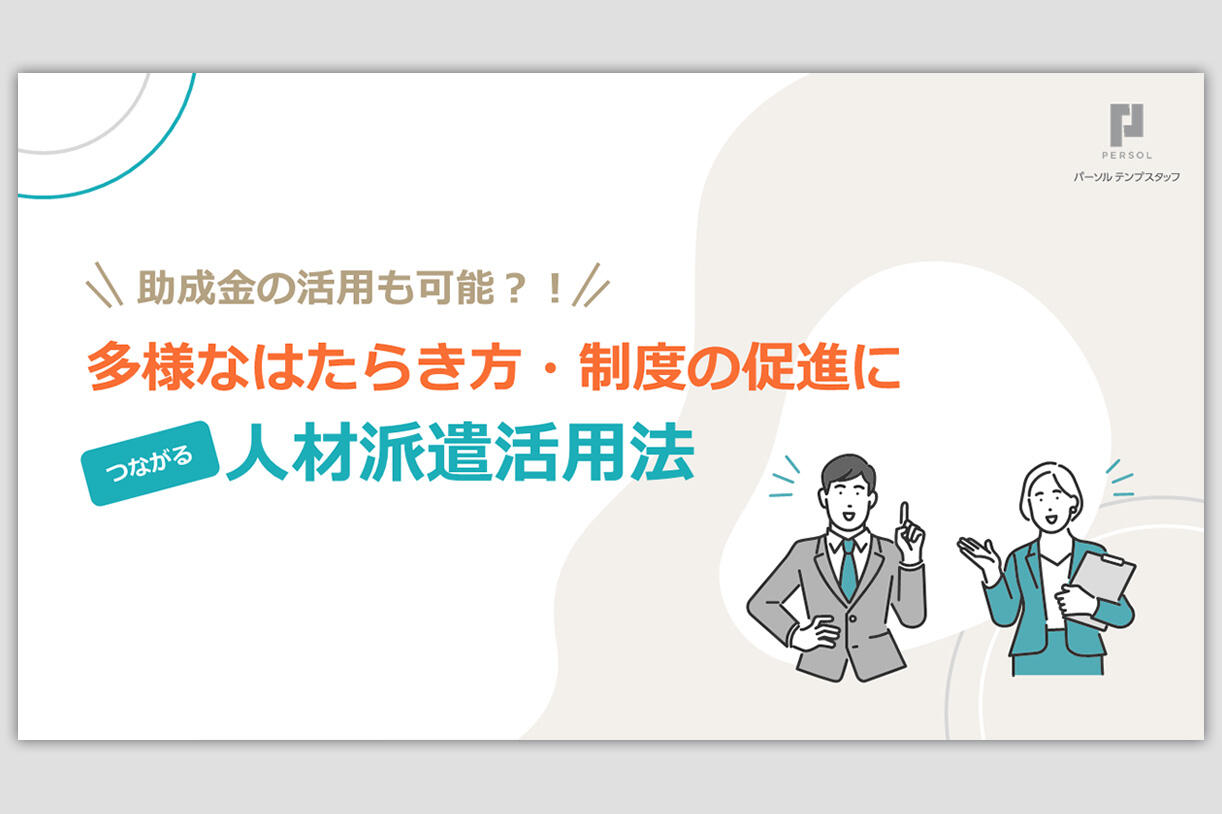HRナレッジライン
カテゴリ一覧
変形労働時間制とは?メリットと導入時の留意点、残業代の計算方法を解説
公開日:2025.07.11
- 記事をシェアする

変形労働時間制とは、労働時間を1年単位や1ヶ月単位などで柔軟に調節できる制度です。
本記事では、変形労働時間制の内容やメリット、導入の流れ、変形労働時間制における残業代の計算方法などを分かりやすく解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて労働時間を調整するための制度です。
労働基準法では労働時間は1日8時間まで、1週40時間と定められています。しかし、変形労働時間制を取り入れていれば、繁忙期や閑散期に合わせて1日の労働時間を柔軟に設定し、月単位・年単位・週単位で労働時間を設定できます。
例えば、やるべき仕事がたくさんある繁忙期には、労働時間を1日8時間以上に設定することで必要な仕事を対応できるでしょう。逆に、閑散期は1日8時間以下に設定すれば、繁忙期に多くはたらいた分の労働時間を調整できます。
みなし労働時間制(裁量労働制)との違い
みなし労働時間制(裁量労働制)は、労使協定であらかじめ決定した時間分を労働したとみなし、労働時間を算定する制度です。例えば、1日8時間とみなして契約した場合、実際の労働時間に関係なく8時間分の賃金を支払えばよいということです。
みなし労働時間制は、進め方などを社員の裁量に委ねられる、変形労働時間制より自由度の高いはたらき方といえます。ただし、実際は長時間の労働があったとしても時間外労働という考え方がないため、残業代などの賃金は発生しません。
交代勤務制(シフト制)との違い
交代勤務制(シフト制)は、原則24時間にわたって対応している病院やコンビニエンスストアなどで多く利用されている制度です。勤務時間は労働契約に基づいて決定されます。早番・中番・遅番などのパターンを決めておき、出勤可能な日・時間帯を選択することが一般的です。そして、曜日や複数に分けられた時間帯ごとに社員が入れ替わり、勤務します。
変形労働時間制は繁忙期や閑散期に合わせ、労働時間の長さを柔軟に細かく調整できる制度です。ただし、労働時間や対象期間などの確定には労使協定を締結しなければなりません。一方のシフト制は、職場側が社員の希望を踏まえてシフトパターンを作成します。そのため、社員が任意で始業・終了時刻を決めることはできません。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
変形労働時間制の種類について
労働基準法では、変形労働時間制として以下の4種類が定められています。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
- 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
- フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
種類ごとの特徴を以下にまとめます。
| 1ヶ月単位の変形労働時間制 | 1年単位の変形労働時間制 | 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | フレックスタイム制 | |
|---|---|---|---|---|
| 休日の付与日数と連続労働日数の制限 | 週1日または4週4日の休日 | 週1日(※1) | 週1日または4週4日の休日 | 週1日または4週4日の休日 |
| 1日の労働時間の上限 | - | 10時間 | 10時間 | - |
| 1週の労働時間の上限 | - | 52時間(※2) | - | - |
| 1週平均の労働時間 | 40時間 (特例44時間) |
40時間 | 40時間 | 40時間 (特例44時間) |
| 時間・時刻の指示 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 出退勤時刻の個人選択 | - | - | - | 〇 |
| 終業規則等での時間・日数の明記 | 〇 | 〇(※3) | - | - |
| 対象となる事業規模・種類の制限 | - | - | 社員数30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店 | - |
- ※1 対象期間における連続労働日数は6日(特定期間については12日)です。
- ※2 対象期間が3ヶ月を超える場合は、回数などの制限があります。
- ※3 1ヶ月以上の期間ごとに区分を設け労働日、労働時間を特定する場合、休日、始・終業時刻に関する考え方、周知方法などの定めを行うこととなります。
- ※引用:徳島労働局|労働時間:変形労働時間制(変形労働時間制)
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の一定の期間で各週の平均が40時間以下となるよう労働時間を決める仕組みです。平均40時間を超えなければ、1日8時間や週40時間などの法定労働時間を超えることができます。また1週間の法定労働時間については、特例的に44時間にすることが認められる場合があります(労働基準法施行規則第25条の2)。
常時10人(パートやアルバイトを含む)未満の社員を使用しており、病院などの医療系や社会福祉施設など特定の業種に該当する事業場は、週44時間の法定労働時間の特例が適用される対象です。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月から1年までの労働時間を平均して週40時間以内に収まるように調整する制度です。
1年単位の変形労働時間制の場合、1日8時間、週40時間を超える労働時間を設定できます。ただし、1日あたりの労働時間の上限は10時間、1週間あたりの労働時間の上限は52時間です。
1年単位の変形労働時間制では、週44時間の法定労働時間の特例は適用されません。
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、1日の労働時間を10時間以内、1週間の労働時間を40時間以内という条件にし、1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に調整できる制度です。導入できる業種は、社員が30人未満の小売業や旅館、料理店、飲食店などに限定されます。
これらの業種が対象となっている理由は繁閑差が大きく、繁閑のサイクルが決まっていないことにより、適切な労働時間が特定しにくいためです。各日の労働時間を就業規則などで決めず、上限を超えない範囲において、週単位で毎日の労働時間を効率的に配分できるようにしています。
フレックスタイム制
フレックスタイム制も変形労働時間制の一つです。フレックスタイム制では、清算期間と呼ばれる最長3ヶ月の期間における総労働時間をあらかじめ定めておき、その中で日々の出退勤時刻や労働時間を社員が自身の裁量で決めて柔軟にはたらけます。
ただし、清算期間を1ヶ月より長く設定する際には、その旨を定めた労使協定を労働基準監督署に提出する必要があります。
変形労働時間制のメリット
変形労働時間制を導入するメリットは以下の2つです。
- はたらきやすさの向上
- 残業時間の削減
それぞれ具体的に解説します。
はたらきやすさの向上
変形労働時間制を導入すると、仕事の状況に応じて労働時間を調整できるため、はたらきやすさの向上が期待できます。例えば、閑散期でやることがないにもかかわらず社員が出社しなければならないといった無駄を省けることがメリットです。
変形労働時間制を導入する企業側のメリットとしては、生産性が高まることが挙げられます。社員のモチベーションや健康状態、ワーク・ライフ・バランスが整うことで、業務の効率化やリソースの最適化が期待できます。
企業が行うべきワーク・ライフ・バランスへの取り組みや、メリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
>>ワーク・ライフ・バランスへの取り組みとは?企業が行うべき社内整備を解説
残業時間の削減
残業時間を減らし、コストを削減できることも、企業が変形労働時間制を導入するメリットです。閑散期は労働時間を短く設定し、その分を繁忙期に充てて労働時間を長くすることによって、残業代が発生しにくくなります。
また、閑散期で仕事が少ない時に一定の給与を支う必要がなくなり、人件費を抑えられることも変形労働時間制で得られるメリットです。
変形労働時間制の留意点
変形労働時間制は残業時間の削減が可能などメリットもありますが、間違いやすい点や気をつけるべき点もあります。導入する上で留意するべきポイントを2つご紹介します。
労働時間の管理が必要
変形労働時間制を導入している場合、労働時間が時期により変動するため、正しい労働時間が把握できず、法定労働時間を超えていることに気付かない可能性があります。このようなトラブルを避けるために、労働時間の適切な管理が必要です。
変形労働時間制では時期によって労働時間が変わるため、勤怠管理や賃金計算などの業務が複雑化する可能性があることも、留意しなくてはなりません。
所定労働時間は繰り越せないため注意が必要
変形労働時間制は、対象期間内の労働時間を一定の範囲内で自由に調整できる点が魅力です。ただし、残業時間と所定労働時間を相殺することはできません。
例えば、所定労働時間で8時間と定められた期間に1日9時間はたらいたとします。しかし、8時間を超えた分を繰り越して翌日の労働時間を1時間短くしても、平均して8時間はたらいたことにはなりません。日をまたいでの労働時間の調整は不可能です。つまり、8時間を超えて仕事をした日は、労働基準法に則って1時間分の残業代が発生することになります。
変形労働時間制手続きの流れ
変形労働時間制を導入する際は、必要事項を決定した上で所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。ここからは、変形労働時間制の届出をするときの流れを手順に沿って解説します。実際に手続きを進めるときは参考にしてください。
対象者と労働時間の選定
まず自社の労働状況を調査し、現状を把握することが大切です。繁忙期と閑散期はどの期間で、所定労働時間はどれくらいが適切かを具体的に把握しておかないと、変形労働時間制の採否の判断や効果的な運用ができないためです。
次に、変形労働時間制の対象となる社員の範囲や労働時間について具体的に決定します。調査内容と照らし合わせながら、繁忙期に残業が多くなりがちな社員や労働時間が超過しやすい時期、どのように変形労働時間制を適用すればよいかを検討していきましょう。
就業規則の見直し
変形労働時間制を導入すると、労働時間を柔軟に調整するため、従来の就業規則に合わない場合があります。社員労働者と企業のニーズを合致させるために、労働時間や休暇、残業などに関する規定の見直しが必要です。
以下のような内容を就業規則に追記し、変形労働時間制に対応できるようにしましょう。
- 対象社員の範囲
- 対象期間および起算日
- 労働日および労働日ごとの労働時間
- 各労働日の始業・終業時刻
- 労使協定の有効期限
労使協定の締結
1年単位の変形労働時間制を導入する場合、労使協定の締結が必要です。
労使協定に定めなければならない項目は以下の通りです。
- 対象社員の範囲
- 対象期間と起算日
- 特定期間
- 労働日と労働日ごとの労働時間
- 当該労使協定の有効期限
変形労働時間制の種類にかかわらず、労使協定条項の要件を満たしていない労働があった場合、労働基準法32条違反として罰則が適用される可能性があります。
労働基準監督署に届出を提出
労使協定を締結したら、速やかに所轄の労働基準監督署に提出します。1ヶ月単位の変形労働時間制を就業規則に定めている場合は、その就業規則の提出が必要です。厚生労働省ホームページよりダウンロードできる「変形労働時間制に関する協定届」を提出用と控え用に1部ずつ用意しましょう。
また、添付書類として就業規則や労使協定、勤務カレンダーなども一緒に提出します。労使協定には有効期限があるため、更新する場合はその都度改めて届け出なければなりません。
変形労働時間制は、労使協定の届出をせずに導入をスタートすると労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が課せられます。適切な手続きを行った上で、変形労働時間制の運用を始めましょう。
変形労働時間制における残業代の計算方法
変形労働時間制を導入する場合であっても、定められた法定労働時間の上限を超えた場合は時間外労働扱いとなり、残業代が発生します。
ここでは、変形労働時間制の種類ごとに、残業代の計算方法を解説します。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合
1ヶ月単位の変形労働時間制では、まず以下の3つの基準で計算した時間を合計し、残業時間を算出します。
| 残業時間と見なされる対象 | |
|---|---|
| 日ごとの基準 | 所定労働時間が8時間を超えている日の場合:所定労働時間を超えてはたらいた分の時間 所定労働時間が8時間以内の日の場合:8時間を超えてはたらいた分の時間 |
| 週ごとの基準 | 所定労働時間が40時間(特例では44時間)を超えている週の場合:所定労働時間を超えてはたらいた分の時間 所定労働時間が40時間(特例では44時間)以内の週の場合:40時間(または44時間)を超えてはたらいた分の時間 ただし、日ごとの基準で残業としてみなされた分の時間を除く |
| 月ごとの基準 | 月ごとの法定労働時間の上限を超えてはたらいた分の時間 ただし、日ごと・週ごとの基準で残業としてみなされた分の時間を除く |
月ごとの法定労働時間の上限は、月の暦の日数や、週の法定労働時間によって変わります。具体的な時間は以下の通りです。
| 暦の日数 | 週の法定労働時間が40時間の場合 | 週の法定労働時間が44時間の場合 |
|---|---|---|
| 28日 | 160時間 | 176時間 |
| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |
| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
上記の基準に従って算出した残業時間に対して発生する基礎賃金に、自社で定める割増率を掛けた賃金が残業代となります。
1年単位の変形労働時間制の場合
1年単位の変形労働時間制でも、残業代を計算する流れは同様です。まず以下の3つの基準で計算した時間を合計し、残業時間を算出します。
| 残業時間と見なされる対象 | |
|---|---|
| 日ごとの基準 | 所定労働時間が8時間を超えている日の場合:所定労働時間を超えてはたらいた分の時間 所定労働時間が8時間以内の日の場合:8時間を超えてはたらいた分の時間 |
| 週ごとの基準 | 所定労働時間が40時間を超えている週の場合:所定労働時間を超えてはたらいた分の時間 所定労働時間が40時間以内の週の場合:40時間を超えてはたらいた分の時間 ただし、日ごとの基準で残業としてみなされた分の時間を除く |
| 1年間の基準 | 1年間の法定労働時間の上限を超えてはたらいた分の時間 ただし、日ごと・週ごとの基準で残業としてみなされた分の時間を除く |
1年間の法定労働時間の上限は、通常は2091.4時間、うるう年は2085.7時間です。算出された残業時間に対して発生する基礎賃金に、自社で定める割増率を掛けることで、残業代を計算できます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合
1週間単位の非定型的変形労働時間制では、以下の2つの基準で計算した時間を合計し、残業時間を算出します。
| 残業時間と見なされる対象 | |
|---|---|
| 日ごとの基準 | 所定労働時間が8時間を超えている日の場合:所定労働時間を超えてはたらいた分の時間 所定労働時間が8時間以内の日の場合:8時間を超えてはたらいた分の時間 |
| 週ごとの基準 | 所定労働時間が40時間を超えている週の場合:所定労働時間を超えてはたらいた分の時間 所定労働時間が40時間以内の週の場合:40時間を超えてはたらいた分の時間 ただし、日ごとの基準で残業としてみなされた分の時間を除く |
算出した残業時間分の基礎賃金に、自社で定める割増率を掛けることで残業代を計算できます。
フレックスタイム制の場合
フレックスタイム制では、予め定めた清算期間中に、月ごとの法定労働時間を超えてはたらいた時間が法定外残業時間として扱われます。月ごとの法定労働時間は以下の通りです。
| 暦の日数 | 週の法定労働時間が40時間の場合 | 週の法定労働時間が44時間の場合 |
|---|---|---|
| 28日 | 160時間 | 176時間 |
| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |
| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
法定外残業時間に対して発生する基礎賃金に、自社で定める割増率を掛けることで残業代を計算できます。
また、フレックスタイム制においても、少なくとも毎週1日、または4週間につき4日の法定休日を設けることが定められています。そのため、法定休日にはたらいた場合は、時間外労働に対する残業代とは別に割増賃金の支払いが必要です。
変形労働時間制についてのよくある質問
ここでは、変形労働時間制について、よくある質問とその回答をご紹介します。
変形労働時間制を導入する際は、労働時間の管理や賃金計算が複雑になりやすい点に注意が必要です。
Q1. 年単位の変形労働時間制の労働日数の限度は?
1年単位の変形労働時間制では、原則として1年あたり280日が労働日数の限度です。
Q2. フレックスタイム制を適用できる対象者は?
フレックスタイム制を適用する対象者は、18歳未満の年少者を除き、各事業者が労使協定で任意に決めることができます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
変形労働時間制の種類やメリットを理解して適切に運用しよう
変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期がある企業において業務の繁閑に合わせて労働時間を柔軟に変更できる制度です。1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制の4種類の中から、自社に合った勤務体制を選択できます。
適切に変形労働時間制を活用できれば、企業にとっては残業時間の抑制や社員の総労働時間の短縮が可能です。社員にとってもメリハリのあるはたらき方が可能になるため、就業満足度の向上やワーク・ライフ・バランスの実現が期待できます。
ただし、変形労働時間制を導入する際は、労働時間の管理が複雑化しやすいことが留意すべきポイントです。変形労働時間制のルールや残業代の計算方法などを理解し、適切に運用しましょう。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする