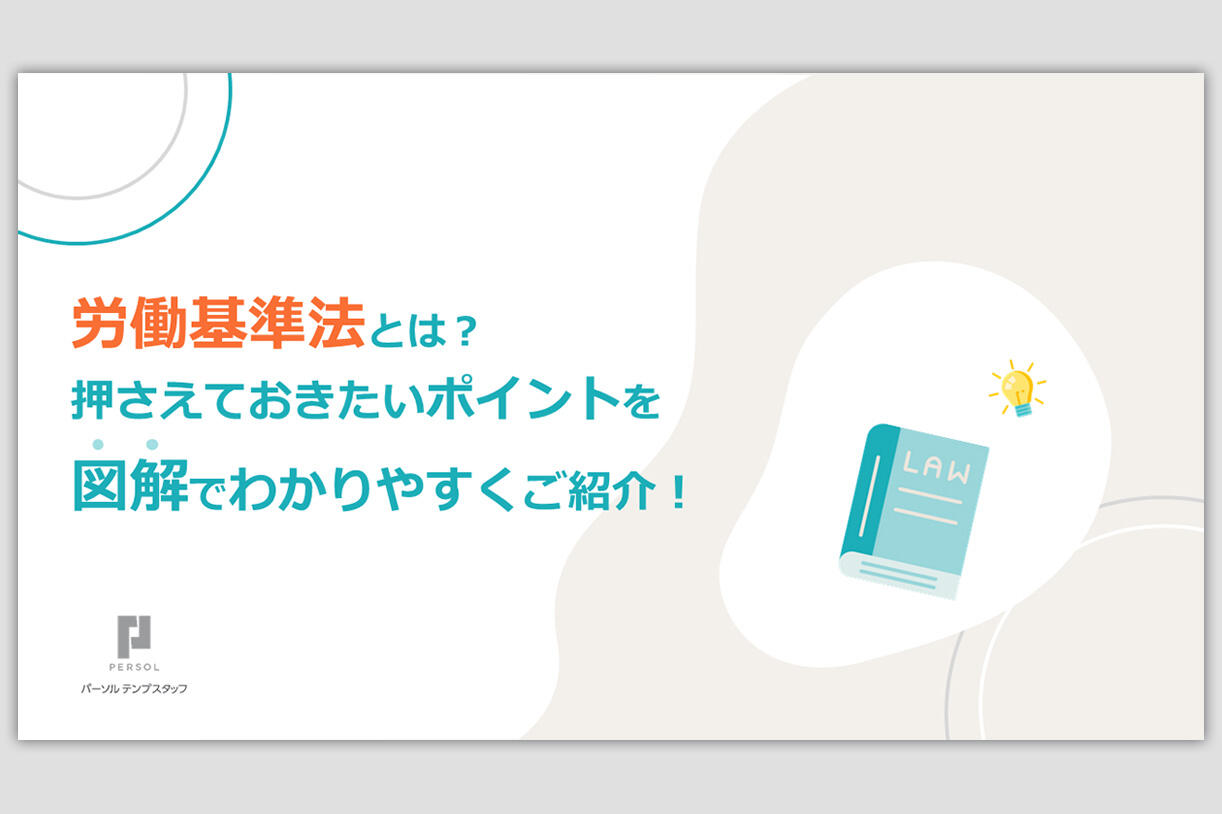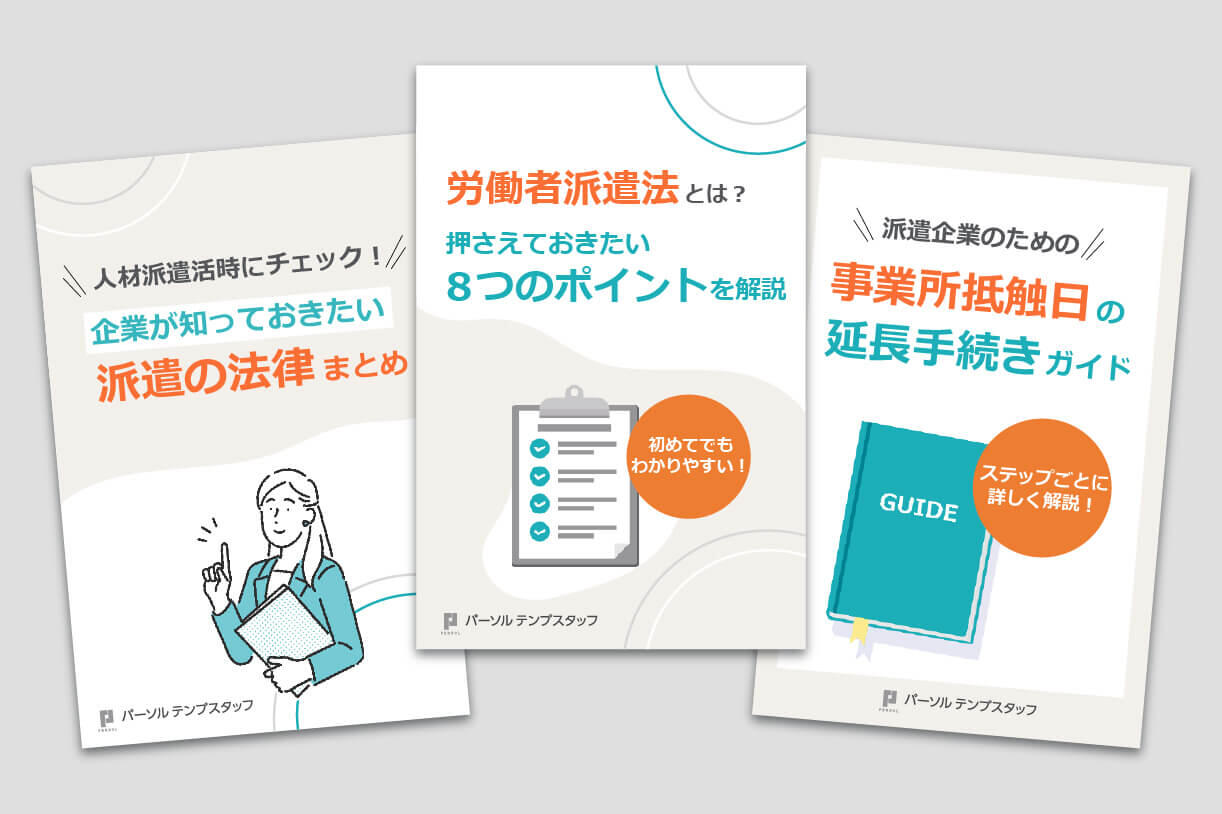HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【企業向け】雇い止めとは?労使間のトラブルを防止するポイントを解説
公開日:2025.08.28
- 記事をシェアする

雇い止めとは、企業が有期労働契約ではたらく従業員に対し、労働契約期間が満了した際に、その契約を更新せずに終了することです。
ただし、雇い止めに関しては法的な注意点が多く、労使間でトラブルになるケースも見られます。
そこで本記事では、雇い止めの定義、無効になる要件や正当な理由、企業からの明示・予告義務、トラブル防止のポイントなどについて解説します。
正しい知識のもとで適切な対応を行い、労使間のトラブルを防ぎましょう。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
雇い止めとは
「雇い止め」とは、企業が有期労働契約ではたらく従業員に対し、労働契約期間が満了した際に、その契約を更新せずに終了することをいいます。つまり、期間の定めのある労働契約において、企業側が労働契約の更新を行わないという意思表示をすることです。
雇い止めは解雇とは異なり、契約期間が満了したことによる契約の終了ですが、企業が注意すべき点が多く、ルールを守る必要があります。
雇い止めと労働契約満了はどう違うのか
労働契約満了とは、期間の定めのある労働契約が、契約書に定められた期間が終了することを指します。契約時に労使間で合意した期間が経過したことによる、自然な形で終了するということです。
一方、雇い止めは、労働契約満了のタイミングで、企業が労働契約の更新を行わないことを決定し、労働契約を終了することを意味します。両者の大きな違いは、法的なルールの適用方法です。単なる労働契約満了であれば、原則として契約は期間の到来とともに終了します。
しかし、雇い止めの場合、特に「契約が繰り返し更新されている」など、従業員が契約の更新を期待することが合理的だと認められる状況には、労働契約法によって契約終了が厳しく判断される場合があります。
雇い止めは、「単に契約期間が終わった」というだけでなく、それ以降の契約更新をしないという意思決定を伴う行為であり、状況によっては解雇に準じた法的な規制を受ける可能性があるという点で、単純な労働契約満了と区別されるのです。
企業が雇い止めを行う際には、労働契約法などのルールに則った適切な対応が求められます。
雇い止めと解雇はどう違うのか
雇い止めと解雇の違いは、労働契約を終了させるタイミングです。
解雇とは、期間の定めのない労働契約や、期間の定めのある労働契約の契約期間の途中で、会社が一方的に従業員との契約を終了させることを指します。例えば、会社の業績不振や従業員の規律違反などを理由に、まだ契約期間が残っているにもかかわらず、会社都合で辞めてもらうといったケースが当てはまります。解雇は、労働契約法によって厳しく規制されており、客観的かつ合理的な理由と、社会通念上の相当性がなければ無効となります。
一方、雇い止めは前述の通り、期間の定めのある労働契約が満了した時点で、会社が契約を更新しないことによって労働契約を終了させることをいいます。
つまり、1番の違いは「いつ」契約を終了させるかという点です。それぞれの契約が終了となるタイミングは以下の通りです。
- 雇い止め:契約期間の満了時に終了(更新しない)
- 解雇:契約期間の途中に終了
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
有期契約労働者の「5年ルール」と従業員を保護する観点の重要性
有期契約労働者を雇用する企業が理解しておくべき重要なルールとして、いわゆる「5年ルール」があります。これは、正式には「無期転換ルール」といい、平成25年4月1日に改正労働契約法が施行された際に導入された制度です。
「5年ルール」(無期転換ルール)とは
「5年ルール(無期転換ルール)」は、有期労働契約が繰り返し更新され、通算の契約期間が5年を超えた場合、従業員からの申し込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものです。
従業員から無期転換の申し込みがあった場合、企業は原則として拒否できません。このルールは、有期契約労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。
5年ルールに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
>>人材派遣の5年ルールとは?概要や3年ルールとの違いを解説
従業員保護の観点が重要
「5年ルール」の導入や、その他の雇い止めに関するルールは、有期契約ではたらく従業員が不安定な雇用から脱却し、長期的なキャリア形成を図れるようにするためのものです。
期間の定めがあるという理由だけで、更新の期待があるにもかかわらず一方的に雇用を打ち切られることがないよう、従業員の立場を保護する観点が重視されています。
雇用形態の違いによる不利益な取扱いをなくすよう、厚生労働省は「同一労働同一賃金」に関するガイドラインも定めています。「同一労働同一賃金」に関しては以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてお読みください。
>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介
雇い止めと失業保険
雇い止めによって従業員が離職した場合の失業保険(雇用保険の基本手当)の扱いは、従業員保護の観点と関連しています。
通常、労働契約期間満了による離職は自己都合退職となることが多いです。しかし、一定の条件に該当する場合、雇い止めによる離職は「会社都合退職」として扱われる場合があります。
特に、3年以上の期間にわたって雇用されていた有期契約労働者が雇い止めによって離職した場合は、原則として会社都合退職として扱われる傾向があります。
会社都合退職と判断されると、従業員は失業保険の給付において、自己都合退職よりも有利な条件で受け取ることが可能です。具体的には、通常7日間の待期期間に加え2~3ヶ月の給付制限期間がある自己都合退職と比べて、待期期間満了後、比較的給付される期間が長くなる場合があります。
これらの制度は、有期契約労働者が、雇用終了時に経済的に困窮することのないよう配慮された、労働者保護のための仕組みです。
よって企業は、「5年ルール」による無期転換権の発生を適切に管理することに加え、雇い止めを行う際には、労働契約法や雇用保険のルールを踏まえ、労働者保護の観点から丁寧な説明と対応を行うことが極めて重要となります。これらのルールを正しく理解し、遵守することが、不要な労使間トラブルを防ぐことにつながります。
雇い止めが認められず無効となる場合
雇い止めが認められず、無効になるケースについて解説します。
期間の定めのある労働契約でも、会社が自由に更新を拒否できるわけではありません。労働契約法第19条では、いわゆる「雇い止め法理」が定められており、特定の条件下での雇い止めは無効となる場合があります。
雇い止めが無効と判断されるのは、主に以下のいずれかの要件を満たし、かつ、会社による雇い止めに「客観的に合理的な理由」がなく「社会通念上相当であると認められない」場合です。
「雇い止め法理」の適用
「雇い止め法理」が適用されるのは、以下の2つのような要件を満たしている場合です。
- 過去に何度も労働契約が更新され、長期間雇用が継続しているなど、実質的に期間の定めのない契約(無期契約)と同じような状態になっていると判断される場合。
- 有期労働契約の契約書に「契約を更新する場合がある」と記載されている、または面接時に長期雇用を期待させるような説明があった、過去の更新手続きが形骸化している、といった状況があり、従業員が「今回も当然更新されるだろう」と期待することに無理がないと判断される場合。
これらの要件のいずれかに該当する場合、会社は容易に雇い止めを行うことはできません。
雇い止めを有効とするためには、解雇と同様に、客観的かつ合理的な理由があり、それが社会通念上相当であると判断される必要があります。
契約期間が満了しても、会社が一方的に契約更新を拒否する「雇い止め」は法的に無効と判断され、従業員から労働契約上の地位確認などを求められるリスクがあります。
企業としては、労働契約内容の明確化や説明責任を果たすとともに、雇い止めを行う際には、その理由が客観的に見て合理的であり、社会的に妥当なものであるかを慎重に判断することが必要です。
雇い止めの正当な理由とは
雇い止めに関して客観的に合理的な理由とは、誰が見ても納得できるような、もっともな理由であるということです。
また、社会通念上相当であることとは、雇い止めを行うことが、社会の一般的な感覚から見てやむを得ない、または許容できる範囲であるということです。
具体的にどのような理由が「正当な理由」と認められるかは、個別のケースによって判断が分かれますが、一般的には以下のようなものが該当しうる理由として挙げられるでしょう。
| 理由 | |
|---|---|
| 会社の経営状況の悪化 | 事業の縮小や廃止に伴い、その職務自体がなくなる場合など |
| 事業所の閉鎖・移転 | 勤務している事業所自体が閉鎖されたり、遠方に移転したりする場合 |
| 勤務態度や能力の不足 | 注意指導を重ねても改善が見られない、業務遂行に必要な能力が著しく不足している場合など |
| 不正行為や規律違反 | 会社の信用を著しく傷つける行為や、重大な服務規律違反があった場合 |
| 有期契約の目的に応じた期間満了 | 特定のプロジェクトのために雇用され、そのプロジェクトが終了した場合など、当初から契約期間満了とともに契約が終了することが明確であった場合 |
ただし、これらの理由があったとしても、雇い止めの必要性や、他の部署への配置転換の可能性など、回避努力の有無なども含めて総合的に判断されます。
特に、有期契約労働者の場合、契約更新への期待の度合いなども考慮されるため、慎重な判断が必要です。
雇い止めに関する明示義務とは
企業は、従業員を雇用する際に、労働条件について明示する義務があります(労働基準法第15条)。
そして、有期労働契約においては、明示義務に加え「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)に基づき、特に以下の事項について書面などの方法で従業員へ明確に伝える義務があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約期間 | いつからいつまでの契約であるか |
| 更新の有無 | 契約が更新されることがあるのか、それとも原則として更新しないのか |
| 更新する場合の判断基準 | もし契約が更新される場合、どのような場合に更新されるのか、その判断基準を具体的に示す (例:「勤務成績、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況により判断する」など) |
この明示義務は、労働者が自身の雇用期間や契約更新の可能性について正確に理解できるようにするためのものです。
これにより、労働者は契約更新の期待度を把握し、雇い止めによる不利益を予測したり、次の仕事を探すなどの準備をしたりすることができます。
企業は、トラブル防止のためにも、これらの事項を曖昧にせず、明確に伝えることが重要です。
雇い止めに関する予告義務とは
会社が有期労働契約の従業員を雇い止めしようとする場合、すべてのケースで予告が必要なわけではありませんが、特定の条件を満たす従業員に対しては、契約期間が満了する前にその旨を予告する義務があります。
これも「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)で定められています。
予告義務の対象となるのは、以下のいずれかに該当する従業員です。
- 過去に3回以上契約が更新されたことがある従業員
- 引き続き1年以上雇用されている従業員
- 1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
これらの従業員を雇い止めしようとする場合、会社は原則として、少なくとも契約期間満了の30日前までに雇い止めの予告をしなければなりません。
予告は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐためには「雇止め通知書」といった書面で、雇い止めの理由と併せて行うことが強く推奨されます。
この予告義務は、雇い止めによって従業員が突然職を失うことのないよう、次の就職活動などの準備期間を確保し、従業員を保護するための制度です。
予告を怠った場合、雇い止め自体が直ちに無効になるわけではありませんが、基準違反となり、損害賠償請求などの対象となる可能性があります。
雇い止めに関するトラブルを防止するポイント
雇い止めに関するトラブルを未然に防ぐためには、企業は労働契約法をはじめとする関連法令を遵守し、従業員に対して誠実かつ丁寧な対応を行うことが不可欠です。ここでは、特に重要なポイントをいくつか解説します。
雇い止めの理由証明書の交付義務を守る
有期労働契約の従業員に対して雇い止めを行った場合、対象となる従業員から請求があった際には、会社は「雇い止めの理由証明書」を交付する義務があります。これは、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)によって定められています。
理由証明書に記載すべき事項
証明書には、雇い止めの具体的な理由を記載する必要があります。単に「契約期間満了のため」といった抽象的な理由では不十分です。
| ケース | 記載内容 | 記載例 |
|---|---|---|
| 就業規則の解雇事由に該当する場合 | 就業規則の該当する条項と、それに該当する具体的な事実を記載 | 「就業規則第〇条(勤務態度不良)に基づき、遅刻・欠勤が多い事実を理由とする」 |
| 就業規則の解雇事由に該当しない場合 | 契約を更新しないこととした客観的な理由を具体的に記載 | 「前年度の業務実績評価が〇〇であったため」「会社の経営状況悪化に伴う〇〇事業の縮小のため」 |
理由証明書の書き方のポイント
理由証明書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
| 具体性 | 抽象的な表現ではなく、客観的な事実にに基づいて具体的に記載 |
|---|---|
| 正確性 | 記載内容に誤りがないよう、事実関係を十分に確認 |
| 根拠の明確化 | 可能であれば、就業規則や評価記録など、根拠となる情報を明示することも有効 |
従業員からの請求があった場合、会社は遅滞なく証明書を交付しなければなりません。この証明書の交付は、従業員がハローワークで失業保険の手続きをする際にも必要となる場合があるため、迅速な対応が求められます。
契約締結・更新時の明確な労働条件の明示
トラブル防止の最も基本的な対策は、労働契約を締結する際や更新する際に、労働条件を明確に明示することです。
特に、有期労働契約においては、契約期間はもちろんのこと、契約更新の有無や、更新する場合の判断基準について従業員が十分に理解できるよう、書面などで具体的に示すことが重要です。これにより、「更新されると思っていたのに、雇い止めに遭ってしまった」といった従業員との認識のずれを防ぐことができるでしょう。
契約期間満了に向けた計画的なコミュニケーション
雇い止めを検討する場合、契約期間満了が近づいてから急に通知するのではなく、契約期間中に何度か面談の機会を設けるなど、計画的にコミュニケーションを取ることが望ましいと考えられます。
特に、企業側で「更新の可能性が低い」と判断している場合は、その状況や理由について、契約期間満了の前から段階的に伝えることで、従業員も心の準備ができ、次の就業先を探すなどの対応を取りやすくなります。
「正当な理由」に基づいた判断の重要性
前述の通り、「雇い止め法理」が適用される場面では、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
安易な理由や、感情的な理由での雇い止めは、無効と判断されるリスクが非常に高いです。
雇い止めを行う可能性がある場合は、その理由が法的に見て正当であるかを十分に検討し、必要であれば弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することも重要です。
無期転換ルールへの適切な対応
通算契約期間が5年を超えた有期契約労働者から無期転換の申し込みがあった場合、会社は原則として拒否できません。
この「5年ルール」を正しく理解し、対象となる従業員の契約期間を適切に管理することが重要です。
無期転換を避けたい場合には、通算5年を迎える前に契約期間を終了させるなどの対応が必要になりますが、その場合も雇い止めに関するルール(明示義務・予告義務・理由証明書交付義務)を遵守する必要があります。
これらのポイントを踏まえ、有期契約労働者の雇用管理を行うことが、雇い止めに関するトラブルを防止し、良好な労使関係を築く上で不可欠です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
従業員の権利を保護する観点が重要
「雇い止め」は有期雇用契約を企業が更新しないことであり、解雇とは異なるものの、法的な規制がいくつかある点に注意が必要です。
労使間のトラブルを防止するためには、客観的かつ合理的な理由に基づいた労働条件の明確な明示・事前の予告・理由証明書の交付といった適切な手続きと、従業員への誠実な対応が不可欠です。
正しい知識を身に付けた上で法令を遵守し、円滑な雇用管理を行いましょう。
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする