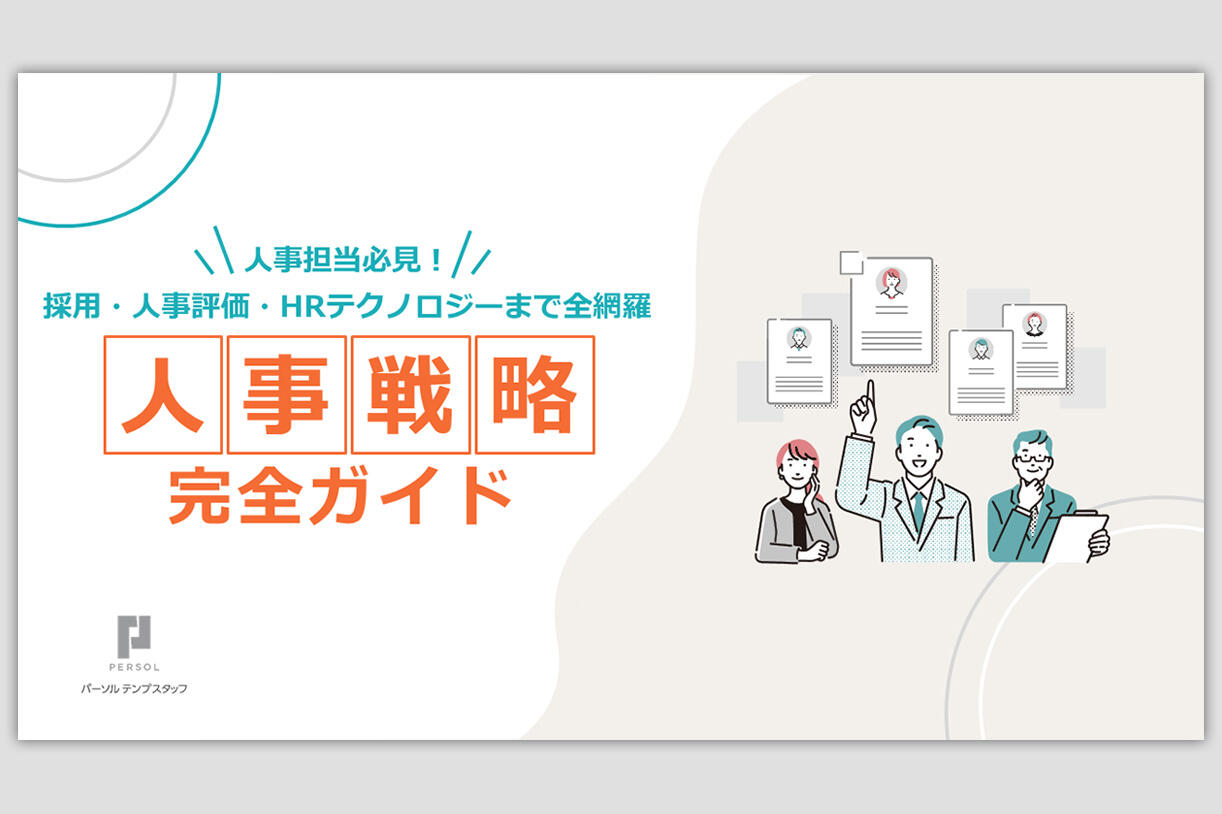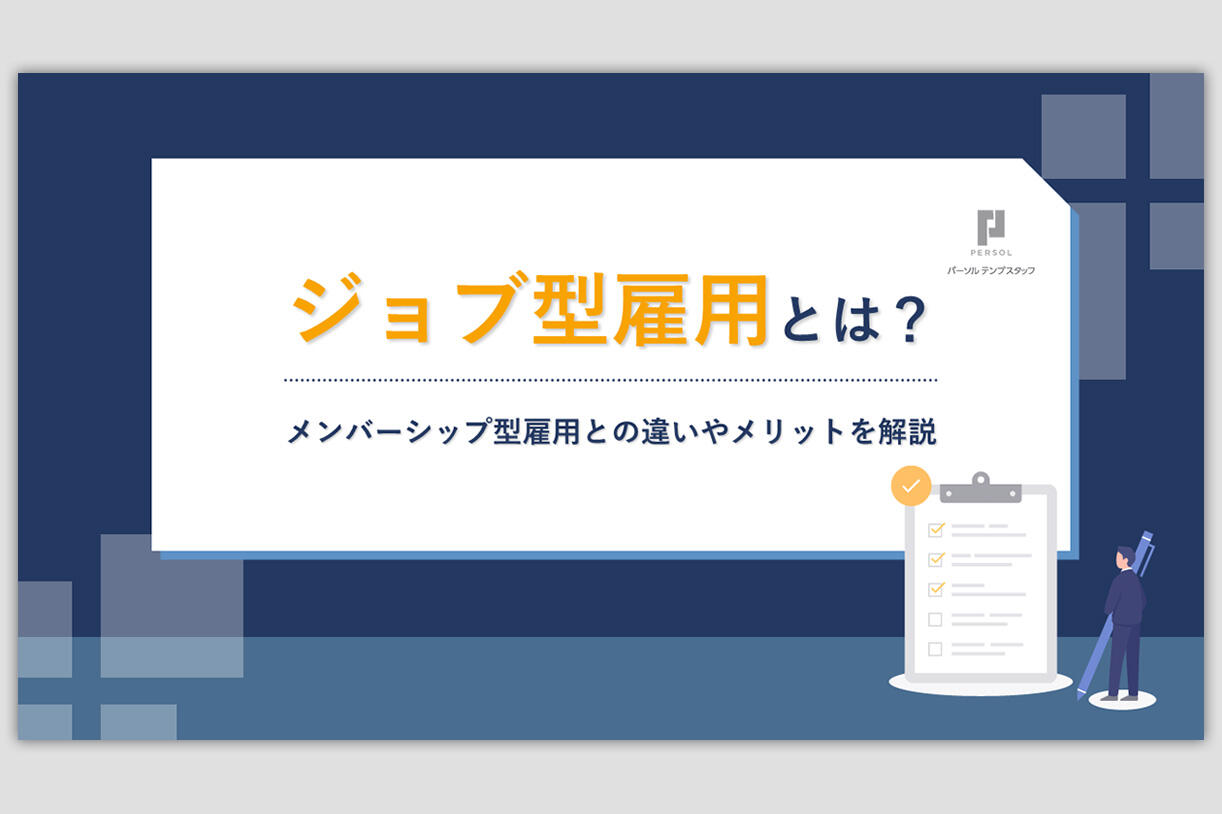HRナレッジライン
カテゴリ一覧
等級制度の3つの種類とは?目的や導入・設計ポイントを解説
- 記事をシェアする

企業における等級制度とは、従業員の能力や遂行している職務内容、または期待される役割などに基づいて等級を設け、人事評価や報酬体系に連動させる人事管理の仕組みです。
現代のビジネス環境では、人材育成の促進や公平な評価の実現のために等級制度の重要性が高まっています。
本記事では等級制度の基本的な考え方や、導入が進む背景、特徴やメリット・デメリット、そして実際に自社に導入・運用するための具体的な手順とポイントなどについて分かりやすく解説します。
等級制度の導入や見直しを検討中の企業や、等級制度の全体像を理解し自社に最適な制度を検討したい方は、ぜひ最後までお読みください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
等級制度とは
企業における等級制度とは、人事評価と関連する制度で、従業員の能力や遂行している職務内容、または期待される役割などに基づいて等級を設け、人事評価や給与・賞与に連動させるための人事管理の仕組みのことです。
等級制度は近年、企業において人材育成の促進やキャリアパスの明確化、評価の公平性・透明性の向上といった目的で導入されつつあります。
等級制度を導入することで、目標が明確になって成長意欲が高まり、自身のキャリアを具体的に描く後押しになったり、評価基準や評価結果への納得度を高めたりできるメリットがあるためです。
企業の人事評価制度については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
>>人事評価制度とは?導入する目的やメリット、設計方法について解説
等級制度の3つの種類
企業における等級制度には、評価の基準や考え方によって、以下で示す3種類があります。自社の文化や目的に合わせて、最適な制度を選択することが重要です。
職能資格制度
職能資格制度は、従業員一人ひとりが「職務を遂行する能力」を基準として等級を定める制度です。
特定のポストや、現在担当している職務内容そのものではなく、個人が持つ知識・スキル・経験といった能力の高さによって序列を決定します。
勤続年数や年齢といった年功的な要素も評価に加味されることが多く、ポストの有無に関わらず能力の向上に応じて等級が上がる可能性がある点が特徴です。日本の多くの企業で長らく導入されてきた人事制度の代表的なスタイルの1つといえます。
職能資格制度については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
>>職能資格制度とは?メリットや導入時の留意点、職務等級制度との違いを解説
職務等級制度
職務等級制度は、従業員が「遂行している職務そのもの」を基準として等級を定める制度です。
個人の能力・経験よりも、担当している職務の難易度、責任の範囲、必要とされる専門性といった「職務の価値」によって等級が決定されます。「ジョブディスクリプション(職務記述書)」によって各職務の詳細な内容や責任範囲が明確に定義される点が大きな特徴です。
職務内容が変わらない限りは原則として等級も変わらないため、「同一労働同一賃金」の考え方と親和性が高く、特に欧米企業で広く導入されています。
「同一労働同一賃金」に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介
役割等級制度
役割等級制度は、従業員一人ひとりに「会社の中で期待される役割」を明確にして、その役割の重要度や、そこから生まれる「成果や貢献」を基準として評価する仕組みです。
どのような仕事(職務)をしているか、どれだけ長い間働いているか(年功)だけでなく、「あなたに、この役割で、このような活躍をしてほしい」という、将来への期待を込めて等級が決まる点が特徴です。
会社を取り巻く状況が変わったときなどに、社員に期待する役割を柔軟に見直し、会社の方向性と個人のはたらきを結びつけやすい新しい考え方の制度として、近年注目されています。
等級制度を導入している企業の割合
等級制度を導入している企業の割合について紹介します。
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が2020年に全国の企業を対象に実施した調査結果によると、等級制度を導入している企業の割合は、職能資格制度は6割弱、職務等級制度は約3割です。
事業所規模別にみると、1,000人以上規模の大企業では職能資格制度を導入している企業が7割強、1,000人未満規模では5割強から6割弱、職務等級制度は 1,000 人以上規模では1割強、1,000人未満規模では3割程度となっていて、主に大企業で導入が進んでいることが伺えます。
等級制度の導入が広がりつつある背景
等級制度の導入が広がりつつある背景について読み解きます。
日本の企業では、年齢や勤続年数に応じて社内での位や給料が上がる「年功序列」の仕組みが一般的でした。
しかし、最近では、等級制度が新たに導入されたり、見直されたりしています。その背景には、社会や経済の大きな変化があります。
大きな変化としてはまず、「人材不足」の課題が挙げられます。 少子高齢化が進み、どの会社も優秀な人材を確保し、辞めずに長く活躍してもらうことが難しくなっています。
また「グローバル化」も挙げられます。 日本国内だけでなく、世界の企業と競争していくためには、従業員一人ひとりが持つ能力や、出した成果を適切に評価し、会社の成長につなげることがより重要になりました。
さらに、「はたらき方や、はたらく人の価値観が変わってきた」という側面も挙げられるでしょう。正社員だけでなく、さまざまなはたらき方をする人が増え、はたらく人が会社に「安定」だけでなく「自分の成長」や「頑張りに見合った評価」を求めるようになっています。
こうした変化の中で、企業は「年齢や勤続年数に関係なく、従業員の能力や貢献を正当に評価したい」「従業員の成長をさらに後押ししたい」と考えるようになり、そのための人事の仕組みとして等級制度の導入が進んでいるのです。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
等級制度のメリット・デメリット
本記事の前半で、等級制度には3種類があると述べました。それぞれにメリット・デメリットの両面があるため、詳しく解説します。
職能資格制度のメリット
職能資格制度のメリットは、従業員の能力向上を促し、長期的な視点での人材育成や、社員の会社への帰属意識を高めやすい点だといえます。また、ポストに縛られずに人員配置を比較的柔軟に行える点も特徴です。
職能資格制度のデメリット
職能資格制度のデメリットは、「能力」という評価基準が曖昧になりやすく、評価者によるばらつきや人件費の高騰リスクが課題となることがある点です。年功的な側面が強い場合、環境変化への対応が遅れたり、入社したばかりの社員はモチベーション維持が難しくなったりする可能性もあります。
職務等級制度のメリット
職務等級制度の大きなメリットは、担当する職務の価値に応じて等級と報酬が決まるため、評価の公平性や透明性が高く、同一労働同一賃金を実現しやすい点です。職務内容が明確なため外部からの人材にも分かりやすく、特定の専門性を追求する環境も作りやすいでしょう。
職務等級制度のデメリット
職能資格制度のデメリットは、社内の全職務を正確に評価し、等級に割り当てる作業が専門的で難易度が高いという点です。職務に紐づくため、ジョブローテーションによる幅広い経験の習得や、ゼネラリストの育成にはあまり向いていません。
役割等級制度のメリット
役割等級制度のメリットは、従業員に期待される役割やそこから生まれる成果・貢献度で評価するため、経営戦略と連動させやすく、市場や事業環境の変化に柔軟に対応できる点です。従業員の成果や貢献への意欲を高め、多様なはたらき方をする人材も評価しやすいでしょう。
役割等級制度のデメリット
役割等級制度のデメリットは、「役割」の定義そのものが難しく、評価基準が曖昧になりやすいリスクがある点です。また、制度を適切に運用するためには評価者の高いスキルが不可欠といった側面も課題となりやすいでしょう。運用が滞ると制度が形骸化し、従業員の納得感を得られなくなる恐れがあります。
等級制度を導入する手順
ここからは、等級制度を導入する手順について解説します。
1.制度導入の目的を明確にする
等級制度を導入する最初のステップとして、「何のために等級制度を導入するのか」という目的を、経営戦略や組織の現状の課題と照らし合わせて明確にしましょう。
例えば、「従業員の成長を促進したい」「評価の公平性を高めたい」「優秀な人材を定着させたい」など、具体的な目的を設定します。
経営層や人事部門だけでなく、現場の意見も聞きながら、全社で共有できる目的を設定することが重要です。目的が曖昧なまま制度設計を進めると、設計の方向性が定まらず、導入後に期待する効果が得られなかったり、従業員から疑問や不満が生じたりする原因となります。
2.等級制度の3種類からどれを導入するのかを決める
最初のステップで明確にした目的や、自社の組織文化、事業内容、目指すはたらき方などを考慮し、前章で解説した「職能資格制度」「職務等級制度」「役割等級制度」の3種類の中から、自社に最も適した制度を選択しましょう。あるいは、これらの制度を組み合わせたハイブリッド型の制度を検討する場合も考えられます。
各制度のメリット・デメリットを理解し、安易に他社の制度を真似るのではなく、自社の特性に合った制度を選ぶことが大切です。制度の種類によって評価の基準や運用方法が大きく異なるため、目的に合わない制度を選んでしまうと、制度が組織に馴染まず、導入効果が得られないだけでなく、組織内での混乱を招く可能性があります。
3.等級の区分を決め、各等級の定義を明確にする
選択した等級制度の種類に基づいて従業員をいくつかの段階(等級)に区分し、それぞれの等級に求められるレベルや基準を具体的に定義します。例えば、等級数をいくつにするかといったことや、各等級に昇格・昇進するための要件などを細かく設定します。
各等級の定義は、従業員が「自分には何が期待されているのか」「どうすれば次の等級に上がれるのか」を明確に理解できるよう、具体的かつ分かりやすい言葉で定める必要があります。
等級の定義が曖昧だと、評価基準が不明確になって従業員が目標設定をしにくくなったり、評価に対する納得感が得られず、モチベーションの低下につながったりする恐れがあるためです。
4.等級制度の運用方法を決める
設計した等級制度を実際にどのように運用していくかを具体的に定めます。等級の昇降格を判断するための人事評価のサイクルや方法(誰がどのような基準で評価するか)、評価結果のフィードバックの進め方、等級と給与・賞与といった報酬をどのように連動させるか、などを詳細に設計します。
制度を公正かつ透明性高く運用するためのルールを明確にし、特に管理職など評価者に対する研修やサポートをしっかりと行うことが成功の鍵となります。
制度を設計しても現場での運用がうまくいかなければ制度は形骸化し、従業員の不満や不信感につながってしまいます。制度が意図した通りに機能し、組織に定着するためには、スムーズで適切な運用が不可欠です。
等級制度設計と運用のポイント
企業における等級制度設計と運用のポイントを解説します。前述した導入の手順とあわせて参考にしてください。
制度設計には現場を理解している従業員にも参画してもらう
等級制度の設計や推進は、人事部門やマネージャー層が中心となって進めることが一般的です。しかし、制度が現場で実際に機能するためには、日頃の職務実態を詳細に理解している現場の従業員にも設計プロセスへ参画してもらうことが非常に重要です。
設計チームに多様な立場や経験を持つ従業員を含めることで、さまざまな視点から制度を検討できます。現場の声を聞くことで、制度と実態のずれを防ぎ、より現実的で運用しやすい制度を設計できます。また、現場の従業員が設計に関わることで、「自分たちのための制度」という意識が生まれ、制度導入後の納得感や受け入れられやすさが大きく向上するでしょう。
制度の運用開始後は定期的に見直しをする
等級制度は、一度設計して運用を開始したらそれで完了ではありません。
組織を取り巻く環境や事業内容は常に変化していくため、導入後も定期的に制度の効果測定を行い、必要に応じて見直しや改定を行うことが不可欠です。
制度の運用状況をモニタリングし、予期せぬ課題や従業員からのフィードバックを収集する仕組みを作りましょう。
定期的な見直しを行わないと、制度が陳腐化して実情に合わなくなる、運用上の問題点が放置されて社員の不満につながるなどのリスクがあります。
時代の変化や組織の成長に合わせて制度をアップデートしていくことで、等級制度は常に有効な人事ツールであり続けることができます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
等級制度は現代のビジネス環境において重要な人事制度
本記事では、企業における等級制度の基本から、評価制度として注目されている理由、制度の種類別の特徴やメリット・デメリット、さらには具体的な導入手順や成功のためのポイントを解説しました。
現代のビジネス環境において、等級制度は従業員の成長を促して公正な評価を行い、組織を活性化させるための重要な人事制度だといえます。
一度制度を導入したら終わりではなく、運用開始後も定期的に効果を測定し、必要に応じて見直しを行うことが制度を長く有効に機能させるために不可欠です。
本記事が等級制度の設計・運用の一助となれば幸いです。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする