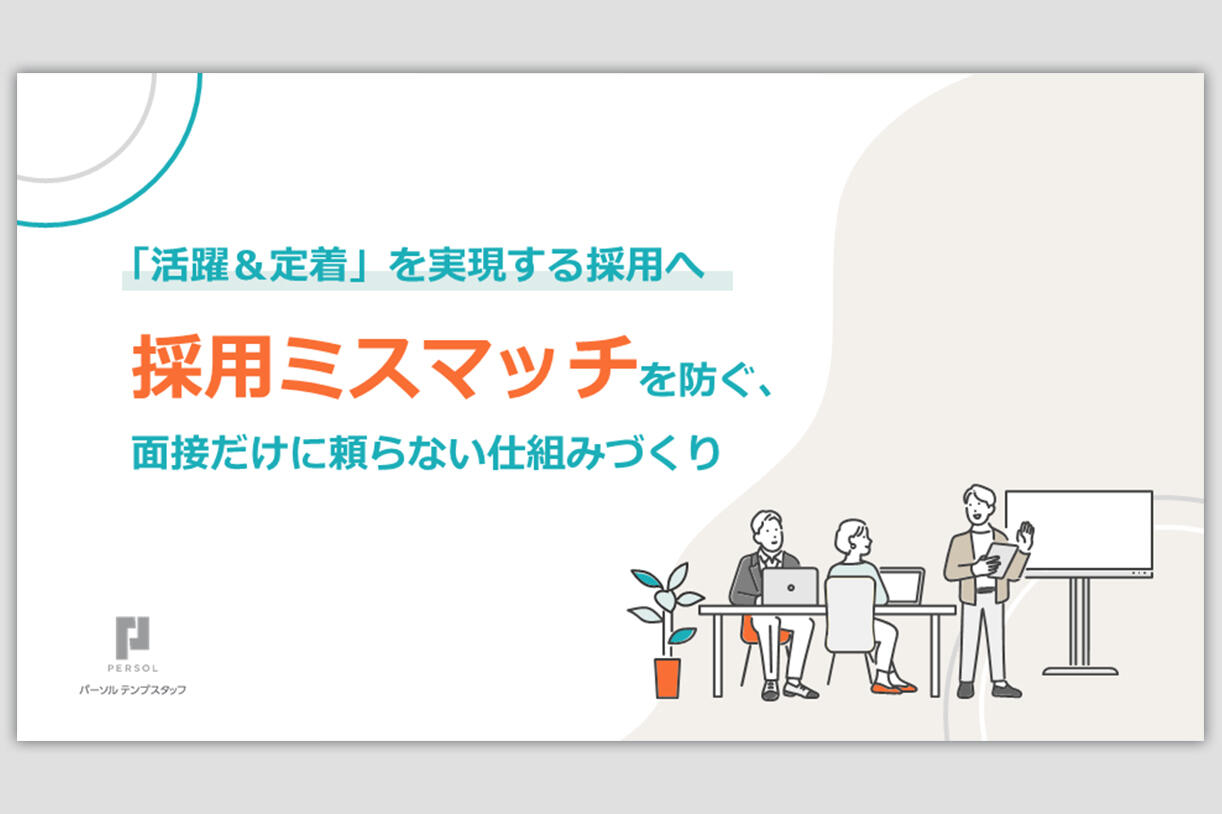HRナレッジライン
カテゴリ一覧
採用KPI設定の5ステップ|人事担当者が知っておくべき指標と活用法
- 記事をシェアする

採用活動を数値で評価し、成果を最大化する「採用KPI」。どのような数値をKPIに設定するべきかによって採用活動の成果が左右される、重要な指標です。
本記事では、KPIの定義や設定方法から、効果的な運用方法と具体的な指標例まで、人事担当者が知っておくべきポイントを網羅的に解説します。
さらに、採用KPIの導入ステップや陥りやすい課題とその解決策、実際の企業の活用事例なども紹介します。採用活動を戦略的に改善し、優秀な人材確保を実現するための第一歩として、ぜひご活用ください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
採用KPIとは
採用KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、採用活動の成果やプロセスを数値化して測定するための指標です。採用活動の現状を客観的に把握し、課題を特定し、効率的に改善するために用いられます。
採用KPIが必要な理由
採用活動は、企業にとって将来の成長を左右する重要な投資です。しかし、その効果を感覚的にしか捉えられていないケースも少なくありません。
採用KPIを設定することで、採用活動の成果を定量的に測定し、客観的なデータに基づいて採用プロセスの効率化や改善点の明確化を図ることができます。特に、無駄なコストの削減や、採用のミスマッチによる早期離職の防止などに有効です。
KGIとの違い
KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とは、組織が達成すべき最終目標を数値で表したものです。採用活動においては、「年間採用人数」や「特定の職種の充足率」などが該当します。
一方、KPIはKGI達成のための中間指標であり、プロセスにおける活動量や効率を数値化したものです。KGIが「結果」を示すのに対し、KPIはその「結果に至るまでのプロセス」を示す指標と言えます。
適切にKPIを設定し、進捗を管理することで、最終目標であるKGI達成の確度を高められます。
【例】エンジニア採用におけるKGIとKPI
KGI:年間でエンジニアを20名採用する
| 採用職種 | 人数 |
|---|---|
| バックエンドエンジニア | 10名 |
| フロントエンドエンジニア | 5名 |
| インフラエンジニア | 5名 |
KPI:採用プロセスごとの目標と現状、施策例
| プロセス | KPI(目標) | 現状 | 施策例 |
|---|---|---|---|
| 応募 | 応募数:200名 | 100名 |
|
| 書類選考 | 書類選考通過率:50% | 30% |
|
| 面接 | 面接通過率:25% | 20% |
|
| 内定承諾 | 内定承諾率:80% | 60% |
|
このように、KGIは最終的な成果を測る指標であり、KPIはその成果を達成するためのプロセスを具体的に管理するための指標です。両者を適切に設定し、PDCAサイクルを回すことで、採用活動の効率と効果を高められます。
採用戦略全体像を把握したい方は、まずはこちらの記事をご覧ください。
>>【採用戦略の決定版】人材獲得競争を勝ち抜くための体系的アプローチ
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
採用KPIの基本要素
採用活動を成功に導くためには、適切なKPI設定が不可欠です。
以下で紹介する13の主要KPIを活用すれば、採用プロセスのボトルネックを特定し、効率的かつ効果的な改善を実現できます。
| KPI | 概要 | 計算方法 | 目標値の例 |
|---|---|---|---|
| 応募率 | 求人広告や採用チャネルに対する応募者の割合を測定する指標。ターゲット人材へのリーチを評価する。 | 応募数÷求人広告の表示回数(または訪問数)×100 | 業界平均、前年実績を参考に設定(2%など) |
| チャネル別応募の質 | 各採用チャネルからの応募者の選考通過率や採用率を比較し、質の高い応募を獲得できているチャネルを特定する。 | 各チャネルからの応募者の選考通過率、採用率 | チャネルごとに目標値を設定(エージェントA:書類通過率30%、採用率5%など) |
| 書類選考通過率 | 書類選考を通過した応募者の割合を測定する指標。書類選考基準の妥当性や応募者の質を評価する。 | 書類選考通過者数÷応募者数×100 | 業界平均、前年実績を参考に設定(30%など) |
| 面接通過率 | 面接を通過した応募者の割合を測定する指標。面接官の評価基準や、候補者の適性を評価する。 | 面接通過者数÷面接実施数×100 | 1次面接:50%、2次面接:25%など、フェーズごとに設定 |
| 選考辞退率 | 選考プロセス中に辞退した応募者の割合を示す指標。選考プロセスの問題や競合状況を把握する。 | 選考辞退者数÷選考参加者数×100 | 業界平均、前年実績を参考に設定(10%など) |
| 内定辞退率 | 内定を提示後に辞退した応募者の割合を示す指標。 | 内定辞退者数÷内定者数×100 | 5%未満など、可能な限り低く抑える |
| 内定承諾率 | 内定を提示した候補者のうち、内定を承諾した割合。優秀な人材に選ばれる企業であるかを測る指標。 | 内定承諾者数÷内定者数×100 | 業界平均、前年実績を参考に設定(80%など) |
| 採用率 | 最終的に採用に至った候補者の割合を測定する指標。採用活動全体の成果を評価する。 | 採用人数÷応募者数×100 | 業界平均、前年実績を参考に設定(5%など) |
| 歩留まり率 | 採用活動における各フェーズで次の工程に進んだ人数の割合をパーセンテージで示した数値。 | 各選考フェーズの通過者数÷各選考フェーズの参加者数×100 | 各フェーズで目標値を設定(書類選考:30%、1次面接:50%、2次面接:25%など) |
| 平均採用期間 | 募集開始から採用決定までの平均所要日数を示す指標。採用スピードを評価し、機会損失を防ぐ。 | 採用決定日-募集開始日の合計÷採用人数 | 業界平均、前年実績を参考に設定(45日など) |
| 採用コスト | 一人当たりの採用にかかった総費用、およびチャネル別にかかった採用コストを測定する指標。費用対効果を改善するための基準となる。 | 採用活動にかかった総費用÷採用人数 各チャネルの採用コスト÷各チャネルからの採用人数 |
業界平均、前年実績を参考に設定(一人当たり50万円、エージェントA:80万円など) |
| 離職率 | 採用後一定期間内に離職した社員の割合を測定する指標。採用の質や企業文化、職場環境との適合性を評価する。 | 一定期間内に離職した社員数÷採用人数×100 | 入社後1年以内の離職率は10%未満など、期間を区切って設定 |
| 社員定着率 | 一定期間経過後も継続して勤務している社員の割合。特に若手社員の定着状況から、オンボーディングや職場環境の問題を洗い出す。 | 一定期間経過後に在籍している社員数÷採用人数×100 | 入社後1年の定着率90%以上など、期間を区切って設定 |
企業や採用フェーズごとに必要なKPIは異なります。自社の採用課題や目的に合わせて、適切なKPIを設定しましょう。
応募率
応募率は、求人広告や採用チャネルに対する応募者の割合を測定する指標です。ターゲット人材へのリーチを評価します。目標値は、業界平均、前年実績などを参考に設定するとよいでしょう。
応募率は、以下の式で求められます。
応募数÷求人広告の表示回数(または訪問数)×100
チャネル別応募の質
各採用チャネルからの応募者の選考通過率や採用率を比較し、質の高い応募を獲得できているチャネルを特定し、チャネルごとに目標値を設定します。目標値には、応募者の書類通過率、採用率などを設定することが多いです。
書類選考通過率
書類選考を通過した応募者の割合を測定する指標です。書類選考基準の妥当性や応募者の質を評価するのに役立ちます。業界平均や前年実績などを参考に設定します。
書類選考通過率は、以下の式で求められます。
書類選考通過者数÷応募者数×100
面接通過率
面接を通過した応募者の割合を測定する指標です。面接官の評価基準や候補者の適性を評価するのに用いられます。フェーズ(1次面接・2次面接など)ごとに目標値を設定すると管理がしやすくなります。
面接通過率は、以下の式で求められます。
面接通過者数÷面接実施数×100
選考辞退率
選考プロセス中に辞退した応募者の割合を示す指標です。選考辞退が多い場合、選考プロセスの長さや内容、または他社との競合状況に原因がある可能性があります。目標値は業界平均や前年実績などを参考に設定します。
選考辞退率は、以下の式で求められます。
選考辞退者数÷選考参加者数×100
内定辞退率
内定を提示後に辞退した応募者の割合を示す指標です。給与条件や社内環境、他社のオファー状況など、内定を辞退する要因を分析し、改善策を検討します。可能な限り低く抑えるのが望ましいとされています。
内定辞退率は、以下の式で求められます。
内定辞退者数÷内定者数×100
内定承諾率
内定を提示した候補者のうち、内定を承諾した割合を示します。自社の魅力や給与条件などが、候補者にとってどの程度魅力的であるかを測る指標です。目標値は業界平均や前年実績などを参考に設定します。
内定承諾率は、以下の式で求められます。
内定承諾者数÷内定者数×100
採用率
最終的に採用に至った候補者の割合を測定する指標です。採用活動全体の成果を評価するために用いられます。業界平均や前年実績などを踏まえ、目標値を設定します。
採用率は、以下の式で求められます。
採用人数÷応募者数×100
歩留まり率
採用活動における各フェーズ(書類選考、面接など)で、次の工程に進んだ人数の割合を示す指標です。各フェーズでの選考基準や応募者の質、選考プロセスの問題点などを把握するのに役立ちます。
歩留まり率は、以下の式で求められます。
選考フェーズの通過者数÷各選考フェーズの参加者数×100
平均採用期間
募集開始から採用決定までの平均所要日数を示す指標です。採用にかかるスピードを把握し、機会損失を防ぐためにも重要とされます。業界平均や前年実績などを参考に目標値を設定します。
平均採用期間は、以下の式で求められます。
(採用決定日-募集開始日の合計)÷採用人数
採用コスト
1人当たりの採用にかかった総費用、またはチャネル別にかかった採用コストを測定する指標です。どの採用チャネルが費用対効果に優れているのかを把握し、採用活動の予算配分を最適化できます。
採用コストは、以下の式で求められます。
全体:採用活動にかかった総費用÷採用人数
チャネル別:各チャネルの採用コスト÷各チャネルからの採用人数
離職率
採用後、一定期間内に離職した社員の割合を測定する指標です。採用のミスマッチや企業文化、職場環境との不適合などの要因を見極めるために用いられます。入社後1年以内の離職率など、期間を区切って管理することが一般的です。
離職率は、以下の式で求められます。
一定期間内に離職した社員数÷採用人数×100
社員定着率
一定期間経過後も継続して勤務している社員の割合を示します。特に若手社員の定着率は、オンボーディングの取り組みや職場環境に関する課題を見つける上で重要です。
社員定着率は、以下の式で求められます。
一定期間経過後に在籍している社員数÷採用人数×100
採用KPIを設定するメリット
採用KPIを設定し、実際の業務で活用することで、以下のようなメリットが得られます。
1.採用活動の可視化
採用KPIによって、採用プロセスの各段階が数値で明確に示されます。これにより、ボトルネックや改善が必要なポイントを特定しやすくなります。
課題例と解決策:低い書類選考通過率への対応
例えば、書類選考通過率が著しく低い場合、その理由として、選考基準が厳しすぎる、求人広告がターゲット人材に訴求できていないことが考えられます。
解決方法として、選考基準を関係者全員で共有するとともに、求人広告のキャッチコピーや募集要項の文言を見直すことが挙げられます。ターゲットにより響く表現に変更することで、通過率の改善が図れるでしょう。
2.効率的なリソース配分
各採用チャネルの費用対効果やプロセスの効率性を分析し、高い成果が見込める領域に予算や人員を重点的に配分できるようになります。
課題例と解決策:非効率なチャネルへの予算配分
例えば、書類選考通過率が低いチャネルばかりに予算を投下している場合、採用目標を達成しづらい状況が生まれます。
この課題に対しては、まず各チャネルの費用対効果を詳細に分析し、書類選考通過率の高いチャネルを特定します。その上で、ターゲット人材に最も響くチャネルを評価し、そこに予算や人員を配分することで、リソースを効率的に活用し、応募数の改善と採用目標の達成に近づけられるでしょう。
3.説得力のある報告・コミュニケーション
定量データに基づいて採用活動の成果を報告できるため、経営層や採用チームへの説明に説得力が増します。進捗報告や会議などの場面でもKPIを活用することによって、採用状況を明確に示し、関係者とのコミュニケーションを円滑に進められます。
課題例と解決策:経営層への説明に説得力が欠ける場合
応募数や内定率が目標に達していないものの、定量的データが不足しているため経営層の理解を得にくいケースがあります。
この課題に対しては、KPIを活用して現状の不足を数値化し、「現在、応募数が目標に対して不足しているため、〇〇の施策を実施し、〇〇名の増加を目指す」と具体的に報告します。数値根拠を示しながら解決策を提案でき、経営層や採用チームの理解と協力を得やすくなるでしょう。
4.採用の質向上
「入社後の早期離職率」や「社員定着率」、「選考辞退率」などのKPIをモニタリングし、原因を分析することで、採用のミスマッチを減らせます。
課題例と解決策:早期離職率の改善
採用人数は達成しているものの、入社後の早期離職率が高い場合、面接でスキルや経験ばかりを重視し、カルチャーフィットを十分に確認していないことが原因である可能性があります。
解決策として、面接プロセスにカルチャーフィットを確認する質問を追加し、自社文化との相性を評価する仕組みを取り入れます。こうした改善により、定着し活躍できる人材を採用しやすくなるでしょう。
より具体的な解決策や事例については、以下のセミナーレポートで詳しく解説しています。
>>【セミナーレポート 】人的資本経営と従業員のリテンション(定着)のためのマネジメント
5.採用戦略の策定・改善への貢献
KPI分析によってデータに基づく客観的な現状把握と課題分析が可能になるため、採用活動の精度と効果を継続的に高められます。採用活動の改善を重ね、結果を検証することによって、中長期的な採用戦略の策定にも大きく貢献します。
課題例と解決策:採用戦略のデータ活用
例えば、KPI分析によって、特定の経験やスキルを持つ人材が入社後に高いパフォーマンスを発揮していることが判明する場合があります。
このようなデータを活用し、次年度はそのタイプの人材を優先的に採用する戦略に切り替えることによって、効率的な採用活動と質の向上を実現できます。
6.採用活動の属人化解消
採用活動が特定社員の経験や勘に依存している場合でも、KPIを設定して進捗を可視化することで属人化を解消できます。採用プロセスや評価基準を数値化・共有化することで、ノウハウをチーム全体に浸透させやすくなり、組織全体の採用力向上につなげられます。
課題例と解決策:属人化した面接プロセスの改善
これまで採用面接をある特定の社員に任せきりだった場合、面接のノウハウが属人化していることが問題になることがあります。
解決策として、チーム全員で面接を担当する仕組みに変更し、面接評価の項目や基準をKPIとして設定します。これにより、誰が面接を行っても同じ基準で評価できるようになり、属人化を解消しながら面接の質を維持できるようになる可能性が高いです。

採用KPIの導入ステップ
採用KPIを効果的に導入し、活用するためには、以下の5つのステップで進めることが重要です。
STEP0:経営戦略・事業戦略との整合性確認
採用KPIを設定する前に、まず企業の経営戦略・事業戦略との整合性を確認することが重要です。採用活動は経営目標達成のための手段であり、採用戦略は経営戦略・事業戦略と密接に連携していなければなりません。
具体的には、自社の経営戦略・事業戦略を正しく理解した上で、事業計画達成のために必要な人材像(スキル・経験など)を明確にします。そして、その採用戦略が経営戦略とどのように連携し、設定する採用KPIが経営目標達成にどう貢献するのかを定義します。
この確認作業により、採用活動の方向性が明確になり、採用KPI設定を効果的に進めるための基盤が築かれます。
STEP1:採用目標(KGI)の設定
採用活動の最終的な目標(KGI)を設定します。この目標は、具体的かつ測定可能であることが重要です。目標設定には、「SMARTの法則」を活用するとよいでしょう。
【KGIの例】
- 1年以内に、自社のカルチャーにマッチしたエンジニアを20名採用する
- 3ヶ月以内に、即戦力となる営業職を5名採用し、売上目標達成に貢献する
- 今後半年以内に、新卒採用において入社3年以内の定着率を90%にする
【SMARTの法則】
- Specific(具体的):誰が読んでも明確でわかりやすい目標になっているか
- Measurable(測定可能):目標の達成度合いを数値で測定できるか
- Achievable(達成可能):現実的に達成可能な目標か
- Relevant(関連性がある):経営戦略や事業戦略と関連性があるか
- Time-bound(期限が明確):目標達成の期限が明確に設定されているか
STEP2:現状の採用プロセス分析と課題の特定
KGI設定後は、現状の採用プロセスを分析し、課題を特定します。過去の採用データを基に、ボトルネックや改善点を洗い出しましょう。
具体的には、求人媒体ごとの応募者数や応募から採用までの期間、書類選考や各面接の通過率、選考・内定辞退率を確認します。さらに、求人広告費や人材紹介料、採用担当者の人件費などから採用1人当たりのコストを算出し、入社後の定着率・離職率、社員満足度も分析対象です。
これらのデータを分析することによって、採用プロセスの具体的な課題が明らかになり、効果的なKPI設定につながります。
STEP3:目標達成に直結するKPIを設定する
KGIを達成するため、適切なKPIを設定します。まず、KGI達成のために重要なプロセス(例:応募数・書類選考通過率・面接通過率・内定承諾率など)を洗い出し、各プロセスに対してKPIを設定します。
重要なのは、自社の現状・採用目標・採用手法などを総合的に考慮し、現実的かつ効果的なKPIを設定することです。
STEP4:KPIを運用できる採用体制を構築する
KPIを効果的に運用するには、データ収集・分析・レポーティングなどを適切に行うための採用体制構築が不可欠です。
採用チーム内で役割を明確にし、責任の所在を明確化しましょう。KPIを継続的に運用し、改善活動につなげるための基盤を整えましょう。
STEP5:モニタリング・改善およびKPIの定期的な見直し
KPI設定後も、定期的にモニタリングを行い、進捗状況を確認することが重要です。目標との乖離が生じた場合は、その原因を分析し、採用プロセスやKPIそのものの見直しを図ります。
その際には、市場動向や競合他社の状況といった事業環境の変化にも目を向け、採用目標の修正や、形骸化したKPIの刷新・廃止も検討しましょう。
こうした継続的な取り組みによって、採用活動を常に最適化し、その成果を最大化できます。
採用KPIの課題とその解決策
採用KPIを効果的に運用し、成果を最大化するためには、いくつかの課題を乗り越える必要があります。ここでは、よくある課題と、それらを解決するための具体的な対策を紹介します。
課題1:データ収集体制の不備とリアルタイムな状況把握の難しさ
採用プロセスにおいて、データが複数のツールやファイルに分散している場合、統一的なデータ収集体制の構築が急務となります。特に、紙の履歴書やExcelでの管理は、集計や分析に多大な労力を要し、人為的なミスも発生しやすくなります。
課題例
全国に多店舗展開する企業が、各店舗で個別に求人活動を行い、応募者情報や選考状況をExcelや紙で管理しているケースを考えてみましょう。この場合、本社人事部では全国の採用状況をリアルタイムで把握することができず、迅速かつ的確な意思決定が困難な状況です。
施策例
この課題を解決するには、全店舗で共通の採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)を導入し、採用データを一元管理することが効果的です。
さらに、ATSのレポート機能を活用し、店舗別・エリア別の応募状況や選考通過率などの主要指標を可視化することによって、採用状況を俯瞰的に把握できる環境を整備します。
期待できる成果
ATSの導入と主要指標の可視化により、本社人事部は全国の採用状況をリアルタイムで正確に把握できるようになります。
その結果、例えば、応募が少ない店舗に対しては求人広告の内容を迅速に改善したり、近隣店舗と合同で採用イベントを企画したりするなど、データに基づいた採用活動の改善策を、タイムリーに、かつ効率的に実行できるようになります。
課題2:採用目標と乖離したKPI設定によるリソース配分の非効率化
採用目標に対して不適切なKPIを設定してしまうと、効果の薄い施策にリソースを浪費することになる可能性があります。そのため、採用目標とKPIの関連性を十分に検討し、適切な指標を設定することが重要です。
課題例
急成長中のITベンチャー企業が、事業拡大に伴い即戦力エンジニア採用を強化しているケースを考えてみましょう。同社は知名度が低いため、「応募数」が伸び悩んでおり、闇雲に応募数を増やすための施策を実行しても、採用目標達成に直結する可能性は低いでしょう。
施策例
このような場合、まずKGIを「即戦力エンジニアの採用」と再定義し、その達成に必要なプロセスを逆算してKPIを再設定します。
例えば、エンジニア向けイベント・勉強会からの応募数や、リファラル採用(社員紹介)経由の応募数、あるいは書類選考通過率や面接通過率など、より採用確度の高いプロセスをKPIに設定し、ターゲットを明確化します。
期待できる成果
この施策により、知名度が低い企業であっても、優秀なエンジニアが集まるコミュニティへの露出強化や、社員への適切なインセンティブ設計など、ターゲットを絞った効果的な採用活動に注力できるようになります。
課題3:データ分析スキル不足と効果的なPDCAサイクルの阻害
データを収集できたとしても、それを適切に分析し、具体的な採用戦略の改善につなげるスキルが不足しているケースは少なくありません。特にデータ分析に基づいた効果的なPDCAサイクルを回せていない企業は、採用活動の最適化が停滞してしまいます。
課題例
例えば、中途採用を行う企業が、複数の求人媒体や人材紹介会社を利用しているにもかかわらず、媒体や人材紹介会社ごとの「採用単価」を算出・比較していない場合を考えてみましょう。
このような場合、各チャネルの費用対効果を正確に把握できず、採用活動のコストパフォーマンスを最大化できていない状況に陥りやすいです。
施策例
この課題を解決するためには、まず採用担当者に対してデータ分析・活用に関する研修を実施し、データリテラシーの向上を図ることが重要です。
さらに、データの可視化ツールを導入し、誰もが容易にデータをグラフ化・共有できる環境を整備することにより、組織全体でのデータに基づいた意思決定を促進できます。
また、定期的な効果測定と改善アクションの実行をルール化し、データドリブンなPDCAサイクルを確立することも不可欠です。
期待できる成果
これらの施策により、採用担当者はデータに基づいて各チャネルの効果を正しく把握し、費用対効果を正確に評価できるようになります。
その結果、費用対効果の低いチャネルへの予算を削減し、効果の高いチャネルに予算を集中投下するなど、データドリブンな採用戦略の立案・実行が可能となり、採用活動の費用対効果を最大化できます。
課題4:採用現場との認識のずれや非協力による採用活動の停滞
採用KPIを設定・運用しても、採用現場の協力が得られなければ、その効果は限定的です。特に、人事部と現場の間で採用要件や選考基準に関する認識のずれがあると、採用活動の停滞を招き、入社後のミスマッチにもつながりかねません。
課題例
例えば、人事部は「自社製品に関する深い知識を持つ人材」を重視している一方、営業現場は「顧客との折衝力や高いコミュニケーション能力を優先すべき」と認識がずれているケースが考えられます。
施策例
このような状況を打開するためには、まずKPI設定の初期段階から現場を巻き込み、現場の意見を積極的に取り入れることで、当事者意識を高めることが重要です。
さらに、定期的なミーティングを通じて採用状況や選考プロセスに関する情報を共有し、現場が協力しやすい環境を整備します。
期待できる成果
これらの施策により、現場のニーズに即した、より実効性の高い採用基準が明確になります。また、人事部と現場が一体となって採用活動に取り組むことで、採用プロセスの精度とスピードが向上します。
課題5:短期的な成果への偏重による中長期的な視点の欠如
採用KPIを設定すると、応募数や内定承諾率といった短期的な数値の改善に注力しがちです。しかし、採用ブランディングの強化や社員定着率の向上などの中長期的な視点を軽視すると、将来的な採用活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
課題例
例えば、採用目標人数の達成のみを最優先KPIとし、強引な動機付けによって内定承諾を獲得した結果、入社後のミスマッチが多発し、早期離職率が上昇してしまうケースが考えられます。
施策例
このような事態を防ぐためには、短期的な指標だけでなく、「入社後1年以内の離職率」や会社に対する愛着度や仕事への熱意、組織への貢献意欲などを測る指標である「社員エンゲージメントスコア」など、中長期的な視点に立った指標もKPIとして設定することが重要です。
また、選考過程においては、企業の魅力だけでなく課題や職場環境についても率直に伝え、入社後のギャップを最小限に抑える努力も必要です。さらに、内定者フォローを充実させるなど、採用した人材が定着・活躍できるようなサポート体制を整備しましょう。
期待できる成果
これらの施策を実行することによって、入社後のミスマッチや早期離職のリスクを低減し、長期的に活躍できる人材の確保につなげられます。さらに、企業の信頼度や企業イメージの向上にも寄与し、将来的な優秀人材の応募増加も期待できます。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
採用KPIを最大限に活用し、人材戦略を成功に導く
採用KPIの適切な設定と運用によって、採用活動の現状を客観的に把握し、課題を特定し、効率的に改善できます。
重要なのは、自社の経営戦略や事業戦略と連動したKGIを設定し、その達成に必要なプロセスを逆算してKPIを設定することです。
本記事でご紹介した知識を参考に、貴社にとって最適なKPIを設定し、戦略的な採用活動を展開してください。
▼パーソルテンプスタッフの人材紹介

人材紹介の活用メリットや対応業務・ご利用の流れを紹介
人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする