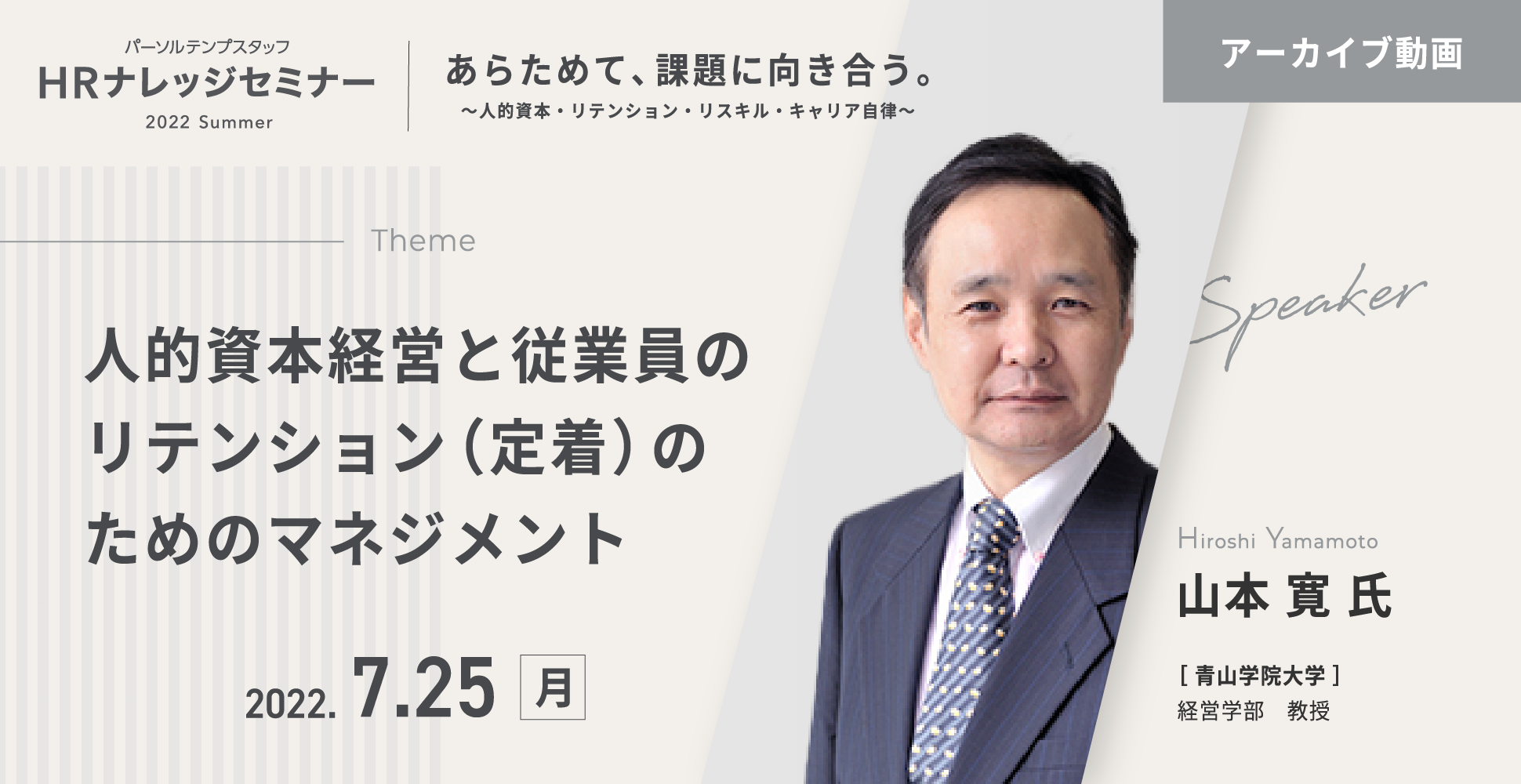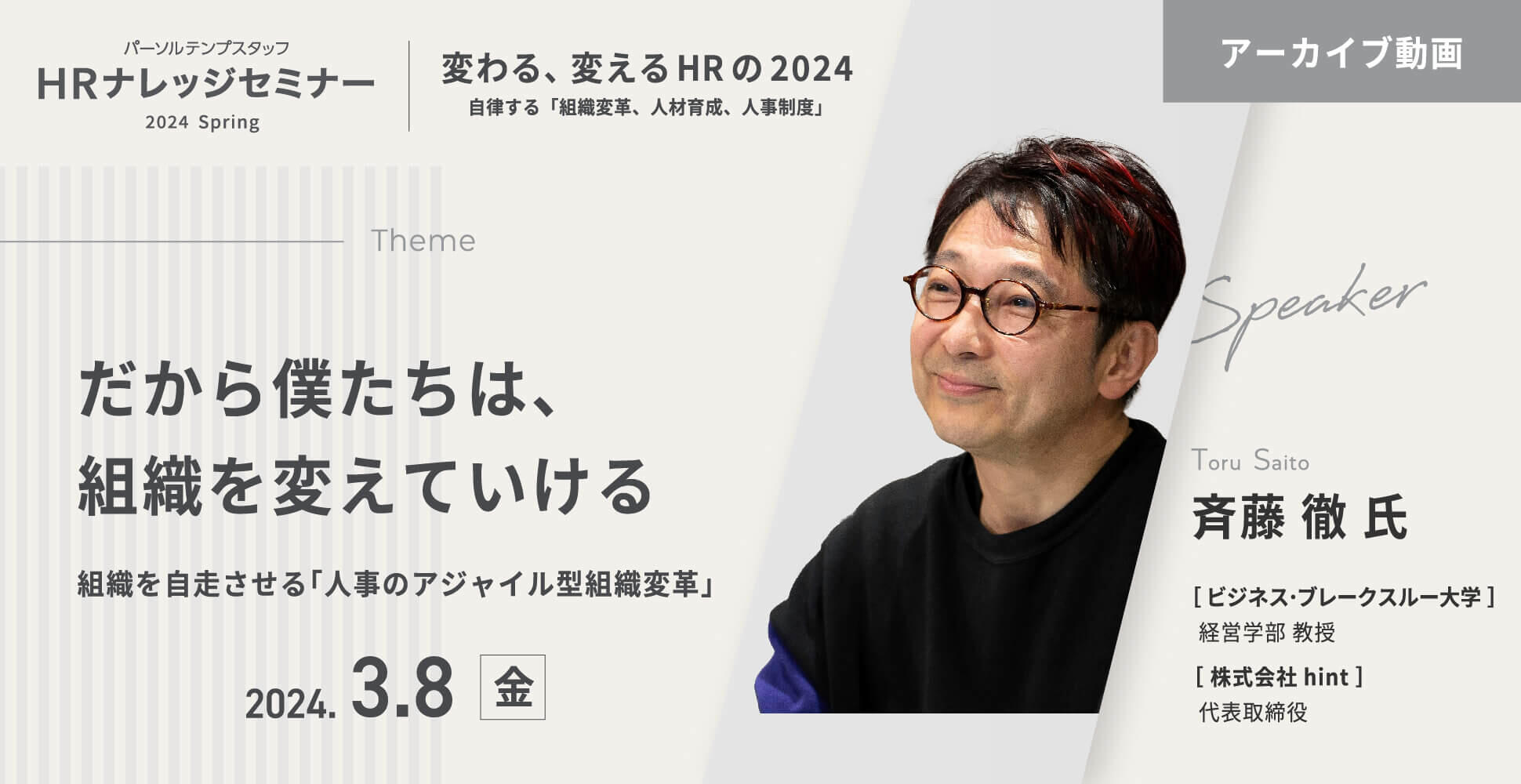HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート】
人的資本経営と従業員のリテンション(定着)のためのマネジメント
公開日:2025.03.28
- 記事をシェアする
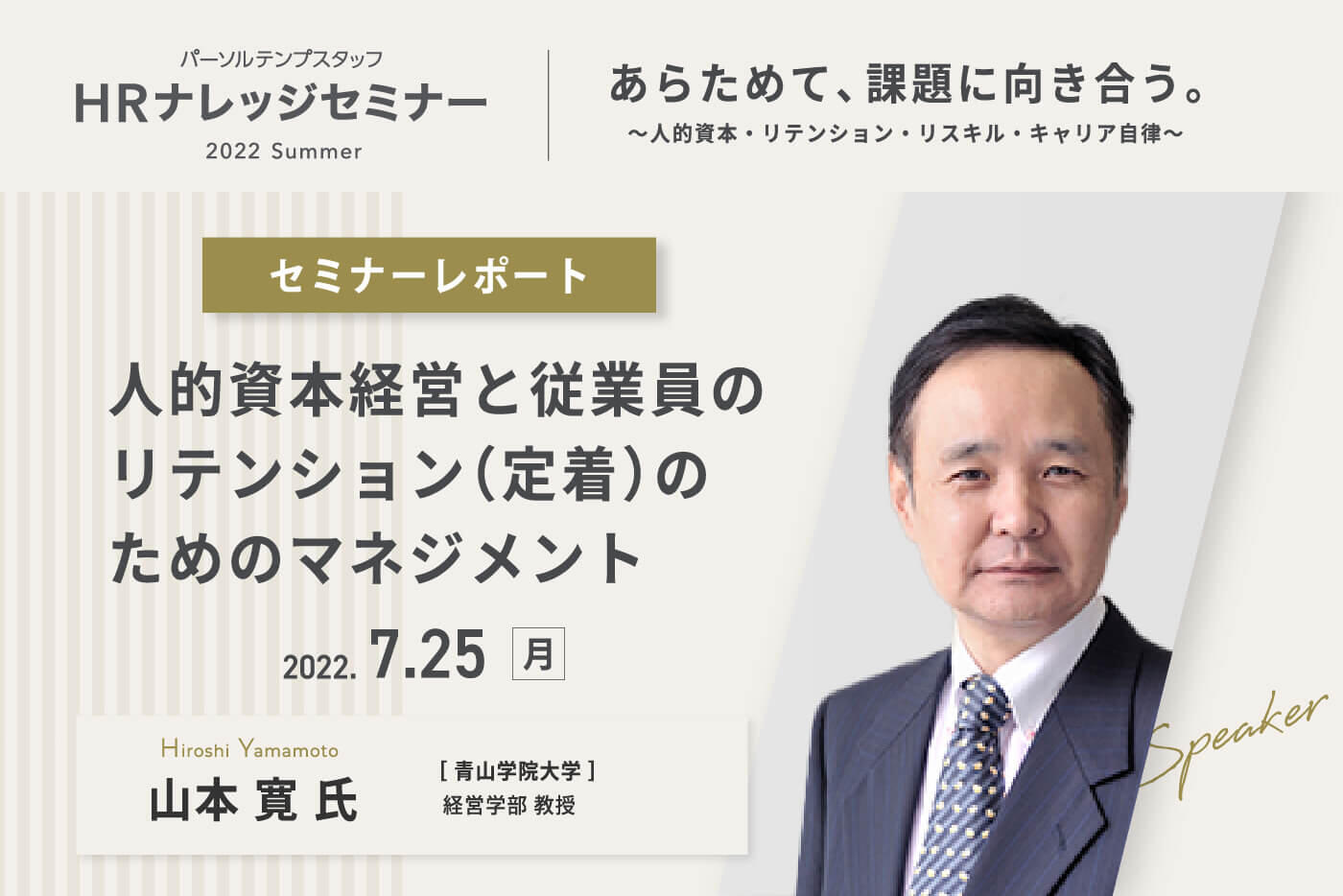
青山学院大学
経営学部
教授
山本 寛 氏
近年、政府や市場関係者において人的資本経営に対する関心が高まっています。人的資本はESG投資(従来の財務情報だけでなく「環境:Environment、社会:Social、ガバナンス:Governance 」要素も考慮した投資)のS(社会)の部分であり、外部評価に大きく関わる要素であるため、企業経営のあり方の変革が迫られています。同時に、少子高齢化を背景とした深刻な課題である人材不足と採用難、それらを解決するためのリテンション(定着) ・ マネジメントに対しても関心が高くなっています。人的資本経営とリテンション ・ マネジメントの現状や企業の対策事例について、青山学院大学経営学部教授山本寛氏の講演をご紹介します。
▼アーカイブ動画はこちら
人的資本開示の積極的対応が迫られるなか、リテンションに関する指標は明確化しやすい
人を資本と捉えて投資をし、生産性を高めれば、必ず見返りがあるという前提に立った考え方が「人的資本」です。
似たような言葉として 「人的資源」という言葉があります。資源はコストとして消費されるもの、資本は投資する対象のことを指します。人を資源として消費するのではなく、人に対して投資を行っていくことで、最大限活用することが可能となるのです。
また、ESG投資への高まりや1S030414の公開など人的資本に関する情報開示の必要性に迫られており、「人的資本経営」への関心が急速に高まっています。
そして、リテンションに関する指標は他の課題に比べ比較的に明確化しやすいものが多いため、リテンションのためのマネジメントを図りやすい環境になってきたと言えるでしょう。
人口が減少し転職が当たり前になった社会で欠かせないリテンション・マネジメント
我が国では、生産年齢人口は減少の一途を辿っている一方で、転職社会に突入したことで正規雇用の転職希望者が増加傾向にあります。これが企業において人手不足や人材流出が進む大きな要因といえます。
こうした状況下でリテンションを強化し、勤続期間の長期化と定着率の向上の2つを指標として施策を行う必要があります。また、近年では特に好業績を挙げる従業員が長期間組織にとどまり能力を発揮できるようにするリテンション・マネジメントが重要です。
多くの企業においては定着のための施策は行われているものの、本人の能カ・適正に合った配置や教育訓練の実施・ 援助、労働時間の短縮·有給の取得奨励については、まだまだ実施率が低いという現状があります。
そうした課題を解決するためにはさまざまな施策が必要となります。リテンションに関する施策は数値化しやすいものとしにくいものがあるため、柔軟に活用していくことが求められます。またリテンション・ マネジメントの強化のためには、人的資本経営の観点が大切です。
まとめ
労働人口が減少し、転職が当たり前となった社会において、リテンションは人的資本経営に欠かせない一部となっています。リテンションの促進と今後の人的資本経営への対応を両立させるには、リテンション・ マネジメントの対象の拡大や活用が必要です。非正規社員を含む全メンバーヘの能力開発の活性化や、数値化しにくいものも柔軟に取り入れ、人的資本の価値向上に向けた施策の実施が必要です
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

青山学院大学
経営学部
教授
山本 寛 氏
人的資源管理論・キャリアデザイン論担当。博士(経営学)。メルボルン大学客員研究員歴任。働く人のキャリアとそれに関わる組織のマネジメントが専門。著書(単著)として『連鎖退職』『なぜ、御社は若手が辞めるのか』『「中だるみ社員」の罠』(以上日経BP社)『人材定着のマネジメント』(中央経済社)『自分のキャリアを磨く方法』『転職とキャリアの研究[改訂版]』『働く人のためのエンプロイアビリティ』『昇進の研究[増補改訂版]』(以上創成社)がある。著書(編著)として『働く人のキャリアの停滞』(創成社)がある。 研究室ホームページ http://yamamoto-lab.jp
- 記事をシェアする