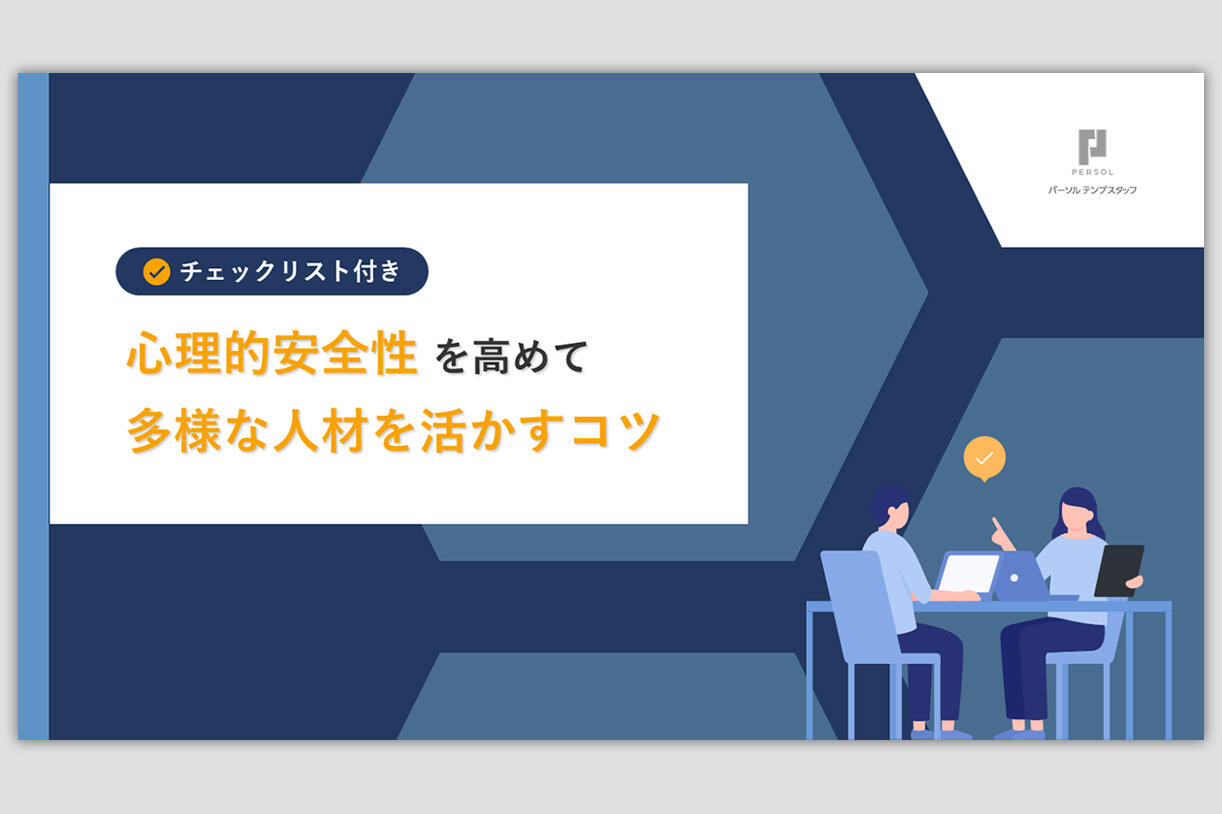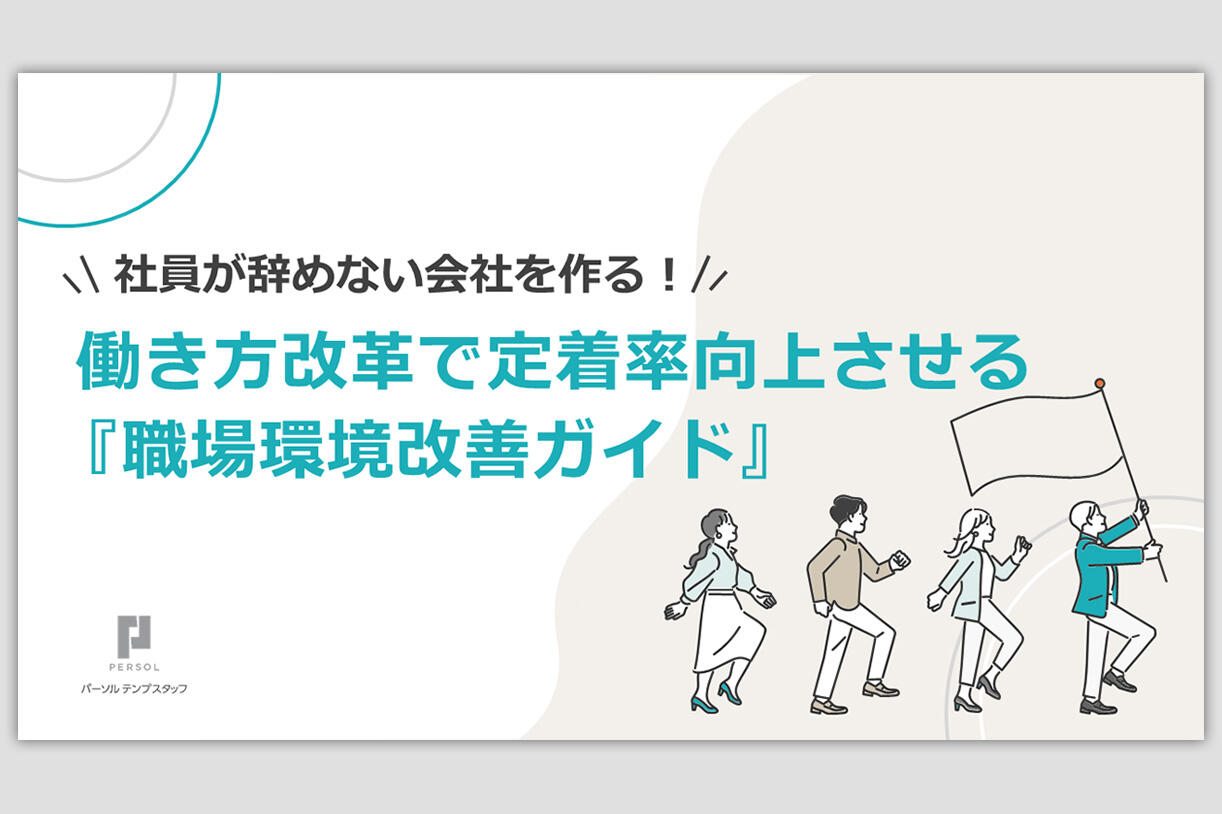HRナレッジライン
カテゴリ一覧
社員の休職・退職を防ぐには?企業に求められるメンタルヘルスケアを具体的に解説
- 記事をシェアする

企業が社員のメンタルヘルスケア対策に取り組むことは重要です。医師から「うつ病」などと診断を受けていなくとも、日頃からストレス・不安を抱えている人は20〜40代で約3割にもおよぶことが分かっています。
企業が社員のメンタルヘルスケアを講じていないと、社員の不調による遅刻・欠勤の増加、作業ミスの発生など組織全体の生産性に影響を及ぼすリスクもあるでしょう。さらに、メンタルヘルスの問題による社員の休職・退職は企業にとって大きな損失となる恐れも考えられます。
そこで本記事では、企業が社員の休職・退職を防ぐためにメンタルヘルス対策に取り組む必要性と効果について紹介します。具体的に推奨される取り組みも詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
メンタルヘルスとは
メンタルヘルスという言葉は、英語の「Mental(精神の)」と「Health(健康)」を組み合わせた造語です。「心の健康」といった意味合いで使われます。
例えば、医師から「うつ病」などと診断を受けていなくとも、日頃からストレスや不安を抱えている状況はメンタルヘルスに問題を抱えている状況だといえます。
社員のメンタルヘルスの問題は、企業にとって重要な課題の一つです。
メンタルヘルスの問題を抱えて休職・退職する人の割合
厚生労働省による2023年の「労働安全衛生調査(実態調査)」では、「過去1年間にメンタルヘルスの問題で休職・退職した社員がいた」と回答した事業所の割合は13.5%で、前年より少し増加しています。
また、公益財団法人「日本生産性本部」が日本企業226社に対して実施した「第9回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果」によると、メンタルヘルスに問題を抱えている社員は20代・30代・40代において、いずれも3割程度もいることが分かっています。世代を問わず、メンタルヘルスに関する課題を抱えながらはたらいている人が少なくないと伺えます。
メンタルヘルスの問題による社員の休職・退職は、企業にとって大きな損失となります。そのため、企業は社員のメンタルヘルス対策を講じることが必要です。
また、企業が社員の心の健康を守ることは、厚生労働省は労働安全衛生法によっても義務付けられています。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
社員の休職・退職を防ぐために企業がメンタルヘルス対策をする効果
前述の通り、社員の休職・退職を防ぐためには企業によるメンタルヘルス対策が重要となります。対策を講じることにより、休職・退職防止にどのような効果があるのか解説します。
生産性向上と社員の定着
メンタルヘルス対策は、社員の休職・退職を防ぐだけではなく、社員のパフォーマンスの向上にもつながります。
ストレスの少ない職場環境作りは、メンタルヘルス対策の中でも必要不可欠です。ストレスとなっていた要素が改善されることにより、社員はモチベーションを高く保ちながらはたらけるようになるでしょう。
その結果、経験・ノウハウを持つ社員が定着し、企業全体の生産性が向上すると期待できます。
社員の定着率を上げる取り組みについては以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介
企業イメージの悪化防止
企業がメンタルヘルス対策を行うことは、企業イメージを守る上でも重要です。
社員が抱えるメンタルヘルスの問題の原因が企業にある場合、社員から賠償請求や訴訟をされるリスクがあります。このような事態になれば、企業イメージの悪化につながるでしょう。また、職場環境が悪いというイメージがつけば、あらたな人材採用にも悪影響が及ぶ可能性も考えられます。
企業価値を高める視点からも社員のメンタルヘルス対策への取り組みは大切です。
企業のメンタルヘルス対策における「4つのケア」とは?
ここからは、企業のメンタルヘルス対策における基本の4つのポイントを紹介します。
1.セルフケア
まずはセルフケア、つまり社員自身によるケアを促すことが大切です。
社員一人ひとりが仕事中どのような場面でストレスを感じるのかを認識してもらい、積極的にリフレッシュに取り組むようはたらきかけましょう。
ストレスチェックの実施
「現状でどのぐらいストレス・不安を感じているのか」「具体的にどのような場面でストレスを感じるのか」といった気付きを促すために、社員へのストレスチェックの実施が有効です。
ストレスチェックは、常勤の社員が50人以上在籍している企業では年に一度実施しなくてはならないと、労働安全衛生法で義務付けられています。厚生労働省が推奨する調査票などを用いて対象者に回答してもらい、その結果を医師などが評価、必要に応じて医師が社員に面談指導などを行います。
社員の回答・医師の評価を経た後は、社内でメンタルヘルス研修などを行って社員のストレス軽減に努めることが大切です。
なお、パーソルテンプスタッフでは、就業中で一定の基準を満たした派遣社員に対して、年に1回ストレスチェックを実施しています。定期的なストレスチェックの実施をすることによって、派遣社員の安全な就業をサポートする体制を築いています。
ストレスチェック制度については以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
>>ストレスチェック制度の目的や対象者、実施時の留意点について説明
メンタルヘルス研修
社員が日頃から自分自身が抱えるストレスに気付き、セルフケアやリフレッシュの重要性を認識するためには、メンタルヘルス研修の実施も有効です。
例えば、厚生労働省のWEBサイトでは、社員向けのメンタルヘルス研修で活用できる15分程度の動画を集めたコンテンツが公開されています。「メンタルヘルス研修で、具体的にどのような内容を社員に提供してよいか分からない」と悩んでいる企業は、利用してみるとよいでしょう。
2.ラインケア
ラインケアとは、同僚や上司によるケアを指します。
具体的なラインケアとして、業務量の調整・有給休暇取得の推進・産業医との面談・職場環境の改善といった項目が考えられます。
同僚・上司向けチェックリスト
同僚・上司から見て「いつもと様子が違って元気がない」と感じる場合、社員がメンタルヘルスの問題を抱えている可能性があります。
社員の様子を確認する基準として、厚生労働省が同僚・上司向けのチェックリストを公開しています。以下はチェックリストの項目です。
- 遅刻、早退、欠勤が増える
- 休みの連絡がない(無断欠勤がある)
- 残業、休日出勤が不釣合いに増える
- 仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が低下する
- 業務の結果がなかなかでてこない
- 報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいはその逆)
- 表情に活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)
- 不自然な言動が目立つ
- ミスや事故が目立つ
- 服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする
3.社内の産業保健スタッフなどによるケア
企業内に産業医・保健師や、衛生管理者・人事労務担当者などの産業保健スタッフが在籍している場合、メンタルヘルスケア実施に関する企画立案・運用に取り組むことも重要です。
具体的なケア方法として、以下のような取り組みが考えられるでしょう。
【企業全体に向けた対策の実施】
- 労働環境の把握
- 企業のメンタルヘルスケアの計画立案
- メンタルヘルス研修実施
- 病院など外部機関の紹介
【悩みを抱えている個別の社員に向けたケアの実施】
- 社員からの個別相談への対応
- 個々の不調の詳細に関して個人情報保護の取り組み
- 休職中社員の職場復帰支援
4.社外の専門家や機関によるケア
場合によっては、社外の専門家や機関によるケアも必要です。具体的には病院・診療所・産業保健総合支援センター・精神保健支援センターなどとの連携が想定されます。
産業保健総合支援センターは各都道府県に拠点が存在し、社員50人未満の企業に対して社員への面談や相談を原則無料で提供しています。また、精神保健支援センターも各都道府県にあり、企業に対する心の健康についての相談やアドバイス、医療機関の紹介などができる窓口となっています。
- ※参考:産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
- ※参考:精神保健福祉センター
企業がメンタルヘルス対策に取り組む際の留意点
ここからは、企業がメンタルヘルス対策に取り組む際の留意点について紹介します。
推進担当者を選任することが望ましい
企業には「安全配慮義務(健康配慮義務)」があります。安全配慮義務とは、労働災害の「危険発見」と「その事前排除(予防)」を意味し、次のような活動が求められます。
- 危険発見
職場における危険、特にはたらいている人の周りにある危険を予知して発見すること。 - 事前排除(予防)
リスクを除去したり低減させたりし、残存したリスクに対しては作業者にその存在などを示し、危険が顕在化しないように対策を取ること。
※参考:厚生労働省|安全衛生規程
上記の観点を踏まえると、メンタルヘルスの問題を抱える社員の発生を未然に防ぐために、企業内でメンタルヘルスケア推進担当者を選任することが望ましいです。
メンタルヘルスケア推進担当者を選任することによって、前述した4つのケアの「社内の産業保健スタッフなどによるケア」を充実させることにもつながります。
社員にとって不利益な待遇をしない
企業が社員一人ひとりに対してメンタルヘルスケアを実施する中で、個々の問題について知ることになります。しかし、それを理由に社員にとって不利益な待遇をしてはいけません。ここで言う不利益な待遇とは、具体的に次のような項目が挙げられます。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
- 退職勧奨を行うこと
- 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること
- その他の労働契約法などの労働関係法令に違反する措置を講じること
社員の職場復帰に向けた具体的な支援を行う
休職する社員がいる場合には、企業は社員の職場復帰に向けた具体的な支援を提供する必要があります。
1.休職開始〜休職中のケア
メンタルヘルスケア推進担当者と人事担当者が連携して社員の休職に向けた手続きを行います。休職することで周りに迷惑がかかると社員が感じないように「代替人材を配置する」など、休職中に企業が行うことについて説明することも大切です。
また、傷病手当金の支払いなど各種手続きも進めましょう。休職者には相談窓口についても伝えておき、安心して休養できるよう企業がサポートします。
2.医師による復帰可能の判断
休職者が職場復帰の意思を企業に表明したら場合は医師に診断書を書いてもらい、復帰に関して客観的な意見をもらいましょう。
3.企業側が復帰可否の判断と、復帰支援プランを作成
休職者が職場復帰できるかどうかについて、企業側でも評価・判断を行います。スムーズに復帰が進むよう、メンタルヘルスケア推進担当者・休職者・その上司などで連携しながら、具体的な復帰プランを策定しましょう。
4.復帰の決定とフォローアップ
休職者の復帰が決定したら、具体的に復帰日を決めます。復帰後は直接の上司などが、社員のはたらく様子・パフォーマンスに配慮しながら管理監督をしましょう。
職場復帰プランは適切だったかをメンタルヘルスケア推進担当者とともに振り返りを行うなどの、フォローアップも大切です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
労働環境の見直し・整備も大事なポイント
本記事では、企業が社員のメンタルヘルスケア対策に取り組む重要性について解説しました。
もし職場内にメンタルヘルスの問題で休職する社員がいる場合には、休職者が安心して休める体制を築いておくことが大切です。休職者の視点に立ち、「自分が休んだ分の人員は一時的に補充してもらえる。しばらくの間は仕事を任せて、療養に集中できる」と感じてもらえるよう、企業が職場環境を整えることもケアの一環だと言えるでしょう。
社員の退職や休職による人材不足に困っている場合、人材派遣会社に相談し、人材の紹介を依頼することによって解決につながります。一時的な人材派遣の利用や直接雇用を前提とした人材派遣、または採用のための人材紹介をご希望の方は、パーソルテンプスタッフまでぜひご相談ください。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする