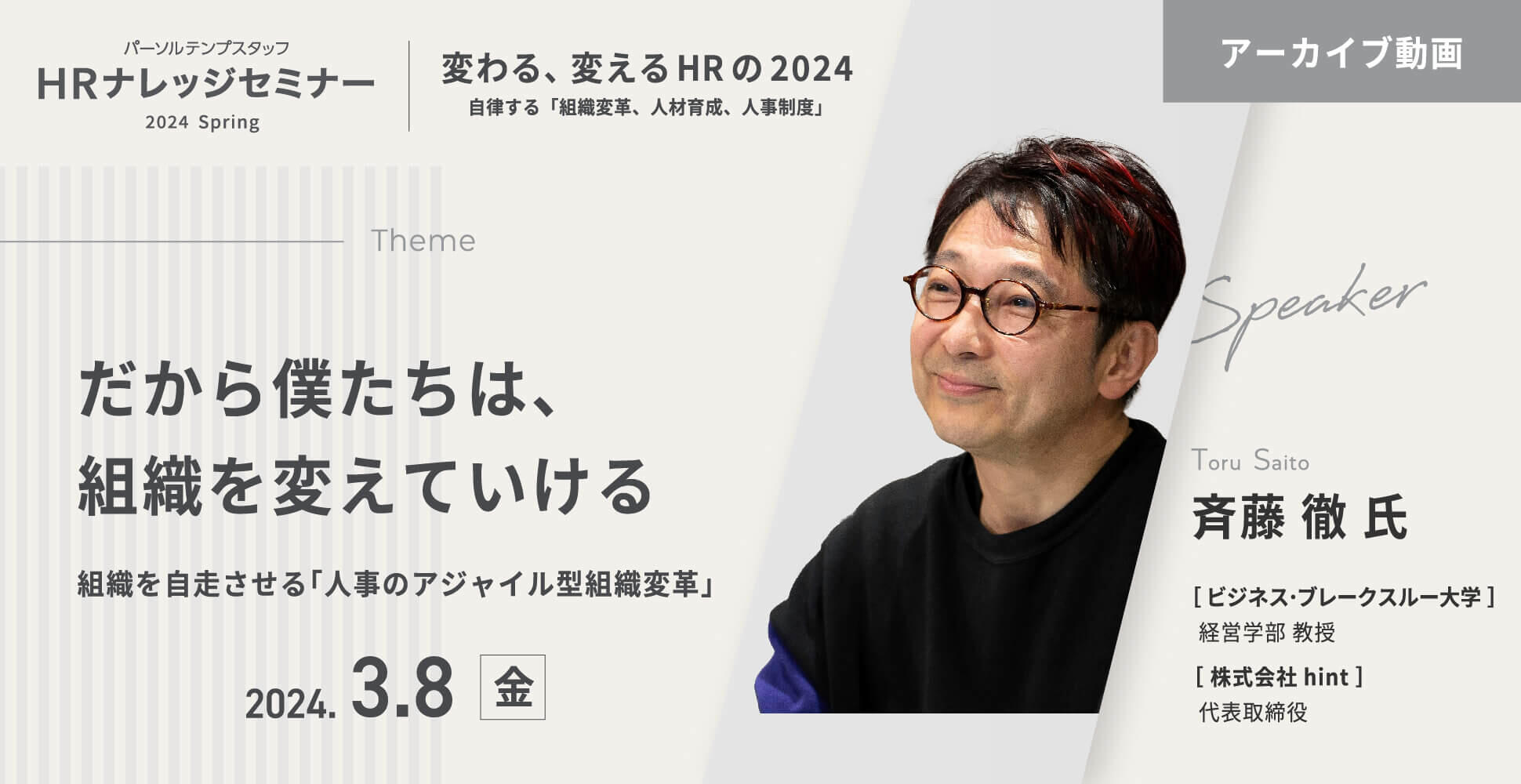HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【人事ライン】
NOT A HOTEL 冨永氏
人事として、まっすぐな信頼関係を築く
公開日:2024.10.18
- 記事をシェアする

NOT A HOTEL株式会社
執行役員 CHRO
冨永 麻美 氏
「他の会社の人事ってどうやっているんだろう」「同じような悩みを抱えているのかな」さまざまな企業の人事パーソンインタビュー『人事ライン』。今回は、NOT A HOTEL 株式会社で執行役員 CHROのを務める冨永 麻美さんです。
目指す世界観を実現する組織に向けて、個々の“超自律”と組織としての“ワンチーム”の総和を高める人事としての想いを聞きました。
― 冨永さんの今までのキャリアや現在の仕事内容を教えてください
2016年にクックパッド株式会社に新卒入社し、人事で採用を担当しました。採用をするためには、まずは会社を好きになってもらう必要がある。採用活動を通じてそう強く感じ、PRや広報、マーケティングの部署に異動し、経験を積みました。部門や役割は違えど、一貫して「会社についての発信を介して、ユーザー・社員・採用候補者・クライアントに“ファン”になってもらう」ことにやりがいを感じていましたね。
そして、2022年にNOT A HOTELへ転職しました。「すベての人にNOT A HOTELを」という壮大でワクワクするミッションと、多様なメンバーが一つのゴールに向かう組織の魅力に惹かれたのが理由です。最初は広報兼採用広報として入社したのですが、入社後すぐに「今、この会社に必要なのは採用だ」と感じ、一人目の人事として採用にフルコミットすることを決めました。入社当時は20名くらいの組織でしたが、事業拡大に伴い約1年で約60名にまで拡大。その次の年には約100名の組織規模にまで成長することができました。現在は200名を超える組織になりました。
入社2年を過ぎた2024年5月から執行役員 CHROになり、「NOT A HOTELが目指す世界観を実現する組織」に向けて、日々邁進しています。
― 人事として見たときに、今の環境特有の部分はありますか。
メンバーが会社のミッションやビジョンを心から信じていて、それに対して全員が自ら考えて行動をする力を持っていることです。一人ひとりの内側にある原動力こそが、さまざまな相乗効果的を生み出し、組織の厚みにつながっていくものだと思っています。会社に入る意味は一人では成し遂げられない大きな挑戦に、組織で向かっていけること。会社とメンバーが互いを高め合えるような関係が、常識を超える価値を生み出す源泉だと感じます。
また、現在の環境のユニークさであり人事に取り組む醍醐味となっているのは、NOT A HOTELという一つの体験を生み出すために、多様な職種のメンバーが集まっていること。そして個々の“超自律”と組織としての“ワンチーム”の総和を高めていく必要があることです。
私たちは新たな拠点の土地探しから、お客さまのチェックアウトまで、すべてのプロセスをインハウスで手がけています。建築、ソフトウェア、セールス、ビジネス、コーポレート、そしてホテルサービス。すべてのメンバーが「自分がNOT A HOTELをつくっている」という視座を持ち、一緒のゴールを目指していくことを組織として大事にしています。

職種がまるで異なる多様なメンバーの手によって、一つのNOT A HOTELがつくられる
― ワンチームを掲げる重要性はどこに感じていますか。
私たちが“ワンチーム”を掲げているのは、どんなに専門性のあるメンバーでも、一人ではNOT A HOTELをつくることができないからです。一例となりますが、私たちの建築にはリモコンやスイッチがなく、空調や電気、サウナなどを、すべてスマートホーム化(タブレット・スマートフォンで管理可能)することで快適な滞在体験を実現しています。これは拠点の構想段階から、建築チームやソフトウェアチーム、運営チームが協働することによって生み出せる価値です。
私たちには「すべての常識を“超えて”いく」という創業当時から大切にするバリュー(行動指針)があります。普通ではない「超」がつくほどのワクワクを提供し続けるためには、既存の手法にとらわれず”超クリエイティブ”な方法を生み出す必要があるという考え方です。人事領域においても同様で、これまでになかった”超クリエイティブ”な組織にどこまでなれるか。抽象的な表現にはなりますが、どんな領域においても視点を変えればクリエイティブになれるはず。私たちのチャレンジングな部分です。
― 評価制度などはどのようにされているのでしょうか。
定期的な個人評価は実施せず、全社の年間目標(OKR)の達成率に応じて、全社員の昇給率と賞与率が一律で決まるというワンチーム評価*を取り入れています。
ワンチームで評価の良い面は、ゴール達成のための自律的な行動を促せる点です。「自分の評価」のために仕事するのではなく、「チームのゴール」を達成するために自分は何をすべきか?という思考が生まれるため、とても本質的なモチベーションのあり方ではないかと感じています。
ただし、この評価システムは全員が“超自律”しているという前提においてのみ機能します。バリューである「超ワクワク」「超クリエイティブ」「超自律」の密度を組織拡大と同様に育て続けていくことが要であり、難しい点でもあります。
*定期での個人評価はありませんが、求める役割を明確にするためグレードを設けています。役割に伴う責任の大きさに合わせて、グレードごとに昇給幅の上限・下限を設けています。グレードの昇降格は自薦、他薦によっていつでもできます。
― 目指す事業成長をするために。組織としてクリエイティブな状態になっているのかを、どのようにウォッチしていますか。
定期的な個人評価はしていないとお話ししましたが、普段のSlackやミーティングでの議論では、高い目標に向かって忌憚のない建設的なフィードバックやディスカションが行われています。ブランドは細部に宿る、という意識が浸透しており、建築の設計や清掃・食事サービスといった部分のみならず、営業や契約プロセスが超ワクワクでスムーズな体験になっているか、滞在者へのコンシェルジュ対応はスピーディーかつ的確であるかなど、どの部門も「自身がNOT A HOTELのブランドを担っている」という意識で取り組んでいるんです。
また、全社目標(OKR)は難易度が非常に高く、なかなか超えられないくらいの高さに設定されています。それに加えてすべての部門のメンバーが「私がここをやっていかないと全体の目標が達成できない」と当事者意識を持てるような内容になっています。各部門が行動計画としてチームの目標に落とし込み、それを年に4回(うち2回は全国から集合して対面実施)にわたり、進捗確認をしています。全員が全社目標の進捗や課題を理解できる機会を頻繁に設けることで、常に視座を高め続けることを大切にしています。

半年に一度、全社員が一同に集まるオフサイトでは、OKR進捗報告やグループワークが行われる
― シビアな部分もあると思うのですが、個々が自律して責任を負っている部分と、会社への帰属意識というかチームとしての意識、両方ともすごく高い組織ですよね。
仕事をタスク(作業)と思ってやっている人が少ないですね。私も採用担当だった頃から「採用数の達成」を目標とするのではなく「NOT A HOTELという組織をつくること」を自分の役割だと思っていました。そんなふうに自分自身の仕事に目的やミッションを、自ら見出して仕事をしている人がすごく多いんですよね。やらねばいけないというよりも、やりたいからやる、というイメージが近いかもしれません。
この組織でしか成し遂げられない仕事を生み出し続け、その成長の先にさらに大きな挑戦を掲げ続けること。代表の濱渦も「好きな人には、努力しても勝てない」とよく言っていますが、その「好き」を極める力こそNOT A HOTELらしさであり、それをうまく組織として醸成できるかが要だと思います。
― そのような中での人事内でのコミュニケーションや、人事として従業員とのコミュニケーションで意識していることはありますか。
人事内では、メンバーの住んでいるところが北は福島から南は沖縄までさまざまなので、対面で会う頻度は多くても月に1回程度です(採用イベント開催時など)。オンラインでは、1日に1回は顔を合わせる時間をつくりコミュニケーションの密度を大切にしています。
もともとすごくフラットな関係なので、役員になり課題発見の舵取りや最終責任を取るのは私なのですが、これまで通り全員がフラットに接してくれて、そこはすごくありがたいです。採用・採用広報・労務・制度企画と担当は分かれていますが、夕会やタスク共有会では人事の全領域を横断して議論するようにしています。それぞれの専門性はありつつも「人事」として、互いを補い合いながら4人で一緒に歩んでいきたいなという思いです。
チーム内外問わず、人事として重要なことはまっすぐな信頼関係を築くことだと考えています。今いるメンバーに対してもそうですし、これから入社してくださる候補者の方、そして退職された方にもそうです。私自身が後ろめたいことが嫌い(苦手)だという性格もあるのですが、正々堂々と人事をするためにも全員に対してまっすぐに、誠実に関わっていくことを大切にしています。
― 他社の人事の方、CHROの方などに聞いてみたいことも出てきそうですね。
たくさんありますね。生産性の高い組織を実現すると言うは易しなのですが、その会社の事業内容やカルチャーによって、生産性の定義やフォーカスすべき課題・施策はそれぞれなのではないかと思います。各社においてこの課題をどうやって自社の状況に合わせて紐解き、育んでいるのか、という人事責任者としての立ち振る舞いについて知りたいです。
ウェブの記事や本などでも参考になる具体的な事例はたくさんあるのですが、それが自社にフィットする内容なのか?というところは、一概には言えないと感じています。だからこそ、具体的な事例の奥にあるこれまで変革を成し遂げてきた人事の先輩方が、どのような試行錯誤を経て解にたどり着いたのか、という内側の思考をのぞいてみたいなと思います。
― 課題に向かっていくにあたり、ご自身としてはこれからどういうことをやっていきたいと思っていますか。
私が役員のポジションに就かせていただいたのは、メンバーへ誠実に寄り添う「現場目線」があったからだと思っています。一方、今後は「経営者目線での組織づくり」にチャレンジする必要を感じています。中長期を見据えた事業成長から逆算した組織とはどうあるべきか。これまで培ってきた現場目線とうまく掛け算しながら、新たな視点から組織を見つめていきたいと考えています。
逆に変えたくないスタンスがあります。それは、会社のコミュニティーマネージャーという存在であれるようにすることです。人事には採用や労務、オンボーディングなどそれぞれの業務がありますが、いかに会社とメンバーのつながりを強くするか、入社するメンバーが会社に馴染む速度を早くするか、組織の課題を自ら一次情報として収集できるかなど、コミュニティのハブになれることが大事だと思っています。
私自身、会社のメンバーが前向きに活躍しているところを見るのが大好きで、一人ひとりに対するリスペクトや応援したい気持ちがいつでも溢れている状態です(笑)「どうしたらみんながもっと超ワクワクして、そして活躍できるのか?」ということを自然と考えているので、そういったモチベーションはこれからも大切にしていきたいですね。

個人として、人事として、そして役員として。ひとつの事象もさまざまな位置や角度から見て、考えている冨永さんのお話は、熱い想いと他者に対するリスペクトの気持ちがあふれていました。
個々の“超自律”と組織としての“ワンチーム”の総和を高め、“超クリエイティブ”な状態を継続させていくためにはどうしたらよいのか。「コミュニティーハブ」であり続けるとともに、事業成長から見た組織づくりに向けて、まっすぐな視点でお話される冨永さんでした。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

NOT A HOTEL株式会社
執行役員 CHRO
グループ長
冨永 麻美 氏
立教大学経営学部卒。クックパッド株式会社にて、採用・採用広報・PR・マーケティングに従事。2022年3月よりNOT A HOTEL参画。一人目のHRとして採用・労務・制度企画を担う。2024年5月、執行役員CHROに就任。
- 記事をシェアする