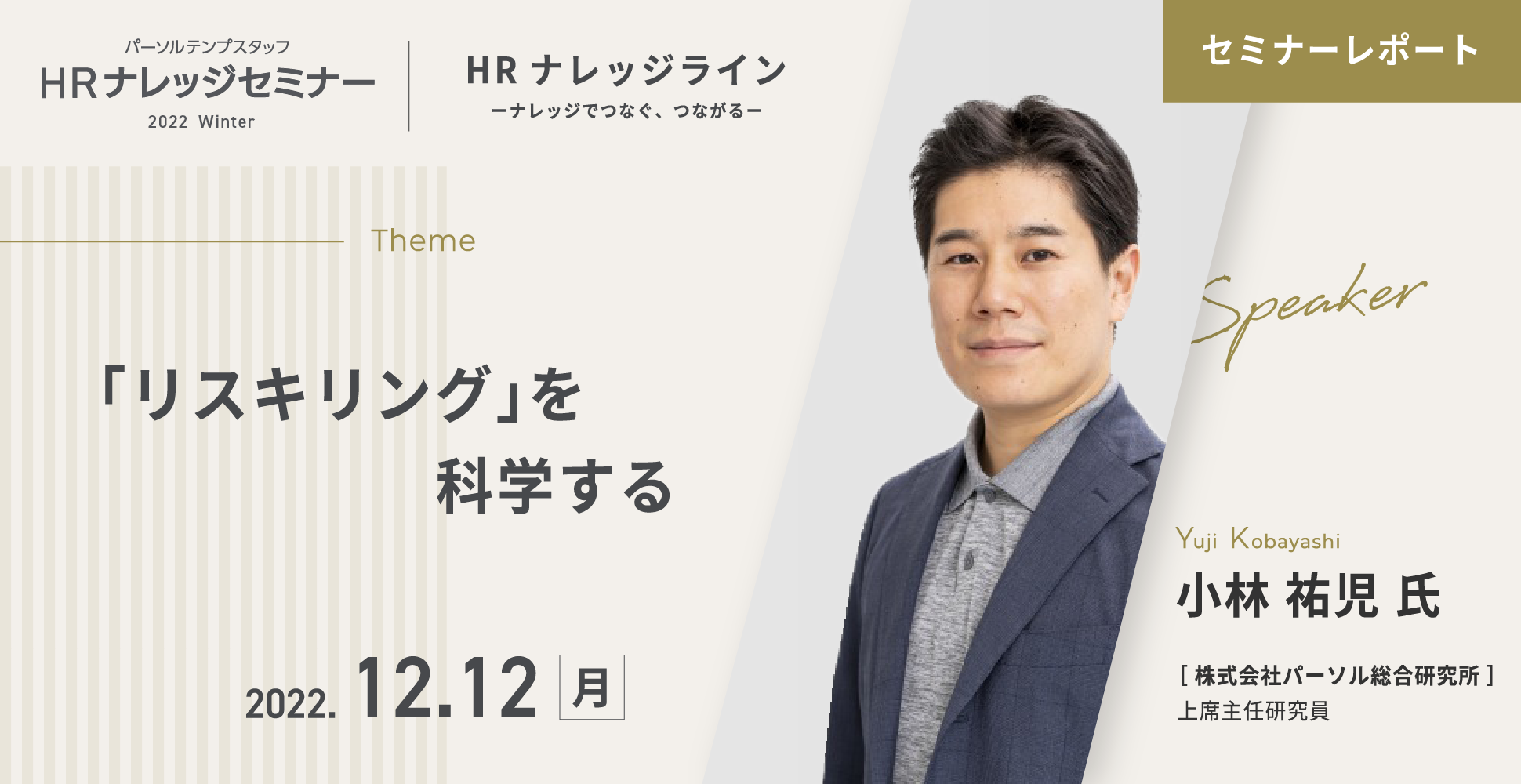HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジインタビュー 】
仕事旅行社 田中氏
ミドルシニアからワクワクはたらく日本を目指す
公開日:2024.07.12
- 記事をシェアする
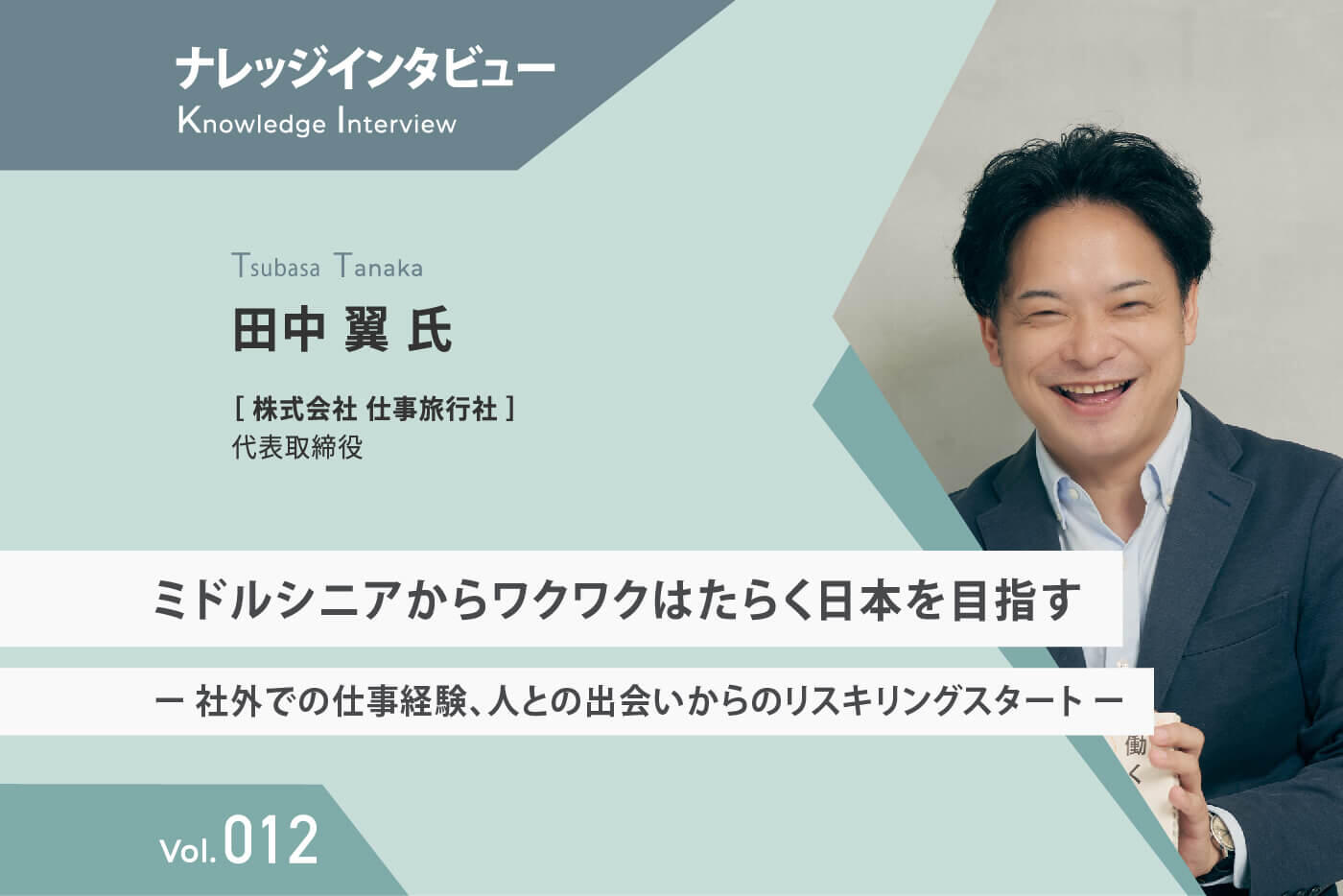
株式会社 仕事旅行社
代表取締役
田中 翼 氏
今回のナレッジインタビューは、社会人向けの仕事体験を行う、仕事旅行社 代表取締役 田中 翼さんです。リスキリングのきっかけとなる社外での異なる仕事体験や外の世界の人との出会うことの意義やもたらす気付きについてお話いただきました。
リスキリングの意味やミドルシニアに対する学びや支援の必要性と重要性と意味についても、さまざまな気付きときっかけを間近で見てこられた田中さんならではの視点でお伝えいただいています。
― 田中さんは社会人向けの仕事体験の事業をされていますが、そのきっかけを教えてください。
前職で仕事へのモチベーションが落ちてしまい、自分のやりたいことも見えなくなっていた時期がありました。そのときにヒントや何かのきっかけになればと、いろいろな企業を訪問させていただいていたのです。ある企業で皆さんがすごくワクワク楽しそうに仕事していたんですね。楽しくなかったら仕事じゃないというようなテンションでやっていて。当時の私は「仕事はつまらないからお金がもらえる」というカルチャーの中ではたらいていたので、衝撃を受けたことがありました。
その後もいろいろな企業を見ていく中で「効率化ばかり走っていても、やりたいことも見えず楽しく仕事ができない人ばかりでは、日本の経済は上向きになっていかないのではないかな」と思ったとき、以前訪問した企業でのワクワク楽しそうに仕事をしていた光景が浮かんできました。あんなふうに仕事をすることが大前提な世の中にしていくべきではないか、好きを仕事にすることが根本の部分になるのではないかと。そのような経験と想いから、さまざまな職種や環境の仕事体験ができる社会人向け事業をはじめました。
また、私たちの事業は「行く体験」「仕事体験」とうたっていますが、人に会うということを意識しています。同じ50代半ばの方でも、会社に可もなく不可もなくしか考えていないとかたまたま参加したような人が、仕事が楽しくて仕方ない人に出会った時「やっぱりこのままではいけないな」ってスイッチが入ったりするんです。異なる仕事体験ということだけではなく、今まで関わりのない人と会うという意味でも、そういう経験は大事だと思っています。
― 今、さまざまな場面でリスキリングが語られていますが、リスキリングのきっかけとして参加される方も多いのではないでしょうか。現状をどのように捉えていらっしゃいますか。
「リスキリング」より前には「リカレント教育」もよく言われていましたね。「リスキリング」と「リカレント教育」は異なるものなのに、意味が混在して語られているように思います。個人目線での学びをリカレント教育、企業目線がリスキリングみたいになっているのかなと。必ずしも仕事に直結することだけではないが自分が興味あることを学んでいくという、学び直しの文脈がリカレント教育。今、リスキリングというと、ある程度ゴールが決まっていて「こういうことを学んで欲しいです」と企業がお題目として与えているイメージです。そういう意味では、私はリスキリングをリカレント寄りに考えています。
リスキリングについても、自分のやりたいことという根本がないままで「学びなさい」と言っても、今までと変わらないのではないかと思っています。「経済合理性を高めろ」「生産性を高めろ」「新たなスキルを身につけろ」と上から言われてもなかなかうまくいかないのは、例えて言うなら、従来の一方的な教育スタイルを再生産しているような状態だからなのではなのでしょうか。リスキリングを本当に進めたいのであれば、まずは最初にやりたいことを見つけられるような支援をすることが重要だと思います。そうして自分の方向付けができると、人は自発的に学んでいけるようになるものです。私の考えるリスキリングというのは、自分のやりたいことを叶えるためのリスキリング、ある種リカレント寄りの感覚なのかもしれません。
特にミドルシニアはやりたいことが明確にないイメージがあり、状況は深刻なのではないかと思っています。実際話を聞いていても、やりたいことがわからない、好きなことが特にないという方が多いです。今の若い方たちは、学校でのキャリア教育で「自分の進むべき道は何なのだろう」ということを学び考える機会を経て社会人になっています。それに対してミドルシニアはそういう機会がないままに会社に入り、そのままずっとはたらいてきているので「今さらそんなことを聞かれても困るよ」というふうになっているのでしょう。
― 自分のやりたいこと以前に自分の強みなどを考える、振り返る機会もあまりないのかもしれないですね。まず、やりたいと思うことを自身で気付くためには何が必要なのでしょう。

私は新たな経験が必要なのではないかと思っています。食べ物に例えると、今の食文化、今あるメニューの中で食べたいものがないのに「あなたは何が好きですか」と聞かれても、それしか知らなかったらその中の食べ物以外は思い付かないし、言えないんですよね。食べたことのないものは、食べたいとは思わないじゃないですか。
キャリア面談も最近増えていますが、今知っているものを振り返る手段でしかないのかなと。その中でいくら振り返っても、今与えられているメニュー以外の好きなものは出てこない。
でも、ここで満足していないのだから、新たなものを知って取りに行かなくてはならないのです。そういう機会が圧倒的に足りてないイメージはありますね。
― どんな手段があるのかわからない中で、視野を広げるきっかけはどのように見つけたらよいのでしょうか。
例えば趣味のサークルに入ってみるとか、そういうすごく簡単なところからでよいのではないかと思っています。私も意図的に、知らない個人経営の飲み屋に一人でふらっと行くようにしているのですが、そういうところに行くと今まで関わりのない人たちと出会っていろいろなつながりができるんです。そのような一歩にも満たないような一歩から、まずはやってみたらよいのではないでしょうか。
― 人事ではミドルシニアに対しての施策を悩まれている方が多いです。会社が用意したものになると、やらされ感や構えてしまう気持ちになる従業員の方もいると思います。会社としての取り組みで参考になるような事例はありますか。
社内サークルを活発化したりする企業もありますが、まずは研修系のハードルを下げて、とにかく参加し経験してもらうことです。一回強制でやってもらうことも一つの方法です。年次研修などでキャリア研修を行った後に、当社のメニューに「一回は行ってきてください」と強制でやってもらうという企業もあります。一回行ってみると「こんな感じなのだな」「思っていたのと違った」と、社外に出ていき他の人たちと交流することを面白いと感じて、2回、3回と今度は自ら行くようになるという流れが作られています。ですので、強制も悪くはない方法だなと思いました。強制といっても、私たちの場合は「100種類くらいのいろいろな体験ラインナップの中から好きなものを選んでね」という、たくさんの中から自分で選べるマイルドな強制なところがよいのかもしれませんね。
― 普段の仕事と離れた体験と、現実にこれからはたらくことを、どのようにつなげているのでしょうか。
やはり「はたらく」に向けてもう一歩進むためには、体験して何かを感じるだけでは難しい方は多いので、考えを深めて次のステップに具体的に進めるように、リフレクションを目的としたグループワークや1on1を行うところまでサポートすることもあります。そういう機会を設けてみた結果、意外だったのは「自社の魅力に再度気が付きました」と思う方が一番多いことです。海外旅行に行くと日本のよさに気付くのと同じような効果で「今の仕事はこういうところがよいところなんだな」「うちの会社っていい会社だったんだな」と気付いて、改めて納得している。今の環境を自己選択している感覚が高くなるというデータも出ています。
― 外での経験は新しい視点や知識を持って帰ることができるというだけではなく、自社の魅力や自己選択感の再認識ができるというメリットもあるのですね。

半年などの一定期間、企業間留学や副業で経験値を積んできて、そこで得たものを自社に持ち帰るという体験もありますよね。
私たちの体験は1回の体験なので、スキルの獲得まではいかないけれどその分複数のところに行けるので、視点が変わったり、自分の立ち位置が分かった、俯瞰できたという実感を得ることができるんです。新しいスキルを身に付けるよりも手前の段階で、まずは視点や考え方、好きなことなどに気付くということが第一歩としては必要だと思っています。
今まで3万人以上の方が私たちの仕事体験に参加してくださった中で、4~5段階ぐらいのステップで自律型の人材に進んでいくということが見えてきました。1段階目は、現状に対して「このままでよいのかな」という危機感を覚える。2段目は、外の情報をいろいろ仕入れる行動をとる。先程お話したような飲み屋に行って今まで関わりのない人と接するとか、勉強会に参加するとかワークショップに行ってみる。そのようなことを繰り返していろいろな違う価値観に触れると、「なんでそう思ったのだろう」というような自分との対話を繰り返していきます。その比較感の中で徐々に「自分はこういう価値観を持っているんだな」「こういうことをやりたかったんだ」というような気付きが芽生えてくる。それが3段階目で、最終的に「自分はこう生きていこう」というようなことがセットされる。
このように私は自律型人材へのステップを4段階で見ていますが、私たちの仕事体験はこの2段階目になると思います。企業間留学や副業で経験値を積んできてスキルを活かすような経験は、ある程度自律意識が芽生えた人たちに対して「スキルプロジェクトを回してさらに経験値を積んでいきましょう」という位置付けになるので4段階目の話であり、私たちのサービスとは似て非なるものだと思っています。
― 田中さんが今後目指すものや、やっていきたいことを教えてください。
私が目指す一番上段は、日本人がみんな仕事にワクワクする状態になることです。そのために、さまざまな選択肢に触れたりいろいろな経験をして、自分のやりたい方向性や価値観を見極めてほしい。現状、そのような経験や行動は、いわゆる情報感度の高い個人の方が多いので、いわゆる「普通の人」もそういう機会を当たり前に持つようになれたらいいですよね。
お話してきているように、特にミドルシニアはさまざまな職業を見たり考える教育も受けてきておらず、そのまま今も機会がない。自分から情報を取りに行く人は限られていますし、諦めてしまっている方も多いのではないかと思います。はたらく期間はどんどん長くなり、ミドルシニアもこの先まだまだはたらく。楽しく活き活きはたらき続けるために、外でのいろいろな経験を通して自分を知っていく機会提供をもっとしていきたいです。
また、企業側もミドルシニアに、まだまだ20年以上戦力になってもらわないとならない中で、もっと本気で手を打ち、注力してもよいのではないかと思っています。若い層はデジタルで情報を自分で取ってこれるし、自分の会社以外の世界に出るという価値も抵抗がない方が多い。副業も当たり前にやるなどして、外との接点が自然にできます。しかしミドルシニアにはそういうことが当たり前ではないので、ずっと同じコミュニティの中にいて気が付かないことがたくさんある。
研修も若手や次世代リーダーには優先が高いですが、ミドルシニアに対しては現実それほど予算がなかったりします。確かに若手を育てることは大事だけれど、組織全体を考えたときにこの層に注力しないということは、巡り巡って若手にも影響があるのではと思っています。今よくある、いわゆる自主性に頼って「リスキリングプログラムを並べました」ということだけでは、ミドルシニアは参加もしないし変わっていかない。もっと本腰をいれて改革していくようにしていかないと、変えていくことは難しいと思っています。諦め感のようなものをどう打破するか、ということはある程度会社側からのアプローチの工夫も、その積み重ねも必要です。
研修メニューを多く作ったりキャリア面談や企業間留学を進める前に、ミドルシニアを活性化させる。戦力になり続けてもらうために何が必要か、どういうアプローチがよいのか、本気で取り組む時期なのではないかと思います。
前回のナレッジインタビューvol.011に続いて、リスキリングとミドルシニアに関するインタビューをお届けしました。意味や意義、やり方などは異なる部分はあるも、必要性やミドルシニアの重要性など共通している部分も多かったと思います。
田中さんは異なるさまざまな仕事体験を旅行と表現し、経験や出会いを通じて、さまざまな気付きを楽しく活き活きはたらき続けるきっかけを作っていました。そこから感じる危機感やリスキリングの段階は、ミドルシニアに関わらずに大事な部分なのかもしれません。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

株式会社 仕事旅行社
代表取締役
田中 翼 氏
1979年生まれ、神奈川県出身。株式会社仕事旅行社代表取締役。米国ミズーリ州立大学を卒業後、国際基督教大学へ編入。卒業後、資産運用会社に勤務。在職中に趣味で様々な業界への会社訪問を繰り返すうちに、その魅力の虜となる。「働く」ということに対する気づきや刺激を多く得られる職場訪問を他人にも勧めたいと考え、2011年に仕事旅行社を設立。700か所以上の職場と仕事をする中で得た「仕事観」や「仕事の魅力」について、大学や企業、地方自治体を対象に講演も多数実施。HRNOTEやJB press、東洋経済オンラインなどの媒体でも執筆中。著書「働くコンパスを手に入れる: 〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ」
- 記事をシェアする