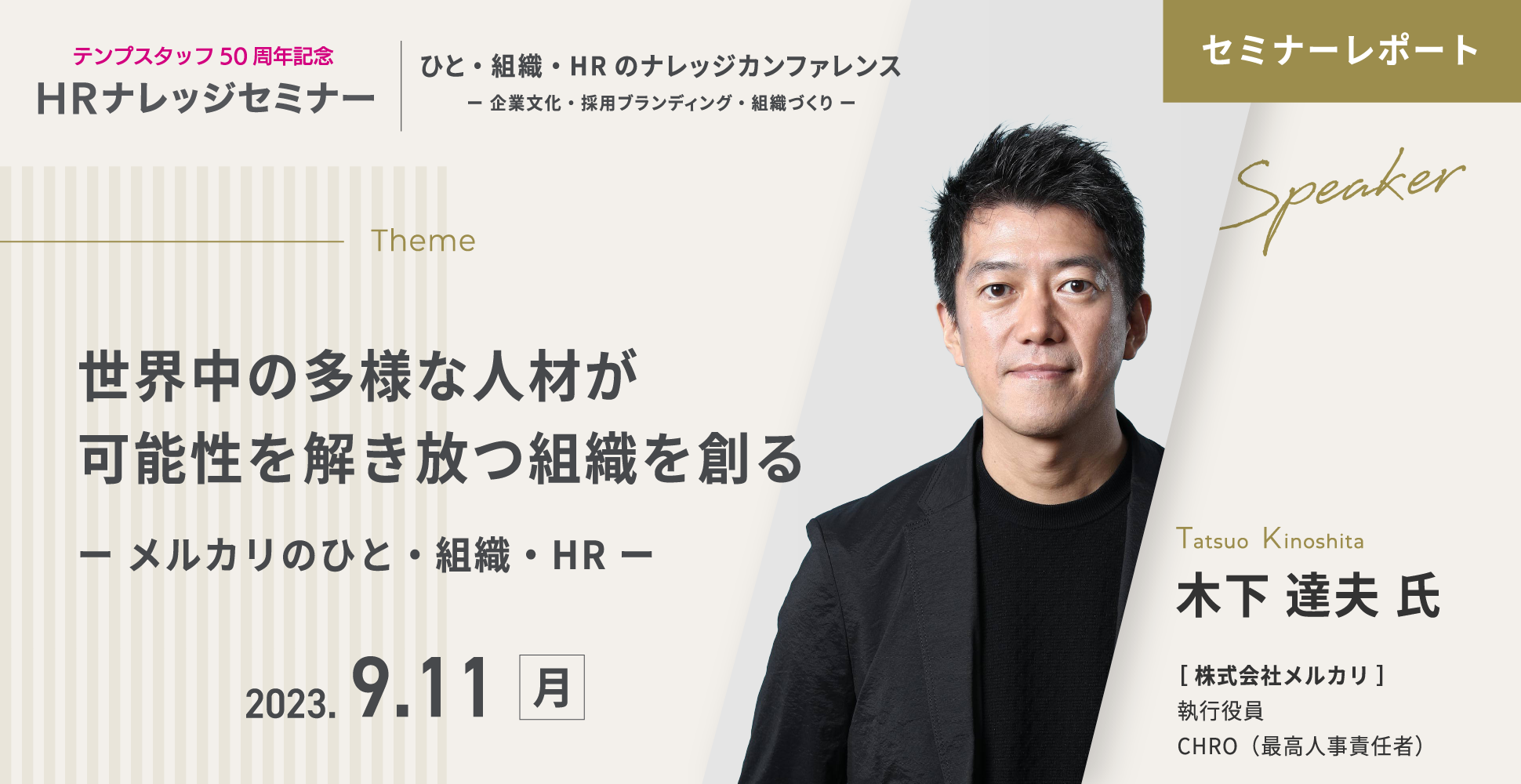HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジインタビュー 】
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東氏
新人事戦略をつくるために「人事が変わる」
公開日:2024.05.31
- 記事をシェアする

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長
東 由紀 氏
今回のナレッジインタビューは、HRナレッジセミナー2024 Spring DAY3 『人、カルチャー、組織を強化する ー 中期経営計画実現の基盤となる新たな「人材戦略」ー』の講演をいただいたコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 東由紀さんのイベント後インタビューです。講演内容を踏まえて、新人事制度までの道のりや「人事が変わる」ことについてお話しいただきました。
― 講演全体を通して、人事だけで進めるのではなく、ビジネス部門である各現場にもKPIを決めてもらい、「現場でも人事戦略について考えてもらう。現場も人事戦略に関わっていくことが重要である」ということが印象的でした。以前からそういう風土・体制だったのでしょうか。
以前からそういった風土や体制だったわけではありません。当社だけでなく以前にはたらいた会社もそうでしたが、「人事のことは人事がやってくれればいい」というような感覚が、多くの会社にあるのではないかと思います。
当社では2017年に設立されてから、さまざまなテーマの変革プロジェクトが進んでいますが、どのプロジェクトも、参加するメンバーは同じような顔ぶれでした。それぞれの組織に変革をリードできる人材が不足していることの現れです。この状態が続くと、変革プロジェクトを常に任されるリーダーは複数のプロジェクトを掛け持ちすることになってしまい、疲弊してきます。上司から見ていても「このままだとこの人を潰してしまう、辞めてしまうのではないか」と感じ、社内に変革をリードできる人材を育てなければならないというニーズが出てきます。 このニーズにこたえるために、全社的に変革リーダーを育成する研修プログラムを立ち上げました。そうすると、経験年数の長さや業務で成果を上げているだけでなく、変革をリードするポテンシャルで人材を評価する必要性が出てきます。「具体的にどのようなスキルや行動で変革リーダーのポテンシャルを測ればいいのか?」「経験年数だけで昇格させることが、今のビジネスのニーズに合っているのか?」という疑問も出てきます。
そのようにビジネス部門が直面する人材に関する課題を知り、そこにアプローチする人事施策をつくっていくことが大事ですね。実情や課題が何なのかを知ると「そこに対して、この施策を打つ」という問題解決の図式ができます。ビジネスの課題を理解するという過程を経ずに、「変革リーダーが必要だから、こんな施策をやってみよう」とKPIも持たずにアクションに飛びついてしまうと、結果の効果検証も適切にできずに「研修をやったはいいけれど、必要な人材が増えていない。」「業務が忙しいのに、研修に人を出すことに何のメリットがあるのか」というクレームが出てきてしまい、いつまでもビジネス側と人事側の狙いの溝が埋まらなくなってしまいます。
そうならないためには、講演でもお伝えした通り、人事施策を進める時に、ビジネス側と人事側の間に価値観やニーズ、心理的な距離を感じたら、まずは物理的な距離を狭めること。そのために、人事が現場に足しげく話を聞きに行って、課題をキャッチし、解決するためにはどうしたらよいのかを一緒に考え、行動することが必要になります。「人事にこういうことをしてもらったら、現場でこんなことがうまくできるようになった」という結果が積み上がってくると、ビジネス側から相談してくれるようになってきます。真に経営、ビジネスに即した人事施策を実行するには、人事から現場に足しげく通って、声を聞き、理解し、動く、その積み重ねだと思います。
― 統合を経て、いろいろなキャリアや価値観を持つ方の目線や意思、目指すものを合わせていくコミュニケーションを、人事部門の中ではどのようにされていますか。

多様なメンバーでのコミュニケーションにこだわっています。そのために、今年から取り組んでいる新たな人事戦略のプロジェクトを人事部門内の横断プロジェクトとして進めることにしました。当社の人事部門はCoE(センターオブエクセレンス)体制にしているので、本来は、変革のためのケイパビリティ強化のための研修は人材開発、現場の人材確保は採用、女性活躍推進はダイバーシティ推進というように、主管の担当組織が対応する業務です。
この体制の下でプロジェクトを動かすと、プロジェクトのオーナーである主幹部署の中だけで施策の検討が進み、専門分野だけの視点で施策を設計してしまいがちです。
例えば、当社では従来、評価制度は制度企画、自律的なキャリア形成のためのキャリアディベロップメント制度は人材開発が担っていました。この二つの制度をそれぞれの組織が担当範囲だけの目線で施策を考えて実行すると、従業員側には、評価制度の一環として期初に目標設定をして、その目標を達成するための育成施策を上司と話し合うように言われ、その後に別の部署からキャリアの目標を設定するように言われ、今度はその目標を達成するための育成施策を上司と話し合うように言われ…「何度も同じようなことをやらされているけれど、何がどうつながっているのだろうか」と混乱してしまいます。
ユーザーである従業員視点で考えると、人事制度企画も、人材戦略も、HRビジネスパートナーも、それぞれの専門分野の知識と経験を活かしながら、人事部門横断で考え、施策を設計し、従業員へのメッセージを統一し、ストーリーをつくらなければだめなんです。そのために、新たな人事戦略の横断プロジェクトでは、プロジェクトのオーナーとリーダーは主管している組織の管理職が務めますが、プロジェクトに関わるメンバーは人事部門横断で構成するようにしました。プロジェクトオーナーには、課題を解決するアクションや施策を提案したり、部署内でプロジェクトや施策の範囲を決めることが彼らの役割ではなく、人事部門横断で行うことによって多様な意見を取り入れ、プロジェクトの成果をできるところまで昇華させることが私の期待値であると話しています。それぞれのプロジェクトにもKPIがついていて、プロジェクトオーナー、リーダー、メンバーそれぞれの目標設定に含まれるので、どれだけそこに貢献したかということが彼らの評価の一つになっています。
― 人事の中でも縦割りになってしまうことや、ビジネス側のリアルな状況や課題の把握などは課題としてよくお聞きします。
そうですよね。CoEは人事の特定の分野の専門家であり、HRBPはビジネスの状況を知っていて、ビジネス部門特有の人的課題について理解している。人事として機能するにはそれぞれが重要な役割を担います。
当社ではHRBPも人事に所属していますが、ビジネス側が直面している人的課題は、常に現場と対峙しているHRBPが熟知しているべきで、そのインプットなしに人事施策を設計することがないように、人事戦略のそれぞれのプロジェクトには必ずHRBPが入るようにし、検討段階からコミュニケーションをとることができるようにしています。
これまで、私が人材開発を担当する中で新たな施策に取り組む際、課題とニーズの把握のためにビジネス部門に直接連絡しようとしたことがあります。その時にHRBPから「ビジネス部門とはHRBPを通してコミュニケーションしてください」と、扉を立てられてしまったことがありました。HRBPはビジネス側に対峙する責任がありますし、何か問題があった時にビジネス側からのクレームを受けるのは自分たちなので、直接話して欲しくないという、これまでのネガティブな経緯もあったのだと思います。ですが、CoE側にいる自分が直接ビジネス部門とコミュニケ―ションできず、課題とニーズを把握するまで時間がかかるというもどかしさがあり…当時は、そのような壁を感じていました。
新たな人事戦略を推進する上で最も避けたかったことは、「CoEが設計した施策をHRBPが実行する」という図式をまた作ってしまうこと。経営・ビジネス戦略の実現を人事として共に遂行するには、プロジェクトの中で人事施策をプランするところからHRBPにもしっかり入ってもらい、フラットに両者が考えていくことを重要にしています。それにより、人事部門内に存在する壁やサイロを壊し、ビジネスの課題を適切に解決する打ち手を講じることができると考えています。
― 人事内での横断体制のほかに、今回の新たな人事戦略にあたって東さんが力を入れたところはどういうところでしょうか。

新たな人事戦略では、ビジネスの声をしっかり入れることにより、経営とビジネス戦略を実現するために必要な人材、カルチャー、組織のあるべき姿を定義し、その姿を達成するための人事戦略というストーリーを構築しました。さらに、人事戦略の実行に対し、ビジネスからコミットメントを得るために、取り組むべき課題の優先順位をビジネスと共に決定しました。一つの施策を提案するときには、「経営戦略を実現するために必要な人材、カルチャー、組織の姿があります。
この姿を実現するために、ビジネス部門にヒアリングした結果、皆さんが直面している人的課題はここにあります。それを解決する人事施策にはこのようなものがあって、その中の一つが今回提案している施策です」と、一つの人事施策がビジネスにとってどの課題を解決できるのか、その先にある人材、カルチャー、組織の姿は何かを伝えることができると、ビジネス側と人事側の両者にとってわかりやすいですよね。
伝え方はとても大事だなと思います。私は、社内のブログや全社タウンホールの場で話をするだけでなく、社外でも当社の人事戦略、施策について発信を多くするようにしています。その中で気を付けていることは、会社の目線、人事の目線で話さないことです。常に聞き手の目線で、聞き手にとってどのような影響やメリットがあるのかを伝えるように心がけているのは、これまでのキャリアの中で営業やマーケティングを経験したからかもしれません。
人事部門のメンバーにも同じように、ユーザー側であるビジネス部門の管理職や従業員にとって、この施策はどういう意味があるのか、これを使うことによってどういうメリットがあるのか、やらないとどんな問題が発生するのかを、ユーザー目線で伝えること徹底しています。
ビジネス部門では、当たり前のようにKPIで達成度を測っています。目標値を達成できない何かしらの課題が見つかった際には解決策を講じ、時には計画を見直すこと、「なぜこれが必要なのか」ということをお客さまの目線で話すということを、日々実行しています。人事がビジネス部門と対等に対話するには、経験則や感覚値だけに頼らないデータドリブンの考え方と決断、ユーザー目線を身に着けるように変わっていく必要があります。
今年に入ってからも、人事部門のメンバーが新しい人事施策や改善案を提案してきますが、「これは人事戦略のどこに当てはまっていて、ビジネス部門が直面しているどの課題を解決するための施策で、ひいては目指すべき人材・カルチャー・組織の在り方のどの実現に貢献するのか、という説明から始まる資料を作って欲しい。そこから話をスタートしてくれないと、話を聞かないよ」と繰り返し伝えています。人事戦略を自分の言葉で説明ができ、何のためにこの提案をしているのかをきちんと伝えられず、すぐに施策の説明に入ってしまう場合は、「もう一度準備してから来てね」とお願いしています。毎度初めから説明するのは面倒くさいと思われているかもしれませんが、このような説明を私にできないということは、ビジネス側に提案したり、施策を実行したりするときにも説明ができないはずです。経営戦略と人事戦略を連携させる考え方とストーリーテリングを習得するには、繰り返し言葉にすることがとても重要なので、「私のところに持ってくるのは何回でも失敗してもいいから、もう1回持ってきて」と言って突き放すようにしています(笑)
2024年からスタートした新人事制度は、設計から、考える順番、「3本の柱」をベースにして考える癖、説得力を持つために必要なことなど、人事がさまざまなことを進めるために、そこに立ち戻りブレないようにメッセージを人事のトップとして伝えながら、ビジネス側や経営を巻き込んで出来上がったものでした。施策を一つでも、人事の考え方、やり方、伝え方などが変わることによりこんなにもいろいろなことが変わる可能性が広がり、成果が見えるものになるのだという事例をお伝えいただきました。始まったばかりの新人事制度の一年後を、お伝えいただく機会をつくりたいと思います。
「社内公募でも人事がやりたいという人が増えてきています。人事が楽しく仕事をしてないといけないなと思います」と最後にお話しされていた東さん。人事が変わり、ビジネス側とのコミュニケーションやさまざまな発信をする中で「楽しく仕事をしている組織」になっているのだなと感じました。
\東氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2024 Spring】
人、カルチャー、組織を強化する
ー 中期経営計画実現の基盤となる新たな「人材戦略」ー
\東氏登壇のセミナーレポート無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2024 Spring】
人、カルチャー、組織を強化する
ー 中期経営計画実現の基盤となる新たな「人材戦略」ー
Profile

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長
東 由紀 氏
金融機関でセールスやマーケティングの業務に従事。2013年に人事へとキャリアチェンジ後、グローバル部門の人財開発、評価昇格制度、ダイバーシティ&インクルーションを統括。2020年にコカ・コーラ ボトラーズジャパン入社後、人財開発部長として人財育成と採用、評価制度を担当。その後、社長補佐を経て、2023年4月より人事・総務本部 ピープル・エクスペリエンス&リレーション統括部長。9月より現職。
- 記事をシェアする