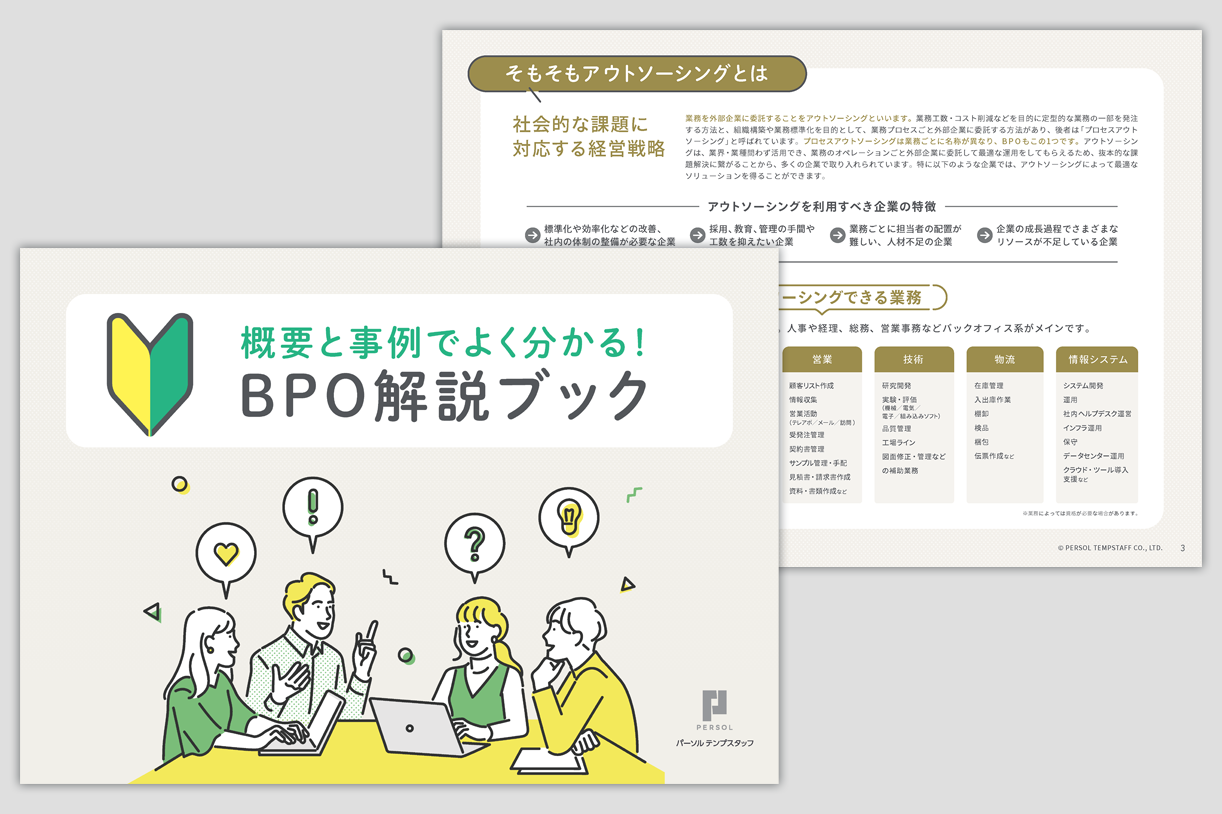HRナレッジライン
カテゴリ一覧
代表電話は誰が出る?代表電話の廃止が進む背景と対応策をご紹介
- 記事をシェアする

総合窓口として設置される代表電話は、企業の印象を左右します。SNSやチャットツールなどの活用が進み、固定電話を使用したことのない若者も増える中、代表電話の対応ができない新入社員も少なくありません。他の業務を進める中で、誰が代表電話に出るのがよいのか悩む方も多いでしょう。さらには代表電話自体を廃止するケースも見られます。
そこで今回は、代表電話は誰が出るとよいのかを解説すると共に、代表電話の廃止が進む背景や特定社員の負荷を軽減する方法、対応で気を付けるポイントなどをご紹介します。
目次
代表電話は誰が出るのがよいのか
企業もしくは部門の窓口として設けられる電話番号を「代表電話」と言います。複数ある部署のいずれかに要件がある場合、当該部署の電話番号が分からなくても代表電話にかけることで取り次ぎが可能です。一方で、特定の部署に設けられた電話番号を「直通番号」と言います。
これらの要素から分かるように、代表電話は不特定多数の人からお問い合わせが来る点が特徴です。企業の「顔」とも言えることから、適切で丁寧な対応が求められます。
OJTとして新入社員が対応
企業によっては、OJTの一環として新入社員に代表電話の対応を任せているケースも少なくありません。OJTとは、「On the Job Training」の略語で、実践を通して必要なスキルや知識を習得する人材育成の方法です。
取り次ぎや同案件の電話応対などであれば、入社して間もない社員でも担当できます。また社会人として欠かせないコミュニケーションスキルや、ビジネスマナーを習得する上でも役立つ業務です。
事務職社員やバックオフィス社員が対応
大企業の多くは、代表電話の対応を専門に担当する社員を配置しています。しかし中小企業の場合、事務職やバックオフィスの社員が対応するケースがほとんどです。
その場合、本来の業務を進めながら兼務する必要があり、手の空いた社員が電話を受けることになります。場合によっては、対応する社員に偏りが生まれる可能性もあるでしょう。特定の社員ばかりが電話に出る場合、企業として困ることがいくつか出てきます。
決まった社員が電話対応する場合の懸念点
事務職やバックオフィス社員など、決まった社員が電話対応している場合、以下のような懸念点が考えられるでしょう。それぞれの懸念点について解説します。
本来の業務が中断されてしまいスケジュールがひっ迫する
事務職やバックオフィス社員は、代表電話の応対を専門に担っているわけではありません。注力したい業務と並行して電話に出ることになります。部署内全体で電話に対応できればよいですが、数人だけに偏ってしまうとその社員の業務が滞り、スケジュールがひっ迫しかねません。
その結果、該当社員のみ残業や休日出勤が増えてしまえば、モチベーション低下につながるでしょう。特に頻繁に電話がかかってくる中小企業で考えられる懸念点です。
ビジネス機会の喪失につながる
代表電話には、新規のお客さまや取引先から大事な電話がかかってくることもあります。決まった社員しか電話に出ない状態では他の社員が頼り切ってしまい、積極的に出なくなることも懸念されます。そのため、当該社員の不在時や手が離せないタイミングにかかってきた電話を取り逃がす可能性があります。
万が一、その電話が重要な内容だった場合、ビジネスにつながる機会を喪失しかねません。
休憩時間を確保できない
場合によっては休憩時間も自分のデスクで過ごすケースがあり、休憩時間にかかってきた電話まで特定の社員が出ることが考えられます。代表電話にかかってくる電話は、取引先やお客さまだけとは限りません。なかには、業務に必要のない営業電話や迷惑電話もかかってくるでしょう。
休憩時間が不要な電話で削られてしまえば、十分な休息が取れず、本来の業務に支障が出る可能性があります。
社員の負荷を軽減する方法
決まった社員だけが代表電話に出ることは、大きな負荷につながります。こうした事態を避けるには、以下に挙げる方法を取り入れて改善を図ることが大切です。それぞれの方法について解説します。
社員全員で対応
事務職社員やバックオフィス社員が代表電話を対応する場合、特定の社員に偏らないように全員が電話に出ることを心がける必要があります。大勢でカバーし合える環境が整っていれば、決まった社員の負荷を軽減できるでしょう。また電話が苦手という理由で対応を避けていた社員の、コミュニケーションスキルアップにもつながります。
注意点として、社員全員で対応したとしても、代表電話に出るために誰かが業務を中断する必要がある点は変わりません。電話に出る役目を決めるわけではないため、全員が忙しい時期はすべての電話に対応できない可能性もあります。そのため、重要な電話を逃すリスクを完全に解消することは難しいでしょう。
電話代行サービスの活用
特定の社員にかかる負担や作業効率の低下、ビジネス機会を逃すリスクを避けるのであれば、電話代行サービスの活用が役立ちます。
電話代行サービスでは、専門のオペレーターが社員に代わって代表電話対応を担います。例えば人材が不足している企業や、オフィスで社員が不在になるケースが多い企業などをサポートするサービスです。電話応対に関するスキルが高く、豊富な知識を持ったオペレーターが電話に出るため、対応品質もよく、顧客満足度の向上も期待できるでしょう。また、業務に必要のない営業電話や迷惑電話に費やす手間と時間を削減できる点も、大きなメリットです。
パーソルテンプスタッフでは、企業受付と合わせて代表電話代行サービスも行っています。高いホスピタリティを持つオペレーターの接客力を強みとして、多くのお客さまにご活用いただいています。パーソルテンプスタッフの幅広い受付サービスについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
代表電話の対応で気を付けるポイント
自社で代表電話の対応をする際、以下のポイントを押さえることが大切です。それぞれのポイントについて解説します。
3コール以内で出る
代表電話は3コール以内で出ることが大切です。一般的に電話のコールは1回で3秒程度かかります。そのため4コールを超える場合、相手を10秒以上待たせることになり不快感を与えかねません。
クレームの電話がかかってきた場合、そもそも不満を抱えているお客さまに対して、さらなる怒りを買うことにもつながります。また商品やサービスに関するお問い合わせでも、長く待たされれば諦めて他社に乗り換えるケースもあるでしょう。
企業のイメージを損なわないことやビジネスの機会を逃さないためにも、代表電話は速やかに出ることが大切です。4コールを超えた場合は「大変お待たせいたしました」と一言を添えて、お詫びの気持ちを伝えるとよいでしょう。
大きな声でハキハキ話す
電話は対面の会話と異なり、こもって聞こえがちです。またお互いの表情や動きが見えないため、無愛想な印象を与える可能性もあるでしょう。
相手に不快感を与えずに正しく伝えるためには、意識的に大きな声でハキハキ話すことが大切です。加えて、普段よりも話すスピードを抑えた方が伝わりやすいでしょう。声のトーンを少し上げると聞き取りやすくなり、明るい印象を与えます。
電話応対に苦手意識があると、他の社員に電話のやり取りを聞かれたくないと思いがちです。その結果、小さな声で対応してしまい、相手に「聞こえづらい」と感じさせることもあるでしょう。恥ずかしさを捨てて、ハキハキと自信を持って笑顔で話すことを意識すると、声のトーンが自然と上がります。
メモを取る
代表電話の近くにメモを置いておくこともポイントです。簡単な用件だったとしても、慌てていると正しく記憶できない可能性があります。特に他の業務の合間に電話を受けた場合、注意力が散漫になりやすいでしょう。
正確に取り次ぐためにも、かかってきた時間や相手、用件などを細かくメモしておくと安心です。ただし、一言一句をメモしていると相手を待たせてしまうため、要点を拾いながら速やかに記録します。
相手の会社名・担当者名・用件を確認する
担当者に取り次ぐ上で相手の会社名や担当者名、用件を確認しておく必要があります。相手が名乗った場合は、復唱してメモを取ると間違えにくいでしょう。
相手が名乗らない場合は、こちらから名前を聞く必要があります。その際に自分の名前を先に伝えることが、ビジネスマナーとして大切なポイントです。よく聞こえなかった場合は聞き取りづらい旨を伝えた上で、再度確認する必要があります。ただし、相手の声が小さいことや早口であることを指摘すると、不快感を与えかねません。「恐れ入りますが少々電話が遠いようです」などの一言を挟むとよいでしょう。
用件を確認する際も唐突に聞くのではなく、「差し支えなければご用件を伺ってもよろしいでしょうか」と丁寧に伝えると相手が話しやすくなります。
電話を取り次ぐ際は必ず保留にする
担当者に電話を取り次ぐときや情報を確認する際は、相手にお待ちいただくことを伝えた上で必ず保留にします。受話器を手で押さえて声が聞こえないようにする方もいますが、こちらの声が漏れてしまうこともあるでしょう。相手に不快感を与えないためにも、保留ボタンを押すことが大切です。
ただし、あまり長い間保留にすることは失礼にあたります。30秒を超える場合は「お待たせして申し訳ございません」とお詫びした上で、こちらからかけ直してもよいか確認するとよいでしょう。折り返す場合は相手の電話番号だけでなく、都合のよい時間を伺っておくと親切です。
なお電話機によってはディスプレイに電話番語が表示されますが、間違いを防ぐためにも相手に確認した番号をメモしておくことが大切です。
代表電話を廃止する企業が増えてきている背景
従来、多くの企業で設置されてきた代表電話ですが、廃止する企業が増えてきています。その理由として考えられる背景を解説します。
在宅勤務が増えている
近年、厚生労働省による働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症をきっかけに、在宅勤務を採用する企業が増加しました。在宅勤務の影響でビジネスチャットの普及が進み、電話よりもチャットをメインに活用するケースも多くなっています。以前は部門ごとに直通電話を設けるケースもありましたが、在宅勤務によりオフィスに滞在する時間が少なくなったため、電話自体を廃止する企業も増えているようです。
しかし、代表電話が不要になったわけではありません。在宅勤務が増えてオフィスに常駐する社員が減るなかで電話対応は企業の大きな課題となっています。
営業電話や迷惑電話がかかってくる
企業を悩ませる入電の一つが営業電話や迷惑電話です。人材不足により代表電話専門の社員がいない場合、各社員が本来の業務をこなしながら対応しなければなりません。営業電話や迷惑電話の対応に時間を費やしたことで、注力したい業務がおろそかになれば生産性も下がってしまいます。
電話対応が社員のプレッシャーになる
代表電話専門の社員がいない場合、手の空いた社員が対応することになります。企業によっては、コミュニケーションスキル向上を目的として、新入社員に任せるケースも多いでしょう。
代表電話を受ける人物は「企業の顔」となるため、高いスキルが求められます。丁寧な対応だけでなく、適切な案内や取り次ぎも重要です。新入社員や電話対応に慣れていない社員にとって、外部からのお問い合わせは大きなプレッシャーでありストレスとなります。
これらの課題を解決する上で、代表電話代行サービスが役立ちます。サービスを活用すると、電話対応のスペシャリストに業務を任せられるため、自社社員の負担を軽減することが可能です。その結果、顧客満足度や生産性の向上が期待でき、自社の成長にもつながります。
電話の対応でお困りの際はパーソルテンプスタッフへご相談ください
大企業では代表電話専門の社員を配置するケースが多いものの、人材不足が叫ばれる昨今、多くの企業では事務職やバックオフィス社員が兼務しているのが実情です。決まった社員ばかりが対応するなど偏りが発生すると本来の業務が滞ったり、ビジネス機会を逃したりすることも考えられるでしょう。企業のイメージを損なわないためにも、代表電話はいつでも速やかに出られる状態にしておくことが大切です。
しかし、在宅勤務の増加や電話対応が社員のプレッシャーになることなどを踏まえて、代表電話の廃止を検討する企業も少なくありません。一方で代表電話は企業の信頼にもつながるため、簡単に廃止できないと悩む方も多いでしょう。そこで代表電話代行サービスを活用すると、代表電話を廃止することなく、社員の負担を軽減することが可能です。
パーソルテンプスタッフでは、受付アウトソーシングにおいて企業受付とセットで代表電話を担っており、多くのお客さまにご選択いただいております。その理由として、高いホスピタリティを有するオペレーターやマネジメントノウハウにより、企業の顔にふさわしい高品質のサービスを提供している点が挙げられます。
また応接室案内や来客数管理など幅広い業務に対応しており、お客さまのご要望に合わせて柔軟に対応範囲を決めることが可能です。代表電話の代行についてお困りのことやご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
その他、コール業務に関する事例は以下のページでご紹介しています。
▼アウトソーシング・BPOサービスの導入事例

大量の申請、繁閑の差、電話がつながらない…。問題解決に向けて試行錯誤を重ねて『円滑な業務』を実現。
大阪市福祉局
社員の業務負担を軽減する代表電話代行サービスの詳細については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。
>>代表電話の代行サービスとは?見落としがちな業務の負担軽減メソッド
- 記事をシェアする