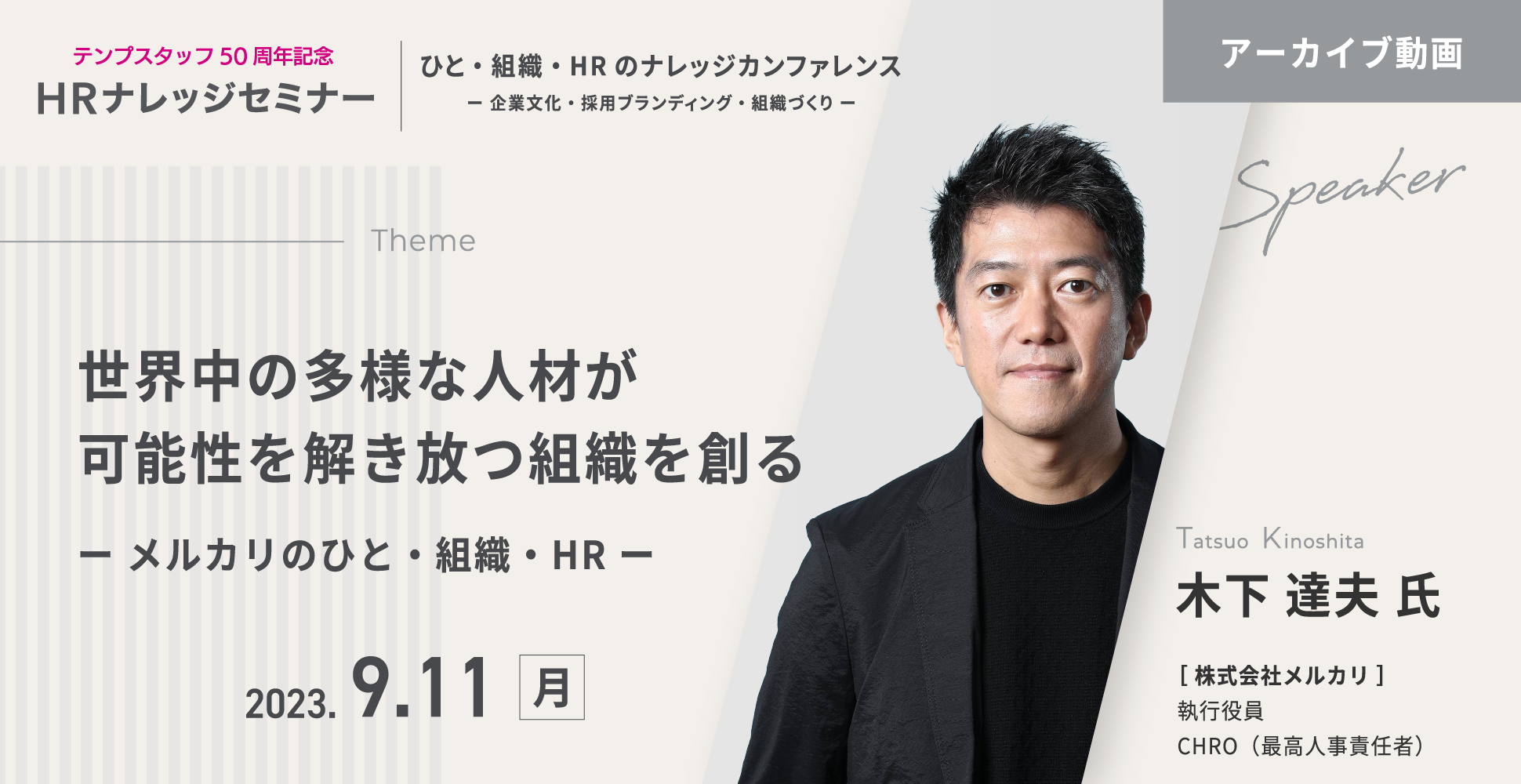HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【人事ライン】
アマゾンウェブサービス 小川氏
おもしろさ、難しさ、やりがい & 誇らしさ
公開日:2025.04.25
- 記事をシェアする

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
人事部
リクルーティングマネージャー
小川 璃紗 氏
「他の会社の人事ってどうやっているんだろう」「同じような悩みを抱えているのかな」さまざまな企業の人事パーソンインタビュー『人事ライン』。今回はアマゾンウェブサービスジャパン合同会社 人事部でエンジニアの採用を担当する小川 璃紗さんです。
ずっと人事のキャリアを歩み、現在はエンジニアの採用を担当されています。人事、その中でも採用業務について、また海外、エンジニア採用のおもしろさ、難しさ、やりがい、そして誇らしさをお話いただきました。
― 今までのキャリアと現在の仕事内容や役割を教えてください。
新卒で株式会社サイバーエージェントに入社し人事本部に配属となり、エンジニアの新卒採用の立ち上げをはじめとして、採用業務を主に人事のさまざまな業務を6年半経験しました。
その後「グローバルにビジネス展開している会社で仕事がしてみたい」という気持ちが芽生え、2013年にアマゾンジャパン合同会社に新卒採用担当として入社しました。その後、産育休を経て、復職後は中途採用担当として、アマゾンジャパン内のさまざまな部門を担当しました。また、Alexa(アレクサ:AmazonのEcho端末の頭脳となるクラウドベースの音声サービス)が日本でローンチされるタイミングで、Alexa関連の全てのチームの立ち上げの採用も約2年担当しました。
その後社内でエンジニア採用にフォーカスできるポジションを探し、2019年に現在のアマゾンウェブサービスジャパン合同会社(Amazon Web Service:以下AWS)に社内異動公募制度を利用して異動しました。昨年(2024年)4月よりAWSデータセンター部門の採用を担当することとなり、現在は日本、台湾、香港、中国、韓国の採用を統括しています。
― 採用が部門ごとになっているのですね。
アマゾンとAWSでは求める職種もスキルも違いますし、AWSの中でも部門が違えばまた異なってきますので、部門毎に採用担当がアサインされています。現場と密にコミュニケーションをとりながら、現場と採用チームの二人三脚で採用活動を進めている形です。現場のことをしっかり理解した上で、並走することが採用チームには求められていますし、“Hire and Develop the Best”という採用に関する項目が行動指針に盛り込まれているほど会社全体として採用に力を入れているので、現場社員も採用活動にとても協力的です。
私自身は、自分が担当する部門の部門長とは月1回は必ず面談をし、情報のキャッチアップをするようにしています。それ以外でもチームメンバーそれぞれが、ハイヤリングマネージャーなど現場部門の社員とも定期的にキャッチアップをして、実際に現場で必要とされている人物像のすり合わせを行うなど、現場社員の生の声を聞くようにしています。
― ずっと人事のキャリアを歩まれていますが、人事以外のことをやってみたいと思われたことはありますか。
あります、あります(笑)。20代の頃は周りを見ていても、現場を経験してから人事に異動してくる人や、人事から現場に出ていく人が先輩でも同期の中でも多かったので、新卒からずっと人事にいる自分は「このままで大丈夫なのだろうか」と不安に駆られることがありました。やっぱり現場を経験した上で候補者と話す方が説得力があるのかなと悩んだ時期もあります。
今は、その悩んだ時期を通り過ぎて、ずっと人事でやってきたからこそ、それが自分の強みになっているかなと思います。直接的な現場の業務には携わっていなくとも人事だからこそ見えることもありますし、採用を通して会社に貢献できていると感じる瞬間も多いです。採用という仕事に誇りをもって取り組んでいますし、今後もずっと人事としてキャリアを積んでいこうと思っています。
― サイバーエージェントとアマゾンの似ている点、異なる点はどのようなところでしたか。

どちらの会社もカルチャーが全社に本当に浸透している点が、一番の共通項だと思います。サイバーエージェントでは、当時「maxims(マキシムズ)」という行動指針があり、その項目を全社員が覚えていて、日常会話の中でも出てくるくらい全社に浸透していました。アマゾンでも「Our Leadership Principles(OLP)(リーダーシッププリンシプルズ)」という行動指針があるのですが、このOLPが人事評価や採用面接の時にも使われますし、ミーティングをしている中でも日常的に出てきます。
違うところは、アマゾンはグローバル企業ならではのダイナミズムと言いますか、全世界に社員がいて、簡単につながれるところがすごくおもしろいと感じる反面、大きな企業なので、何かやろうと思ったら日本の中だけで承認できることもあれば、そうではないこともあります。私が入社した当時のサイバーエージェントはまだ1,000人に満たない従業員規模だったので、かなりスピードが速く、自分の裁量で決断して、どんどん動かせるおもしろさがありました。
― 長く携わっている採用の、どのような部分におもしろさや難しさを感じていますか。
採用の仕事は新卒、中途問わず奥深いですし、やりがいを感じています。人の人生の大きな転機に携わる職種なので、一人ひとりのキャリアに対してきちんと向き合いながら、その人自身が気付いていなくとも、「こういう道もあるのでは?」と新たな選択肢に光を当てて、提案することができます。
また、人々の人生やキャリアに寄り添うだけではなく、一人の新入社員が入社することによって社内が活性化されたり、新入社員の活躍によって全社の売上げが伸びたり、採用は会社に対してもインパクトが出せる仕事だと思っています。人に対しても会社に対しても、間接的でありながら、何かしら自分が貢献できるポイントがあるのかなと感じています。
一方、人にかかわる職種なので、決まった型がなく、「この方法でうまくいったから、次も同じようにやってみよう」と思っても、 同じ方法でまた成果が出るとは限りません。一人ひとり状況や価値観も違うので、それに合わせてカスタマイズして、自分のアプローチも変えていく、コミュニケーションも変えていく・・・そのような柔軟性が必要になっていきます。また、会社自体も日々変わっていきますので、求める人物像のベースは変わらないにしても、会社のフェーズが変われば採用要件を変えていかなければいけない場合もあります。そういった会社の変化やニーズを常にキャッチアップしながら柔軟に進めていくことが、おもしろいところでもあり、難しさでもあるかなと思います。
― 新卒採用と中途採用では、どのような違いがありますか。
日本はまだまだ新卒一括採用が主流なので、忙しいピーク時期も決まっていますし、大体のスケジュールが1年の中で見えています。その中でいかに会社のカラーを出していくか、どのような工夫を凝らすかが新卒採用担当の手腕が問われるところであり、やりがいに繋がる部分だと思います。どういうインターンを企画するのか、どう広報していくのか、また選考中にどう魅力づけをしていくのかなど、全体のプログラム設計およびプログラムマネジメント力が、新卒採用は特に求められると思います。
対して中途採用は、当社の場合は基本的にはジョブ型採用ということもあり、募集ポジションによってとるべきアプローチも充足するのにかかる時間も異なります。特に決まったスケジュールがあるわけではないですし、応募から内定出しまでにかかる時間も新卒採用に比べると短く、短期で成果が見えやすいです。ポジション毎に必要なスキルや経験は何なのか現場部門とすり合わせ、採用基準や採用フローを設計し、候補者をさまざまな経路から探すことが必要になります。ジョブ型採用の場合は、一つ一つのポジションをしっかりと理解し、候補者のスキル・経験とマッチングさせていく力が重要になります。
― そこにグローバルとなると、さらに違いがありそうです。
特に新卒採用は全然違います。日本の新卒採用市場は特殊とよく言われますが、新卒採用のスケジュール感や動き方を海外の人に理解してもらうのには苦労することが多いですね。日本の新卒採用は元々リードタイムが長いですが、近年では大学2年生ぐらいからインターンを始める学生も多くなっており、就職活動はさらに長期化しています。早い段階から新卒採用イベントに出展して学生との接点を持ち、企業の魅力付けをしていく必要性が海外だとなかなか理解されないので、日本の採用マーケットがどうなっているのかという説明からしなければなりません。
中途採用に関しても、違いはあります。例えばインドは人口もバイリンガル人材も多く、求職者の母数が日本とは全然違います。また、ジョブディスクリプションを見て、要件に全部当てはまらなくても「とりあえず応募してみる」という方も多く、一日に何十件も応募が自然と流入してくる。日本は海外に比べるとまだまだ転職市場が動いておらず、待っていてもなかなか自然流入での応募は集まらないので、企業側から積極的にスカウトメールを送り魅力を伝えるというアクションが必要です。インドなどと比べると応募総数が大きく違うので、数字だけを見ると「日本はどうしてこんなに応募者がいないのか」と海外メンバーから質問されることもあります。
他の国でうまくいったことが日本でもうまくいくとは限りません。英語の障壁や、文化の違いなどを考慮して日本は独自の施策を考えなければならないこともありますが、予算が必要な場合はなぜ日本だけ独自に動く必要があるのかなど、グローバルチームを説得しなければならない場合もあります。日本に限らず、それぞれの国に合う形にカスタマイズしていくためにも、各国の転職市場の状況や文化についての理解を深めることは欠かせません。言語や文化の違いによる苦労ももちろんありますが、それがグローバルな環境で働くおもしろさでもあります。日本のことをもっと知ってもらいたい、伝えたいという思いもありますし、日本にいるだけでは知り得なかったことがたくさんあるので、他の国、世界全体を知ることができるのはとても学びがあります。
― 小川さんがこれからやりたいこと、実現したいことはどんなことでしょうか。

日本国内での新卒と中途の採用は経験してきましたが、去年(2024年)の4月からスコープが広がり、海外も担当することになりました。海外の採用を担当してみると日本でやってきたことが全然通用しないこともあり、あらたに学ばないといけないと思うことが増えました。苦しいときもありますが、視野も広がり成長している実感を得られているので、今はアジア圏だけではありますが、ゆくゆくはさらにスコープを広げて他の地域も担当することができるといいなと思っています。
また、私はこれまで長年エンジニア採用に携わってきましたが、データセンター部門ではこれまで私が担当したことのない、電気設備や消防設備などのハード寄りのエンジニア職種が多くあります。今までエンジニア採用はたくさん経験を積んできたと思っていたのですが、まだまだ経験できていない部分があったことを実感しています。世の中にはいろいろな仕事があって、自分が知らない世界がまだまだあるのだなと思って。これからも好奇心を忘れずに、学びをさらに深めていきたいです。
会社としては、部門ごとに採用戦略を作っていく中で、部門横断で「何かイベントをやってみよう」とか「コラボレーションできることはないか」という動きが活発になりつつあります。全社として動くからこそできることもあると思うので、日本だけではなく、他の国々の採用チームともコラボレーションでできるとおもしろそうだなと思っています。
― 部門間とグローバル、二重のコラボレーションが楽しみですね。それにしても、エンジニアの仕事は専門的かつ幅広いので採用担当として、ある程度理解していないといけないのは大変です。
私自身は理数系でもないですし、コードも書けません。ただ、自分にはないスキルを持っている人たち、自分では経験できない世界を見ている人たちなので、エンジニアの方々と接することで自分の世界が広がっていく感じがして、採用の中でもエンジニア採用にすごく魅力を感じています。
エンジニアのスキルがあるというのは素晴らしいことで、その人自身や他の人が思い描いていることを、自らの手で実現でき、それが社会に還元されている。そういうスキルを持っている人たちのキャリアをサポートすることで、社会貢献につながっていけばいいなと。素晴らしいスキルを持つエンジニアの方々が活き活きと働くこと自体が、社会がより良くなることにつながっていくと思っています。
自分が採用したエンジニアが創ったり、改善に携わったりしたサービスや機能やアプリを、街中で使っているユーザーを見掛けると私もうれしい気持ちになります。間接的にでも自分も少しそこに携われている感じがして、誇らしい瞬間です。

人事部門、その中でも採用のキャリアを重ねている小川さん。その中でも部門に所属する人事として、エンジニアそしてグローバル採用の「ならでは」の大変さ、おもしろさ、やりがい、想いをお話いただきました。
また「採用のその先」に生み出されていくものを目にしたときの「そこに携われている感じがして、誇らしい瞬間」と話す小川さんは、ひとつひとつの採用に真摯に向き合い、採用するエンジニアの皆さんをリスペクトが感じられました。
長い採用業務の経験に甘んじることなく、変化に柔軟に対応し進めること、新たなことを学んでいく、常に前を向き、広い視点で捉えていることを端々で感じる時間でした。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
人事部
リクルーティングマネージャー
小川 璃紗 氏
大学卒業後、株式会社サイバーエージェントにて技術職の新卒採用担当。
2011年より人事本部マネージャー。2013年にアマゾンジャパン合同会社に転職、新卒採用担当を経てさまざまな部門の中途採用に従事。
2019年にアマゾンウェブサービスジャパン合同会社に社内異動し、日本のソリューションアーキテクト部門の中途採用をリードし、2021年よりリクルーティングマネージャー。2024年4月よりAWSデータセンター部門の日本、中国、香港、台湾、韓国の中途採用を統括。
- 記事をシェアする