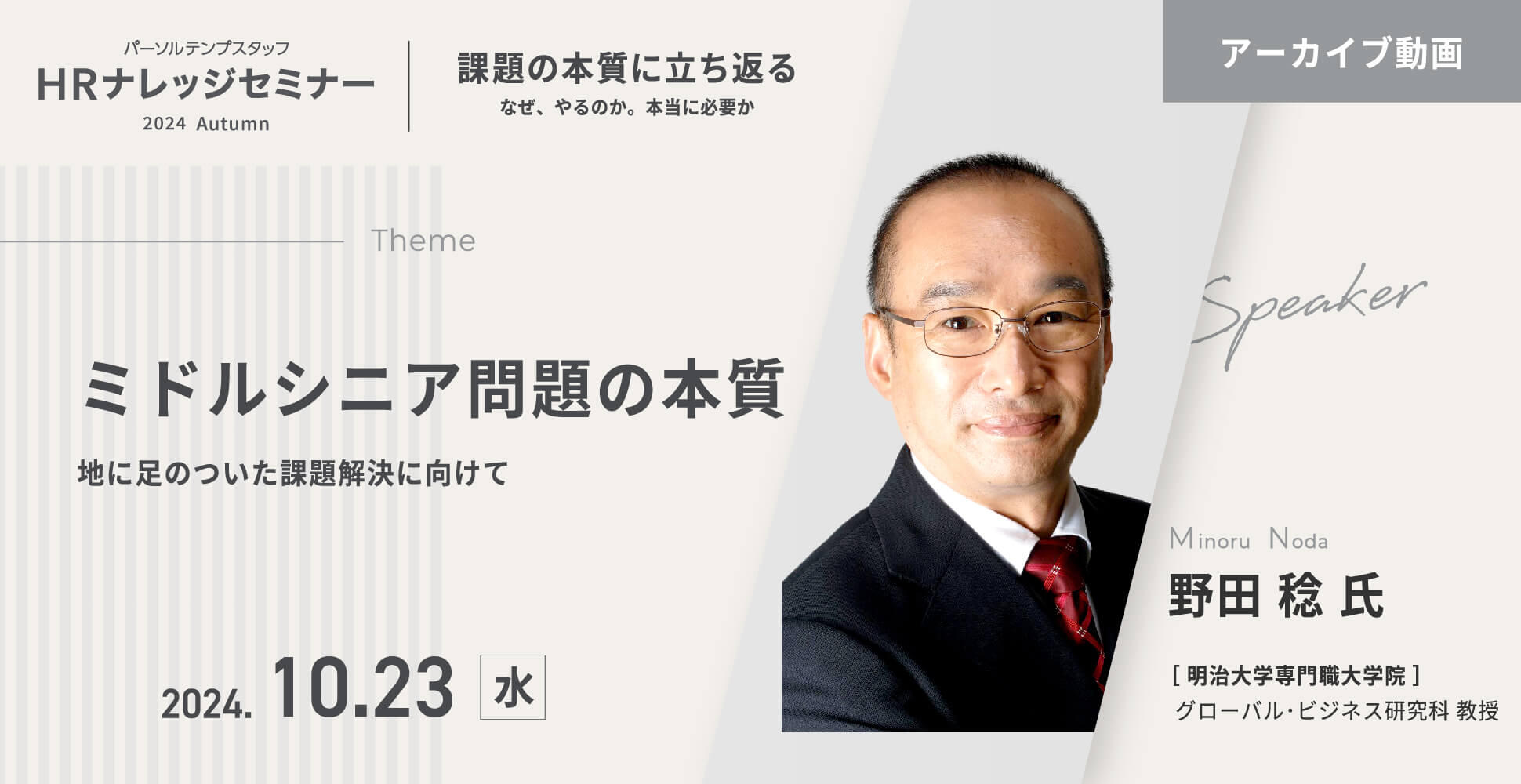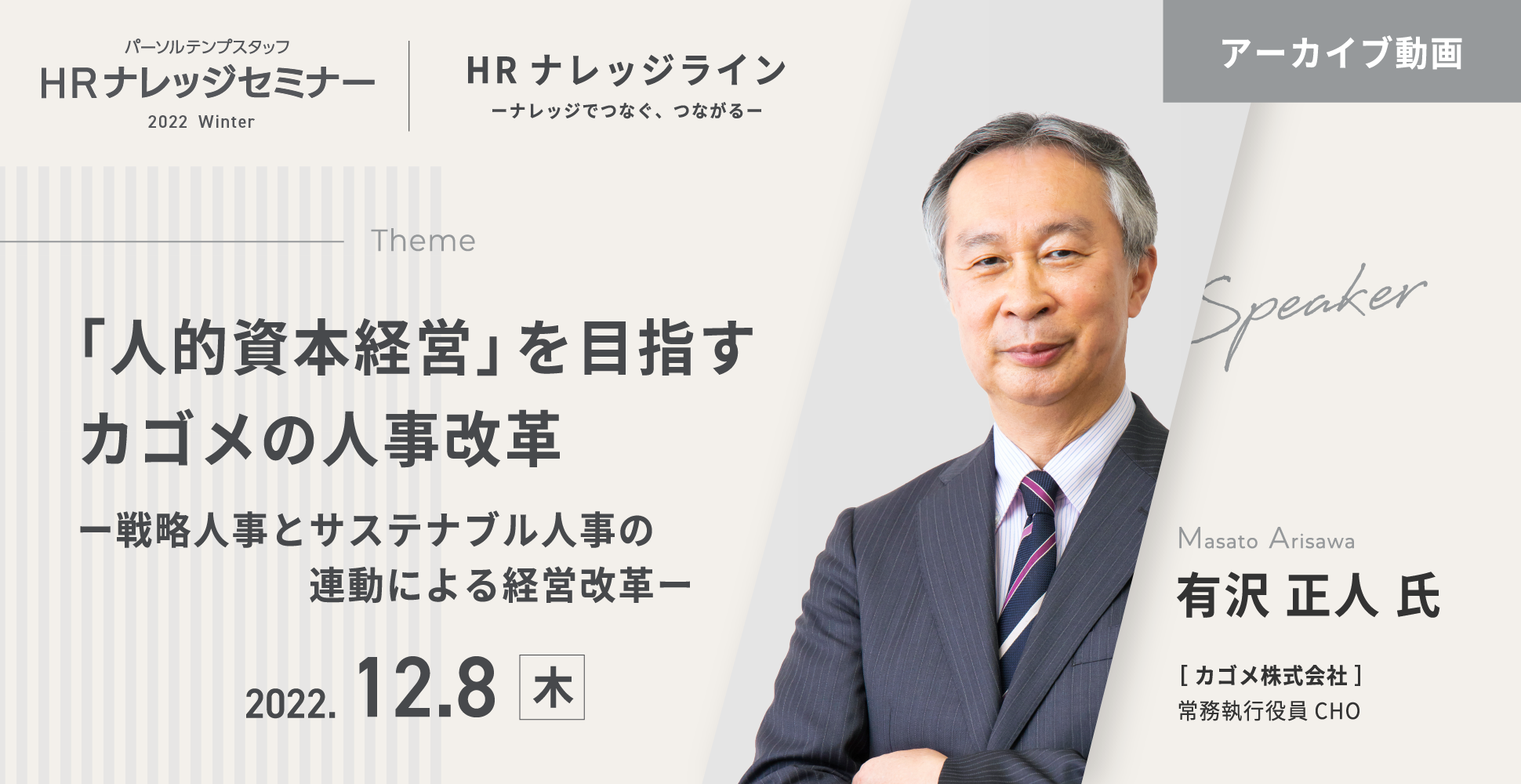HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート】
テンプスタッフ50周年記念 HRナレッジセミナー申込・参加者限定 続編企画!
カゴメ有沢氏&ロート髙倉氏の「とことん答える1時間」
公開日:2025.05.14
- 記事をシェアする

カゴメ株式会社 常務執行役員
カゴメアクシス株式会社 代表取締役社長
有沢 正人 氏
髙倉&Company合同会社 共同代表
ロート製薬株式会社 戦略アドバイザー
髙倉 千春 氏
2023年9月、5日間にわたり開催された「テンプスタッフ50周年記念 HRナレッジセミナー」。DAY2ではHRのエキスパートであるカゴメCHO有沢氏とロート戦略アドバイザー髙倉氏が登壇。参加者からは人事に関する課題や疑問、悩みなどのご質問が数多く寄せられました。10月には続編企画として、セミナーで回答できなかったご質問にお答えする「カゴメ有沢氏&ロート髙倉氏の『とことん答える1時間』」を開催。60分間のフリートークのなかで、ひとや組織、HRにまつわる貴重なアドバイスやお二人の人事に対する想いをお伝えいただきました。その一部をご紹介いたします。
▼有沢氏インタビューはこちら
定量化が難しい?HRBPの評価と役割
HRBP(Human Resource Business Partner)の評価は定量化が難しいため、カゴメではKPI評価シートを用いてきました。HRBPは、どれくらい役にたったのかは現場での満足度が大事です。また、現場からトップへ有益な情報をもたらしてくれたのか、トップからの戦略を現場に伝えていけたのか、事業戦略や各事業部門長とどこまで連携できたのかも重要なポイントです。そのようなことを、定量的にはかるためにKPIシートで評価します。シートには具体的なアクションや目標値といった項目があります。さらに社員との面談回数や、取り組んだ行動についてのフィードバックも行っています。またHRBPの貢献度を把握するために、現場社員へのアンケートも実施しています。(有沢氏)
HRBPと人事の役割は違っていて、人事はCoE(センターオブエクセレンス)、自社にとっての最適な施策を取り入れ、会社全体にとっての戦略を行います。 HRBPはそれをどう現場に伝えていくか、現場のことを見ながら部分最適で運用していくかがミッションです。そして、現場の声を人事にあげていくこと。それで人事の戦略も変わってきますから。HRBPが人事にタイムリーに情報を伝えていき、CHROがHRBPとCoEの両方からの情報を踏まえ、全体最適と部分最適の複眼視点で現場の状況を考えながら将来を見据えて判断していくというのが外資で見てきた形ですね。(髙倉氏)
ロート製薬の副業としての社内起業制度における評価は?
ロートではマルチジョブなはたらき方を推進するため、起業家を支援する社内プロジェクト「明日ニハ」を2020年からスタートしました。クラフトビールの醸造販売会社はじめ、これまで3つの会社が設立されました。これらの社内起業は副業扱いとなるため、人事評価に直接反映されません。一方で、社内起業で得たネットワークが本業に活かされるなど、よい循環が創出されています。結果的にロートの事業に価値をもたらし、評価にプラスに働くという現象が起きています。(髙倉氏)
カゴメのポストオフのルールと役職定年について
カゴメの役職定年は課長が55歳、部長が57歳です。ただし、余人をもって代えがたい人材の場合は、本人の上司にあたる本部長から人材開発委員会に申請をあげる形で「役職定年の特例延長」を行うケースがあります。一方で今後、役職定年制度を継続していくのはなかなか難しいというのが私の考えです。年齢による役職定年はある意味差別的とみなされる可能性もあり、多くの会社でも廃止されつつあります。このような背景から、当社では定年退職者にスキルを発揮していただくために、「定年退職者の嘱託再雇用制度」を改めて整備しました。その中では条件付きですが最長で70歳まで嘱託として契約延長可能な形態で雇用するケースも認めることにしました。(有沢氏)
社員のWILLを把握する方法
社員のWILLを明確に捉えるには、本人とどう向き合うのかが重要であり、最終的には上司との対話につながると思います。一方で、部下の将来を見据え、意向を忖度できる管理職が少ないのが現状です。そのためロートでは管理職研修で、部下との対話を適切に行えるプログラムを導入しています。(髙倉氏)
人事配置がマッチしなかった場合にはどうするか
人事配置がマッチしなかったと判明した場合は、まず社員本人に話を聞き、異動したいという意向が確認できれば、速やかに異動させるのがよいでしょう。適さないポジションに配置したままでは、本人にとっても会社にとっても有益ではありません。ただし、人事配置の成果を判断するには、少なくとも1年程度の期間は必要となります。(有沢氏)
日本企業と新卒一括採用について
日本企業が新卒一括採用を止めない背景には、雇用の安定性を重視し、また新卒採用が社会的義務と捉えていることが大きいです。とはいえ変化が激しいこの現代においては、専門性で勝負する人材に目を向けなければ、新規事業創出の可能性は低くなると言えるでしょう。(髙倉氏)
日本が新卒一括採用を止めない根本的な理由は、欧米に比べ人材の流動性が圧倒的に低いからだと思います。最近はそうでなくなってきてはいるも、まだまだ日本の場合「就職」ではなく「就社」というイメージが強いです。
もう一つは、年次に対しての考えなどの社会構造があると思っています。日本企業自身が人材の流動化を進め、年次管理を脱却することが必要だと考えます。(有沢氏)
最後に
人事パーソンとして活躍するには、財務とマーケティングを学ぶことがカギと言えます。財務では人的資本と深く関わり、マーケティングでは商品やサービスを社会に届けるにあたり必要なバリューチェーンを理解し、人材育成を進めていくためです。また、経営者と共に、経営課題について向き合う姿勢も必要となります。(有沢氏)
人材育成と採用にはリードタイムがかかるため、人事パーソンは将来目線を持つことが不可欠です。常に未来を見据えて行動することが肝心とも言えます。また、人に関心を持つことも人事に欠かせない要素です。最近の流行トレンドなども含め、ぜひ人の行動にも注視してみてください。(髙倉氏)
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

カゴメ株式会社
常務執行役員CHO(最高人事責任者)
有沢 正人 氏
1984年に協和銀行(現りそな銀行)に入行し、主に人事、経営企画に携わる。2004年にHOYA株式会社に入社。人事担当ディレクターとして全世界のHOYAグループの人事を統括。2009年にAIU保険会社に人事担当執行役員として入社。ニューヨークの本社とともに日本独自のジョブグレーディング制度や評価体系を構築する。2012年1月にカゴメ株式会社に特別顧問として入社。カゴメ株式会社の人事面でのグローバル化の統括責任者となり、全世界共通の人事制度の構築を行っている。2018年4月より現職となり、国内だけでなく全世界のカゴメの最高人事責任者となる。

ロート製薬株式会社
取締役 CHRO
髙倉 千春 氏
1983年、農林水産省入省後、米国Georgetown大学にて、MBAを取得。1993年コンサルティング会社にて、新規事業に伴う人材開発などに携わった後、1999年ファイザー株式会社、2004年日本べクトン・ディッキンソン株式会社、2006年ノバルティスファーマ株式会社の人事部長を歴任。2014年より味の素株式会社にてグローバル戦略推進に向けた人事制度の構築をリード。2020年ロート製薬株式会社に入社、取締役 人財・WellBeing経営推進本部E. Designerを経て2022年4月から現職。
- 記事をシェアする