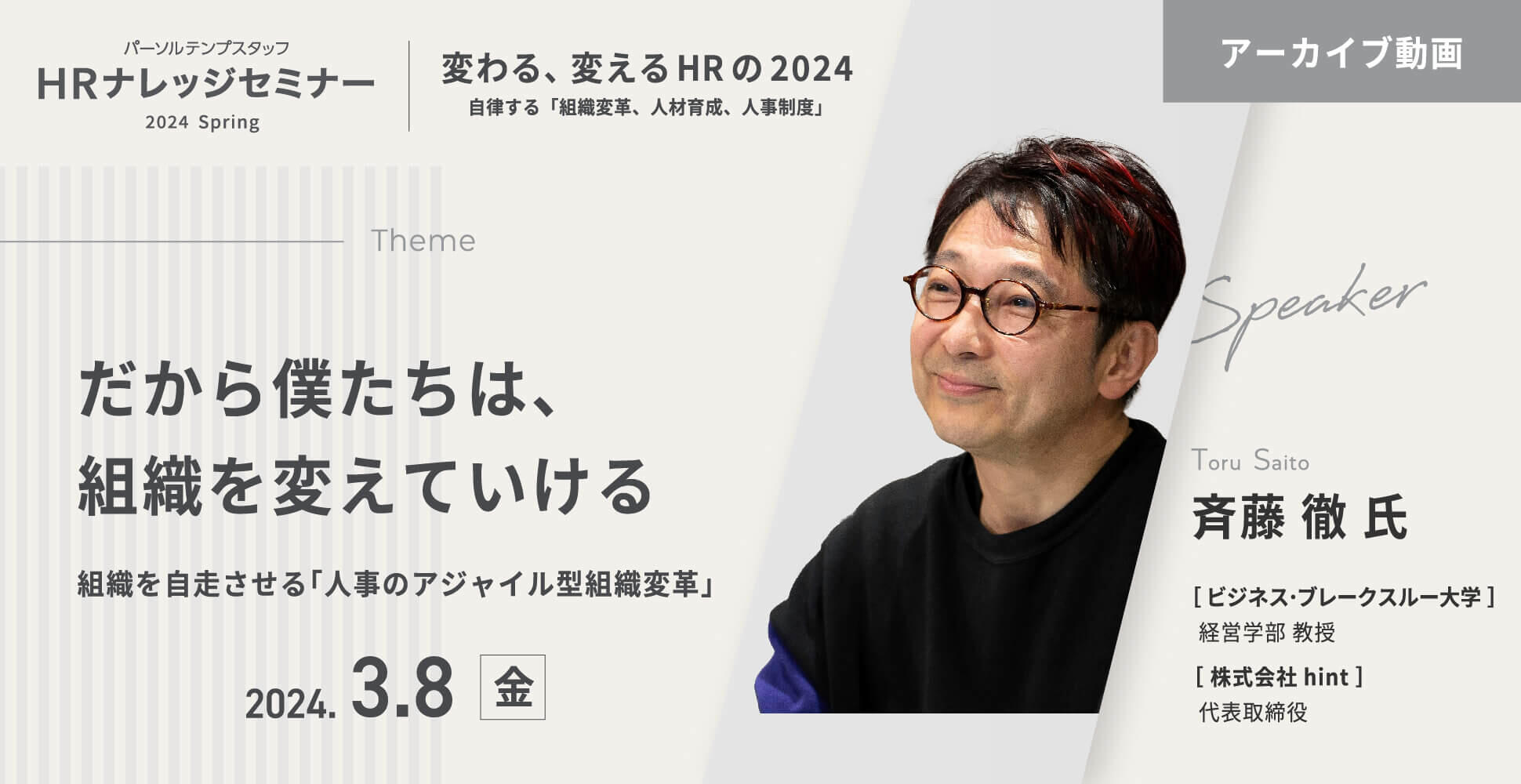HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート 】
ウェルビーイング(幸せ)な組織の作り方
ー大規模調査から読み解く「幸せ」のヒントー
公開日:2025.04.11
- 記事をシェアする
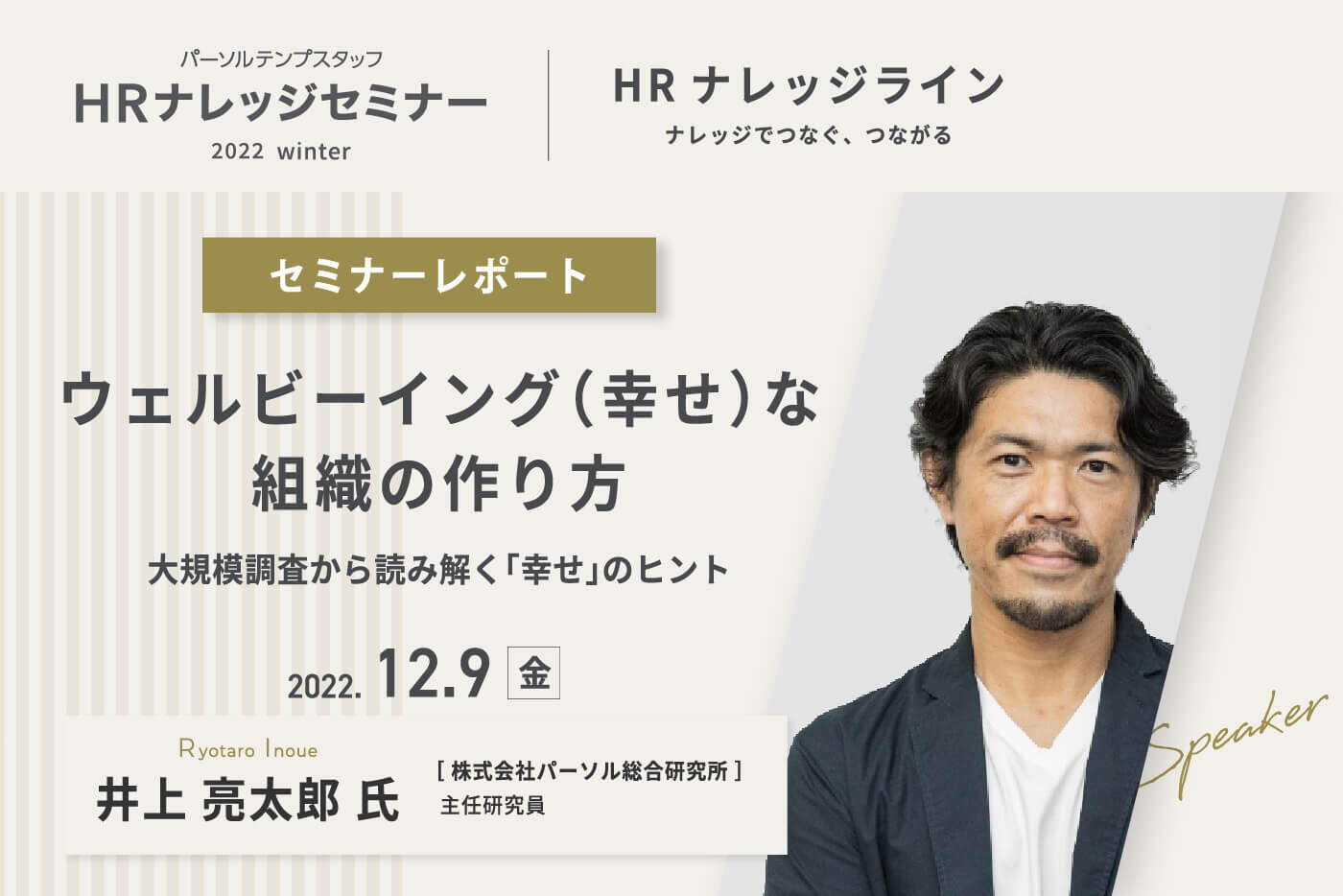
株式会社パーソル総合研究所
主任研究員
井上 亮太郎 氏
従業員のウェルビーイング(幸せ)がワーク・エンゲイジメントやパフォーマンス行動を促す源泉として、また人的資本経営の新たな指標として注目を集めています。ウェルビーイングな組織の作り方のヒントについて、慶應義塾大学の特任講師(パーソル総合研究所・主任研究員)の井上亮太郎氏による“はたらく人の幸せ”に着目し、従業員の幸福が個人や組織のパフォーマンスへ与える影響への科学的なエビデンスなどをご紹介します。
▼アーカイブ動画はこちら
ウェルビーイングの可視化がもたらすもの
職業生活におけるウェルビーイングとは、「仕事を通じて社会とのつながりや貢献、喜びや楽しみを感じることが多く、怒りや悲しみといった感情をあまり感じずにいる状態。また、そのような仕事やはたらき方を自分で決められる状態」であると私は定義しています。
はたらく人の幸せの要因に着目すると、幸せの7因子(自己成長、リフレッシュ、チームワーク、役割認識、他者承認、他者貢献、自己裁量)と、不幸せの7因子(自己抑圧、理不尽、不快空間、オーバーワーク、協働不全、疎外感、評価不満)で説明することができるとわかりました。
はたらき方の幸福度を測る大規模調査を行ったところ、例えば雇用形態別では正社員が最も低いことがわかり、幸せ因子では企画職といった職種で見ると、成長や他者貢献ではスコアが高かったものの、リフレッシュや役割認識は低く、不幸せ因子では自己抑圧や評価不満のスコアは低いという結果になりました。このように「幸せ/不幸せ」という2つの側面から分析するとウェルビーイングの状態が可視化でき、マネジメント介入のポイントを絞り込むことにも有効なツールとなるのです。
ウェルビーイングは組織のパフォーマンス向上に寄与する
「はたらく人の幸せ・不幸せ」のパフォーマンスに関する実証研究を行ったところ、はたらく幸せ実感が高まるとワーク・エンゲイジメント(仕事への熱意・集中・没頭)や挑戦志向が高まり、パフォーマンスが向上することが確認できました。また個人のはたらく幸せ実感が高まると、チームのはたらく幸せ実感が高まり、相乗的に個人のはたらく幸せ実感もより高まるという波及効果が見られました。
つまり、従業員の幸せを実現するための取り組みとは、組織としてのパフォーマンス向上という経済的利益にもつながる重要なマネジメント施策であり、主観的な幸せの実感値とは予測性の高い非財務指標だと言えるのです。
さらに、はたらく人を幸せ・不幸せにする組織マネジメント要因を調査したところ、人事施策においてはたらく幸せ実感を高めるのは「組織目標の落とし込み」「ワークライフバランスの良さ」、低下させるのは「異動・転勤の多さ」「終身雇用」といった人事施策が確認されました。また、「組織目標の落とし込み」「ワークバランスの良さ」は、はたらく不幸せ実感を低下させることが確認されました。これらの結果からも、皆さまの職場でマネジメント施策を検討する際には、それぞれの因子を高める機能を意図して要求に加えて頂きたいと思います。そのように考えておければ、その後の結果で意図した通りそれぞれの因子スコアが向上したかどうかで施策の効果検証もできるためおすすめです。
まとめ
昨今、企業の経営層や人事領域の方々において関心の高い人的資本投資とその情報開示とは、非財務情報の可視化を通じてステークホルダーからの良質なフィードバックを得て、中長期的な企業価値向上に資する「良き循環」を志向するものです。そして、その先に見据えるのは活力ある「Well-being(幸福)な社会」の実現だと言えます。すなわち、人的資本経営=ウェルビーイング経営とも換言できるのです。
とはいえ、いたずらに従業員にサーベイを繰り返すことは避けるべきです。何のために、何を可視化(測る)するのかを明確にし、従業員と組織の双方向でのコミュニケーションの一環としてデザインすることができれば、多様な従業員のはたらく目的と持続可能な組織の成長を整合させるマネジメントの重要なツールとなることでしょう。「はたらく幸せの7因子/不幸せの7因子尺度(WAW77)」が皆さまの議論を明瞭にする一助となれば幸いです。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

株式会社パーソル総合研究所
主任研究員
井上 亮太郎 氏
大手総合建材メーカー(現LIXIL株式会社)にて営業、マーケティング、PMI(業務・意識統合)を経験。その後、学校法人産業能率大学に移り組織・人材開発のコンサルティング事業に従事した後、2019年よりパーソル総合研究所にて調査・研究に従事。2020年より慶應義塾大学大学院特任講師。
人や組織、社会が直面する複雑な諸問題をシステマティック&システミックに捉え、創造的に解決するための調査・研究、教育、事業支援を行っている。その他、不動産管理会社代表取締役、一般社団法人にて副代表・アドバイザリー等を兼任。
- 記事をシェアする