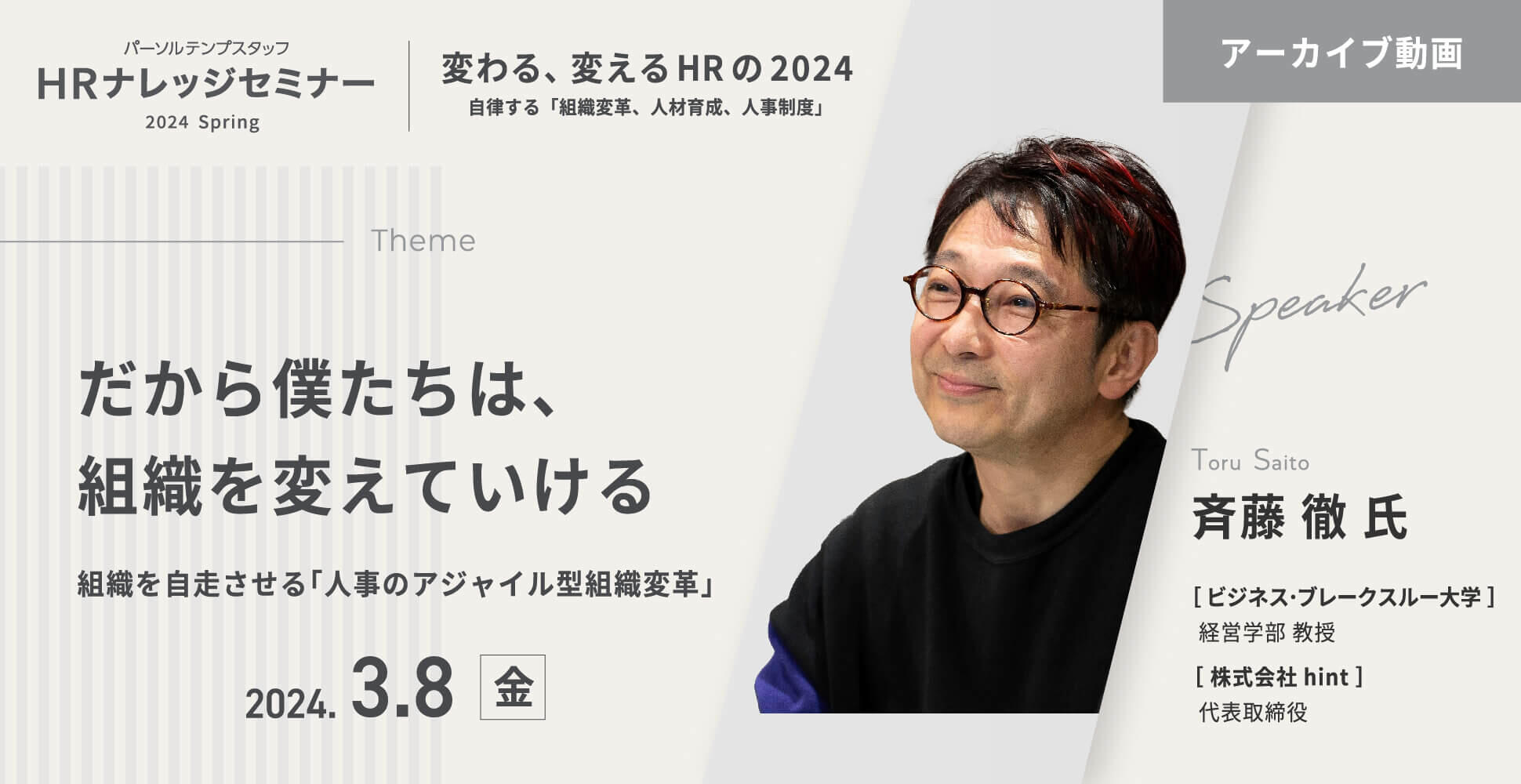HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート】
組織と自分のマナビ時間
公開日:2025.03.13
- 記事をシェアする

2022年3月、3日間にわたり「組織と自分のマナビ時間」をテーマに「HRナレッジセミナー2022 Spring」を開催しました。
「ひと」と「組織」に関するさまざまな施策を講じる役割を担う、HRのみなさまにお届けした3つの学び時間
「組織と人事の幸福学」「個と組織のアップデート方法」「伝える力、動く力、リーダーシップとマインド」
をダイジェストで振り返ります。
組織と人事の幸福学
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
兼ウェルビーイングリサーチセンター長
前野 隆司 氏
DAY1は慶應義塾大学大学院教授で、同大学のウェルビーイングリサーチセンター長も務める前野隆司氏が登壇。「はたらく幸せ」は、仕事自体にやりがいを持ち、信頼しあえる仲間とともにはたらくことだけで得られるものではなく、ワークとライフ両方が幸せな状態であることが重要である、という話からスタートしました。
前野氏は幸せな社員の特徴として、「創造性が3倍高い」「生産性が1.3倍高い」「離職率や欠勤率が低い」「健康長寿である」ことなどが研究データで出ていると紹介。
続いて、身体的・精神的・社会的な幸福を包括的に求めるWell-beingの概念が、これからのHRには重要なキーワードになると述べました。
変わる「はたらく幸せ」「幸せな会社」とは
前野氏は、幸せのかたちが時代によって変化していると指摘。経営の第一目標となりがちなお金やモノや地位といったものではなく、「非地位財」の幸せが求められるようになったと述べました。
非地位財の幸せとは、身体的・精神的・社会的に良好な状態であることをいいます。前野氏は、これからの時代はこの3つの要素が欠けることのない組織であることが幸せな会社であり、そうでなければよい人材が確保できなくなると語りました。そして、必要な人材を確保するためには、社員を幸せにする経営が必須であると提言しました。
社員が幸せになるためには、どうすればよいのでしょうか。前野氏は「自己実現と成長」「つながりと感謝」「前向きと楽観」「独立と自分らしさ」の4つのポイントを挙げ、これらを満たす組織づくりを可能にすることが、個々の社員の幸せにつながると述べました。
最後にWell-beingを実現する際には、まず経営陣が一丸となって、想いを伝えていくことが大事であり、組織規模が大きくても、チーム(部門)そして社員への伝播させることで、実現できると語りました。
まとめ
DAY1の講演では、時代とともに幸せの概念も変化しており、これからの組織には非地位財型の幸せが必要になってきていることが示唆されました。
社員が幸せであるということは、目の前の生産性(業務効率や新規事業も創出など)だけでなく、広い意味での生産性(欠勤率や離職率など)にも良い影響があると前野氏は述べています。
HRとして、いかに個々の社員が幸せであるかを考えることが、組織・会社全体のパフォーマンスにつながります。人事や経営者は、その幸せを形成する要となり、個人から組織全体への、幸せを伝播させていくことが求められるのです。
HRの『個と組織のアップデート』方法
サイバーエージェント株式会社 常務執行役員 CHO
曽山 哲人 氏
株式会社人材研究所 代表取締役社長
曽和 利光 氏
DAY2は、人材研究所代表の曽和利光氏とサイバーエージェントCHOの曽山哲人氏が、HRの「個と組織のアップデート」方法をテーマに対談しました。はじめに曽和氏が、人事のコアスキルとは組織や人の状態を「見立てる力」であり、この力自体は普遍的な能力であるも、構成要素についてはアップデートし続ける必要があると提言。これを踏まえ、3つのテーマでセッションを行いました。
経営課題を「人と組織」というテーマで解決するのが“人事”
1つ目は「コロナ禍で人事を取り巻く環境にはどのような変化があったか」。このテーマに対し、曽山氏は、人事や経営者はさまざまな事柄に対してリモートとリアル、どちらがよいかといった「極論をマネジメントする力」が求められるようになったといいます。またその中で、リアルタイムで社員の状況を把握するためにさまざまなツールを活用し、データをもとに全体を俯瞰した上で個別アプロ―チをしていく重要性について、事例を交えて説明しました。
2つ目のテーマは「変化の中で身につける能力・スキルは何か」。曽山氏は、データの活用とそれをもとに学習と実験を繰り返していく力、またオンラインコミュニケーションリテラシーの向上を挙げ、言語化能力を高めていく必要性について説明しました。
最後に「組織として“人事部”はどう変化していくべきか」というテーマに対し、曽山氏は経営課題を「人と組織」というテーマで解決するのが人事の役割であり、人も組織も変化し続ける中で、会社に足りないものは何かを常に見極めていくことが重要であると述べました。
まとめ
最後に曽和氏は、「これからの人事は社内のネットワークハブであることが必要」と提言。曽山氏も、そのためには対話の習慣化が重要であり、特に1年目の社員とのコミュニケーションが会社風土の醸成に大きく影響し、組織の課題も見えてくると述べました。
対談を通じて両氏がポイントとして挙げたのは、これからの人事には「データリテラシーやコミュニケーションリテラシーを学ぶこと」「組織のネットワークハブになるために言語化能力を高めること」が必要だということでした。
人事のなかの「個」として日々学習と実験を繰り返しながら、振り返る習慣をつけること。一見当たり前に思えるこの繰り返しが、スキルをアップデートするために必要不可欠であるといえるでしょう。
自分を知り自分を導き、成長する ー 伝える力、動く力、リーダーシップとマインド ー
Zホールディングス株式会社 Zアカデミア学長
武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長
Voicy パーソナリティ
伊藤 羊一 氏
DAY3は、Zアカデミア学長の伊藤羊一市が登壇。伊藤氏は、現在の社会に求められるものは、経済成長だけでなくサスティナビリティとの両立に変化してきているといいます。こうした変化に対し、会社はより個人にフォーカスし、一人ひとりが輝く会社・チームをつくる必要があると提言しました。
マネジメントとは何か。リーダーの役割と必要な力とは。
伊藤氏は、マネジメントとは管理するだけでなく「何とかすること」であり、リーダーやマネージャーはチームをゴールに導くために、チームの力を最大化することが重要な役割であると述べました。
そのため、リーダーやマネージャーにもっとも必要な能力はコミュニケーション力であり、それは個人間でメンバーと対話し(1on1Meeting)、メンバーが「話す→考える→気付く→習慣にする」といったプロセスを通して、自分で問題解決するためのサポートが重油です。このような対話ではコーチングスキルが不可欠です。
メンバーの話を傾聴しながら目標達成の筋道を考えさせ、自ら気付き行動に移せるように導く。そして、このサイクルを高速で回せるようにしていくことが、リーダーやマネージャーに求められる役割であると述べました。
最後に伊藤氏は、リーダーやマネージャーこそ、自分を知ること(Lead the Self)が必要であると述べました。マネジメントする人自身が「これが大事」「これがやりたい」といった気持ちを持つことが重要であり、未来に向けたその熱量によって自身と周囲の行動もが変わっていく。そのようにして組織に欠かせない強力なリーダーシップが生まれるのです。
まとめ
1on1Meetingでは、一人ひとりにフォーカスして対話し、相手が話し考える時間を持つことが重要です。そしてマネジメント側の役割は、相手が考え気付くことをサポートし行動までのサイクルを高めていくことと、チームの力を最大化しゴールへ導くことです。
それにはマネジメントする人自身が「自分を知る」ことが重要であり、自分の原動力となる想いの熱量こそが自身とチームを導く力になることを学びました。
DAY3では、HRとして「マネージャーの教育、育成が組織にとって重要である」ことをあらためて認識する機会となりました。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
兼ウェルビーイングリサーチセンター長
前野 隆司 氏
1984年東京工業大学卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現職。博士(工学)。 著書に、『幸せな職場の経営学』(2019年)、『幸福学×経営学』(2018年)、『幸せのメカニズム』(2013年)、『脳はなぜ「心」を作ったのか』(2004年)など多数。専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育など。

サイバーエージェント株式会社 常務執行役員 CHO
曽山 哲人 氏
上智大学文学部英文学科卒。高校時代はダンス甲子園で全国3位。1998年に株式会社伊勢丹に入社し、紳士服の販売とECサイト立ち上げに従事。
1999年に当時社員数20名程度だった株式会社サイバーエージェントに入社。 インターネット広告事業部門の営業統括を経て、2005年人事本部長に就任。 現在は常務執行役員CHOとして人事全般を統括。
キャリアアップ系YouTuber「ソヤマン」としてSNSで情報発信しているほか、『若手育成の教科書』『クリエイティブ人事』『強みを活かす』などの著作がある。

株式会社人材研究所 代表取締役社長
曽和 利光 氏
リクルート人事部ゼネラルマネジャー、ライフネット生命総務部長、オープンハウス組織開発本部長と、人事・採用部門の責任者を務め、主に採用・教育・組織開発の分野で実務やコンサルティングを経験。また多数の就活セミナー・面接対策セミナー講師や情報経営イノベーション専門職大学客員教授も務め、学生向けにも就活関連情報を精力的に発信中。人事歴約20年、これまでに面接した人数は2万人以上。2011年に株式会社人材研究所設立。『人と組織のマネジメントバイアス』『コミュ障のための面接戦略』など、著書多数。
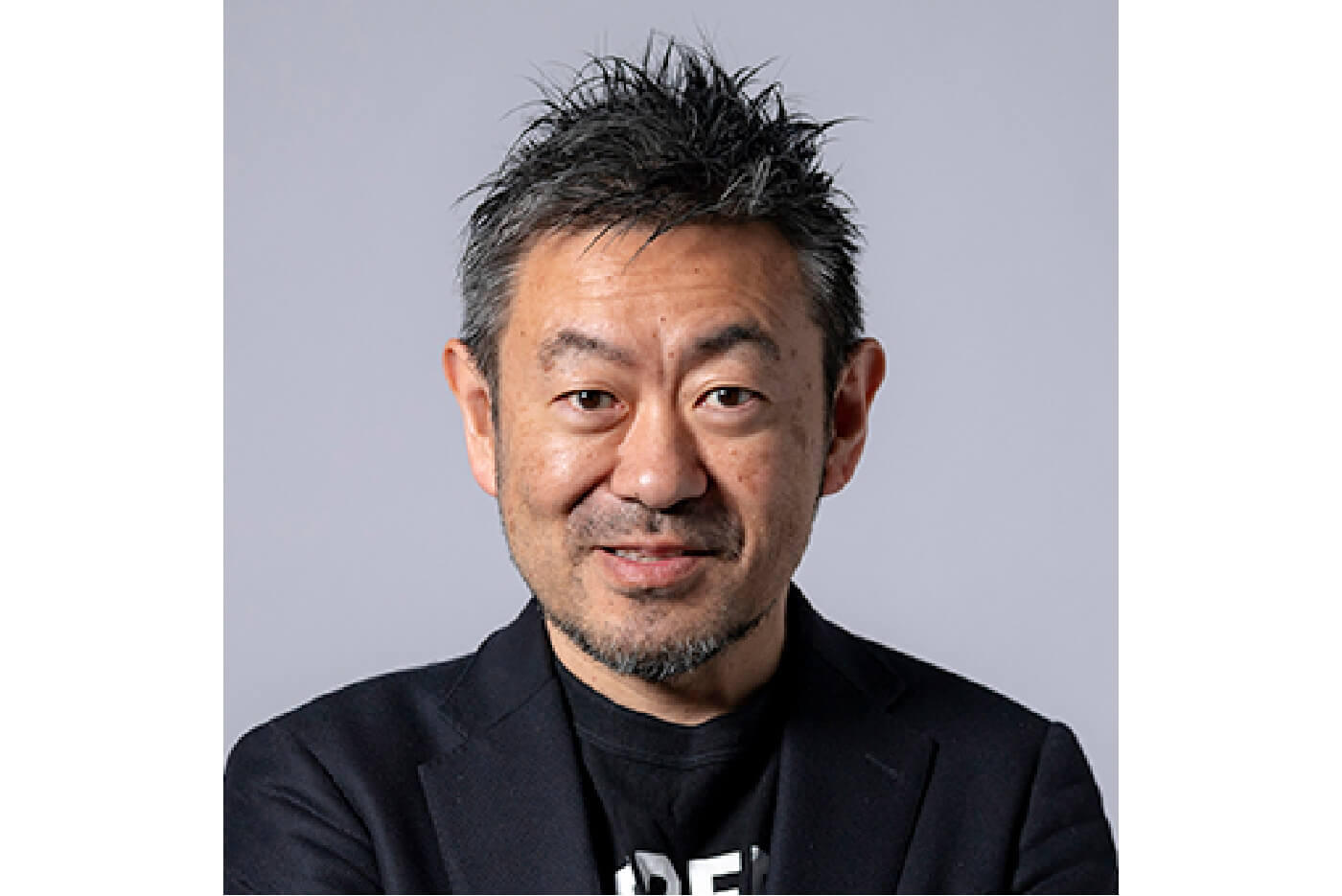
Zホールディングス株式会社 Zアカデミア学長
武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長
Voicy パーソナリティ
伊藤 羊一 氏
日本興業銀行、プラスを経て2015年よりヤフー。現在Zアカデミア学長としてZホールディングス全体の次世代リーダー開発を行う。またウェイウェイ代表、グロービス経営大学院客員教授としてもリーダー開発に注力する。2021年4月に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)の学部長に就任。
代表作に56万部超ベストセラー『1分で話せ』ほか、『1行書くだけ日記』『FREE, FLAT, FUN』など。
- 記事をシェアする