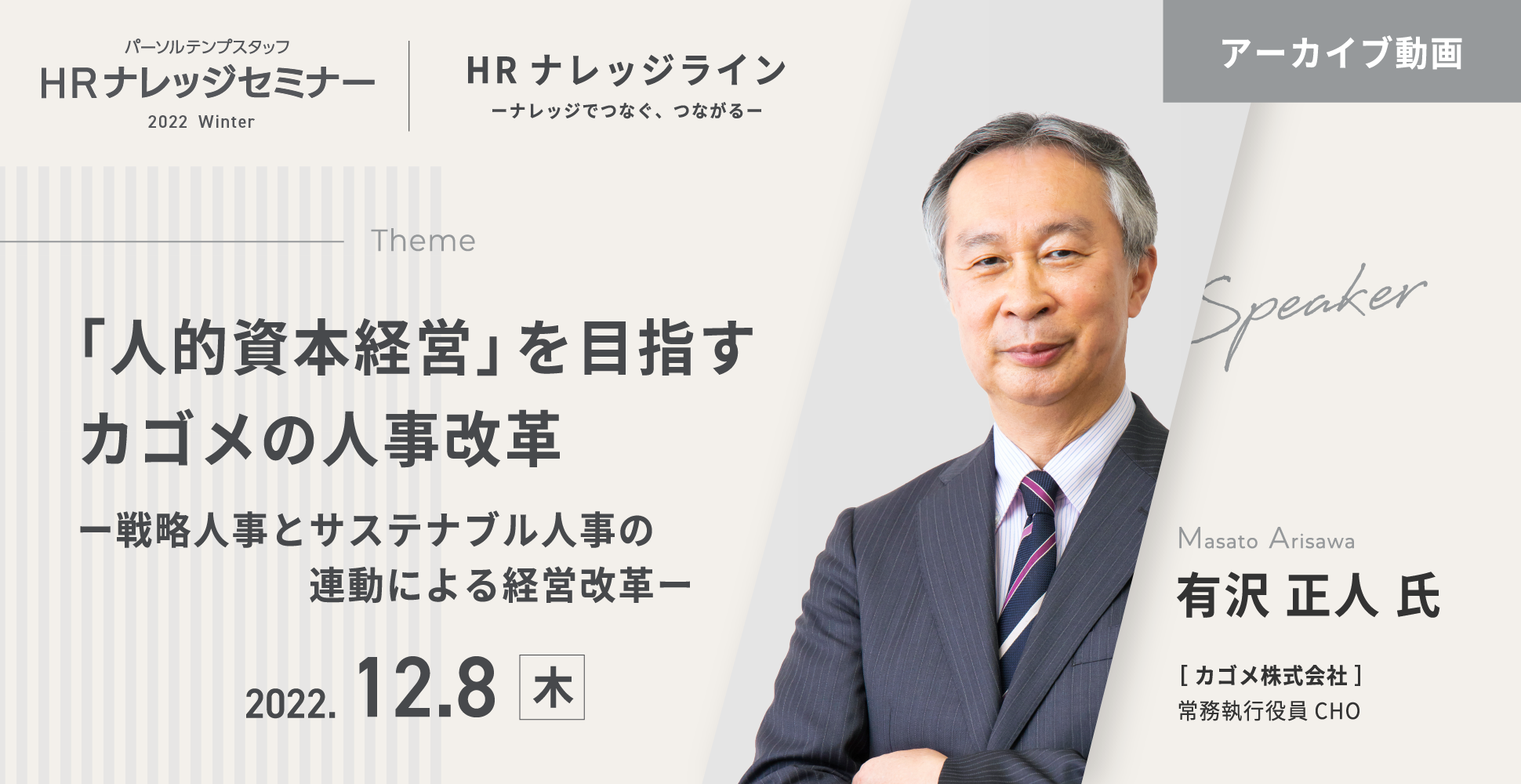HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【セミナーレポート】
HR の今、そして「これから」
ー 求められるものは何か?どうすればよいのかを考える ー
公開日:2025.03.13
- 記事をシェアする
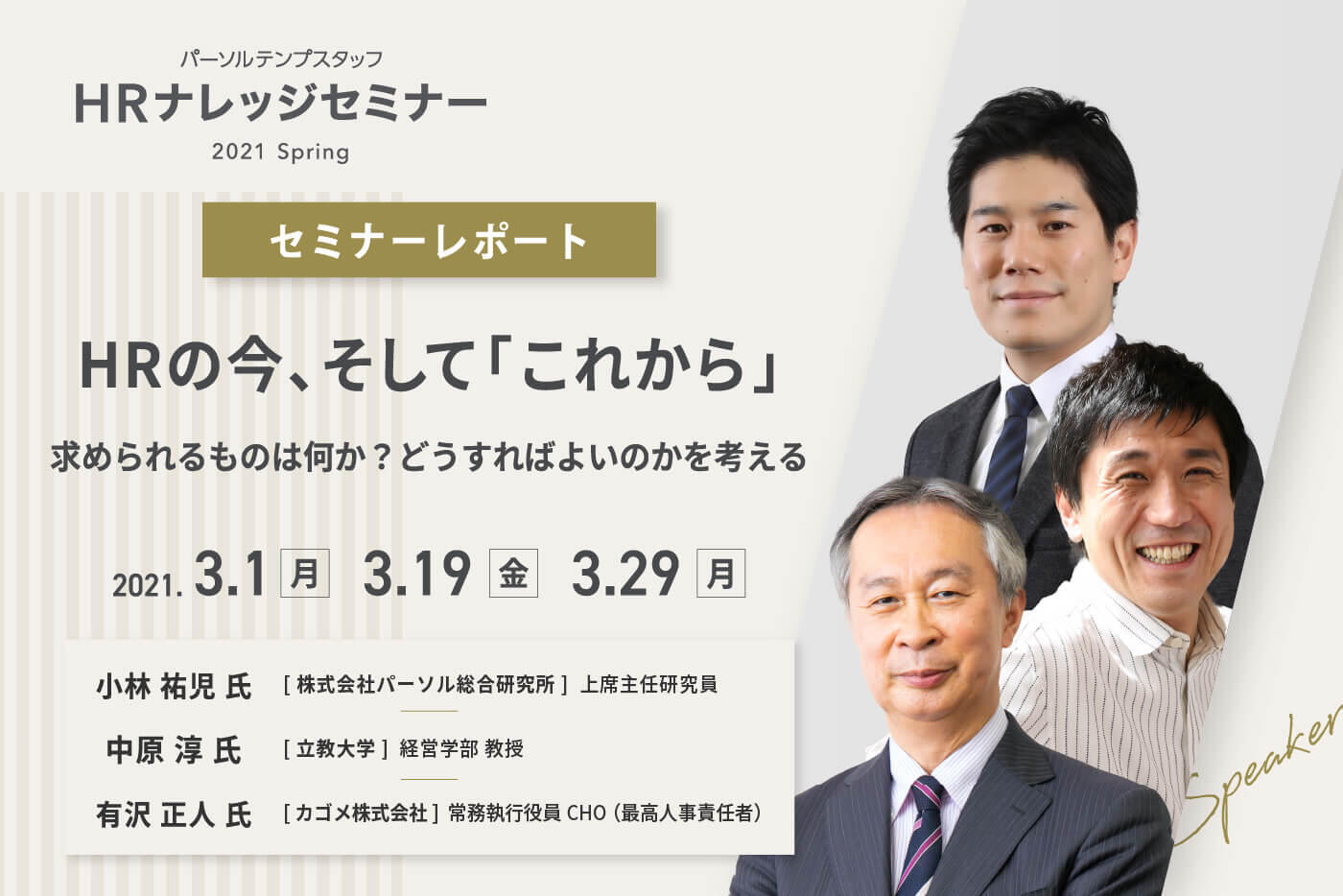
2021年3月、3日間にわたり「HRナレッジセミナー2021 Spring」が開催されました。
さまざまな変化や状況の中、2021年度に向け今、そして「これから」を見据えたHRの知っておきたいナレッジや課題解決のヒントを3つの異なる視点・テーマでライブ配信。
1,000名を超える全国のHRに視聴いただきました。
人事分野のプロフェッショナルによる「テレワークと生産性・組織マネジメント」「転職メカニズムと中途採用」「これからの人事制度と人事の在り方」
の3講演の内容をダイジェストでお届けします。
先が見えにくい「今、そしてこれから」のヒントが満載です。ぜひご覧ください。
「まだらテレワーク」時代の生産性はいかにして高められるか? ー 組織マネジメントの観点から ー
株式会社パーソル総合研究所
上席主任研究員
小林 祐児 氏
コロナ禍で推進されたテレワークですが、今後また「原則出社」の流れに戻っていくことが、過去のデータから予想されます。
しかし、今回のテレワークの促進によって、企業の働き方格差があらわになり、今後はテレワークを前提とした住む場所の境界を越えての希望に添えるか否かで、組織・職歴・居住地にも寄らない人材獲得が活発化すると話しました。
小林氏は、テレワークの生産性を高める要因として、プロセスとマインドの柔軟性と結果重視の組織を挙げました。
しかし一方で、テレワークを促進するかどうかを、生産性だけで是非を議論するのはおすすめしないとも話しました。なぜなら従業員は生産性で働いているわけではなく、重要視しているのは、企業の社会性であると説明し、コロナ禍という状況をきっかけにし、経営・人事が、企業ポリシーが明確になるよう、自社の「働く」について、コミュニケーションすべき時であると提言しました。
働くみんなの「転職学」 ー 転職メカニズムの探究 中途採用者をいかに迎え入れるのか? ー
立教大学
経営学部 教授
中原 淳氏
生涯年数が延びていることや、働く選択肢やキャリア観の変化から、勤労年数(はたらく年数)が長くなっていることが要因となり、一社で生涯務めることが難しいと考え、転職を視野に入れている人が増えていることが予想されます。「転職学」の見地から、人が会社を辞める要因として、スイスチーズモデルを例に、職場の不満が変わらない状況の積み重ねがあふれた時に、人は転職行動を起こすと話しました。
しかし、転職活動時にリアリティショックを感じてしまうと、スムーズな転職につながらず、自己認識の自己価値と社会的価値のギャップと転職への焦りで、転職に失敗してしまうことが多いといいます。これを回避するには、自己を知ることと、自分の経験を棚卸しすることを挙げ、他人からのフィードバックで自分を見つめ直すことが必要であるとまとめています。
また一方で、企業側としては、転職後の早期の離職を防止するために、中途採用や外部人材も含め、経験者であるからといって、すべて丸投げするのではなく、上司や同僚による職場定着の支援が必要とも話しました。
最後に、転職の実践とは従来のマッチング思考を捨て、自己を知り、学び直す覚悟が必要である提言しました。
毎年進化するカゴメの“生き方改革”とこれからの人事制度のあり方 ー Withコロナ時代へのあるべき対応と経営に資する人材の育成 ー
カゴメ株式会社
常務執行役員CHO
有沢 正人氏
カゴメの年功序列人事をジョブ型人事に変え、仕事に対して報酬を決める制度の導入について冒頭で説明しました。上の役員から手をつけていくことが、会社のあり方を変えることにつながることを説いています。この改革によって、カゴメの労働生産性が上がり、会社における働き方改革と合わせて、個人の暮らし方が変わり、個々の価値観に応じたはたらき方が可能になると話しました。
「暮らし方改革」を合わせた、時間を個人に割り当てる「生き方改革」へとつながり、「個人は自分の価値観に応じた働き方が可能となる」と話しました。
また有沢氏は、最高人事担当者として、次期社長の後継者を育成し、経営と連携し人材育成を行っています。ただ縦割りで業務を行うのではなく、経営戦略の一つの機能として人を育てることの重要性を説いていました。
最後に、「経営戦略は人がいなければ動かすことができない」、そのためには「何よりも一番先に人事戦略が進んでいなければならない」と提言しました。
まとめ
コロナ禍で、人の「働き方」や「雇用形態」はこれまで以上に大きく変化しています。
企業は厳しい状況が続くなかでも、目の前のことに対応しつつ変化への対応を模索しなければなりません。
会社や組織、そして人事の課題は山積しているといえるでしょう。
2021年度をむかえるにあたり「これからやっていくべきこと」「やらなければならないこと」の一部を、3つのテーマに絞ったナレッジとしてお届けしました。今後の課題解決のヒントとして、お役立ていただければ幸いです。
コロナ禍は、企業や働く人のさまざまな課題をあぶりだしました。困難はまだ続くかもしれません。
しかしながら、それを気づきや変革のチャンスとして活かしていくこともきっとできます。
わたしたちパーソルテンプスタッフは、人の「はたらく」を多角的な視点でみつめながら、少しでもみなさまの課題解決の力になりたいと願い、
これからも全力で取り組んでまいります。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

株式会社パーソル総合研究所
上席主任研究員
小林 祐児 氏
上智大学大学院・総合人間科学研究科 博士前期課程 社会学専攻修了。世論調査機関、総合マーケティングリサーチファームを経て現職。主な研究領域は理論社会学・情報社会論・長時間労働問題など。主な著作に『転職学講義(仮)』(近刊・共著・KADOKAWA)、『残業学 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか?』(共著・光文社)、『会社人生を後悔しない 40代からの仕事術』(共著・ダイヤモンド社)など多数。
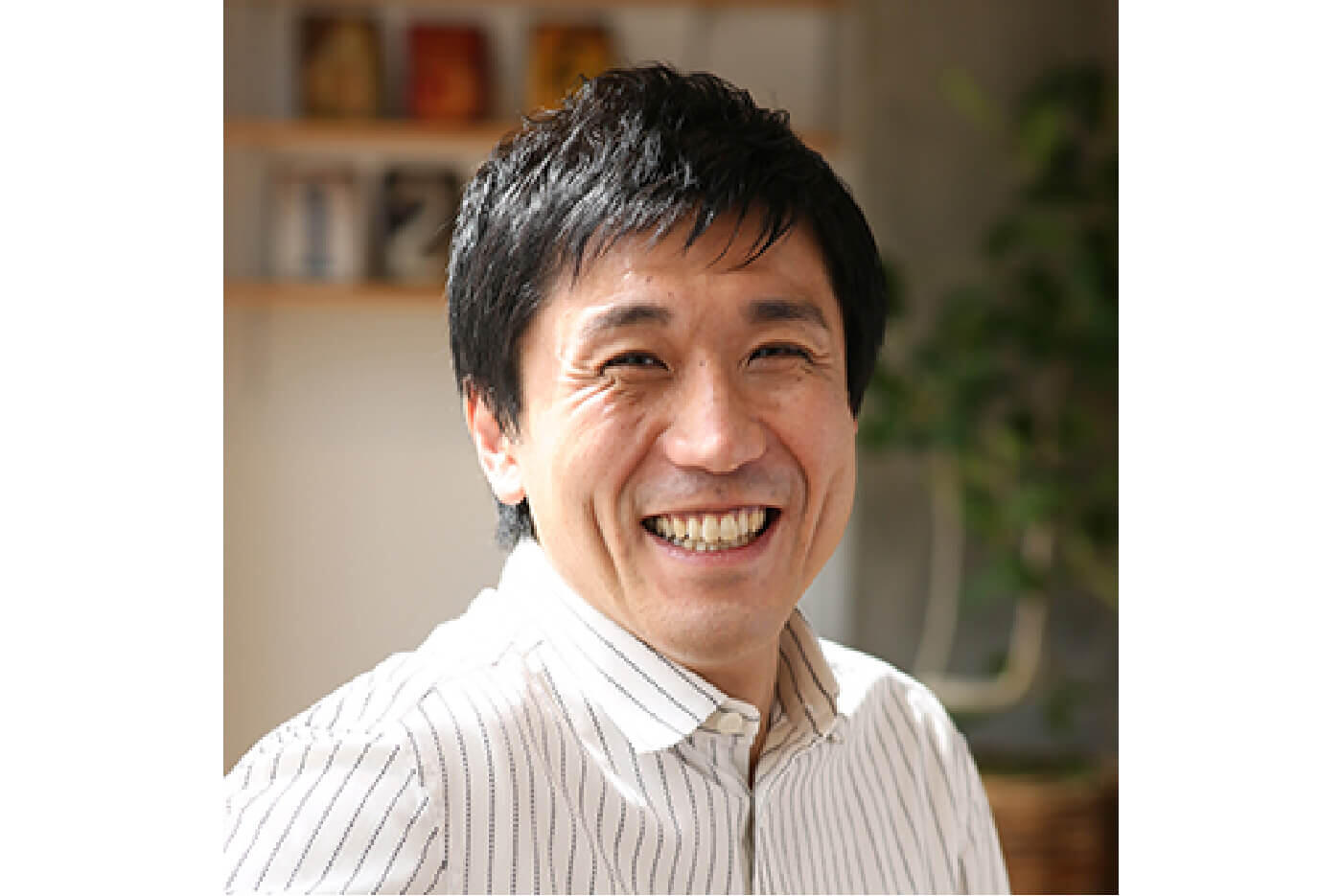
立教大学
経営学部 教授
中原 淳 氏
立教大学大学院 経営学研究科 リーダーシップ開発コース主査、立教大学経営学部リーダーシップ研究所 副所長などを兼任。 「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・組織開発について研究。【著書】「経営学習論」「研修開発入門」「駆け出しマネジャーの成長論」「組織開発の探求」(中村和彦氏との共著)「サーベイ・フィードバック入門」など多数。パーソル総合研究所との共著に「残業学」「アルバイトパート採用育成入門」がある。

カゴメ株式会社
常務執行役員CHO (最高人事責任者)
有沢 正人 氏
1984年に協和銀行(現りそな銀行)に入行し、主に人事、経営企画に携わる。2004年にHOYA株式会社に入社。人事担当ディレクターとして全世界のHOYAグループの人事を統括。全世界共通の職務等級制度や評価制度の導入を行う。また委員会設置会社として指名委員会、報酬委員会の事務局長も兼任。グローバルサクセッションプランの導入等を通じて事業部の枠を超えたグローバルな人事制度を構築する。2009年にAIU保険会社に人事担当執行役員として入社。ニューヨークの本社とともに日本独自のジョブグレーディング制度や評価体系を構築する。2012年1月にカゴメ株式会社に特別顧問として入社。カゴメ株式会社の人事面でのグローバル化の統括責任者となり、全世界共通の人事制度の構築を行っている。2018年4月より現職となり、国内だけでなく全世界のカゴメの最高人事責任者となる。
- 記事をシェアする